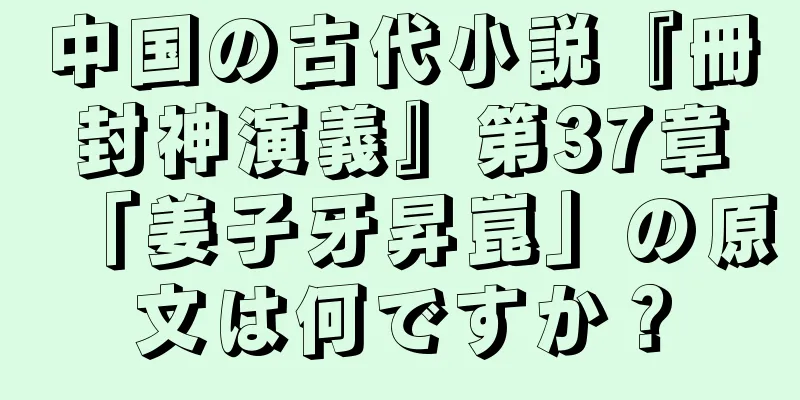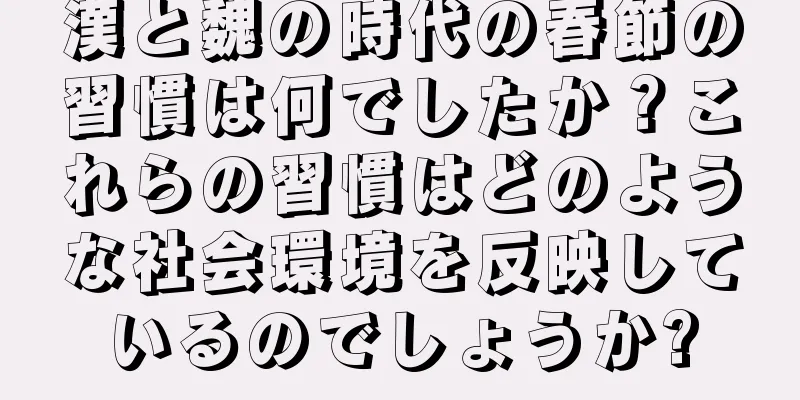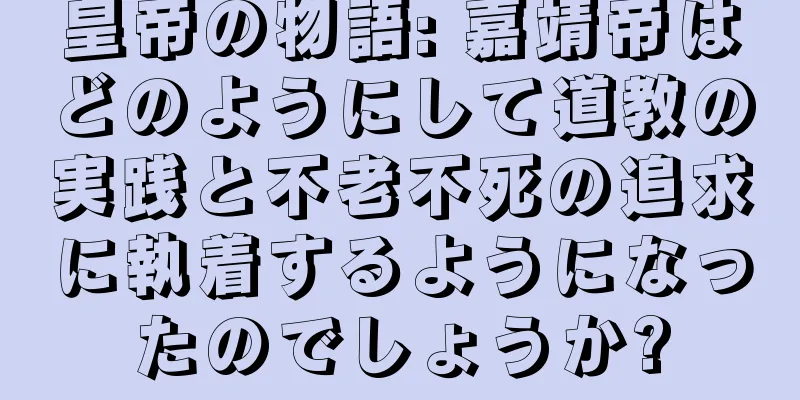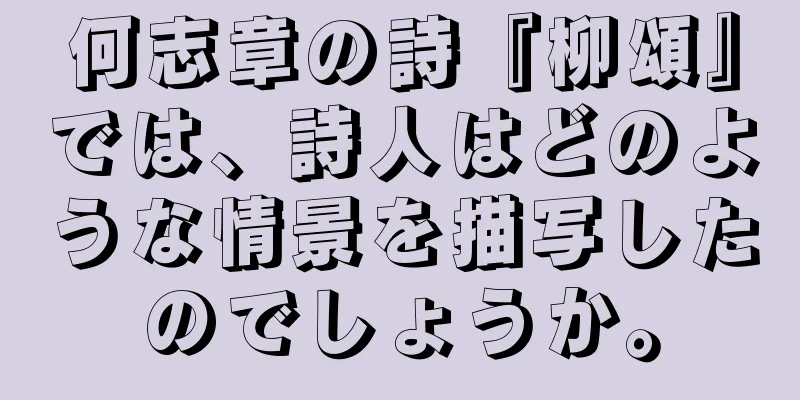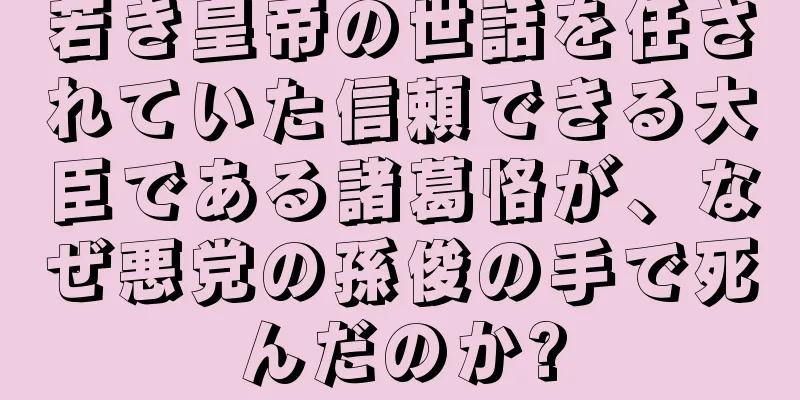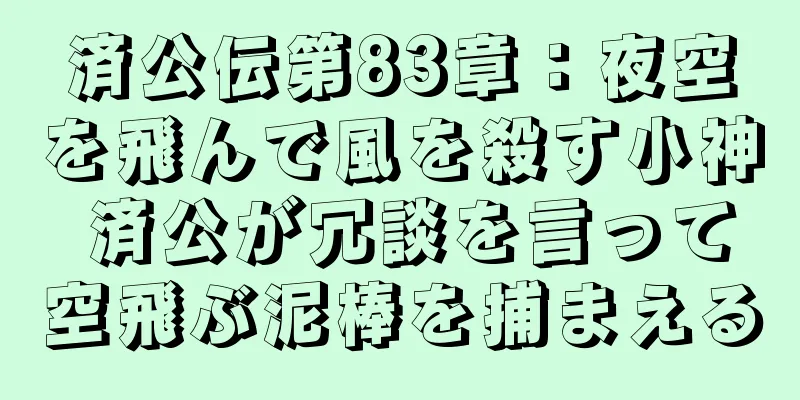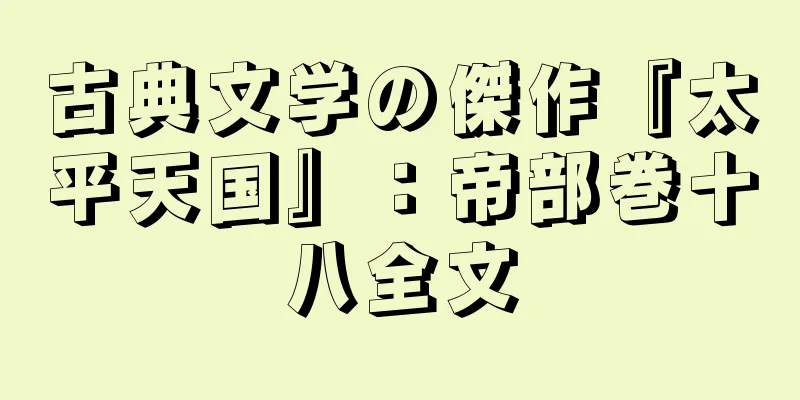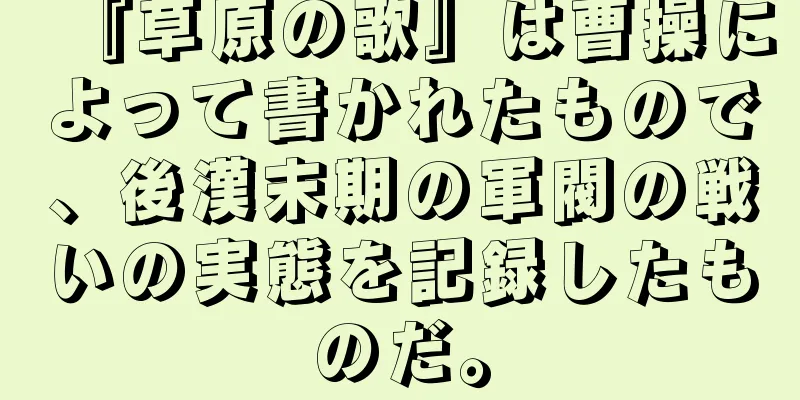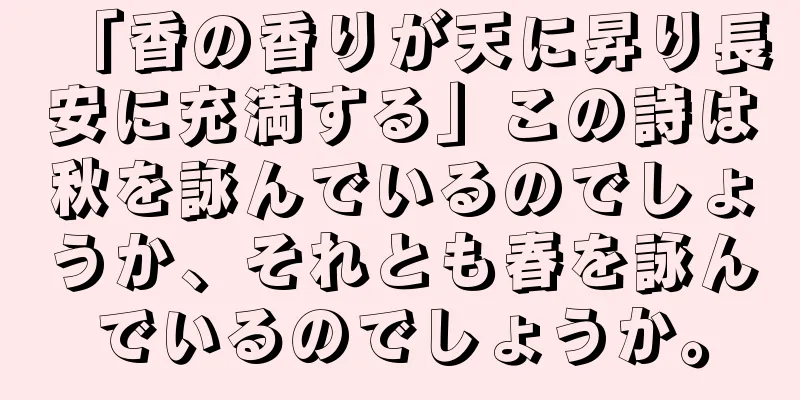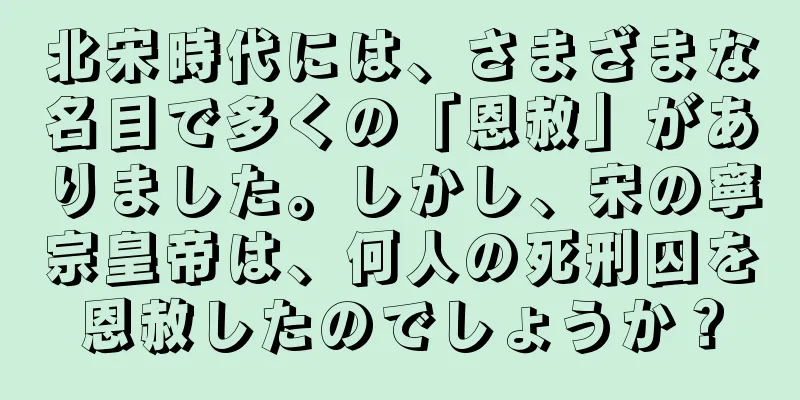古代人はもともと一日二食しか食べていなかったのに、なぜ後に「一日三食」になったのでしょうか?
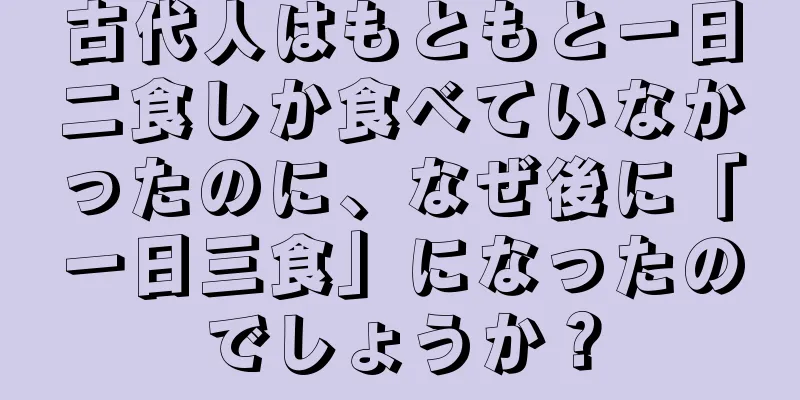
|
当初、食料が限られていたため、人々の食事は『黄帝内経』に記されている「空腹の時は食物を求め、満腹の時は余ったものを捨てる」という食事と同じで、決まった時間はありませんでした。その後、社会が発展するにつれて、食事の作法や時間も生まれました。古代の人々は1日に2食しか食べなかったのに、どのようにして「1日3食」に進化したのでしょうか? 一日二食から一日三食への進化 空腹や満腹のときは、人々は一日に何回食事を摂るかに注意を払う意識もエネルギーもありません。農業文化が発達し、農業技術が向上し、より多くの土地が開拓され、穀物の生産が増加し、食糧がより安定的に供給されるようになると、1日に数回の食事を摂るという考えが徐々に重要視されるようになりました。 商・周の時代になると、経済がある程度発展し、さまざまな礼儀作法や法制度が整い始め、次第に決まった時間と場所で食事をする習慣が生まれました。この習慣はゆっくりと発展し、戦国時代から秦の先代にかけては、1日2食の習慣が徐々に確立されました。この時期、ほとんどの人は朝と夕方に食事をします。 孔子が生きた春秋時代には、「朝を饔、夕方を飧」と呼んでいました。戦国時代には、朝食を「朝食」、夕食を「餔食」と呼ぶのが一般的でした。一日二食。 食事の時間は日の出と日の入りの時刻によって異なります。朝食は通常日の出後に食べられるため、午前 7 時から 9 時の間に食べる食事は朝食とみなされます。夕食は日没前に食べられ、午後 2 時から 4 時の間に予定されています。食事の具体的な時間は、家族が日中に仕事や勉強をどのように調整しているかによって異なります。 また、夕食は「餔食」とも呼ばれ、通常は朝食の残り物を温めたものですが、温めずにそのまま冷たいまま食べることもあります。いずれの場合も、新しい食事は用意されません。食後は休憩に時間がかからないので、次の食事をとる必要はありません。 漢の時代には、一日三食の考えが徐々に現れましたが、それは狭い範囲でのみ実施され、権力者と富裕層だけがそれに慣れていました。彼らにはお金と自由な時間があったので、多くの時間を働く必要がなかった。また、彼らのために働く奴隷もたくさんいたので、食事の準備に自然とエネルギーが余っていた。 一般的に、私たちは午前 5 時から午前 7 時の間に 1 食、午後 12 時から午後 2 時の間に 1 食、午後 5 時から午後 7 時の間に 1 食を食べます。権力者や富裕層は、たとえ罪を犯して罰せられることになったとしても、1日3食の食事を要求するでしょう。これは、食事が3回か2回かは、空腹か満腹かの違いだけではなく、社会的地位の違いでもあることを示しています。 普通の人のほとんどは、一日三食の食事さえとることができません。しかし、庶民の生活の中に「ハンジュ」というものが登場しました。これはスナック菓子のことであり、食事の合間に小腹が空いたときに食べられる軽食のことです。そのため、漢の時代には、一日三食の習慣がすでに王子や貴族の間で広く定着し、庶民の間でも定着していました。 しかし、特別な状況は常に存在します。たとえば、皇帝は特に裕福で、1日に4食食べることができます。 『百胡同礼月』には、皇帝の食事は明けの食事、昼の食事、晩の食事、夜の食事から成り、明らかに一日四食であったと記録されています。 しかし、大きな自然災害が発生して食糧生産が著しく減少し、人々が困窮する場合には、皇帝は自らの罰として食事を減らすという行動に出ました。しかし、皇帝自身に課せられた罰は、国民の苦しみに比べればはるかに軽いものでした。 戦時中や飢饉の時には、庶民は一日三食どころか、一日二食を食べるだけでも大変な努力が必要でした。一日一食で餓死しないよう努力するのも大変なことです。 家族に子供がたくさんいる場合、子供がまだ成人労働者に成長していないときは、食料消費は収入よりはるかに少なく、食事も影響を受けます。1日に1食しか食べられないこともあります。2回の食事をきちんと食べられる人は、非常に良い家庭環境にあると考えられます。 一般的に言えば、秦と漢の長い文明の時代において、一般の人々の生活水準はそれほど大きな改善は見られませんでした。裕福で権力のある人ほど、贅沢で絶品の食べ物をどんどん食べます。そして、富裕層や権力者の贅沢で裕福な生活を支えているのは、一日三食の食事もままならず、一日中働かなければならない一般の人々なのです。 唐宋代に入ると、我が国は経済的に非常に繁栄した時代に入りました。物質的な条件は以前に比べて大幅に改善され、商品経済は非常に繁栄し、人々は豊かな生活を送り、多くの野菜、穀物、果物が栽培され、人々の一日三食の推進が促進されました。 宋代にはさらにそうでした。さらに、宋代には制度上の変化があり、夜間の就寝時間を遅らせる門限が廃止されました。 外出禁止令が解除された後、宋代の夜市文化は非常に繁栄し、遊ぶもの、食べるもの、飲むものがたくさんありました。当時、汴梁は夜になると明るく照らされ、多くの高官や裕福な家庭が遊びに出かけ、当然のことながら飲食もしていた。 普通の人は夜遅くに買い物をするとお腹が空いてしまいます。そしてお腹が空いたら夜市でまた食事をします。この食事は、現在では夜食と呼ばれていますが、当時の一般の人々にとっては三食目でした。 しかし、当時はまだ1日2食が主流で、1日3食は高官や裕福な家庭に限られており、1日3食食べている一般人はごくわずかでした。 明代には、米の豊富な江南地域や、南東部のより発展し繁栄した地域で、一日三食が本当に普及し始め、都市の小作農や職人でさえ一日三食食べることができました。 しかし北部では、ほとんどの一般人は今でも1日2食を食べています。清朝後期、あるいは中華民国になって初めて、全国の人々が一日三食という概念を持つようになった。この時期、穀物の生産量が大幅に増加し、人々の労働時間も大幅に延長されました。 皇帝は例外でした。清朝初期、皇帝は1日2食を食べていました。それは、関に入って統治する前の生活は主に漁業と狩猟であり、生活必需品がそれほど豊富ではなかったためです。皇帝は1日2食の習慣があり、関に入って皇帝になった後もこの規則を守りました。 清朝の皇帝は「正食二回、秘食四回」を食べたという記録のみが残っており、正食二回のほかに、朝食と夕食も食べていた。だから、二度の食事は単なる表面的なものでした。結局のところ、彼は皇帝でした。彼には権力があり、自らを苦しめるようなことはしませんでした。テレビドラマでは、皇帝を喜ばせるために側室がお菓子を贈り、一日に何度も食事を摂る様子も見られます。 一日の食事回数は最終的には経済基盤によって決まる 一日の食事回数の変遷を振り返ると、この問題は特定の人物によって決められたものではないことがわかります。たとえ皇帝が一日三食を命じたとしても、国民がそれを買えなければ実行されません。 一日二食から一日三食への進化の最も根本的な理由は、経済的な基盤です。さらに、生産中心の生活と照明条件の不足も一定の影響を与えます。 経済基盤が上部構造を決定し、当然ながら飲食文化も決定します。食事の概念がなかった時代から、1日2食、そして1日3食へと進化したことから、1日の食事回数は経済発展と密接に関係していることがわかります。 経済が発展すれば、一日三食食べられる人が増える。時代が進み、経済が発展すればするほど、より多くの物質的なものが供給され、人々のニーズも高まり、先祖よりも多くのものを享受できるようになる。 一日三食が北部よりも早く南部で普及した理由は、単純に南部の方が豊かで、人々の手元にはより多くの食料があり、ポケットにはより多くのお金があったからです。規模の大小にかかわらず、同じ論理が当てはまります。家族の経済状況が良ければ、1日3食食べられる可能性が高くなります。 同じ時代でも、1日1食の家庭もあれば、1日2食の家庭もあり、また「冷たい食べ物」を買う余裕があって1日3食の家庭もありました。もちろん、すべてはそれぞれの経済状況によって決まります。 現代でも、北部の一部の農村地域では、農業を営む家庭では、1日に2食か3食かは決まっておらず、農繁期か閑散期かによって変わってきます。 農繁期には、人々は通常一日三食です。朝の6時か7時に簡単な食事をとり、まだ涼しいうちに畑仕事に出かけます。11時頃、暑くなり日差しが強くなると家に帰って休憩し、昼食をとります。午後3時か4時、だんだん涼しくなってきて、また畑仕事に出かけます。夜7時か8時、だんだん暗くなって蚊が群がり始めると、家に帰って夕食をとります。 農家が暇な冬は、学校に行く子供以外は早起きしても何もすることがないので、たいていは8時か9時まで寝て、10時頃に起きて、午後4時か5時頃にもう一度食事をします。これは時間と労力を節約でき、とても合理的です。 人々の生活が主に農業を中心に展開されていた古代でも同様でした。しかし、農繁期にはエネルギーを補給できる重要な食事である昼食をまだ用意していなかった。その主な理由は、古代では夜間の照明が大きな問題だったためである。 照明は古代では大きな問題でした。農繁期には昼休憩して食事をし、夜遅く帰宅しても何ら影響はありません。 古代の農民にとって、これは不可能でした。なぜなら、一日の時間は限られていたからです。その時間を休憩や食事に使うと、農作業がおろそかになります。また、明かりがなく、ランプの油やろうそくを買う余裕もないため、夜間に働くこともできませんでした。そのため、最も重要な作業は夜明けに行う必要があり、時間を無駄にすることは決してありませんでした。 明かりを盗むために壁に穴を開けたという有名な話は、古代の多くの人々が夜間は基本的に何もできなかったことを間接的に伝えています。日中に時間を無駄にしている人は軽蔑されます。たとえば、孔子の弟子の在邑は真昼間に寝ていたため、孔子は彼を「腐った木は彫刻できない」と嘲笑しました。 このように、夜明け後に食事をとり、食後に働き、暗くなる前に食事をとり、食後に休むのが合理的です。日の出とともに働き、日没とともに休むことも、自然の法則に逆らうことができない人間が行う自然な選択です。 要約する 物質的な欠乏から大きな豊かさに至るまでには長い時間がかかりましたが、ようやく私たちは今日のような豊かな生活を手に入れました。私たちが今生きている生活は、太古の昔には想像もできないものです。技術はともかく、食生活だけでも雲泥の差があります。 古代の人々は、現代人が減量のためにこれほど苦労するとは想像できなかったでしょう。減量のために、1日3食を2食、あるいは1食に減らす人もいます。一日三食食べるのが大変だった古代の人たちがこれを知ったらどう思うだろうか。 もちろん、これは私たちが今良い生活をしていることの証拠でもあります。私たちは今日の生活を大切にし、食べ物をむだにしてはいけません。一粒一粒が苦労して得たものなのです。 |
<<: 二十四節気の「六夏」の由来は何ですか?どのような気候変化が起こるでしょうか?
>>: 二十四節気の中の「夏至」はどこから来たのでしょうか?習慣は何ですか?
推薦する
『紅楼夢』で王夫人が初めて賈邸に入ったとき、林黛玉をどのように試しましたか?
林黛玉が賈邸に入ったことは多くの人が聞いたことがあると思いますし、彼女もそれをよく知っています。本日...
『西遊記』で、文殊菩薩はなぜ獅子豹の怪物を管理人として派遣することに抵抗を感じなかったのでしょうか?
獅子山猫の怪物は文殊菩薩の特使とも言える。彼は道士に変身し、黒鶏王国に雨を降らせるのを手伝った。彼は...
小説『紅楼夢』ではなぜ家政婦全員が女性として権力を握っているのでしょうか?
『紅楼夢』は中国の四大古典小説の一つであり、中国の封建社会の百科事典であり、伝統文化の縮図です。 今...
翔玲が詩を学ぶ物語と翔玲の詩を学ぶことから得たインスピレーションの簡単な紹介
相霊の詩を学ぶ物語は曹学芹の『紅楼夢』の中の名作で、かつて中国の教科書にも選ばれたことがある。芝延寨...
有史の才能と徳は王希峰と同じくらい素晴らしいのに、なぜ二人の人生はこんなにも違うのでしょうか?
Interesting History の編集者をフォローして、歴史上の本当の妖精について探ってみま...
『東周記』第22章 友良公と斉公が単独で魯王に立ち向かう
清王の父は、名を鍾といい、魯の荘公の異母兄弟であったと伝えられている。同じ母から生まれた弟は、雅とい...
紅楼夢第26話:蜂の腰橋の物語が語られ、小湘閣の春の眠気が秘めた感情を引き出す
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...
宋王朝は儒教で国を統治しました。繁栄しましたが、儒教のせいで滅びました。
本日は、Interesting History の編集者が宋代に関する関連コンテンツをお届けします。...
『紅楼夢』で石向雲は歓楽街を去った後どこへ行きましたか?結末はどうでしたか?
石向雲は小説『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。今日は、Interesting Hist...
宋の真宗皇帝の死後、劉鄂は政権を担う際に、権力者が政府を混乱させるのをどのように防いだのでしょうか。
宋の真宗皇帝の死後、劉鄂はどのようにして朝廷に確固たる地位を築き、権力者による政府への妨害を防いだの...
もし関羽が東呉の包囲を突破することに成功したら、劉備は関羽に対してどのような態度をとるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
宋代の詩「滴蓮花・月雨石波酔筆」を鑑賞します。この詩はどのような感情を表現していますか?
蝶恋花·月雨石波下酔筆[宋代] 辛其記、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見...
『紅楼夢』に登場する3杯のお茶にはどんな意味があるのでしょうか?
『紅楼夢』は、章立ての形式をとった古代中国の長編小説であり、中国の四大古典小説の一つです。今日は、お...
中国で現存する最古の建物はどこですか?この最も古い建物の名前は何ですか?
知らない読者のために:中国に現存する最古の建物については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介するので...
Xi ShiとPearlの間の物語は何ですか?伝説によれば彼女は西施の化身である
真珠は何千年もの間人類に利用されており、西施の化身であると言われています。次は興味深い歴史エディター...