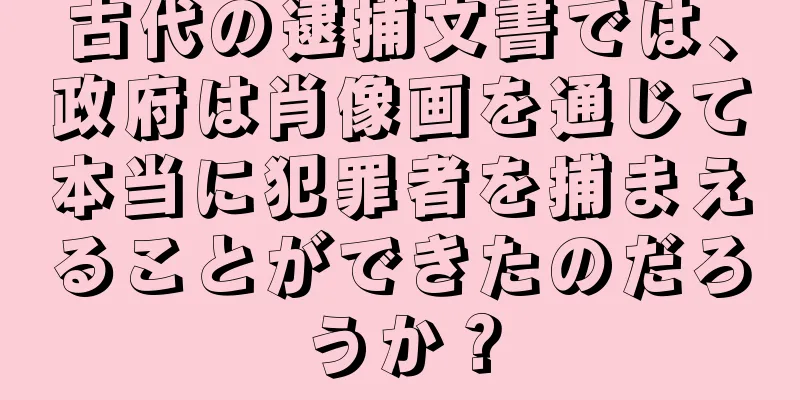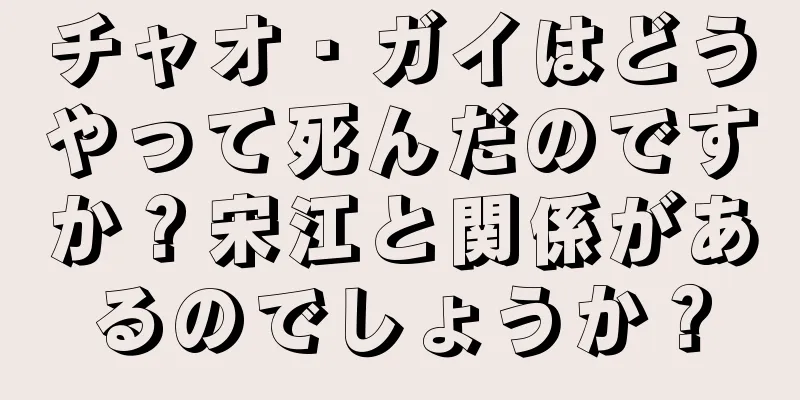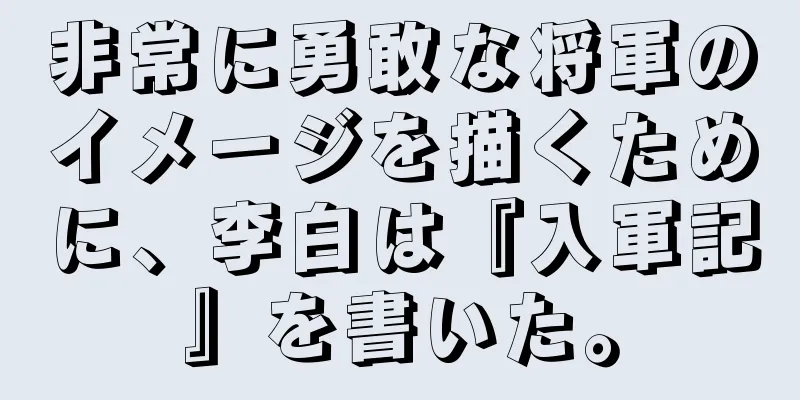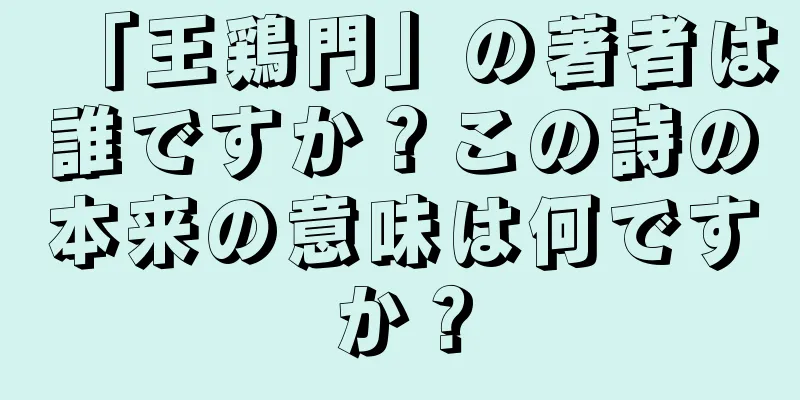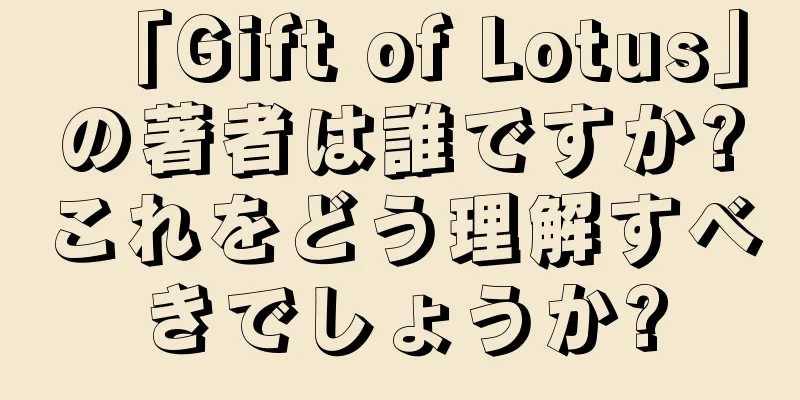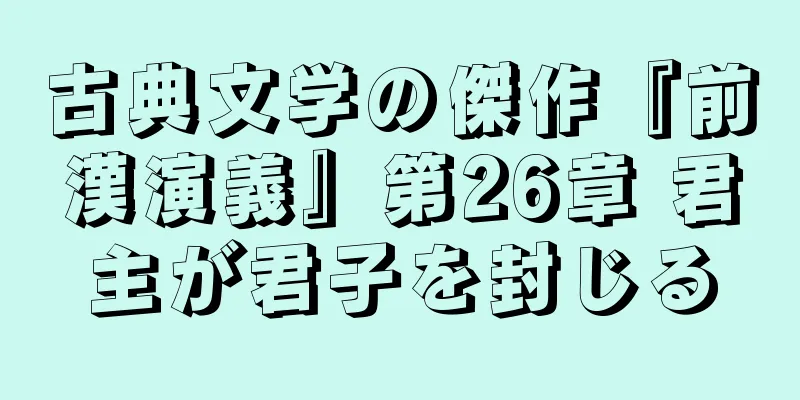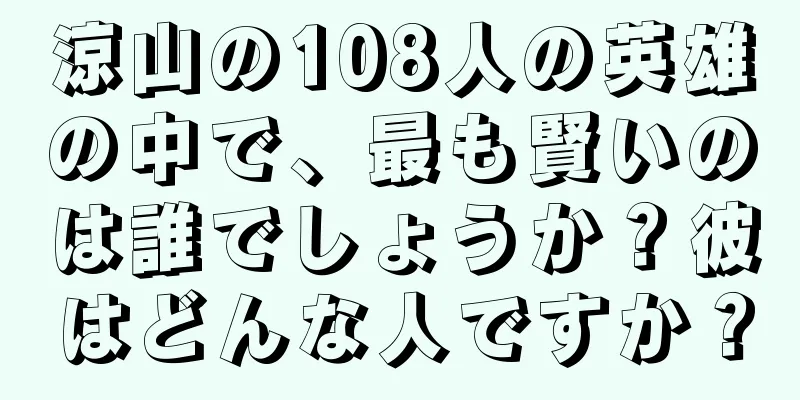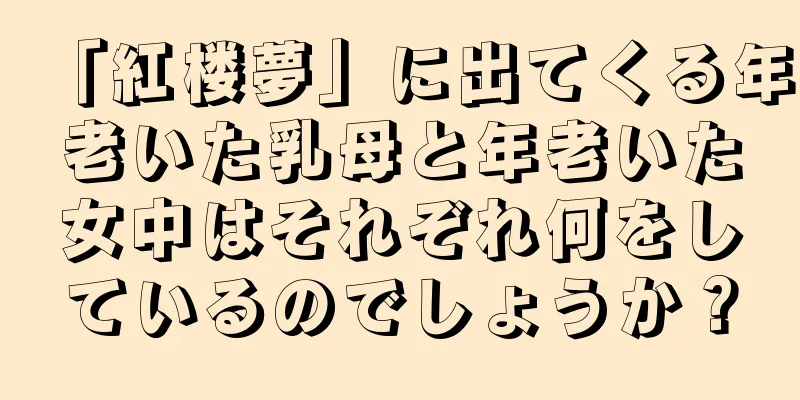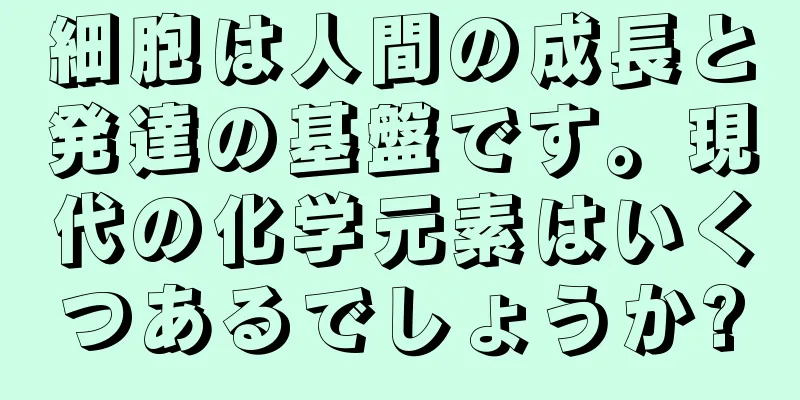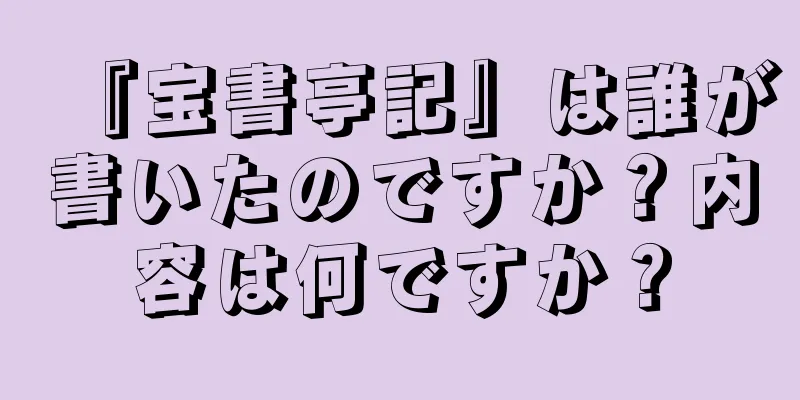古代の学者はどのような役人だったのでしょうか?学者の地位と待遇

|
秀才は古代中国で官吏を選抜する科目であった。学校の生徒に対する特別な用語としても使用されました。漢の武帝は官選制度を改革し、地方官庁に人材の審査と推薦を命じ、これを「曹儒」と呼んだ。元豊4年(紀元前107年)、皇帝は大臣と諸侯に毎年1人の優れた才能を持つ学者を推薦するよう命じました。後漢の時代には光武帝の名を避けるため茅菜と改名された。三国時代に曹魏は推薦制度を継承し、それを秀才と改名した。南北朝時代においては学者の推薦が特に重視された。隋代に初めて科挙制度が実施され、学者という部門が設立されました。この科目は唐代初期まで存続し、合格した者は学者と呼ばれました。その後、学者という区分は廃止され、学者は学者の総称となった。宋代には学者や志願者の総称であった。明朝はかつて推薦という方式を採用し、学者も推薦した。明・清時代には、「修才」という用語は、県、州、郡の学生を指すためにも使用されていました。 『水滸伝』には王倫という白衣の学者が登場します。 「白衣の学者」とは何ですか?彼はいつも白い服を着ているのですか?実は、「白衣の学者」とは「科挙に失敗した学者」を指します。 「落第生」という用語は宋代に初めて使われた。 「学者」とは何でしょうか?それはもともと『礼記』に出てくる「秀氏」のように、優れた才能を持つ人を指し、一般的な用語であり、経文に精通している人に限定されません。漢・晋・南北朝の時代になると、学者という分野は人材を推薦する対象の一つとなっていた。唐代初期の科挙には多くの科目があり、学者はその中の1つに過ぎず、すぐに廃止されました。同時に、「秀才」は学者の総称となった。宋代には、各県が朝廷に人材を提出し、礼部が共同で試験を行うという制度が設けられた。唐代末期の方式に倣い、まず選抜試験が実施され、推薦を受けるために選抜試験を受けた者は学者と呼ばれた。 『水滸伝』では、王倫は「落第生」と表現されているが、これは昇進に失敗し、選抜試験にも失敗したことを指して、侮辱的な表現である。宋代では、試験に合格しなくても学者の称号を得ることができましたが、明代や清代では状況が異なりました。学者の称号を得るのは容易ではなく、何度も試験に合格する必要がありました。また、学者は最終的に科挙に合格できないこともありました。 明清時代、「修才」という用語は、特に県立学校(または直轄県)や県立学校の生徒を指し、四書五経を読む学者を指す特別な用語でした。この資格を取得するには、道教の学校(通子試験とも呼ばれる)に入学する必要があります。年齢に関係なく、男子のテストを受ける人は誰でも男子と呼ばれます。魯迅の小説『孔一基』と『白光』の主人公である孔一基と陳世成は、清朝時代に何度も男子試験に落ちた。彼らは高齢であったが、やはり少年、あるいは老人であった。県、州、学院の三科に合格し、県立学校、国立(直轄地)学校、県立学校に入学すると、金学(俗称は聖元、秀才の俗称)と呼ばれる。学生は定期的に学校に通い、学問官吏による監督と評価を受けるほか、科挙選抜(不合格者は科挙を2回受けることができ、1回は合格、もう1回は不合格)を経て、当時の省試(各省で行われる試験で、合格者は科挙と呼ばれる)に参加する必要があった。 学者 男子の試験はハードルが高い。官僚になるには他の方法があるのだろうか?実は、男子の試験や科挙を受けない受験者も、地方の試験を受けることができる。その方法は、いわゆる「入獄料を払って穀物を払う」という行為に参加することである。この制度は明朝中期に始まり、清朝末期まで続きました。 「貢物を納めて入宮する」とは、貢物を納めて宮廷の学生となり、国試を受ける資格を得ることである(お金はあるが勉強する気がない者は、貢物を納めても国試を受けないことがほとんどである)。この道は軽蔑されることが多いが、いつも驚きがある。明代の羅桂は少年試験に7回失敗したが、勉強のためにお金を寄付した後、省と首都の試験で1位を獲得した。 地方試験は秋(中秋節の頃)に行われるため、秋季試験(闱は試験会場の意味)と呼ばれていました。統一試験は翌年の春(旧暦2月以降)に行われ、春季試験と呼ばれました。科挙は礼部省が主宰し、礼部試験あるいは礼科試験とも呼ばれた。合同試験の後は宮中試験です。明・清の時代には、通常、このような科挙は3年ごとに行われ、国家の祝祭の場合には追加の特別科挙が実施されました。 Liu Hongping によって作成されました。 科挙制度の時代 「秀才」という用語は、隋代に科挙制度が導入される以前から存在していました。漢代に推薦制度が採用されていた頃、各国が推薦した文民の人材は「秀才」と呼ばれていました。東漢の時代、漢の光武帝劉秀の禁忌を避けるため、秀才の名は茅才、あるいは毛賽と改められた。茅才科は主に優れた才能や能力を持つ人を選抜するための科目であるため、通常は「茅才易登」または「茅才特至師」と呼ばれます。秀才はもともと特別選抜であったが、前漢末期には州知事を審査官とする年次選抜となり、国が学者を選抜し、郡が孝行な官吏を選抜する制度が形成された。 科挙期間 隋の時代は学者を選抜するために科挙を実施し始めましたが、当初は学者を選抜するためでもありました。唐代初期には、修才は定期的な試験でした。しかし後に「秀才階級」は廃止され、「秀才」という言葉は学者の総称となった。宋代には、地方県の試験に合格した者は、合格したかどうかに関係なく、学者と呼ばれることができました。そのため、当時彼は「失敗した学者」として知られていました。 明・清の時代、「秀才」は学問の試験に合格し入学を許可された「学生」の一般的な呼び名でした。学者資格を取得することは、学者官吏クラスに入るための最低条件です。学者になるということは、地元で一定の「功績」を持ち、尊敬されるということであり、またさまざまな特権も得られるということである。例えば、彼は賦役から免除され、郡知事に面会する際にひざまずく必要はなく、郡知事は彼を勝手に拷問することができず、公務があるときは郡知事に報告することができた、などであった。学者の中には貧しい家庭出身の者もいたが、学者の称号を得ることが必ずしも富をもたらすわけではない。学生の身分しか持たない学者は給料をもらえず、その後の地方試験に合格しなければ官吏になる資格も得られなかった。多くの学者は公職でさらなる進歩を遂げることができず、故郷に戻って教えることで生計を立てることしかできなかった。経済的には裕福ではなかったが、庶民より少しだけ社会的地位が高かったこれらの学者は、「貧乏学者」と呼ばれていました。 明・清時代の中国では、学者は地方の貴族階級の支柱の一つでした。地元の村々では、彼らは「教養があり礼儀正しい」学者の代表です。彼らは地方の役人から特権を享受していたため、一般市民と政府との間の連絡経路として機能することが多かった。地方で紛争があったり、庶民が政府役人と交渉する必要がある場合、学者を介さなければならないことが多かった。一般の人々が結婚式や葬式、その他の祭りを行う際には、村の学者に連句や祭旗を書くのを手伝ってもらうよう頼んだ。 |
<<: 官書の創始者は誰か? - 秦の時代の書家、程妙の略歴
>>: 古代における科挙合格に相当するものは何ですか?科挙に合格した者だけが官吏になる資格がある。
推薦する
秦以前の学術書『管子』の背後にある原理は何ですか?
秦以前の学術書『管子』に書かれた思想は、当時の政治家が国を治め、世界を平定するために用いた偉大な原則...
漢代の西域護国はどこにあったのでしょうか?西部地域保護領は今どこにありますか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が古代の西部...
「彭公の場合」第296章:不幸を幸運に変え、名前を尋ね、幸運にも仙人に会って理由を告げる
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『紅楼夢』では、青文はただの女中なのに、なぜ王夫人は彼女を嫌うのですか?
中国の伝統文化は歴史が長く、奥深いです!今日は、興味深い歴史の編集者が、紅楼夢の王夫人の関連コンテン...
唐代の詩「李少夫を峡に流す」と「王少夫を長沙に流す」をどのように評価すればよいでしょうか?高石がこの詩を書いた意図は何でしたか?
唐代の李少福は下中に左遷され、王少福は長沙に左遷されたが、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届け...
ユグル族のトーテムとは何ですか?それは何を示しているのでしょうか?
蘇南ユグル族自治県前潭郷のユグル族の間では、次のような伝説が伝えられている。ある家族は非常に裕福で、...
左派宰相の沈一基とはどんな人物だったのか?歴史は沈一基をどのように評価しているのだろうか?
沈易基(?-紀元前177年)は、沛県出身の劉邦の同郷人であった。彼は召使として劉邦の妻子の世話をし、...
劉邦と項羽の顧問として、張良と范増のどちらがより有能でしょうか?
秦末期の楚漢の争いは、中国史上非常にエキサイティングな時代であったと言えるでしょう。この戦争では、双...
『紅楼夢』で薛宝琴が賈の家に入ることと薛叔母との関係は何ですか?
『紅楼夢』に登場する宮廷商人の娘、薛宝琴は幼い頃、父親と一緒に様々な場所を旅しました。今日は、Int...
孫権は本当に自らの戦略目標を達成するために孫策の権力を掌握したのだろうか?
孫策と孫権は性格が異なり、戦略的な見解も大きく矛盾している。孫権が戦略目標を達成したいのであれば、孫...
辛其記の『臨江仙・譚美』は何を表現しているのでしょうか?
以下、興史編集長が辛其記の『臨江仙・譚美』の原文と評価をお届けします。ご興味のある読者と興史編集長は...
「七つの田園歌第6番」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
七つの田園歌、第6番王維(唐代)桃の花は夜の雨でまだ赤く、柳は朝霧で緑のままです。 (朝煙は春煙とも...
『半神半魔』に出てくる小窯宗と霊九宮は同じ宗派ですか?徐朱が王位に就いたときの正体は何だったのでしょうか?
本日は、興味深い歴史の編集者が『半神半魔』における小遁宗と霊九宮の関係について解説します。皆様のお役...
唐王朝は最も強力な王朝の一つでした。なぜ唐は、包囲されている中で吐蕃と王女を結婚させたり、和平協定に署名したりすることを選んだのでしょうか?
唐は高祖李淵の時代から、高原で台頭してきた吐蕃と絶えず戦争をしていた。両者は河西、関中、西域、さらに...
第5章:龐煖首相とその娘が権力を乱用し、胡一家全員が殺害される
『胡氏将軍伝』は清代の小説で、『胡氏全伝』、『胡氏子孫全伝』、『紫金鞭物語』、『金鞭』とも呼ばれてい...