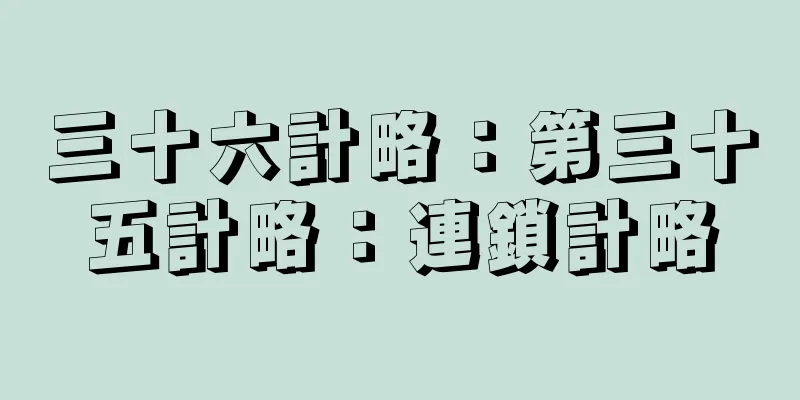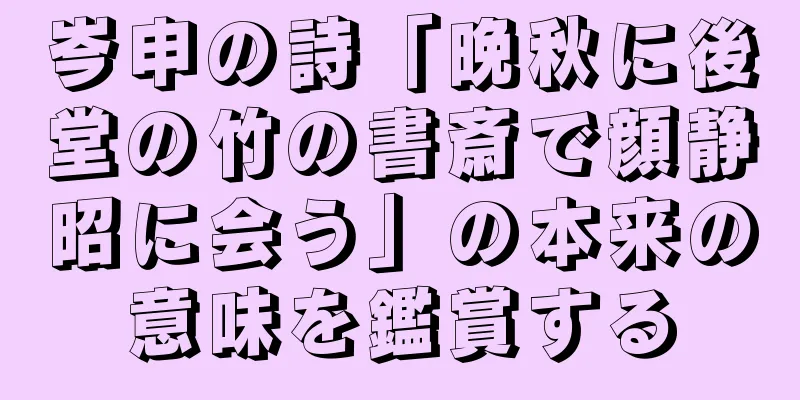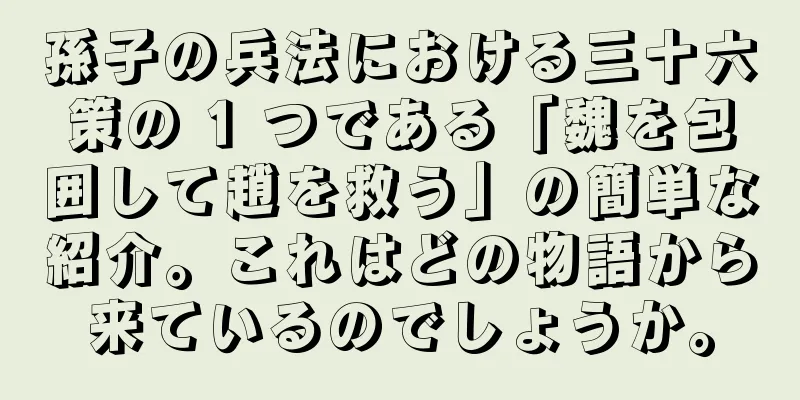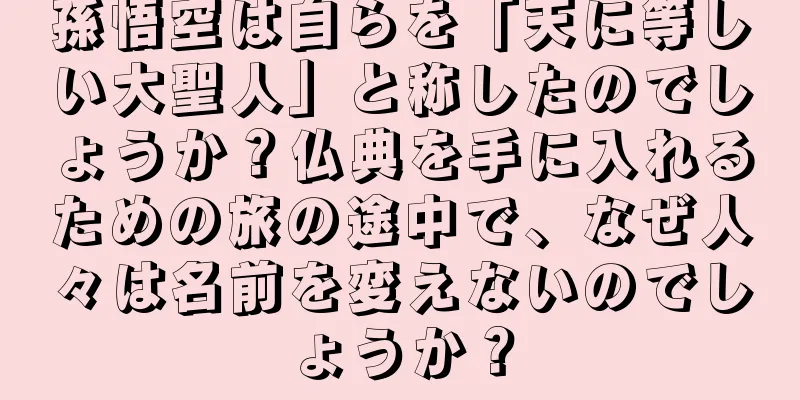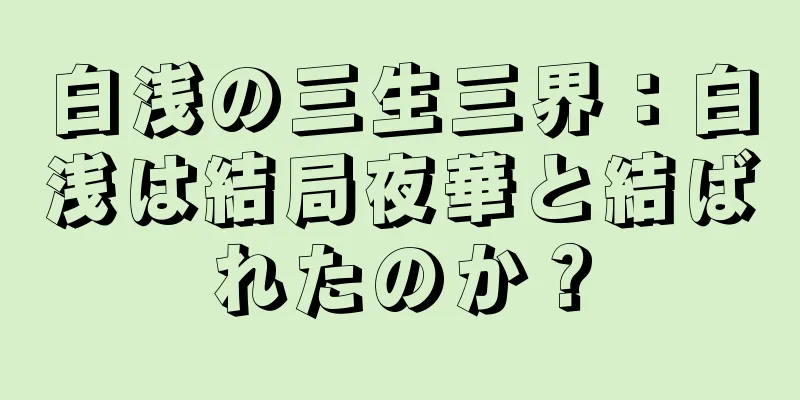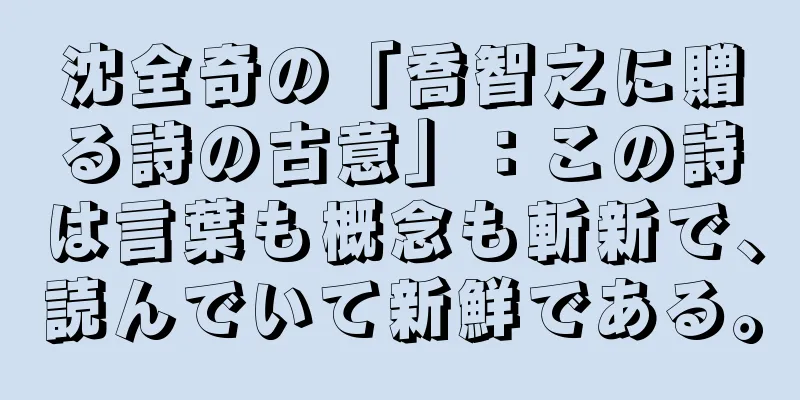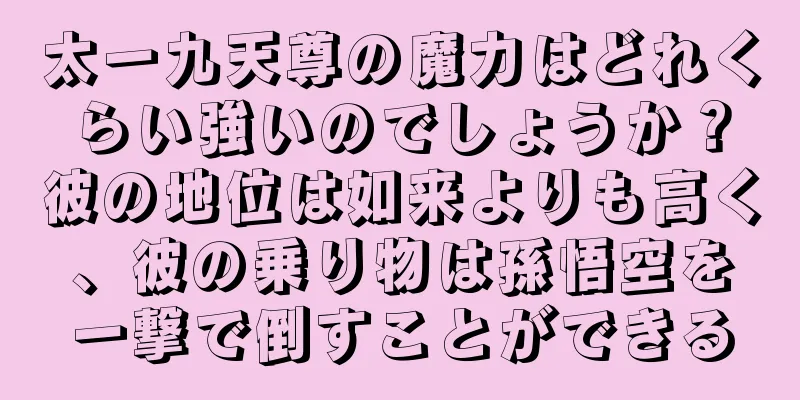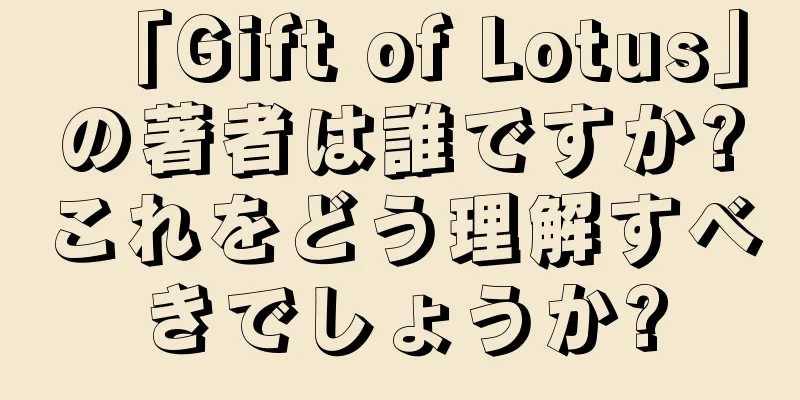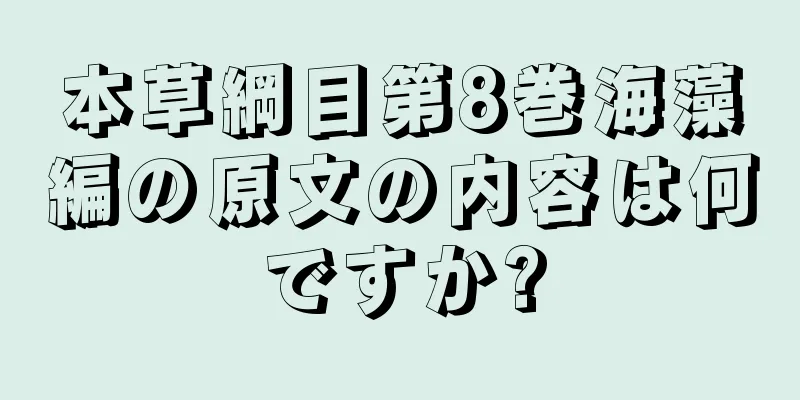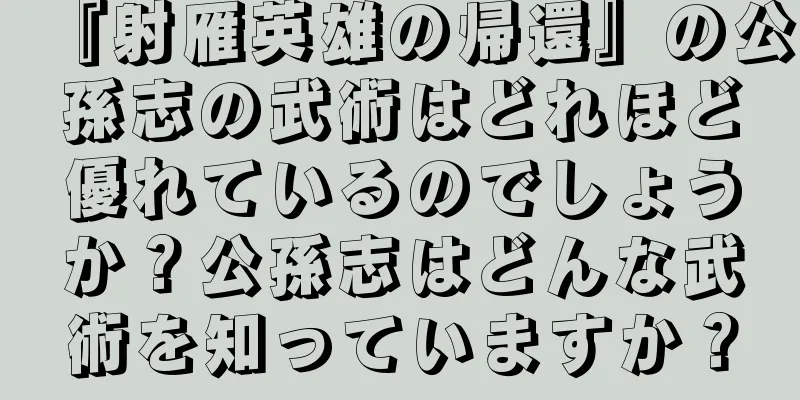ドラマに出てくる「元外」とはどんな役人ですか? 「元外」には本当に力があるのでしょうか?
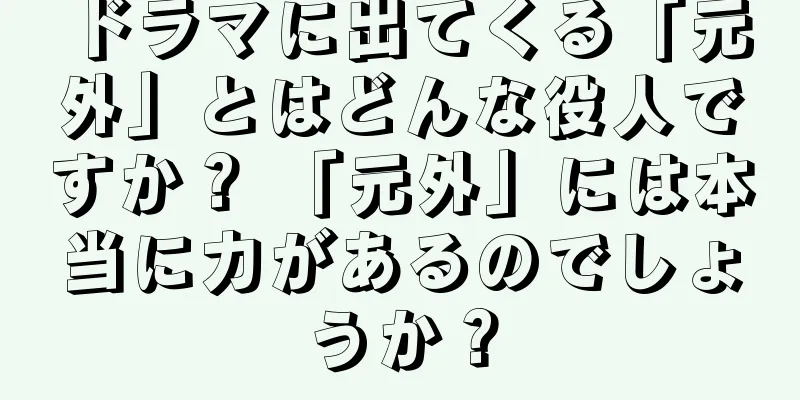
|
ドラマの中の「元外」とはどんな役人でしょうか?「元外」には本当に権力があるのでしょうか?興味深い歴史の編集者が詳細な関連コンテンツを提供します。 『西遊記』や『水滸伝』を読んだ人なら、「元外」という言葉に馴染みがあるはずだ。多くの時代劇では、元外のイメージは基本的に長いひげと豪華な服を着た老人です。では、これはどのような役人なのでしょうか?古代ではどれほどの権力を持っていたのでしょうか? 元外とは、元外朗の役職の略称で、「定員外の追加」を意味します。元外三卿長師の地位は三国時代の魏末期に初めて設置され、元外三卿士郎は晋の初期に設置されました。どちらも皇帝の侍従でした。南北朝時代には、宮中侍や宮中侍司馬などの新しい役職が設けられた。隋代には、袁外は尚書省の二十四省の副長官となり、その地位はさらに向上した。唐、宋、遼、金、元、明、清の各朝は隋の制度を踏襲し、六省のそれぞれに阮中と袁外郎が長官と副長官を務めた。袁外はすでに体制に組み込まれ、重要な地位にあった。 『白蛇伝』の陳元偉 特に注目すべきは、唐代にはこうした役職があまりにも多く、ほとんど不要になったということである。 唐代の元外官吏の問題はかなり複雑である。『唐六法』や『通典官吏法』では、元外官吏は正規の官吏ではないとしているが、任命の面では、元外官吏といわゆる代理官吏や検閲官吏との間には依然として一定の違いがある。 例えば、元外官吏の中には朝廷から降格された官吏もおり、少数民族の取り込みのために朝廷から任命された者もいた。これらは地方の知事によって任命されたものではないが、いずれにしても元外官吏が正規の官吏ではなかったことは確かである。 トルファンで発掘された文書からは、西州の地方政府や車夫にも元外官吏がいたことがわかり、さらにそれ以前には軍政府にも元外官吏がいたことがうかがえる。 唐代に元外官が初めて設置されたのは永徽5年(654年)であるが、当時はその種類や人数に制限があった。実際に元外官が大規模に設置されたのは、武則天が皇帝を称し、唐を周に変えた後であった。 『紫禁同鑑』巻26に「神功元年(697年)、李嬌は天官の選任を担当し、数千人の官吏を任命し始めた」と記されている。同書第208巻には、「神龍2年(706年)3月、都から諸国まで多数の官吏が任命され、その数は2,000人を超えた」とも記されている。 神功元年より10年前、溪州には沙伯、康、何という姓の官吏がおり、それぞれ突厥九姓と昭武九姓に属していた。 西州は内陸部よりも早くこれらの少数民族官僚を設置したが、それには独自の理由があった。楚公年間、西域の状況は緊迫していた。東突厥の首領であるクトルグが勢力を増し、唐の国境を脅かした。九姓ウイグル族の銅洛と普姑は唐に反抗し、東突厥汗国に加わった。吐蕃はこれを機に河西を侵略した。唐に比較的近かった十姓西突厥諸部族は、東突厥の攻撃を頻繁に受け、内部で混乱が生じ、ほとんどが散り散りになって滅ぼされた。安渓の四鎮は危機的な状況にあり、軍事力の不足により、唐朝は咸公二年十一月に四鎮の放棄を命じざるを得なかった。 西突厥を鎮め、西域の情勢を安定させるため、西突厥ハーンの末裔である阿斯名元卿を左于秦将軍、崑陵守護将軍に任命し、興西王ハーンを攻撃し、五都露族を掌握させた。阿斯名胡素洛を右于秦将軍、守護将軍に任命し、済王覚ハーンを攻撃し、五州師比族を掌握させた。この時、沙伯元外国易が西州に任命されたが、これはおそらく西突厥を鎮め、西域の情勢を安定させるためであった。その後、康延と何は副官に任命されたが、これは阿史名元卿と阿史名胡素洛の任命と一貫しており、どちらも西突厥と昭武九姓を味方につけ、その力で西域の情勢を安定させることを狙っていた。 地方官僚の出現は比較的遅く、中原の状況とほぼ同じでした。 In August of the second year of Emperor Suzong's Qianyuan reign, a special imperial decree was issued on the issue of Yuwen officials in prefectures and counties, stating: "Today, there are too many Yuwen officials in various places. They do not perform their duties and just run around in vain. They are about to return to their hometowns and refuse to take up their posts. Considering their residence, they should be treated with sympathy. Yuwen officials in prefectures and counties should be appointed to their respective places. After their terms have been fulfilled, they will be given a salary. One or two of their original qualifications will be reduced and they will be retained. Those who have committed crimes in the past are not included in this limit. Among the Yuwen officials, those who are capable and have served in prefectures and counties before can also be retained. There should be no more than five people in each upper prefecture, no more than four in a middle prefecture, and no more than three in a lower prefecture. There should be no more than one person in an upper county or above." This shows that there were already many Yuwen officials in the second year of Qianyuan reign, and the court had to limit the number in each prefecture. 「清明節河畔」の「王元外」旅館 一般的に言えば、武則天の治世中に、才能を引き付けるために科挙制度を開発・改善し、官吏や考試官に立候補することを認め、元外官吏の地位を確立し、元外官吏の急増につながった。唐堯によれば、「元外と鑑修の官位はいずれも神龍帝の治世以降に与えられた。」 唐の玄宗皇帝が即位した後、彼は祖母の振る舞いに非常に不満を抱きました。官吏、検事、監察官を全て解任する勅令が発布され、今後これら三官吏の任命について明確な規定が設けられた。 「開元の改革以前には、元外官吏や検事などの斜称官の職はほとんど廃止されていた。皇室に軍事的貢献をした者だけが再任されない。今は降格された者だけが元外官吏に任命される。」この記録から、唐の玄宗皇帝以降、元外官を務めたのは主に降格された官吏であったことが分かる。 しかし、明代以降は状況が変わり、「元外」という用語が広く普及するようになりました。 明代の六省の下級官吏として、元外郎の地位は、設立当初から慣習的な設立に至るまで、一定の変化の過程を経た。明代初期には、元の旧制度が踏襲され、六つの部を統括する官房が設けられ、その下に尚書、士郎、郎中、元外郎、州司が属した。人事省が最初に設立されたとき、人事省は総務省、栄誉省、試験省の 3 つの下部組織から構成され、それぞれに副局長が 1 人ずついました。陸軍省は人事省と同じように組織されている。当初は祭祀省が本部として設置され、その下に祭祀省、食糧省、客人省の4つの部署が置かれ、各部署に副部長が1人ずつ配置されました。税務部には第一部、第二部、第三部、第四部の5つの部があり、各部には元外郎1人と一般元外郎2人がいます。法務省は、総務部、比較部、首都官吏部、保安部の4つの下部組織から構成され、それぞれに2人の副部長がいます。当初は、公共事業省とその下部官吏が置かれ、本部、陸軍省、水資源省、軍事農場省の4つの下部部局が置かれていた。本部には2人の副大臣がおり、他の3つの部局にはそれぞれ1人ずつ、合計31人であった。 洪武8年、官房は皇帝に、税部、司法部、工部の事務が複雑であると報告し、人員の増員を要請した。その結果、税部5部の副部長が2人に削減され、司法部と工部の4部が追加され、各部に2人の副部長が配置された。6つの部署の副部長は合計38人に増加した。 洪武13年、胡惟容事件の後、明の太祖朱元璋は書記官制と宰相制度を廃止し、権力を六つの省に分割し、六つの省が皇帝に直接責任を負うようにした。六省の規模が拡大するにつれ、その傘下機関の人事体制も充実していった。 この時期、6つの省はそれぞれ4つの下部組織に分かれ、それぞれに1つの院外郎が置かれ、比較的統一された体制がとられていた。彼が所属していた省庁の名称は清理司に変更されたが、職員構成は慣例通りのままであった。洪武23年、税務部と司法部は12の部署に分割され、それぞれに副部長が1人ずつ置かれた。宣徳10年、清礼司の数は13人に増加し、それぞれに元外郎が1人ずつ配された。各司法省には、税務省の制度に似た独自の職員がいた。この期間中、6つの省庁に合計42人の院外郎がいた。後期には、税務部が四川省と雲南省にそれぞれ1名の元外郎を追加したが、これは一時的な任命と解任であり、固定的な政策ではなかった。 明代中期から後期にかけて、庶民の間でも元外という称号が使われるようになったが、これは正式な称号である元外郎とは異なっていた。世俗化した元外は政治や政策決定に参加する機能を持っておらず、朝廷の役人ではないため、当然、官吏の元外郎としての権利や義務も持っていなかった。世俗化した元外は正式な元外郎ではないし、役人でもない。彼らは「元外」と呼ばれていますが、一般の人々の目には役人ではありません。彼らと本物の役人の間には、家系の面でもまだ違いがあります。 この時代の「元外」はもはや官職としての地位を持たなかったため、そのような称号は単なる尊敬称に過ぎなかった。 『二科排安経記』の「程超鋒が首なし女に遭遇し、王童班双雪が不正があったことを知る」という章には、恵州直隷県に程という名の富豪がいたという記録がある。地元の慣習により、人々は富豪を超鋒と呼ぶのに慣れている。 「金持ちの人を『元外』と呼ぶのと同じように、あなたはいつも彼を尊敬しています。」 『龍陽易史』には、さらに具体的な記録がある。「廬陵に千坤という役人がいたという。この役人は人事部、内務部、礼軍部、懲罰部の役人ではなかったが、二厘の紙幣を持っていたため、人々は彼の名声を称えた。」 『連成秘』では、女性が莫大な財産を築き、夫に名官の称号を与えた。 明清時代には、多くの官僚が豊富な財産を持ち、裕福な生活を送っていました。彼らの記録である手記や小説には、「百万の財産」「裕福」「非常に裕福」「金持ち」などの言葉がよく使われ、彼らの富の豊富さが強調されています。例えば、「連成壁」の楊氏は「数百万ドルの資産があったので、人々は彼を楊百万と呼んだ」。 明清時代の小説には、こうした民間官僚に関する記述が多く残されており、当時の官僚は主に町や都市に集中しており、農村部にはほとんどいなかったことも分かります。これは主に、当時の社会の富が都市部に集中していたためであり、元外朗の世俗化は富に基づいていました。私たちが目にする元外と呼ばれる人々はすべて裕福な家庭の出身であり、そのほとんどは産業や商業に従事していました。 テレビドラマ「西遊記」の高元外は、まさに当時の元外の姿と一致していると言える。 しかし、これらの役人は、時には朝廷が民衆を統制するための手段でもありました。明朝政府は社会の安定を確保するために、太祖朱元璋の治世以来、里家制度を実施し、老人制度を補助として農村社会を効果的に管理するために使用しました。明朝初期、政府は税金を多く納めている人や裕福な家庭の人を穀物長や村長に任命しました。これらの人々は「元外」と呼ばれていました。彼らは、政府主導の組織的枠組みに彼らを組み込むことで彼らに対する制約と統制を強化するだけでなく、この集団を通じて社会統制の目的を達成しようとします。明代の社会経済の発展に伴い、農村の草の根組織も絶えず変化しました。 朝廷の統制手段として、元外は社会救済などの一定の社会的責任も果たさなければならなかった。 『世に目覚める物語』第31巻には、張さんはいつも親切で寛大だったと記録されている。12月初旬に大雪が降ったとき、張さんは人々に倉庫を開けて貧しい家庭にお金と穀物を配るよう求めた。 明代には、官僚の出身者もいたが、清代、特に中期から後期にかけては、「元外」は基本的に「富豪」と同義語となり、一部の裕福な実業家は基本的に「元外」と呼ばれ、この言葉は完全に一般的なものとなった。 |
<<: 姿を消した柔然はどこへ行ったのか?中国文明への大きな貢献
>>: 聖母皇太后と太后皇太后は違うのではないですか?どちらの方がランクが高いでしょうか?
推薦する
北宋時代の軍事書『武経宗要』全文:第二巻、第16巻
『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...
北周の武帝、宇文雍の息子の一覧。宇文雍には何人の息子がいたでしょうか?
北周の武帝宇文雍(543年 - 578年)は、字を倪洛團(にらくと)といい、鮮卑族の人で、代県武川の...
『長湘寺 西梅』の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】寒さが来ます。温もりが促す。咲く時もあれば、枯れる時もある。ディンニンの花は遅く咲きま...
武陵擂茶には長い歴史がありますが、現代ではどのような特別な作り方をしているのでしょうか?
五陵雷茶は洞庭湖一帯で長い歴史を持っています。2000年以上前、馬遠が軍隊を率いて南下し、司馬坎城(...
上官万児の古詩「勅命に応えて、立春の日に内殿の宴会に奉仕し、勅命に応えて色とりどりの花を切った」の本来の意味を鑑賞
古代詩:「勅命に応えて、内宮の春の初めの宴に出席し、勅命に応えて色とりどりの花を切る」時代: 唐代著...
グルメが流行した宋代に火鍋はなぜ「博下宮」と呼ばれたのでしょうか?
中国絵画の歴史には、宋代の文人や学者が茶を飲みながら集まっている様子を描いた「文会図」という絵があり...
周徳衛はどのようにして亡くなったのですか?五代十国の有名な将軍、周徳衛は何年に亡くなったのですか?
中国五代を代表する名将。名は鎮遠、号は楊武。朔州馬邑(現在の山西省朔県)の出身。彼は勇敢で機知に富み...
水滸伝における劉唐のイメージとは?彼らと涼山の英雄たちとの違いは何でしょうか?
劉唐に非常に興味がある方のために、『Interesting History』の編集者が詳しい記事を参...
商王朝の官僚制度はどのようなものだったのでしょうか?官僚制度にはどのような2つの種類がありますか?
今日は、Interesting Historyの編集者が商王朝の官僚制度についての記事をお届けします...
三国時代の呉の将軍、周泰はどのようにして亡くなったのでしょうか?
三国時代の呉の将軍、周泰はどのようにして亡くなったのでしょうか?周泰は、雅号を有平といい、九江の下菜...
秦の始皇帝の治世中に国内で反乱がほとんど起こらなかったのはなぜですか?
秦の始皇帝といえば、歴史上さまざまな評価を受けてきました。始皇帝は史上最も偉大な皇帝だと言う人もいれ...
古代軍事著作『江元』:第2巻:『江元』全文とその翻訳と注釈
『江源』は、将軍の在り方を論じた中国古代の軍事書です。『諸葛亮将軍園』『武侯将軍園』『心中書』『武侯...
ヌルハチの姓は何ですか?ヌルハチの姓についての推測は何ですか?
ヌルハチとその後継者がアイシン・ジョロという姓を持っていたことは疑いのない事実のようです。アイシン・...
『紅楼夢』の栄果屋敷はどの程度豪華だったのでしょうか?
『紅楼夢』の栄果屋敷の豪華さはどの程度でしょうか。曹雪芹は、施夫人が主催した2回の宴会の描写を通じて...
「申子を江東に返す」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
沈子を江東に送り返す王維(唐代)楊柳渡し場には乗客が少なく、漁師たちが臨斉に向かって漕いでいます。恋...