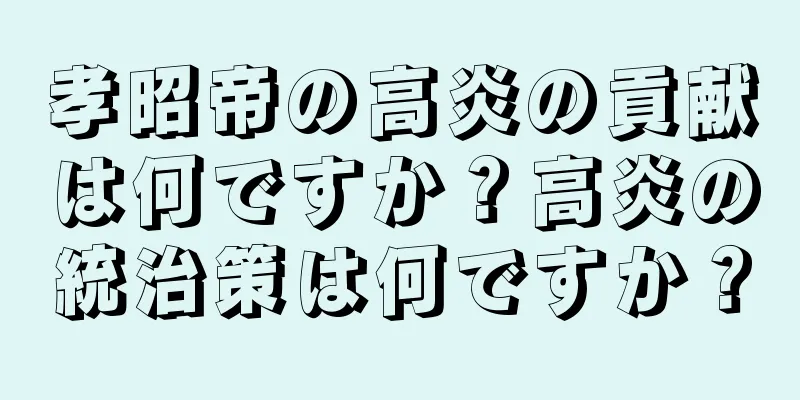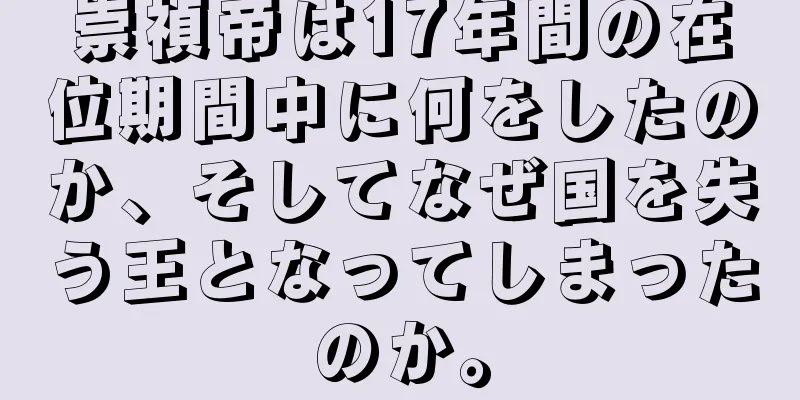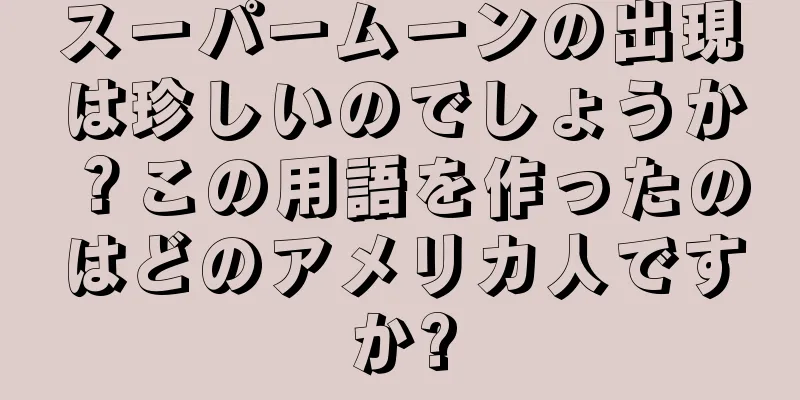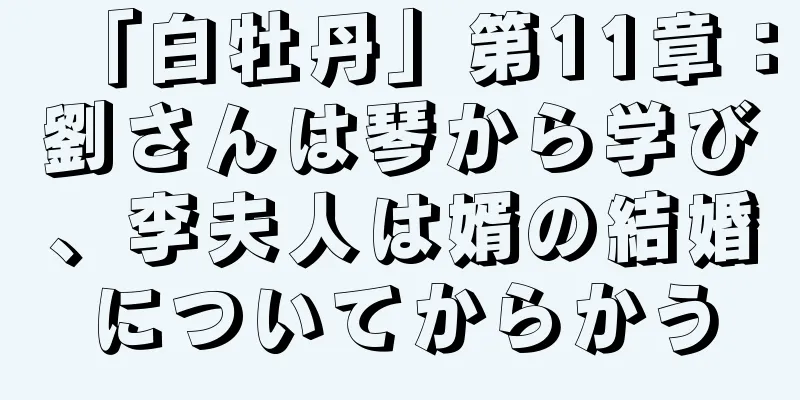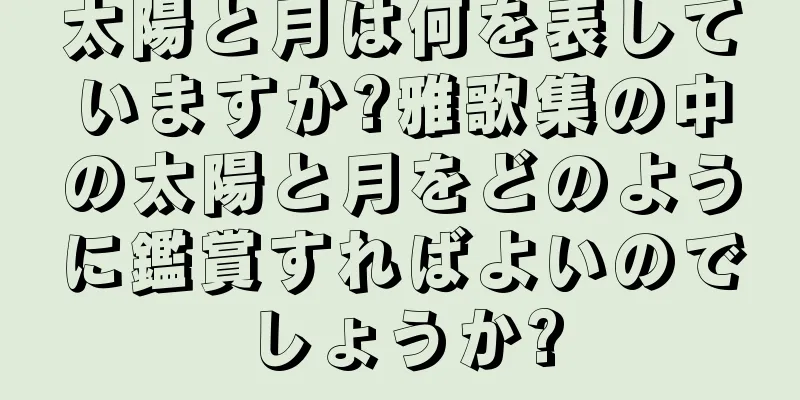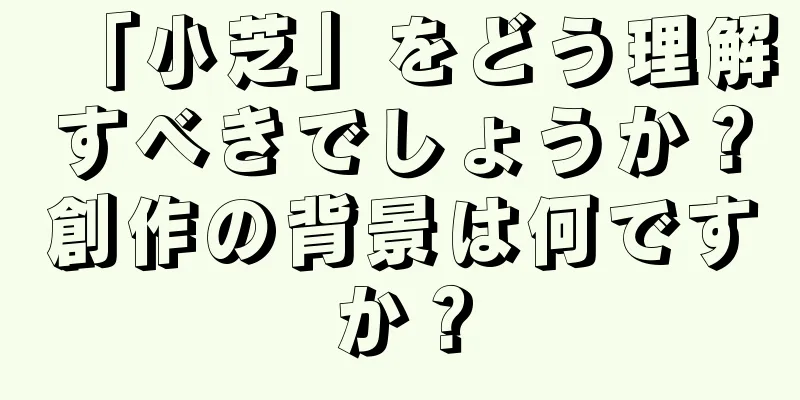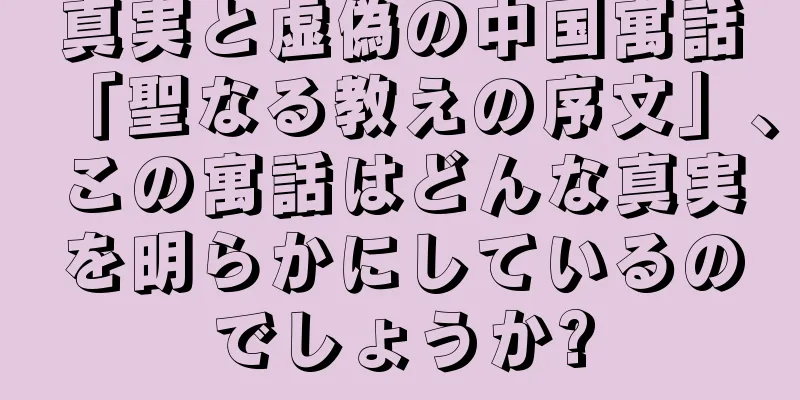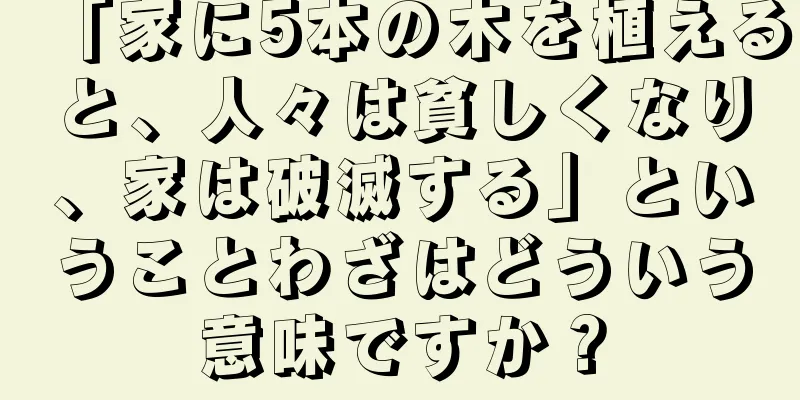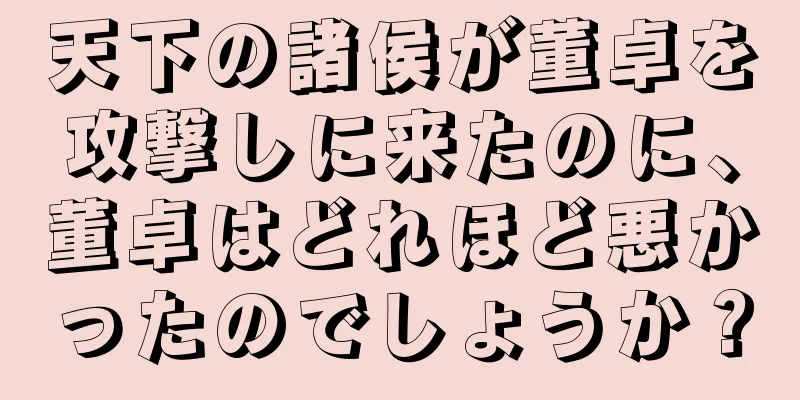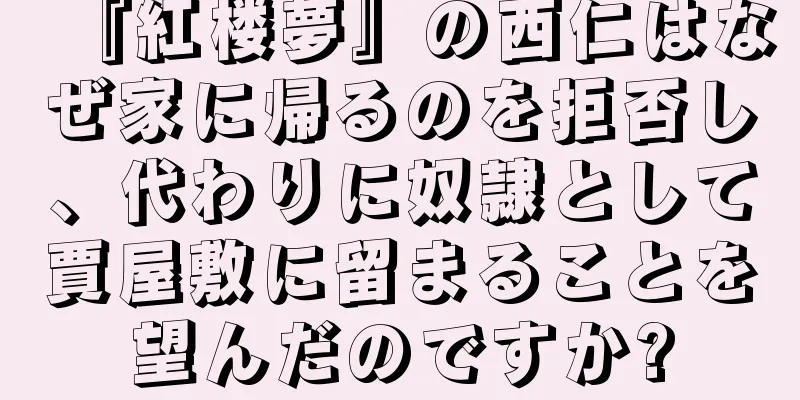唐使とは何ですか?唐の使節の役割は何ですか?
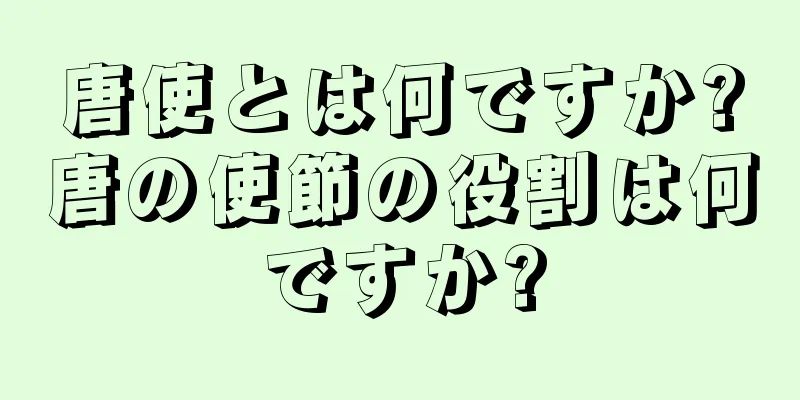
|
唐の使節とは何ですか? その役割は何ですか? Interesting History の編集者が詳細な関連コンテンツを提供します。 1. 遣唐使の派遣 日本の王室は、隋・唐の統治経験や先進的な科学・文化を吸収するため、中国や唐に何度も使節を派遣し、友好関係を築きました。舒明天皇2年(630年)から観応6年(894年)にかけて、計19人の遣唐使が派遣され、そのうち13人が無事に出発し長安に到着した。 唐に派遣された使節には、大使、副使、判事、記録官の4つの階級がありました。大使の上には、特別な権限を持つ使節や代表者がいることもありました。これらの人物は、古典や歴史に精通し、文章に優れ、唐代の情勢に精通し、あるいは特別な技能を持つ人物の中から選ばれました。使節団の構成員は、航海責任者(船長に相当)、造船頭、船長、船大工、曳船長、召使(高官に仕える召使)、操舵手、甲板長、船乗り、弓手、雑使、通訳、主神(神官)、医師、陰陽師、画家、史家、占い師、楽長、音響家、玉器家、鍛冶家、鋳造家、工人(職人)であった。留学生の同行者も多く、前期は約250人、後期は約500人、ピーク時には600人を超えるほどの人数が集まりました。これは世界の古代史上稀に見る、友情と学問の大規模な使節団であったことが分かる。 2. 遣唐使のルート 初期の唐の使節は2隻の船で中国へ渡り、各船には約120人が乗船していました。後期には、通常4隻の船で渡航しました。一行は難波の三ツ浦(現在の大阪市南区三ツ利付近)を出発し、瀬戸内海を西に渡り筑紫の大津浦(現在の博多)に向かいました。ここから中国へは北ルートと南ルートの2つのルートがあります。北ルートは大津浦から始まり、壱岐、対馬を経て、朝鮮半島の西海岸に沿って北上するか、仁川付近で西に転じて黄海を渡るか、あるいはさらに北上して中国の遼東半島の東海岸に沿って進み、最終的に渤海湾口を越えて山東半島の鄧州地域に上陸するルートである。これは、西暦 8 世紀以前に唐王朝に遣わされた使節が一般的に通ったルートです。この航路は時間がかかりますが、海岸近くを航行するため安全です。南行ルートは2つあり、一つは大津浦を出航し、筑紫の西海岸に沿って南下し、屋久島、奄美(大島)を経て東シナ海を渡り、長江河口に至るルートです。 701年以降、朝鮮半島を統一した新羅と日本との緊張関係のため、唐に遣わされた日本の使節のほとんどはこのルートを取った。当時、南西諸島は日本に属しており、これらの島々を経由して唐王朝に到達することができました。もう一つのルートは、大津浦から筑紫郡千賀島(現在の五島列島と平戸島)までで、そこから東シナ海を渡り揚子江の河口まで続きました。これは、西暦 7 世紀 70 年代以降、唐王朝への使節がよく通ったルートです。このルートが選ばれたのは、南島経由のルートは時間がかかるだけでなく、東シナ海を渡るリスクも伴うためです。リスクは同じなので、筑紫から直接東シナ海を渡った方が、行程が短くなり、時間の節約になります。南ルートでは東シナ海を横断する必要がありましたが、造船技術や航海技術が未熟で海洋気象に関する知識も不足していたため、これは極めて困難でした。遣唐使は往来の途中で嵐に遭遇することが多く、船が破壊されて人が亡くなったり、南の島に流されて島民に殺されたりした。 III. 遣唐使の使命と役割 代表団のメンバーは唐代で過ごした約1年間を利用して、唐代の科学と文化の知識を積極的に学びました。例えば、多治比郡守はかつて四門の趙玄墨から経文を学び、判官藤原貞俊はピアノが上手で、唐代には上都の劉二朗から琵琶を学び、凡庸な医師で嘱託医の応元帝神も唐代に医学を学び、帰国後は鍼灸医や主治医として日本医学の発展に貢献した。当時、長安は唐代の文化の中心地であっただけでなく、ペルシャ、インド、ビザンチン、中央アジア、南シナ海などの東西文化が集まる場所でもあり、代表団メンバーの学習内容はさらに充実しました。 唐の使節は貿易使節としても機能した。雍に到着した後、彼らは唐朝に日本政府から贈られた贈り物を献上したが、主に銀、リボン、絹、綿、布などであった。帰国の際には、主に色とりどりの絹、香辛料、薬品、手工芸品など唐朝からの贈り物を持ち帰った。これは、相互の贈り物の形での二国間の貿易と見ることができます。もちろん、これらの贈り物は直接市場に出回るわけではなく、主に皇帝や貴族の贅沢なニーズを満たすために使われました。それにもかかわらず、唐の借金は依然として貴族や大臣の間で取引されていた。「建里門の前には3つのイナゴが立てられ、さまざまな唐の品物が並べられ、内陣にいる盲人や宦官はそこで取引を行い、これを官市場と呼んだ。」[注11]このように、唐の借金の一部は必然的に首都の市場に流れ込み、貿易の役割を果たした。 同時に、日本朝廷は使節団の身分に応じて旅費として絹、綿、布などを分配し、大使と副使には大量の砂金を与えた。唐朝も日本の使節に贈り物を贈りました。そのため、使節団が日本から中国に持ち帰った品々は貿易に利用することができ、唐代の品々を大量に購入して日本に持ち帰り、資本市場に流入させることができた。唐の使節は官僚や商人としての役割も果たしていたことがわかります。 唐の使節には、学生や僧侶を唐に留学させ、学業を終えた彼らを母国に連れ戻すという重要な使命もありました。例えば、吉備真備、玄昉、最澄、空海などは遣唐使の船に乗って日本と唐を行き来しており、遣唐使は日本と唐の文化交流において非常に重要な役割を果たしました。 4. 唐に留学した学生 唐に留学する学生は留学生と学僧に分かれており、一般的には才能のある貴族の子弟や僧侶から選ばれました。留学生は皇学院の6つの学院のいずれかに入学し、それぞれの専攻を学び、僧侶は主に長安、洛陽などの主要な寺院で仏教を学んだ。木宮安彦の『日中文化交流史』によれば、唐代に留学した留学生は約144名で、そのほとんどは僧侶であり、留学生はわずか14名であった。平安郎以前には、唐に派遣された中国の留学生は皆、そこで長い期間勉強し、中には20年から30年も勉強した者もいた。彼らの日常生活は唐の人々と同じです。留学生の中には、唐で結婚して子供をもうけた人もいます。彼らは長期にわたって中国人との共同生活と勉学に励んだため、文化知識だけでなく生活習慣も唐代の影響を強く受け、日中文化交流と日本社会文化の発展に多大な貢献を果たした。例えば、大岡禅は長安の官学で古典や歴史を学び、帰国後は大学の助教授を務めた。長岡大和は唐で唐法を学び、帰国後は吉備真備とともに唐法二十四ヶ条を改訂した。鄭英元は唐で医学を学び、帰国後は鍼灸院の医師を務めた。桀達子は唐代に文才で名高く、帰国後は書道を奨励した。他にも、阿倍仲麻呂、吉備真備、空海、最澄、玄昉、円珍、円仁といった有名な人物がいます。 阿倍仲麻呂(698-770)は、717年に唐に入り、学問を修めた後、唐に仕えた。趙衡という名を授かった。経蔵(第九位下)、左舎利帥(第八位上)、左夫易(第七位上)、李礼王(唐の玄宗皇帝の12番目の息子)の有、衛衛少卿(第四位)、衛衛青(第3位)、秘書長(第3位、経書を担当)を歴任した。彼は詩や散文に優れ、唐代の詩人である李白、王維、朱光璋、趙弼などと親交が深かった。趙衡が753年に中国に帰国したとき、多くの詩人が彼に別れを告げる詩を書いた。王維の詩にはこうある。「故郷の木は扶桑の木の外にあり、師匠は孤島にいる。異国の地で離れ離れになっているが、それでも連絡は取れる。」途中で、彼は安南に飛ばされた。李白は彼が難破船に遭ったと勘違いし、彼を悼む詩を書いた。「倭寇は皇都を離れ、遠征の帆は澎湖を回った。明るい月は戻ってこず、青い海に沈み、白い雲が蒼梧を憂鬱で満たした。」この愛情あふれる詩は、古代の日中友好の歴史における美しい物語です。 755年、趙衡は長安に戻り、左侍(三位下)、鎮南守、鎮南解度使(三位)を歴任した。彼は770年に長安で73歳で亡くなった。唐朝は彼に死後、蘆州太守(二位)の爵位を贈り、日本政府は彼に死後、二位の爵位を贈った。 吉備真備(693年 - 775年)は717年に長安に行き、阿倍仲間に師事し、35年後に日本に帰国した。唐代に17年間滞在し、古典、歴史、天文学、軍事、音楽などの知識を学び、帰国の際には「唐暦」や暦、音楽書、楽器、武器などを持ち帰りました。帰国後、大学の助教授として五経、三史、法律、算術、音韻、篆書などを教える。持ち帰られた「唐暦」は越元朝廷の礼法に大きな影響を与え、天平宝字7年(763年)に大延暦が豊暦に取って代わった。 752年、真備は副使として唐に帰国した。 754年に帰国後、宰相に任命され、易図城を建設した。称徳天皇の治世に従二位右大臣を務めた。作品に『私設教授コレクション』などがある。彼は唐の文化を日本に紹介する上で重要な役割を果たした。 空海(774年 - 835年)は804年に使節藤原桂野麻呂とともに唐に渡り、長安の青龍寺で慧果のもとで密教を学んだ。 806年に中国に帰国後、真言密教を広めた。 816年、高野山に金剛峯寺が建立され、日本における山岳仏教の始まりとなりました。 828年、教育を普及させるために京都に荘子院が設立されました。空海は詩文や散文に優れ、『文経密譜』『文必演心潮』『残礼万象易明』などの著作がある。死後、彼は洪法師と呼ばれた。 最澄(766年 - 822年)は、804年に空海とともに唐に渡り、天台山の国清寺で道遂と興曼の師のもとで密教を学びました。翌年、彼は230冊の仏典を携えて中国に戻り、天台宗を宣伝し、南道諸宗に対抗して大乗戒壇を確立した。 『先界論』『国境を守る篇』を執筆。死後説教の達人となった。 玄芳(?-746年)は、716年に吉備真備とともに唐に入朝した。唐の玄宗皇帝は、玄芳に紫の法衣と三位の官位を与えた。 735年、五千冊以上の経典や論書、仏像などを携えて帰国し、興福寺で法華経を広めた。聖武天皇の母・藤原宮子の病気を治したことにより宮中に入り政治に参加した。その後、聖武天皇の寵愛を受けて管長に任じられ、吉備真備とともに国政に影響力を発揮した。しかし貴族たちの反対に遭い、筑紫観音寺に配流となった。 円仁(794年 - 864年)は838年に唐に入唐し、唐代に顕教と密教の両方を学びました。帰国後、天台宗を広め、常行三昧堂を建立し、比叡山仏教発展の基礎を築きました。彼の著作『唐代求法紀行』は唐代の社会を理解するための第一級の情報源である。易爾傑師匠。 袁貞(814年 - 891年)は853年に唐に入り、唐代に天台宗を学びました。 858年に日本に帰国し天台宗を創始した。 『法華経注釈』『大日如来入門』を著した。易之政先生。 |
<<: 「四佳橋」という名前はどのようにして生まれたのですか?四家橋と何志章の関係は何ですか?
>>: 「牛・李派閥争い」と「派閥争い」の違いは何ですか?なぜ結果が異なるのでしょうか?
推薦する
古代には電気がありませんでした。古代の人々は夜をどのように過ごしていたのでしょうか?
Interesting History の編集者をフォローして、歴史上の古代のナイトライフを探索しま...
中国古典の鑑賞:『春秋実録』朱子雨蕾第83巻原文
△プログラム春秋実録には理解しにくいところがある。水泳。春秋実録は難解だと言われるが、ある理論によれ...
劉長青の「雪中蓮山滞在」:労働者の貧しい生活への共感
劉長清(生没年不詳)、法名は文芳、宣城(現在の安徽省)出身の漢民族で、唐代の詩人。彼は詩作に優れ、特...
聶小倩と寧才塵:愛と信仰を運ぶ生死の別れ
中国の古典文学において、『中国奇譚』は、その独特の魅力と深い人間的関心によって強い足跡を残しました。...
第91章: 壁に挿入されたコイン
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
『新説世界物語』第63話の原文は何ですか?どう理解すればいいですか?
『新説世界物語』第63条の原文は? どう理解すればいい? これは多くの読者が気になる疑問です。次に、...
詩人ヤン・ジダオの独創的でユニークな曲「遠人を想う:晩秋の紅葉と黄色い花」鑑賞
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
戦国時代後期の作品『韓非子』全文と翻訳注
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...
「真夜中の武歌・春歌」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
真夜中のウーソング:春の歌李白(唐)秦の国の羅福の娘が、緑の水のそばで桑の葉を摘んでいる。緑の帯の上...
伝統文化としてのレイチャの主な流派は何ですか?
伝統文化としてのレイチャの主な流派は何ですか?実際、レイチャの製造方法は場所によって異なり、特に材料...
漢の昭帝の皇后、劉福陵とは誰ですか?
孝昭皇后(紀元前88年 - 紀元前37年)は、姓を尚官といい、漢の昭帝劉福陵の皇后であった。彼女は尚...
謝万は北へ戦いに行き、しばしば口笛を吹き歌いながら優位性を示した。
謝万は北伐に出たとき、自分の優位性を誇示するために口笛を吹いたり歌ったりすることが多かったが、決して...
古典文学の傑作「太平天国」:道教第7巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『北亭西郊の医師が降伏文書を受理し帰還軍に提出』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
北庭西郊後鋒大夫は降伏を受け入れ、軍に戻って岑神(唐代)胡国のアルファルファは美味しく、倫台の馬は太...
寒衣祭における祖先崇拝のタブーは何ですか?寒着まつりの民俗行事と注意事項
毎年旧暦10月1日は「十月節」「祖先祭」「明陰節」「秋節」とも呼ばれ、人々は鬼頭節と呼んでいます。こ...