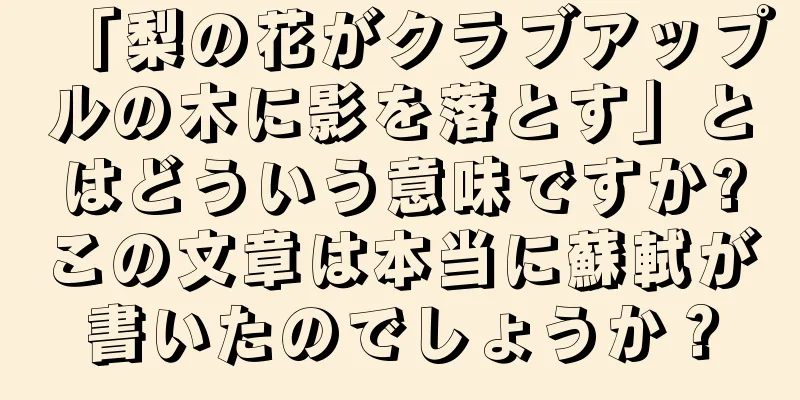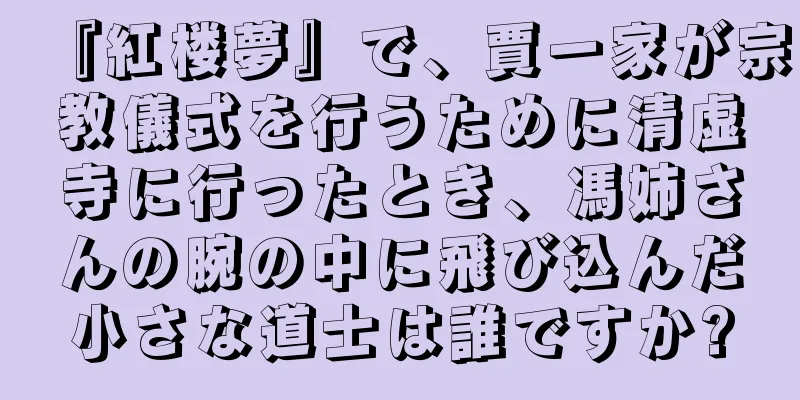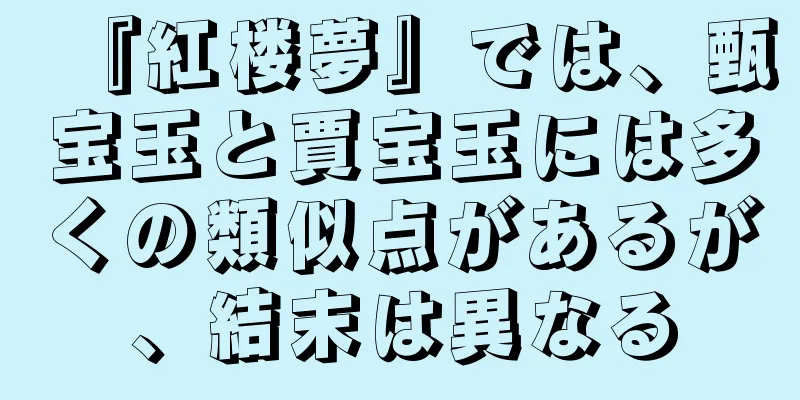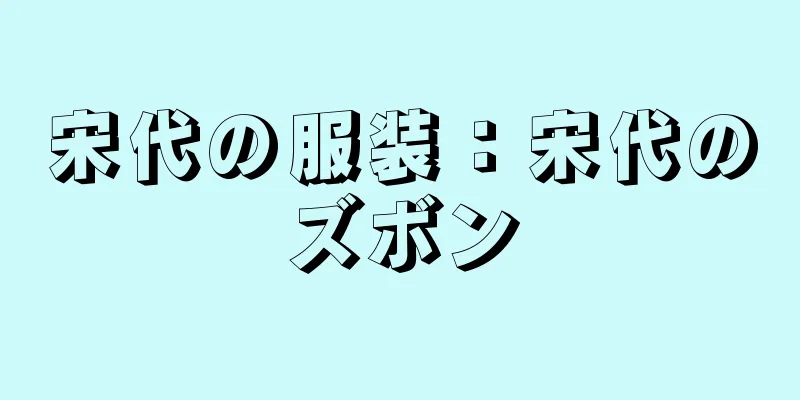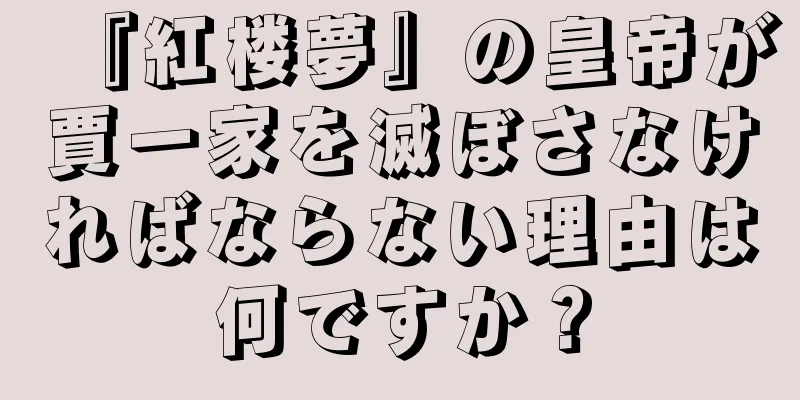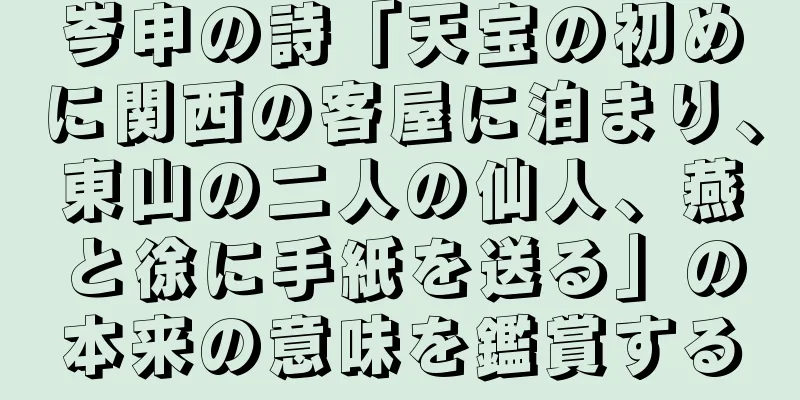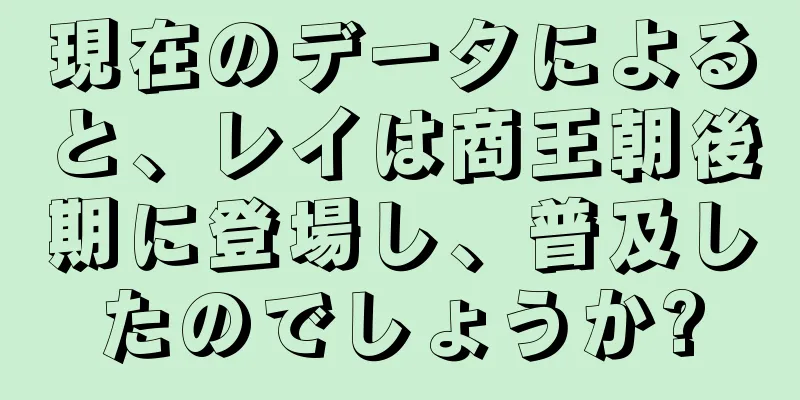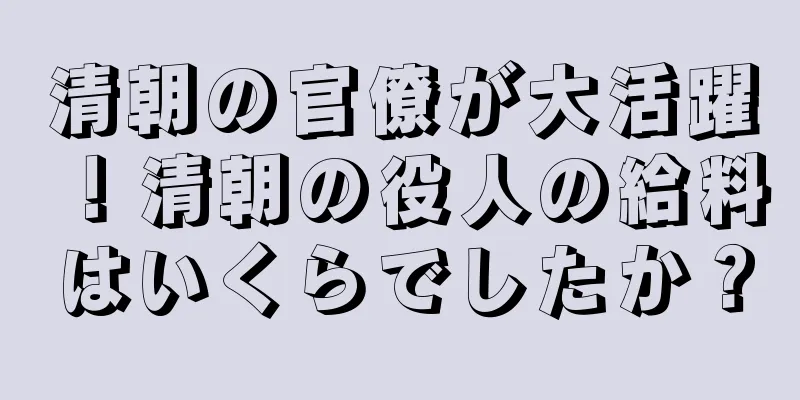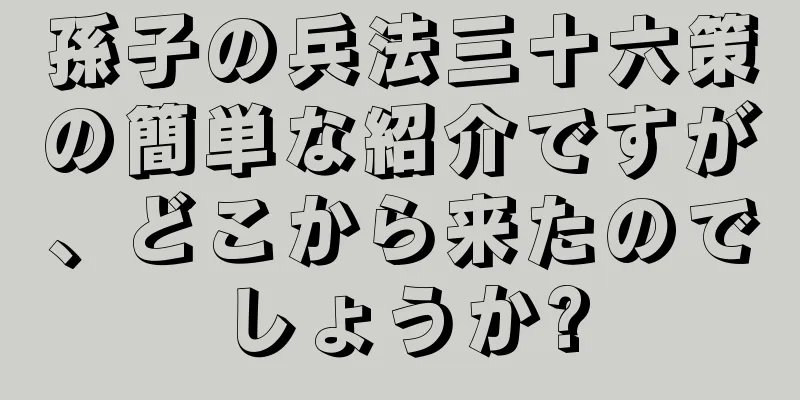「徴兵制度」はいつから始まったのでしょうか?明代の「徴兵制度」の利点と欠点は何ですか?
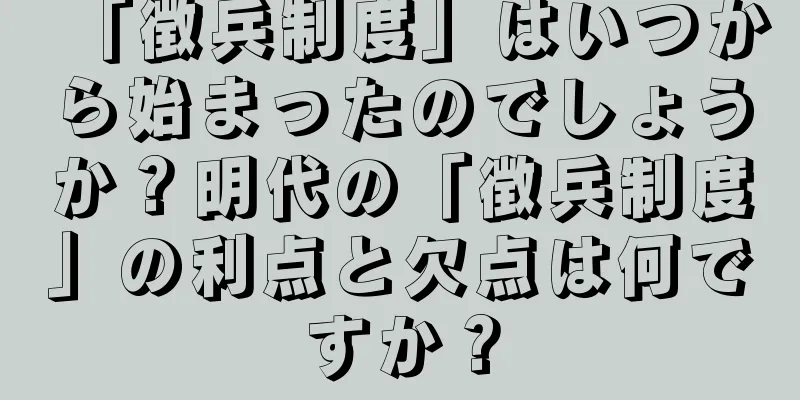
|
「徴兵制度」はいつから発展し始めたのか?明代の「徴兵制度」の長所と短所は何なのか?興味深い歴史の編集者と一緒に理解してみましょう。 徴兵制度は春秋時代に始まり、徐々に徴兵制度に取って代わり、古代の軍事制度改革における大きな出来事となった。宋代の兵士のほとんどは徴兵され、飢えた人々や難民を徴兵することが伝統的な国家政策となった。明代、景帝が即位した後、徴兵制度が再び主流となった。しかし、徴兵制度の欠点は軍事費が比較的高いことであるが、徴兵された兵士の質が高くなるという利点もある。次は、明代が徴兵制度を採用した理由やメリット、デメリットについてお話しします。ご興味がありましたら、一緒に学んでいきましょう。 明朝軍の魏索制度については常にさまざまな意見があったが、常に批判が賞賛を上回った。明朝軍の戦闘能力は「時代遅れ」の管理モデルのため極めて低く、明代中期から後期にかけての大規模戦争の圧力に耐えられなくなった。そのため、明代の君主や大臣は後に駐屯軍制度に代えて大隊制度を導入した。 しかし、この改革は一夜にして達成されたわけではなく、また明王朝にとって完全に有益だったわけでもなかった。 まず、Weisuo システムが誕生した背景についてお話ししましょう。洪武帝が「韃靼を追放し、中国を復興させた」後、明の軍隊の規模は前例のないレベルに達し、「建国当初、衛兵491名、駐屯地311か所」、兵士総数は約310万人に達した。明代初期には軍隊に不足はほとんどなかったため、この数字はかなり信頼できる。つまり、国が平定されたばかりで、国の生産力がまだ回復しておらず、国の生産人口も少なかった当時、明の軍隊の規模は300万人以上に達し、後期明朝の常備軍の3~4倍の規模であり、当時の社会にとって耐え難いものであった。 しかし、性急な軍縮は、社会に大量の引退した兵士を瞬く間に生み出し、社会の安定を損なうだけでなく、新設された明の政権を脅かすことになるため、軍営と駐屯地制度の実施が唯一の選択肢となった。 衛朔制度は明軍の戦闘能力が低かった根本的な原因であった。これは、明代初期の駐屯地の設計からもわかる。「兵士の十分の三は城の警備を担当し、十分の七は農業を担当する」。土地の肥沃度に応じて、軍隊の配置には別の計画があるだろうが、農地に駐屯する兵士の数は、戦闘兵士の数をはるかに上回っている。洪武帝はまた、五軍の将軍たちにこう言った。「今、国は平和で、国境は安全だ。兵士たちがただ座って農民から食べ物をもらっているだけでは、農民は苦しむだろう。これでは長期的な安定は確保できない。全国の駐屯軍に命じて兵士たちが作物を植えるのを監督させ、兵士と農民を一体化させ、国の出費を軽減すべきだ」。彼の目標はすべて、生産需要を満たすことだった。 したがって、魏索制度下の明軍の戦闘力が弱かったのは当然であり、その当初の設計意図は、膨大な軍事人口とまだ成長していない生産人口との間の矛盾を解決することであった。 明代初期の魏索制度が洪武帝の目標を達成したことは事実が証明している。各魏索は自給自足だっただけでなく、余剰があったものもあった。例えば、国境地帯の塩水鎮には「10万トン以上の食糧と飼料」があった。しかし、このような制度では、駐屯軍の大半は軍事訓練を受けたことがなく、あるいは訓練の強度も不十分であった。また、兵士は終身在職で、中級・下級将校のほとんどが世襲であったため、部隊の高齢化は深刻で、昇進の余地はほとんどなく、戦闘能力は極めて低かった。せいぜい、地方の治安維持くらいしかできなかった。当初はこれが目的でした。しかし、後には大規模な戦争にも利用されるようになりました。例えば、永楽年間には、6回の北伐、3回の安南攻撃、北西進攻があり、その兵力は数十万規模で、駐屯軍も多数含まれていました。 渭朔制度は一時的なものに過ぎず、改革は急務であった。前述のように、衛戍制度の本来の目的は、建国初期に兵農を一体化し、生産力不足の問題を解決することであった。中期から後期にかけて、国の生産力が徐々に回復し、生産人口が増加したため、衛戍制度の存在意義は薄れた。政府は徐々に計画的に軍制を改革し、衛戍制度を徐々に廃止すべきである。 永楽帝はこの点を非常に明確に認識していたため、北京に遷都した後、直ちに北京駐屯地を設立し、20万人以上の常備軍を訓練した。また、九辺などの駐屯軍を徐々に職業軍人に置き換えていった。しかし、広大な内陸部には、土地や記録はあるものの人がいない「幽霊駐屯地」が今も数多く存在し、将校たちの忙しさは深刻で、駐屯地を脱走する兵士も増えている。しかし、一連の政治的出来事により、この改革は無期限に延期され、事態はますます制御不能となり、魏蘇制度は徐々に歴史の舞台から退いていった。 その後の戦争により大隊制度が誕生した。洪武帝の後の5代皇帝である明朝の英宗皇帝の正統帝の時代に、改革は徐々に始まりました。トゥムの戦いの後、明軍の北京駐屯地はほぼ完全に破壊され、各地の国境防衛は危機に瀕していました。その後、モンゴル族が北京に侵攻しました。駐屯軍が役に立たなくなったり、不十分になったりしたため、明朝は皇帝の検閲官を内陸部に派遣して兵士を募集しました。 その後、戦争が続くと、兵力不足を補い、随時兵力を補充するために、徴兵が常態化し、嘉靖年間には大規模に実施され、駐屯軍制度は完全に廃れ、徴兵が明軍の主力となった。 徴兵された兵士は大隊兵士と呼ばれ、その組織や待遇は守備隊とは異なっていた。 大隊制では将軍、副将軍、中将、遊撃将軍、千人指揮官、大隊指揮官などに分かれ、衛兵制では総司令官、副司令官、千戸、百戸、将軍旗、小旗などに分かれていた。衛兵は約5,600人で構成され、大隊の兵力はおよそ2,250人から4,500人の間です。駐屯地の兵士たちは耕作する土地を与えられ、駐屯地の兵士たちは軍の給料を受け取った。 徴兵制度の実施後、明軍の戦闘力は大幅に向上しました。最も有名なのは、南東地域の斉家軍と虞家軍、北東地域の関寧騎兵、北西地域の秦兵です。これらの兵士は適齢期に軍に入隊し、プロとして戦います。軍功に応じて褒賞や昇進を受けることができ、階級転換も達成されるため、戦闘士気も高まります。 大隊制度があったおかげで、明軍は国内外の反対勢力と戦うことができた。例えば、万暦年間、明軍は朝鮮に侵攻して倭寇と戦った。兵力は少なかったが、すべて遼東、宣府、塩水、浙江などの精鋭戦闘部隊から集められており、倭寇との戦いに勝利した。もし明朝がこの時点でまだ魏索の制度を広く使用していたとしたら、軍隊の戦闘力は長距離の遠征や長期にわたる戦争に対処できなかったであろう。 大隊制度は明朝の軍事改革の始まりとなったが、最後まで続かなかった。徴兵制度は費用がかかりすぎたからだ。明朝初期は国家財政がまだ潤沢で、対外戦争の激しさも比較的小さかったため、大隊兵士の軍給規模は大きくなかった。しかし、中期から後期にかけては徴兵制が主流となり、徴兵費用もどんどん上昇したが、国の財政はどんどん破綻していった。 小氷期の到来後、農民反乱が相次ぎ、長年悩みの種であったモンゴル族も必死に国境を攻撃した。東北では女真族が台頭し、略奪や虐殺によって華北と東北地方における明朝の勢力を弱めた。明朝は事態に対処するために兵士を増員せざるを得ず、「流を開いて源を減らす」という状況に陥った。 例えば、明代の儒家の将軍譚倫はかつて朝廷で嘆いた。「中国の強みは銃器だ。3万人の兵士を訓練し、3千人のマスケット銃兵に突撃させたい」しかし、「3万人の兵士には、1人あたり1両5銭の銀を与えなければならない。年間の費用は45万で、農務省は資金が不足しているため、私たちが負担しなければならない」。計算してみると、これは兵士1人あたり18両の銀に相当することがわかり、これはすでに税収部と陸軍部を震え上がらせた水準であり、これは龍清時代のことだった。 崇禎年間、財政状況はさらに悪化しましたが、兵士一人当たりの年俸は40両を超えていました。十分な給与が支払われなかったため、反乱が頻繁に発生し、兵士の忠誠心と士気に直接影響を及ぼしました。 さらに深刻なのは、徴兵制度下での軍隊の所属問題だ。明代末期の将兵の私有化問題は常に深刻であった。例えば、各国境の町には大勢の召使がいた。徴兵制度の台頭後、軍隊のほとんどは将軍の所有となった。例えば、浙江省の徴兵制度では、もはや将軍が軍隊を選抜することはなく、将軍が自ら兵士を徴兵する。100人を徴兵すれば大尉に任命され、3000人を徴兵すれば将軍に任命される。 こうして、軍隊の民営化の問題は覆すことが困難になった。崇禎帝が祖国のために亡くなった後、江北には4つの鎮、荊郷には左良宇があり、兵士は100万人近くいた。しかし、これらの兵士はすべて将軍に直接仕えており、彼らの運命は将軍と同じだった。高潔が暗殺された後、軍隊は徐々に崩壊し、分裂し、劉沢清と劉良左は清朝に降伏し、彼らの軍隊は清軍の先鋒となり、黄徳公の軍隊は祖国のために死ぬまで戦い、死んだ。 これらの軍隊の最終目的地は将軍たちによって決められており、彼らは決して朝廷からの命令を受け入れません。これは当然、明代の兵士たちが暮らしていた一般的な環境に関係していますが、将軍たちの個人的な権力の拡大も重要な要因の一つでした。 したがって、いかなる改革も社会的かつ包括的なものでなければなりません。明朝の軍事改革の問題は次の通りであった。 一方では、時すでに遅しで、初期段階で徐々に国情に合った道筋を見出せず、戦争が勃発すると、結果を考えずに突然、軍事力を大規模に拡大した。 一方、後進的な経済体制では、軍隊の莫大な支出を保証することはできない。 同時代、明代の農民の税負担は日本の20分の1、イギリスの40分の1であったが、国民の負担は重く、国家は恒常的な赤字に陥っていた。社会は足かせを破るための全面的な改革を緊急に必要としており、軍事改革だけでは到底不十分であった。 |
<<: 世襲制はどのようにして退位制度に取って代わったのでしょうか?堯、舜、禹の時代の退位制度はどのようなものだったのでしょうか?
>>: 曜変天目とは?曜変天目は一般的にどれくらいの価値があるのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』でデュオガールが使用する方法は何ですか?彼女はどれくらいすごいですか?
中国の伝統文化は歴史が長く、奥が深いです!今日は、Interesting Historyの編集者が、...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第24巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
諸葛亮はなぜ劉備に劉鋒を殺すよう強制したのですか?劉鋒は死ぬ前に何と言ったのですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『旧唐書』巻73にはどんな物語が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
隋の二税法は軽い税と低い賦課金で国を豊かにした。
隋代は当初、北魏の地代・税制を採用し、「50歳以上の者は労役・徴税を免除する」と規定した。労役の代わ...
水滸伝 第25章:何九は葬儀に出席するために骨を盗み、呉二は生贄として人間の首を捧げる
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
その時の李白の別れの気持ちは雄大な巴江のようだったので、「巴霊星別れ」を書いた。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
十九古詩という名前はどのようにして生まれたのですか? 十九古詩とは何ですか?
十九古詩とは何ですか?十九古詩の名前はどこから来たのですか?十九古詩にはどんな詩が含まれていますか?...
汪希峰によって女中に昇進した後、平児の主な仕事は何でしたか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
キルギスの人々は一夫一婦制を実践していますか?
キルギスの家族は一夫一婦制です。昔は宗教の影響で裕福な人の中にも複数の妻を持つ人がいました。男性は大...
『紅楼夢』で青文が追い出されたとき、賈の母は意見を述べませんでした。王夫人と仲違いしたくなかったのでしょうか?
『紅楼夢』では、大観園の捜索の後、青文は叔母の叔父の家へ送り返された。下記の興味深い歴史編集者が詳細...
大師、大導師、大護衛、大宰相、大司令官の正式な役職は何ですか?
古代の官職について言えば、その数は非常に多く、同じ官職でも王朝によって責任が異なり、誰もが少し混乱し...
襄公7年に古梁邇が書いた『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
古梁邁が書いた『春秋古梁伝』には、襄公七年に何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が気になる...
『西遊記』で太白金星が沙生を助けなかったのはなぜですか?
『西遊記』の太白金星は悟空を助け、八戒も助けたが、なぜ沙生を助けなかったのか?次の興味深い歴史編集者...
なぜ人々は龐統の死は彼自身のせいだと言うのでしょうか?彼はよりリスクの高い戦略を好むから
『三国志演義』には優れた軍師がたくさん登場します。彼らは主君を補佐し、覇権を握るのを助けました。軍師...