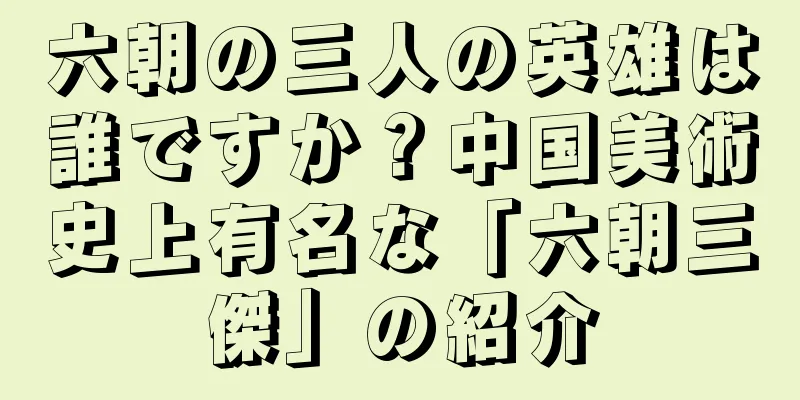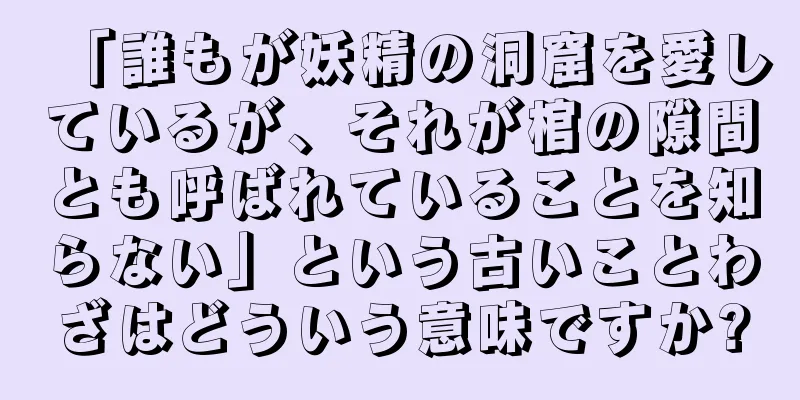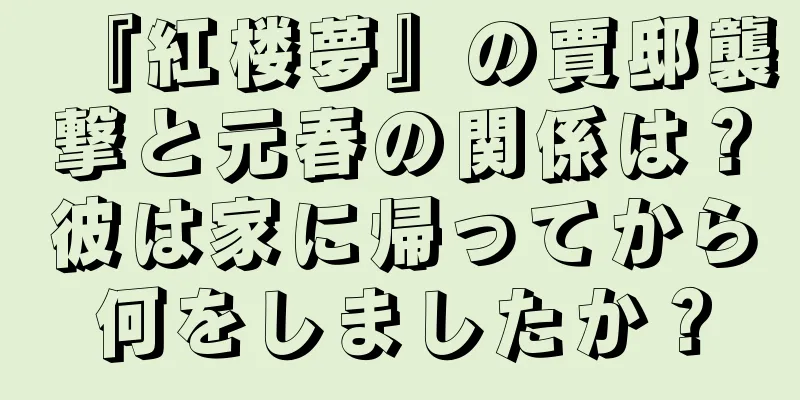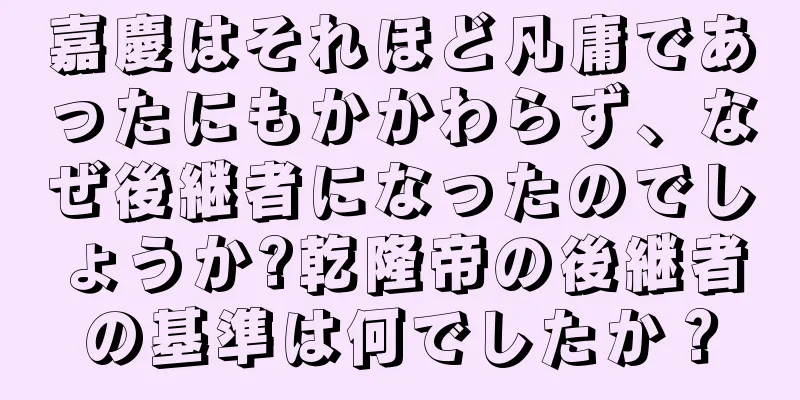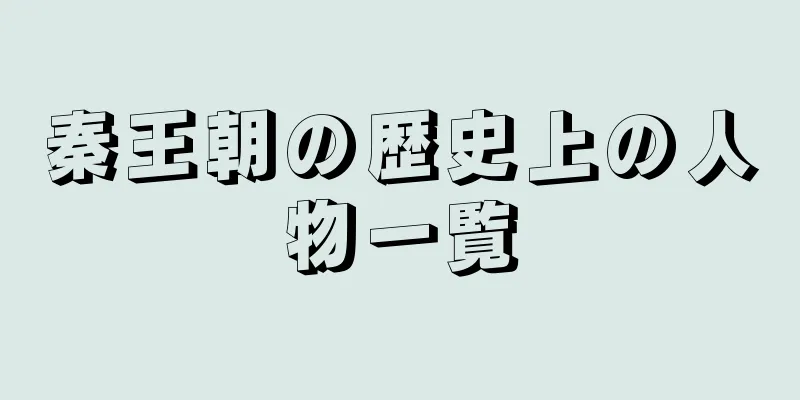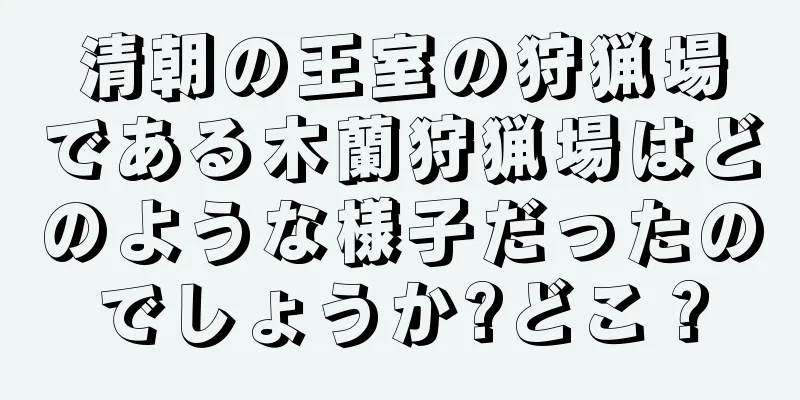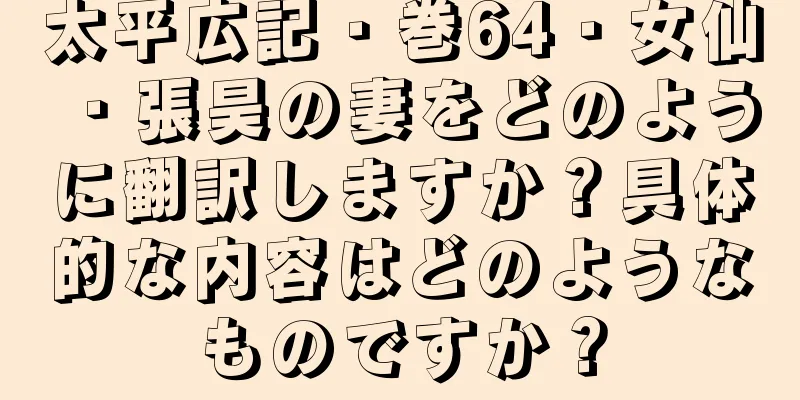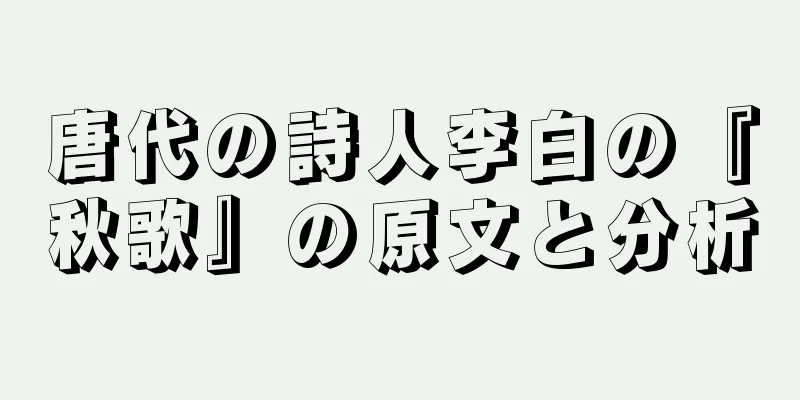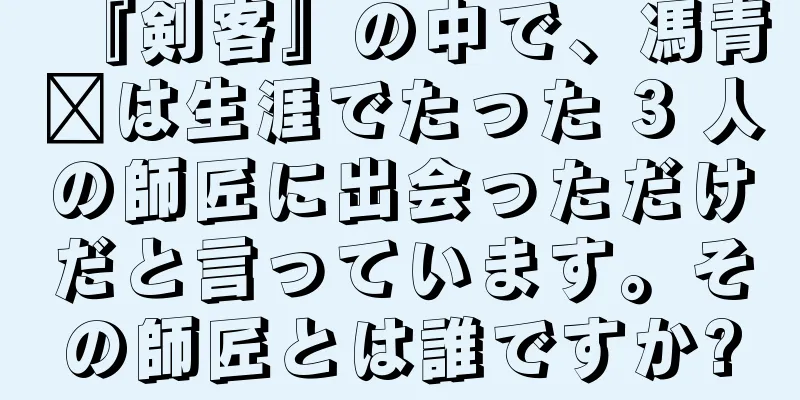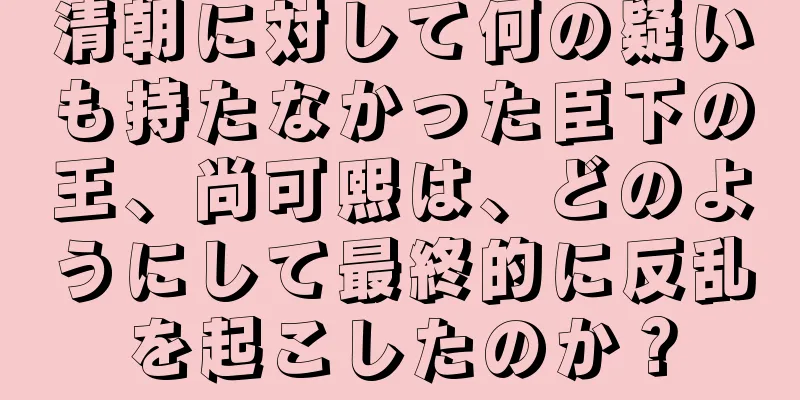太古の昔、最初の人物は「私」ではなかったのか?それがこの武器だったのだ!
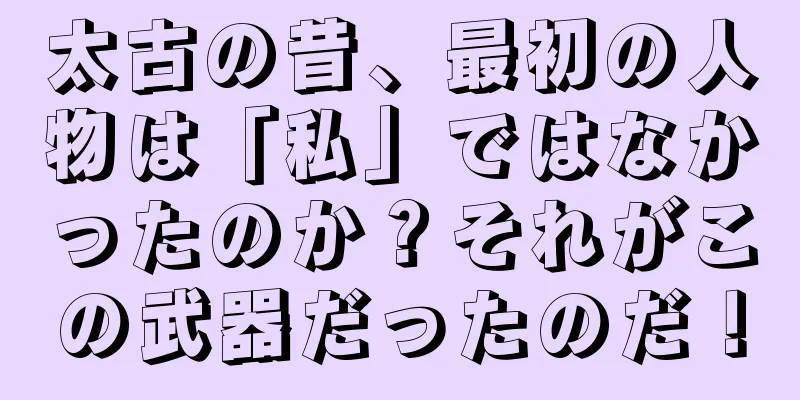
|
古代の一人称は「私」ではなかったのか?実はこの武器だった!よく分からない読者は、Interesting Historyの編集者と一緒に読み進めてください。 「私」という言葉は、今では一人称の表現になっていますが、実は古代では武器でした。現在の一人称代名詞「私」を意味するものではありません。現在の「我」は「伐」「战」「戟」「戣」など、戦闘や殺害に関する言葉と非常によく似ており、古代では「我」がそれらの近縁種であったことを示しています。その意味は現在の「我」とは大きく異なります。 『朔文街子』には「戌は殺生の古語である」とある。戌という武器は商代から戦国時代にかけて流行し、秦代以降は次第に姿を消した。現在故宮博物院に所蔵されている西周時代の青銅製「傅」と、現在陝西省阜風博物館に所蔵されている西周時代の青銅製「傅」によると、「傅」の形は『西遊記』で朱八傑が持っていた鉄の熊手に少し似ているが、「傅」には3本の歯がある。 「I」は長い柄を装備して戦場で切り倒して殺すためにのみ使用できる短い武器です。鋭い三角形のスパイクが切り倒されると、通常の革製の鎧を保存することは困難になります。 古代、「私」が武器だった頃、人々が使っていた一人称代名詞は「私」「私」「無能」「無能」「悪人」「不可触民」、そして「于」「呉」などでした。もちろん、最もよく使われていたのは「于」と「呉」でした。当時、「朕」と「寡人」は皇帝専用の用語ではありませんでした。『爾雅史考』では、「朕は自分を意味する」と説明されています。秦の始皇帝が天下を統一した後、「朕」は皇帝が自分自身を指す場合にのみ使用できると規定しました。 「卦人」は俗語で、『詩経・北風』には「祖先の恩恵が我を励ます」などの一節がある。「卦人」が皇帝の専称となったのは唐代になってからである。 「私」を一人称代名詞として使用するのは、商王朝の甲骨文字で初めて見られました。当時、「私」は「私たち」を指す代名詞として使われていました。 「私」はどのようにして武器から人称代名詞になったのでしょうか?実は「私」は象形文字で、古代の代表的な武器である「戈」から構成されています。みんなの闘志を奮い立たせるのは簡単です。諺にあるように、本当の男はいつでも戦う準備ができていなければなりません。彼は「武器を取って国を守る」ことができるはずです。そのため、戦士は槍を手に取り、自分で持つことが多かった。槍を持っている人は、私たちの側に属していた。そして、「私」という言葉は、自分自身を意味するように拡張され、「私」の意味はそれ以来ずっと使われており、変わることはない。 |
<<: 最も特徴的な歴史上の蜂起のスローガン 10 個のうち、どれに賛成しますか?
>>: 商王朝の人々はどのようにして統治し、日常生活を送っていたのでしょうか?
推薦する
王維の古詩「方城の魏明福に別れを告げる」の本来の意味を理解する
古代詩「方城の魏明福に別れを告げる」時代: 唐代著者: 王偉遠くの葦やイグサ、そして孤独に歩く楚の人...
二科派安経奇 第12巻:難事件、偉大な学者が些細なことで議論、騎士道精神のある女性が罰を受け入れて有名になる
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
「バカないじめっ子」薛潘と結婚した後、翔玲の生活はどうなったのでしょうか?どれだけ幸せなのか?
翔玲が「鈍いいじめっ子」薛潘と結婚した後の生活がどうなったか知っていますか? 知らなくても大丈夫です...
「忠勇五人男の物語」の第 11 章ではどのような物語が語られていますか?
蒋氏は陸と陸の話を聞いて、今朝、鵲頭峰から投げ落とされた赤い絹で結ばれた印章を見たという。四代目師匠...
『紅楼夢』の小湘閣の裏庭はどんな感じでしょうか?それはどういう意味ですか?
『紅楼夢』の大観園の一場面である小湘亭は、林黛玉が栄果屋敷に住んでいたころの住居である。以下の記事は...
『紅楼夢』で、賈宝玉の所持品が小湘閣から没収された場合、それは盗品とみなされますか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
晋の文公が鹿を追いかけて逃げたというのはどういう意味ですか?
オリジナル:晋の文公はヘラジカを追いかけて、見失った。彼は農夫の老孤に尋ねた。「私のヘラジカはどこに...
唐代の李春鋒とはどんな人物だったのでしょうか?李春鋒の結末はどうなったのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が李春鋒につい...
辛其の最も美しい詩。その言葉は何千年もの間受け継がれてきた。
興味深い歴史編集者に従って、辛其記の詩を鑑賞しましょう!唐詩と宋詩は中国の古典文化であり、中国文学史...
『紅楼夢』では、秦忠と邢秀燕はどちらも貴族社会に進出した貧しい子供でした。彼らの結末はどうなりましたか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
黄庭堅の有名な詩行の鑑賞:人々の背中にはそれぞれ故郷への思いがあり、太陽と月は雪が頂上を覆うように促す
黄庭堅(1045年6月12日 - 1105年9月30日)、字は盧直、幼名は聖泉、別名は清風歌、善宇道...
二人ともクーデターを起こした皇帝なのに、なぜ李世民は朱棣よりも父親を攻撃しようとしたのでしょうか?
唐の太宗皇帝・李世民や明の永楽帝・朱棣といえば、誰もがその名前を知っているに違いありません。唐の太宗...
中国古典文学原典の鑑賞:易伝・相伝・第1部
「湘伝」は「大湘伝」と「小湘伝」に分かれています。 『大相伝』は六十四卦のテキストを解説しており、主...
蔡邊の「夏車亭登り」:降格後の作者の怠惰な状態を描写
蔡邵(1037-1093)、号は智徴、泉州県の出身。北宋の大臣、哲宗皇帝の治世の宰相、王安石の改革の...
『紅楼夢』のタンチュンと邢夫人の関係は?彼女は何に不満を持っているのか?
賈丹春は曹雪芹の『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。これを聞いたら何を思い浮かべますか?...