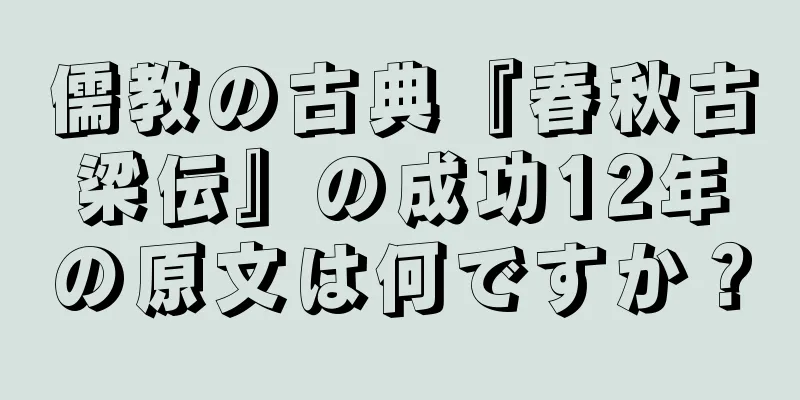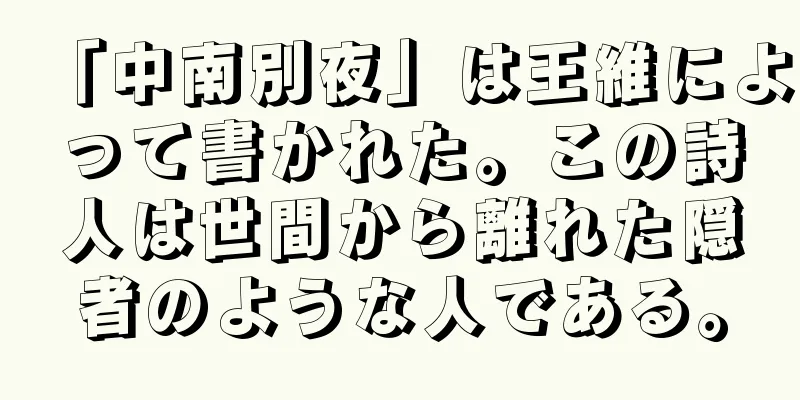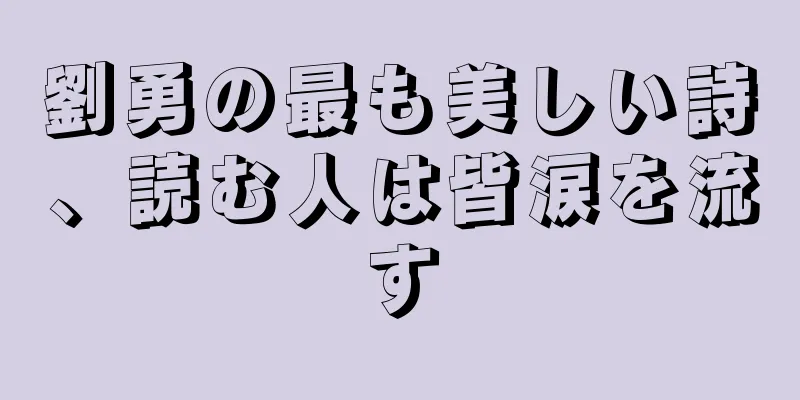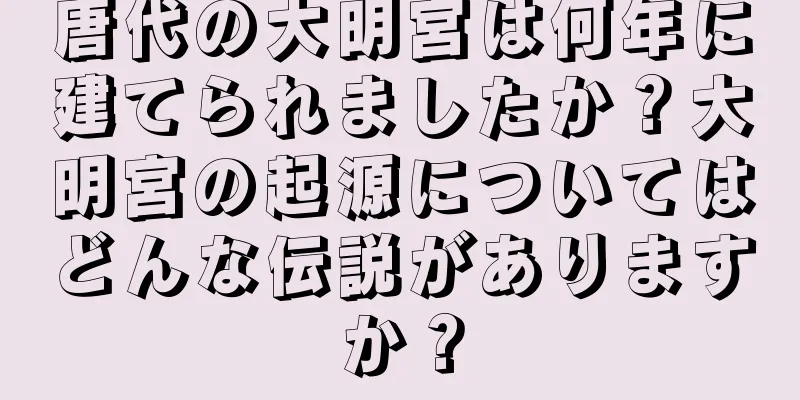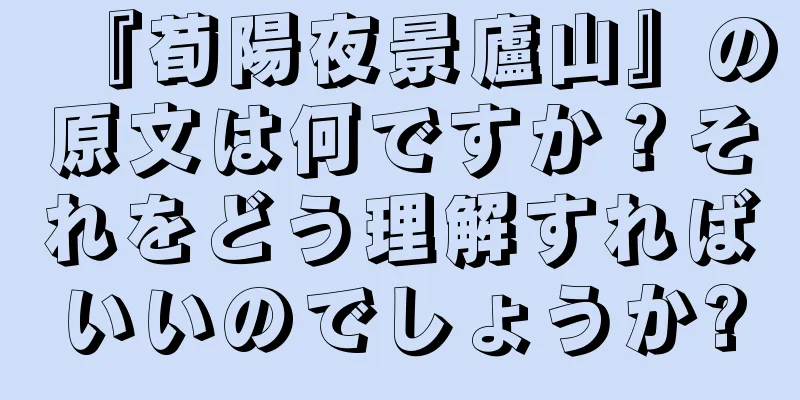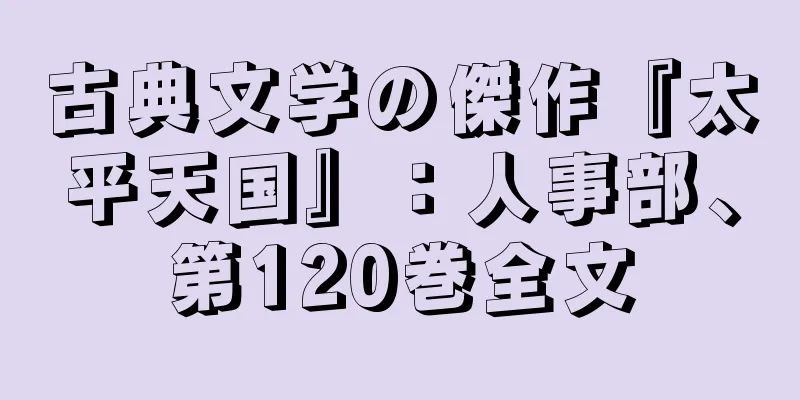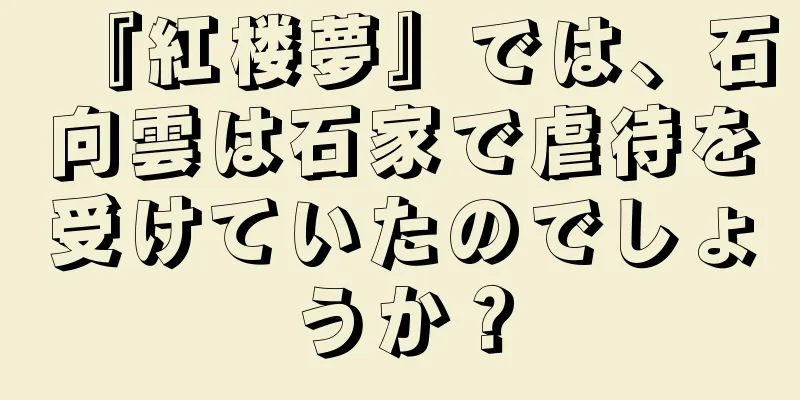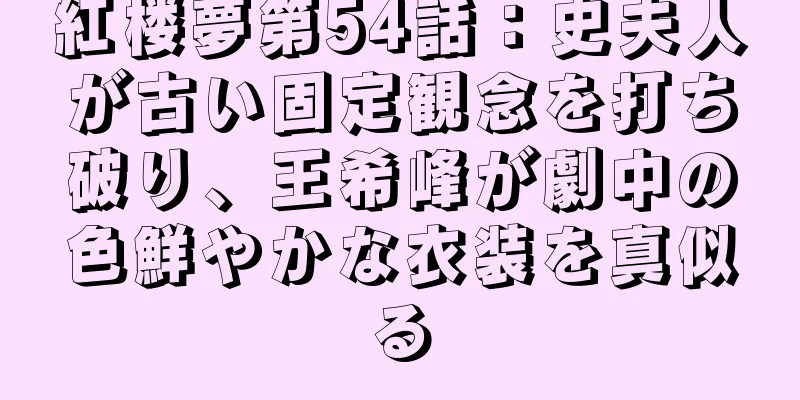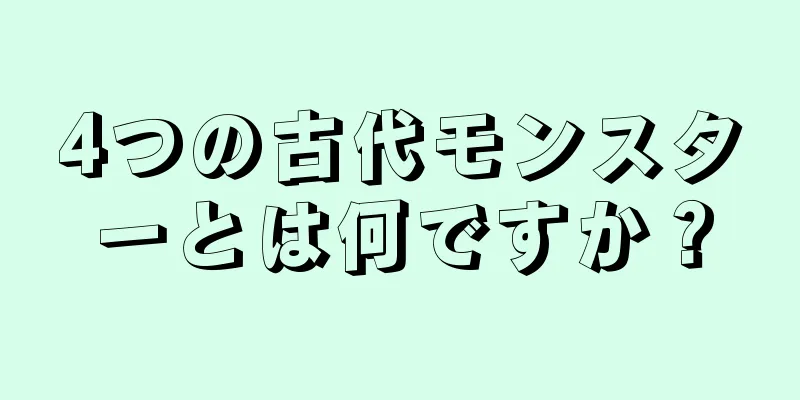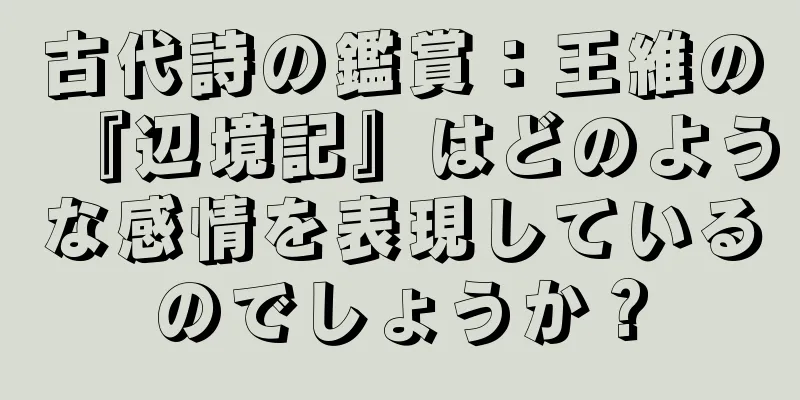漢の武帝の治世中に自然災害はいくつ発生しましたか?漢王朝はどのように反応したのでしょうか?
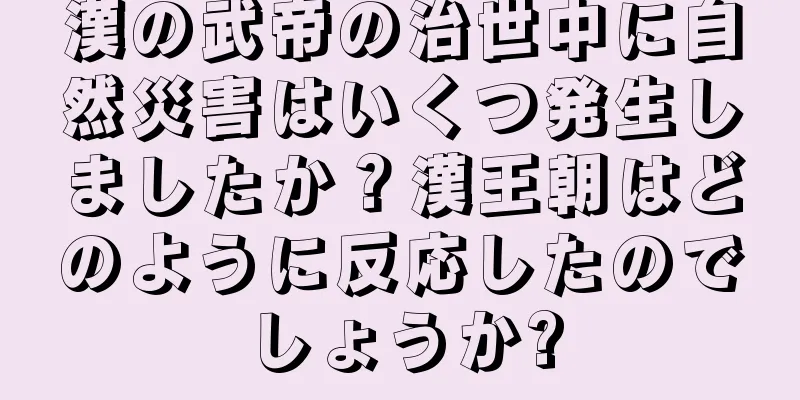
|
今日は、興味深い歴史の編集者が、漢の武帝の治世中にどれだけの自然災害が発生したかをお話しします。皆さんのお役に立てれば幸いです。 前漢時代は、中国史上、先秦時代に次いで二度目の自然災害多発期であると言える。この時代には、洪水、干ばつ、イナゴの害虫、雹、疫病、地震などの災害が多発し、集中的に発生する傾向が見られた。 既存のデータによると、西漢の210年の歴史の中で、洪水32回、干ばつ38回、地震35回、イナゴの害虫20回、風災19回、霜災5回、雹災10回、疫病13回、凍結災13回など、186件の大規模自然災害が記録されている。最も深刻な自然災害は漢の武帝の治世中に発生しました。統計によると、武帝の治世55年間に、干ばつ10回、イナゴの大量発生11回、洪水6回、地震3回、風災3回、霜・氷雪4回、雹災2回、飢饉3回、疫病1回など、合計43件の自然災害が発生しました。 以下は武帝の治世中に発生した自然災害の記録です。 紀元前138年: 3 年目の春、川の水が平野に溢れ、大飢饉が発生し、人々は互いに食い合うようになりました。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前137年: 四年目の夏、血のように赤い風が吹いた。 - 『漢書:武帝の記録』 6月、干ばつ。 - 『紫智同鑑・韓記9』 紀元前136年: 5月にはイナゴの大発生がありました。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前135年: 六年二月、遼東の高廟で災害が起こった。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前132年: 夏の5月、冰子の日に、濮陽湖子ダムが再び決壊し、巨野に流れ込み、淮河と泗河を結び、16の県を洪水で浸した。 - 「紫智通鑑・漢書10」 紀元前131年: 夏の4月に霜が降りて草が枯れてしまいました。 - 「紫智通鑑・漢書10」 5月に地震がありました。世間を許して。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前130年: 夏には深刻な干ばつとイナゴが発生しました。 - 『漢書:武帝の記録』 秋の七月に、強風が木々を根こそぎ倒した。 - 「紫智通鑑・漢書10」 8月、穴掘り虫。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前129年: 夏には深刻な干ばつとイナゴが発生しました。 - 「紫智通鑑・漢書10」 紀元前124年: 5年目の春に、ひどい干ばつが起こりました。 - 「紫之同鑑・韓記熙」 紀元前123年: 12月には大雨と大雪が降り、人々は凍死した。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前120年: 山東省では大洪水が発生し、多くの人々が飢えに苦しんでいました。 - 「紫之同鑑・韓記熙」 紀元前117年: 雨は氷を消滅させます。 - 『漢書:武帝の記録』 冬、10月、雨、氷なし。 - 「紫之同鑑・韓済十二」 紀元前115年: 3月は大雨と大雪が降りました。夏には大洪水が発生し、広東省では何千人もの人々が餓死した。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前114年: 4月には雹が降ります。 - 『漢書:武帝の記録』 広東省東部の40以上の県と州で飢餓が発生し、人々は互いに食べ合うような状況だった。 - 「紫之同鑑・韓済十二」 紀元前112年: 秋になると、カエルとヒキガエルが戦います。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前110年: 当時、ちょっとした干ばつが起こっていたので、皇帝は役人たちに雨乞いの祈りをするように命じました。 - 「紫之同鑑・韓済十二」 紀元前109年: 皇帝は干ばつを心配していた。公孫卿は「黄帝の時代に封印されたとき、干ばつがあったので、封印は3年間続いた」と言った。そこで皇帝は「干ばつがあるのに、封印して乾かすのか」という勅令を出した。 - 『紫禁同鑑・韓記13』 紀元前108年: 冬、12月、馬の頭ほどの大きさの雷と雹。 - 『紫智同鑑・韓記13』 紀元前107年: 夏にはひどい干ばつが起こり、多くの人が渇きで亡くなりました。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前105年: 秋には深刻な干ばつとイナゴの発生がありました。 - 『紫智同鑑・韓記13』 紀元前104年: イナゴが東から敦煌まで飛んできた。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前103年: 秋、イナゴ。 - 『紫智同鑑・韓記13』 紀元前100年: 白い毛布が降ってきました。夏には深刻な干ばつがありました。 - 『紫智同鑑・韓記13』 紀元前95年: 秋、干ばつ。 - 『紫智同鑑・韓記14』 紀元前92年: 夏には深刻な干ばつがありました。 - 『紫智同鑑・韓記14』 紀元前91年: 夏の4か月目には強風で屋根が吹き飛ばされ、木が折れました。 -- 『紫智同鑑・韓記 14』 貴海、地震。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前90年: 秋、イナゴ。 - 『漢書:武帝の記録』 紀元前88年: 秋の七月には地震が起こり、泉が湧き出ることが多い。 - 『漢書:武帝の記録』 上記の記録から、武帝の治世中に最も頻繁に発生した自然災害は干ばつであり、紀元前130年の「夏の大干ばつ」、紀元前107年の「夏の大干ばつ」、紀元前105年の「秋の大干ばつ」、紀元前95年の「秋の大干ばつ」など、夏と秋に多く発生したことがわかります。夏と秋に作物が成長して成熟することは誰もが知っていますが、武帝の治世中、この2つの季節に大規模な干ばつが発生しました。紀元前130年の「夏、深刻な干ばつとイナゴ」や紀元前105年の「秋、深刻な干ばつとイナゴ」など、さらに追い打ちをかけるような「イナゴの災害」も何度か発生しました。 さらに、漢王朝の穀物生産量は技術的な問題によりそれほど高くなく、干ばつやイナゴの害虫にも見舞われました。そうです。西漢の各地では不作の状況が頻繁に発生しました。その結果、武帝の時代には「人が互いに食べ合う」状況が頻繁に発生しました。たとえば、紀元前 138 年には、「川が平野に氾濫し、大飢饉が発生し、人々は互いに食い合いました。」 別の例としては、紀元前 114 年には、「広東の 40 以上の郡と州で飢饉が発生し、人々は互いに食い合いました。」武帝の治世中に大規模な飢饉が起こることは珍しくなく、いずれもかなり深刻なものであったと言えます。 「天候が良く、農作物が実れば、国は平和で、民は安泰である」という諺がある。よく知られているように、王朝が頻繁に自然災害に見舞われると、民は必然的に苦しみ、国は混乱する。さらに悪いことに、王朝の滅亡に直接つながる。例えば、新王朝、明王朝、その他の王朝の滅亡は、多かれ少なかれ、頻繁な自然災害、民の飢餓、広範囲にわたる飢餓と関係していた。漢の武帝の治世中に、人食いが蔓延し、凍死や渇きで死ぬ人々まで現れた、頻繁で深刻な自然災害があったにもかかわらず、なぜ武帝の漢王朝は盤石な安定を保っていたのか、多くの人は理解できない。 そして、武帝の中期から後期にかけて、絶え間ない外国との戦争により、「郡の金庫は空っぽ」、「十軒のうち九軒は空っぽ」という状況がすでに現れていたことは周知の事実です。また、当時は自然災害がひどく、大規模な飢饉が発生しました。他の王朝でこのようなことが起きていたら、国はとっくに滅んでいたでしょう。しかし、なぜ武帝は漢王朝の基盤を揺るがすことがなかったのでしょうか。この時代、民衆は一度も反乱を起こしませんでした。これほどの苦難にもかかわらず、民衆が漢王朝の世界統治を支持した理由は何だったのでしょうか。 実際、武帝が「国全体が絶望し、人々が再び互いに食い合っていた」状況でも漢王朝の統治を安定させることができたのは、これは武帝の時代に実施されたさまざまな飢饉救済政策と切り離せないものであり、これらの適切かつ効果的な災害救済策があったからこそ、漢王朝の統治が安定したと言えるでしょう。それで、武帝はどのような政策を実行したのでしょうか? 飢餓防止政策 古いことわざに「家庭をうまく切り盛りする人は、問題が起きる前に予防策を講じる人だ」というものがあります。家庭を仕切る人が円満な家庭を築きたいのであれば、問題が起きる前に予防策を講じる方法を知っていなければなりません。これは国を治める場合にはなおさらです。武帝の治世中、飢饉を防ぐために多くの対策が実施されました。まず、武帝は時代と地域の状況に応じて穀物を栽培することを人々に奨励しました。董仲舒はかつて「今、関中の人々は小麦を栽培することを好まない...関中の人々に古小麦を栽培させよう」と言った。そして元寿3年、漢の武帝は「使者を派遣して、洪水被害を受けた県に古小麦を植えるよう説得した」。いわゆる「古小麦」とは、秋から冬にかけて植えられる小麦のことである。これらの地域では、生命力が強く、干ばつや強風に強い小麦が大量に植えられるようになったのは、武帝の奨励によるものだと言えます。このように、小麦の大規模な栽培により、人々が「飢饉の年」を生き延びる可能性が高まり、漢王朝の災害に対する抵抗力が強くなりました。結局のところ、食糧が増えれば災害の年もそれほど恐ろしくはなくなるでしょう。 もちろん、武帝は農民に地元の状況に合わせて穀物を栽培することを思いとどまらせただけではありません。彼はまた、さまざまな先進的な農法や農具を普及させました。例えば、紀元前89年、武帝は穀物栽培の専門家である趙果に、彼の「代田法」と、連結した鋤と鋤鋤などの先進的な農具を全国に普及させるよう命じました。 「代田方式」は乾燥地帯での穀物栽培に非常に適した農法で、その収穫量は「1畝当たり1斗以上、良質の土地では2倍の年間収穫量」に達する。夫婦鋤と鋤車も併用することで、当時の農民が得た成果は「より少ない労力でより多くの穀物を収穫でき、誰にとっても便利」だった。 もちろん、災害年の到来を防ぐには、上記の方法だけに頼るだけでは十分ではありません。結局のところ、すべての場所が小麦の栽培に適しているわけではなく、「大天法」の実施に適した場所もありません。そのため、武帝はこれらの方法を推進すると同時に、全国各地で大規模な水利・灌漑事業を数多く建設しました。例えば、『漢書疏許志』には、鄭氏が当時農務大臣を務めていたことが記録されており、「昔、広東の穀物は渭水から運ばれ、関中の土地を豊かにし、穀物を生産した」と述べている。 「皇帝は同意し、斉の水利技師である徐伯表に数万人の兵士を派遣して運河を掘るよう命じました。運河は3年で完成しました。」当時、黄河から始まり長安に至る全長150キロメートルを超える運河である衛草運河は、関中東部の水源問題を解決しただけでなく、広東地域に数万ヘクタールの肥沃な農地を生み出しました。 武帝が先見の明を持って全国各地で「現地の事情に適応した」穀物栽培法や先進的な農具を積極的に推進し、数多くの水利灌漑事業を建設したからこそ、漢王朝の災害に対する抵抗力は大きく強化されたと言える。そして、武帝の時代には、災害に対する耐性が強化されていたからこそ、大規模な自然災害が何度も発生しても、迅速に復興することができ、人々は何度も自然災害の襲来に耐えることができたのです。 災害救援方針 もちろん、「自然災害は予測不可能だが、人為的災害は回避可能」である。武帝の治世中に人為的災害によって飢饉が深刻化する問題は大幅に回避されたが、自然災害の発生は常に避けられない。武帝が飢饉を防ぐためにどれほど努力したとしても、自然災害は常に漢王朝に一定の影響を及ぼしました。それで、武帝は飢饉にどのように対処したのでしょうか? 国が飢饉に遭遇したとき、まず最初にすべきことは救済策を講じることであることはよく知られており、武帝の治世も例外ではありませんでした。当時、武帝の治世下では、人民に配給された金銭、穀物、資材、さらには土地などの救済物資はすべて無料で、人民は料金を払う必要がなかった。例えば、元寿3年、「山東省が洪水に見舞われ、多くの人々が飢えていた」とき、武帝は「使者を派遣して郡や州の穀倉を空にして貧しい人々を助けよ」と命じ、郡や州の役人に穀倉を開いて被災者に無料で食糧を配給するよう求めました。 同時に、災害が広範囲に及び、朝廷が救援活動に追われていたとき、朝廷が時宜にかなわずに救援食糧を配給したために被災民が餓死するのを防ぐため、武帝は朝廷の私有地であった山、川、森林、沼地を一時的に開墾し、被災民が自ら山や川へ行って食糧を採取できるように命じることもあった。例えば、元定2年、関中で「数千人が餓死」し、朝廷の救援が間に合わなかったため、武帝は「山林池沼の富を民に分け与えよ」という勅令を出し、被災地の山林池沼を開放し、これ以上の餓死者を出さないようにした。例えば、武帝はかつて、民衆を助けるために、もともと朝廷のものであった私有牧場を開放せよという勅令を出したことがある。建元6年、蝗害が国中を襲ったため、武帝は「宮廷から馬を撤去し、貧しい人々に与えよ」という勅令を出し、皇帝の馬牧場を民衆に与えて利用させた。 もちろん、災害救助の過程では、朝廷が食糧不足に直面することは避けられず、このとき武帝は被災者を見捨てるよう命じなかった。それどころか、彼は災害の被災者を救援するために、穀物が豊富な地域から穀物を輸送するためにより多くの資金を費やした。例えば、元定二年夏、「大洪水が起こり、広東で数千人が餓死した」とき、武帝は「長江以南の地域では、火で耕し、水で鍬を働かせ、巴蜀から江陵に粟を送れ」という勅令を出した。これは、災害の影響を受けず、豊作だった巴蜀から、被害が大きかった広東に穀物を運び、被災者を救援すべきという意味だった。 災害が発生したとき、武帝は被災者に対して「決して諦めない」という理念を常に守り、彼らの救出に全力を尽くしたと言える。朝廷が私有していた山、川、森林、沼地さえも被災者に開放した。食糧が不足すると、武帝は他の地域から穀物を運んできて人々に無償で与えようとしました。このような習慣があったからこそ、このような困難な時代でも、被災した人々は漢王朝の統治に反抗しませんでした。なぜなら、人々は自然災害は避けられないものであり、武帝のせいではないことを知っていたからです。災害が発生したとき、武帝は人々を見捨てず、懸命に助けようとしました。人々はそれを自分の目で見て、心に留めました。 震災復興政策 災害が発生したときに最も重要なことは、迅速な災害救助です。災害救助が完了した後、次に重要なことは「災害後の復興」です。最優先事項は、これらの人々をいかにして再定住させ、被災者がいかにしてできるだけ早く復興できるようにするかである。この点では、武帝は非常に優れた仕事をし、非常に成功したとさえ言えるでしょう。 災害の救援を終えた後、武帝が最初に行ったのは、被災した人々に最も必要な土地を与えることだった。結局、災害が起きた後、朝廷が被災者に無償で援助し続けることはできない。最も大切なことは、被災者に自立してもらうことであり、そのためには土地の助けが必要なのだ。土地の付与に関して、武帝は主に「人民への公有地の付与」と「移民の定住と開拓」という2つの政策を実施しました。 『塩鉄談・第3巻・庭園と池』には、「今日、郡役人は多くの庭園や公営の田畑や池を造っている…三県は山や川に近く、面積は小さいが人口は多い。四方八方から人がやって来て、作物や薪や野菜を賄うことができない。公営の田畑は私有地になっている…」とある。 「偽の公有地」とは、公有地、荒れ地、灌漑地、裁判所が使用する庭園や公園の一部を土地を持たない難民に貸し出すことを意味する。貸し出しの最初の年は農民は税金を払う必要がなく、その後は30分の1の税金を払うだけで済んだ。これは難民の生活問題をある程度解決できるとともに、災害救助後の裁判所の財政問題も解決できる、非常に良い政策であるといえる。 「移住・開拓」とは、災害などで土地を失った難民を国境地域に移住させることだ。周知のように、武帝の治世中、人々は長年の戦争でひどく苦しんでいたにもかかわらず、漢王朝は豊かな報酬も得ました。最も寛大な報酬は領土の返還でした。武帝の治世中、武威県、張掖県、敦煌県、酒泉県などの新しい県が次々と出現しました。しかし、これらの郡は国境地帯に位置しているため、人口は多くなく、土地が広く人口がまばらというのが最も現実的な描写です。このため、漢代の領土は拡大したにもかかわらず、耕作地の面積は増加せず、これらの地域では多くの土地が放棄された状態となっていました。 土地はあるが人が住んでいない国境地帯とは対照的に、中原地域には人が住んでいるが土地がない。これを見ると、武帝が何をするかは誰もが分かると思います。答えは非常に簡単で、中原の余分な土地を持たない犠牲者を、土地は豊富だが人がいない国境地域に移住させることです。もちろん、この移住は無駄ではありません。結局のところ、利益がなければ、人々はこれらの貧しい場所に行くことを決して望まないでしょう。 当時、武帝はこれらの人々が喜んでこれらの場所に行くようにするために、一連の優遇政策を講じました。まず、自発的に国境に赴いた人々は、土地を無料で得られるだけでなく、最初の1年間は「県役人の商売促進のための食料と衣服」の待遇も受けており、つまり、到着当初の生活費はすべて朝廷が負担していたことになる。同時に、国境地帯に土地を開墾しに行った人々は数年間の免税を享受できた。このような寛大な政策の推進力により、元寿4年だけで「広東省の貧困者72万5千人が竜渓、北堤、西河、上軍、会稽に移住した」。つまり、この年だけで中原の72万5千世帯が国境地帯に移住したことになる。 もちろん、土地だけでなく、種子や生産用具、復興のための道具なども被災者には必要であり、被災したばかりの人たちがこれらをすべて購入することは到底不可能だと思います。そこで、武帝もこの問題を考慮し、人々に「融資」を行うことで解決しました。例えば、元寿3年、武帝は「貧しい人々に金を貸し、名声を博すことのできる官吏や庶民を選び出し、金持ちや権力者を募って金を貸させる」という勅令を出した。つまり、金を貸すことのできる官吏や庶民は、貧しい人々に食料の種子や復興に必要なその他の品物を融資という形で貸し付け、1年経ってからゆっくりと返済することが許されたのである。例えば、元寿6年、漢の武帝は「雨氷消失」のため、各県に「事業再建の資力のない者に金を貸せ」という勅令を出した。 さらに、武帝は他の方法でも災害被災者の負担を軽減しました。例えば、元寿3年、一部の地域が深刻な災害被害を受けたため、武帝は「隴渓、北堤、上邑の駐屯兵を半減せよ」という勅令を出した。これは、一部の災害被災地域の被災者に対し、本来行うべき労役を免除することを意味した。こうすることで、労役を免除された被災者は、災害後の復旧作業に従事するエネルギーをより多く持つことができた。 つまり、武帝の直接的な政策により、漢代の人々は多くの大規模な自然災害に見舞われながらも平和に生き延びることができたのです。人々は災害の後、土地やその他すべてを失いましたが、武帝の助けにより、ほとんど無料でそれらを取り戻しました。彼らに必要なのは、以前と同じように勤勉に働き続けることだけでした。もしそうなら、災害に苦しんだ民衆がどうして武帝に反抗できたのでしょうか? 武帝の積極的な軍事政策、郡役人の不足、そして頻発する自然災害という二重の打撃にもかかわらず、漢王朝が揺るぎない安定を保てたのは、武帝が実施したこれらの積極的かつ効果的な飢餓救済政策のおかげであったと言える。武帝が飢饉が起こる前に積極的に予防し、飢饉が起こったときに積極的に対応し、飢饉が起こった後も「民を第一に考える」という姿勢を貫き、被害者が以前の生活状態に戻れるよう全力を尽くしたからこそ、漢王朝は安定していたのである。だからこそ、人々は互いに食べ合っていたにもかかわらず、庶民は依然として武帝の統治に喜んで従ったのです。 |
<<: 大月氏とはどのような民族だったのでしょうか?大月志の開発の歴史!
>>: ホータンにはなぜヒスイが豊富なのでしょうか?何世碧は和田翡翠ですか?
推薦する
伝説の人物である陳廷静を後世の人々はどのような評価をしているのでしょうか?
陳廷景は誠実な官吏であり、在任中は康熙帝から厚い信頼を得ていた。博学で先見の明があっただけでなく、国...
厳吉道の「皇街を歩く:春には南の緑の木々が花を咲かせている」:これは報われない愛についての詩です
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
黄文氷は宋江と涼山の関係を知っていた。涼山の復讐を恐れなかったのだろうか?
宋江は江州に流され、そこで黄文兵という権力者に出会った。黄文兵は宋江にあらゆる方法で反対し、何度も宋...
『紅楼夢』の登場人物4人の名前の意味は何ですか?
前回はバオ、ダイ、チャイについてお話しましたが、今回は四姉妹と王希峰についてお話します。四泉の名前は...
周敦義は『蓮の愛について』をどこで書いたのでしょうか? 『鄭家系図』には何が記録されているのでしょうか?
「夜の西湖に白い蓮が咲く」は「衡州八景」の詩の結びの一文であり、衡陽は優れた人々、美しい景色、そして...
李和の有名な詩句を鑑賞する:西の白帝は驚いて、秋の田園で幽霊の母は泣いた
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
宋代の「団」組織はどのようにして誕生したのでしょうか? 「団」の成立と進化!
今日は、Interesting History編集長が「団」の成立と進化の過程をお届けします!皆さん...
荘族の風習 荘族の「肩棒打ち」とは何ですか?
昔、郎を打つことを「大チョンタン」と呼び、肩棒を打つことも「大郎」に由来しています。唐代の学者、劉勲...
『墨子』第68章「英帝廟(2)」をどのように理解すればよいのでしょうか?どんな物語が語られるのでしょうか?
『墨子』は戦国時代の哲学書で、墨子の弟子や後世の弟子たちによって記録、整理、編纂されたと一般に考えら...
星堂伝第12章:愚か者が大陽山で道を塞ぎ、秦瓊が月来旅館で親戚に会う
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
皇帝の食事には何品あるのですか?本当に200種類以上あるんですか?
皇帝の宮廷料理には何品あるかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting Hist...
『紅楼夢』で邱童は幽二潔をどのように扱いましたか?彼女の最終的な結末はどうだったのでしょうか?
秋童は『紅楼夢』の登場人物で、元々は賈舍の侍女でした。次に、Interesting Historyの...
司馬懿が魏の政権を握った後に実施した氏族政治の特徴は何でしたか?
貴族は地主階級の中でも特権階級であった。それは後漢時代に始まり、魏・晋時代に形作られました。次は興味...
五代十国時代の絶世の美女、華建秀の生涯
導入五代十国時代の名高い美女である華建秀は、李嗣源のお気に入りの側室でした。彼女の本姓は王であり、汪...
『剣客』の柴玉冠の妻、雲夢仙女の簡単な紹介
古龍の武侠小説『武林外史』より、夫:「万家勝佛」柴玉冠、息子:「千面小僧」王連花。武術界一の女魔神で...