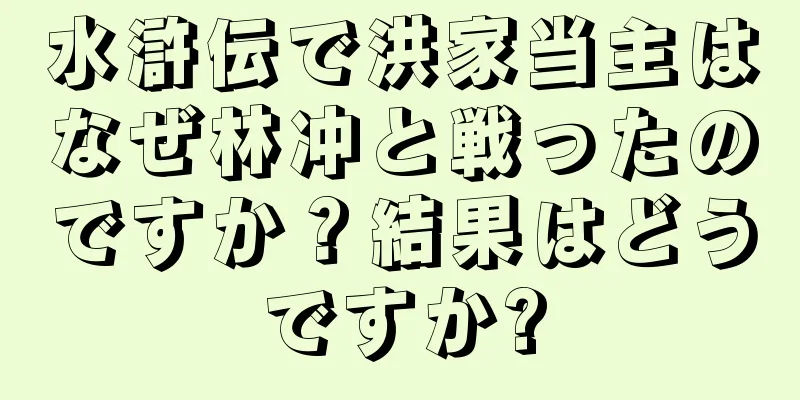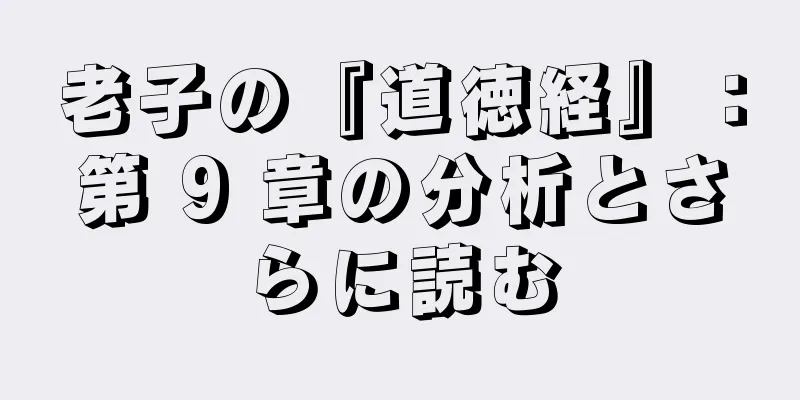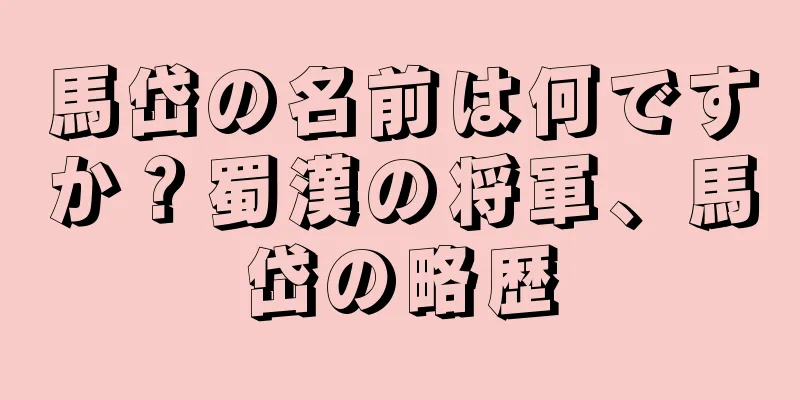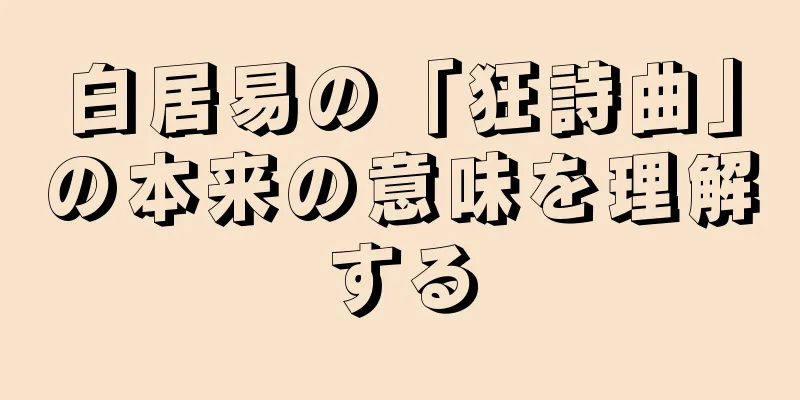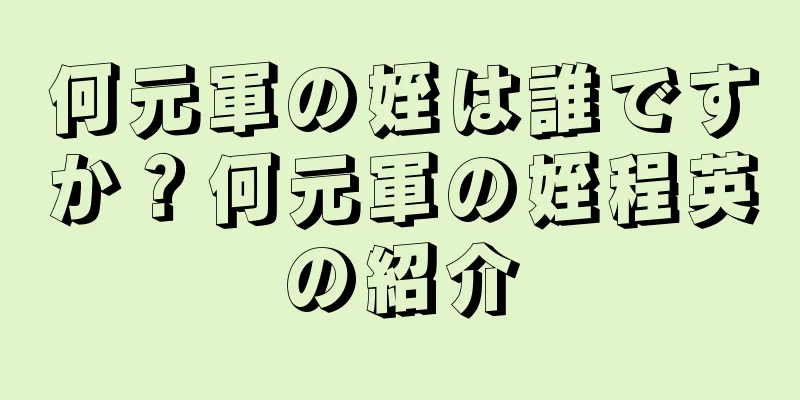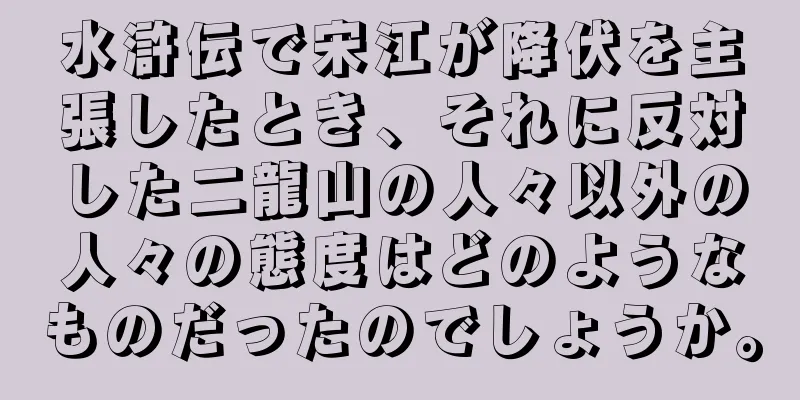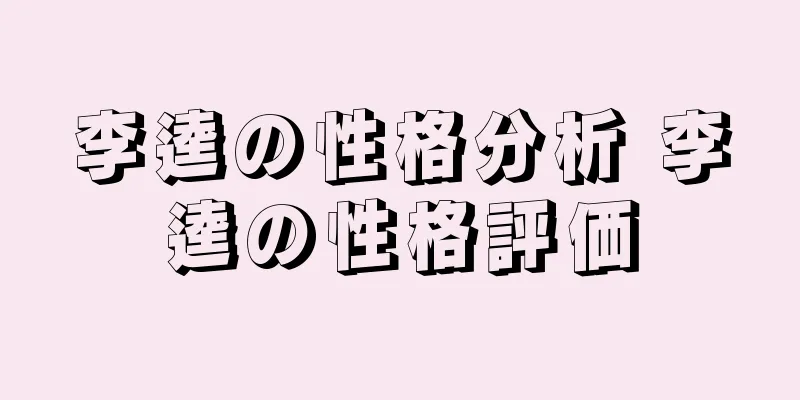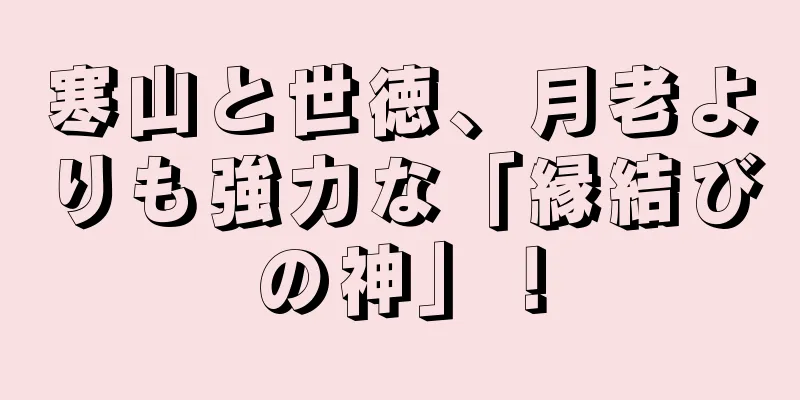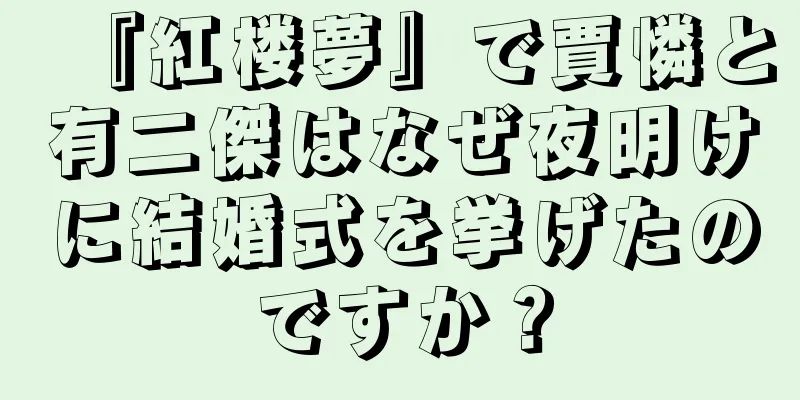科挙制度はいつ始まったのですか?科挙制度の影響は何でしょうか?
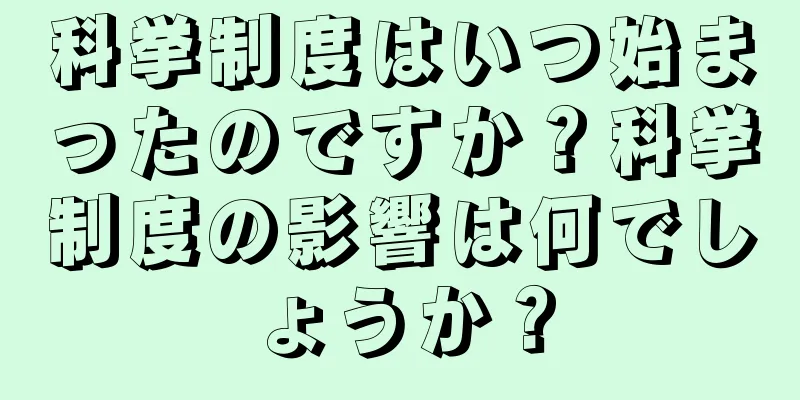
|
科挙制度は、中国や中国の影響を受けた周辺諸国で、試験によって官僚を選抜する制度であった。科挙制度がいつ最初に確立されたかについては歴史学界で論争があり、漢代、隋代、唐代などさまざまな説がある。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 歴史家の中には、隋の時代に科挙制度が始まったと考える者もいる。その理由は、隋の時代に科挙制度が科挙人(じゅれん)と進士(しんし)の2つに分けられたためである。一部の歴史家は科挙制度が漢代に始まったと検証しており、漢代には学科や科挙による候補者選抜だけでなく、昇進のための試験もあったことを証明している。隋代に進士試験があったことを証明する信頼できる証拠はない。一部の歴史家は、科挙制度の本質は唐代に始まったと検証している。唐代には、受験者が(大臣や郡役人からの特別な推薦を必要とせず)自ら科挙に申し込むことが許され、科挙免除制度も存在したため、科挙制度は唐代に始まったことになる。 科挙制度は、その発足から清朝の光緒帝の治世31年(1905年)の最後の科挙まで、1,300年以上続いた(世界で最後の科挙は、1919年のベトナムの阮朝で終了した)。科挙制度の主要な試験が定期的に行われた。 科挙制度は封建時代に利用できた最も公正な人材選抜方式であり、封建国家における人材導入の社会的側面を拡大し、中流階級と下層階級の多くの人々を支配階級に吸収した。特に唐・宋時代に科挙制度が初めて確立されると、科挙制度は活発かつ進歩的な性格を示し、古代中国文化発展の黄金時代を形成しました。 科挙制度は漢代に始まったと検証している歴史家もいる。科挙制度が隋代に始まったと考える人は、科挙制度の始まりとして、隋の「五等以上の都官、総督、地方長官を含む、誠実で勤勉な二類の官吏から候補者を選抜せよ」という勅令をよく挙げるが、この勅令は基本的に北周の「開府以上の武官、下級医官以上の官吏、地方長官以上の、誠実で勤勉な三人を派遣せよ」という勅令と同じであり、西漢の文帝二年以来、歴代王朝が徳の高い人材を選抜するために出した勅令と全く同じである。 隋の煬帝が進士試験を各種の試験の一つとして制定したことから、科挙制度が隋の時代に始まったという説もある。しかし、科挙制度が漢代に始まったと考える人々は、科挙制度は「科目ごとに選抜し、試験によって昇進させる」という完全なシステムであったと指摘しており、漢代には修才、明経、明法、先良方正、小連など多くの科目があり、漢代の『対策』と『詩経』は試験であった。こうして科挙制度は漢の時代に始まりました。 隋・唐時代に新たに追加された壬氏については、その名前はもともと『周書』に由来しています。漢・魏時代には、朝廷に貢献した孝行で誠実な人を「壬氏」に例える習慣がありました。したがって、隋代に設立された進士試験は、古代の制度に従って学者を選抜するための科目名の一覧にすぎず、漢代以来の科目制度全体に完全に従属し、修才、献良などと同じ意味を持っていました。 調査の結果、楊占が進士であったことは文献がないため確認できなかったが、他の5人は証拠がないか、現在の制度と古代の制度を比較していたことが判明した。科挙制度が隋に始まったと考える人たちは、隋の進士枠の設置を科挙制度の始まりとみなしていた。進士枠は大業年間(605-618年)に設置されたと言う人もいれば、実際には開皇7年(587年)に設置されたと言う人もいる。 Historian He Zhongli denied the existence of Jinshi and Jinshi examinations in the Sui Dynasty for two reasons: first, after examining the "Book of Sui" and Sui Dynasty documents, although many examination titles were recorded in Kaihuang and Daye, there was no mention of the Jinshi examination, nor was there any record of the actual Jinshi examination; second, according to Tang and Five Dynasties documents, there were six Jinshis in the Sui Dynasty, namely Fang Xuanling, Wen Yanbo, Hou Junsu, Sun Fujia, Zhang Sunzhi, and Yang Zhan. However, after verification, except for Yang Zhan's Jinshi status, which could not be verified due to lack of documents, the other five people either had no evidence to prove their status, or compared the current system with the ancient system, and compared the Sui Dynasty's system of selecting officials through the Xiucai and Mingjing examinations to the Jinshi examination. Although there are records that the Jinshi examination was founded in the Sui Dynasty, there are also records that the Jinshi examination was founded in the Tang Dynasty. Therefore, he believed that the Sui Dynasty still implemented the recommendation system, and the Jinshi examination also originated in the Tang Dynasty. 隋代の官選方式は漢代の官選方式を継承したものである。隋の開皇18年(589年)、文帝は諸国に志、誠実、功績の2つのカテゴリーに従って学者を推薦するよう命じた。大業3年(607年)、隋の煬帝は10のカテゴリーに分けて人物を推薦するよう命じた。大業5年(609年)、彼は諸国に人々を推薦するよう命じ、彼らを4つのカテゴリーに分けました。 隋の時代には降伏を求める手段がなかった。 「煬帝が初めて進士試験を制定した」とも言われ、隋代には「進士と明経の二つの試験が制定された」とも言われています。しかし、歴史の記録によれば、隋の文帝の二臣、隋の煬帝の十臣、隋の煬帝の四臣には壬氏と明経の臣は存在しなかった。科目別に候補者を推薦する方式は、隋代に始まったものではない。漢代の科挙はすでに科目ごとに分かれており、戦略によって試験されていました。また、隋代に進士に相当する科目があったとしても、それが科挙制度であったとは言えない。 なぜなら、従来の官選制度と比較すると、科挙制度の最も重要な特徴は、第一に、官吏の推薦を必要とせず、勉学に励む人なら誰でも願書を提出して受験できること、第二に、試験が定期的に実施されること、第三に、試験が厳格であることである。隋の官選制度には、上記3つの特徴がなかった。隋の文帝と煬帝の勅令は、官選に参加したい学者はやはりまず高官の推薦を受けなければならず、学者が自ら請願書を提出する権利は与えられていないとしていた。 隋代には臣下の選挙が3回行われたが、いずれも皇帝の要請により行われ、定期的に行う制度はなかった。開皇七年の勅令「諸国から毎年三人を貢ぐ」は、漢代に諸国や郡が朝廷に毎年貢学者を推薦したことと同じで、数も少なく試験も重要でなく、唐・宋代に定期的に行われた国家試験にも用いられなかった。上記の3点が科挙制度の特徴とみなされないのであれば、漢代の科挙制度も科挙制度であったことになる。したがって、科挙制度は隋の時代ではなく、唐の時代に始まったということしか確認できない。 隋の時代は、人材の選抜に関して画期的な規則や規制を制定することができなかった。隋の皇帝たちは皆、才能のある人々に対して嫉妬心を抱いていた。隋の文帝は、首都と地方の県や郡の学校を廃止する勅令を出した。隋の煬帝は放縦な暴君であったが、詩人でもあった。しかし、曹操や曹丕のような才能ある人々を愛し、包容する寛大さは持ち合わせていなかった。 有名な学者薛道衡は「西渓塩」という詩を書き、その中の「暗い窓から蜘蛛の巣が垂れ下がり、空の梁から泥が落ちる」という一節は、当時の人々に広く朗誦された。隋の煬帝は嫉妬心が強く、薛道衡を讒言して処刑した。処刑前に「また『虚梁燕泥』を書けるか」と尋ねた。煬帝は才能のある人に対して嫉妬心が強かったので、隋の時代の選挙で才能のある人が出なかったのも不思議ではない。 |
<<: 隋代の図書館である観文殿はどのように設計されていたのでしょうか?観文堂に保管されている古書は今も残っているのでしょうか?
>>: 隋の軍事制度はどのようなものだったのでしょうか?隋の軍隊の構造はどのようなものだったのでしょうか?
推薦する
白居易の『霊公に応えて緑堂に花を植える図』は、師の名声と成功に対する賛辞を表現しています。
白居易は、字を楽天といい、別名を向山居士、随音献生とも呼ばれた。写実主義の詩人で、唐代の三大詩人の一...
馬頭壁は明代にはすでに記録が残っています。では、なぜ馬頭壁は耐火性があるのでしょうか?
馬頭壁はレンガと土で作られているため、火で燃えることはありません。木造家屋の間に馬頭壁を築くことで、...
唐の徳宗皇帝の王妃、李施は誰ですか?唐の徳宗皇帝の皇后、王昭徳の簡単な紹介
唐の徳宗皇帝、李氏(kuò)は唐王朝の第9代皇帝であり、皇后は昭徳王皇后であった。王后(8世紀? -...
楊虎伝の原文『朱梅雲』漢史第67巻
楊王孫は孝武帝の治世中に生きた。彼は黄老の芸術を学び、千ドル以上の財産を所有していました。彼は自分の...
賈元春が自ら創り出した、みんなの夢の集いの場を誰が破壊したのか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
三寸金蓮華の起源古代の縛られた足がなぜ三寸金蓮華と呼ばれるのか
三寸金蓮華の由来: 「三寸金蓮華」といえば、なぜ纏足のため女性の足を縛ることを「金蓮華」と呼ぶのか、...
孟子:李楼第2章第19節原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
徐霞客の『雁蕩山遊覧記』原文
仁清元年(1632年)3月に兄の鍾昭とともに天台を訪れた。 4月28日、黄岩に到着し、再び燕山を訪れ...
那藍星徳と曹雪芹の関係は何ですか?曹雪芹が演じる賈宝玉は那藍星徳と同一人物ですか?
那藍星徳と曹雪芹の祖父曹寅はともに宮廷の護衛兵として仕えていた。同僚同士のこのような関係は珍しいので...
中国の歴史上の「六聖人」とは誰ですか?
我が国の歴史には、西漢の時代から繁栄した唐の時代まで、「歴史の聖人」「草書の聖人」「医聖人」「書道の...
古典文学の傑作「太平天国」:人事部第26巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
「書礼」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
シュリ匿名(秦以前)キビの種が撒かれ、モロコシの苗がまばらに植えられています。足取りはおぼつかず、心...
天啓帝はどのようにして東林党と仲違いしたのですか?仲違いした後、何が起こったのですか?
東林党の栄光の姿を理解するには、明代末期の三大怪事件である亭済事件、洪願事件、易公事件を大まかに理解...
王希峰、宝玉らが鉄観寺に死者を送りに行ったとき、何が起こったのでしょうか?
王希峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物で、聡明で有能な人物です。今日は、Interesting ...
唐代の西州城は今どこにありますか?唐代の西州城はどのような様子だったのでしょうか?
唐代の溪州城は今どこにあるのか?唐代の溪州城はどんな様子だったのか?『おもしろ歴史』編集者と一緒にそ...