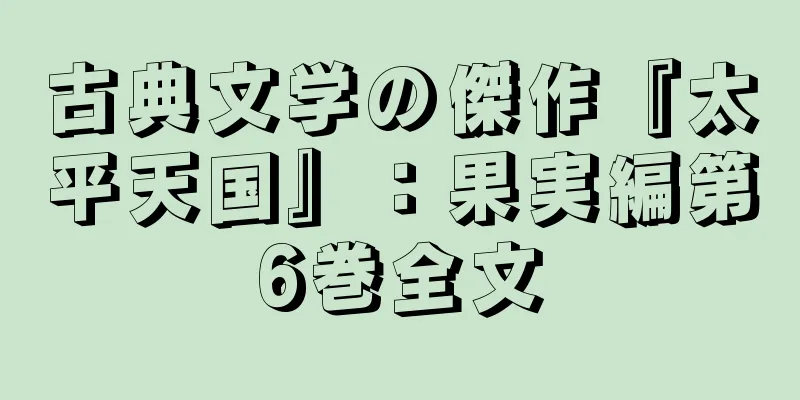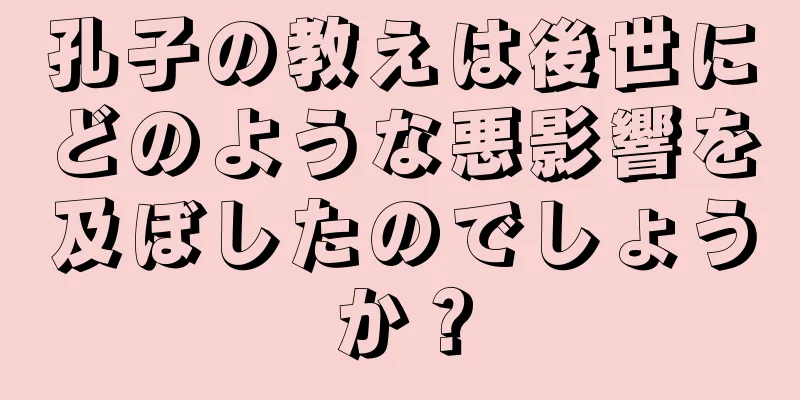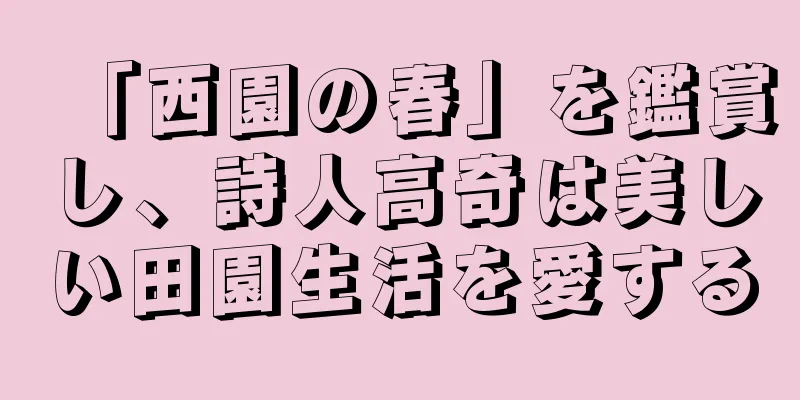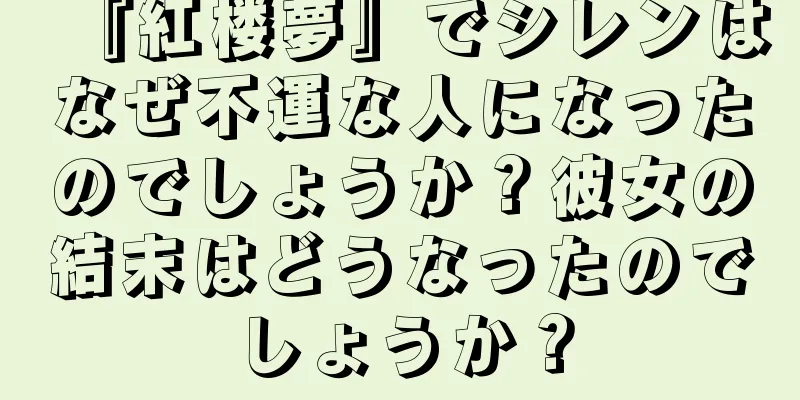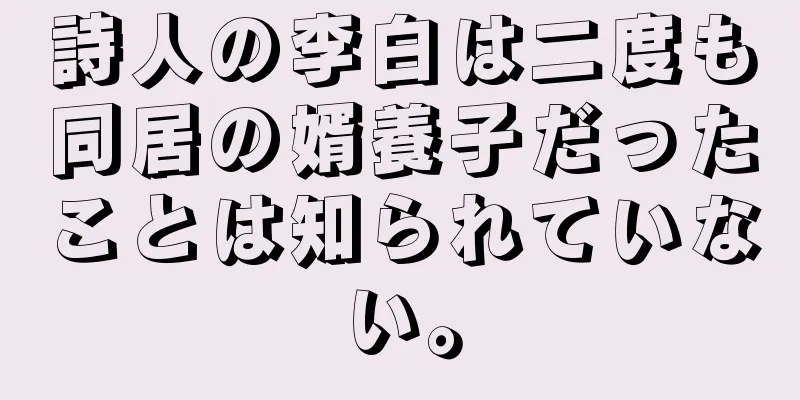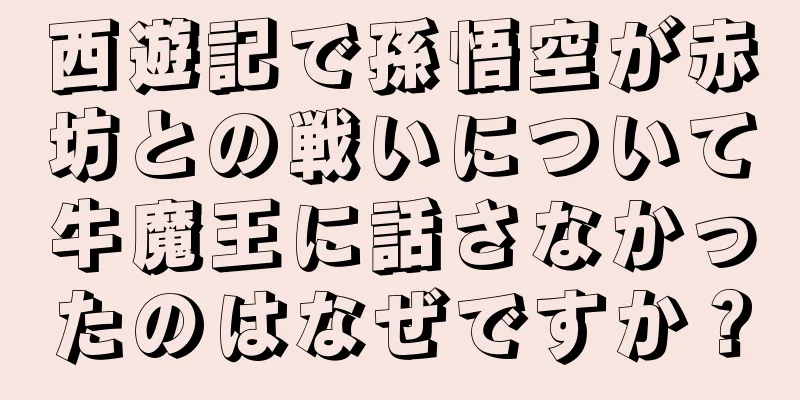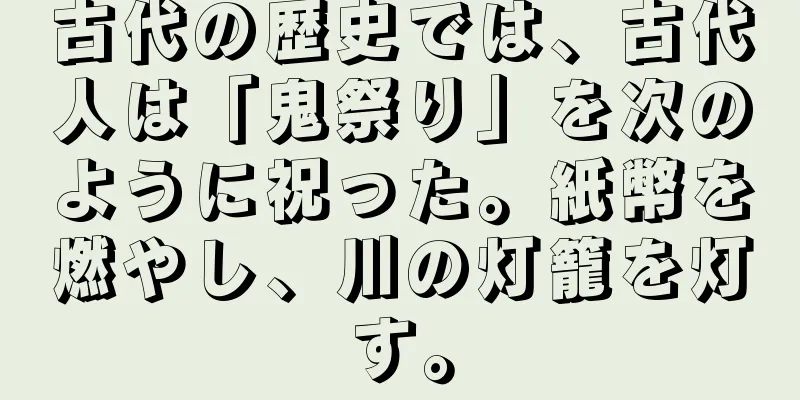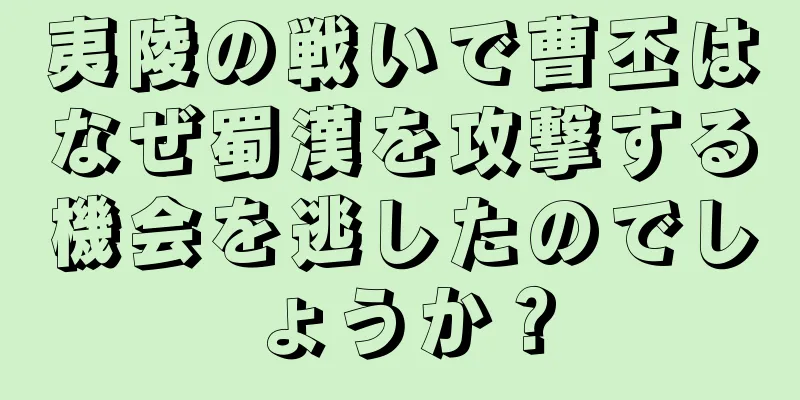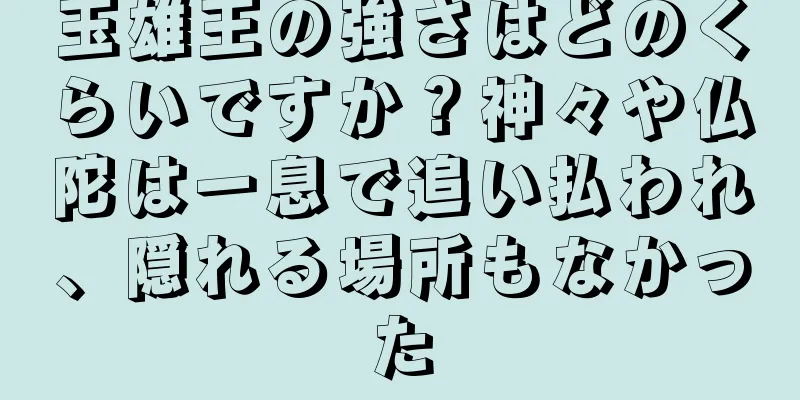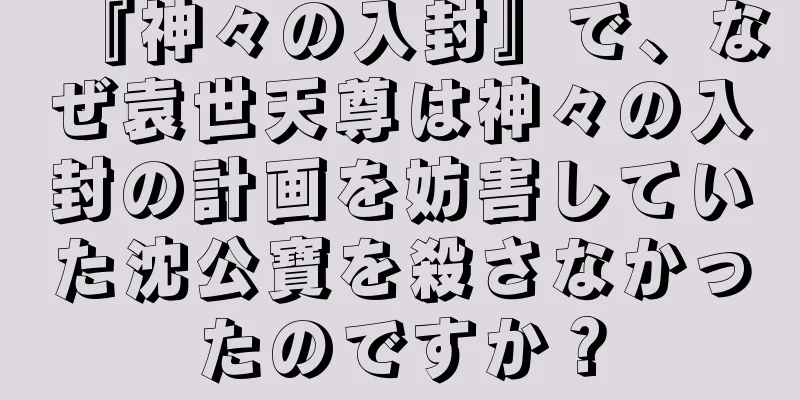徐霞客の『雁蕩山遊覧記』原文
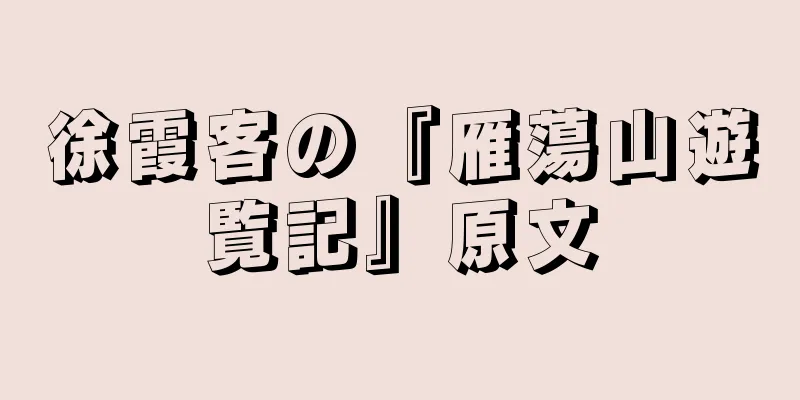
|
仁清元年(1632年)3月に兄の鍾昭とともに天台を訪れた。 4月28日、黄岩に到着し、再び燕山を訪れました。乗り手を見つけて南門から出て、方山に沿って10マイル進み、南西に曲がって30マイル歩き、秀嶺を越え、岩の前の店で昼食をとります。五里は楽清の境界であり、五里は上盤山脈である。南西の雲の中にかすかに蓮の花の群れが見えますが、それが燕山です。 10マイル離れたところに鄭家嶺、10マイル離れたところに大井義。雨のため増水し、馬の腹まで水が溜まっている石門渓を渡りました。私たちは5マイル離れた燕山の東側の外谷である張家楼に滞在しました。張家が最盛期だった頃、山登りの観光客が休憩できるように建物を建てました。今ではホテルや旅館はほとんどありませんが、建物の名前は今も残っています。 29日は西から山に入り、オールドモンクロックへ向かいました。 2マイルほど行くと山の麓を通過します。さらに2マイル進み、小川を北に渡り、石梁洞まで登ります。川に戻って2マイル西に行き、謝公嶺を越えます。尾根の内側の地域はイースト・インナー・バレーと呼ばれています。尾根の麓には北から流れ出る小川があり、その両岸には重い岩や奇怪な峰がそびえ立ち、陸地がないほど急峻で、さまざまな形に削り出されている。川を渡り、北に約1マイル進むと霊峰寺に入ります。山頂は非常に急峻で、私たちの目の前にそびえ立っています。寺院の後ろには、真ん中に頂上まで貫通する割れ目がある孤立した峰があり、霊峰洞と呼ばれています。数千段の階段を登り、石の基壇が再編成され、洞窟内の羅漢像もすべて新しくなりました。下凡寺にて。私は昭丹潭の僧侶と一緒に川を左に渡り、風洞を訪れました。洞窟の入り口は半円形になっており、数歩離れたところから風が吹き出します。それから私たちは川の左側から崖の間の洞窟を探検しました。お寺に戻ると大雨が降っていたので、傘をさして裸足で北の川を上っていきました。真済寺に着く頃には山は深く霧がかかっていて何も見えなかったので、私たちは再び川を渡って東へ戻り、碧霄洞に入りました。そこには寿瑜先生の住居があります。私は何かおかしいと感じたので、少年に戻って中昭を呼ぶように頼みました。中昭も小川に沿ってやって来ました。会うのがこんなに遅いことを後悔し、日暮れに霊峰に戻って一泊しました。 30日、私たちは雨の中、小川に沿って西に2マイル進み、さらに強い北西からの流れに合流しました。川を渡って西に向かい、上流に向かって北西に3マイル歩くと、景明寺に入ります。雨はますます激しくなってきた。雲と霧の隙間から見上げると、両側に重い岩がそびえ立つ二つの崖が見えた。岩は層が重なり合っていて、層の区別がつかなかった。西の谷の奥深くへ進むにつれ、私の服と靴はびしょ濡れになりました。そこで私は、水のカーテンの谷、維摩の石室、そして法壇を見つけました。襄岩まで2マイル。岩の右側には洞窟が 2 つあり、その外側は滝で覆われています。危険な茂みやイバラの間を抜けて登りました。この洞窟は龍王洞窟、三台洞窟とも呼ばれています。 2 番目の洞窟の前にはテラスのような突き出た岩があり、板を使ってアクセスできます。洞窟から出て、襄岩の上を振り返ると、山頂に耳を向けた石が見えます。それが「詩を聞く老人」です。さらに西に2マイル進むと霊岩に入ります。霊峰から西に曲がると、そびえ立つ岩とカーテンがあります。一部は開けて景明峰となり、他の部分はまっすぐに入っていき、一仙天と呼ばれています。他の部分は開けて霊岩峰となり、峰々が重なり合って曲がりくねった道があり、真ん中に寺院があります。 5月1日、私と中昭は一緒に天蒼洞に登りました。洞窟内には東側に丸い洞窟が二つ、北側に長い洞窟が一つあり、どちらも明るく澄んでいます。しかし、真っ直ぐ下に向かって急な岩が続いており、歩くことはできません。それから私は再び寺院に下り、雑草の中を梯子を運び、子供たちを別の桟橋に導き、まっすぐに円形の洞窟の底に行き、そこで梯子を使って登りました。頂上に届かなければ、木片を切って岩の間に埋め込み、その木片の上を踏んで登りました。それでも頂上に届かなければ、ロープを使って岩の隙間の木に梯子を吊るしました。梯子も木材も使い果たしたら、ロープを使って木をこすり、丸い穴に入って中昭を呼んで話をします。私たちは同じように長い洞窟を歩き続けましたが、もう正午になっていました。彼らは西の小龍丘の麓に到着し、剣の泉を探そうとしたが、見つけられなかった。石の稜線に座り、見上げると、曲がりくねった峰々が空に近づき、険しい峰々が逆さまに差し込み、その間を流れる急流が、まるで九日間の絹糸が空から引きずり下ろすかのように見える。リトルシザーズピークを過ぎて西へ進み、アイアンプレートピークまで進みます。山は岩の上に高くスクリーンのように広がり、その下には扉のような隙間があるが、雲が現れたり消えたりして、人の痕跡を一切隠している。観音岩を過ぎると道は徐々に西に向かい、岩山は次第に広くなり、長雲峰と並んで聳える麗江峰となる。長雲峰は南に下り、下がって再び上昇し、大塵峰となる。川が流れ落ちる場所には馬鞍嶺と呼ばれる窪地があり、この尾根によって内谷の東側と西側が分けられています。霊岩から馬鞍嶺までは4マイルあり、山々はあまりにも高く険しく、圧倒されるほどです。山を越えるとだんだんと日差しが弱まり、西に太陽が沈んでいきました。西に2マイル進み、大龍丘河の河口を過ぎ、さらに南西に2マイル進むと能人寺に入ります。 2日目はお寺の裏の谷で四角い竹を探したのですが、いいものが見つかりませんでした。頂上にはエピフィラム寺院があり、とても静かで人里離れています。寺院の右側に出ると、龍丘から流れてくる水が2つに分かれて岩の間を流れる燕尾泉が見えます。そのためこの名前が付けられました。上流に向かって2マイル北へ進み、その後西へ流れて龍丘渓の河口に流れ込みます。さらに西に2マイル進み、連雲張から入ると、川の中にそびえ立つ大はさみ峰と、2つの崖と石壁が互いに融合し、大龍丘の水が空から流れ落ちるのを見ることができます。歩竹亭に座って眺めると、正面に龍潭、背後に鋏山が臨み、まるで四つの山に囲まれているような気分になります。連雲張を出て華厳嶺を渡り、合計2マイルを歩いて羅漢寺に入ります。この寺院は長い間放置されていましたが、最近、Wo Yun師によって修復されました。ウォ・ユンは80歳を超えており、その容貌は山を開いた巨大な手である飛石羅漢に似ています。私は師匠を瓊定に誘い、師匠も一緒に長雲に行くことに同意しました。しかし、燕湖は西にあるので、石門寺に行く方が便利です。すでに午後になっていて、張雲は翌日会う約束をしていたため、張雲と弟子たちは東稜を西に越え、石門寺の廃墟を通り過ぎて合計4マイルの西外谷に到着した。川を西に1マイルほど進むと、西から流れてきて合流する別の川が見つかります。これが凌雲川と保管川です。2つの川は合流して南に流れ、海に流れ込みます。それから彼は西から流れてくる川を遡り、霊雲寺に滞在しました。寺院は漢竹峰の麓に位置し、天を突き抜ける孤立した峰で、頂上から裾までわずか数センチの間隔で突然二つに分かれています。真ん中には真珠のような丸い石があり、特に素晴らしいです。川を北にたどって石家、梅魚潭に向かいます。崖から流れ落ちる滝は、ただの霧雨ではなく、とても雄大です。 3日目、私たちは東に3マイル歩き続け、小川に沿って北へ進み、石門に入り、黄の墓廟に立ち寄りました。道は北に向かって燕湖の頂上まで続いており、それほど急ではありません。まっすぐ2マイル登っていくと、山が徐々に下がっていくのが見えます。目の前に島々が見え、高く登るほど海が足元に近づいてきます。さらに4マイル進むと、私たちは山の頂上に到着しました。山は北東の最高地点から曲がりくねって連続的に伸び、その後 4 つの支流に分かれており、そのすべては石と土でできています。四つの枝の尾根はわずかに盛り上がっており、その合流地点には三つの窪みが形成されています。それぞれの窪みには南北に走る尾根があり、窪みを二つに分けています。全部で六つ以上の窪みがあります。窪地に溜まった水は雑草が生い茂る場所となり、景色全体が緑になったことから、燕湖と呼ばれました。南に落ちる水は石門から流れ、あるいは聳え立つ梅雨となり、あるいは保観滝となり、北に落ちる水は当陰水となり、大龍丘とは比べものにならないほど美しい。丘を登りきると、南には海、北には南河が一望できます。東峰だけが雲の上に高くそびえていますが、それ以外は遮るものはありません。私は大切な王冠を北西から残して行きたかったのですが、岩や茂みが密集していて休む場所がありませんでした。私たちは古い道を辿って石門まで下り、西の凌雲を過ぎ、漢竹峰から2マイル離れたところで、小川沿いにある保観寺を訪れました。この寺院は西の奥地にある人里離れた谷間に位置し、長い間放置されており、最深部では石の断崖が曲がりくねり、階段は完全に途切れています。高い崖のふもとに洞窟があり、その入り口には傾斜した岩が立てかけられています。門は2つの部分に分かれており、東屋は開放的で爽やかで、空気中に泉が吹きわたります。中には福建のカンナによく似たバナナの木がたくさん植えられており、外には新竹の鞘が上下に伸び、次第に森を形成しています。洞窟に着くと、雷のような滝の轟音が聞こえましたが、崖の岩に隠れて何も見えませんでした。それから私たちは山を下り、小川を渡りました。洞窟の右側を振り返ってみると、崖が割れ目の中に入り込んでいて、その割れ目から滝がまっすぐに流れ落ち、丸い窪みにぶつかり、窪みから飛び出して小川になっているのが見えました。高さは龍丘に次いで高く、雄大さも上回っているため、当山の中では二番目というわけではありません。古い道を東に進み、羅漢寺に泊まります。 4日目の朝、私は白い雲に覆われた長雲峰を見上げました。しかし、私は立ち止まらず、ウォユンと一緒に急いで登りました。華厳を越えて東に2マイル進み、連雲張の左側、道松洞の右側から合計3マイルの階段を登ると、下を見ると足元に間島峰が見えます。 1マイル離れたところに、龍丘の上流にあたる山から流れ出る小川があります。小川を渡り、白雲閣と雲外閣を通り過ぎ、北に進んで雲景寺に向かいます。庵も山道も以前とは違って、よく整備されていました。 倭雲は弟子たちに竹の子を摘んだり、ご飯を炊いたりするように命じました。昼食後、山頂の雲が突然消えた。中昭は尼寺に留まり、私と彼はまっすぐ東峰へ向かった。さらに2マイル進むと、徐々に水の音が聞こえてきて、大きなドラゴンプールから崖から水が流れ落ちているのが見えました。水は山頂の南と雲の北から流れ出ており、その源は谷にあります。上流へ2マイルほど行くと、水の音は次第に小さくなっていきます。あと2マイル進むと山の尾根に着きます。この尾根は北に険しい峰があり、南で2つの枝に分かれています。東の枝は観音岩、西の枝は長雲峰です。ここが鉱脈が通る場所です。主稜線の東側には五家坑がある。山頂は曲がりくねっており、近くには鉄板丈、外側には霊岩、景明、霊峰、謝公嶺があります。尾根の西側には龍丘北と呼ばれる坑道がある。峰々は曲がりくねって並んでおり、最も近いのは竜丘の対岸の断崖で、そこから芙蓉峰、凌雲峰、宝観峰と続き、最後は麗佳山で終わる。これらは燕山の南側にある山頂です。観音峰と長雲峰は真ん中にあり、すでに杖と靴の下に横たわっています。北峰だけが、まるで衝立の後ろにあるかのように後ろにそびえているようです。 2マイル北に、両端が盛り上がり、北に向かって下がっている、壁のように狭い平らな尾根があります。ここが南河の境界で、南河ほど円形ではありません。東峰から西峰まで登っていると、突然大きな足音が聞こえてきました。何十頭もの怯えた鹿の足音でした。北側には斧で真ん中を割ったような山頂があり、その中央にはギザギザの石の石筍、そびえ立つ断崖、そして底なしの深さが広がっています。鹿たちは皆逃げて溝に落ち、溝の中で死んだものもいたようです。僧侶たちが到着すると、布を引き裂くような音を立てながら、鹿に石を投げつけました。しばらくすると音は静まり、鹿はさらに大きな声で泣きました。ここから西に向かうと、石稜線は途切れ、山頂は徐々に低くなります。北西を見ると、遠くに行くほど低くなっている燕湖が見えます。 20年前、私は燕湖を探検し、東の高い峰を探しましたが、崖に阻まれて、ロープを使って降りてきました。ここがその場所です。私は過去に西へ旅しましたが、今は後悔することなく東の頂上へ旅しています。下雲井寺に戻り、小川に沿って大龍丘の頂上まで行きます。池の底にある龍池を見下ろします。崖の間にある円形で、波打つ壁から水が池に落ち、流れ落ちます。不思議な光は明るすぎて、直接見ることができません。それから私たちは渓流の西側を登り、竜丘の反対側の断崖の南に出て、二つの峰を過ぎて南に向かいました。尾根は石門の東、羅漢の西にあります。南には芙蓉峰があり、さらに南には東嶺があります。芙蓉峰は丸くて独特な山で、羅漢寺の南西の角に位置しています。底に着いて初めて私たちは道を見つけました。彼らが東の寺院に着いたとき、太陽はすでに沈んでおり、鍾昭が先に着いていました。 5日目、私たちは臥雲に別れを告げて羅漢寺を出発し、川に沿って1マイルほど進み、龍丘渓の河口に到着しました。 4マイル歩いた後、私たちは鞍部を越えて下山しました。観音峰の麓の北側を見ると、石に扉のような割れ目があり、何層にも重なった割れ目が見られます。鍾昭はすでに霊岩に向かっていた。私は少年を連れて北の峰の麓まで行き、薪の道を西に2マイルほど進み、観音と長雲の麓に到着しました。その時初めて、2つの峰は遠く離れているにもかかわらず、その下の石垣が都市のようにつながっていることに気付きました。崖を東に1マイルほど進むと、岩だらけの崖の上に出ました。木々が生い茂り、木陰もあり、道は通り抜けられず、手探りで通り抜けられるほどでした。山の外側には、雲のように薄くて丸い頂上を持つ峰がそびえ立っています。その高さは老僧の岩のように、そして立っている子供のように荘厳です。道の角には、呉姓の住民がほとんどで、そのうちの一人、呉英月さんが私を食事に誘ってくれました。私はそれを上流に運んでいき、それが鉄板と観音の間の山頂から見える五家坑渓であることに気づいた。渓流を上っていくと、左側の黄色い崖に洞窟があります。崖は鉄板丈の西側にあり、洞窟は崖の左側にあり、まるで上下二層になっているようです。底まで来ると上へは行けません。頂上から出ると洞窟は崖の間にあり、下へ降りることはできません。それから彼は崖に沿って東へ歩いていき、もう一つの石の鍵を見つけました。見上げると、入ることができるものが何層にも重なっているのが見えました。木製のはしごがなければ登るのは不可能でした。それから、私たちは英嘴岩と呼ばれる小さな山頂を下り、呉さんに別れを告げました。鉄板丈を東に過ぎると、岩の割れ目がさらに大きくなっており、その下には小川を形成する洞窟があるようでした。急いで川を遡り、洞窟の底に着きました。岩で塞がれていましたが、崖の左側にまっすぐ上へ続く道がありました。崖と垂れ下がった蔓の間には登れる道が掘られていました。そこで彼は勇敢に登り、邪魔になる服は脱ぎ、邪魔になる杖は捨てました。真っ直ぐに一つの崖を登り、次に別の崖を水平に渡り、これを二度繰り返しました。それから木の板で二度橋を架け、ついに岩の洞窟に入りました。石は扉のように向かい合って立っており、中央は広く階段で上ることができます。さらに二つの石門をくぐり、見上げてみると、四方八方に石垣が立ち並び、その周囲を青い空が取り囲んでいて、真ん中に井戸がかかっているのが見えました。壁は終わり、洞窟に貫通しています。洞窟の底には日光が差し込む木製の梯子があり、猿が猿らしく登って東屋のように見えます。亭から左に曲がると、大きな平緒山が見え、その背後には高い鉄板丈山脈があり、東西は険しい断崖に囲まれ、南には低い石の洞窟があります。家は広く、曲がりくねった道があり、まさに仙人の住居です。中には茅葺き屋根の小屋がありますが、誰も住んでいません。隙間には茶の木がたくさん生えているので、人が行き来できるように岩の上に梯子がかけられています。川沿いには住民が住んでいます。それから彼は小鋏峰を越えて東に2マイル進み、霊岩に到着し、そこで鍾昭と出会った。 6日目に、私は霊岩の僧侶たちを連れて平峡樟へ旅をしました。龍壁洞窟の右側から岩の割れ目を半マイルほど登ると、非常に奇妙な洞窟が見つかります。さらに半マイルほど登ると、崖の上の道は塞がれています。崖の端に梯子が立てかけてありますが、おそらく炭焼きの人が残したのでしょう。頂上まで階段があり、二つの崖に渡って三つの巨大な岩が積み重なっています。内側は石で覆われて部屋になっており、外側に渡っているのは妖精の橋です。部屋は明るく広く、重い岩で隠されています。奇妙で壮大な鉄板や石の扉はありませんが、人里離れた隔離された空間で、独自の世界を形成しています。再び洞窟を左上に進み、蔓や板を登ると、龍壁の頂上である平峡峰の中層に出ます。崖の端も広く、地形も高く乾燥しているので、家を建てることもできます。後ろの峰は依然として空に傾いており、峰の右側には外側を覆う岩があり、その前に飛泉が落ちています。右から再び崖を登り、頂上に近づきそうになったが、切り立った岩に阻まれてしまった。横の岩に小さな隙間があり、そこに草や木が生えていたので、足を乗せることができたので、そこを辿って下りました。崖の間にはたくさんの蔓が垂れ下がっていて、みんなはそれを摘んで持ち去りました。岩が鋭くて木を支えられない、または木が裸で足場が立たないときは、つる植物が垂れ下がります。西に向かって進むと、5層の石の丘を越え、数マイル以上の上り下りを経て、深い渓谷にたどり着きます。そこが小龍丘の上流です。峡谷は燕頂の南東に源を発し、右は鉄板、左は平峡である。峡谷は二つの峰の間の深い峡谷に流れ落ち、険しい断崖に遮られている。上へも下へも道はなく、ロープを掛けずには飛んで渡ることはできない。川に入り、石を踏みながら流れに沿って東に1マイルほど歩くと、川の向こうに大きな岩があり、水はそこを越えることができません。岩の下には穴があり、両側は険しい崖で、旅人の行く手を阻んでいます。彼らは木を束ねて梯子を作り、崖を登り、目の前の渓谷の低いところまでロープを下ろした。水平の岩の下には中空のドームがあり、そこには 10 フィートの旗を立てられるほどの広さがあった。岩の裏から水が流れ落ちて透明な池を形成しており、そののんびりとした様子が清々しい。左右の崖の上には高い位置に洞窟がそびえ立っています。ここから先は龍丘が陥落する場所です。私は二度、建泉を尋ねましたが、寺の僧侶はいつも「それは竜丘の上にあり、そこへ行ける人はほとんどいません」と言いました。それは今もどこにも見つからず、長い間失われていたことがわかっています。ここからは二つの峰を越えて仙橋から石室に行けるので、木を切り、梯子を結び、険しい崖を4回登りました。下を見ると、靴の真下に独秀峰と双洛峰が見えます。仙橋に近づいたとき、橋が崖で遮断されているのが分かりました。日が沈みかけ、私たちはとても疲れていました。そこで、以前通った道を探しに戻り、平峡の横にある石室を通って寺院に戻りました。私たちは荷物を背負って景明を通り、霊峰で一泊しました。 七日目に、私は寺の前の小川を上って、南の青空の丘を眺めました。あずまやは高くて広くて開けていて、特に目立つものはありませんでした。さらに3マイル進み、西に曲がると、小川の北の谷間に鎮済寺が見えます。渓流は西側の断崖から流れ出て峡谷を突き抜け、峡谷の南側の峰は「五頭天馬」と呼ばれ、特に雄大です。両側には狭い石畳の道があり、住民はおらず、道はイバラや雑草で塞がれています。旅は数マイルですが、非常に困難で、全部を完了することはできません。北には鎮済寺があり、北の谷間にひっそりと佇んでおり、観光客の手が届かない場所にあります。寺院の右側から、小川に沿って3マイルほど上って、瑪家山の尾根を登ります。道は非常に急です。頂上に着くと、蓮のような形をした山頂の稜線が見え、北から南を見ると、すでに靴の下にある山の南側が見えます。 「疾走二侠」は全速力で走るという意味です。「疾」(発音は「xì」)は靴の総称です。 4マイル以上歩いた後、私たちは新しい寺院を見つけました。そこで荷物を下ろし、南河を遡って当陰の景勝地を探索しました。南河は、30マイル以上離れた燕山の北西にある若若鳥嶺に源を発し、永嘉との境界となっている。尾根から南に行くと芙蓉に至り、楽清に入ることができます。尾根から西に行くと、鳳林を通り、奥県への道に入ります。渓流の南側には燕山の影があり、山は高く険しく、竹や木々が密生し、険しい南側は見えません。渓流の北側の山々は若鳥から伸びており、いずれも断崖が何層にも重なり、奇怪な形をした峰々が広がり、変化しながら広がり、雲や霧と競い合いながら、ついには途切れてしまう。山の北側にはもう一つ川があり、北河から東に流れて石門潭に至ります。門の内側には千エーカーの平野があり、住民は皆石門を戸や窓、窓として使っています。これが門の名前の由来です。北と南は小川で区切られています。南には張公義の邸宅があり、西には石仏洞、三水岩、東仙岩がある。北側には白岩寺の旧跡があり、さらに西側には特にユニークな王子金仙橋があります。私は雨の中、南門へ行きました。まず、鞏怡の家の横を通り過ぎました。そこには、家族が大勢集まっていました。上流に5マイル進み、里頭寺を過ぎると、南に石仏洞がありますが、道路が草に覆われているため入ることができません。西に10マイルのところに荘武があり、ここの嘉溪の住民は皆、葉姓を名乗っています。三水岩は北霧に位置し、岩壁が広がり、両岸から滝が流れ落ちています。岩の左側には小さな寺院があります。夕方、雨が降っていましたが、地元の人たちは村に泊まり、東仙源の美しさについて詳しく話してくれました。 8日目になっても雨は止まなかった。小川に沿って西に3マイル歩くと、渓流はさらに人里離れた場所になります。さらに 2 マイル北に小川に沿って進むと、小川を渡って雲登に続く小さな道が見えます。東に流れを渡り、それに沿って進みます。突然、山々が流れに沿って向きを変え、谷の奥深くへと入り込みます。混沌とした山と丘があります。荘武の背後から山頂がここまで伸び、その後に隙間ができ、この不思議さが現れています。地元の人たちがそれについて尋ねると、彼らは「これは飾りのついた小さな家です。洞窟の妖精はまだ外、大きな川の上流にいます」と言いました。彼らは再び外に出て、約1マイルの川を渡りました。東から流れ込む小川があり、それが東仙武渓です。大きな川を渡り、東の小さな川を上っていきます。そこには先ほどまでと変わらない山々と茅葺き屋根の家々が並んでいます。洞窟は北側の山頂に寄りかかる内側の崖に位置し、何層にも重なる黄色い竹林に覆われています。それから私たちは茂みを抜けて、岩の割れ目から入りました。最初はとても狭かったのですが、頂上に向かって徐々に広くなっていきました。彼は荘武を南に残し、東の里頭寺に戻ったが、石仏洞への道はまだ見つけられなかった。そこで彼は南河を抜けて北河から20マイル離れた紫金仙橋を訪れた。年仲昭は新しいお寺にとても近かったので、お寺まで会いに行きました。すでに日が沈みかけており、北河を訪れる時間がなかったので、東の大井に向かい、そこから戻った。 |
<<: リン・チョンは弱くて愚かな人ですか?彼の性格はどんな感じですか?
推薦する
第18章:孫宦官が密かに皇帝の印章を奪い、徐王は使者を連れてくるために役人を派遣する
『海公小紅謠全伝』は、清代の李春芳が著した伝記である。『海公大紅謠全伝』の続編であり、海睿の晩年72...
杜甫の人生においてどのような転機があったのでしょうか?なぜ李林甫によって滅ぼされたと言われているのでしょうか?
玄宗皇帝が即位して以来、唐代は平和と繁栄の時代に入り始めました。政治的安全保障は比較的安定し、社会秩...
『紅楼夢』で王希峰はなぜ賈廉との結婚を選んだのですか?
『紅楼夢』を注意深く読んだ人なら誰でも、『紅楼夢』が「賈、石、王、薛」の四大家の縁結びの物語であるこ...
「ある人への手紙」の執筆背景を教えてください。どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】別れの夢は、狭い廊下と湾曲した手すりのある謝の家に着いたときにも消えなかった。唯一愛お...
『紅楼夢』で薛宝才はなぜ長い間賈邸に留まり、出て行かなかったのでしょうか?
古典小説『紅楼夢』のヒロインの一人、金陵十二美女の一人、薛宝才。これは多くの読者が気になる疑問です。...
『天空の剣と龍の剣』の王宝宝は本当に歴史上に存在したのでしょうか?
『天剣龍驤』では、趙敏の弟である王宝宝は小説の中では脇役に過ぎず、2、3回しか登場しない。しかし、歴...
『紅楼夢』の夏夫人は誰ですか?趙叔母さんが一宏院で起こした騒動は彼女と何の関係があるのでしょうか?
『紅楼夢』の賈家には数百人の奴隷がおり、そのほとんどは賈家に生まれた召使、つまり何代にもわたって賈家...
西魏の文帝、袁宝嬪の妻は誰ですか?袁宝嬪には何人の妻がいましたか?
袁宝舒(507年 - 551年3月28日)は鮮卑人。北魏の孝文帝・袁弘の孫であり、景昭王・袁與の息子...
『易堅志』第9巻の主人公は誰ですか?
尚珠観音紹興二年、良浙の進士試験が臨安と湖州で行われた。易は村人七人とともに天柱観音を訪れ、夢占いを...
太平広済・第96巻・奇僧・藍燦をどう翻訳しますか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
『紅楼夢』で彩雲はなぜ趙叔母と賈歓を喜ばせようとしたのでしょうか?
「彩雲は小説『紅楼夢』の登場人物で、賈歓と仲良しなメイドです。これは多くの読者が気になる疑問です。次...
厳書の「環西沙・小亭の重厚な幕の裏に飛ぶツバメ」:尾を落とす龍のように、とてもドラマチック
顔叔(991年 - 1055年2月27日)、号は同叔、福州臨川県江南西路(現在の江西省臨川市)の人。...
楊家の女将軍、王蘭英とは誰ですか?楊柳浪の2番目の妻、王蘭英の簡単な紹介
楊家の女将軍、王蘭英とは?楊柳浪の2番目の妻、王蘭英の紹介王蘭英は楊柳浪の2番目の妻で、いくつかの書...
王維の古詩「世興公に贈る」の本来の意味を鑑賞する
古詩「世興公に贈る」時代: 唐代著者 王維私はむしろ野生の森に住んで小川の水を飲みたいです。王や王子...
もし趙雲と夏侯惇が実際に戦ったら、どちらが勝つでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...