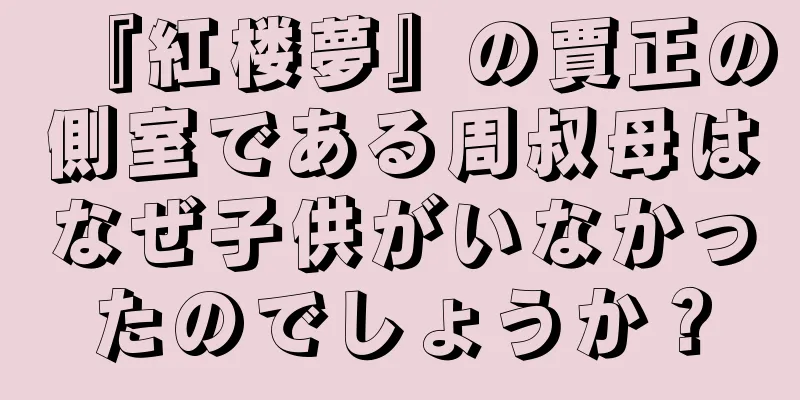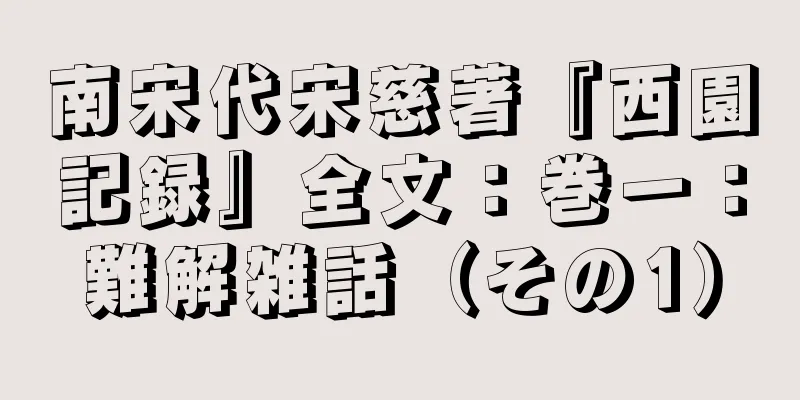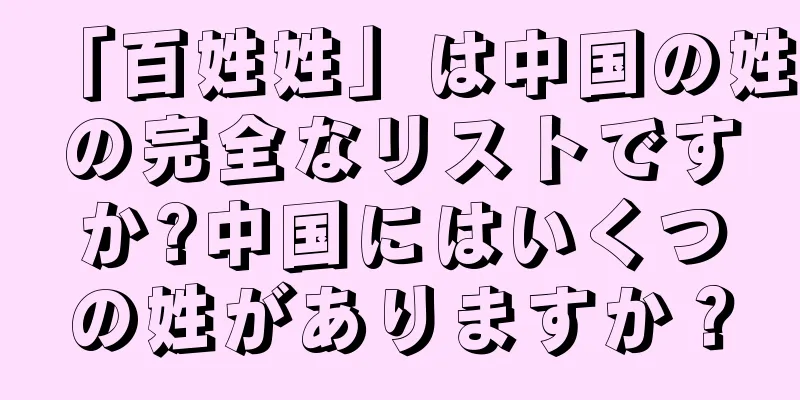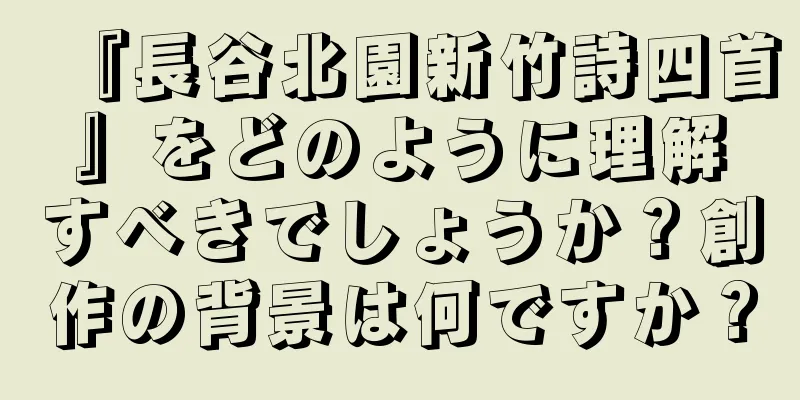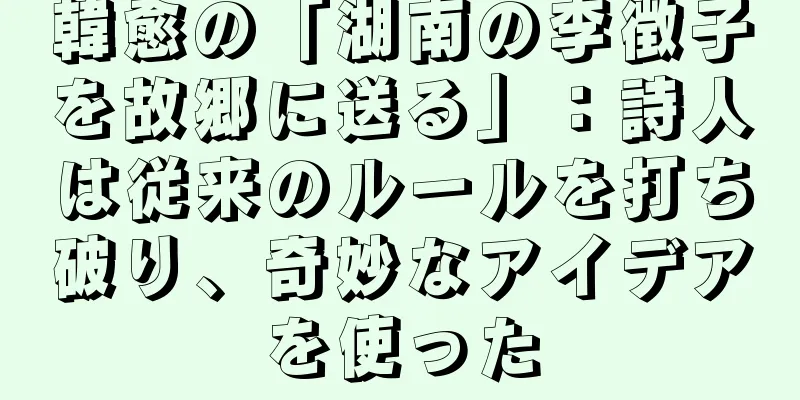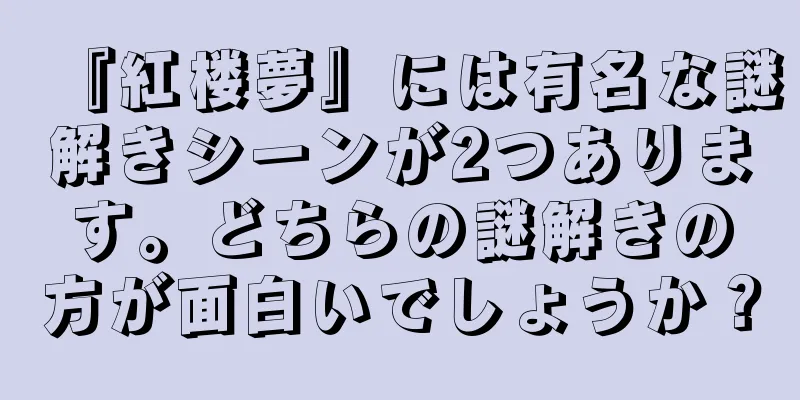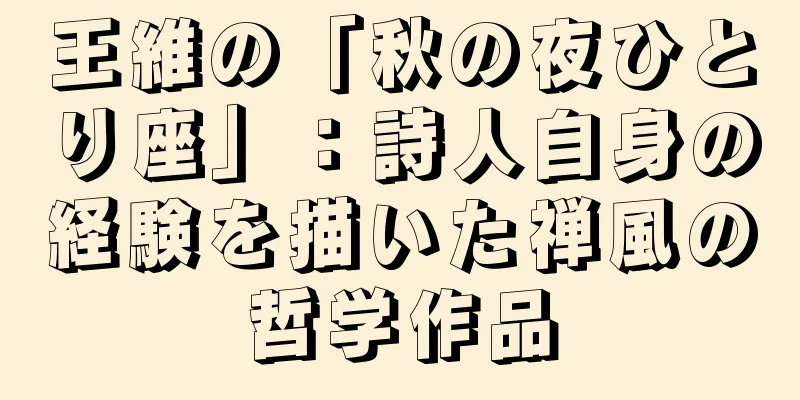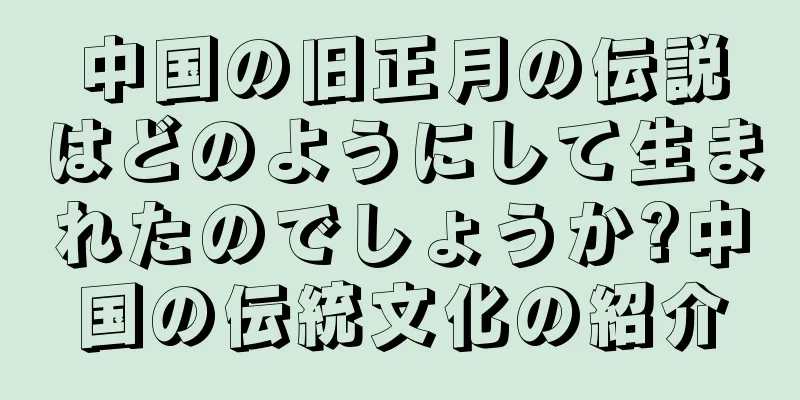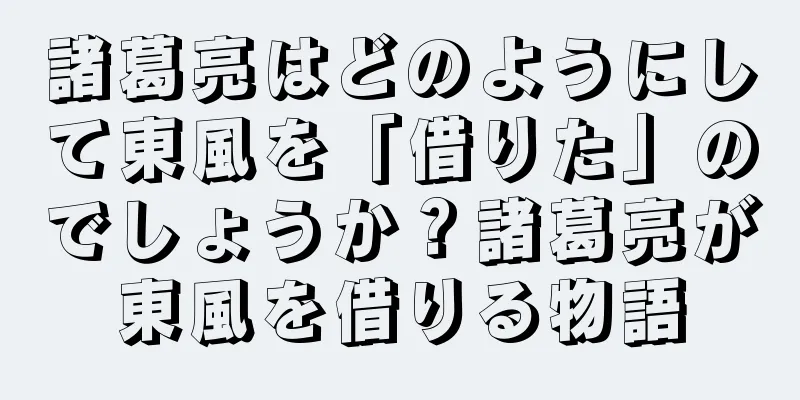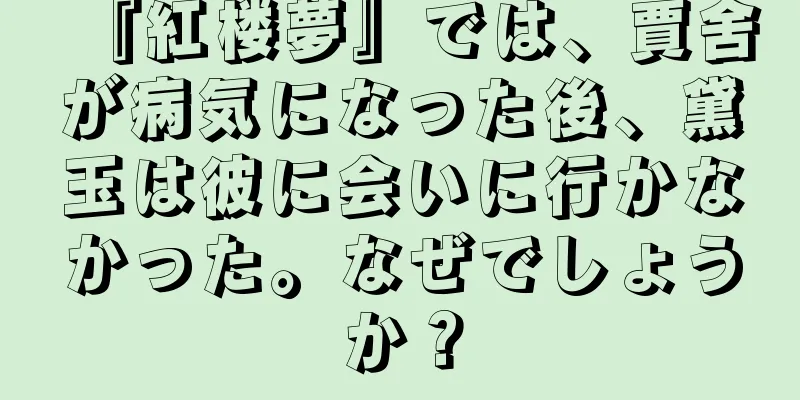なぜ曹操は司馬懿を殺す機会がなかったのでしょうか?それは司馬懿があまりにも忍耐強かったからだ。
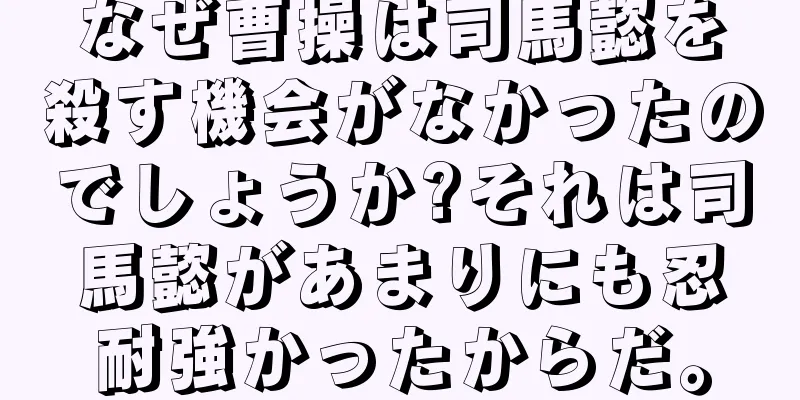
|
司馬懿は非常に有能であったが、官僚になったのは非常に遅く、30代になるまで曹操の宮廷には入らなかった。司馬懿が家系の出身であれば朝廷の官吏となるのは容易だったはずであり、その機会は建安6年、彼が20代前半の頃にはすでに訪れていた。曹操は当時、司馬懿を召集しようとしたが、司馬懿は「リウマチを患っていて起き上がることができない」という理由でその申し出を断った。これは本当に人々に傲慢さを感じさせる。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! しかし、司馬懿には、彼が誇れる独自の長所がありました。当時、ハノイで最も有名な評論家は楊俊でした。彼に評価され認められた人は、若い才能と言えるでしょう。司馬朗と司馬懿が最初に有名になったのは、彼の評論のおかげでした。しかし楊俊は司馬懿に会ったとき衝撃を受けた。「彼は普通の人ではない!」さらに、当時人を判断する能力で有名だった崔延も司馬懿を高く評価していた。彼は司馬懿の才能が兄の司馬朗よりはるかに優れていることを一目で見抜いた。崔延は曹操に頼りにされていたため、司馬懿のこともある程度理解していました。また、司馬懿は文人の間でも高く評価されていたため、曹操はずっと司馬懿を仲間にしたいと考えていました。 司馬懿を召集する最初の試みが失敗した後、曹操は司馬懿が本当に自分に仕えるには病弱であるかどうかを密かに調査するために人を派遣した。残念ながら、司馬懿はそれを非常にうまく隠蔽したため、最終的に欠陥は明らかにされませんでした。司馬懿が官職に就いたのは建安13年、曹操が再び司馬懿を召還したときであった。結局のところ、司馬懿は非常に野心的な人物でした。官職に就かなければ、おそらく彼の野望を実現する機会を失うことになるでしょう。しかし、時が経つにつれ、曹操は司馬懿が狼のような野心を持っていることに気づいたようだ。歴史の記録によると、曹操は司馬懿が「狼のような容貌」を持っていると信じていたという。彼には邪悪な野心があり、将来曹魏に害を及ぼすのではないかと心配しています。曹操の性格を考えれば、終わりのないトラブルを避けるために、そのような危険人物をできるだけ早く殺すのは当然だ。しかし曹操は司馬懿を何度も殺そうとしたにもかかわらず、死ぬまで一度も殺さなかった。なぜか? 主な理由は 2 つあります。まず、司馬懿は秘密主義で、何をするにも非常に慎重でした。彼は間違いを犯さず、曹操に殺害の証拠を見つけさせませんでした。そのため、曹操が司馬懿を殺そうとするたびに、司馬懿の邪悪な野心を疑う以外に、曹操を失望させるような行動を司馬懿が取ったことは何も見つけられなかった。今回の件は、疑いはあるものの、結局何の兆候も見られないので、諦めて警戒を強化するしかない。 第二に、その理由は曹丕です。その後、司馬懿は曹丕に選ばれ、曹丕に常に助言を与え、多くの問題の解決を助けました。重要なのは、曹丕が皇太子、つまり曹操の次の後継者になるのを助けたことです。曹丕は将来の後継者として、彼を補佐する者を必要としている。曹操は司馬懿を常に警戒していたが、司馬懿が曹丕に熱心に仕えていたのを見て、彼を殺すことを思いとどまることができた。司馬懿は非常に有能だったので、曹丕にとって彼の援助は大きな助けとなるはずでした。そのため、この時点で司馬懿を殺すことはできませんでした。そうしなければ、曹丕は将来政権を安定させるために頼れる人がいなくなってしまうからです。 しかし、これは曹操が司馬懿に対する警戒を完全に緩めたことを意味するものではない。それどころか、曹操は依然として常に警戒を怠らず、司馬懿を利用する際にはより慎重になるよう曹丕に繰り返し警告した。曹丕に「司馬懿は人間の大臣ではない。彼は必ずあなたの家事に干渉するだろう」と警告した。しかし曹操が何度も警告したにもかかわらず、曹丕は依然として司馬懿を非常に評価していました。おそらく、曹丕の油断のせいではないだろう。司馬懿は自分の行動を完璧に隠し、並外れた忍耐力を持っていたとしか言えない。だからこそ、司馬懿は最終的に曹魏の政権を掌握することができたのだ。 |
<<: 連合軍は董卓と長い間戦ってきたが、なぜ最終的に敗北したのか?
>>: 玄武門の変はなぜ成功したのか?それはすべて、李世民によって門番の一人に任命された彼のおかげだった。
推薦する
唐代の詩と酒の文化を探ります。詩と酒の文化は唐代に何をもたらしたのでしょうか?
中国文明は長い歴史を持ち、その中でもワイン文化は無視できません。次の Interesting His...
『紅楼夢』では、宝仔が宝玉を皆に知られるように手助けする一方、林黛玉は知られていないままである。
「紅楼夢」では、宝釵が宝玉を助けたことは誰もが知ることになる。宝釵の侍女が賈宝玉のために錦を作り、賈...
李尚銀の短編詩「晩陽」にはどのような感情が表現されているのでしょうか?
李尚胤の『晩陽』は雨上がりの清らかさと爽やかさの独特の美しさを表現しており、その中で「天は草を憐れみ...
蜀漢の五虎将軍は次々と亡くなりました。関興以外に五虎将軍に匹敵できる者はいるでしょうか?
三国時代は多くの武将がいた時代です。魏には五大将軍がおり、蜀には五虎将軍がいました。しかし、夷陵の戦...
曹植の『哀れな妾、第一部』は曹叡の放蕩な生活の一端を描いている。
曹植は、字を子堅といい、曹操の息子で、魏の文帝曹丕の弟である。三国時代の有名な作家であり、建安文学の...
『紅楼夢』で劉おばあちゃんが二度目に栄果屋敷を訪れたとき、何を得たのでしょうか?
『紅楼夢』では、劉おばあちゃんというキャラクターが特別な意味を持っています。これについて言えば、皆さ...
「大口と小口が出会うと、一族は滅び、民の財産は散り散りになる」という古い諺はどういう意味ですか?
諺にあるように、年長者の忠告に耳を傾けなければ、結果に苦しむことになります。では、「金持ちが貧乏人に...
水滸伝 第53話:如雲龍が決闘で高蓮を破り、黒旋風が井戸に降りて柴金を救う
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
『紅楼夢』で、王夫人はなぜ宝玉を大観園から強制的に退去させたのですか?
王夫人は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公の一人です。次は『おもしろ歴史』編集者が歴史物語をお届けしま...
明代の数秘術書『三明通会』第5巻:正式全文について
『三明通卦』は中国の伝統的な数秘術において非常に高い地位を占めています。その著者は明代の進士である万...
李游の詩『夕洛春:夜の化粧、雪のように輝く肌』は、宮廷での歌や踊り、宴会の盛大な行事を描写しています。
李郁は五代十国時代の南唐最後の君主であり、唐の元宗皇帝李靖の6番目の息子でした。李毓は皇帝の座に就く...
厳書の「燕は梁に帰る:二羽の燕が絵堂を飛び回る」:これは盛大な宴会を描写した詩である
顔叔(991年 - 1055年2月27日)、号は同叔、福州臨川県江南西路(現在の江西省臨川市)の人。...
もし、街亭の戦いで馬謖が主将でなかったら、北伐の結果はどうなっていたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『新世界物語集』第 39 話「美徳の章」はどのような物語を語っていますか?
周知のように、『新世界物語』は魏晋時代の逸話小説の集大成です。では、『新世界物語・徳』第39篇はどん...
黄巣蜂起の具体的な状況はどうだったのでしょうか?黄巣の反乱は唐王朝を倒した可能性があるか?
本日は、Interesting History の編集者が黄巣蜂起に関する関連コンテンツをお届けしま...