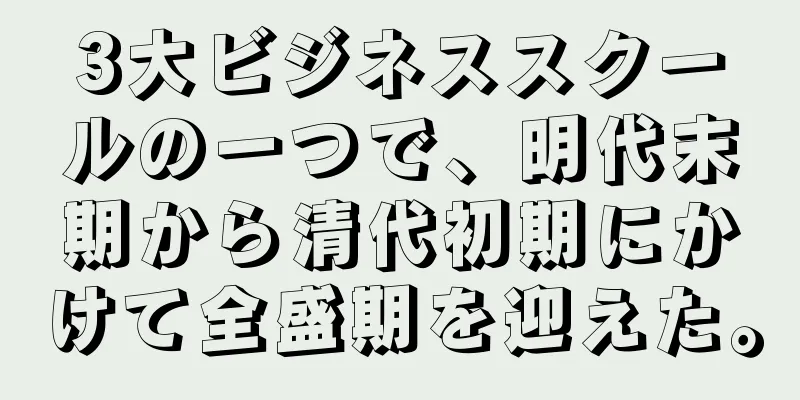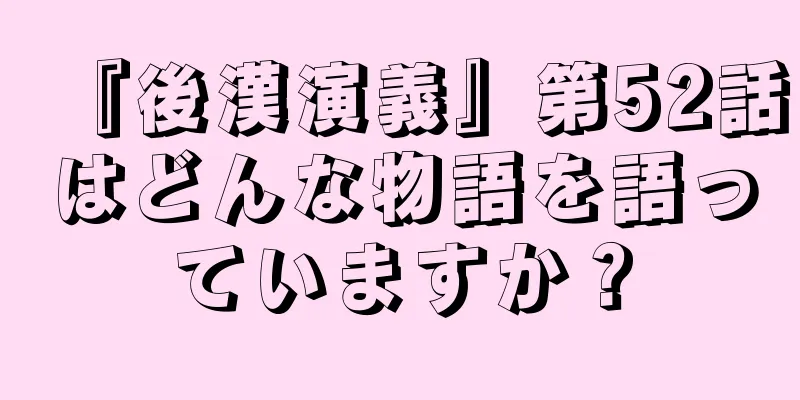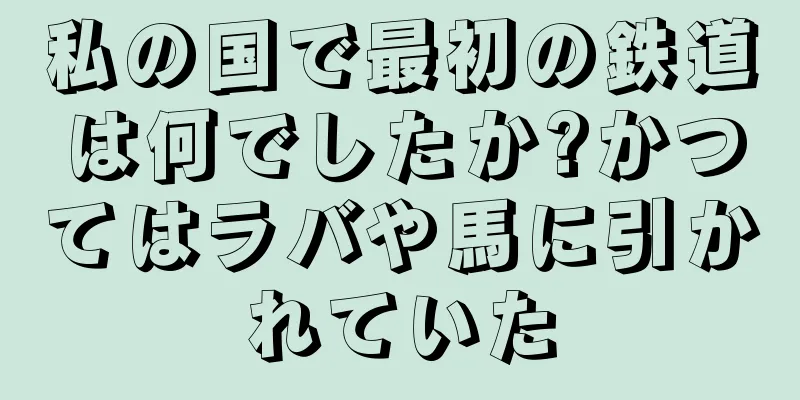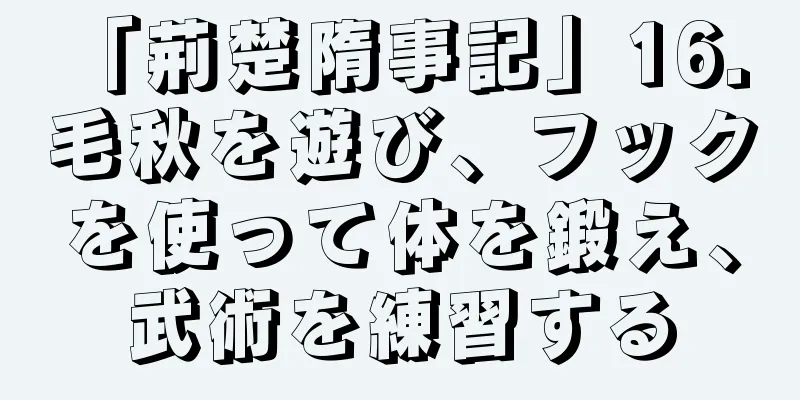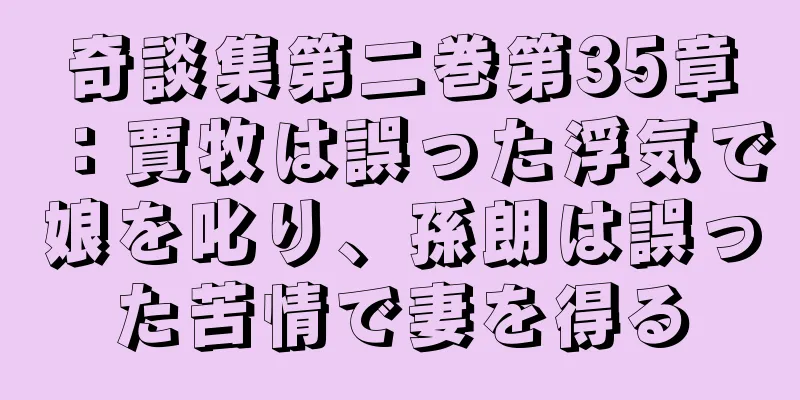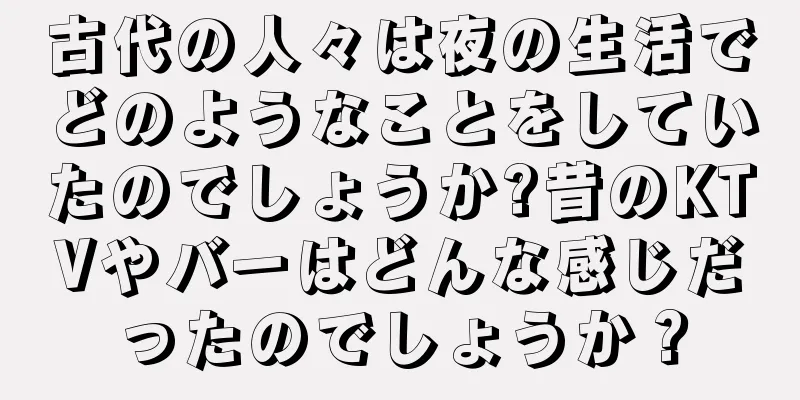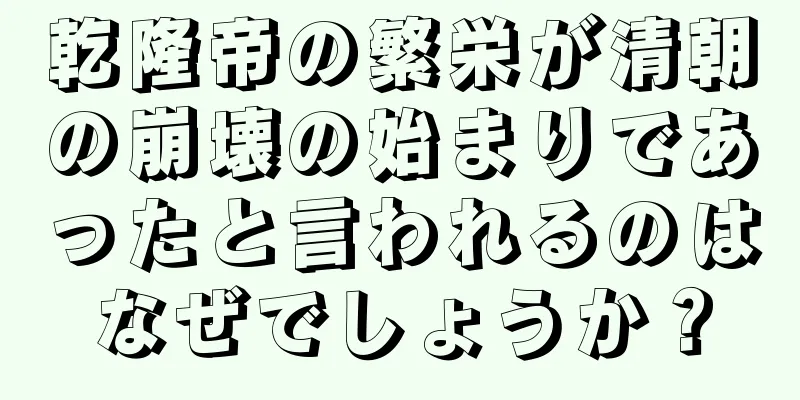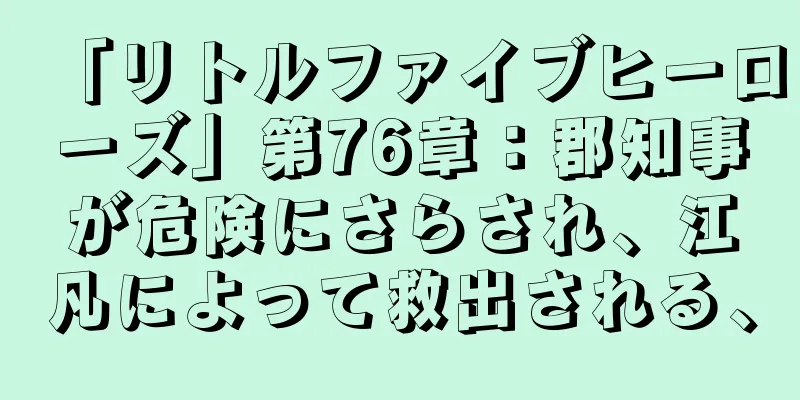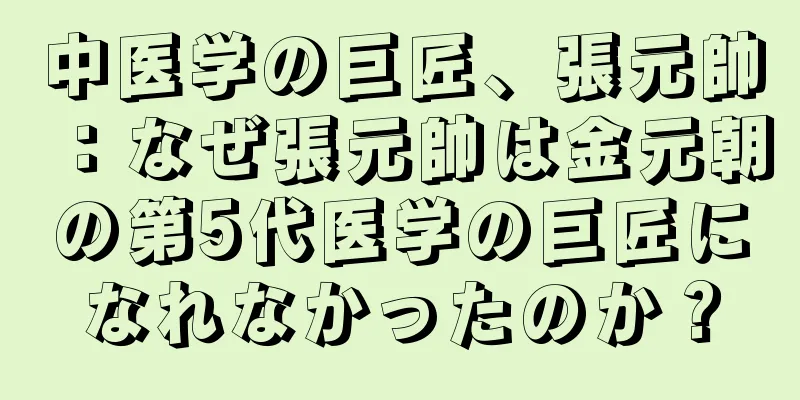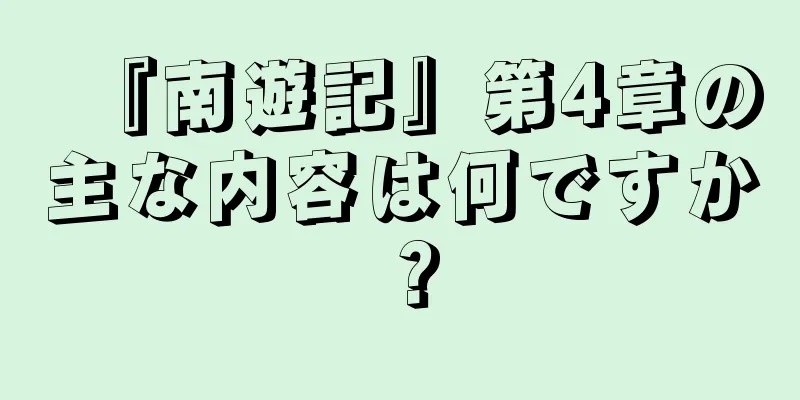項羽はなぜ揚子江を渡らずに自殺したのでしょうか?それは彼が「江東の長老たちを見るのが恥ずかしかった」からだった。
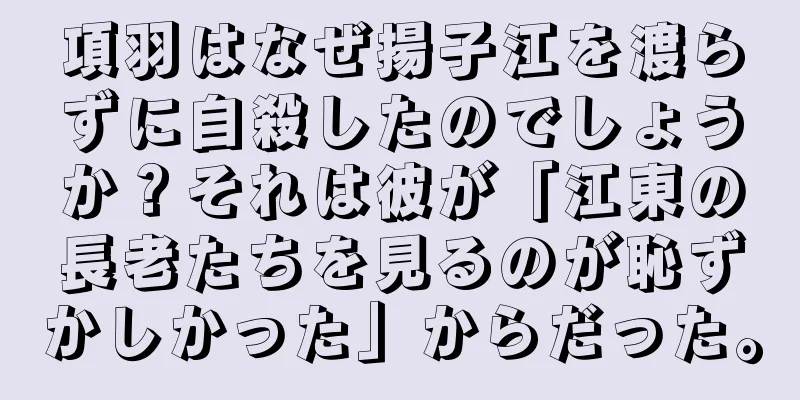
|
『史記・項羽伝』の中で、司馬遷は項羽が長江を渡らずに自殺した理由は「江東の長老たちに会うのが恥ずかしかった」ためだと信じていた。 『項羽記』には、項王がため息をついたと記されている。「天が私を滅ぼしたのに、なぜ川を渡らなければならないのか。さらに、私と江東の若者8000人は西へ川を渡ったが、今は誰も戻ってこない。たとえ江東の長老たちが私を憐れんで王にしてくれたとしても、どうやって彼らに向き合えばいいのか。何も言わなくても、罪悪感は残るのではないか」。この記録があるからこそ、後世の人々は項羽の死について語るたびにため息をつくのである。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 1. 司馬遷は、項羽が「江東の長老たちに会うのが恥ずかしかった」ために揚子江を渡らずに自殺したと信じていた。 しかし、宋代の学者である劉寶は、その著書『平山全集』の中で、項羽がそのような言葉を言ったのは、庄屋が不正をしているのではないかと疑っていたからだと信じている。劉子は、当時劉邦が項羽の命を買うために千金と十万戸の賞金を出していたと信じていた。項羽がこのような困難な状況にあったとき、亭主がこのような優しい言葉をかけたので、項羽は亭主が自分を騙しているのではないかと疑わずにはいられなかった。 2. 宋代の学者である劉子は、項羽が衛兵が不正行為をしていると疑っていたためにそう言ったのだと信じていました。 また、項羽が蓋下への逃亡を選んだのは、逃げ出せると期待したからだとも信じていた。四方を敵に囲まれているのに、どうして亭長の言葉に耳を傾けることができただろうか?そこで項羽は劉邦の軍と死ぬまで戦うことを選んだ。 1980年代に、新たな理論が生まれました。呉如宇氏に代表される学者たちは、長期にわたる内戦が人民に大きな苦しみをもたらしたと考えました。項羽はこれに気づき、できるだけ早く戦争を終わらせるという考えを思いつきました。それで彼は決然と自殺した。 3. 項羽はできるだけ早く戦争を終わらせたかった しかし、すぐに異論を唱える者もいた。『史記』には、項羽は秦を滅ぼす過程でも、楚漢戦争勃発後も、非常に残酷な人物だったと記されている。そのような人物が、自らを犠牲にして民の苦しみをなくすことができるでしょうか。これは明らかに項羽の性格と一致しません。 項羽の自殺の真相解明:長江を渡ることを拒否したのには理由があった 呂陽祥は、項羽が長江を渡ることを嫌がった理由は、彼の特異な性格と特殊な心理的要因によるものだと信じていた。項羽は常に「彼か私か」という闘争哲学を信じていた。彼は勝利すると敵を完全に滅ぼし、妨害されると自らを滅ぼすこともいとわない。そのため、敗北したとき、彼は呉江で喉を切って自殺することを選んだ。 4. 項羽は常に「彼か私か」という闘争哲学を信じていた もう一つの分析は、項羽は楚の人であり、楚の人には戦いに敗れた後に自殺するという伝統があったというものです。そのため、弾薬も食料も尽きて敗北した項羽に残された唯一の選択肢は自殺することだった。項羽が揚子江を渡ることができなかったのか、それとも揚子江を渡る意志がなかったのかは、今日に至るまで判明していない。私たちに残されているのは、呉江のほとりでの彼の英雄的行為と、呉江のほとりでの彼の悲劇的な最期だけです。おそらく、こうした不完全さがあるからこそ、歴史は違った種類の美しさを見せてくれるのでしょう。 |
<<: 劉勇はどのようにして「せむし男」というあだ名を得たのでしょうか?昼夜を問わず国政に尽力してきたからこそ
>>: 「少しの忍耐力の欠如が大きな計画を台無しにする」ということわざがありますが、三国時代で最も忍耐力があった人は誰でしょうか?
推薦する
唐代の宰相、魏昭渡の評価はどのようなものでしょうか?
魏昭都の紹介文には、魏昭都が中国の唐代の宰相であったことが記されている。歴史書には魏昭都の生年に関す...
古代人はなぜ小豆を「アカシア豆」と呼んだのでしょうか?
小豆は古来より恋煩いの象徴として使われてきました。また、バレンタインデーにはカップルが愛を表現するた...
東周紀伝第35章:金崇允が諸国を旅し、秦淮英が王子と再婚する
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
なぜ曹操は王秀を自分の配下に置き、自分に仕えさせたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
岑申の古詩「許青国務大臣東帰の草庵に詩を残す」の本来の意味を鑑賞する
古詩「徐青国務大臣の草庵に詩を残す」時代: 唐代著者: セン・シェン古来の名将に感謝することなく、私...
中国の神話では、水蓮はどのようにして人工的に火を起こしたのでしょうか?
古代我が国には、人類の生活が原始的な集団から初期の氏族共同体へとどのように進化したかについての伝説が...
『紅楼夢』の青文が最終的に犠牲者となった本当の理由は何ですか?
青文は小説『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の第一号であり、賈宝玉の部屋の四大侍女の一人である。「...
渾源金杯、金剛腕輪、人族袋の中で、最も強力な魔法の武器はどれですか?
『封神演義』と『西遊記』に登場する三つの宝物、渾源金杯、金剛腕輪、人族袋のうち、どれが一番強いのか知...
「卜算子·咏梅」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
不算子:梅の花の頌歌陸游(宋代)宿場町の壊れた橋の脇には、主のない寂しい花が咲いている。もう夕暮れで...
初代皇帝である道武帝拓跋桂はなぜ自分の息子によって殺害されたのでしょうか?
道武帝拓跋桂は、初代皇帝として、治世の初期には積極的に領土を拡大し、国を治めることに尽力し、北魏政権...
魏英武は『楊子を初めて出発する時に袁大小書に宛てた手紙』の中でどのような感情を表現したのでしょうか?
「楊子を初めて去る時、校長袁達に宛てた手紙」は、魏英武が広陵から洛陽に帰る途中に書かれたものです。袁...
奇談集第28巻:程超鋒が首なし女と一人で遭遇、王童班双雪は説明不能
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
西遊記で白龍馬がなぜ小白龍と呼ばれているのか?西海龍王の決断が本当の理由を明らかにする
『西遊記』では、唐僧が二番目に受け入れた弟子は実は蕭白龍だったが、彼は後から来た八戒と沙僧を兄貴と呼...
知っておくべき西洋神話9選:スフィンクスの謎とは?
▲パンドラの箱パンドラはギリシャ神話に登場する最初の地上の女性です。プロメテウスが天から火を盗んで人...
潘璋とは誰ですか?そしてなぜ関羽と黄忠は彼に対して何もできないのですか?
劉備は、その個性的な魅力で多くの賢者や野心家を魅了しました。例えば、「武聖」として知られる関羽は、誰...