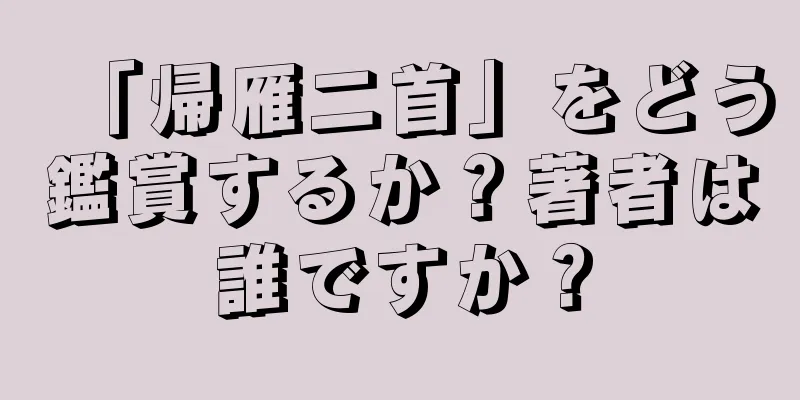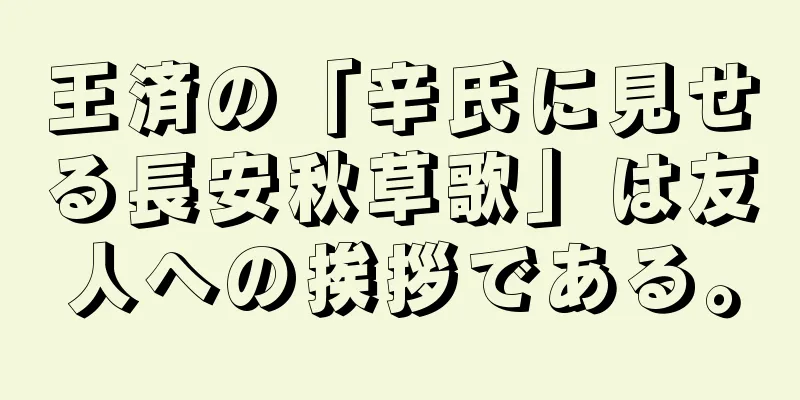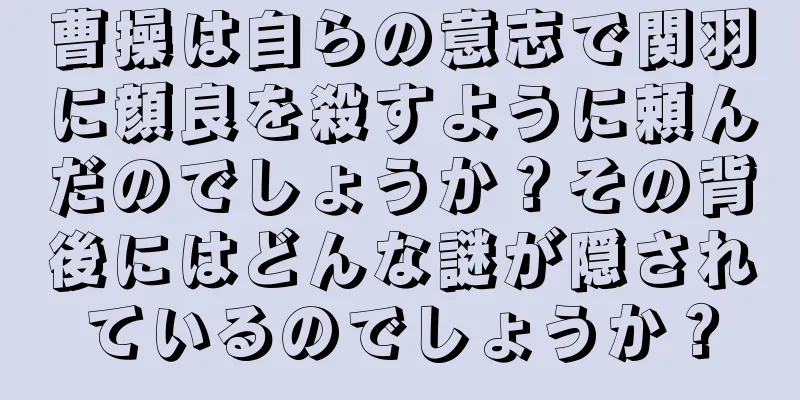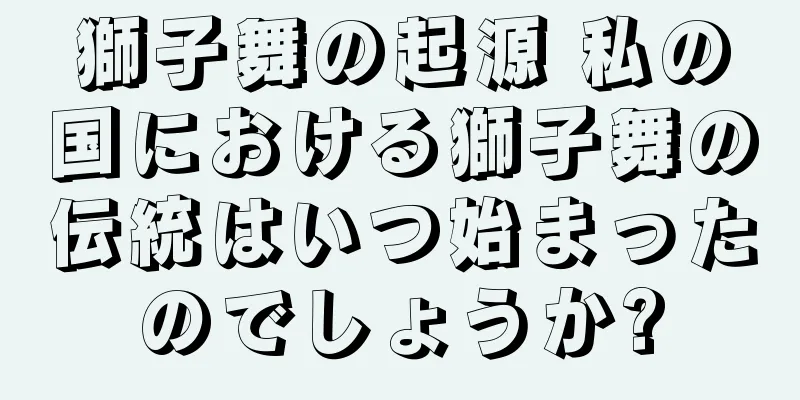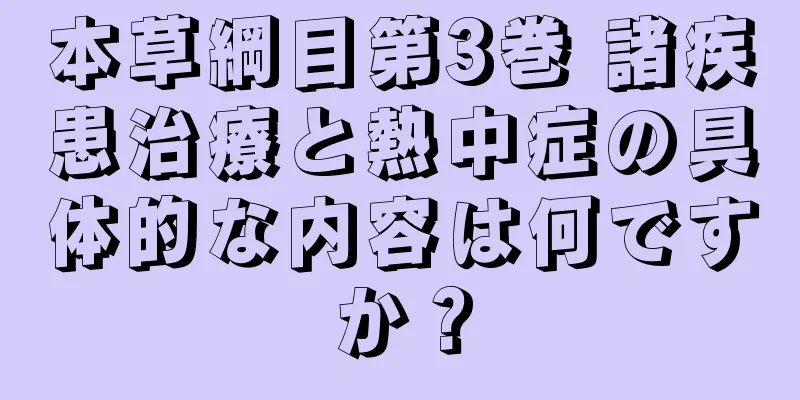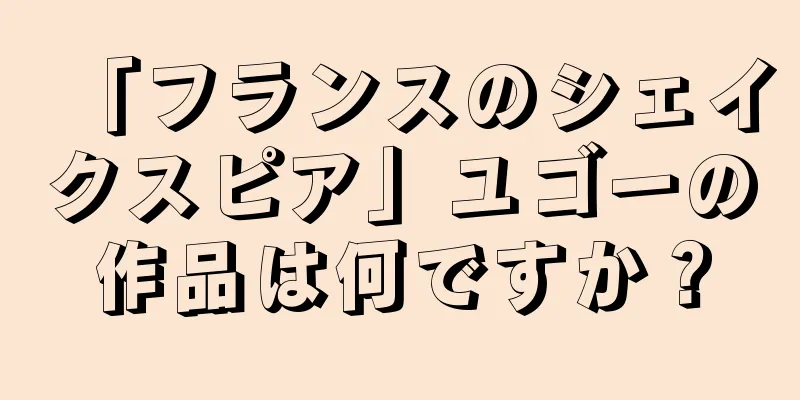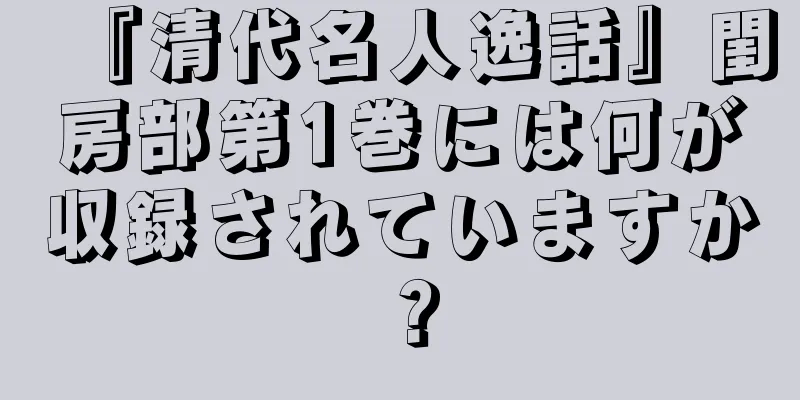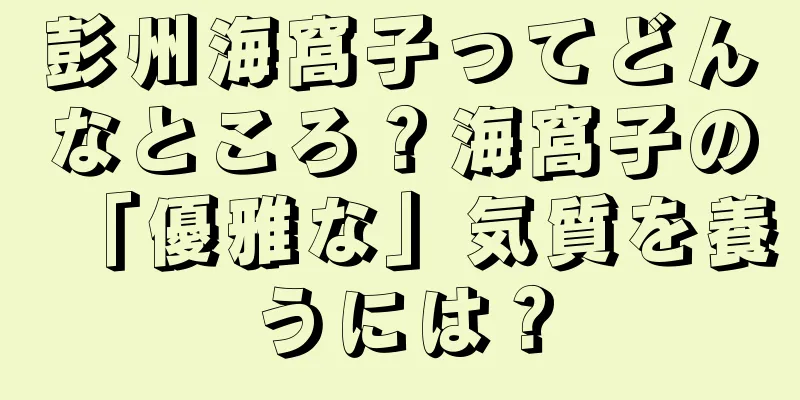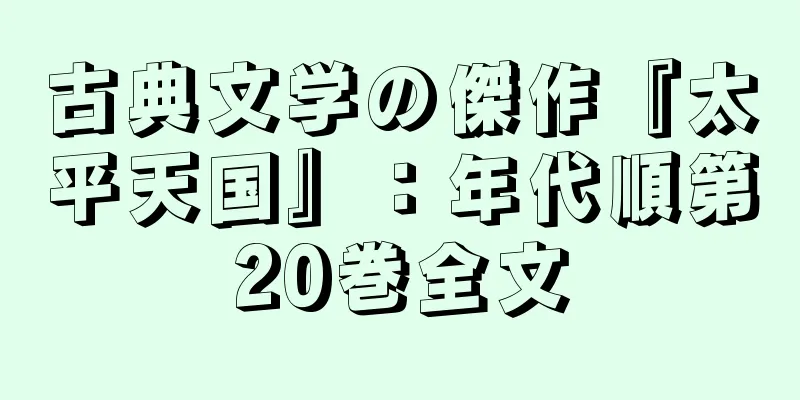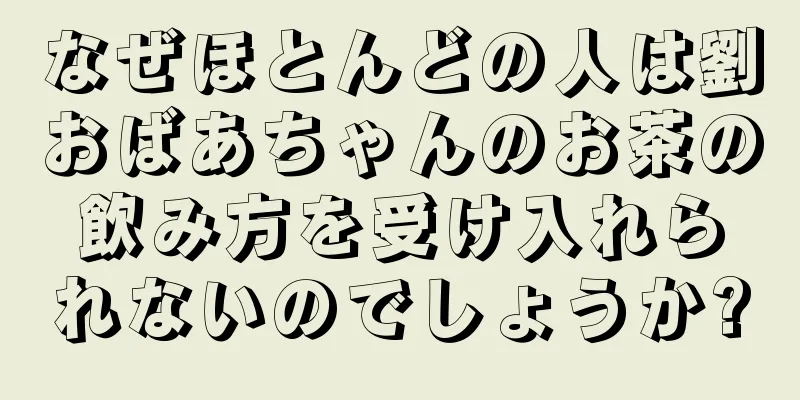秦の統治者に大きな影響を与えた思想はどれですか?秦の始皇帝の統治思想はどこから来たのでしょうか?
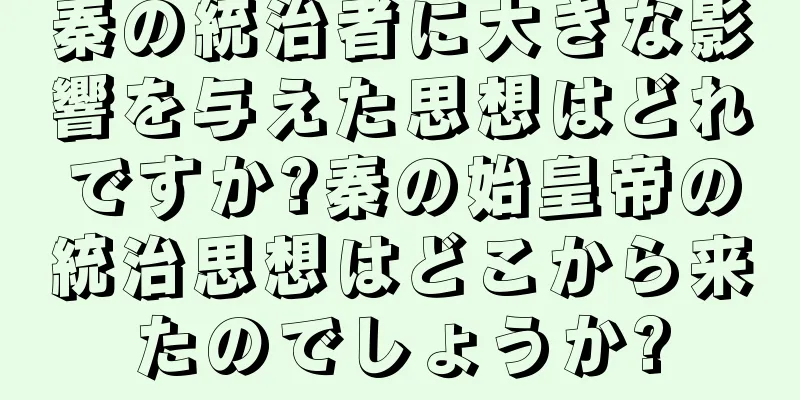
|
「法による教育」は、『韓非子』の「五蘊」の章に由来しています。「故に、賢い君主のいる国には文書がなく、教育は法律に基づいている。」つまり、人々は知識を学ぶことができるが、その内容は朝廷の法律と制度に限定されるということです。このようにして、人々が目にするのは裁判所の法律と布告だけとなり、人々は政府の要求に従うことになり、「統一された政府布告」という目標が達成される。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! これは秦王朝が国民を無知に保つために実施した政策の一つであり、また、思想統制を強化し、国家の統一を強化するための手段でもあった。しかし、システムは何もないところから生まれるものではなく、その作成と実装には理由がなければなりません。秦の時代に実施された「法を教とする」政策も同様であり、秦国におけるその創設と実施には深い歴史的ルーツがある。 秦が統一する前、商閻の改革を経験していたにもかかわらず、政治と経済において東の六国よりも優位に立っていました。しかし、秦国は西の辺境に位置しており、その文化は常に比較的遅れていました。秦の歴代の王たちも領土の拡大に主な努力を注いだ。秦の孝公の前に、穆公と献公が容族と狄族と戦い、秦が関中地方にしっかりと根付くことを可能にした。秦の孝公は商阳を任命し、その改革政策は富国強兵に重点を置いた。商阳は農業と戦争に力を入れたが、文化と教育は比較的弱かった。後世の人々は「孔子が西に旅しても秦に至らなかった」という言葉をよく使い、秦の文化と教育の遅れを象徴している。戦国時代、各国に百家万家の思想が生まれた時代、秦の国は荒廃し、基本的には法家、外交家、墨家の影響のみが見られた。 法家が秦の国に大きな影響力を持っていたことは前回の記事で何度も指摘した。 『史記』には秦の孝公が商阳と出会ったときの様子が記録されている。 公叔が亡くなった後、公孫楊は秦の孝公が穆公の跡を継いで再び東を侵略するために国内で人材を探すよう命じたと聞き、秦の西へ行き、穆公の寵臣である荊堅を通して穆公に面会を求めた。蕭公が衛陽と会ったとき、二人は長い間話をしたが、蕭公は眠ってしまい、話を聞かなかった。解任後、蕭公は荊建に腹を立てて言った。「あなたの客はただの愚か者だ。どうして利用されるのだ?」荊建は衛陽に譲った。魏楊は「皇帝の道については説いたが、あなたの志は未だに実現していない」と言った。5日後、彼は楊にもう一度会いたいと申し出た。商阳は再び小公王に会ってさらに善良になったが、それでも王の承認は得られなかった。罷免後、孝公は再び荊簡に帝位を与え、荊簡もまた楊に帝位を与えた。商阳は言った。「私はあなたに王の道を勧めましたが、あなたはそれを受け入れませんでした。もう一度商阳に会いに来てください。」商阳は再び蕭公に会いましたが、蕭公は彼を気に入ってはいましたが、利用しませんでした。 それでは出発します。蕭公は荊建に言った。「あなたは良い客人であり、話しても構わない。」楊楊は言った。「私はあなたに覇者になる方法を説き伏せたのに、あなたは私を利用したいようです。あなたがまた私に会いに来れば、何が起こったのか分かります。」蕭公は再び楊に会った。公爵が彼と話しているとき、彼は自分の膝がマットの上に前に出ていることに気づいていなかった。何日もこのことについて話しても飽きることはありません。荊建は言った。「どうやって主君を殴ったのですか? とても深刻です。 「商阳は言った。「皇帝の道を三代の王朝に例えよと言ったが、お前は『長すぎる、待てない』と言った。さらに、賢明な君主は皆、自分の名声を世界中に知られています。皇帝になるまで何十年、何百年も待つことができるでしょうか。『それで、私はあなたに国を強くする方法を勧めました。そしてあなたは大いに喜んでいます。しかし、その徳を殷や周の時代の徳と比較することは困難です。 ” この一節から、秦の孝公は富国強兵の方法を見つけることにのみ関心があり、他の理論には関心がなかったことがわかります。法家の教義は秦孝公の心理にぴったり合ったため、秦孝公と商阳は意気投合し、すぐに「黄金の二人組」を形成し、秦で抜本的な改革を実行し始めました。 前述のように、改革は大成功し、秦はすぐに戦国時代最強の国となった。この即効性は秦の政府と人民に深い印象を残し、秦の人民は次第に商鞅の「法を教とする」という考えを受け入れるようになった。それ以来、法家思想は秦国内で確固たる地位を築きました。商鞅の改革に反対していた保守派も、商鞅の死後は法家の政策を支持しており、秦国内における法家の影響力がうかがえます。 法家に加えて、墨家や外交学派も秦の国に一定の影響力を持っていました。 墨家は「普遍的な愛」、「非侵略」、「高潔な人々への尊敬」、「団結への尊敬」を主張した。この四大命題のうち、「不可侵」は秦国では絶対に通用しない。秦人は農耕と戦争で国を築き、商閭以降は武勲と貴族制度を実施していたため、秦人が墨家の「不可侵」理論に従うことは不可能だった。墨家思想が秦の国で地位を占めることができたのは、それが法家思想と類似点を持っていたからである。 「商統」理論は、「上人が正しいと思うことは、下人も正しいと考えなければならない。上人が間違っていると思うことは、下人も間違っていると考えなければならない」としている。この理論は、君主制を強化し、中央集権的な行政システムを確立するという法家の考えと非常に一致している。また、墨家自体も極めて厳格な組織と厳格な内部規律を有しており、これは秦の人々の法治思想とも合致していた。 かつて、秦の国で墨家の指導者(墨家は最高指導者を指導者と呼んでいた)が活躍していたとき、その息子が秦の国で人を殺した。秦の法律によれば、人を殺せば死刑に処せられる。しかし秦の恵文王は居子を見つけ、居子には息子が一人しかいないので赦免の勅令を発することができると言い、居子が同意することを期待した。しかし墨家の指導者は、墨家は独自の規則を持っていると言いました。「殺した者は死刑に処せられ、傷つけた者は罰せられる。これが殺傷が禁じられている理由です。」さらに、殺傷を禁じることは「世界の大正義」です。たとえ王が赦免できたとしても、墨家の規則に従って死ななければなりません。結局、居子は秦王の要求に同意せず、彼の息子は秦で亡くなりました。 この厳格でほとんど宗教的なほどの法の尊重は、まさに秦国が尊重した法治の精神であり、これが墨家が秦国に足場を築くことができた理由である。しかし秦の統一後、墨家は衰退し、おそらく法家へと変化し、秦の法官僚組織に統合された。 外交官たちも秦国内で一定の影響力を持っていた。当時の外交官たちは、各国の君主や大臣から愛され、また憎まれていた集団でした。多くの場合、彼らの雄弁さは数百万の兵士、特に蘇秦と張儀に匹敵します。彼らは口だけで「王子たちが怒って恐れ、天下が平和になる」ことさえできます。しかし、現実には、彼らは明確な社会政治的な考えを持っていないため、本当の意味での思想学派とは言えません。今日まで受け継がれてきた考え方が一つあるとすれば、それは利益を追求する実用主義である。 外交官たちの考えは浅はかで、目的を達成するためには手段を選ばなかったが、秦国の何世代もの統治者は、外交官たちが秦国の強さに貢献したことを自分の目で目撃した。特に、張儀は秦の六国統一の際、東方の国々を弱体化させるのに貢献したが、これは何十万もの秦の軍隊をもってしても容易には成し遂げられなかったことである。そのため、秦の歴代の君主たちは常に外交官を好んでいた。外交官たちの実利的なスタイルと、目的を達成するための無節操なアプローチも、秦の統治者の思想とスタイルに深く影響を与えました。 |
<<: 秦の始皇帝は、秦軍が白越で敗北したことを知った後、後世に利益をもたらすどんな偉業を成し遂げたのでしょうか。
>>: 「律法を教えとして用い、役人を教師として用いる」とはどういう意味ですか?秦の始皇帝はなぜこの政策を実施したのでしょうか?
推薦する
黄庭堅の『清遠:益州に到着し、同じ韻で詩を書いて七番目の兄に報いる』:著者は人々に心の広い態度を与える
黄庭堅(1045年6月12日 - 1105年9月30日)、字は盧直、幼名は聖泉、別名は清風歌、善宇道...
チワン族の建築:チワン族が慣れ親しんでいる高床式建築の特徴は何ですか?
連山荘族の村落の住宅建築は、明代末期から清代初期にかけて、茅葺き屋根の家からレンガや瓦の家へと徐々に...
鏡の中の花 第89章:チャン・ユアンジが新しい詩を語り、過去を遡り、過去を説明する
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
『紅楼夢』で賈宝玉は誰と関係を持っていましたか?
『紅楼夢』のファンとして、突然このような話題を持ち出すのは冒涜のように思えます。しかし、古典の名作、...
諸葛亮はなぜ馬謖を街亭の守護に使ったのでしょうか?諸葛亮は新しい人材を昇進させたいと考えていることが判明
諸葛亮はなぜ馬蘇を昇進させたのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょ...
蒙恬は秦王朝にどのような貢献をしたのでしょうか?蒙天はどのようにして秦の道を完成させたのでしょうか?
孟天は匈奴を破り、数千マイルにわたって敵を撃退した後、軍隊を率いて国境を守り続けた。孟天は「危険を利...
『年女嬌:赤壁の過去を思い出す』をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
年奴嬌:赤壁の追憶蘇軾(宋代)川は東へ流れ、その波は歴代の英雄たちを洗い流した。古城の西側は三国時代...
春秋戦国時代は奴隷社会でしたが、奴隷は具体的に何をしていたのでしょうか?
春秋戦国時代は奴隷社会でした。では奴隷たちは何をしていたのでしょうか?次の面白い歴史編集者が詳しく紹...
岳飛伝説第54章:秦檜は権力を乱用したために降格され、皇帝の使節である唐淮は自殺させられた。
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
諸葛亮が死ぬ前に「龐徳公よ、助けて」と叫んだというのは本当ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
関寒卿の『大徳歌下』:最初の一文「喬敵」は詩全体を支配する鍵となる一文である。
関寒卿(1234年以前 - 1300年頃)は、本名は不明、号は寒卿、号は易寨(易寨、易寨索とも表記)...
岳飛伝第59章:兵士を呼び戻し、勅令を偽造して金メダルを授与、悪夢の禅師が詩を贈った詳細
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
『紅楼夢』の黛玉の乳母は誰ですか?彼女は本の中でどのように描写されていますか?
『紅楼夢』では乳母が特別な存在です。『おもしろ歴史』編集者が関連コンテンツをお届けします。ご興味のあ...
「バラの洞窟」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
ローズケーブ古林(明代)数百フィートの長さのバラの枝が巻き付いて、花嫁の部屋を形成しています。密集し...
なぜ趙匡胤は「一杯の酒のために武力を放棄する」という大胆な行動に出たのか?彼は勇敢な将軍たちが反乱を起こすことを恐れていないのでしょうか?
趙匡胤は陳橋の乱を経て宋王朝を建国したので、当然軍事力の重要性を理解しており、即位後は属国の勢力を弱...