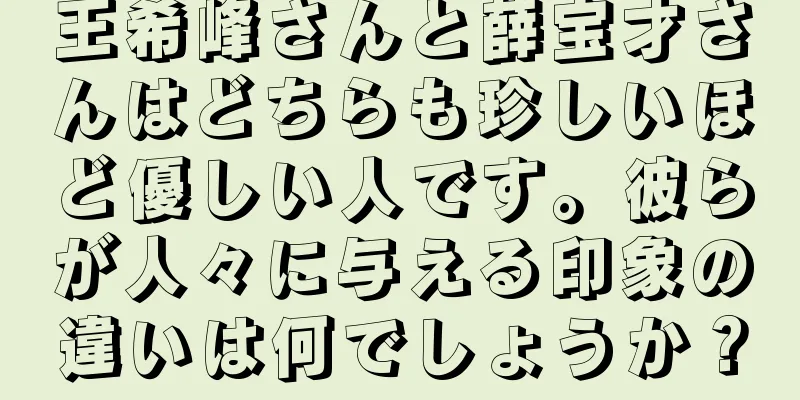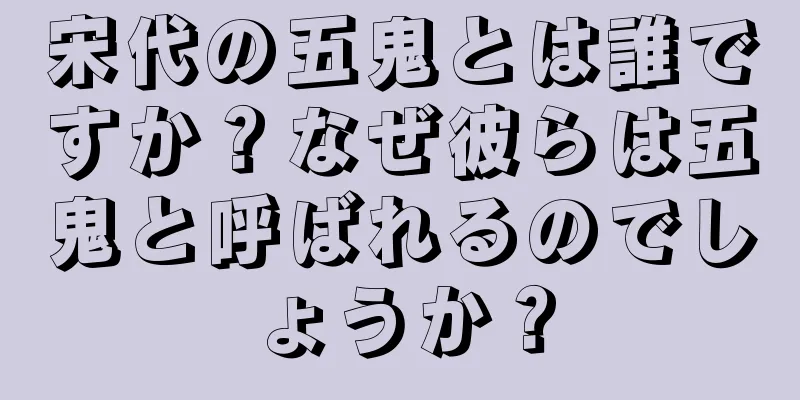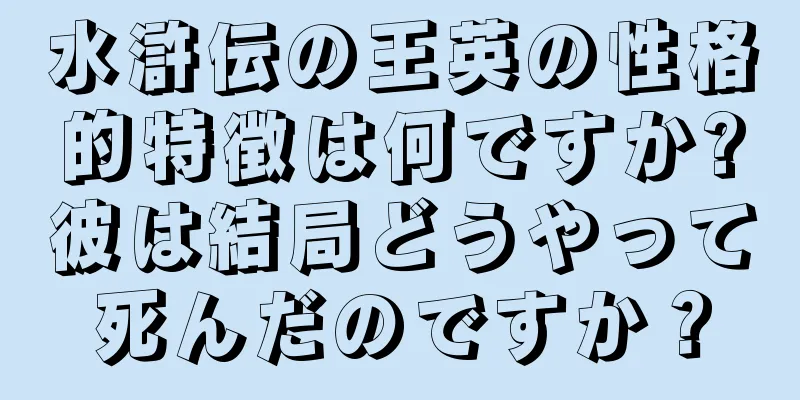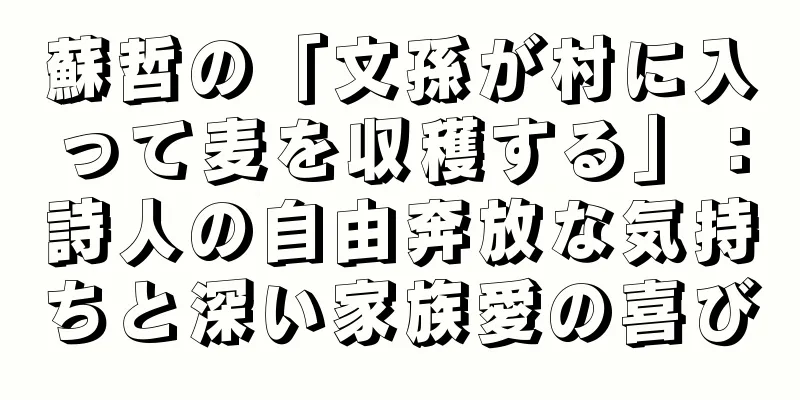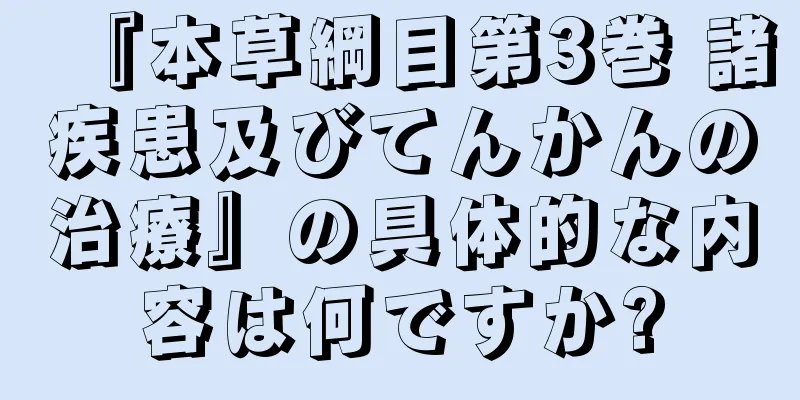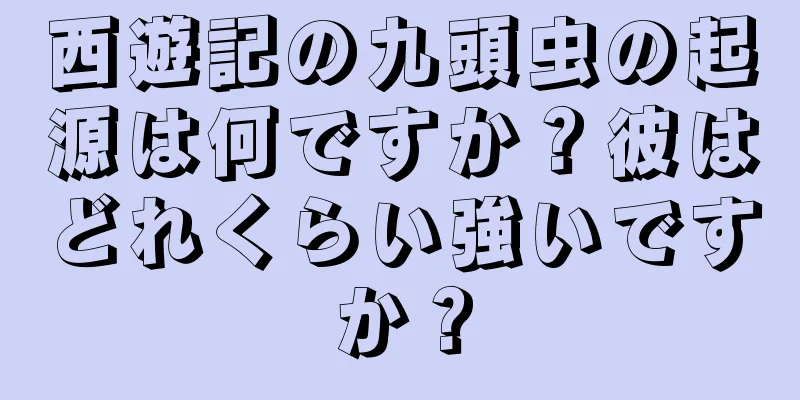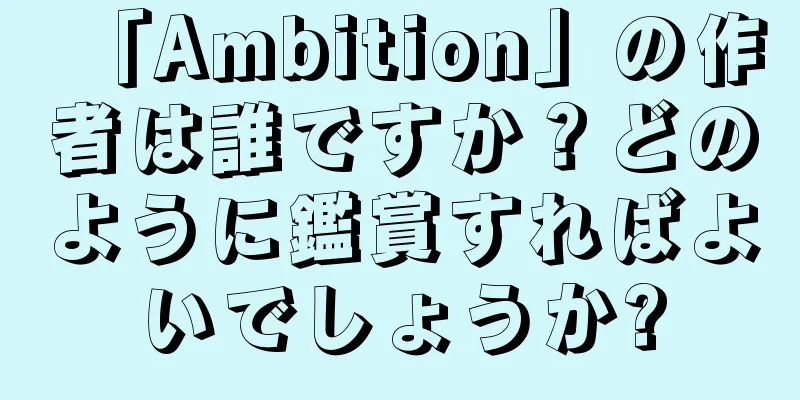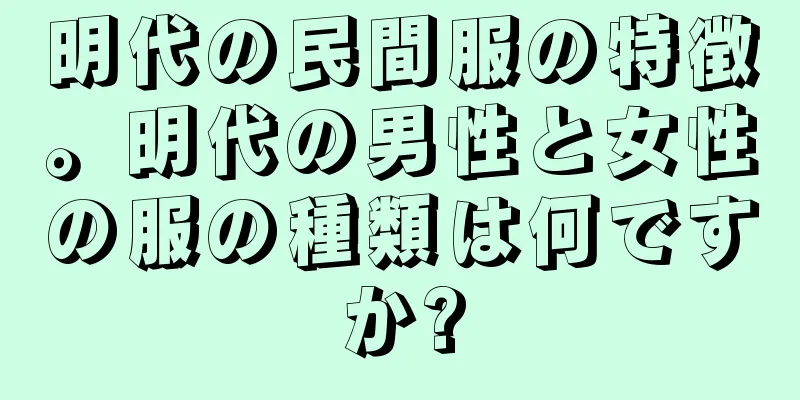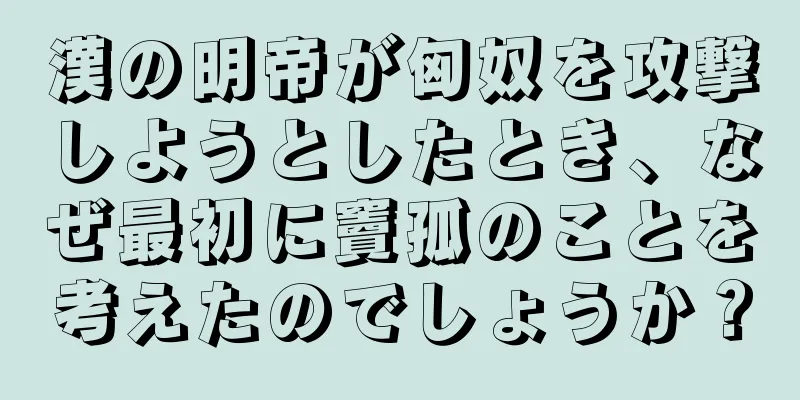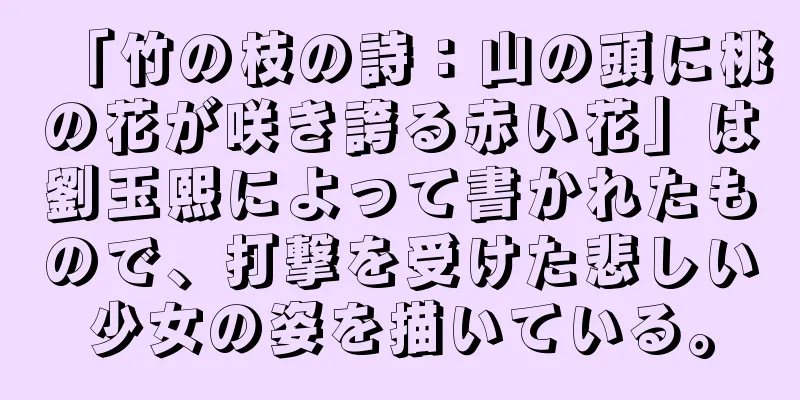王莽の六字体の一つである苗伝の紹介:漢代に印章を写すために使われた篆書の一種
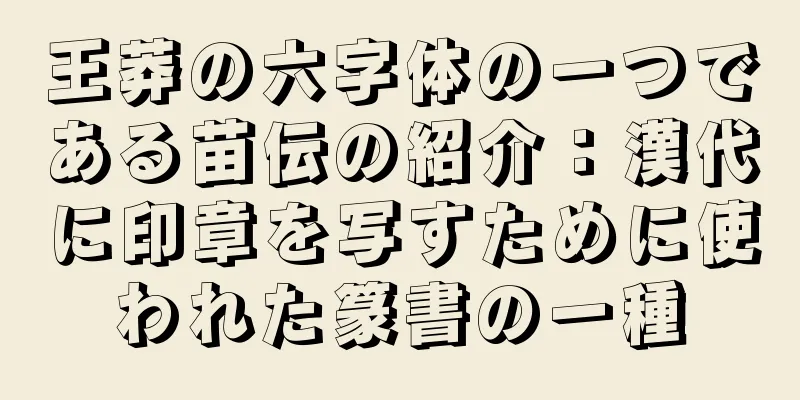
|
苗伝は漢代に印章を写すために使われた篆書体の一種です。王莽の六書のうちの一つ。東漢の許申は『説文解字抄』に心芬の六字を記録して「第五は妙伝で、印章を模したものである」と述べている。形は四角く均一で、官書の趣があり、筆致は丸みを帯びた優美な小篆書体から曲がりくねった曲線の書体へと進化した。準備という意味があり、それが名前の由来です。清代の桂復の『苗伝分韻』では、漢魏の印章に使われた様々な篆書体を総称して「苗伝」と呼んでいる。 「篆書道」とも呼ばれる。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 苗伝の概要 漢印に使用される書体には、苗字体、鳥背書体、礼字体の3種類があります。苗璽が主な書体で、大部分を占めています。鳥虫文は少数の印章にのみ使用され、官文は埋葬用の石印にのみ見られます。 苗伝は、漢王莽の時代に制定された六字体(古字、奇字、小篆書、補字、苗伝、鳥虫書)の一つで、漢代初期の秦の八字体の一つであった「蒙陰」文字であるため、蒙陰伝とも呼ばれています。 清代の謝景清は『漢音分韻』の序文で次のように書いている。「秦には八つの書体があり、そのうち五つは墨音と呼ばれる。漢には六つの書体があり、そのうち五つは苗伝と呼ばれる。したがって墨音と苗伝は別々のスタイルであり、紆余曲折があり、誤りを正すという意味がある。礼に似ているが、朔文と完全に一致しているわけではない。その損失、利益、変化は意図的で消えず、構成の組み合わせは自然で素晴らしい。古いものを愛する人はそれを大事にするだろう。」 苗伝の起源 廟伝は秦の時代の『莫因伝』を基にして作られた。 「墨音伝」は周代の青銅銘文や石刻とは少し異なり、天目や日目の中に書かれています。特定のニーズに合わせて形を合わせるため、四角く比較的均一な傾向があります。時には配置のためにずらす方法も採用されていますが、少し粗いです。 西漢初期の篆書体は基本的にこのスタイルを継承し、対称的な構造と丸い線へと発展し、枠がなくても大きさが均一で均一になりました。文字は絡み合って曲線を描き、線は太くなっています。新莽の頃には苗伝と名付けられました。 当時、印章師の中には、一つの文字を縦画または横画で6本、あるいはそれに近い数で構成する人もいました。判読に支障がない限り、均等で密度が高く、意味のある字になるように、画数を省略したり増やしたりしていました。戴同は『六字源』の中で「字数が多くても字数が少ない字は、便利である傾向があり、字数が少なくても字数が多い字は、賢くて不正確である傾向がある」と述べています。東漢の時代以降、この傾向はますます発展しました。 このシステムは魏、晋、南北朝時代を通じてほとんど変更されることなく使用され続けましたが、隋の時代に絹紙が広く使用されるようになったことで印章の形状が大きく変わり、印章の文字も大きく変わり、もはや苗伝ではなくなりました。 苗伝の特徴 苗伝の基本的な筆法 楷書の基本画には、いわゆる「勇」の八画(「勇」の字の8つの文字)が含まれます。官書の画数は楷書ほど多様ではありませんが、点、横、縦、左下がり、右下がり、折れ、波、鉤などの基本画もあります。小伝の筆法は多種多様ですが、一般的に使用される筆法は少なく、横筆、縦筆、さまざまな折り返し筆、対称的な弧筆などがあります。苗伝の基本的な筆法はより単純で、横筆、縦筆、折り返し筆などがあります。さらに、重なり合う筆法、弧筆法、斜めの筆法が使われることもあります。 苗伝の構造的特徴 苗伝には5つの構造的特徴があります。1つは四角で、文字の形が四角いことを意味します。2つは平で、水平線と垂直線がまっすぐであることを意味します。3つは均等で、画が均等に分布していることを意味します。4つは積み重ねで、線が折り畳まれていることを意味します。5つは満で、上部の枠を埋めることを意味します。 苗伝のレイアウト 漢代の官印のほとんどは正方形であったが、下級官吏の印章は「半透し印」と呼ばれる長方形のものを使用していた。印鑑の形状は、正方形、長方形、円形、またはその他の形状にすることができます。篆書の文字の配列は文字数によって異なり、配列の順序も複雑ですが、一般的には上から下、右から左の順で配列されます。 苗伝の芸術的価値 苗伝のさまざまな王朝における篆刻の制度 印章に使われる文字は、一般的に3種類あります。1つ目は大篆書体で、文字の大きさや形が異なり、秦以前の古代の印章に代表されます。2つ目は苗篆書体で、文字は四角く、線がほとんど直線で、漢代の印章に代表されます。3つ目は小篆書体で、文字は丸く、線が滑らかで、元代の丸い赤い印章に代表されます。その中でも、苗伝方式が最も代表的です。 明代には、豹石が印章の材料として使えることが発見され、文人による印章彫刻が盛んになりました。文鵬や何珍以来、多くの有名な芸術家が登場し、印章の歴史に最高潮をもたらしました。彼らがこのような偉大な業績を達成できた根本的な理由は、漢代の篆書を踏襲していたことにあります。例えば、趙坤一や鄧三牧の玉山派は、線の太さに変化を加えて構図や思想を強化し、部首の動きに力を入れました。斉白石は苗伝をもとに、呉天法の神塵碑の筆法を借用し、虚と実の対比を大胆に強調し、斜線を強調し、独特の打ち抜き法で線を表現しました。彼らの作品は、漢代の印章である苗伝から生まれ、独自の個性を帯び、後世に受け継がれました。 時代を超えて芸術創作に応用されてきた妙伝 歴代にわたる篆刻の発展の法則は、苗伝が今日でも強い生命力を持ち、篆刻芸術の創造にとって尽きることのない源泉であることを物語っています。苗伝を基礎として、各王朝の民間印章や書道から栄養を得て、革新し、独自のスタイルと特徴を持つ苗伝の印章文字を創造することで、篆刻芸術に革新的な発展をもたらすことができます。 また、苗伝は小篆書体や大篆書体に比べて比較的シンプルで習得しやすいため、篆書を学習している人に適しています。特に漢文を基礎に持つ書家にとっては、苗伝で創作することが近道です。絵画の碑文に「苗伝」を使用すると、シンプルさと優雅さの感覚を加えることもできます。しかし、苗伝は四角い形をしているため、文字の多い作品は構成が比較的平坦なので、文字の少ない作品の方が文字の多い作品よりも効果が高いはずです。銘文、連句、そして少数の正方形、横長、巻物の作品が苗伝書道創作の主流であるはずです。 |
<<: 鳥虫文は「鳥虫印」とも呼ばれ、春秋戦国時代にはどの属国で流行したのでしょうか。
>>: 新莽六文字の紹介:王莽帝の治世中に王莽が提唱した六文字
推薦する
岑申の詩「冀州客家で酒を飲んだ後、王其に詩を贈り、南楼で詩を書いた」の本来の意味を鑑賞
古詩「冀州客家で酒を飲んだ後、王琦に詩を送り、南楼に書いた」時代: 唐代著者: セン・シェン先生は傲...
星堂伝第36章:洛成は桓竹巷で叔母に気付き、秦瓊は佳里宿で客をもてなす
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
太平光記·第79巻·錬金術師·趙師匠をどのように翻訳しますか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
曹操はすでに葬儀の準備を済ませているのに、なぜため息をつく必要があるのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
北宋時代の軍事書『武経宗要』全文:第二巻、第12巻
『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...
『阮朗貴:蕪陽路張楚福代筆』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
阮朗貴 - 張楚福に捧げる雷陽への道の詩新奇集(宋代)山の前の明かりは暗くなりつつあり、山頂には雲が...
唐代の中元節の風習はどのようなものだったのでしょうか?現代のお祭りと比べてどう違うのでしょうか?
鬼節は、死者の日や中秋節としても知られています。鬼祭りの期間中、人々は一般的に先祖を崇拝する行事を行...
古典文学の傑作「太平天国」:平八編・第11巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『長安殿壁銘』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
長安の主人の壁に刻まれた孟浩然(唐代)私は南山の農地を長い間放棄してきましたが、今は東歌の賢者たちに...
田園詩人陶淵明の『酒呑三』の原文、翻訳、注釈
陶淵明の「飲酒、第3部」次回はInteresting History編集長が関連コンテンツを詳しく紹...
『清代名人故事』第13巻原文の「学問と行状」の項には何が記されているか?
◎朱高安の学問と行い朱高安は幼い頃から勉強が好きで、全力を尽くす決意をしていました。一度、家庭教師が...
魏英武の『滁州西渓』の創作背景は何ですか?
魏応武の『滁州西渓』の創作背景を知りたいですか?この詩は、魏応武が滁州太守であった781年(唐の徳宗...
太平広記第470巻「水生部族7」の登場人物は誰ですか?
李玉、謝二、荊州の漁師、劉成、薛二娘、趙平原、高宇、法志僧侶李宇唐代の敦煌出身の李愈は、開元の時代に...
諸葛亮は馬に乗ることができたのに、なぜいつも車椅子で戦争に行ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
フビライ・ハーンは生涯を軍務に費やしましたが、肥満が原因でどのような病気にかかって苦しんだのでしょうか?
フビライ・ハーンはチンギス・ハーンの孫であり、トルイの息子です。諺にあるように、親に似た子は子に似て...