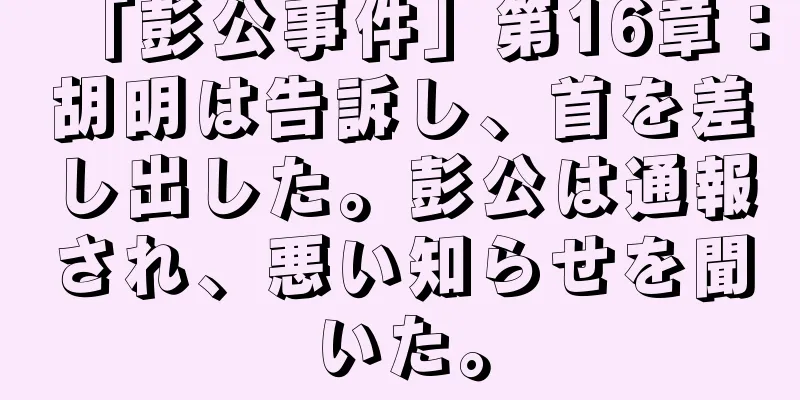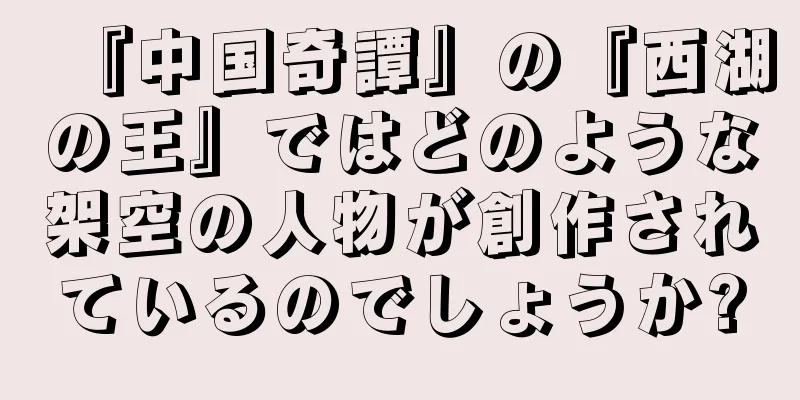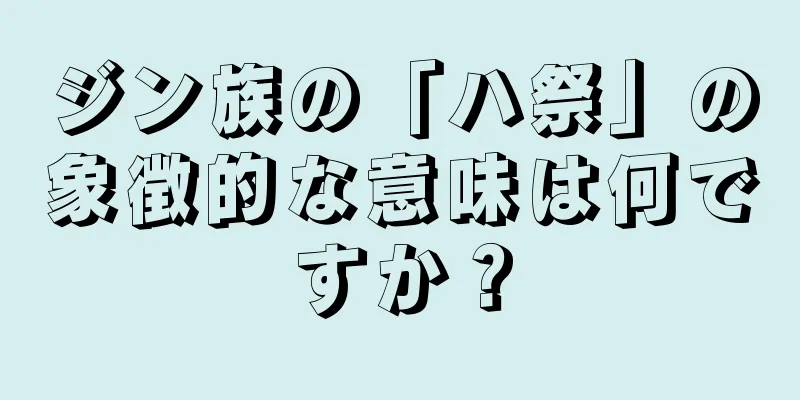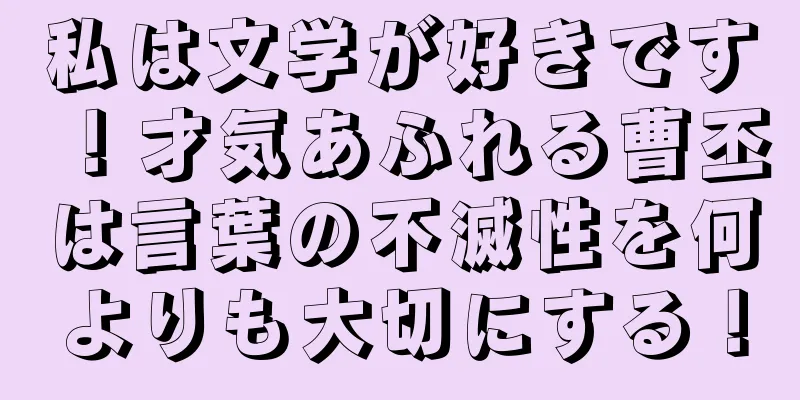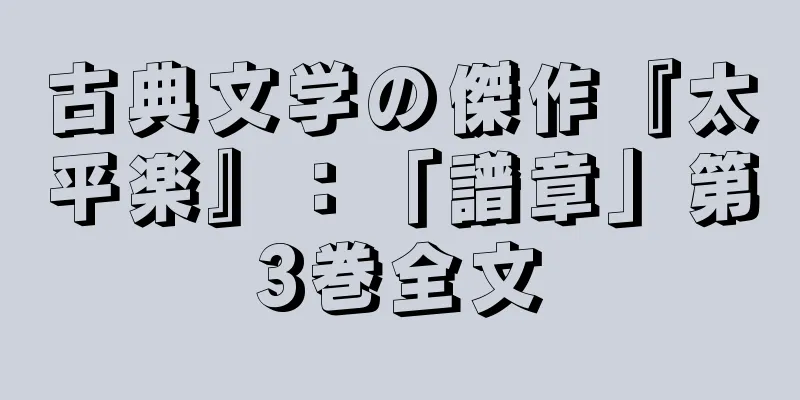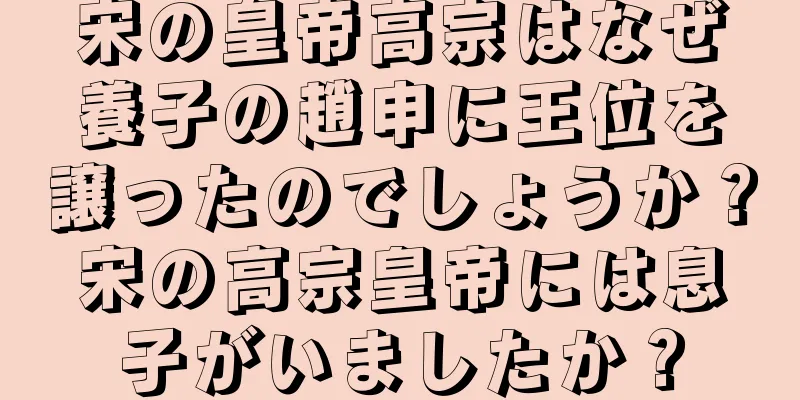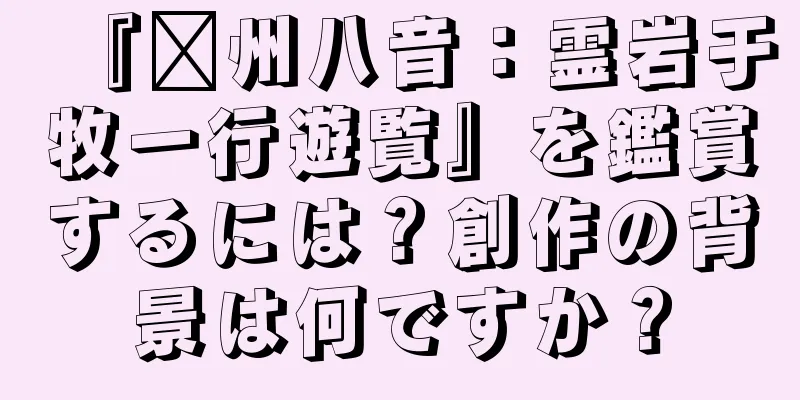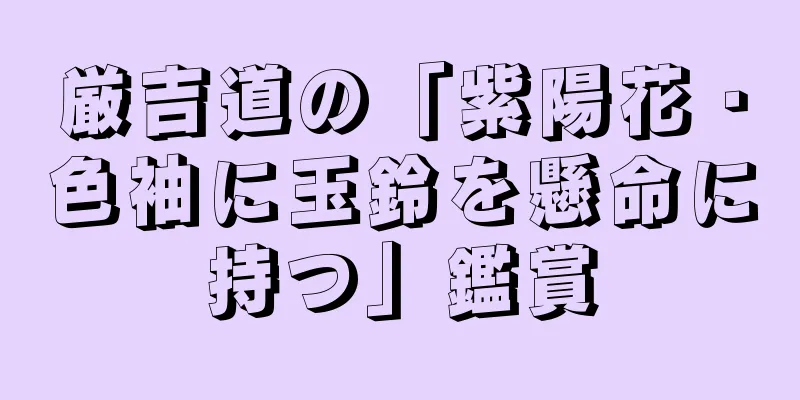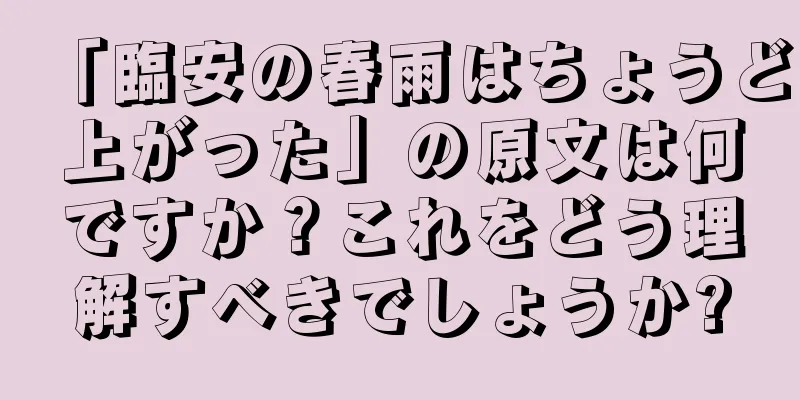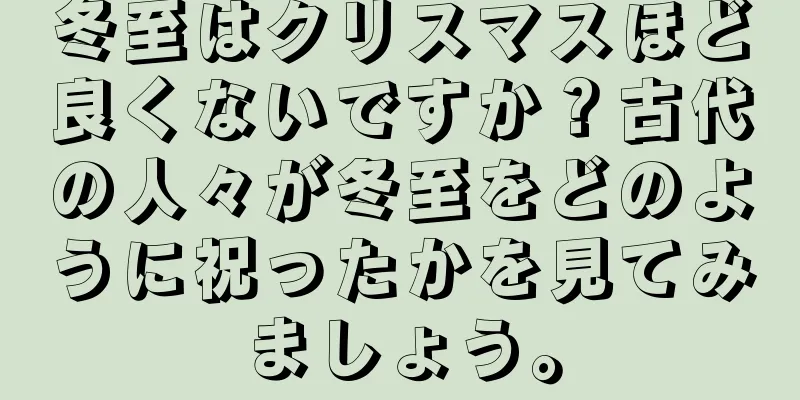古代の生活では、「紅秀天香」で使用される線香はどのように作られましたか?
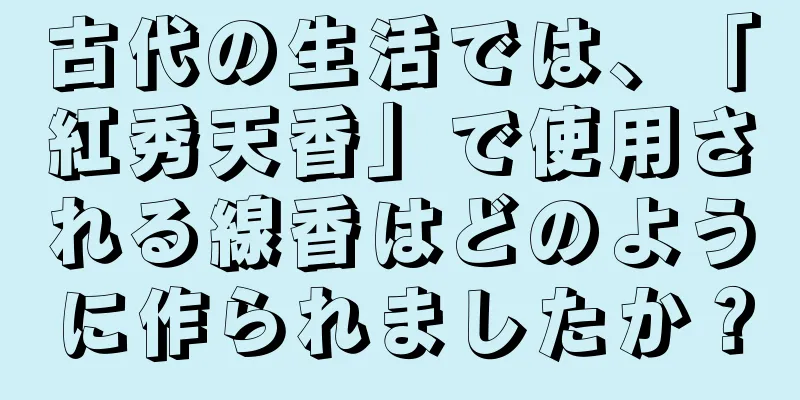
|
「赤い袖に香りを添える」というイメージは、中国の古典文化において非常に時代を超えたものであり、間違いなく非常に美しいイメージです。しかし、現代の人々は、おそらく「紅秀」が当時どのように香りをつけていたのか理解していないでしょう。私たちがよく知っている「お香を焚く」方法は、線香に火をつけることです。紙筒に入った細い麺状の線香を香炉に挿し、香頭に火をつけると、線香から煙が上がります。しかし、「紅袖香」は香炉に線香を挿すだけの単純なものではありません。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 実際、古代の絵画に描かれた香炉をよく観察すると、香炉の中に線香が挿してあるのはほとんど見当たりません。線香の歴史は比較的新しいものです。古代の生活において、焚くために使われた「香」は、香丸、香玉、香菓子、または「香調合」法で作られた粉末など、さまざまな種類でした。 「映映焼夜香」の有名なストーリーは、明代の無名の画家による作品「千年の美」に具現化されています。 写真では、崔英英は背の高い香台の前に立っており、その上には香を焚くために必要な「3つのもの」のうちの2つ、香壷と香匙、そして小さな香炉が置かれている。しかし、香炉にも崔英英の手にも線香の痕跡はなかった。ここでは、彼女が右手に香箱を持ち、左手で箱から小さな香玉を取り出して香炉に入れようとしているところが示されています。古代の女性が「香りを添える」光景が、私たちの目の前に現れます。しかし、「赤い袖が香りを加える」は、単に香炉に線香を入れるということではありません。 「香を焚く」というのは、香玉や香菓子を直接燃やすということではなく、香玉や香菓子に香りを漂わせるためには炭火の力が必要なのです。古代の人々は、できるだけ煙を減らし、香りを長く持続させるという香の焚き方を追求しました。そのため、香炉の炭火はできるだけゆっくり燃え、弱火で長時間燃え続けるようにする必要があります。この目的のために、人々は複雑な香の焚き方を発明しました。一般的な手順は、特別に作られた小さな炭をよく燃やし、それを香炉に入れ、特別に作られた細かい香の灰を炭に詰めるというものです。次に、線香の灰にいくつか穴を開けて、炭が酸素と接触し、酸素不足で消えないようにします。 香灰の上に磁器、雲母、金貨、銀箔、砂片などの薄くて硬い「火仕切り」を置きます。小さな香玉や香餅を火仕切りの上に置いて、灰の下の炭の弱火で焙り、ゆっくりと香りを放ちます。昔の人が香を焚く方法について語るとき、いつも「焚く」「燃やす」「挿す」などの言葉が使われていましたが、実際には香に直接火をつけて燃やすのではなく、小さな耐火物の上に香を置き、ゆっくりと焙って香りを引き出したのです。 明らかに、このプロセスは非常に面倒です。しかし、話はこれで終わりではありません。お香が「燃やされた」後も、常に観察する必要があります。そうでないと、「お香が強ければ、香りは拡散して一瞬で消えてしまいます。」しかし、灰の中に埋もれて見えなくなった炭や線香の状況は、どのように判断すればよいのでしょうか。正しい方法は、灰の上に手をかざして、灰の下の線香の火が強すぎるか弱すぎるかを感覚で判断することです。 そのため、唐代の詩人たちは「香を盛る」ことに加え、女性が「香を試している」場面も好んで描写し、女性が「手で火の強さを試している」様子を描写しています。例えば、何寧の『山花子』には、「彼女は何度も香を盛ってみると、細い手が温かくなり、一度酒を味わうと唇が赤くなった」という女性の描写があります。香を盛るにしても、香を試しているにしても、男性文人の著作では、香を焚くことは常に何もしない女性のイメージと結びついているようです。香炉の前に立つ女性たちは、宮廷詩に出てくる欲求不満の妾であろうと、『華厳記』に出てくる芸者であろうと、生活の心配をする必要はなく、男性を待つこと、または恨みと裏切りの苦しみで彼と恋しいことばかり考えている。 |
<<: 竹は何を象徴していますか?タケノコは学者や役人の好む野菜の一つとなった。
>>: 「風とともに夜に忍び込み、静かに物を湿らせる」、杜甫はどのようにしてこの詩を書いたのでしょうか?
推薦する
康有為と梁啓超はいずれも改革で知られていたが、譚思同はまさに崑崙に忠誠を誓い続けた人物であった。
私は張建を見ると同情し、杜根に直接アドバイスをすると恥ずかしく思います。彼はヨーロッパの剣を空中に投...
曹雪芹の『五人の美女:西施』:この詩は林黛玉が自分を西施と比較していることを描いている。
曹雪芹(1715年5月28日頃 - 1763年2月12日頃)は、本名を詹、字を孟阮、号を雪芹、秦溪、...
ジノ族の独特な工芸品は何ですか?ジノ族のユニークな職人技
ジノ族のマチェーテ布ジノ族の女性は機織りが得意です。ジヌオ族の村に入ると、村の入り口、村外れ、畑の小...
「元湖曲」の歴史的背景は何ですか? 「元湖区」の詳しい説明
有名な詩「元湖曲」の歴史的背景を知りたいですか?これは古代詩の一ジャンルで、元湖は南湖を指します。今...
『紅楼夢』で宝仔と賈玉村は何回交流しましたか?いつ交流しましたか?
薛宝柴は『紅楼夢』のヒロインの一人です。これは多くの読者が気になる問題です。一緒に勉強して参考にしま...
宋代の三人の息子に贈った感謝の詩の中で、陳士道はどのような場面を詩に表現しましたか。
宋代の三男、陳世道については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!その時、...
劉備が孫権に南君を借りるよう頼まなければならなかったのは、どのような二つの不利な要因のためですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
賈丹春はもうすぐ結婚します。賈丹春が遠く離れた所で結婚するのは本当にかわいそうでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
白居易の『五言無量寿詩第五』は人生に対する正しい姿勢を芸術的に表現している
白居易は、字を楽天といい、別名を向山居士、随音献生とも呼ばれた。写実主義の詩人で、唐代の三大詩人の一...
古代の敦煌の発展の歴史はどのようなものですか?莫高窟はどのようにして誕生したのでしょうか?
敦煌には長い歴史と素晴らしい文化があります。原始社会の終わりごろ、中原部族戦争の失敗後に河西に移住し...
西遊記続編第28章:二つの気を貫けば寒さも暑さもなく、陰陽に落ちれば生死がある
明代の神話小説『続西遊記』は、『西遊記』の3大続編のうちの1つです。 (他の2冊は『続西遊記』と『補...
『七剣士と十三勇士』第 116 章: 知事は羊を率いてワインを運び、兵士たちに報酬を与えます。反乱軍は兵士を失ったことを謝罪します。
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
古典文学の傑作「劉公安」第73章:遊女が禅寺で馴染みの客に出会う
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
夏松と韓起は共同で軍事防衛を担当していたのに、なぜ昊水川で惨敗を喫してしまったのでしょうか?
三川口の戦いでの敗北後、北宋朝廷は西夏軍の強さを再認識し、積極的な対抗策を取り始めた。宋仁宗はまず敗...
『紅楼夢』の元陽と西人の間にはどのような関係があるのでしょうか?王希峰との関係は?
希仁の本名は華真珠。中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物。次の『興味深い歴史』編集者が関連内容を詳しく...