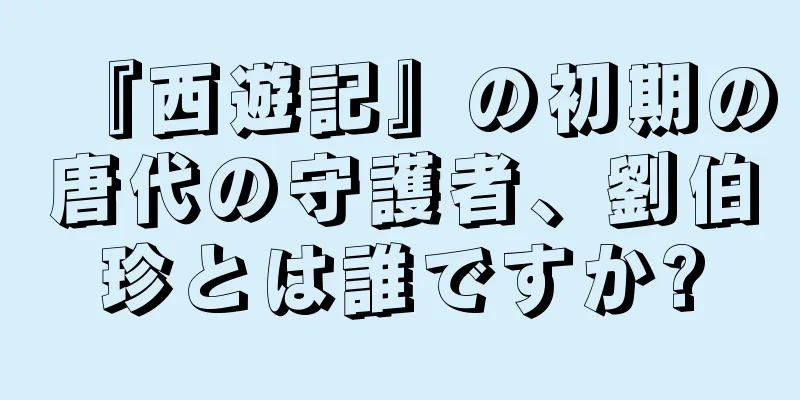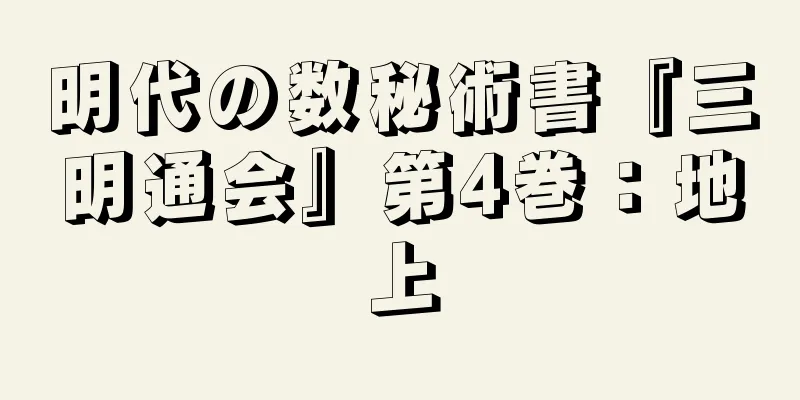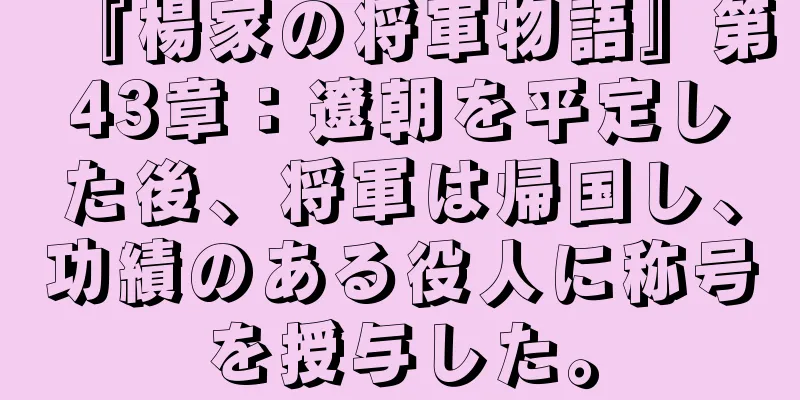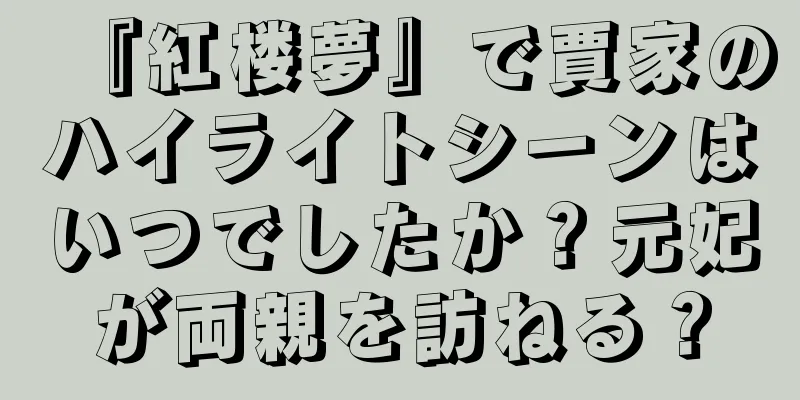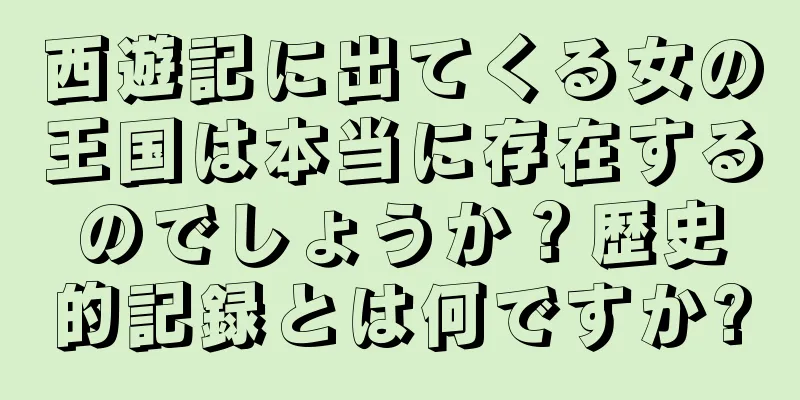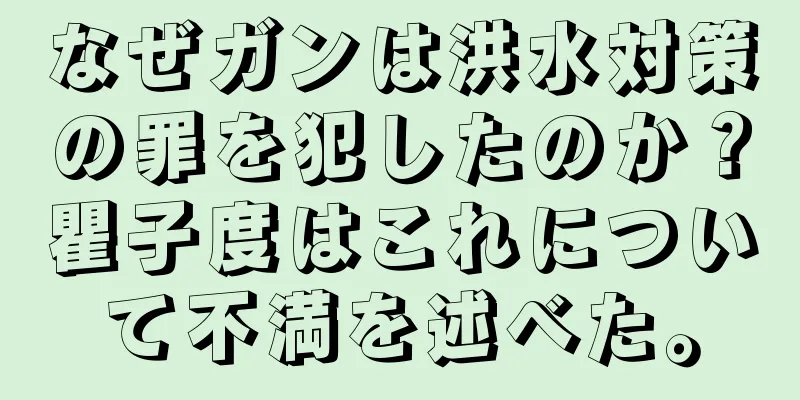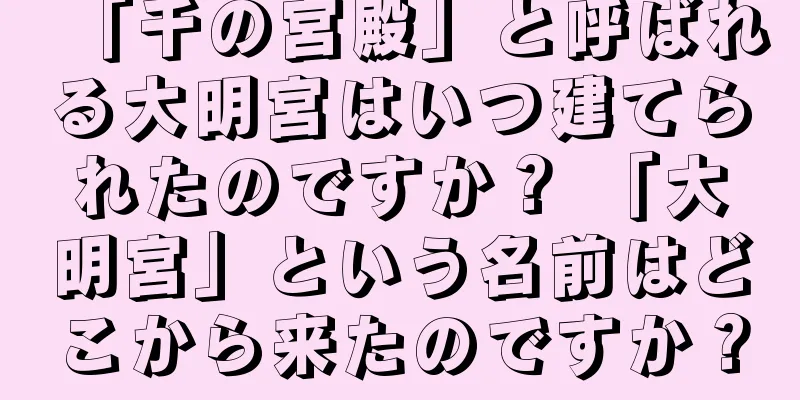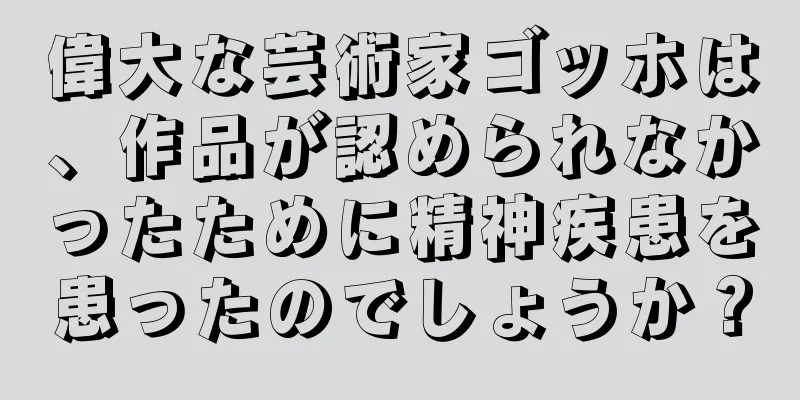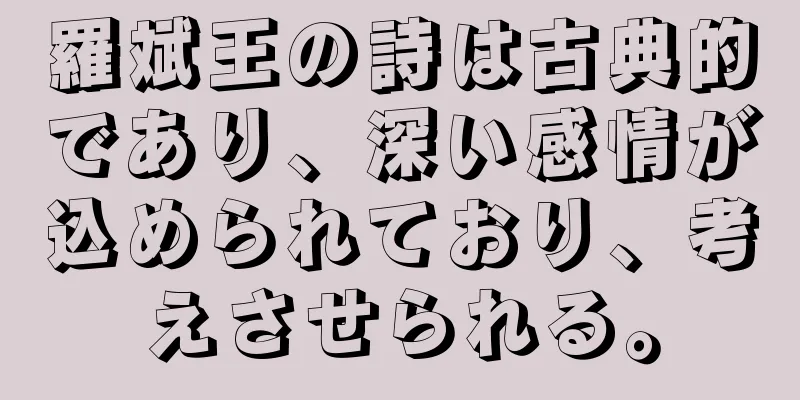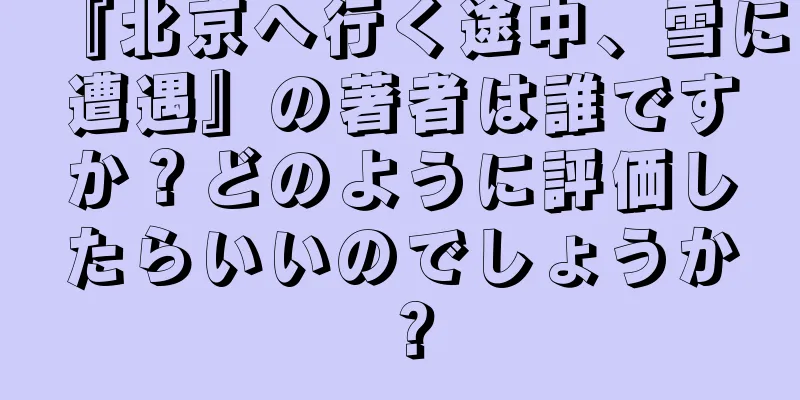『史記・李斯伝』の記録によると、古代の皇帝はなぜ自らを「朕」と呼んだのでしょうか?
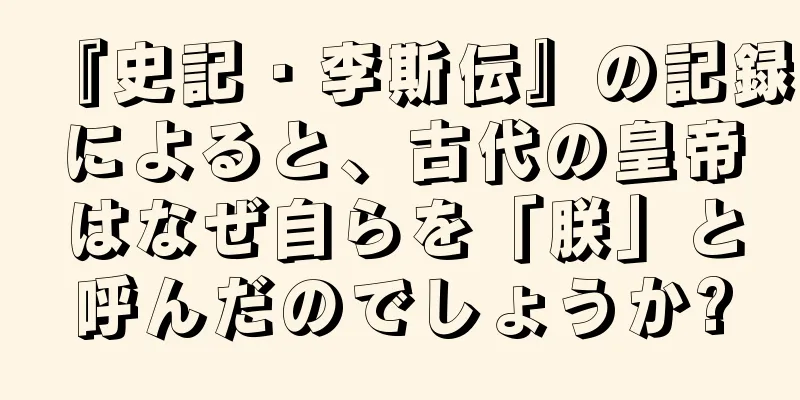
|
「皇帝が高貴なのは、声だけが聞こえ、臣下は誰もその顔を見ることができないため、彼を「朕」と呼ぶ。」これは『史記・李斯伝』に記録されている一文です。多くの友人がこの質問に興味を持っていると思います。古代の皇帝の中には、なぜ「朕」と名乗った人がいるのでしょうか。「朕」の意味は何ですか。秦の始皇帝が統一の大業を成し遂げた後、「帝」と「王」を「皇」に置き換え、最初の皇帝になりました。李斯は後に皇帝の一人称代名詞は「朕」であるべきだと提案しました。これは「皇帝の権力の優位性」を意味します。そして、当時の「朕」という字の書き方から、いくつかの手がかりも見えてきます。次の興味深い歴史編集者が、詳しい紹介をお届けします。見てみましょう! 中国の2000年以上の封建制の歴史の中で、秦王朝は紀元前221年に始皇帝嬰誠が「六王を滅ぼし天下を統一」して建国してから、2代目に滅亡するまで、わずか十数年しか続かなかった。歴史の深遠さから見れば、ほんの一瞬の出来事だった。しかし、中国史上初の統一封建王朝として、嬰誠と秦王朝は後世に数え切れないほどの政治的遺産を残した。 「皇帝制」は嬴政から始まりました。紀元前221年に六国を統一した後、嬴政は「功績は三君を超え、徳は五帝を超える」と考え、李斯の提案により「三君五帝」の称号を組み合わせて皇帝の称号を作りました。帝国の権力の優位性に加えて、「私」という称号の排他性もあります。それ以来、1912年に清朝が崩壊するまで、皇帝は自らを「朕」と称した。 皇帝の専制政治が封建社会と封建制度の必然的な結果であることは、私たちにとっては理解しにくいことではありません。さらに、この結果は封建制度のさらなる発展と改善とともに継続し、明と清の時代にピークに達しました。 しかし、春秋戦国時代、つまり「余」「朕」「我」「吾」「台」「卬」などの一人称代名詞が流行していた時代に、なぜ秦の始皇帝嬰誠は最終的に皇帝の独占名詞として「朕」を選んだのか、という疑問を抱かずにはいられません。偶然だったのでしょうか。 「朕」という用語は秦以前の時代には珍しくなかった。 「朕」は一人称代名詞として「私」を意味し、高官、文人、国王から一般人まで幅広く使われます。 屈原には「私の父は伯雍という」「私は時が来ないことを嘆く」「私が道に迷ってしまう前に、私の馬車を道に戻してください」という一節があり、『堯経』には「あなたは私の後を継ぐことができます」という一節もあります。 「朕」は『二亜世古』に出てきます。後漢の作家蔡邕は率直にこう言っています。「朕は私を意味します。昔は、貴人と卑人を区別せず、富者と貧者を同じように扱っていました。」意味は非常に明確です。一人称代名詞「朕」は、まさに貴人と貧者の両方が使う言葉です。 では、「朕」が際立つ魅力とは何でしょうか。実は、「朕」は甲骨文字に初めて登場した人称代名詞で、「余」「吾」「我」に比べ、その起源と使用はもっと早いのです。さらに、時代の発展とともに、戦国時代後期には「朕」の使い方にかなりの変化が見られました。もともと日常の話し言葉でよく使われていた「朕」は、書き言葉でしか見られなくなりました。逆に、より口語的で、より流通していて、大衆に近い「我」と「吾」が主流になっています。 このように、秦の始皇帝は「朕」を自分の代名詞として選びました。これは、民衆のタブーによる殺人を避けることができただけでなく、天下の統治者としての皇帝の「荘厳さ」と「威厳」を反映するものでもありました。顧潔剛氏と劉啓宇氏が『尚書唐詩』の注釈と翻訳の研究で指摘したもう一つの点は、「朕」という一人称代名詞は、秦以前の時代の「我」や「余」に相当しないということです。 「朕」は「私の」を意味し、「我」や「余」などの単語とは異なり、所有格と主格があります。すべての甲骨文字において、「朕」は「私の」を意味する単数一人称属格としてのみ使用されています。 『上書順典』には「汝は我が山湖の司令官となれ」という一文がある。『大于定』(銅銘)には「我の命令を廃止してはならない」という一文がある。 「私の命令を放棄するな」と説明する方が簡単です。この意味から、李斯の「世界は私のものであり、皇帝の権力は最高である」という言葉も説明しやすいです。 しかし、この説明に対して、有名な歴史学者で言語学者の戴震は、船の継ぎ目を「朕」と呼ぶという見解を提唱しました。 --戴震、「高公記図・寒仁注」。 『朕文街子』によれば、「朕」という字は「舟」と「灷」という字から成り、本来の意味は「船の中の火」を指す。戴震は、「朕」という字が「舟」と「灷」の間の隙間を繋ぐ役割を果たしていると信じていた。 「周」と「灷」は古代の水上民族の発展、繁栄、成長に欠かせないものであり、アイデンティティ、権力、地位、富の象徴であり、「朕」は間違いなくそれらをつなぐ最も重要なもの、要点でした。 この発言は、一人称代名詞の登場が早いか遅いか、明らかな所有格の解釈よりも説得力があり、始皇帝嬰誠が築き上げた統一状況は前例のない偉業だったため、このような自信から、始皇帝嬰誠が自らを国家の最優先課題に位置付けたのは必然の結果であると考えられています。 |
<<: 古代人は高いベッドや柔らかい枕を好まなかったのに、なぜ古代の人々はそのような高い枕を使ったのでしょうか?
>>: 喬潔は『紅楼夢』にはあまり登場しないのに、なぜ十二美女の一人なのでしょうか?
推薦する
唐代の莫道軍はどれほど恐ろしかったのでしょうか?唐代の莫道軍の詳細な説明
唐代の莫道軍はどれほど恐ろしいものだったのでしょうか? ご存知のとおり、漢唐時代はおそらく漢民族が軍...
『紅楼夢』で石向雲はなぜ蟹宴会で詩を書かなかったのでしょうか?
蟹宴は『紅楼夢』第38話に登場します。大観園で最も賑やかな私的宴会とも言えます。これは多くの読者が気...
賈宝玉、薛宝柴、林黛玉のうちどれが最良の選択でしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は賈宝玉の物語をお話しし...
薛剛の反乱、第77章:呉承思は巧みに10の陣形を組み、徐美祖は敵の攻撃を予測した
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
清朝における「去勢と流刑」という刑罰とは何だったのでしょうか?判決を受けた者はむしろ死んだほうがましだ!
「去勢と追放」という刑罰がどのようなものかご存じですか? 知らなくても大丈夫です。Interesti...
「世界覚醒物語」第83章
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
明代読書本『遊学瓊林』第1巻 四季全文と翻訳注釈
『遊学瓊林』は、程雲生が書いた古代中国の子供向けの啓蒙書です。 『遊学瓊林』は、明代に西昌の程登基(...
『白牡丹』第33章:居庸関の裏切り者の囚人が尋問のため金鑾宮の老侍従に連行された
『白牡丹』は清代の洪綬が書いた小説です。その主な内容は、正徳帝が夢に見た美しい女性、白牡丹と紅牡丹を...
宋代の詩『清平楽:博山王寺に独り泊まる』を鑑賞します。詩人はどのような感情を表現しているのでしょうか。
宋代の新啓基『清平楽・博山王寺独居』について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみま...
宋代には「花見の宴」が何種類あったのでしょうか?具体的にはどうすればいいのでしょうか?
周知のように、宋代の国策は「軍事より文化を重んじる」というもので、国全体の雰囲気は自然と穏やかになり...
王安石の『西泰宜宮壁二首』は、父や兄弟たちと旅をした喜びに対する限りない郷愁を表現している。
王安石は、号を潔夫、号を半山といい、北宋時代の政治家、改革者、作家、思想家であった。彼は文学において...
王維の古詩「李氏に別れを告げる」の本来の意味を理解する
古代詩「李氏に別れを告げる」時代: 唐代著者 王維若者はどこへ行くのでしょうか。彼は稲を背負って銅梁...
『Strange Stories from a Chinese Studio』の Du Xiaolei の章ではどんな物語が語られますか?原文はどのように説明されていますか?
中国のスタジオからの奇妙な物語からの杜暁雷の原文杜小雷は宜都西山の出身である[1]。母親たちは二重盲...
北宋の五鬼の一人である丁維と王欽若の類似点は何ですか?
王秦若と丁維王欽若と丁維はともに北宋朝の宮廷官僚であった。宋の真宗皇帝の治世中、両者とも皇帝の寵愛を...
李白の『静夜思索』は皆さんによく知られていますが、辛其記の『静夜思索』をご存知でしょうか?
本日、『Interesting History』編集者は、辛其記の『静かな夜の思索』をお届けします。...