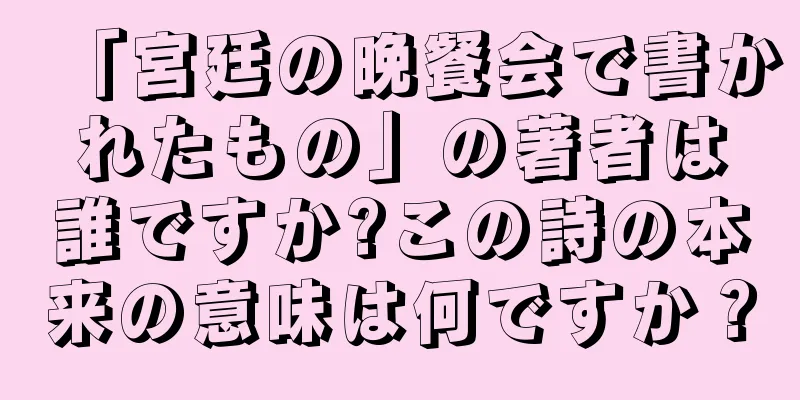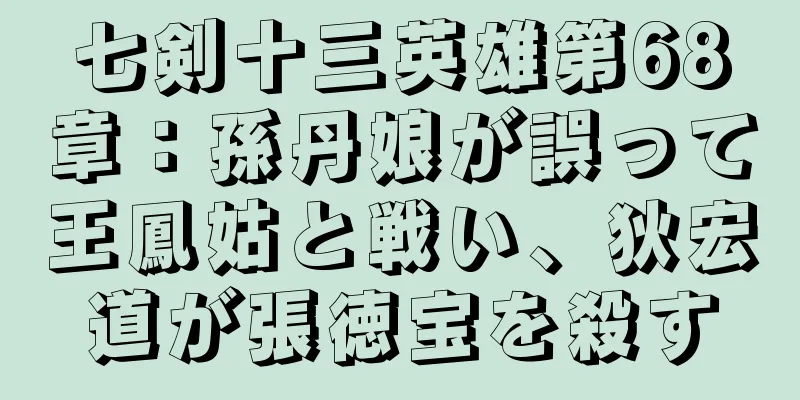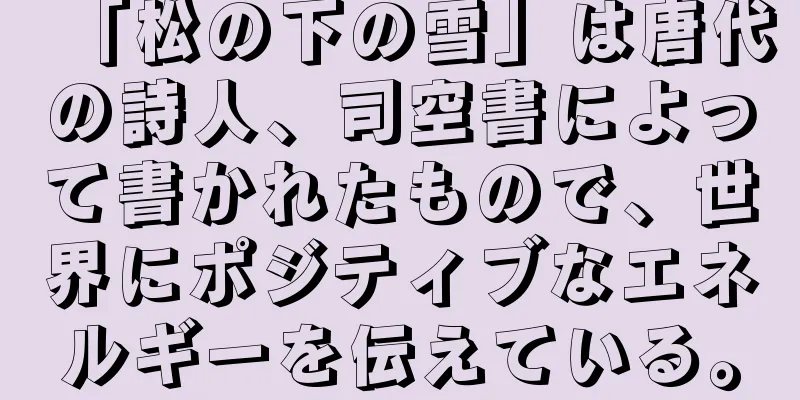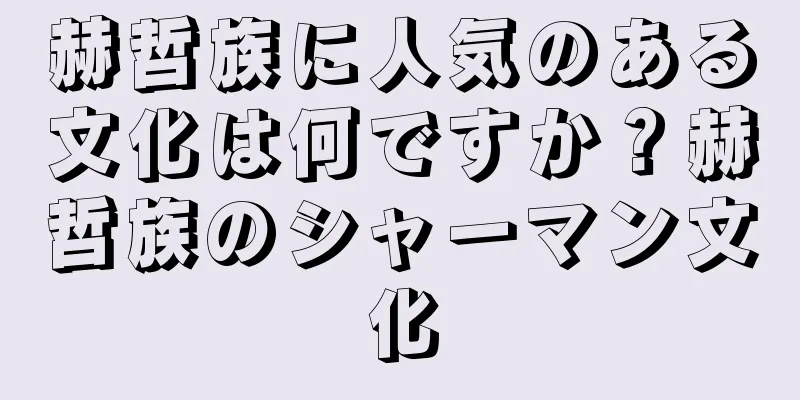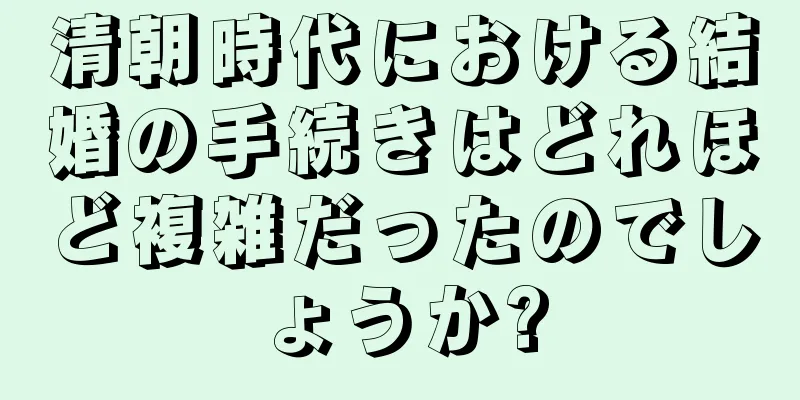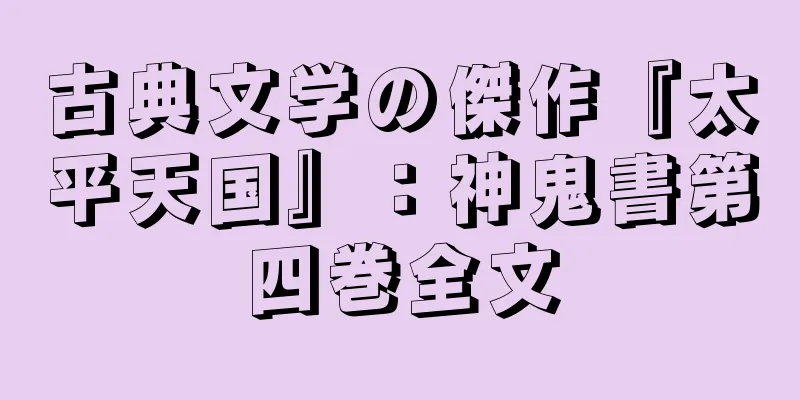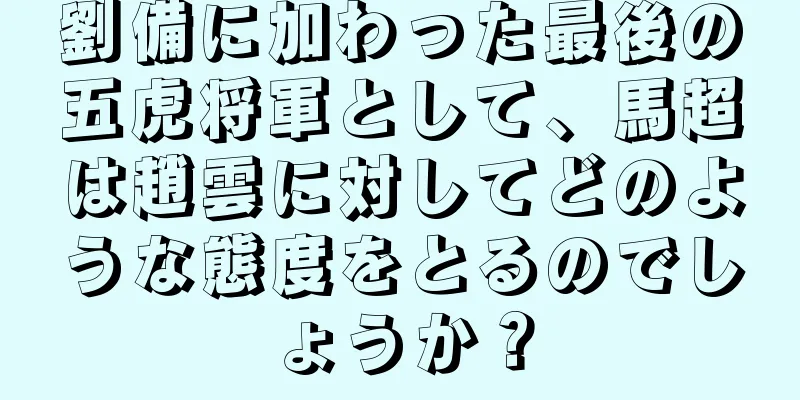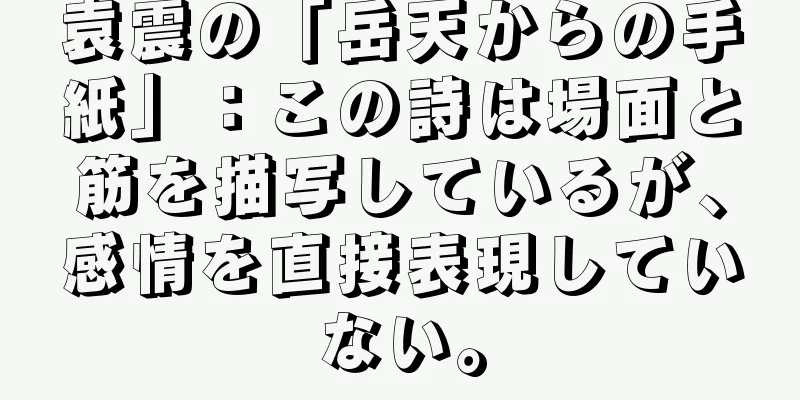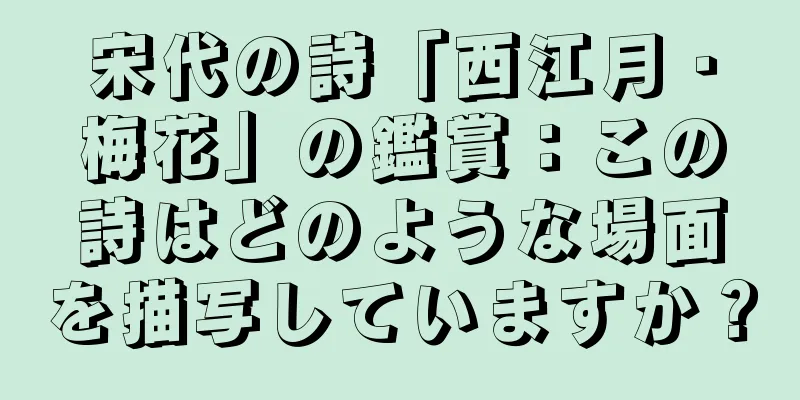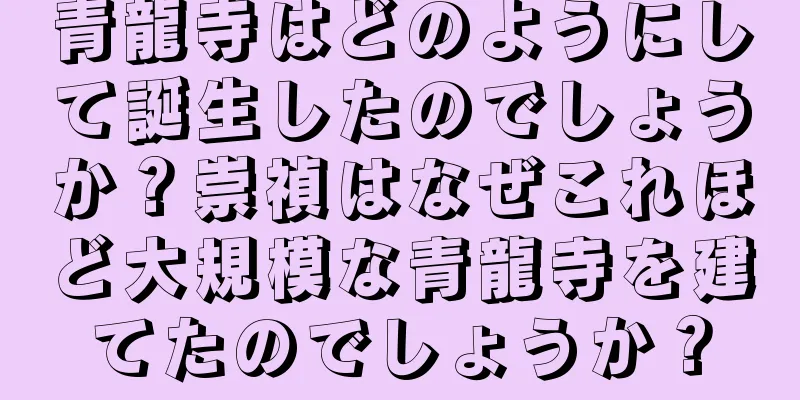唐代の官僚同士の呼び方を見てみましょう。明代と清代の呼び方の違いは何でしょうか。
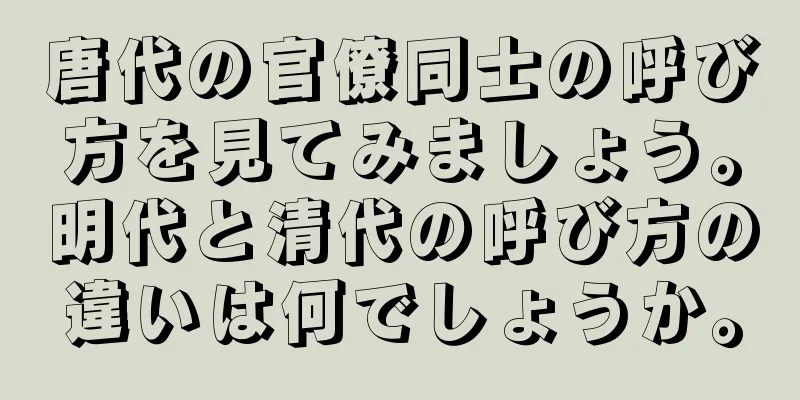
|
唐代では、皇帝は主に「聖人」と呼ばれ、皇帝の側近や従者は「皆」と呼ばれていました。興味深いことに、唐代では、女性も義理の母を「皆」と呼んでいました。唐の明皇帝のようなロマンチックな皇帝の場合、皇帝の側近は皆彼を「三郎」、太真妃を「娘子」と呼んだ。皇太后は「真」と名乗った。これは『旧唐書・武則天伝』の武則天即位前の会話記録に見られる。皇太子は周囲の人々から「郎君」と呼ばれることが多かった。皇太子や王は「私」と名乗ることもあった。これは順宗が皇太子だった頃の王書文との会話や『旧唐書・永王林伝』で永王が「私は天帝の子孫であり、皇帝の友である」と言っていることに見られる。公は「顧」と名乗った。これは当時唐の公であった李淵の『建唐記』の演説に見られる。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 太真妃と太子を「奥様」「殿様」と呼ぶのは根拠のないことではありません。唐代には「殿様」という称号はありませんでした。召使たちは男性の主人を「阿朗」、若い主人を「殿様」と呼び、女主人と若い女性はどちらも「奥様」と呼ばれていました。しかし、「娘子」や「朗君」は奴隷が主人に呼びかけるときにだけ使われるのではありません。他の奴隷は女性を見ると「娘子」と呼び、若い女の子を「小娘子」と呼ぶ人もいます。年配の人も若い男性を「朗」や「朗君」と呼びます。例えば、李白の詩には、老人が李白に「今日はなぜ川を渡ろうとするのか」と尋ね、そして「こんな嵐では無理だ」と警告したという記述があります。 唐代には、親しい男性同士は、姓、生まれ順、または末尾に「朗」を付けて呼ばれることが多かった。例えば、白居易は袁真を「袁九」と呼び、唐の徳宗皇帝は陸智を「陸九」と呼んだ。一方、女性は姓、生まれ順、および「娘」で呼ばれることが多かった。例えば、「公孫大娘」、「李世兒娘」などである。 「小郎」と「小娘」は、昔からよく知られている愛称です。 また、「郎」について言えば、他の二つの称号も無視できません。当時、女性は夫の弟を「小郎」と呼び、婿は「郎子」と呼ばれていました。『武双伝説』にあるように、武双の家族は子供の頃から、王仙科を冗談で「王郎子」と呼んでいました。 ここまで話してきたが、当時の自分の呼び方についてはまだ話していないことに気づいた。当時の男性のほとんどは、自分自身を「○○さん」と呼び、中には謙虚に「召使」と呼ぶ人もいたので、他にもさまざまな名前がありました。後の時代の女性たちが自らを「奴隷」と謙遜して呼ぶようになったほか、女性は自らを「あの方」と呼ぶことが増えた。同時に、自らを「誰か」と呼ぶ女性もいた。 唐代には、宰相だけが「項公」と呼ばれたが、これは後代ほど一般的ではなかった。官房と人事部の役人は互いに「葛老」と呼び合い、使節は敬意を込めて「士君」と呼ばれ、県知事は敬意を込めて「明夫」と呼ばれ、県知事は「少夫」と呼ばれた。そして、彼らはしばしば敬意を込めて「ミンゴン」と呼ばれます。 さらに、唐代の官僚同士の呼び方や、庶民が皇帝や官僚に呼びかける様子を見ると、当時の人々の関係は明清時代のそれよりもはるかに平等であったことがわかります。 唐代において、「先生」は父親に対する敬称に過ぎず、自分より身分の高い役人に対しては使われなかった。また、下級の役人が上級の役人に会うときや、庶民が役人に会うときも、後の世代のように卑屈な態度を取ることはなかった。当時、役人は一般に正式な肩書きで呼ばれていたが、お互いに親しい場合は「上級の役人」で呼ばれることもあった。首相が使節と会うとき、彼は自分を「誰それ」と呼び、使節を「誰それ使節」または「誰それ使節」と呼び、使節も首相に対して自分を「誰それ」と呼ぶ。同様に、使節の支配下にある国民は使節を「誰それ使節」または「誰それ使節」と呼び、国民が使節に対して自分を「誰それ」と呼ぶのと同じように、使節も国民に対して自分を呼ぶ。同様に、大臣は上司であろうと、部下であろうと、あるいは一般人であろうと、「○○さん」と呼ばれます。また、大理寺の大臣は、刑務所で裁判を待つ囚人であっても、「○○さん」と呼ばれます。法廷でも、男性は「誰それ」と呼び、女性は「えー」と呼ぶのが普通でした。 例えば、郭子怡のような地位の人が、自分の家の壁を修理している作業員に話しかける際、自分を「誰それ」と呼び、作業員たちも自分を「誰それ」と呼んで応えた。 また、庶民も皇帝に会うと、役人と同じように「大臣」と呼んだ。これは明皇帝が逃亡中に老人と交わした会話や、徳宗帝が巡幸中に農民と交わした会話に見て取れる。 また、よくわからない点が 1 つあります。それは、唐代の王の王子たちは、別の称号がなかったとしたら、どのように呼ばれていたかということです。おそらく、「何某王子」とも呼ばれていたのではないかと思います。 『全唐詩』には「冀皇太子」の記事があり、『旧唐書粛宗志』では粛宗皇帝が改名した理由について述べており、粛宗皇帝の名前が「紹」から「衡」に変わったのは、「紹」が宋皇太子の名前と同じだからだとされている。 |
<<: 北宋時代の汴津皇宮の火災後、丁維はどのようにして再建事業を成し遂げたのでしょうか。
>>: 鳳凰冠は古代の皇帝や側室がかぶっていた冠ですが、どのような装飾が施されていたのでしょうか。
推薦する
遼朝には四季の奴伯制度の他にどのような政治制度が存在したのでしょうか?
遼王朝(907-1125)は、中国の歴史上、契丹族によって建国された王朝です。9人の皇帝がいて、21...
古代中国の王族の血統を持つ10の姓が明らかに
誰もが生まれたときに家族の姓を受け継ぎます。それは私たちの生来のコードであると同時に、家族の血縁関係...
中国の道教で有名な四つの山はどこですか?
道教は中国固有の宗教であり、中国人の根源です。道教は中国の倫理、道徳、考え方、民俗習慣、民間信仰に深...
周公の東征はいつ起こりましたか?戦後の対策は?
周公東征の時:周公は反乱が拡大し、事態が深刻になったのを見て、「国の安泰はこの東の地にある」と深く感...
春節の習慣は何ですか?春節の起源は何ですか?
1. 春節の紹介春節は旧暦の最初の月の最初の日であり、旧暦の年とも呼ばれ、一般に「新年」として知られ...
「寒山路」は唐代の詩僧寒山が、人里離れた寒山に住み、世俗のことに煩わされない心境を表現するために書いたものです。
寒山は詩人で僧侶でもあり、浙江省東部の天台山の冷たい岩山に隠遁して暮らし、自らを「寒山」と称した。興...
現代医学では高山病は何と呼ばれていますか?高山病の原因は何ですか?
高山病の発生率は、登山速度、高度、滞在時間、体調に関係します。一般的に、平地から急に標高3,000メ...
艾新覚羅ニカンに関する情報 ニカンの軍事的功績は何ですか?
アイシン・ジオロ二館アイシン・ジョロ・ニカンは非常に有名な将軍ですが、軍功の優れた軍人であるだけでな...
商鞅の改革によって秦国はどのようにして強大になったのでしょうか?商鞅の改革はなぜそれほど効果的だったのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、商閻の改革がなぜそれほど強力だったのかをお...
本草綱目第8巻Artemisia selengensisの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
なぜ古代日本には「眉毛を剃る」「歯を黒く塗る」という習慣があったのでしょうか?日本には他にどんな習慣がありますか?
今日は、おもしろ歴史編集長が、古代日本にはどんな風習があったのかをお届けします。皆さんの参考になれば...
王維の詩「崔九兄は南山へ行き、馬上でスローガンを叫び、別れを告げる」の本来の意味を鑑賞
古代詩「崔九兄弟は南山へ向かう途中、スローガンを叫び、別れを告げる」時代: 唐代著者 王維私たちは街...
明朝初期には元朝を模倣して紙幣が発行されましたが、どのようなインフレが起こったのでしょうか?
中国の紙幣発行は北宋時代の「交子」から始まり、続いて南宋時代の「千音」、そして「会子」が発行された。...
『詩経』の「法克」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
木を切る匿名(秦以前)どうやって木を切るか?斧だけでは不十分です。どうやって妻を手に入れるか?仲人な...
『旧唐書伝』巻11にはどのような出来事が記録されていますか?原文は何ですか?
『旧唐書』は唐代の歴史を記録した偉大な歴史文学作品です。後金の開雲2年(945年)に完成し、全200...