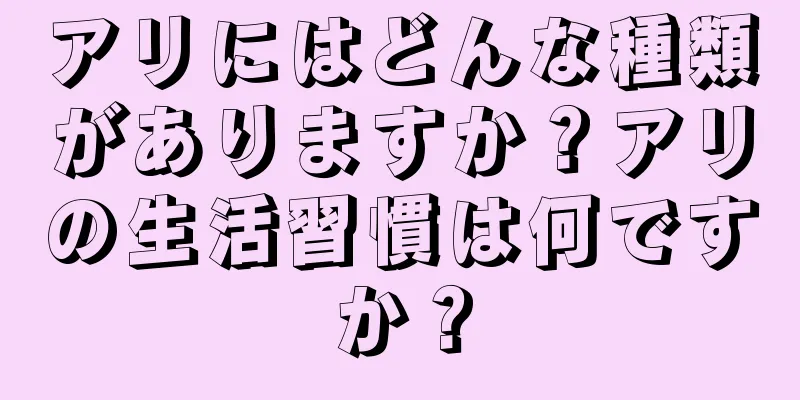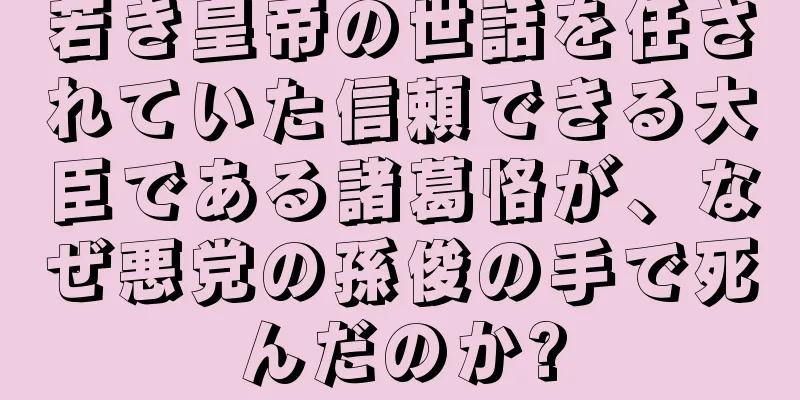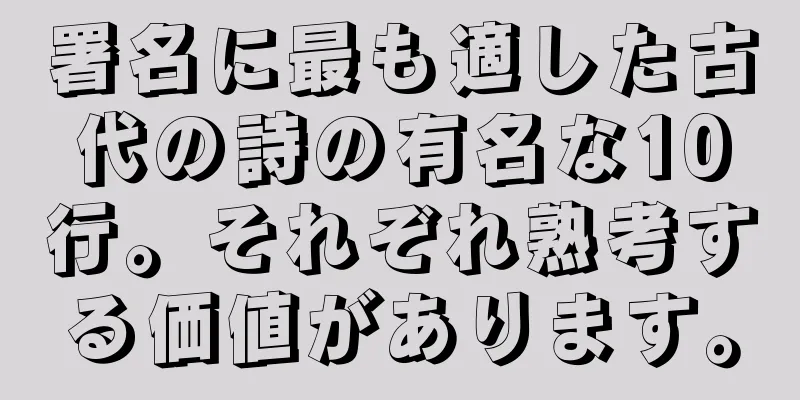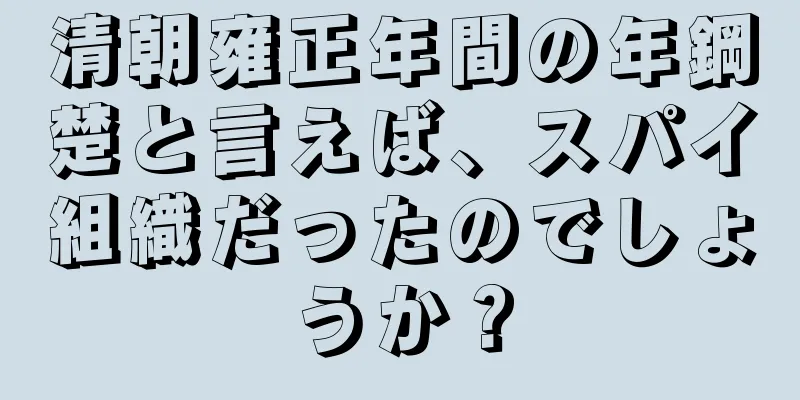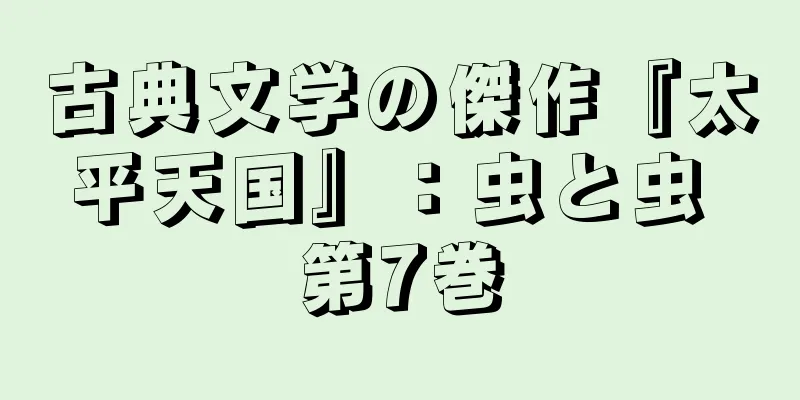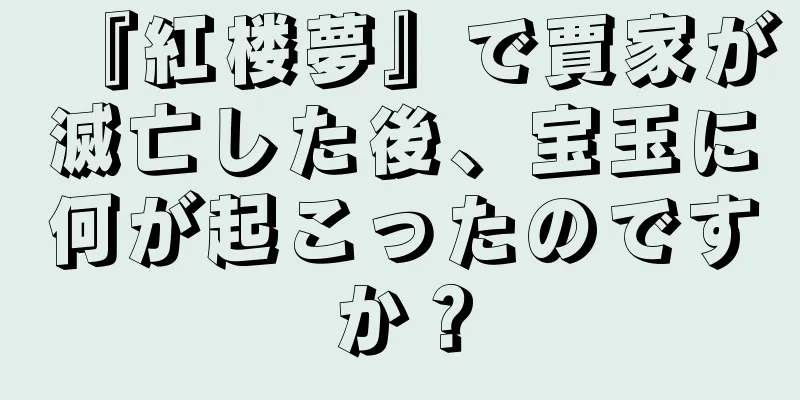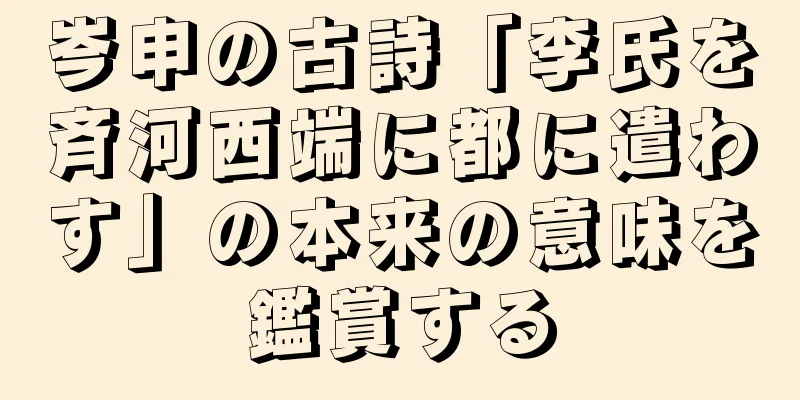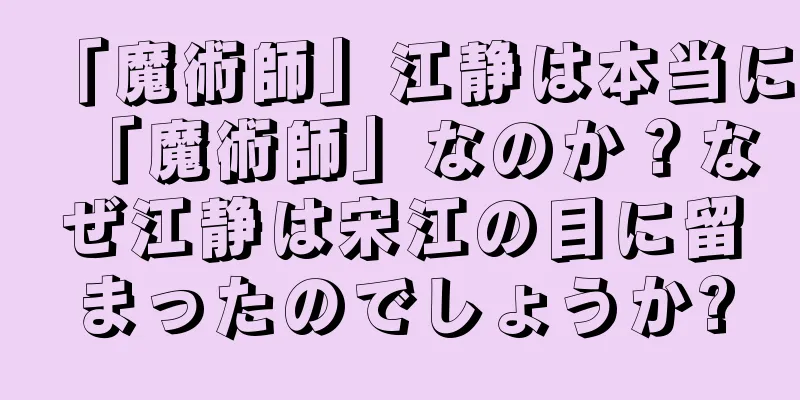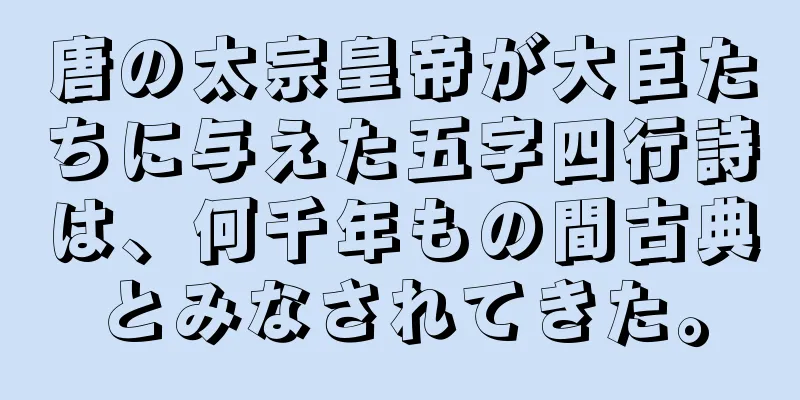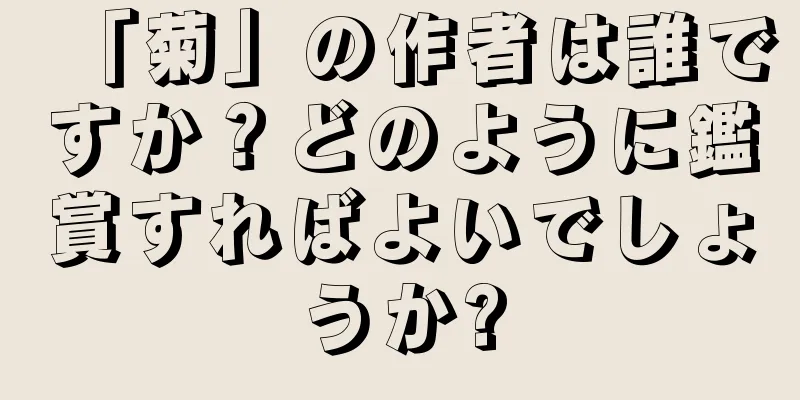名前の通りボーンレスペインティングとは何でしょうか?骨のない絵画はどの古代に始まったのでしょうか?
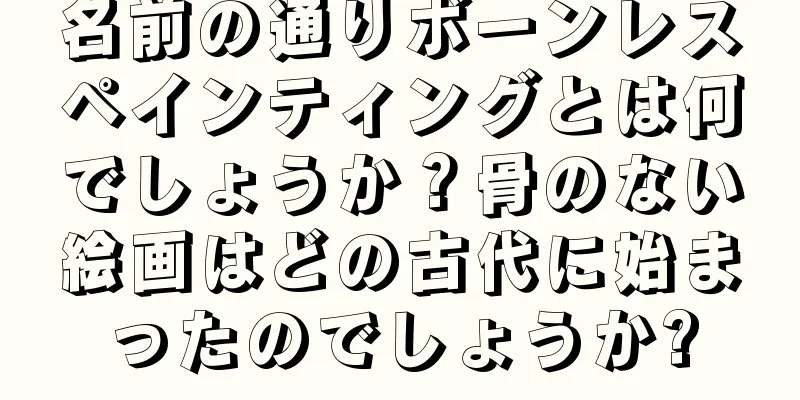
|
ボーンレス・ペインティングは、その名の通り、骨を皮膚と肉の中に隠すというものです。つまり、無骨画法とは、絵の中の物の輪郭を描かず、墨と色で物を直接(点と染料で)描く画法です。そのため、輪郭線に制約されず、細筆とフリーハンドの筆遣いの間で独特の自然で鮮やかな造形を十分に発揮することができ、また、必要に応じて細筆とフリーハンドの筆遣いを自由に選択することもできます。では、骨なし絵画はいつ始まったのでしょうか? 次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 【説明1】:この技法は、古代の陶器の彩色文様など、古代中国の絵画で古くから使われてきました。 【説明2】:記録によると、南北朝時代の張僧有はかつて建康宜成寺に赤と緑を使って凹凸の花を描いた。伝説によると、張僧有の『観碑図』も全彩色で描かれており、張僧有は無骨画法の創始者とみなされている。 張僧有は6世紀の仏教絵画の巨匠で、インドの影絵技法を用いて仏画を描いたと言われています。かつて宜城寺で天柱画の技法を用いて「凹凸花」を描いたことについて、『建康録』には次のように記されている。「宜城寺は梁の少陵王王倫が建てた。寺の門には凹凸花の絵があり、張僧有の作と伝えられている。花は天柱様式で作られ、赤と緑の色彩が使われている。遠くから見ると目がくらんで凹んでいるが、近くで見ると平らである。世間の人々はこれに驚いたので、凹凸寺と名付けられた。」 色彩面では海外の画家たちの色彩技法を吸収した。伝説によれば、彼は輪郭線を必要とせず色だけを使用する「骨なし」の絵画技法も考案した。宋代の画家、婁観は山水画の銘文に次のように記している。「梁朝の天津年間、張僧有は絹の上に筆や墨を使わず、代わりに濃い緑や暗い色を使って山頂や霧、泉、岩などを描いた。これは骨拭き法と呼ばれ、一時期有名だった。後に楊勝だけが彼から学び、その秘法を習得した。」 【説明三】:唐代の明皇の時代に楊勝という画家がいました。張僧有の影響を受け、山水画を描くとき、山や岩の輪郭を墨線で描くことも、山や岩の質感で凹凸や陰陽を区別することもせず、直接色彩で表現しました。木を描くときは、幹を一筆で描き、葉っぱは直接色を塗ります。楊勝の絵画は骨のない山水画と呼ばれています。 【説明4】唐代の壁画では、骨抜き図が基本的な絵画技法として広く用いられており、骨抜き図が唐代あるいはそれ以前に始まったものであることがわかる。例えば、敦煌壁画の第61窟西側北壁にある「五台山大仏光寺細部図」は五代時代の作品で、その中にあるバナナの木は無骨法で描かれている。木は墨線で輪郭を描くのではなく、色で直接描かれ、その形状や構造は余白と彩度の変化によって表現されています。もう一つの例は、第95窟南壁の西側にある「長眉羅漢図」で、羅漢の足元に描かれた植物にも無骨法が用いられ、余白を残すことで体の構造関係を表現しており、線描法で描かれた別の植物とは対照的である。 【説明五】:宋代の郭若胥の『画稿』によれば、無骨画法は五代の祖父と孫の徐熙と徐崇嗣に由来し、より正確には徐崇嗣に由来する。 「無骨画」という名前は、北宋時代の郭若胥が著した『画稿集』に初めて登場します。「徐崇嗣は無骨画を描き、筆と墨がないことからその名がつけられたが、その生態は豊かで美しいと評価された。」 後に、二人の禁じられた客に絵を見せたとき、蔡君墨は次のような碑文を書いた。「昔、絵画はすべて筆と墨で描かれていたが、崇嗣が布と色を使って写実的に描いたので、趙昌らはそれを真似た。」チョンシは気分が良いときには時々このような作品を描いていたと私は信じており、後年の作品は必ずしも墨と筆を使わないものではなかっただろう。 6 つの原則を検討すると、ブラシの使用が次に重要です。趙昌の場合、筆と墨が全くないわけではないが、主に固定されたモデルを使って模写しており、筆遣いが弱く、色を塗る効果のみに重点を置いている。 「徐崇嗣の絵画のすべてが無骨画というわけではないが、彼は「気分が乗ったときにたまにそのような絵を描く」だけであり、「彼の絵画は必ずしもすべて筆と墨を使い果たしているわけではない」ことがわかる。 この書物には、徐崇嗣が牡丹五輪を描いた花の絵を所蔵していたことも記されている。どの絵も筆墨で描かれたものではなく、色鮮やかな布で描かれたものだった。絵の横には「翰林侍官の黄坤らが徐崇嗣の無骨画を最高級のものと認めた」というキャプションが付いていた。 郭若胥と同時代の沈括は『孟熙湛』の中でこう述べている。「(徐)崇嗣は新しい思想を生み出した。墨を使わず花を描き、直接色を塗って染めた。これを無骨花と呼んだ。」徐崇嗣は「朱煌の作風を模倣した。筆と墨を使わず、直接色を塗った。これを無骨画と呼んだ。」その後、作家の蘇哲も『洛城集』の中で、徐崇嗣の絵画は「五色で染められ、筆の跡が全く見えず、無骨画と呼ばれる」と述べている。 【説6】:無骨画は実は黄権に由来し、徐崇嗣は単に「黄権の作風を模倣した」に過ぎない。宋代の『董田清録』はこう書いている。「孟叔の画家である黄権は富貴を夢見ており、その絵は主に豪華な庭の花や錦を描いたものだった。それらは本当に円や線(墨の線)のない粉(さまざまな色を指す)の山のように見えた。」明代の『葛古用論』には、「昔、杼一本で絹を捺す人がいた。黄権はザクロの花と百合を作った。いずれも筆も墨も使わず、色とりどりの布だけで作った。ザクロの木には百花以上、百合は一本の茎に四つの花が咲いていた。花の色はまるで今咲いたばかりのようで、非常に生き生きとしていて、本当に神秘的だった」と記されている。 明代の『清河書画船』には、「黄権は無骨画に優れている。ほとんどの花や果物は墨を使わず、五色で描かれている。花の色は咲いたばかりのようで、とても生き生きしていて、本当に素晴らしい」と記されている。黄権は壁画の制作にも参加した。黄秀傅は『益州名画』の中で、黄権がかつて八卦堂に「四季の花木、兎、雉、鳥、雀を描いた」と記録している。欧陽瓊もこれについて『壁画奇録』を著している。 『宣和画帖』には黄泉の「骨無花枝」という作品が収録されている。黄権の貢献は、古来の無骨画技法を軸物作品の制作に導入したことにあります。 |
<<: 明代の書物『絵画入門』に載っている線画技法18種類とは何ですか?
>>: 無骨画は中国絵画のスタイルの一つです。いわゆる「骨」とは何のことでしょうか?
推薦する
司馬叡はなぜ牛叡と呼ばれるのですか?司馬叡は誰の息子ですか?
司馬睿牛睿司馬叡は、ある歴史書に司馬家の王家の血筋ではないと記されているため、世間で牛叡と呼ばれてい...
西遊記第33章:異端者は本性を失い、原初の精神が本来の心を助けた
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...
龍済公主はなぜ洪瑾と結婚したのですか?神ハオティアンが言った理由は
洪瑾については、本には彼の師匠が明記されておらず、彼が結界宗の弟子であり、奇門遁甲の内旗と五行に精通...
成漢の初代皇帝、李雄には何人の息子がいましたか? 李雄の息子は誰でしたか?
李雄(274-334)は、名を仲君といい、李徳の三男で、母は羅であった。十六国時代の成漢の初代皇帝で...
蘇軾は黄州に流刑された後、最後の二行が非常に退廃的な詩を書いた。
今日は、『Interesting History』の編集者が蘇軾の物語をお届けします。興味のある読者...
第17章:秋左清は恋人と再会し、陳国九とその友人たちは共謀している
『海公小紅謠全伝』は、清代の李春芳が著した伝記である。『海公大紅謠全伝』の続編であり、海睿の晩年72...
壮劇の秘密を解き明かす:壮族の総合芸術
荘劇は「荘劇」とも呼ばれ、荘族の民間文学、歌と踊り、物語の語りの技術に基づいて発展しました。昔、壮族...
『紅楼夢』の雪の中で薪を集める物語の中で、劉おばあさんは薛宝柴の結末を語る。
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
貴族の家系はいつ誕生したのでしょうか?氏族制度の衰退の原因は何ですか?
封建階級制度の特殊な形態。東漢時代に形成され、魏、晋、南北朝時代に流行しました。古代中国では、役人の...
済公第90章:乱れた幽霊が英雄の華雲龍と出会い、逃げて古い友人に会う
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
『紅楼夢』の青文が宝玉と結婚したらどうなるでしょうか?
青文は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、第二巻の金陵十二美女の第一人者である。次回は、Int...
「忠勇五人男物語」第28話の主な内容は何ですか?
甥がキャンプ地で自分の姿を褒めているのを見て、ライオン・グローブの老召使はこっそりと盗み聞きした。鍾...
清朝時代に仏教はどのように発展したのでしょうか?清代仏教の発展史の詳細な解説
清朝の仏教はどのように発展したのでしょうか。これは多くの読者が特に知りたい質問です。次の興味深い歴史...
明代の十二監獄とは何ですか?明代の十二監獄の詳細な説明
明代の十二官とは何ですか? 十二官は、明代に皇室の内政を管理するために設置された 12 の官庁で、そ...
「李洙」の芸術的業績は何ですか?どのような技術が使われましたか?
「李璜」は写実主義とロマン主義を融合させた芸術的傑作であることはよく知られています。では、その芸術的...