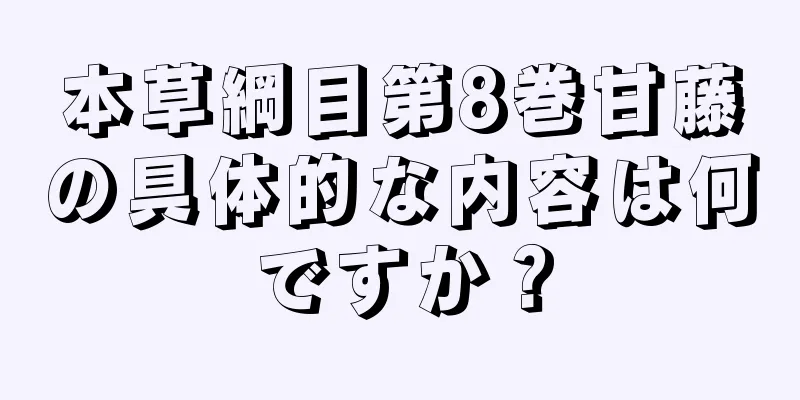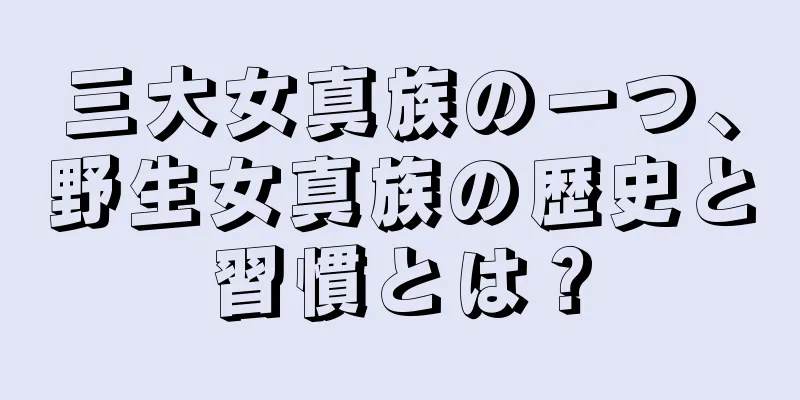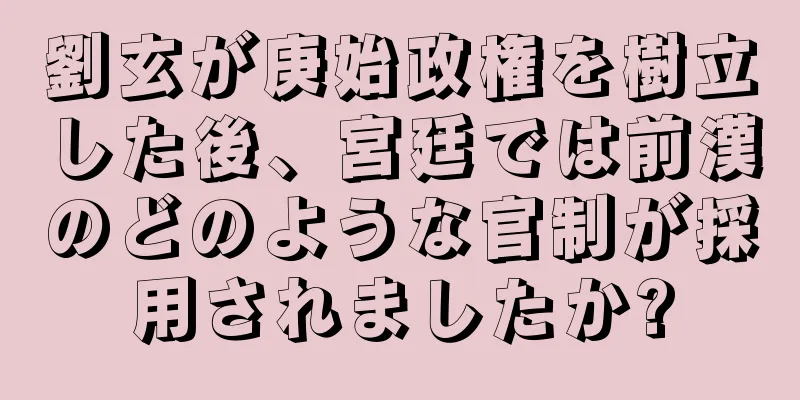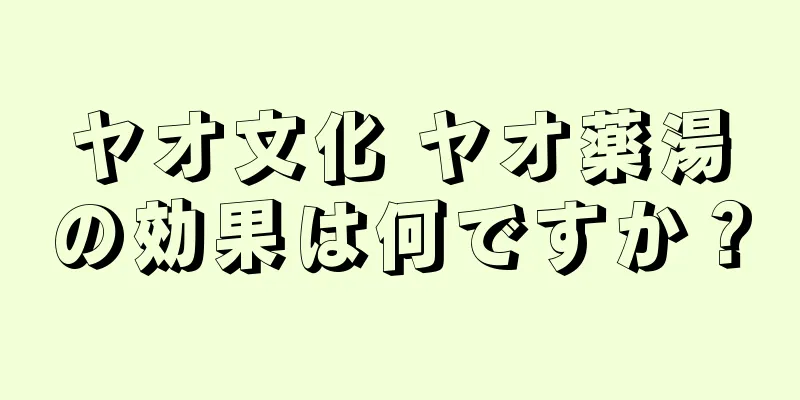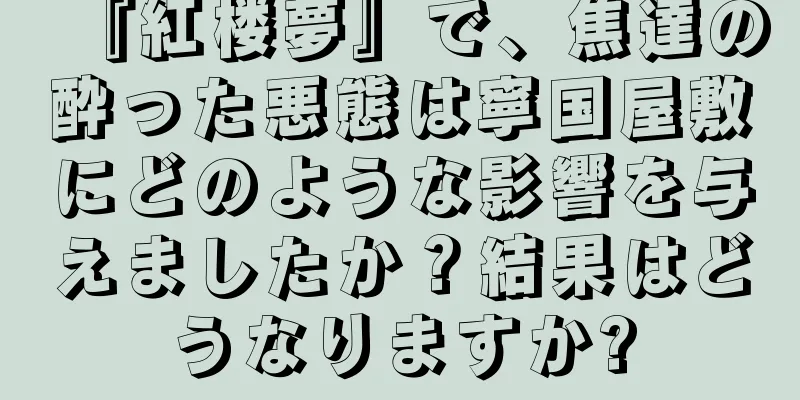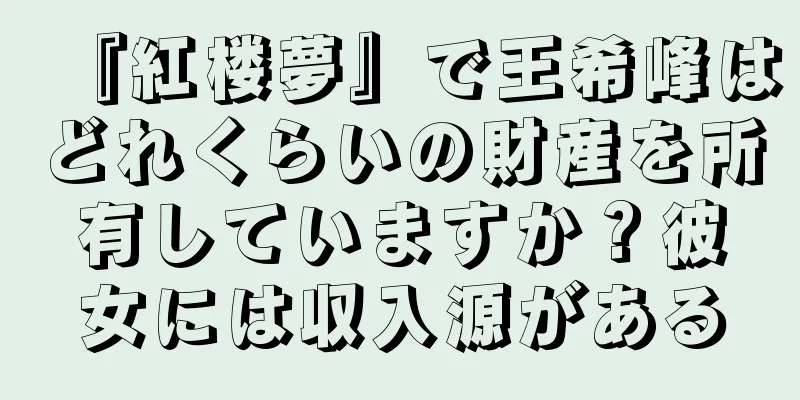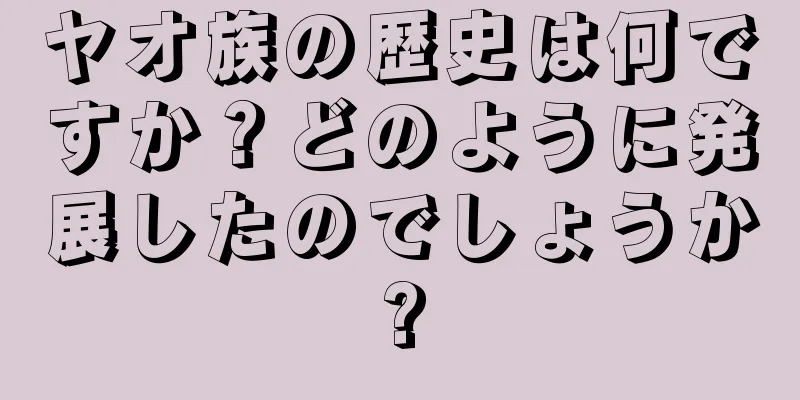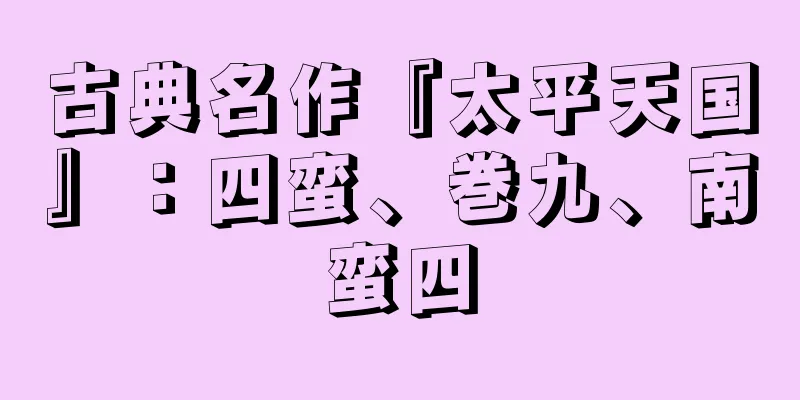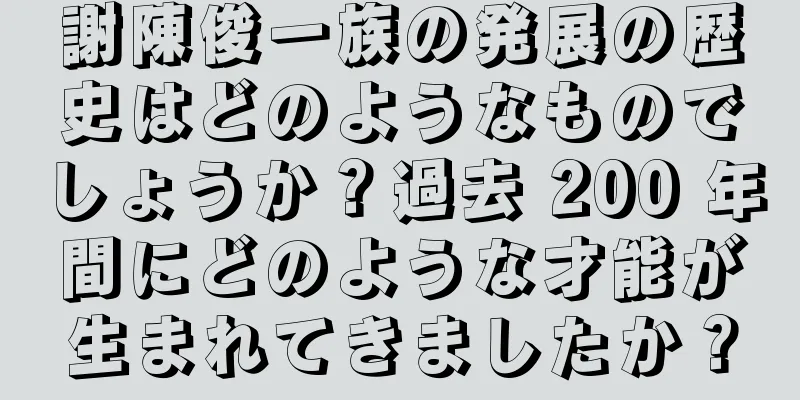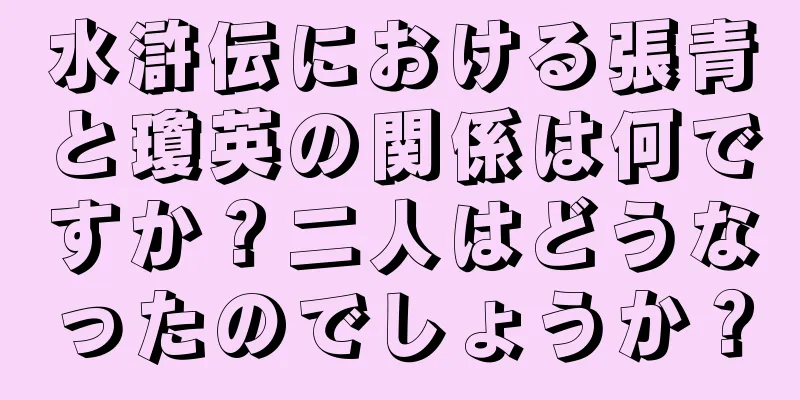乾隆帝はなぜ生前に退位することを選んだのでしょうか?乾隆帝は退位後何をしましたか?
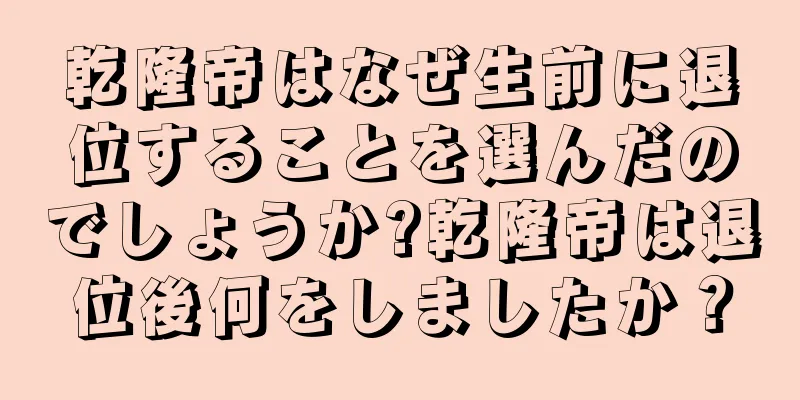
|
周知のとおり、我が国の古代の皇帝は終身在位であり、死ぬまでその地位に就きました。在位中に特別な事情が生じない限り、天皇が自ら退位することはなく、「一王朝に二人の皇帝」という現象は起こり得ない。 しかし、歴史上、至高の皇帝と呼ばれる特別な現象も存在しました。数は少ないですが、実に興味深い存在です。乾隆帝は退位後3年間、上皇として君臨しました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! では、なぜ乾隆帝は生前に退位することを選んだのでしょうか。退位後、乾隆帝は何をしましたか。 乾隆帝は若い頃、康熙帝に高く評価され、康熙帝の最も愛された孫でした。乾隆帝は康熙帝を常に尊敬し、彼の文武両道の功績を心から賞賛していた。そのため、乾隆帝は在位中に線香を焚き、「私の曽祖父は60年間統治しましたが、私は彼とは比べものになりません。もし天の加護があれば、乾隆帝の60年目、つまり私が85歳になった時に、息子に王位を譲り、政務から退こうと思います」と願い事をしました。 案の定、乾隆60年9月3日、乾隆帝は約束を果たし、乾清宮の「正大光明」の額に隠されていた密勅を取り出し、第15皇子永厳に帝位を譲り、皇太子として生きると宣言した。 乾隆帝の退位は歴史的に進歩的な意義を持っていたと言わざるを得ない。彼は強制や健康上の理由ではなく、自発的に王位を退位した。 しかし、乾隆帝の退位は表面的で不完全なものだった。彼は帝位を譲ってから3年経ったが、実際には依然として皇帝の権力をしっかりと掌握しており、自分が依然として国の実質的な支配者であるとあらゆるところで宣言していた。 なぜそう言うのでしょうか。乾隆帝が退位した後の皇帝の生涯を見ればそれが分かります。 1. 軍事力、政治力、人事権を掌握し、嘉慶を育成する。 乾隆帝は退位の際、「権力を回復した後も、軍事、国家、人事、行政のすべてを無視するつもりはない。引き続き精力的に活動し、自ら指示を与える。次の皇帝は昼夜を問わず私の指示に耳を傾け、何に注意し従うべきかを知り、間違いを犯さないよう努めるだろう」と宣言した。 この一節には、乾隆帝が退位した後も、乾隆帝が朝廷の軍事や国家の事柄、官僚の任免について最終決定権を持ち、嘉慶帝が毎日乾隆帝のもとに通って訓練を受けることが義務付けられていたことが明記されている。 乾隆帝の勅令によれば、退位後も彼は自らを「私」と呼び、勅令は依然として「勅令」と呼ばれていた。乾隆帝の誕生日は「万万歳」と呼ばれたが、嘉慶帝の誕生日は「万歳」としか呼ばれなかった。文武の官吏が北京に参拝に来たり、新しい職に就くために北京を離れるときには、乾隆帝の前に出向き、その指示を聞き、健康を祈らなければならなかった。乾隆帝が持っていた儀礼の基準と実際の権力は、嘉慶帝のそれよりはるかに優れていた。 嘉慶帝ができることは、定期的に勤勉さを報告し、彼の訓練を受け入れること以外には、祭祀、勅語、農耕の儀式、閲兵式などのさまざまな儀式に予定通りに参加することだけだった。 2. 乾隆帝は依然修心殿に住み、嘉慶帝は玉清宮に住んでいた。 乾隆帝は退位する前に、自身の安息の地として壮麗な寧寿宮を建てた。しかし、彼は修行の殿堂から出ることはなかった。その理由は「六十年間寝て起きて心を養う」という十分なものでした。つまり、六十年間も安楽長寿宮に住み、それに慣れていたのです。 「静寂長寿宮に住み続ければ、万事うまくいく」とは、静寂長寿宮に住んでいる限り、万事がうまくいき、安全であるという意味です。 乾隆帝が修心殿に住んだもう一つの理由は、国を治めやすくするために、自分だけでなく他人にとっても便利な場所に住んだかったからである。また、文民や軍の役人が彼に報告し、仕事に関する指示を求めるのにも便利になります。乾隆帝は、できるだけ早く修心殿を出て寧寿宮に住むつもりだと何度も述べていた。しかし、乾隆帝は死ぬまで修心殿に住んでいた。 3. 乾隆帝の称号は現在でも貨幣の鋳造に使用されている。 嘉慶帝は即位後、年号を嘉慶元年に改めたが、清宮内務省の文書には乾隆帝の治世61年と62年の暦が今も残っている。乾隆帝が亡くなるまで宮殿では乾隆帝の称号が使われており、乾隆帝の退位が完全ではなかったことが分かります。 論理的に言えば、嘉慶帝が即位した後、帝国の造幣局と各省の造幣局は嘉慶通宝を使用するはずだった。しかし、造幣局は乾隆帝に敬意を表すため、「乾隆帝の号を半分鋳造し、嘉慶帝の号を半分鋳造する」という方式を採用した。乾隆帝はこれを快く受け入れ、異議を唱えなかった。 嘉慶4年正月3日、権力に執着していた乾隆帝はついに89歳の生涯を終え、修心殿の寝室で亡くなった。 40歳の嘉慶帝が真に皇帝の権力と地位を手に入れたのはこの頃になってからであった。 |
<<: 中国の封建時代、清朝で最後に皇太子の称号を保持していた人物は誰ですか?
推薦する
ダオ・バイフェンの夫は誰ですか?道百峰の夫、段正春のプロフィール
段正春は、金庸の武侠小説『半神半魔』の登場人物。主人公段羽の養父であり、北宋大理国の鎮南王道百峰の夫...
古典文学の傑作「太平天国」:人事部第105巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
詩経第39巻第29章「官吏」の原文は何ですか?
太宰、一人。周の武王の治世中、周公は最初にここに住み、六大臣の長として国政を担当しました。秦、漢、魏...
李和の「忘れられない歌」:詩全体が人々に無限の美しさの余韻を与える
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
『紫智同鑑』の影響は何ですか? 「紫智通鑑」の詳しい説明
周知のように、『紫禁城同鑑』は古代中国の有名な歴史書であり、人々に高く評価され、読まれ、研究されてき...
『紅楼夢』ではなぜ中秋節が描かれているのでしょうか? u の背後にある深い意味は何ですか?
『紅楼夢』の第 75 章と第 76 章では中秋節について説明されており、これは本全体で最後の中秋節で...
東皇鐘の起源は何ですか?十大古器の紹介:東皇鐘
東煌鐘の用途は何ですか:東煌鐘は天国への門であり、その所在は不明であり、その力は不明です。一般的には...
もしオボイが死ななかったら、武三桂はまだ康熙帝に反抗する勇気を持っていただろうか?
康熙帝は三封を廃止し、呉三桂は清朝に対して反乱を起こさざるを得なくなった。康熙帝による三藩平定の有名...
十月革命の原因 十月革命の影響
十月革命は1917年11月7日、ロシア暦の10月25日に起こったため、十月革命と呼ばれています。この...
那蘭星徳の『菩薩男:小小、数葉の風雨』:作者は歌詞に悲しい気持ちを溢れさせる
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
唐代全書第36章:氷は白花を打ち、天の剣を認識し、奇妙な幽霊を殺し、邪悪な星を避ける
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、全68章から成り、「元湖漁夫編」と題され、略称は『唐物語』。...
北宋時代の作家蘇軾の詩「菩薩男 ― 回文秋房愁」の鑑賞
以下、Interesting History の編集者が蘇軾の『菩薩人・回文秋房告』の原文と評価をご...
羅巴建築の特徴は何ですか?
モンバ族はヒマラヤ山脈の南斜面にある低くて暑い谷に住んでおり、高床式の家に住んでいます。家は一般的に...
南宋文芸詩奇譚集第8巻『易堅志全文』
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
拓跋涛の母親は誰ですか?拓跋涛の母親、明元密皇后の簡単な紹介
拓跋涛(408-452)は、名を「佛」といい、鮮卑族の出身で、明元帝拓跋涛の長男で、母は明元密皇后で...