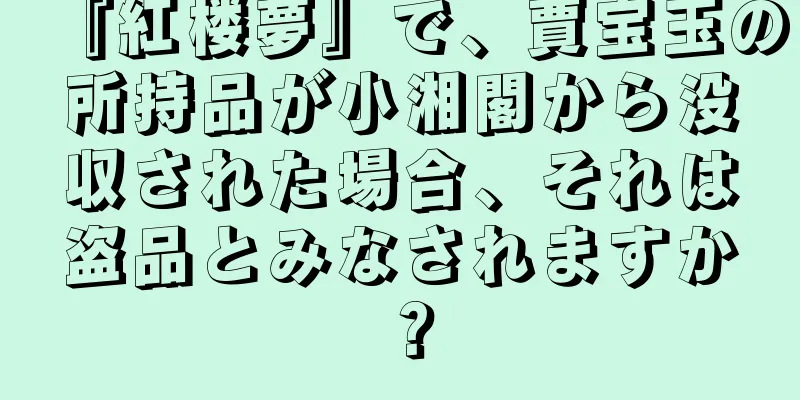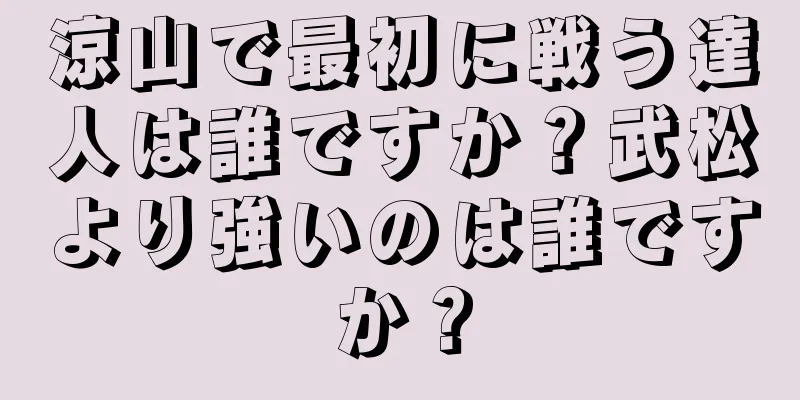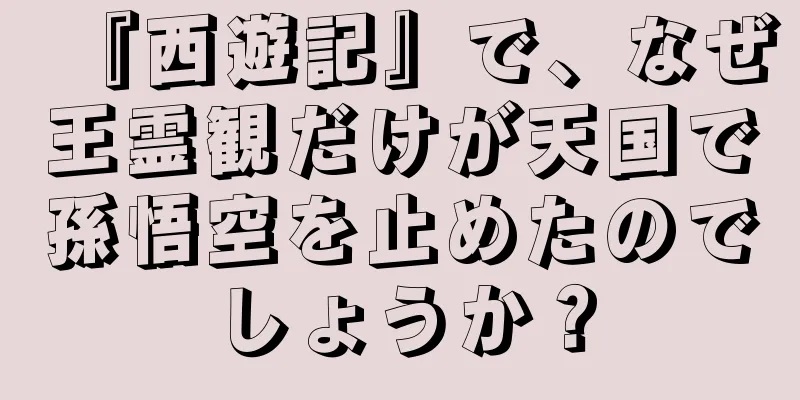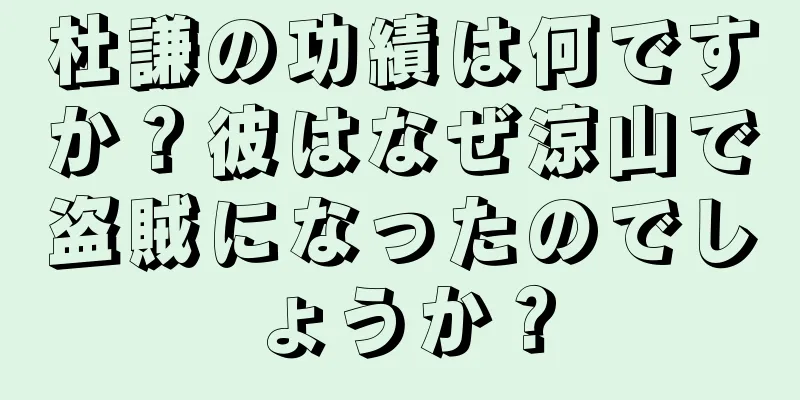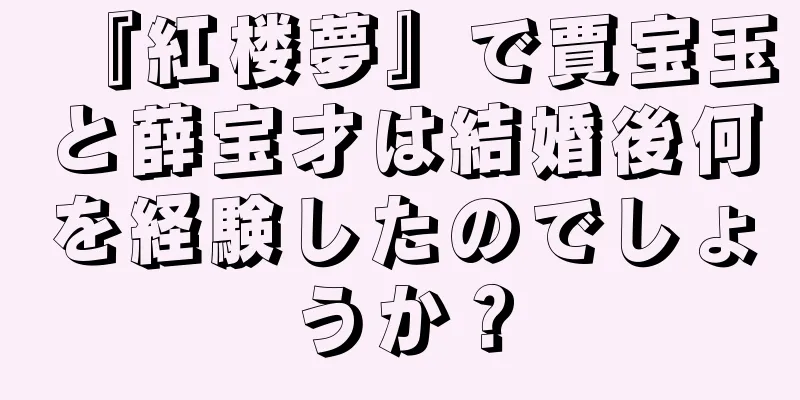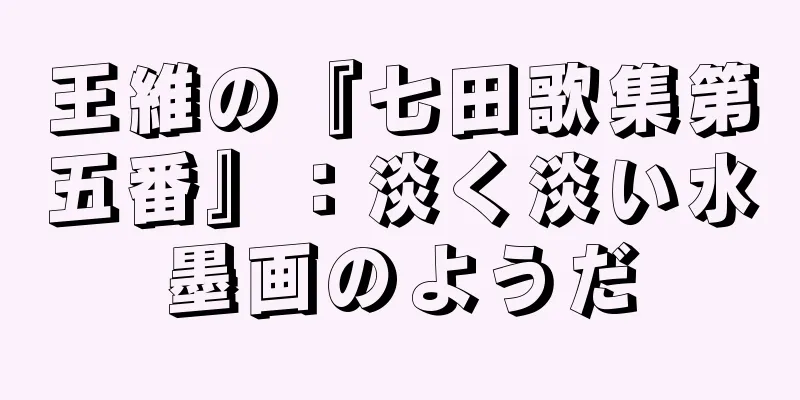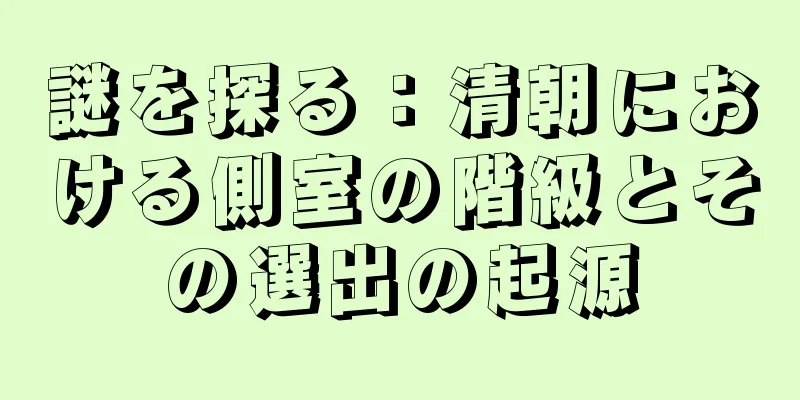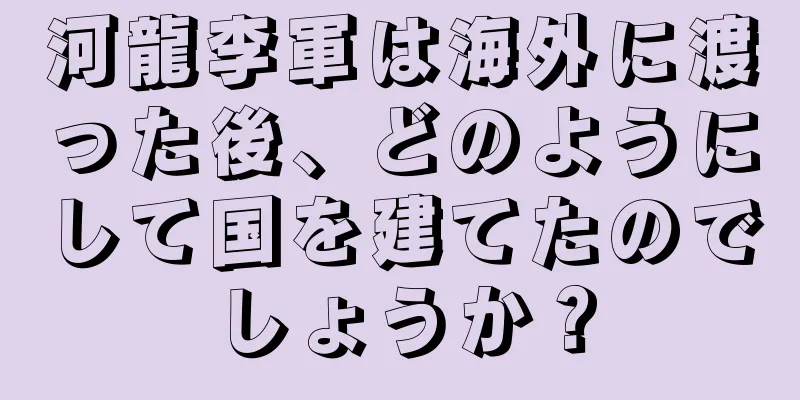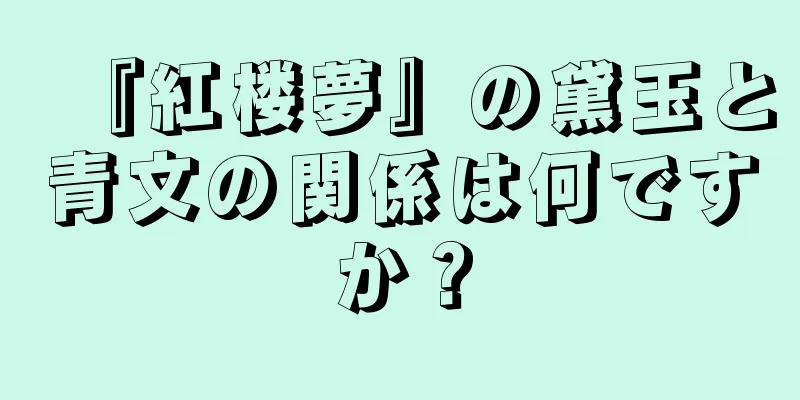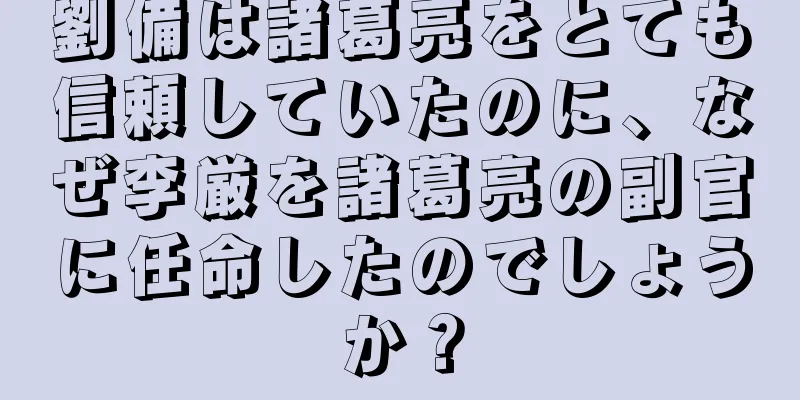『三国志演義』では孔明が東風を借りる様子をどのように描写していますか? 「風を借りる」の謎を解くには?
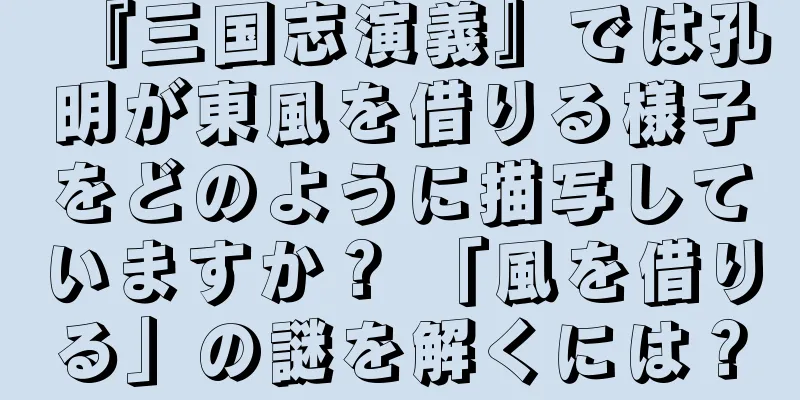
|
三国志演義の諸葛亮が東風を借りる話は諸葛亮の知恵を完璧に表現しており、この話は今でも広く流布され、誰もが知っています。現代の科学技術の発展に伴い、諸葛亮の東風借用について疑問を呈する人が増えています。風は本当に「借用」できるのでしょうか?諸葛亮はどのようにして東風を「借用」したのでしょうか?建安13年(208年)、曹操は軍隊を率いて南下し、孫権を攻撃しました。10月、曹操は軍隊を長江北岸に駐留させ、龐統が提案した鎖の計画を受け入れました。曹操は鉄の鎖で軍船をつなぎ合わせました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 揚子江南岸に位置する孫・劉連合軍は、揚子江という自然の防壁で守られていたものの、人員が不足していた。曹操に火攻めを仕掛けるのが最善の方法だった。しかし、真冬で北西の風しか吹いておらず、風上にいる孫・劉連合軍が火攻めを行えば、自軍の軍艦を焼くだけだ。 「すべて準備は整ったが、東風だけが足りない」という状況も周瑜を心配させた。この時、諸葛亮は「梁には才能はないが、かつて私は風雨を呼ぶことができる八門逃避の書を教えてくれた素晴らしい人に会ったことがある」と提案した。諸葛亮と周瑜は11月20日に東風を借りることに同意した。案の定、約束の時間に東風が吹いた。孔明は策略を使って、ベテランの黄蓋に降伏のふりをさせ、赤壁を焼き払い、曹軍を破った。これは三国志演義で孔明が東風を借りたという記述です。では、「風を借りる」という謎をどうやって解くのでしょうか? 研究により、いわゆる東風借用は、実際には諸葛亮が天文気象学を柔軟に利用したものに過ぎなかったことが判明した。まず、諸葛亮はなぜ11月20日を風を借りる日としたのでしょうか?古代中国も気象学を徹底的に研究しており、「夏至に陰が生まれる」「冬至に陽が生まれる」という記録がずっと残っていました。 11月20日は冬至です。この法則によると、冬至前は陰のエネルギーが強いと、長江沿いに北西の風として現れます。冬至後は陽のエネルギーが強くなり、風向が変わり、南東の風として現れます。孔明は「冬至に陽が生まれる」という気候変化の法則を知っており、東風が吹く時間を正確に把握していました。 諸葛亮が知っていた原理は、曹操も理解していたに違いない。 「陽のエネルギーが冬至に生まれて戻ってくるのに、どうして南東の風が吹かないのか? 不思議ではない!」しかし、曹操は問題を見落としていました。「真冬には西風と北風しかありません。」これは一定期間の気候条件の判断ですが、冬至の特殊性を考慮することを忘れていました。 冬至の日の気候は、前の時期と比べて大きく変化します。諸葛亮がこの問題を考慮していたことは明らかであり、それが彼の優れた点でもある。 また、孔明の家は赤壁からそれほど遠くなく、地元の状況をよく知っていました。そのため、彼はその日の天気の変化を正確に予測することができます。南東の風が吹くというのは、彼が理論と実践を組み合わせて得た結論です。 では、諸葛亮が祭壇に軍隊を配置した意図は何だったのでしょうか。赤壁の戦いで曹操の軍を破った後、劉備は諸葛亮を孫権とともに荊州で戦わせました。諸葛亮は「もし私が南東の風を借りていなかったら、周朗はどうして成功の半分も達成できなかっただろう」と言いました。 これは諸葛亮が謎めいた目的をも説明しています。孔明は成功の功績を自分のものにし、東風を口実に将来荊州を占領しようとしたのです。 諸葛亮のもう一つの目的は、祭壇で呪文を唱える機会を利用して周瑜の支配を排除し、すぐに自分の軍に戻って軍隊を展開し、曹操の失われた領土をめぐって周瑜と戦うことでした。 『三国志演義』第45章では、孔明が周瑜と出陣したばかりの時、劉備に「東南風が吹くのを待てば、梁は必ず戻ってくる」と言った。つまり、孔明は劉備に趙雲を派遣して、11月20日に約束の場所で待つように頼んだ。そのため、周瑜が諸葛亮を捕らえるために軍隊を派遣したとき、諸葛亮はすでに劉備の陣営に戻っていた。 諸葛亮が奇門遁甲の術を使って東風を借りたという説もある。斉門屯匡は、方向性と攻撃性の強い理論に基づいた、軍隊を配置する古代の方法である。 易門屯甲は易経、天文学、地理、暦、軍事、気象、政治、経済などの膨大な知識を結集した、洗練された予測技術です。 諸葛亮はこの高度な予報技術を習得し、11月21日から強い南東風が吹くと予言した。したがって、諸葛亮が東風を「借りた」主な理由は、天文学と気象学に関する彼の徹底的な研究によるものでした。 |
<<: 当時の偉大な英雄であった曹操の野心は、年を重ねるにつれてどのように薄れていったのでしょうか。
>>: 赤壁の戦いが勃発したとき、曹操の顧問である程毓は何らかの役割を果たしましたか?
推薦する
道光帝の娘、寿蔵和碩公主の簡単な紹介
寿蔵和碩公主の簡単な紹介古代中国、清朝の道光帝の五女として、道光9年(1829年)10月19日に生ま...
段延卿とともに四大悪人の一人、南シナ海のワニ神のプロフィール
金庸の小説『半神半魔』の登場人物。姓は岳、四悪人の三番目。あだ名は「凶暴な悪人」だが、自らを二番手と...
水滸伝で、趙蓋が曽頭城への攻撃に失敗することを知っていたのに、なぜ公孫勝は彼を止めなかったのですか?
曽頭城は『水滸伝』に登場する地名で、山東省の奥地、凌州の南西部に位置しています。今日は、興味深い歴史...
三国時代には多くの軍師がいましたが、なぜ夏侯は武将の中で最高だったのでしょうか?
「荀家の八龍」、「諸葛三英雄」、「馬家の五常徳」、「司馬八人」とは…上記はすべて歴史上有名な学者であ...
漢民族の最も特徴的な楽器は何ですか?
中国の楽器の中で、最も華やかなのは静胡です。静胡は個性のない役者ですが、あらゆる点で美しく、オペラで...
『徐如子祠』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
徐如子祠黄庭堅(宋代) 3エーカーの家に住み、草の束だけを相手に話す隠者は、誰と話すのでしょうか?ブ...
柳に関する詩を 7 つ見て、そのうちのいくつを読んだことがあるか確認してみましょう。
ここに柳の詩を 7 つ紹介します。興味のある読者と Interesting History の編集者...
呉文英の『宋代鴉歌序』をどう鑑賞すべきか ― 春節祭の感想
応体旭:宋代呉文英の春節祭の感想、以下興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届けしますので、見てみましょ...
中国古典文学『礼記』原文の鑑賞:葬式記録第22章
内側と外側の両方に病気がある。王と大臣たちは職を解かれ、学者たちは琴やハープを手放した。寝室は東側、...
軍事著作『百戦百策』第2巻 柯戦全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
今日の世界では、同じ量の水を燃やすのに電気を使うのと天然ガスを使うのとではどちらが費用対効果が高いのでしょうか?
お湯を沸かすには、通常、電気か天然ガスを使用します。社会の進歩に伴い、天然ガスはすでに何千もの家庭に...
『紅楼夢』の賈邸での中秋節の夜、石向雲はどのように振る舞いましたか?
石向雲は『紅楼夢』の金陵十二美女の一人です。これに非常に興味がある方のために、『おもしろ歴史』の編集...
道教の書物『管子・環公文』の原文は何ですか?管子入門:桓公の質問
『管子』は秦以前の時代のさまざまな学派の意見を集めたものです。法家、儒家、道家、陰陽家、名家、兵学、...
この唐代の王子はどれほど奇妙だったのでしょうか?彼は実際に石に刻まれた王位を放棄した
古代社会では、皇帝よりも権力を持つ者はいなかった。皇帝になるために、多くの人々は兄弟や父親、さらには...
新婚の白居易が書いた恋愛詩のことで叱られたのはなぜでしょうか?
白居易の物語をご存知ですか?次はInteresting Historyの編集者が解説します。白居易は...