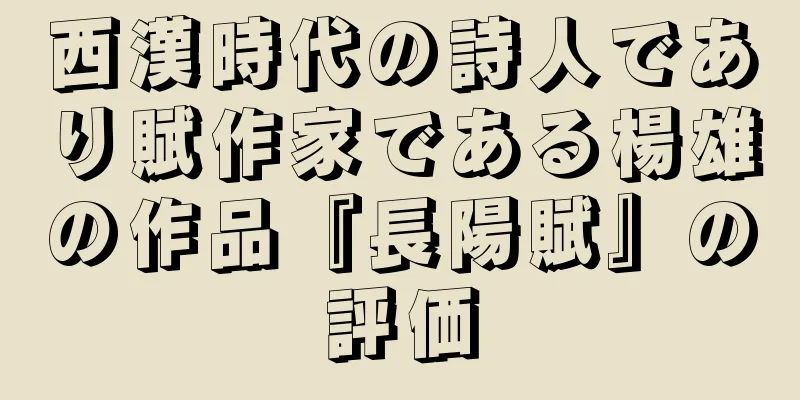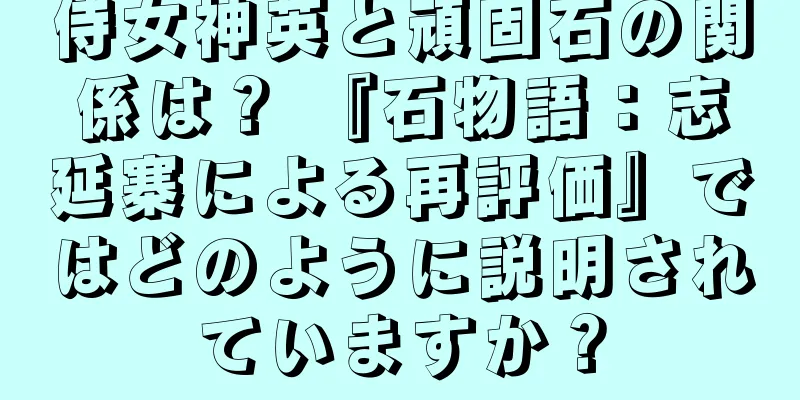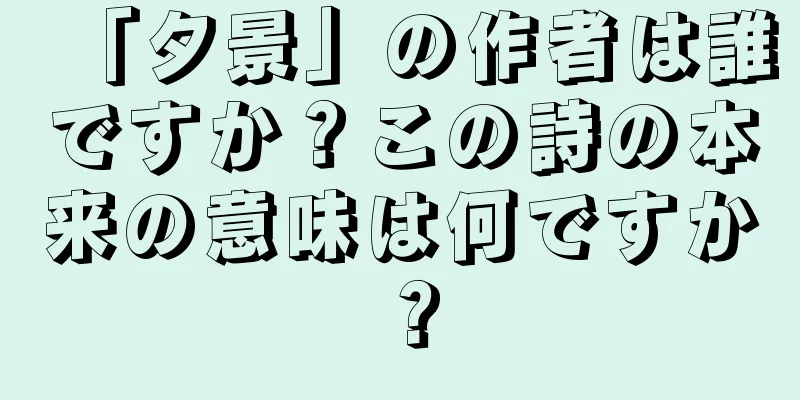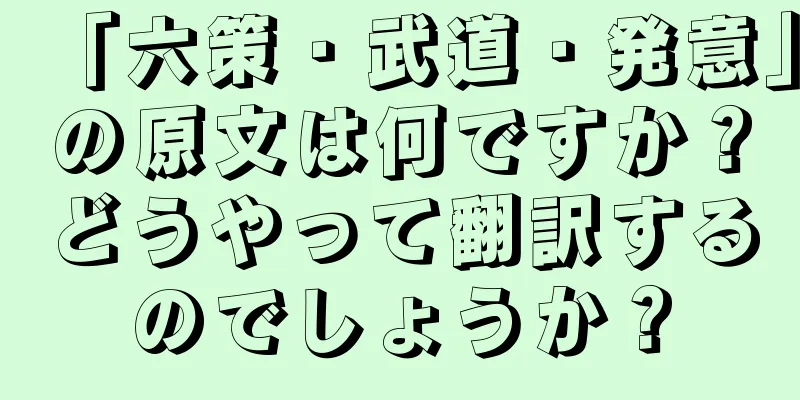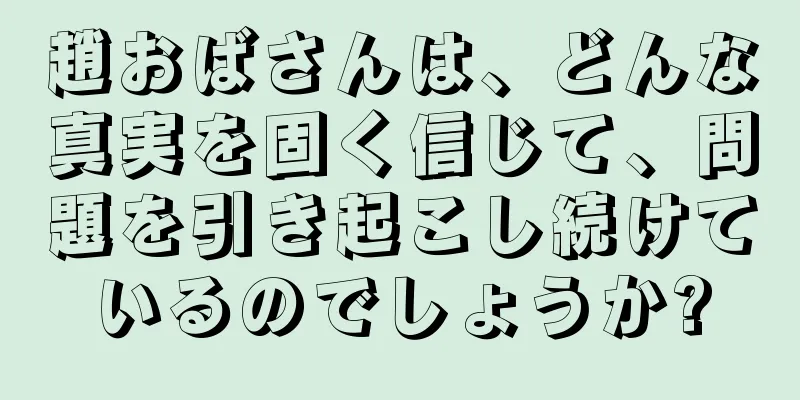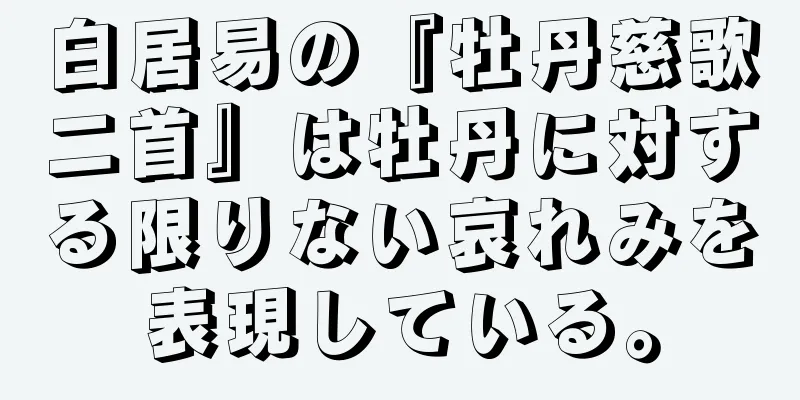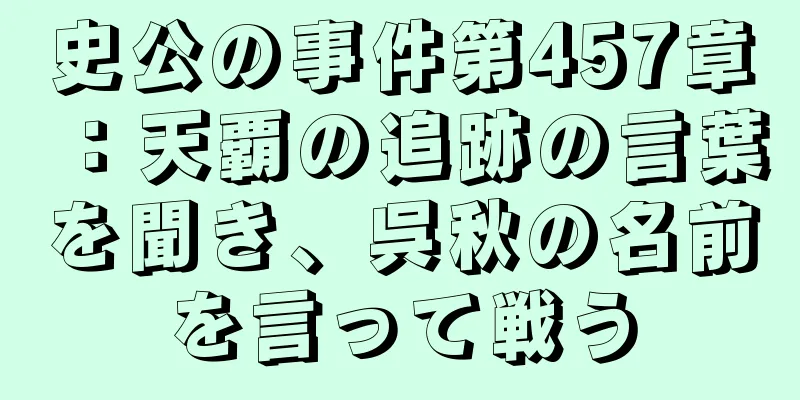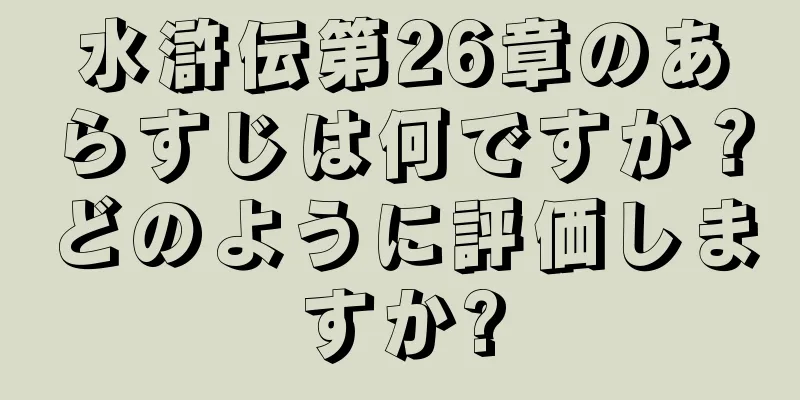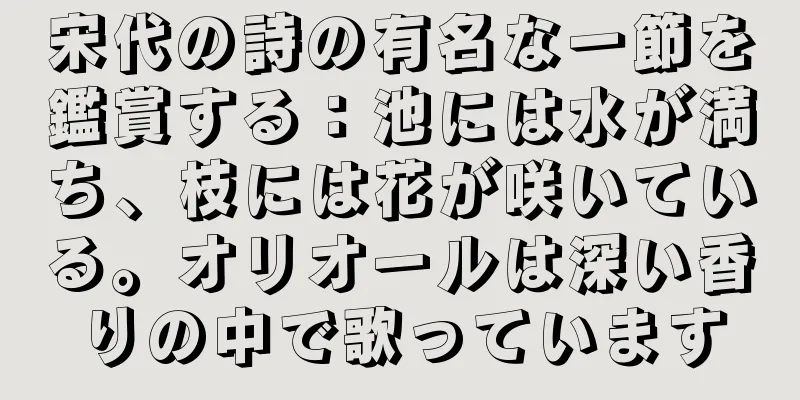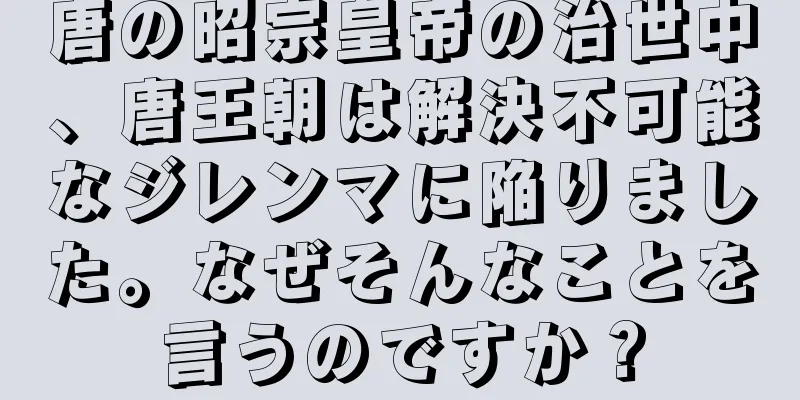諸葛亮の空城作戦に直面して、司馬懿の撤退は誤った判断だったのか?
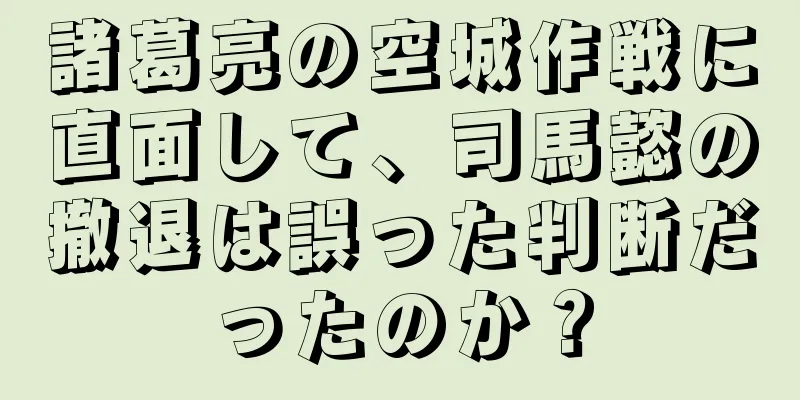
|
三国志演義第95章に登場する空城の計は皆さんもよくご存知でしょう。曹操は司馬懿に軍を率いて蜀漢の街亭を攻撃させた。諸葛亮は馬蘇に守備を任せた。馬蘇が防御を失うと、司馬懿は勝利に乗じて西城まで追撃した。諸葛亮は西城にいた。当時、城には兵力が不足していたと言っても過言ではない。実際、兵士はまったくおらず、周囲には数人の従者がいるだけだった。司馬懿の軍隊が城に近づいてくるのを見て、諸葛亮は心を落ち着かせ、魔法作戦を開始した。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 諸葛亮はまず正直な指示を与えた。「魏の兵士が到着したら、動くな。私のやり方は私のものだ。」彼の指揮下にある兵士たちは懐疑的で、動く勇気がなかった。諸葛亮のクローズアップを撮りましょう。彼は鶴の外套(おそらく鶴の羽で作られた外套)を着ており、頭にはターバンを巻き、手には羽扇を持っています。彼はそよ風が吹く城壁の上に立っています。なんとハンサムな男性でしょう! さて、戦争の状況に戻りましょう。諸葛亮は二人の子供に古琴を持たせて城壁に置き、線香に火を灯し、座ってゆっくりと古琴を弾きました。ピアノの音は、時には高く、時には美しく、時には柔らかく、数曲演奏した後、諸葛亮は目を閉じて首を振りました。まるで酔ったようで、まるで敵が全く近づいておらず、城門が大きく開いているかのようでした。 司馬懿の軍が西城に到着した。司馬懿は城壁の状況を見て、一瞬混乱した。何が起こっているのか?諸葛亮は何をしているのか?城内に私を待ち伏せしている軍隊がいるのだろうか?諸葛亮は私を城内に誘い込み、待ち伏せしているのだろうか?司馬懿は常に疑い深く、この瞬間、動く勇気はなかった。 これを見た司馬懿の息子は、状況を確認するために小さな部隊を城に派遣することを提案した。もし諸葛亮が本当に待ち伏せしていたら、まだ逃げる時間はあるだろう。司馬懿は考えた末に反対し、撤退を命じた。これが有名な空城作戦である。諸葛亮は兵士を一人も失うことなく司馬懿の軍を追い返した。 諸葛亮の魔力作戦は後世に広く伝えられ、誰もが諸葛亮を称賛し、彼はとても賢くてまるで悪魔のようだったと言った。しかし、彼らは司馬懿の行動に非常に困惑していた。結局のところ、司馬懿の息子の言うとおりであれば、状況を調べるために少数の軍隊を城に派遣するのが最善の決定だろう。それで、司馬懿の撤退は間違いだったのでしょうか? 諸葛亮は神と呼べるというのは一致した見解ですが、司馬懿は本当に諸葛亮より劣っているのでしょうか?歴史上、最後に笑ったのは司馬懿であり、司馬家は顧問として勝利しただけでなく、最終的に天下を勝ち取り、司馬家王朝を樹立しました。司馬懿のIQは絶対に正しいようですが、この単純明快な撤退の理由は何でしょうか? 三国時代を扱った他の本や映画、テレビ作品をもっと読むと、「三国志演義」の司馬懿の設定が少し薄すぎることに気づくだろう。もちろん、これは作者が諸葛亮を際立たせるために作った設定であり、理解できる。さまざまな歴史資料に基づいて、後世の司馬懿に対する評価は徐々に高まってきています。諸葛亮の才気があまりにも眩しかったため、司馬懿の才気が影を潜めてしまった。 司馬懿の才能には全く問題がなかったのに、どうして諸葛亮の空城戦術に騙されるのでしょうか? 司馬懿が軍を撤退させた後、諸葛亮はこう言いました。「空城戦術は司馬懿に対してのみ使える。」この文は熟考する価値がある。後世の多くの人は、諸葛亮の言葉を、諸葛亮は司馬懿のことをよく知っていて、司馬懿が疑い深く、軽率な行動はしないだろうと知っていたという意味だと解釈した。 しかし、この解釈には実は欠陥がある。司馬懿が疑念を抱いていたのは事実だが、司馬懿の息子が解決策を提案した。この解決策は完全に実行可能だったが、司馬懿はそれを採用せず、軍の撤退を主張した。空の城の計画は確かに素晴らしいですが、司馬懿が振り返って歩き去っていくのも非常に不思議です。この二人は脳波を通じて意思疎通し、合意に達したのでしょうか? はい、空城作戦で軍を撤退させることができたのは、諸葛亮と司馬懿の間に神々のレベルに達した暗黙の了解があったからこそだと言えます。こうした暗黙の了解は、口に出さなくても二人の兄弟だけが理解できるものなのです。司馬懿はその秘密を持ち去ることはなかった。死ぬ前に、その理由を息子の司馬昭に伝えた。司馬家が再起できたのは、ライバルである諸葛亮の存在によるところが大きい。 蜀漢は基本的に諸葛亮に支えられており、諸葛亮が亡くなれば蜀漢は一挙に滅亡し、魏が容易に蜀漢を制圧することになる。戦うべき蜀漢も諸葛亮もいなくなったとき、司馬家は曹魏政権にとってまだ役に立つだろうか? 実際、曹家は司馬家を最大の敵とみなし、司馬家は悲惨な運命をたどることになるだろう。 この分析は本当に悲痛ですが、これが現実です。曹操はかつて子孫にこう言いました。「司馬一族を使えるなら使え、使えないなら殺せ! いいか、曹魏は司馬一族をただ使うためだけに使ったんだ。物を使うのと同じだ。役に立たないなら捨てろ。有害なら叩き潰せ! 最も冷酷なのは皇族だ!」 『史記』にはこう記されている。「鳥が全て撃ち落とされると、弓矢はしまわれ、ウサギが全て死ぬと、猟犬は殺され、調理されて食べられた。」ここでの意味は単純です。鳥やウサギがすべて殺されてしまうと、弓矢や狩猟犬は飼い主にとって役に立たなくなります。人間同士で使う場合も全く同じです。他人の問題解決を手伝った後は、もう役に立たなくなります。 司馬懿はこの真実を知っていたし、諸葛亮も当然それを知っていた。司馬懿は自分が知っていることを司馬懿も知っているとさらに確信した。想像してみてほしい。もし司馬懿が諸葛亮の意図を理解しておらず、本当に西城を占領していなかったら、諸葛亮が先に死に、司馬懿の死は少し遅れただけだっただろう。 概要: 一人は城壁の上に立ち、衣服をはためかせ、ピアノの音色が美しく響き渡ります。もう一人は城のふもとで馬に乗って立っており、その背後には15万人の軍隊が出撃する準備を整えています。短い対決の間に、二人は少なくとも千回は考えたが、一瞬にして二人のチャンネルがつながり、司馬懿は手を振って「撤退」と言った。 |
<<: 「羽扇と青いターバン」とは、具体的には諸葛亮や周瑜のことでしょうか?
>>: 諸葛亮はなぜ腹心の馬素を街亭の護衛に選んだのでしょうか?軍事力をコントロールし続けるために
推薦する
王毓の「秋に王長世に別れを告げる」:この詩は作者の本当の気持ちを率直かつ直接的に表現することから始まります。
王毓(650-676)、号は子安、江州龍門県(現在の山西省河津市)の出身。唐代の作家で、文仲子王通の...
「ホームレス」をどう鑑賞するか?著者は誰ですか?
ホームレス杜甫(唐代)孤独な天宝時代が過ぎ、庭も家も雑草に覆われてしまいました。私の村には100以上...
『紅楼夢』で平児はどのようにして王希峰が栄果屋敷を管理するのを手伝いましたか?
平児は『紅楼夢』の登場人物。王希峰の持参金係であり、賈廉の側室である。今日は、おもしろ歴史編集長が皆...
王安石の名詩:「桂枝郷・金陵郷愁」鑑賞
以下、興史編集長が王安石の『桂枝祥・金陵懐古』の原文と評価をお届けします。ご興味のある読者と興史編集...
『紅楼夢』の賈家の女中たちは何を着ているのでしょうか?
曹雪芹の『紅楼夢』に登場する賈家はもともと貴族の家系であり、その家系は隆盛を極めていた。 Inter...
もし諸葛亮が馬謖を使って街亭を守らなかったら、歴史は書き換えられただろうか?
三国が三つに分かれた後、当時の蜀の指導者である諸葛亮は、劉備の天下統一の野望をできるだけ早く実現する...
羅斌王の生涯における最高傑作は何ですか?千年にわたる驚異
今日は、Interesting Historyの編集者が羅斌王に関する記事をお届けします。ぜひお読み...
唐代の呂太一が書いた「庭竹頌」は竹の高貴な性質を称賛している。
「庭竹詩」は唐代の陸太一によって書かれたものです。次の興味深い歴史編集者が、関連するコンテンツを皆さ...
劉表は荊州を20年近く統治しました。彼のチームはどれほど豪華だったのでしょうか?
後漢時代の13の国の中で、荊州は世界で2番目に大きな国で、面積は益州に次ぐものでした。また、荊州管轄...
『新世界物語』第六章「方正」はどのような真実を表現しているのでしょうか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。それでは、『十碩心於・方正篇』第六章で表現...
『西遊記』の孫悟空は何人の人に平伏したのでしょうか?
『西遊記』の孫悟空は何人に平伏したのでしょうか?孫悟空自身が「私は善人であり、3人にだけ平伏した」と...
武術ドラマに2本一組で登場するあの夫婦刀!
| 冷兵器| 騎士道文化| 人文科学|中国5000年の歴史を振り返り、中国の冷兵器の謎を探り、古代冷...
水滸伝で十字架の丘で酒を飲みながら英雄を論じる話は何ですか?ウー・ソンにとって人生の転機となったのはなぜでしょうか?
中国の四大古典小説の一つである『水滸伝』は、その特徴的な登場人物とストーリー展開で、あなたに深い印象...
『三朝北孟慧編』第77巻の原文には何が記録されているか?
静康時代、第52巻。それは、静康二年旧暦正月19日に始まり、氷塵の26日に終わりました。その月の19...
なぜ孟達の死は諸葛亮と直接関係していると言われているのでしょうか?何が起こっているのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...