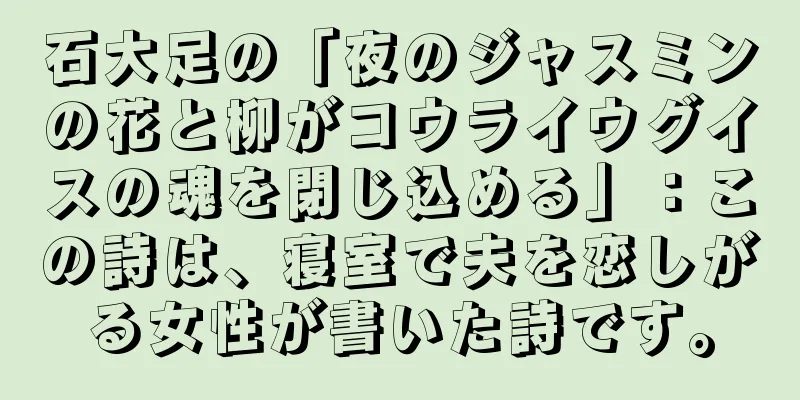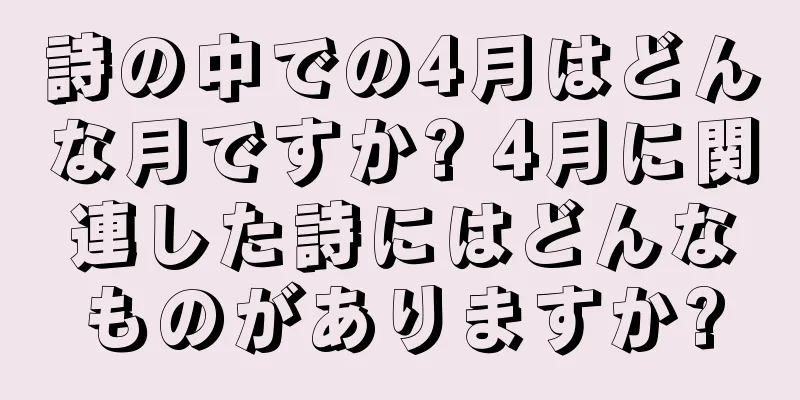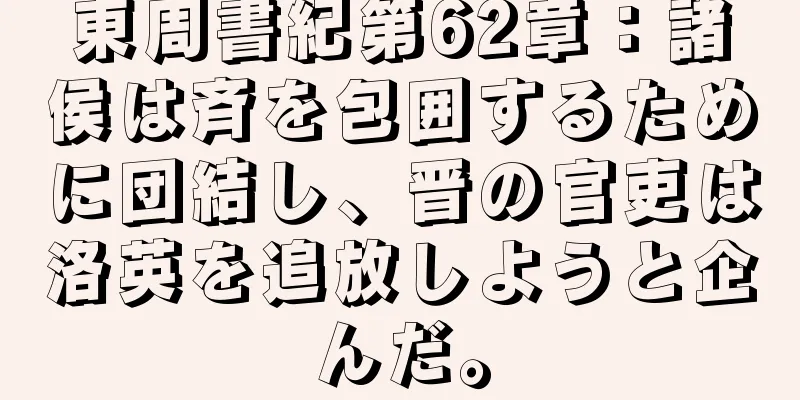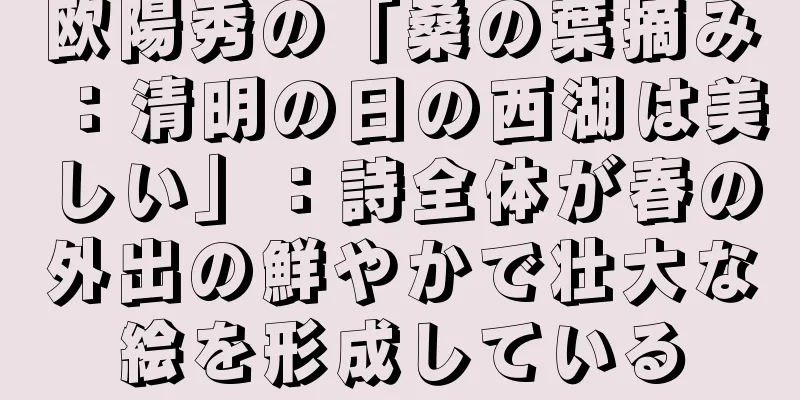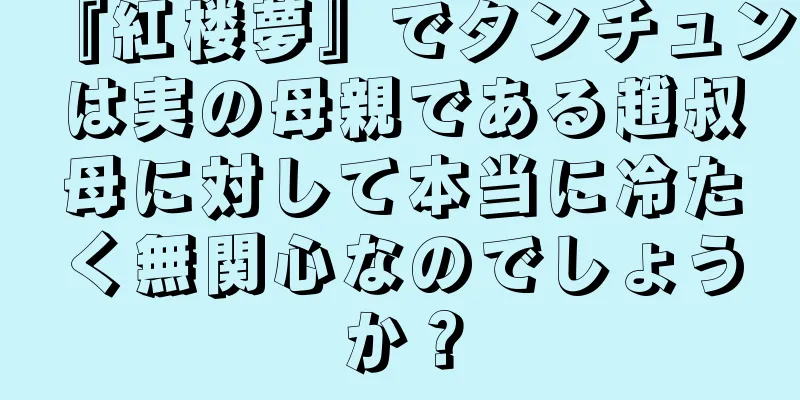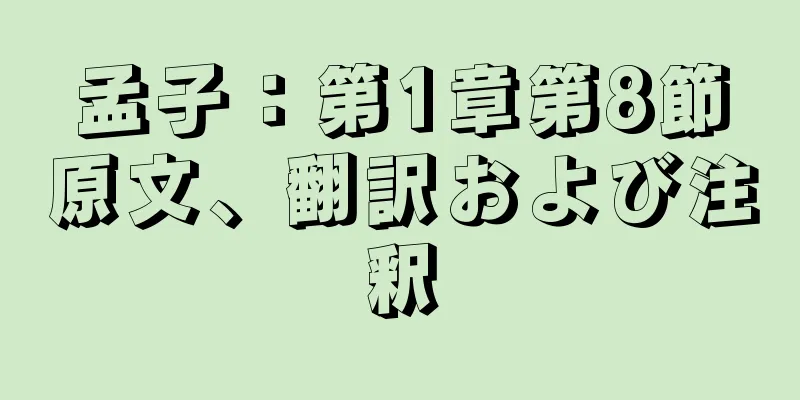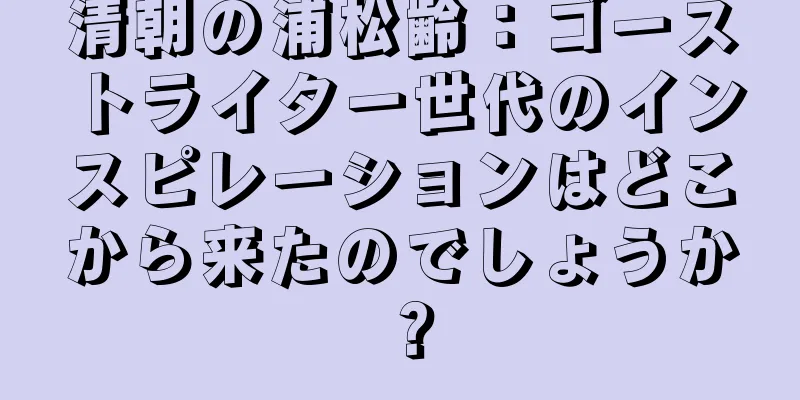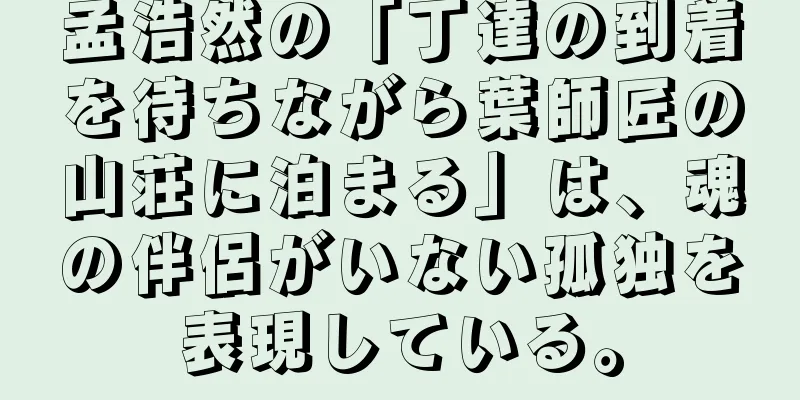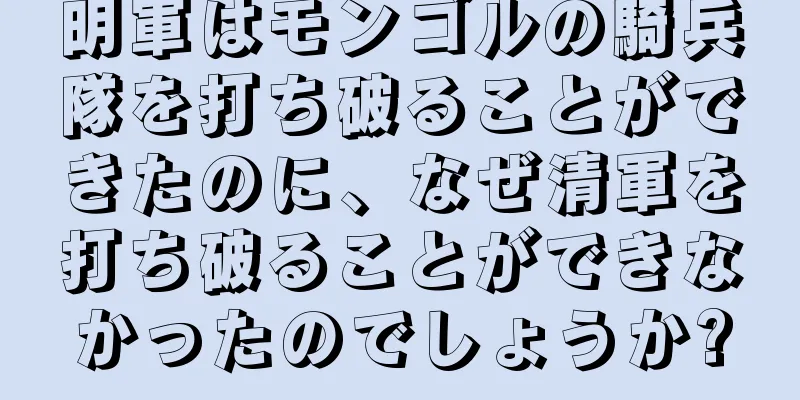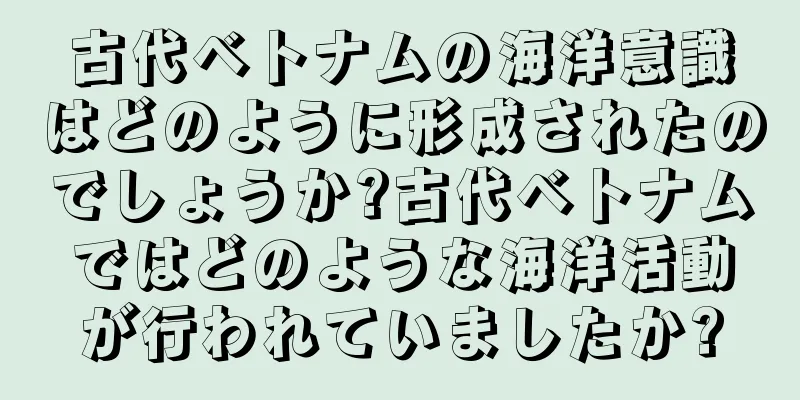徐庶の才能は程毓の10倍も優れていたのに、なぜ曹操に評価されなかったのでしょうか?
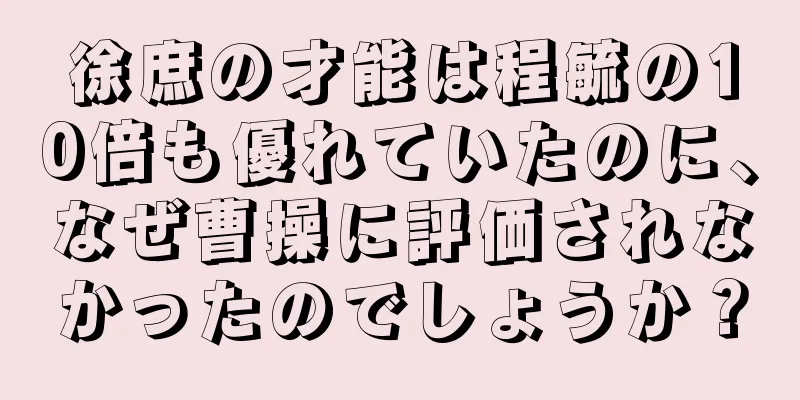
|
『三国志演義』は三国志の歴史を題材にした小説です。基本的には歴史の流れに沿っていますが、芸術的な効果を出すために細部が加工されており、徐庶などの登場人物の結末や人生までも変えています。正史によれば、徐庶はもともと劉備の顧問だった。母親が曹操の軍に捕らえられたため曹操に寝返らざるを得なかったが、生涯曹操のために計画を立てないと誓った。小説では、曹操配下の軍師である程毓に陥れられ、曹操に降伏せざるを得なかった。小説には、程毓がかつて曹操に徐庶の才能を褒め、徐庶は自分よりはるかに優れていると言ったと書かれています。しかし、徐庶が曹嬰に加わった後、彼の地位は非常に低く、程毓よりはるかに劣っていました。何が起こったのでしょうか?次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 三国志演義第36章では、段福という異名を持つ徐庶が、魏の将軍曹仁を破って劉備に寝返ったばかりで、その才能を存分に発揮した。しかし、喜ぶ者もいれば、心配する者もいた。曹操はその知らせを聞いて激怒した。この時、程宇が前に出て徐庶の経歴を詳しく説明した。曹操が「徐庶の才能はあなたの才能と比べてどうですか」と尋ねると、程宇は「禹の十倍です」と答えた。常に才能ある人材を集めることに熱心だった曹操は、徐庶を自分の配下に迎え入れたいと望み、程宇は計画を立て始めた。その後、程毓は徐庶の母を曹操の陣営に誘い込み、徐庶の母の名を騙って徐庶を劉備の元から呼び出した。しかし、程毓の10倍の才能があると賞賛されていたにもかかわらず、曹操からは評価されず、官職も程毓に及ばなかった。 1. 徐庶は曹操のために何も計画せず、曹操からいかなる報酬も受け取らないと決心した。 三国志演義では、徐庶は漢王朝を支える野望を抱いていた。徐庶が従いたかった主君は、漢王朝の裏切り者として非難された曹操ではなく、正統派を代表する劉備だった。孝行をするために曹操の陣営に来るしかなかったが、曹操のために働くことは望んでいなかった。母親が正義のために自殺したとき、彼の考えはさらに強くなった。想像してみて下さい。この時、曹操が彼にさらに高い官職を与えたとしても、彼はそれを受け入れるでしょうか? 答えは当然ノーです。 2. 徐叔の資質は程宇ほど良くない 程毓は早くから曹操に従いました。193年頃、曹操が兗州を占領し人材の募集を始めたとき、程毓は荀攸の推薦を受け、曹操に学者として採用されました。徐庶が曹操の陣営に誘い込まれたのは、すでに西暦208年のことであり、程毓は徐庶よりも15歳年上だったことになる。曹操が曹操の陣営に入った後、彼を程毓より上に置いたとしても、程毓は気にしなかったとしても、他の人はどうなのか?曹操は愚か者ではなかった。それどころか、非常に抜け目のない人物だった。彼は、一人の人物のせいで昔の大臣たちが自分と疎遠になることを許さなかった。そのため、たとえ徐庶の才能が程宇の10倍あったとしても、程宇は徐庶に直接高い地位を与えることはしなかった。 3. 徐淑の貢献は程宇ほど良くない 『三国志演義』では、程宇は曹操の最も重要な顧問の一人であり、曹操陣営の発展に多大な貢献をしました。優秀な人材を推薦する点では、郭嘉氏を推薦した。洞察力の面では、皇帝を利用して諸侯を統制することを曹操に進言したことがあるほか、皇帝を廃位して即位させないように進言したこともある。劉備の英雄的性格を早くから見抜いて曹操に殺害を進言したこともある。赤壁の戦いでは、黄蓋の偽りの降伏を真っ先に暴露した人物でもある。知恵の面では、関羽の一時降伏を促したり、劉備が袁紹に殺されそうになるような計画を立案したりした。しかし、徐庶が曹の陣営に到着した後、何も成し遂げられなかった。このような状況下では、曹操が徐庶の官職を程愈より高くすることは、なおさら不可能であった。 全体を分析すると、程毓は徐庶の才能は自分よりはるかに優れていると言ったものの、徐庶の官職は程毓よりはるかに劣っていたことが分かります。これは徐庶自身が曹操に仕えることを望まず、曹操の陣営で才能を発揮しなかったためです。これは曹操が昔の大臣たちに説明したことでもありました。 |
<<: 清朝は王子の教育を非常に重視していましたが、関連する教育制度はどのようなものだったのでしょうか?
>>: 諸葛亮は火攻めが得意だったが、なぜ蜀漢の未来を焼き尽くさなかったのか? ?
推薦する
唐代の詩人劉玉熙の「竹枝詩:山桃花紅花」の原文、翻訳、注釈、鑑賞
「竹枝歌 山桃花頭上」は唐代の詩人劉玉熙によって書かれたものです。次の『興味深い歴史』編集者が詳しく...
『紅楼夢』における王希峰の「身代わり計画」とは何を指しているのでしょうか?なぜ賢くないのか?
『紅楼夢』の中で、曹公は王希峰を「賢すぎて陰謀を企んでいる」と評しているが、それはまさにその通りだ。...
何卓の「鴛鴦の夢:酔って遅く起きる午後」:詩全体の描写は新鮮で表現は広い
何朱(1052-1125)は北宋時代の詩人。号は方慧、別名は何三嶼。またの名を何美子、号は青湖一老。...
李和の「野歌」は、怒りの中にある野性的で勇敢、そして自由奔放なイメージを表現している。
李和は、字を昌吉といい、中唐時代の浪漫詩人である。李白、李商隠とともに「唐の三里」の一人とされ、後世...
唐の玄宗皇帝の息子、李茂とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は李茂をどのように評価しているのでしょうか?
李茂は唐の玄宗皇帝の18番目の息子でした。彼の本名は李青であった。開元13年、寿王に任じられ、遠路益...
「エンターテインメント産業」を支えているのは誰でしょうか?古代の「芸能界」はどのようにして誕生したのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が古代の「娯楽界」の起源についての記事をお届けします。ぜひお読みください...
文京政権の内容は何ですか?文京政権ではどのような思想が採用されましたか?
文帝と景帝の治世は紀元前167年から紀元前141年まで続き、西漢の第5代皇帝である漢の文帝、劉衡と第...
劉備は張任の才能を高く評価していたが、なぜ諸葛亮は張任を処刑しようとしたのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝で、陸俊義の妻はなぜ家政婦と不倫をしたのですか?
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編集者は、一般に施...
古典文学の名作『夜船』:天文学部・雪霜全文
『夜船』は、明代末期から清代初期の作家・歴史家である張岱が著した百科事典である。この本は、あらゆる職...
本草綱目第8巻野生植物の本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
道教の創始者である老子は生涯で何人の弟子を持っていましたか?
老子といえば、彼が道教の創始者であり、道教思想の普及に多大な貢献をしたことは誰もが知っています。しか...
蜃気楼の紹介 蜃気楼の原因は何ですか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が蜃気楼につ...
秦以前の地理書:「山海経 大荒野東経」の原典と鑑賞
『山海経』は秦以前の時代の地理書である。この本の著者は不明である。現代の学者は、この本は一度に書かれ...
戦国時代後期の作品『韓非子』:八評全文と訳注
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...