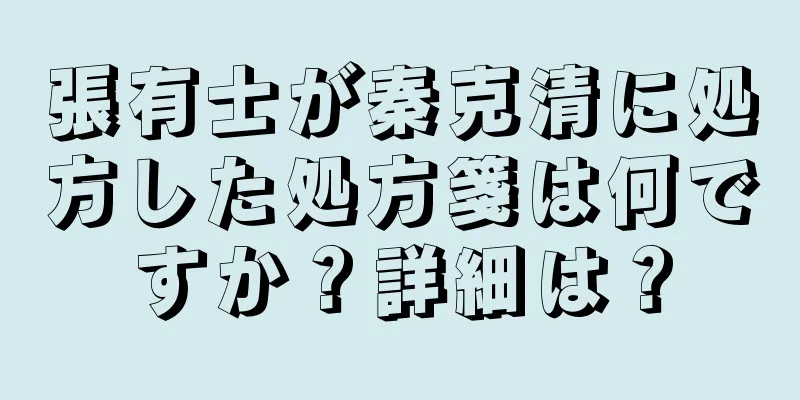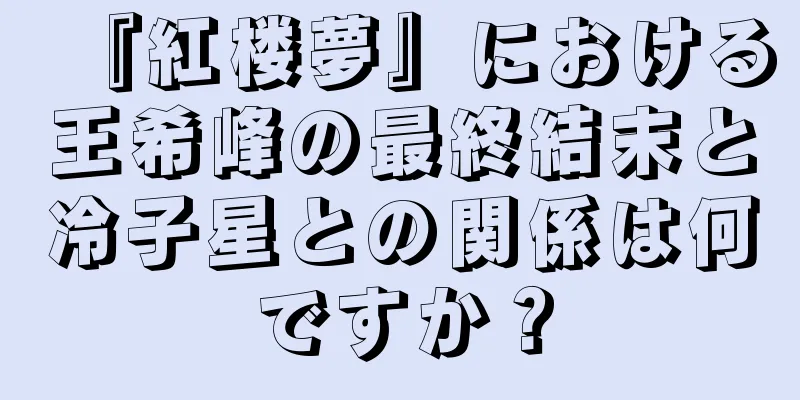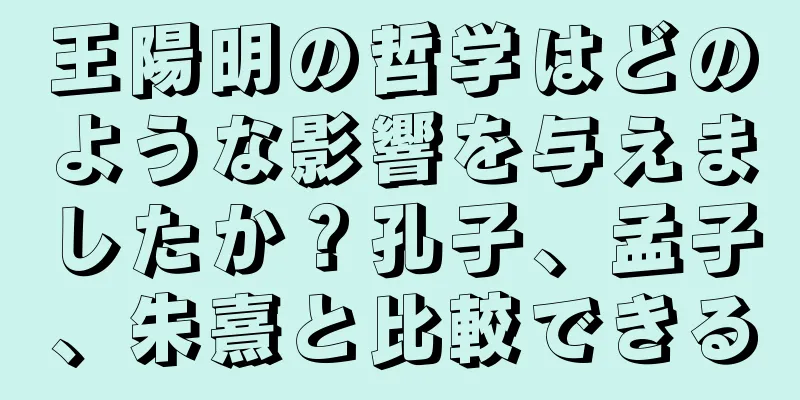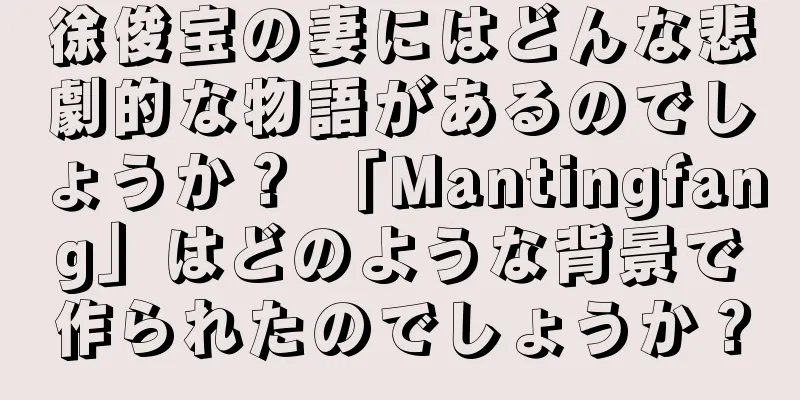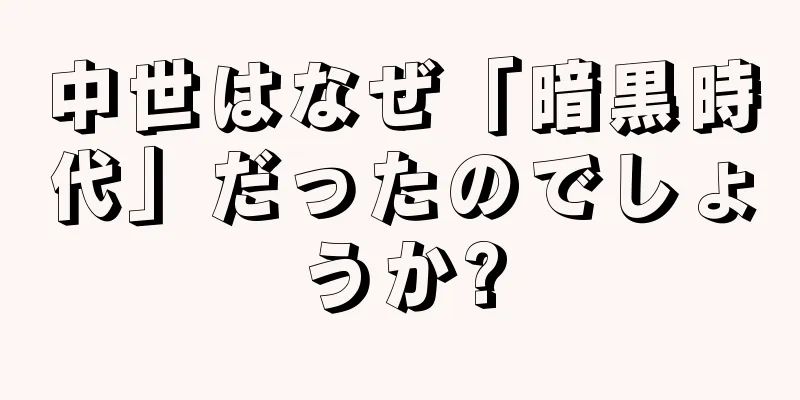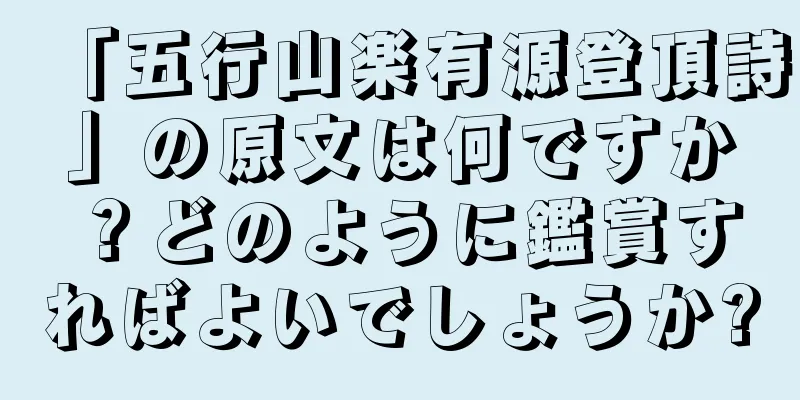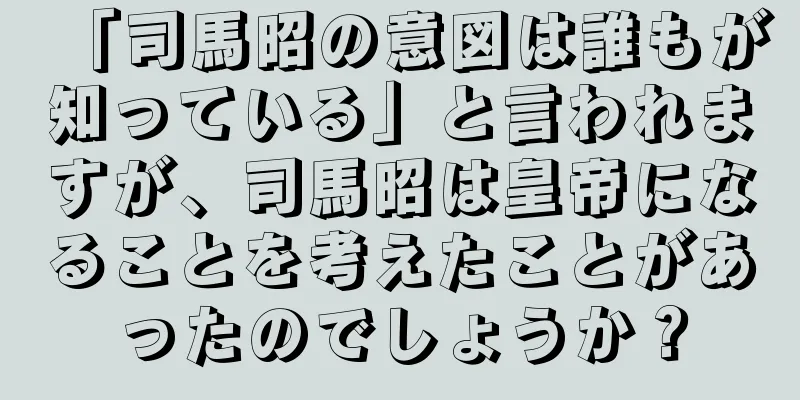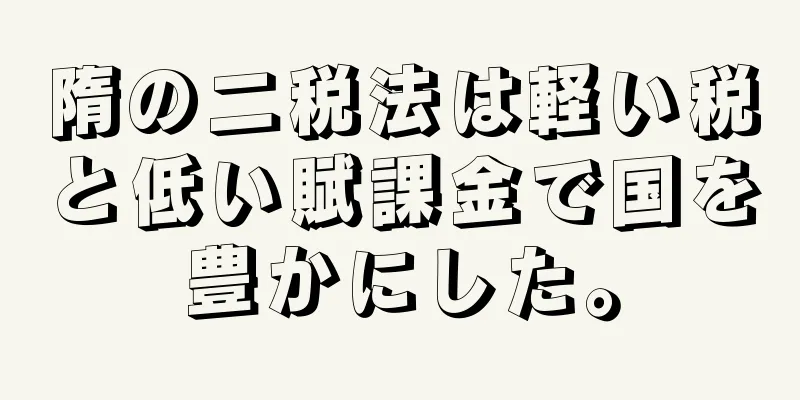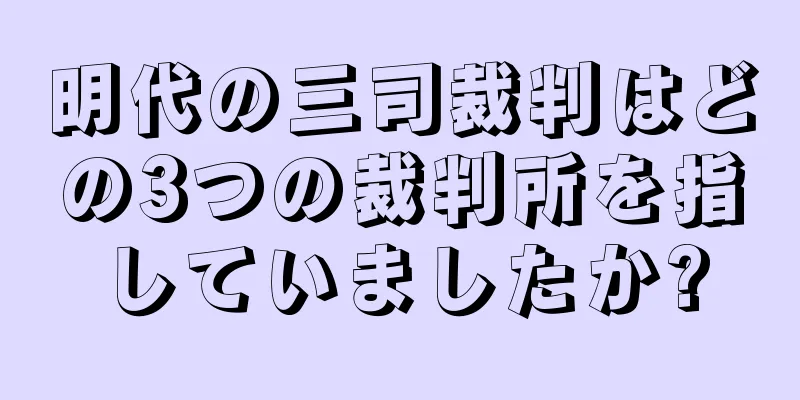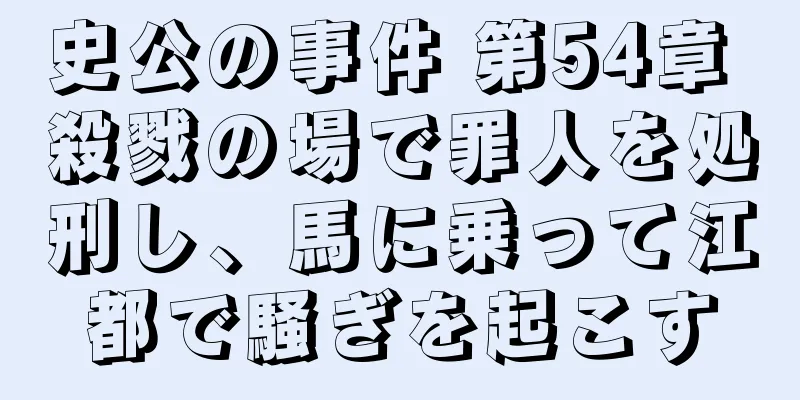宋代の廟の給与制度はどのようなものだったのでしょうか?宋代独特の制度
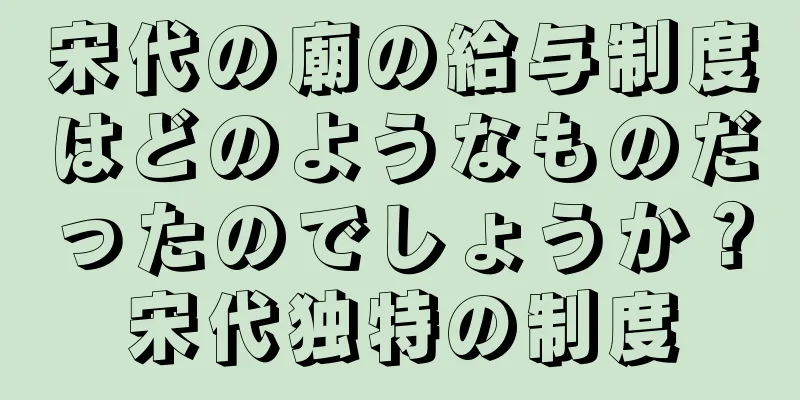
|
宋代の祠舎人給制度とは何ですか?祠舎人給制度は宋代特有の制度です。祠舎人給制度は唐代まで遡ることができますが、内容は全く異なります。家督給与制度は、当時の高官に与えられた特別な恩恵ともいえるが、賛否両論ある。下記の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しているので、ぜひ読んでみてください〜 祖廟の給与制度は宋代に公式に存在した制度である。隋・唐代には盛んにならず、明・清代には廃止された。宋代の有文政策の産物の一つである。この制度は宋代の真宗皇帝の時代に初めて確立されました。当初の意図は「老人と善人への依存」でした。高級官僚に特化した福祉政策でした。簡単に言えば、彼らは退職時に「退職金」を受け取りましたが、家に帰ることは許されず、閑職を与えられました。 南宋時代の文官集団は強力な存在であった。宋代の君主が官吏を好んだことはよく知られていた。そのため、多くの官職は数級の官吏に分かれていた。このようにして、文人は官吏になる機会が多く、その数も多かった。 祖先のお寺の給与制度が、変化をもたらしたいと願う一部の学者にとって人生の最低点だと考えられるなら、それは志のない人々やキャリアアップを追求できない人々にとって良い逃げ道となる。 なぜなら、「皇帝の祭司として仕える」ことは、彼にとって確かにより良い選択だったからです。皇帝に仕えることができないのなら、故郷に戻って講義をしたり、哲学について話したり、それについて書いたりしたほうが、国からいくらかのお金をもらえるからです。 宋代には「某寺の監」や「某宮寺の長官」といった肩書きがよくあったが、彼らは実際には宮寺の実務を掌握しているわけではなく、単にその肩書きを使って給料をもらっているだけだった。 初期には、このような待遇を受けることができたのは、主に朝廷の重要な役人、つまり中級・高級の文人であった。しかし、時代が進むにつれて、先祖代々の給与制度から「恩恵」を受ける役人の数は驚くほど増えました。 宋代の多くの有名な文人は「寺に祀られ」ていました。例えば、朱熹、陸游、辛其基などです。朱熹は有名な儒学者であり、陸游と辛其基は有名な作家です。 これは必然的に宋代の経済に大きな圧力をかけることになるため、歴史学界では一般的に否定的な評価となっている。 なぜなら、客観的に言えば、裁判所に対する経済的圧力に加えて、実際には多くの欠点があるからです。 (1)党員が祖先の廟を崇拝すると、党の災難がさらに深刻になる。 (2)腐敗した役人たちが皇帝を崇拝し、富を蓄積することが流行した。 (3)祖先を祀る寺院の義務を果たさず維持しなかったため、公的統治が悪化した。 (4)自制心の喪失と祖先の寺院の喪失は、 しかし、祖廟と俸禄制度に良い影響がなかったわけではない。それは宋代の文学と学問の発展に良い影響を与えた。 |
<<: 唐代の数多くの珍味の中でも、「渾楊莫胡」という料理はどのように調理されたのでしょうか?
>>: 周王朝の儀式と音楽のシステムの現れは何ですか?周王朝の祭祀と音楽制度の詳細な説明
推薦する
古代の皇帝はなぜ大きな扇風機の後ろに立たなければならなかったのでしょうか?古代の扇子の要件と重要性は何ですか?
古代の皇帝はなぜ背後に大きな扇子を設置しなければならなかったのでしょうか?古代の扇子の要件と意味は何...
宋代の女性は読み書きができたのでしょうか?はい、でも家でしか勉強できません。
ドラマを見るのが好きな友達は、時代劇「明蘭伝」を見たことがあるはずです!ドラマの中の趙麗穎は頭が良く...
太平広記・巻107・報復・強伯達の原作の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
医者の家に生まれ、弟子となり謙虚な師から学んだ葉天師の物語とは?
こちらは葉天師さんのプロフィールです。彼は清朝時代に生き、医学の深い伝統を持つ医師の家に生まれました...
『水滸伝』第39章の筋書きは何ですか、そしてそれをどのように評価すべきですか?
宋江は浚陽楼に来て、一人で飲食し、抗日詩を二首詠んだ。彼は子供の頃から古典と歴史を学び、成長するにつ...
杜甫の古詩「地遊」の本来の意味を理解する
古代詩「地球の片隅」時代: 唐代著者: 杜甫江漢江は山々に遮られ、荒地の一角となっている。年は違えど...
呉広はどうやって死んだのですか?呉広の死因が明らかに
秦二世の治世の元年(紀元前209年)、全国で農民反乱が勃発し、最終的に秦王朝は滅亡した。革命の火を最...
江魁の「小崇山嶺:傅旦洲紅梅」:この詩は梅の花について書くだけにとどまらない
蒋逵(1155-1221)は、字を堯章、号を白石道人、鄱陽(現在の江西省)に生まれた南宋時代の作家、...
明代史第350巻第193伝の原文
◎宦官2 ○ 李芳、馮宝、張静、陳増(陳馮、高懐)、梁勇(楊栄)、陳菊、王安、魏忠賢、王堤謙(李勇珍...
『紅楼夢』における王夫人のイメージとはどのようなものでしょうか?彼は本当に慈善的な人ですか?
王夫人は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公の一人です。これに非常に興味がある方のために、『Intere...
『山海経』には伝説上の獣「白澤」が登場しますか?白澤に関する伝説とは何ですか?
白澤は山海経に載っていますか?これは多くの読者が気になる質問です。一緒に学び、参考にしましょう。白澤...
『楊貴妃と別れ』を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
ヤンの娘を送る魏英武(唐代)一日は長くて悲しいですが、旅はゆったりとしています。その女性は今日、軽い...
黄耀師と洪気功のどちらが優れているか?黄耀師の武術の方が優れているか?
欧陽鋒は香港の武侠小説家金庸氏の代表作『射雁英雄伝』の一番の悪役で、「西毒」の異名を持ち、「五奇」の...
『紅楼夢』では、お茶は梅雪水で5年間煮沸して初めて一番美味しくなると書かれていますが、これは何の比喩でしょうか?
『紅楼夢』では、お茶は五年ものの梅の水で沸かして初めて一番美味しいとされています。これは何の比喩でし...
袁浩文の「突然の雨が蓮の葉を襲い、緑の葉が厚く陰を生やす」:「蓮子居慈花」は、この歌が歌詞と曲で構成されていると考えている。
袁浩文(1190年8月10日 - 1257年10月12日)、号は毓之、号は易山、通称は易山氏。彼は太...