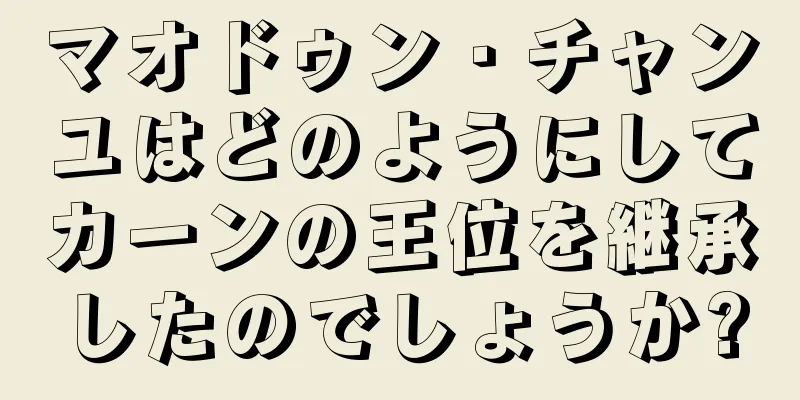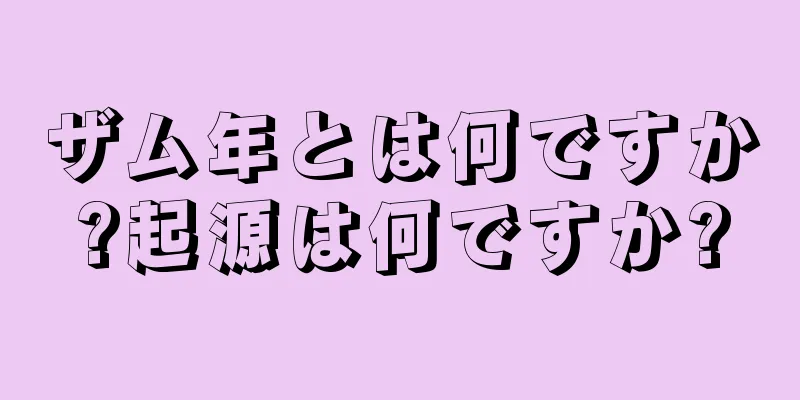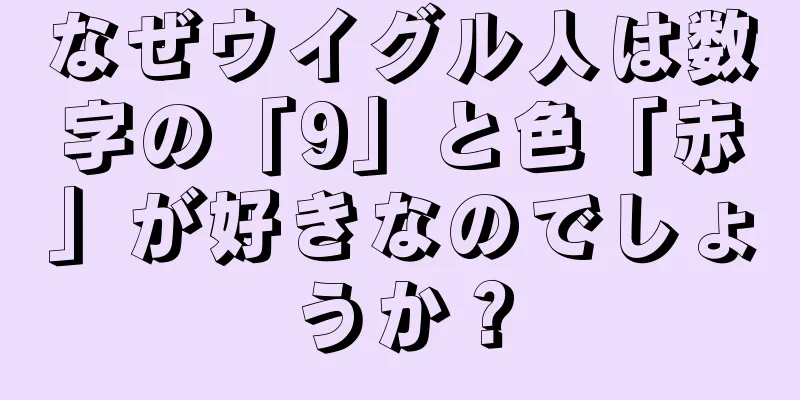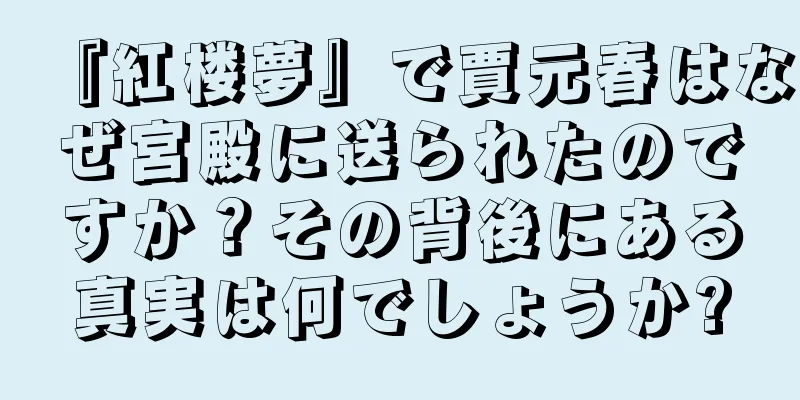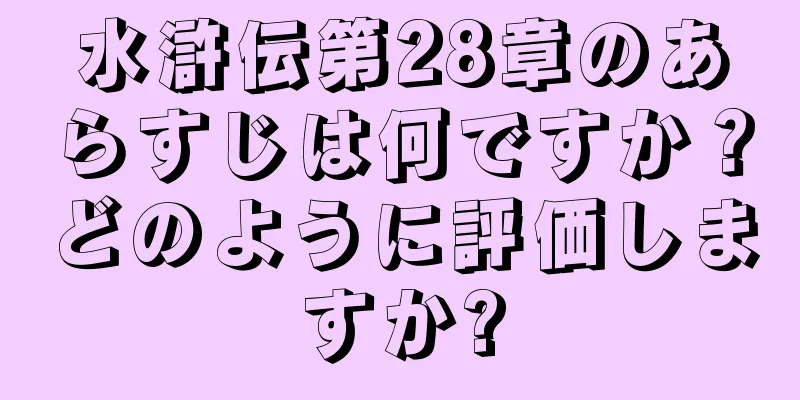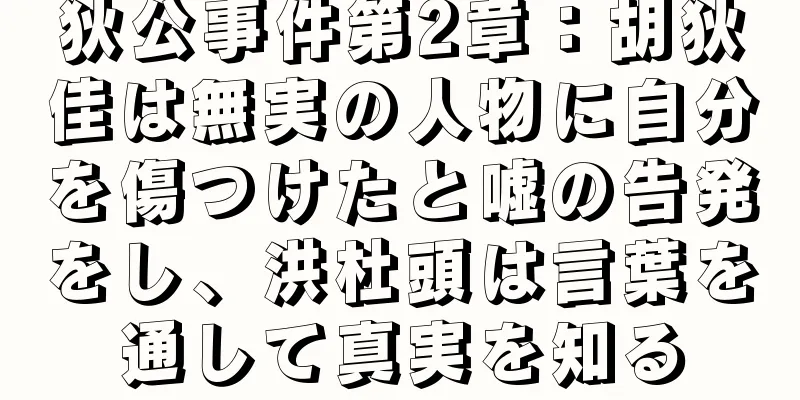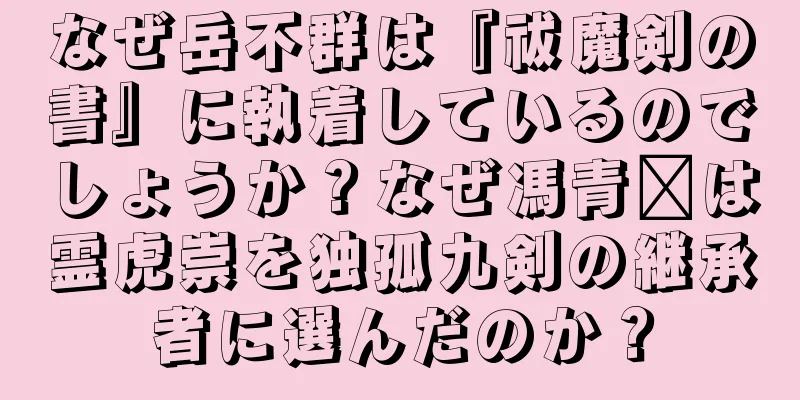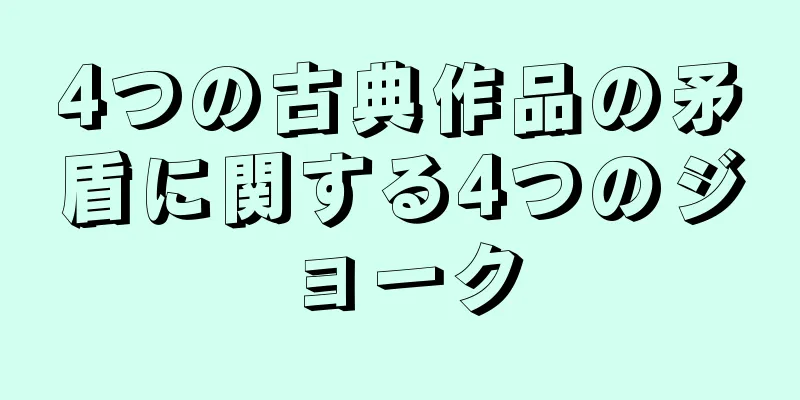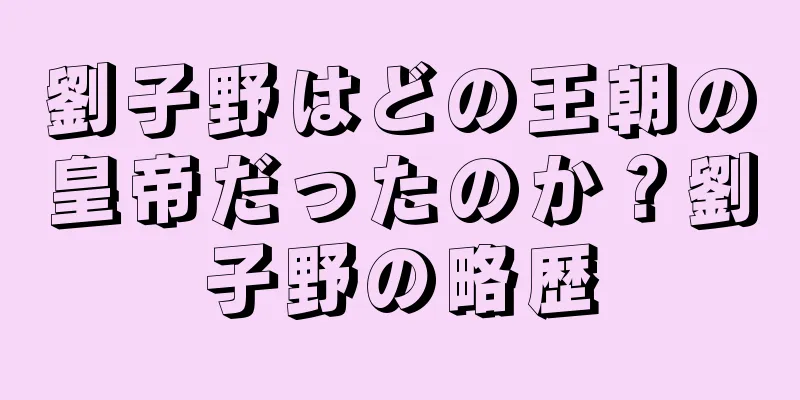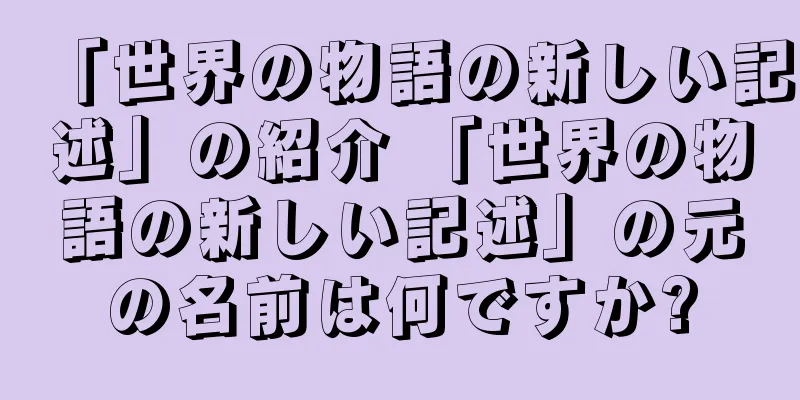私たちの髪と体は両親から受け継がれるものですが、古代の人たちは本当に一生髪を切らなかったのでしょうか?
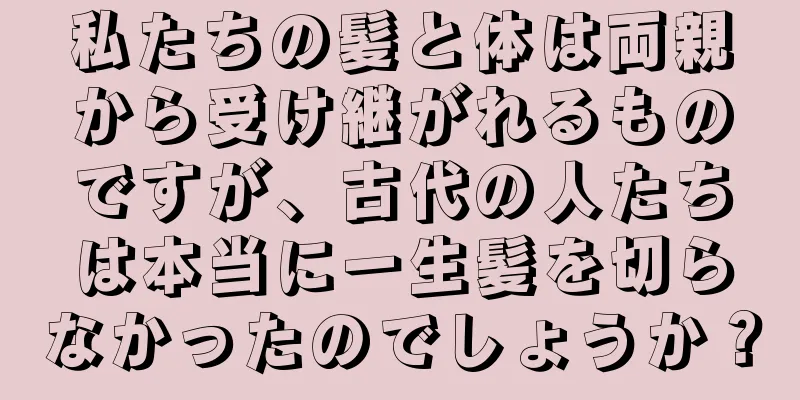
|
体毛は親から授かったもので、簡単には動かせないと言われています。では、古代人は本当に一生髪を切らなかったのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、読み続けてください〜 三国志演義を読んだことのある人なら誰でも、かつて曹操が軍を率いて麦畑を通り抜け、命令を出したことを知っている。「兵士は麦を傷つけてはならない。命令に違反した者は死刑に処せられる!」馬に乗っていた兵士たちは全員馬から降り、手を支えながら麦畑を歩いた。予想外に、曹操の馬は麦畑に突っ込んでしまい、曹操の侍従が呼び出されて罪を裁いた。侍従は春秋時代の暗示で応じた。「昔から、刑法は貴族に対しては適用されなかった。」 曹操は言った。「私が定めた法律を破って、部下を統率できるだろうか?しかし、軍の指揮官として、死ぬわけにはいかない。罰してほしい。」それから、彼は剣を取り、髪を切り落とし、地面に投げ捨てた。 昔から「体毛を傷つけてはいけない、これは聖人の教えだ」という諺があります。つまり、古代の人々は髪の毛は親から受け継がれるものだと信じており、髪の毛を無造作に切ることは凶悪な犯罪であるだけでなく、親孝行のしるしでもあるのです。封建社会の政治家として、曹操は首と引き換えに髪を切り、自分自身に厳格であったことは本当に称賛に値する。 昔、私の国には「散髪」という言葉がなかったので、男性も女性も髪は長かったのですが、髪の結び方が違っていました。理髪と美容は古代から存在してきました。伝説によれば、伏羲の時代に人々は髪を束ねるようになり、髪を下ろさなくなったそうです。髪型に関して言えば、漢民族は髪を下ろしたり、切ったり、編んだりする点で少数民族とは異なります。 『詩経・小夜・蔡録』には、青菜を摘みながら夫の帰りを思いながら「歌を奏でて別れを告げる」という女性の姿が描かれている。つまり、私の髪はカールしていてふわふわしているので、家に帰って髪を洗って櫛でとかさないといけないのです。 『左伝・熙公二十二年』には「我が王は侍女にタオルと櫛を持たせて髪を結わせた」と記録されている。これは古代貴族には髪を梳くための特別な人がいたことを示している。春秋時代の散髪に関する記録。 漢の時代には、髪を切ることで生計を立てる職人がいました。 南北朝時代、南梁の貴族の子弟は皆、頭を剃り、顔を剃りました。その頃、理髪業はすでに非常に発達しており、プロの理髪師も現れました。 「散髪」という言葉は、宋代の文献に初めて登場しました。朱熹は『詩経・周宋・梁書』の解説にある「その喩えは櫛」という文章で、「櫛は散髪道具である」と説明しています。 「散髪」という言葉は、宋代の文献に初めて登場しました。朱熹は『詩経・周宋・梁書』の注釈にある「その喩えは櫛である」という文章で、「櫛は散髪道具である。 この頃は理容業界が比較的発達しており、理容道具の製造を専門とする工房もありました。当時、理髪師には「戴昭」と呼ばれる特別な称号がありました。その後、徐々に技術や産業として発展していきました。宋代には、民間の理髪業はすでにある程度の規模にまで発展していました。当時、理容師は店だけでなく組合も持っており、理容組合は 1940 年代まで存続していました。 宋鴻邁著『易軒志易』第12巻「成都の毛抜き師」には、次のように記されている。「鄭和の初め、成都に毛抜き師がいた。彼は民衆の間を旅しており、妻は一人で暮らしていた。髭を生やした道士が彼のもとにやって来て、髭を抜くように頼んだ。彼は前金として200元を渡した。」 宋代の張端易の『桂二記』には、秦檜が毛抜き工を呼んで髪をとかし、毛抜き工に銭貨二枚に相当する五千元を報酬として与えたという記録もある。 宋周密の『武林九氏協会』には、当時、臨安(杭州)に「洗髪協会」があったことが記録されている。 元朝と明朝の時代には、人々が髪を切ることはより一般的でした。清朝では、長期統治を実現するために、満州族の貴族はすべての男性に頭を剃り、三つ編みをすることを強制しました。「頭は残しても髪は残さず、髪は残しても頭は残さない」人々は額の上の毛を剃るしかなくなり、理髪産業はかつてないほど発展しました。当時は、どこにでも床屋の看板があり、床屋は鉄のハサミを持って路上で商品を売りながら人々の髪を切っていた。 王朝によって髪の手入れや衛生方法が異なっていたため、名前も異なっていました。明代には「頭を梳く」、清代には「頭を剃る」といい、「頭を切る」「頭を押さえる」などの呼び名もありました。 |
<<: 古代人はどのように狩りをしたのでしょうか?古代の狩猟道具は何ですか?
>>: 古代人はなぜ翡翠を身に着けることを好んだのでしょうか?翡翠の文化は長い歴史を持つ
推薦する
荘公14年の儒教古典『古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
元王朝が崩壊した主な原因は何でしたか?支配グループは権力をめぐって争っている。
元王朝の崩壊の主な原因は、政治的暗黒、民族差別、政治的抑圧政策であった。支配集団は、集団内の権力闘争...
なぜ孝荘皇太后とその息子順治帝の関係は悪化していったのでしょうか?
孝荘文皇后、または私たちがよく呼ぶ孝荘皇太后は、天明、天聡、崇徳、順治、康熙の5人の皇帝の治世中に生...
漢の安帝はどのようにして皇帝になったのですか?彼の治世中にどんな大きな出来事が起こりましたか?
漢の安帝は劉虎と名付けられました。彼の祖父は漢の章帝劉荘、祖母は宋妃でした。宋妃は劉青という息子を産...
「西然迪竹庭」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
西蘭地竹閣孟浩然(唐代)私は生涯を通じてあなた方二人、三人と深い友情を育んできました。私たちは皆、高...
『紅楼夢』の王希峰はなぜ満州語と中国語の両方に堪能なのでしょうか?
王希峰は、中国の古典小説『紅楼夢』の主要登場人物で、馮莎子とも呼ばれ、『紅楼夢』の主な舞台である賈家...
中国ではなぜ周の時代から白を喪服として使うようになったのでしょうか?白い喪服
喪服とは、故人と親しい関係にある親族が葬儀の際に着用するさまざまな衣服を指します。若い世代が年長者を...
実際の歴史では、周瑜の方が強かったのでしょうか、それとも魯迅の方が少しだけ優れていたのでしょうか?
三国時代の東呉には数人の知事がいたが、その中で最も権力を握っていたのは周瑜と陸遜だった。周瑜と陸遜に...
『紅楼夢』の賈家における黎馬の地位はどのくらいですか?
ナニー・ライは『紅楼夢』の中では非凡な人物だ。次はInteresting Historyの編集者が詳...
なぜ陳寿は張郃の将軍を過大評価していると考えて、張郃に対してそれほど悪い印象を持っていたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
後漢書第49巻の王充、王扶忠、長同の伝記原文
王充(本名は鍾仁)は会稽の上虞の出身で、先祖は衛君の元城から移住してきた。彼は幼い頃に孤児となり、村...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第50巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
太平広記・巻13・神仙・陰桂の具体的な内容は何ですか?どのように翻訳しますか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
籐の鎧を着た兵士は歴史上に本当に存在したのでしょうか?籐甲冑兵とはどんな兵種でしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が歴史上の籐の鎧を着た兵士についての記事をお届...
周の平王が東進した後、なぜ東周王朝が長く続いたのでしょうか?
周王朝は中国の第三王朝です。西周と東周は合わせて791年間存続しましたが、東周だけでも514年間続き...