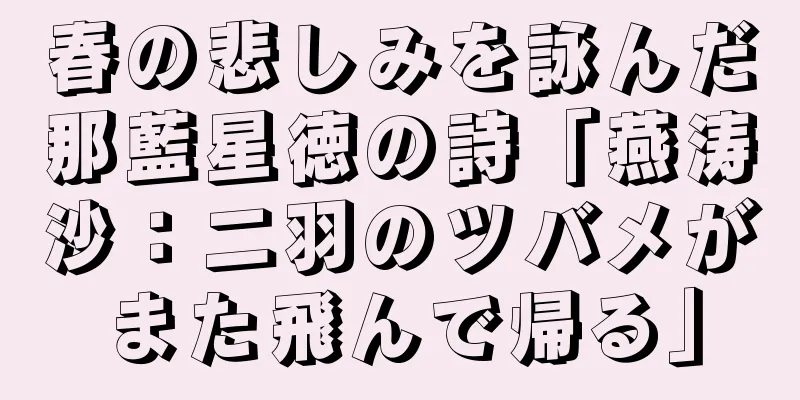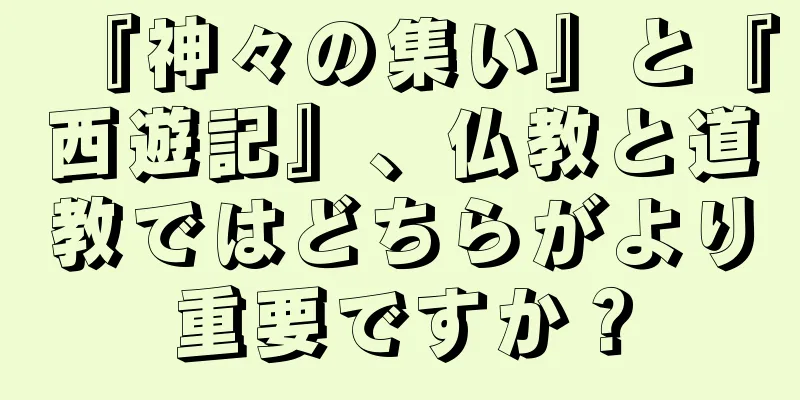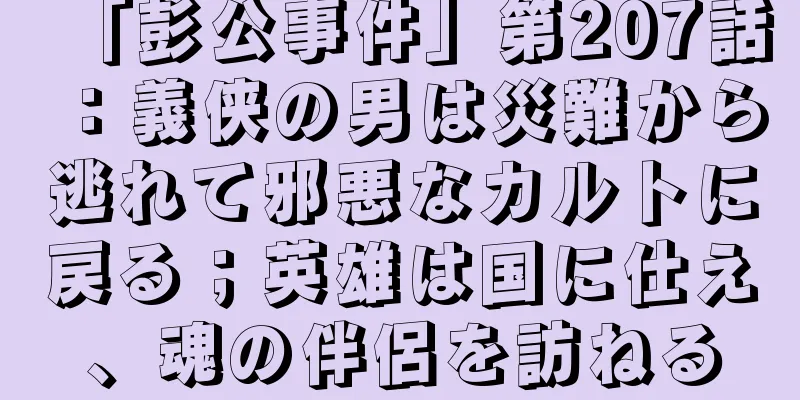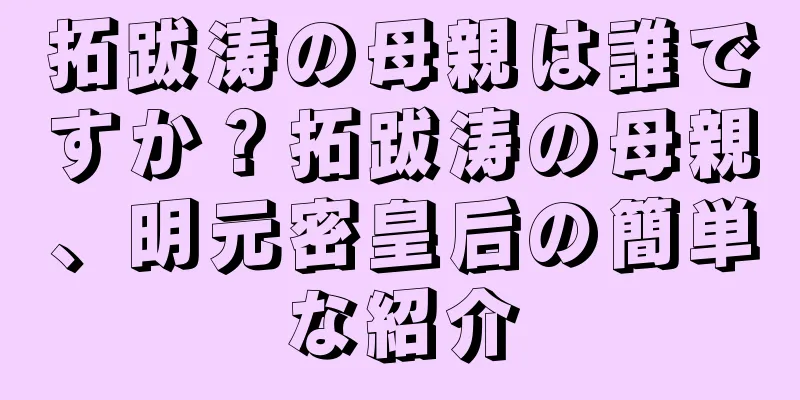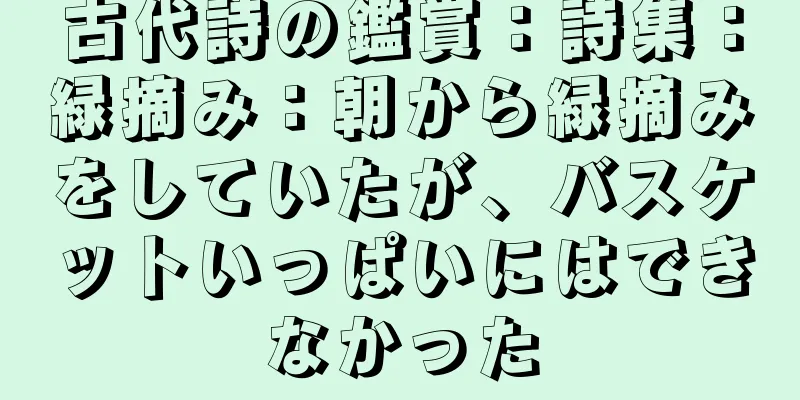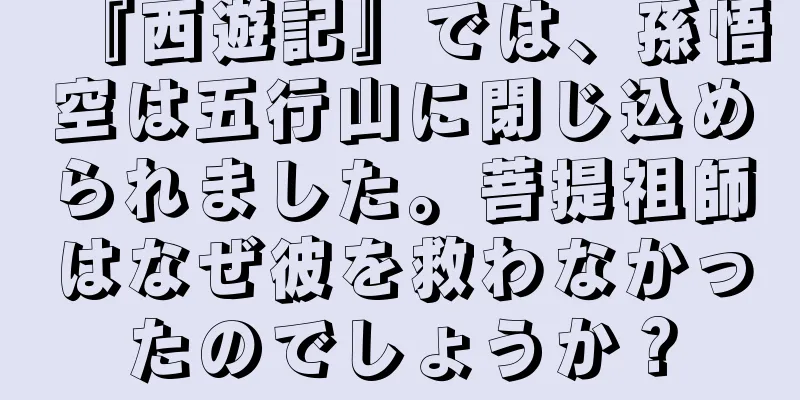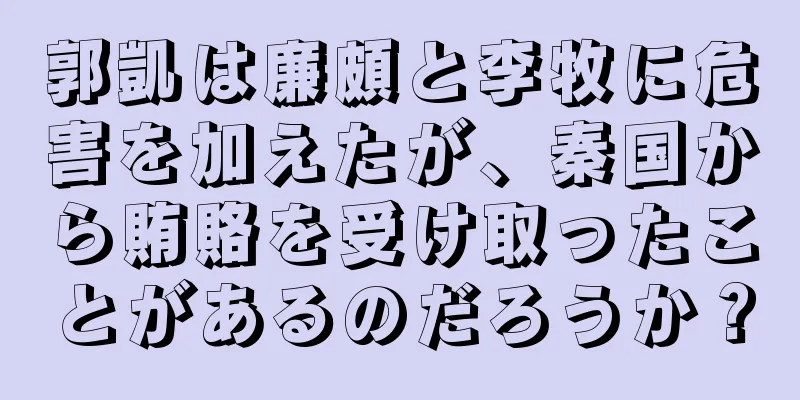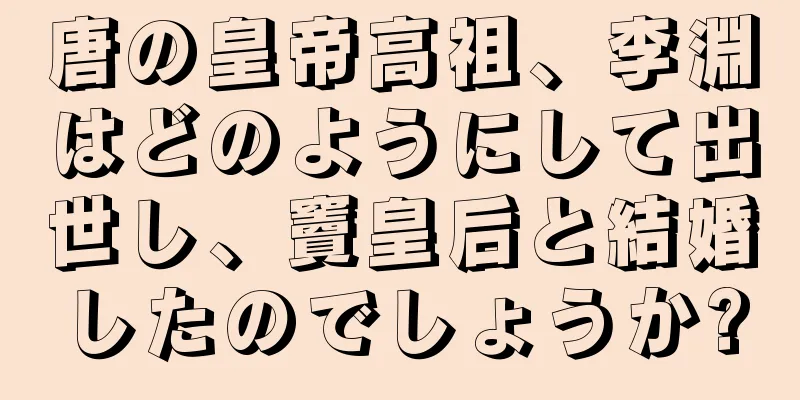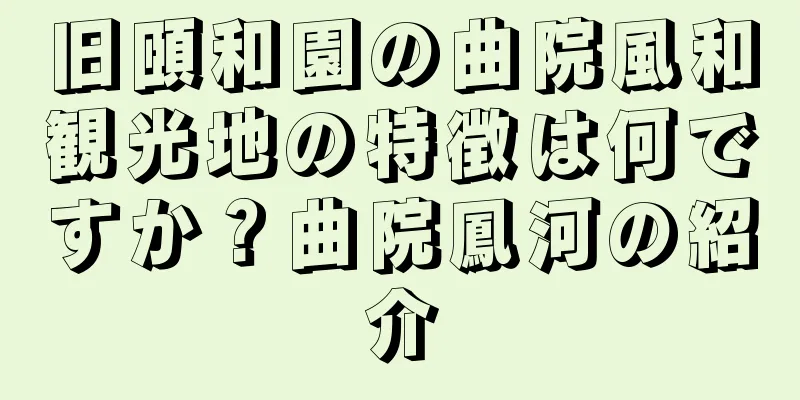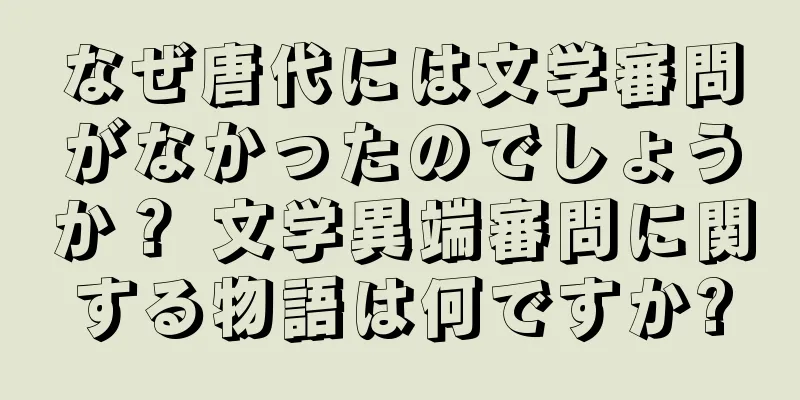許褚はなぜ馬超と戦うときに鎧を全部脱いだのですか?
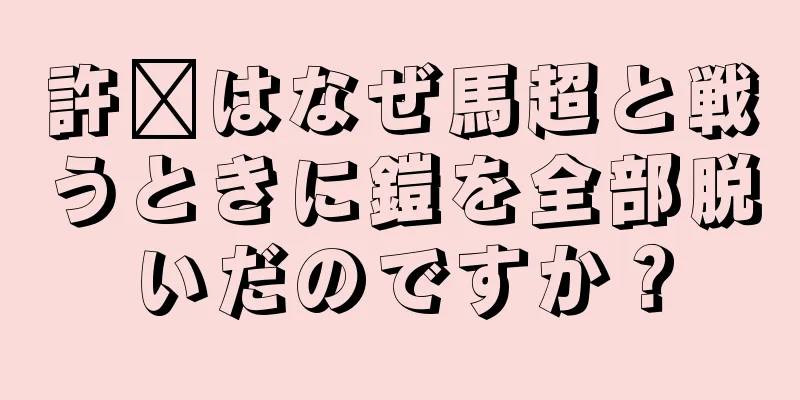
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、許褚と馬超について詳しく紹介しますので、見てみましょう! 三国志演義では、馬超が潼関で曹操を殺し、髭を切り、袈裟を捨てるように強制した。この状況で、彼の最も強力な将軍である許褚が登場し、馬超とスリリングな決闘を繰り広げました。この戦いについて馬超は「許褚ほど戦場で猛々しい者は見たことがない。本当に虎の道化だ」と評した。両者の決闘には興味深い点がある。許褚が全身の甲冑を脱いだのだ。なぜ彼はそうしたのだろうか? 1. 裸で馬超と戦った許褚。 許褚と馬超の決闘の結果、乱闘中に許褚の腕に二本の矢が命中した。後に陸遜は、鎧を脱いだのが自分のせいだから当然の報いだったとコメントした。それでは三国志演義の記述を見て、許褚と馬超の決闘を見て、彼が鎧を脱いだ本当の理由を見つけてみましょう。 潼関の戦いで馬超は曹操の軍を破り、彼らを混乱に陥れて敗走させたが、ライバルの許褚とも遭遇した。徐褚は「虎狂い」として知られ、曹操軍最強の戦士であることを知った彼は、彼を見るとすぐに避けたいと思った。許褚が屈服せず、曹操の挑発を受けて宣戦布告し、馬超に決闘を挑むとは誰が予想しただろうか。馬超は激怒し、許褚に決闘を申し込んだ。 この戦いでは、両軍は3段階に分かれて200ラウンド以上戦いました。最初のステージは最初の約 100 ラウンドで、その間の結果は互角でした。この時、二人の馬は疲れていたので、馬を乗り換えて再び戦いました。第二段階は100ラウンド以上続きました。許褚は陣地に戻り、鎧を脱ぎ、再び裸で剣を持って馬超と戦いました。 第3ステージは比較的短く、両チームが戦ったのはわずか30ラウンドでした。馬超は徐褚のナイフを避けた後、馬超の槍で心臓を刺された。徐褚は剣を投げ捨て、馬超の槍を掴んだ。その後の戦いで許褚は槍の柄を折り、両者はそれぞれ槍の柄の半分を持ち、馬上で戦った。曹操は許褚が危険にさらされることを恐れ、夏侯淵と曹洪を救援に派遣したが、乱闘が起こった。馬超と許褚の決闘は軍の混乱により中断され、許褚は負傷して戻ってきた。 2. 徐褚は鎧を脱ぐしかなかった。 馬超と許褚の決闘を見ると、両者の違いが分かります。馬超は常に冷静沈着で、名将らしい態度を保っていた。彼は戦闘中も端正な風貌を保ち、「金馬超」の名声に恥じない活躍を見せた。対照的に、許褚は非常に残酷で凶暴であり、勝つためには何でもするという印象を与えます。 実は、この違いは両者の武術的特徴によって生じているのです。馬超は技術に優れた将軍で、槍の腕前が優れていたため、敵は防御するのが困難でした。許褚は、二頭の牛を後ろに引っ張る力と、敵を倒す剣術を頼りにした強力な将軍でした。したがって、両者が戦ったとき、それぞれが勝利を目指して自らの強みを生かした。 徐褚は行動を起こすとすぐに、全力を尽くし、その力を最大限に発揮した。しかし、許褚が驚いたことに、馬超は許褚の強さに圧倒されなかった。この状況は双方の馬の状態から見て取れます。両馬とも再び戦うには疲れきっており、交代しなければなりません。これは、許褚と馬超の力の大部分が馬に伝わり、馬を圧倒したことを示しています。 しかし、第2段階になると状況は変化しました。この段階では、両者の遭遇回数は第 1 段階と同程度でしたが、双方の馬は第 1 段階と同じ状況を経験しませんでした。これは、第 2 段階では許褚の力が衰え始めており、この状況が馬に反映されていたことを示しています。 この場合、許褚が鎧を脱いで戦闘隊形に戻った理由が明らかになりました。つまり、許褚は長い間攻撃に失敗した後、体力が衰え始めたのです。馬超は技術系の将軍なので、許褚と比べて体力面で優位に立っています。許褚は馬超を抑えるために完全に力に頼っていました。体力が衰えた今、馬超と戦うことは不可能だと感じています。 馬超を倒すために、許褚は死ぬまで戦うことを決意した。彼は鎧を脱ぎ捨て、最後の力を振り絞って戦いに挑んだ。戦いの最終段階で、徐褚はすでに危険にさらされていました。馬超との最後の戦いでは、自ら武器を手放し、銃をめぐって馬超と戦うという、完全にパニックに陥った演技だった。馬超に抵抗できるなら、誰が武器を捨てるだろうか? 馬超の武器を破壊した後、許褚は力を使い果たした。二人の男はまるで子供の遊びのように銃身半分で戦った。この状況では、誰も相手に致命的なダメージを与えることはできません。このような状況でも、曹操は許褚が危険にさらされているのではないかと恐れ、彼を救出するために人を派遣しました。これは、曹操にとって許褚の状況がいかに危機的であったかを示しています。 乱闘の中で曹の軍は敗北し、いつも勇敢だった許褚も敵に抵抗する勇気がなく、陣地へ逃げ帰らざるを得なかった。この間、許褚も腕に二本の矢を受けて負傷した。この矢傷は許褚にとっては軽傷とみなされるべきだったが、それ以降許褚が馬超と単独で戦う姿は見られなかった。馬超は一日中曹操の陣営の周りで自分の力を誇示していたため、曹操は激怒し、「馬が死ななければ、私には埋葬する場所がない」と言った。 結論: 潼関の戦いでは、許褚は裸で馬超と戦った。このスリリングな戦いの中で、馬超は常にきちんとした態度を保ち、名将のように見えたので、許褚が裸で剣を持っているイメージはさらに衝撃的なものになりました。しかし、許褚は馬超と戦うために鎧を脱いだ。それは選択の余地がなかったからだ。状況が非常に不利であり、そうでなければ戦い続けることができなかったからだ。 この戦いでは、技術志向の将軍である馬超が、権力志向の将軍である許褚に対して、権力の交換において優位に立っています。両者の戦いが長引くにつれ、許褚の体力は急激に低下し、勝利のバランスは徐々に馬超に傾いていった。勝つために、許褚は鎧を脱ぎ捨て、死ぬまで戦った。それでも、彼の状況は極めて危機的であり、曹操の目には、助けるために人を派遣する必要があると映った。結局、許褚は負傷して逃げ去り、二度と馬超と戦う勇気はなかった。 |
<<: 官渡の戦いで劉表が曹操を攻撃していたらどうなっていたでしょうか?
>>: 長阪坡の戦いで、関羽と張飛は趙雲のように七回出入りできたでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』では、賈宝玉と林黛玉の恋愛が明かされないと言われているのはなぜですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
唐の皇帝・中宗李献は、即位後、退位を余儀なくされた母・武則天をどのように扱ったでしょうか?
歴史上、皇帝になった女性は複数いるが、武則天は後世に認められた唯一の女性皇帝である。後世の彼女に対す...
グアルジア族の分布 グアルジア族の主な居住地の紹介
グァエルジア族の分布:グァエルジア族は満州族の姓であり、8つの主要な満州族の姓の1つです。グワルジア...
『紅楼夢』でなぜ宝玉は宝仔を怒らせたのですか?彼は何をしましたか?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。賈宝玉と聞いて何を思い浮かべますか?清虚寺での祈祷会の...
黄小麦の「清明湖南春夜月」:長江の南、楚、湖南を旅する人のために書かれた詩で、春の去りゆく悲しみと別れを惜しむ気持ちを表現している。
黄小麦(生没年不詳)は南宋代の詩人で、号は徳夫、号は雪舟。ある人は、彼は「並外れた才能、溢れる雄弁、...
『浙桂嶺臥鹿臥』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】鎮元時代には学者があまりおらず、見て回っているとあっという間に時間が過ぎてしまいました...
漢民族の人口 漢民族の分布地域
漢民族の人口は約 13 億人で、世界の総人口の 19% を占めています。漢民族は世界で最も人口の多い...
『蘇太朗古』の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
スータイ古代古い庭園の荒れたテラスの柳の木々は青々と茂り⑵、蓮の歌の澄んだ歌声は春よりも美しい⑶。今...
曹振勇の経歴は何ですか?曹振勇はどのようにして亡くなったのですか?
曹振勇について曹振勇(1755-1835)、号は礼勝、号は易佳、字は智子。 46年(1781年)、進...
鏡の中の花 第67話:若く才能のある卞夫人が師匠を訪ね、黄門おじさんが嘆願書を提出
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
賈懿の作品は文帝に高く評価されていたにもかかわらず、なぜ文帝に雇われなかったのでしょうか?
『賈懿の官吏不成事』は北宋時代の有名な政治家であり作家であった欧陽秀によって書かれた。この記事におけ...
清朝のどのような官僚組織が皇帝から金銭を差し控えようとしたのでしょうか?
清朝の歴史には数え切れないほどの汚職官僚がいた。最も汚職にまみれた官僚は、人民の金を横領するだけだっ...
「四川の僧侶ジュンのピアノ演奏を聞く」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】牛竹の西河の夜空は青く雲ひとつない。私は船に乗って秋の月を眺めながら、謝将軍のことばか...
徐庶の伝記:三国時代の戦略家、徐庶の生涯の紹介
徐叔(生没年不詳)、号は元之、潘川県長沙県(現在の河南省昌歌市の東)の出身。三国時代の蜀漢の人物。後...
王長齢の『夫峰師に代わる答辞』:作品全体が優れた辺境詩である
王長陵(698-757)は、名を少伯といい、唐代の官僚であり、有名な辺境の詩人であった。彼は李白、高...