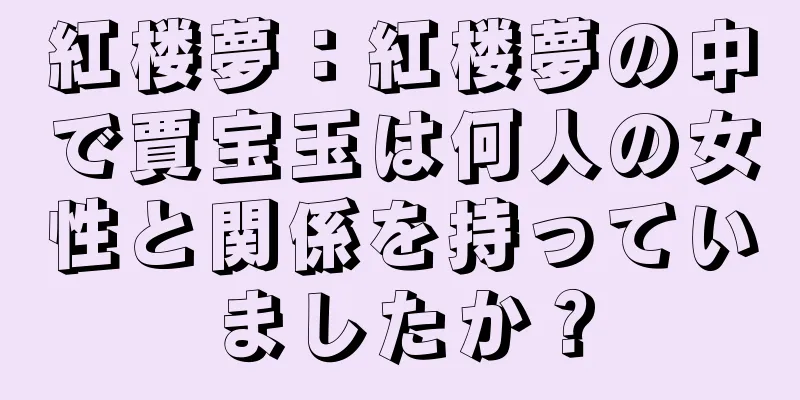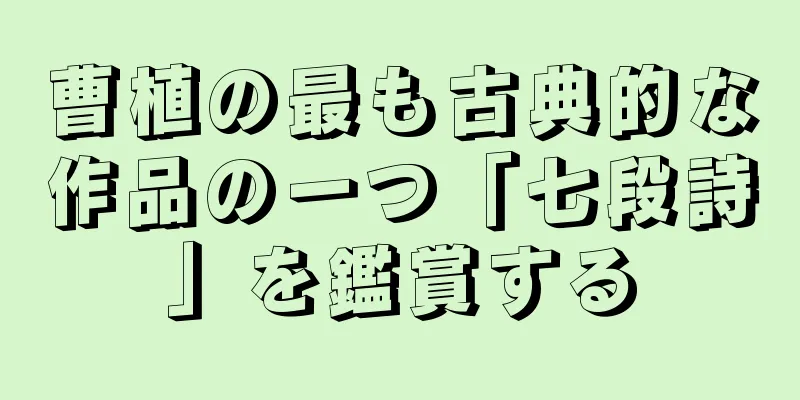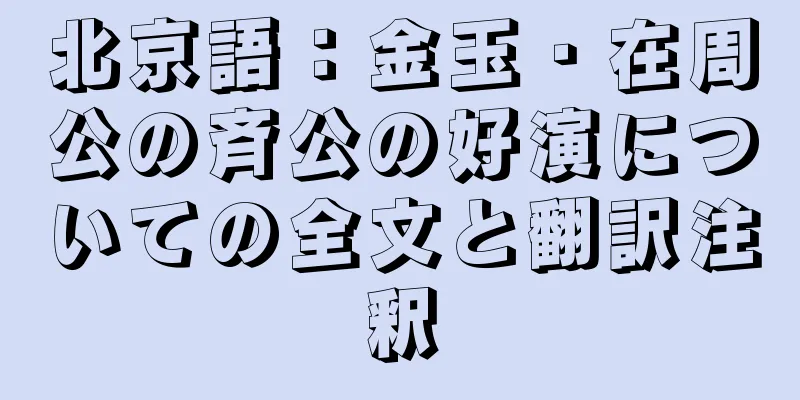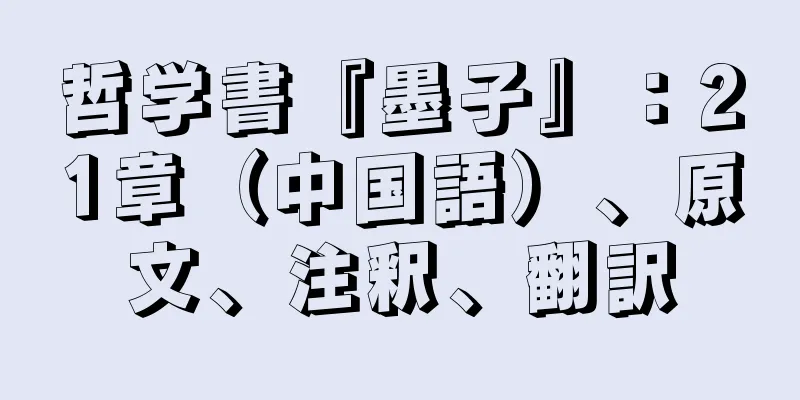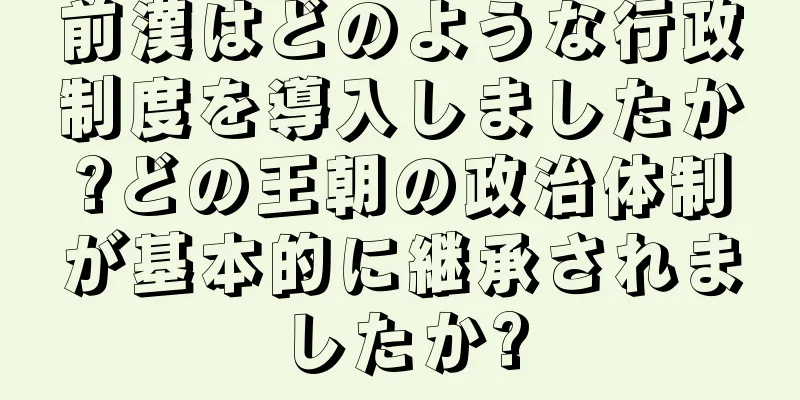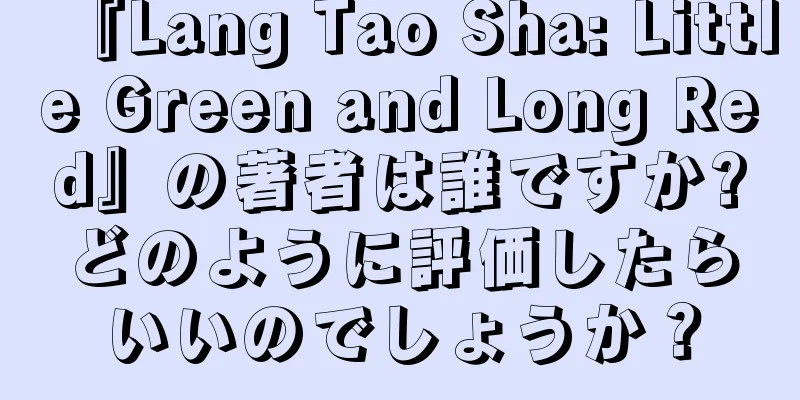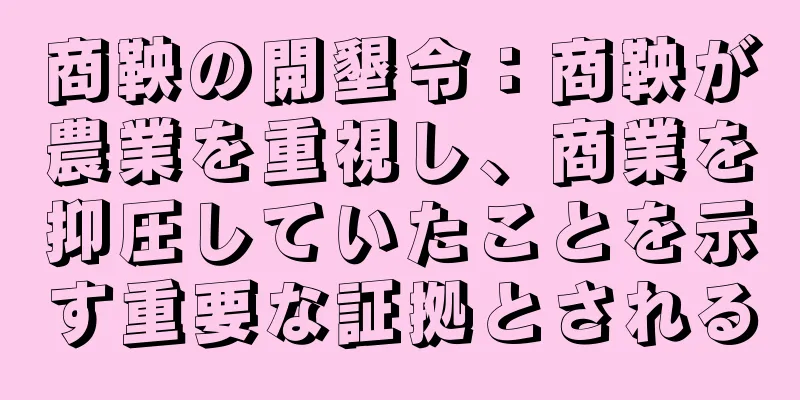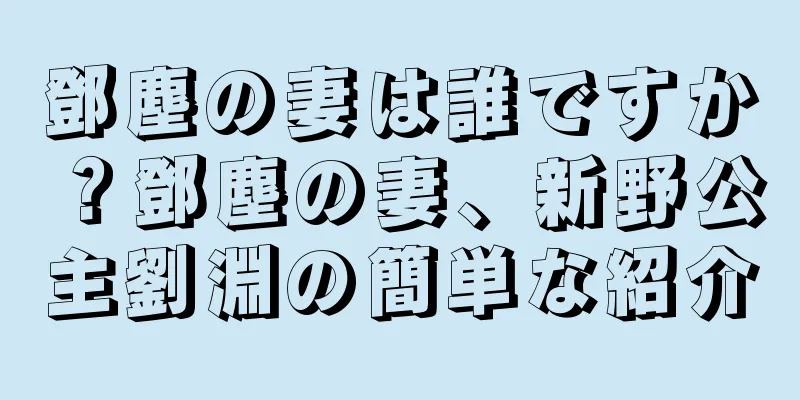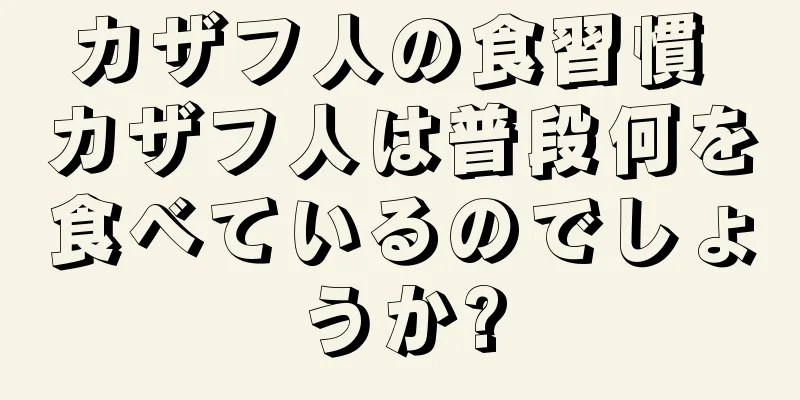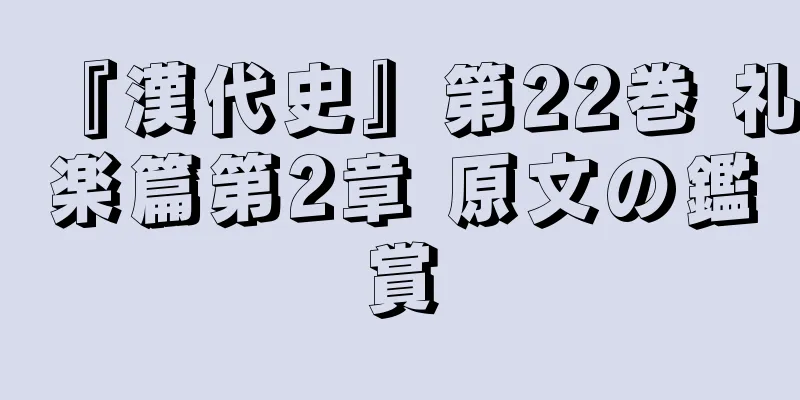なぜ張郃のような有名な将軍が諸葛亮の待ち伏せで死んだのでしょうか?
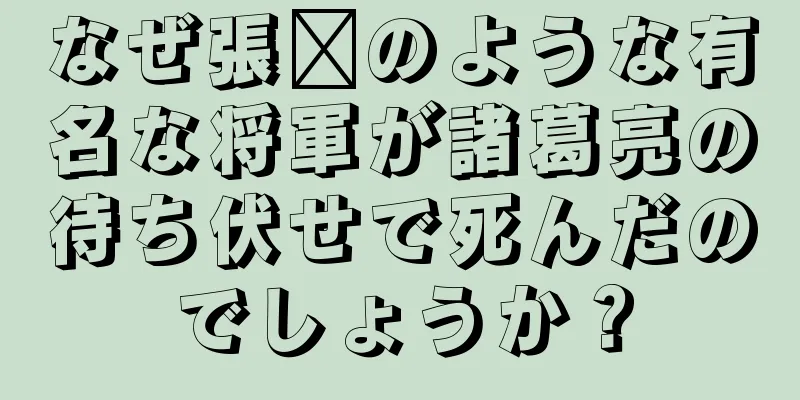
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が張郃の戦死について詳細に紹介しますので、見てみましょう! 張郃は曹操軍の五大将軍の一人であり、袁紹の指揮下では河北の四柱の一人でもあり、顔良、文殊、高蘭などの名将と並んで有名であった。彼は官渡の戦いの途中で曹操に寝返り、袁紹軍に混乱を引き起こし、袁紹の敗北につながった。曹操の軍に入隊した後、彼は多くの軍事的功績を挙げ、皆の注目を集めました。漢中の戦いの際、黄忠は曹操の指揮官夏侯淵の首を切った。その首が劉備に差し出されたとき、劉備は夏侯淵のような将軍の首を切るよりも張郃の首を切るほうが悪いと軽蔑して言った。案の定、張郃の再編により曹操軍は劉備の攻勢を阻止し、曹操の援軍の到着を待った。 諸葛亮の治世中、五大将軍が次々と亡くなり、張郃だけが残った。彼は戦場で才能を存分に発揮し、諸葛亮の強力なライバルとなった。諸葛亮が最初の北伐を開始したとき、張郃は彼を支援するために何千マイルも旅し、非常に不利な状況下で街亭で馬謖を破り、一挙に諸葛亮を撃退し、彼の遠征を失敗に導いた。その後の戦争では、張郃は関龍戦場で活躍し、魏の関龍軍団のリーダーとなった。しかし、このような名将は、諸葛亮の第四次北伐の際に、木門路で諸葛亮の伏兵に射殺された。ここで何が起こっているのですか? 1. 張郃が戦いでどのように死んだか。 張郃の死は実はとても卑怯なものでした。張郃自身も自分がこんなふうに死ぬとは思ってもいませんでした。諸葛亮の第四次北伐の際、張郃の指揮下では諸葛亮の攻撃を容易に撃退できたはずであったが、司馬懿の指揮下では戦いは混乱した。また、呂城の戦いの謎も後世に残した。 諸葛亮が8万人の蜀軍を率いて第四次北伐を開始したとき、曹魏の状況は緊迫していませんでした。これは諸葛亮が過去の教訓から学び、曹魏の防衛の要所を攻撃せずに迂回して包囲したためである。これらの重要拠点には、旗山包、上桂、龙渓などの要塞が含まれます。特に旗山砦は諸葛亮の穀物輸送ルートを遮断した。穀物の輸送路が貧弱だったため、諸葛亮は食糧と牧草の面で直接困難に直面しました。 魏軍の元司令官である曹真がこの時重病であったため、曹魏の皇帝曹睿は曹真に代わって司馬懿を関龍に派遣した。張郃は関龍軍の総大将として、司馬懿と協力して数え切れないほどの衝突を経験しました。諸葛亮の四次北伐に対する戦いの全過程は、張郃と司馬懿の争いに費やされたと言える。 司馬懿は軍を掌握するとすぐに、全軍を率いて旗山を救出しました。張郃は、諸葛亮が他の部隊に迂回させて曹魏の後方を攻撃させないように、部隊を前方と後方の二つに分けることを提案した。司馬懿は拒否した後、全軍を率いて旗山へ向かった。諸葛亮は司馬懿が全軍を率いているのを見て、司馬懿を動かすために、自分の軍を3万に分け、自ら軍を率いて上桂を攻撃した。曹の軍を破った後、急いで上桂の麦刈りに向かった。知らせを聞いた司馬懿は魏軍を率いて急行したが、諸葛亮と会って戦うことを拒否し、諸葛亮が上桂で麦を収穫して岐山に戻るのを見守った。 この時、張郃は司馬懿に、諸葛亮が上桂で小麦を収穫したにもかかわらず、食糧不足の問題を根本的に解決することはできないと再度提言した。魏軍は諸葛亮の動きを気にする必要はなく、ここに留まり、諸葛亮の背後を攻撃するために軍隊を派遣するだけでよい。こうして、旗山砦の魏軍は持ちこたえる自信を得た。諸葛亮を追いかけるべきではないが、近づいたときに戦う勇気がなくなれば、皆が失望することになる。諸葛亮の軍隊は魏軍に阻まれ、食料が尽きると撤退した。司馬懿は張郃の忠告を受け入れず、再び諸葛亮を追い詰めた。 事実は張郃の予想通りであった。司馬懿は鹿城方面で諸葛亮に追いついた後、諸葛亮の反撃に直面し、すぐに山に退却し、防御のために陣地を掘った。司馬懿の部下たちは激怒し、戦争を要求した。司馬懿は仕方なく軍を派遣して諸葛亮の陣営を攻撃したが、諸葛亮に敗れ、再び守勢に立たされた。これは後に鹿城の戦いとして知られるようになる。この後、司馬懿は持ちこたえ、諸葛亮が食糧と草を使い果たして漢中に撤退するまで戦わなかった。 この時、司馬懿は追撃するかどうかについて張郃と最後の口論をしていた。張郃は追撃に反対した。彼は兵法では帰還軍を追撃すべきではないとしており、諸葛亮を追撃する必要はないと考えていた。しかし、司馬懿は張郃に諸葛亮を追わせることを主張した。諸葛亮が食料を使い果たして撤退すれば、張郃の軍は間違いなくパニックに陥り、魏軍は必ずや諸葛亮を追撃して勝利するだろうと考えたからである。張郃は仕方なく1万の騎兵を率いて諸葛亮を追撃したが、木門路で諸葛亮に待ち伏せされ、戦闘中に右膝を撃たれて死亡した。 『三国志演義』ではこの歴史が書き換えられました。司馬懿が諸葛亮を恐れていたという設定を表現するために、追撃を主張する人物が張郃に、追撃に反対する人物が司馬懿に変更された。その結果、貢献したいという熱意に燃えていた張郃は諸葛亮の罠に陥り、木門路で射殺された。 2. 司馬懿と諸葛亮が協力して張郃を殺害した可能性。 張郃が戦死していく過程を見ていると、いつも何かがおかしいと感じます。そのため、司馬懿と張郃はいつも意見が合わなかった。戦いの間、張郃の提案が明らかに正しかったにもかかわらず、司馬懿はそれを採用しなかった。このため、司馬懿は呂城の戦いでの敗北や張郃の死など、大きな代償を払った。 では、張郃と司馬懿の緊張関係は何を表しているのでしょうか? 主な問題は、関龍軍団のリーダーシップをめぐる争いです。関龍軍はもともと曹真が指揮していた。曹真が病気で辞任したとき、関龍軍で最も経験豊富で有能な将軍である張郃は、当然ながら曹真の後任として最適な候補者だった。しかし、曹叡は曹真に代わって司馬懿を派遣した。 さらに、曹叡が司馬懿を派遣して関龍軍を指揮させたとき、諸葛亮が曹魏を攻撃しに来ているという情報が曹叡に伝えられ、軍には荷物がなく、食料や飼料の輸送が困難になっていた。諸葛亮に抵抗するために軍隊を送る必要はなかった。上桂の小麦がすべて収穫されれば、食糧不足のため諸葛亮は自然に撤退するだろう。曹叡はこの意見に耳を傾けなかったが、ここから曹魏の宮廷内には司馬懿が関龍軍を掌握することに反対する者がいたことが分かる。司馬懿が関龍軍を掌握しなかったら、張郃が自然に関龍軍の指揮権を引き継ぐだろうと想像できる。 司馬懿はかつて軍を指揮したことはあったが、関龍地域で戦ったことはなかった。諸葛亮が強力な敵に直面していたとき、司馬懿を一時的に交代させることは最善の選択ではなかった。司馬懿が軍に到着したとき、彼は同時に戦闘と軍の統合しか行えなかったため、魏軍に多くの困難をもたらした。特に、張郃率いる歴戦の将軍たちは司馬懿に納得していなかった。そのため、張郃は表面上は魏軍の利益を考慮し、司馬懿に何度も進言していたが、実は内心では司馬懿を嘲笑していたのである。 もちろん、司馬懿はこのことをよく知っていました。彼は張郃らの考えを無視し、常に自らの戦略を主張した。呂城の戦いの際、内外からの圧力を受け、彼は将軍たちの助言に従い、敗北を喫した。しかし、この敗北は実際には魏軍における司馬懿の威信を確立し、彼にとって有利なものとなった。諸葛亮が軍を撤退させたとき、張郃は彼の強い要請により蜀軍を追撃せざるを得ず、戦場で命を落とした。 最後に張郃が追撃してきたとき、状況はさらに混乱した。まず、張郃は諸葛亮を追撃することに反対した。その理由は帰還軍を追撃すべきではないというもので、軍事戦略上は間違っていなかった。しかし司馬懿は同意を拒否し、張郃に追撃を要求した。第二に、諸葛亮を追撃する過程で軍が損失を被った例もある。例えば、王爽が最後に諸葛亮を追跡したとき、彼は諸葛亮に殺されました。張郃はこの戦闘例を知っていたが、それでも罠に落ちた。それは本当に間違っていた。第三に、張郃は百戦錬磨の将軍であり、数万の軍勢を率いて突撃するべきではなかった。しかし、彼は接近戦で戦死したが、これはまったく常識に反する。諸葛亮がすでに待ち伏せして敵将軍の斬首作戦を準備していない限り、成功するのは困難だろう。 上記の兆候から判断すると、張郃の死は確かに非常に奇妙なものだった。張郃と司馬懿の対立も加えて、張郃の死によって誰が最も恩恵を受けたかを考えると、張郃の死には確かに陰謀の兆しがある。これは、関龍軍における司馬懿に対する最大の障害であった張郃が排除され、司馬懿が比較的スムーズに関龍軍を掌握することができたためである。司馬懿のその後の苦心の努力により、関龍軍団は司馬家が権力を握るための首都となった。その後、司馬一族は関龍軍の支援を受けて蜀を滅ぼし、魏王朝を奪取した。 この観点からすると、張郃の死は、反体制派を排除し、関龍軍団の支配権を得るために司馬懿が仕掛けた陰謀であった可能性が高い。それで、これは本当にそうなのでしょうか? 3. 張郃は実は司馬懿が諸葛亮の戦術を試そうとした際の犠牲者だった。 実際、張郃と司馬懿の違いを見てみると、それは主に戦略と戦術の違いです。曹真時代、曹魏軍の主な戦略は防御的な反撃でした。戦術としては、まず諸葛亮の主な攻撃方向を見つけ出し、その後全軍で反撃するというものです。この戦略と戦術は過去にも効果を発揮してきました。そのため、今回司馬懿が軍を掌握した後、張郃は自らの経験に基づいて司馬懿に積極的に提言を行った。これは張郃が司馬懿に熱心で、知っていることすべてを司馬懿に伝えたということであり、そのことに何ら問題はなかった。 しかし、今度は諸葛亮の戦術が変わり、司馬懿率いる魏軍の戦術も変化した。諸葛亮の第四次北伐は、双方が互いを試し、新たな戦略や戦術を試行錯誤する対決であったと言える。この北伐の際、諸葛亮の指導を受けた蜀軍は八卦陣を完成させ、戦闘力が大幅に向上した。諸葛亮もまた、自らの物流問題を解決するために木の牛を活用しました。そのため、諸葛亮は短期的な攻撃から長期的な膠着状態へと戦略を変更しました。戦術は攻撃から防御の反撃へと変わった。この北伐の間、諸葛亮は新たな戦術を試し、呂城の戦いで勝利した。 司馬懿は関龍軍を掌握したばかりで、彼自身の戦略と戦術を戦争に適用したいと考えていました。司馬懿は軍隊に溶け込み、最高レベルの連携を達成し、部下の信頼を得る必要がありました。一方、諸葛亮の第四次北伐における双方の軍事行動の奇妙さをもたらした諸葛亮の戦略と戦術について、総合的な調査を行う必要がある。司馬懿が張郃の忠告に従わなかったのは、一方では諸葛亮の戦略と戦術が根本的に変化し、曹真が残した戦略と戦術がもはや戦争の新たな要求に適さなかったからである。一方、司馬懿は戦いを通して諸葛亮の戦略や戦術を観察し理解し、自らの戦略や戦術の考えを試したいと考えていた。 そのため、司馬懿は常に諸葛亮の勢力圏内で活動し、諸葛亮に決戦の機会を与えなかった。その結果、諸葛亮は攻撃も防御もできず、常に受け身の状況に陥りました。この状況を打開するために、諸葛亮は知恵と勇気で司馬懿に対抗しようと全力を尽くし、呂城の戦いで勝利した。しかし、この勝利により司馬懿は関龍軍における権威を固めることができたが、状況に根本的な変化をもたらすことはなかった。結局、食糧や飼料の輸送が困難になったため、諸葛亮は軍隊を撤退させざるを得ませんでした。 諸葛亮が軍を撤退させたとき、司馬懿は張郃を派遣して諸葛亮を追わせたが、これは司馬懿自身の戦術の最後の実験でもあった。彼は撤退中に諸葛亮の欠点を見つけ出そうとした。しかし、司馬懿が予想していなかったのは、追撃中に張郃が諸葛亮の待ち伏せにより殺されたことであった。 司馬懿はこの戦いで張郃の死を含めて大きな犠牲を払ったが、多くのものを得た。司馬懿は諸葛亮の軍の配置パターンを徹底的に理解し、諸葛亮の次の北伐に抵抗するための基礎を築いた。諸葛亮が軍を撤退させたとき、誰もが来年には軍を送るだろうと考えていた。しかし、司馬懿は諸葛亮が兵站を非常に重視しており、3年間の食料と飼料の蓄積なしには軍隊を派遣しないだろうと判断した。その後、事実が司馬懿の判断を裏付けた。 諸葛亮は第五次北伐を開始したとき、第四次北伐の経験を生かし、一回の戦いで勝利を収めようとした。しかし、司馬懿は曹叡とともに諸葛亮の第四次北伐に抵抗する防衛戦略も展開した。この戦略は、「敵の進撃を鈍らせるために、強固な城壁で都市を守らなければならない。敵は前進できず、撤退すれば戦うこともできない。敵が長く留まれば、食料が尽き、略奪しても何も得られなくなる。敵は逃げる。逃げた後に追いつけば、完全な勝利が得られる。」というものである。 この戦略的アプローチを見ると、諸葛亮の第四次北伐に対する司馬懿の防衛の功績が理解できる。この戦略政策は、その戦いから得られた教訓から抽出されたものです。司馬懿は諸葛亮の第五次北伐を防御する際にこの戦略的アプローチを採用し、諸葛亮に決戦の機会を与えなかった。さらに、蜀軍が撤退する際には用心深く、蜀軍が反撃の準備をしているのを見て、張郃の失敗を繰り返さないようにすぐに撤退した。 張郃が戦闘中に待ち伏せされ殺されたのは、司馬懿の「逃走追撃」戦略を実行しようとしたためだと分かります。したがって、張郃の死は単なる事故であり、彼はその命を司馬懿が立てた戦略に完璧に終止符を打つために使ったのである。張郃の死から得た教訓により、司馬懿は諸葛亮の第五次北伐から防衛することができた。 結論: 張郃の死は曹魏にとって大きな損失であった。曹魏の関龍軍の中心的将軍として、彼の死は関龍軍の歴史に新たな一章を開いた。張郃の死は司馬懿に多大な利益をもたらした。それ以来、司馬懿は関龍軍団を慎重に管理し、徐々にこの精鋭軍団に自分の命令に従わせていった。彼とその息子による晋王朝の建国に大きな役割を果たした。これは張郃の死の異常性を示しているように思われる。 しかし、張郃と司馬懿の間の意見の相違は主に戦略と戦術に関するものであり、他の側面には関係がなかった。張郃は曹真時代の戦略と戦術を忠実に守り、それを用いて司馬懿に助言や提案を行った。しかし、すべてが変わってしまったため、司馬懿は張郃の助言を採用しませんでした。諸葛亮は戦略と戦術を変え、司馬懿もそれに応じて変化しなければなりませんでした。 結局、諸葛亮の第四次北伐の後、諸葛亮と司馬懿は互いの長所と短所を理解し、そこから得た教訓を諸葛亮の第五次北伐に活かした。諸葛亮の第四次北伐に抵抗する戦いこそが、司馬懿が諸葛亮の第五次北伐に抵抗する成功を決定づけたと言える。張郃の死は、退却する諸葛亮の軍を追撃できるかどうかを確かめるために支払われた代償であり、完全に偶然の出来事だった。彼の死により、司馬懿は正しい戦略的方向性を得ることができた。司馬懿に関龍軍団をうまく管理する機会を与えたことは、もう一つの驚きだった。 |
<<: 清明節の起源と伝説 清明節はいつ始まったのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』の宝玉はなぜ大観園に引っ越した後、一日中外で遊んでいたのですか?
宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の男性主人公です。次のInteresting History編集者が詳...
中国史上最も有名な5人の将軍を振り返ってみると、彼らの運命はどうだったのでしょうか?
中国の5000年にわたる文明の歴史の中で、歴史に名を残した将軍は数多く存在した。以下、Interes...
「小五英雄」第120章:北の英雄は道士に網を破るように頼み、韓良は師匠の計画を明らかにする
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
孟浩然の詩「宗直寺塔登り」の本来の意味を鑑賞
古詩「宗直寺の塔に登る」時代: 唐代著者: 孟浩然空中の塔に登って首都全体を一望しましょう。渭水は竹...
西遊記続編第40章:経典の再検討による解決と同盟の確認
明代の神話小説『続西遊記』は、『西遊記』の3大続編のうちの1つです。 (他の2冊は『続西遊記』と『補...
遼・金・元の衣装:遼の女性の衣装
契丹の女性はあらゆる種類の頭飾りを好んだ。陸珍が孝皇太后に会ったとき、彼女は2回異なる頭飾りをしてい...
唐心本草:唐代に孫思邈が著した世界初の国家薬局方
隋の開皇元年(581年)、孫思邈は陝西省の中南山に隠遁し、民間の医学体験を重視し、絶えず訪問を重ねて...
水滸伝における丁徳孫のあだ名は何ですか?なぜ「矢をつけた虎」と呼ばれるのでしょうか?
矢に射られた虎、丁徳孫丁徳孫は張青の副将軍でもあった。顔や首に傷があったため、彼は「矢傷虎」と呼ばれ...
『紅楼夢』の賈貴は本当に宝仔と宝玉の子供ですか?真実とは何でしょうか?
現在広く伝わる伝説では、賈宝玉と薛宝才の間には賈桂という息子が死後に誕生した。今日は、おもしろ歴史編...
『彩桑子:月は感傷的だから私を笑うべきだ』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
彩桑子:月は感傷的だから笑うべきだ那蘭興徳(清朝)感傷的な月は私を笑うべきだ、今私を笑うべきだ。春の...
張飛の思里小薇はどんな役だったんですか?それは大きな力ですか?
張飛の弗里小衛はどのような地位にあったのでしょうか?権力が強かったのでしょうか?張飛の死後、諸葛亮は...
呉と越の争いで越国が敗北を勝利に変えた主な理由は何ですか?
敗北後、越王の郭堅は国辱を忘れず、絶えず自分を反省し、より強くなるために努力する必要がありました。ま...
水滸伝で金翠廉はどうやって鄭図の魔の手から逃れたのでしょうか?
中国文学の四大傑作の一つである『水滸伝』は、英雄の物語を語る章立ての長編小説です。 Interest...
『啓東夜話』第3巻第3章はどんな物語ですか?
○ 紹熙内禅紹熙二年十一月、光宗皇帝は初めて円墳に祭祀を捧げた。当初、黄妃は寵愛を受けており、李皇后...
『紅楼夢』で、賈おばあさんは宝琴を宝玉と結婚させたかったので、宝琴に誕生日を尋ねたのですか?
賈おばあさんは、石夫人とも呼ばれ、賈家の皆から「おばあさん」「老祖」と敬意を持って呼ばれています。こ...