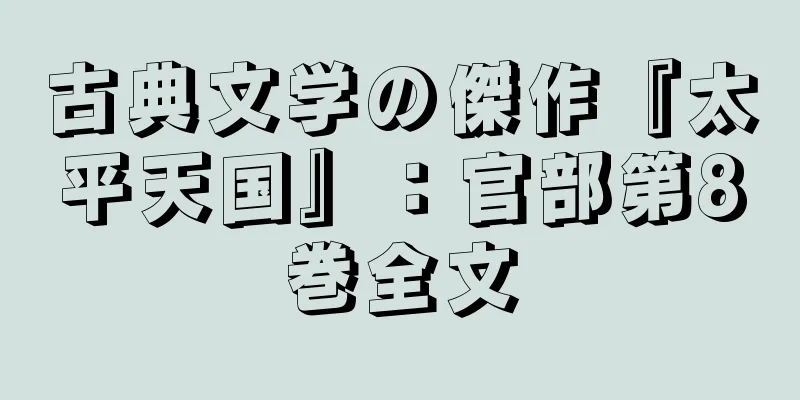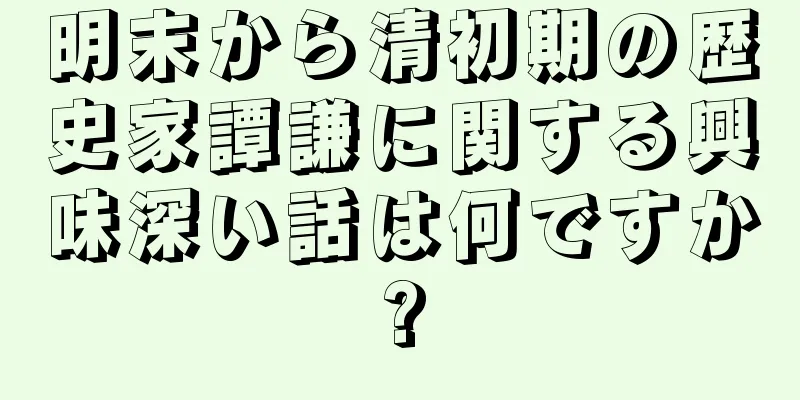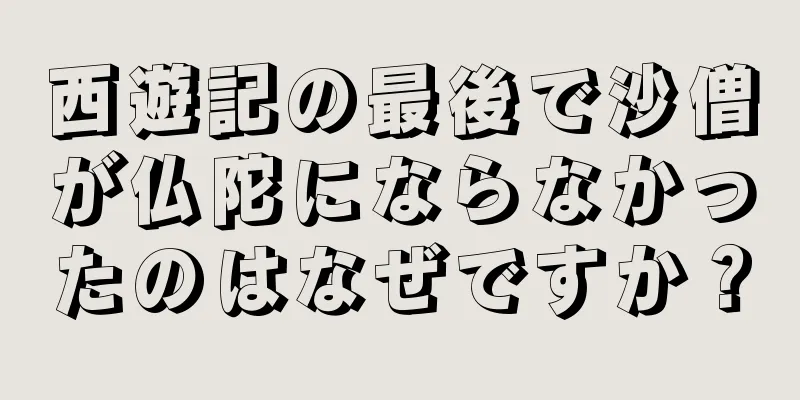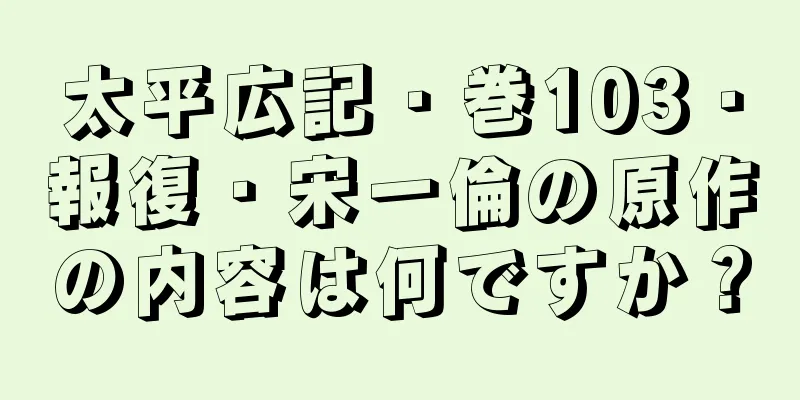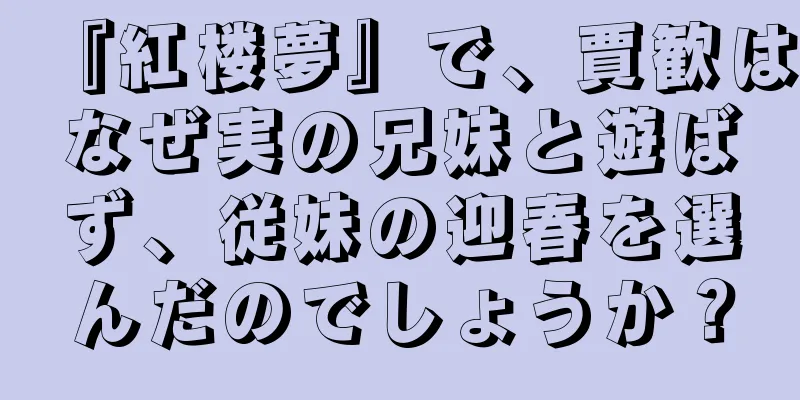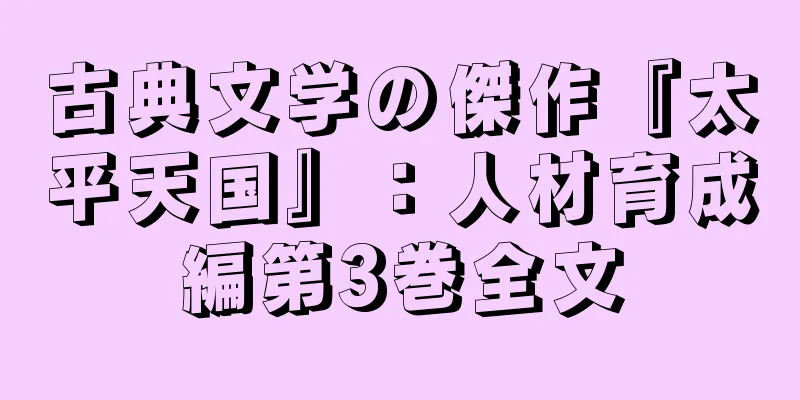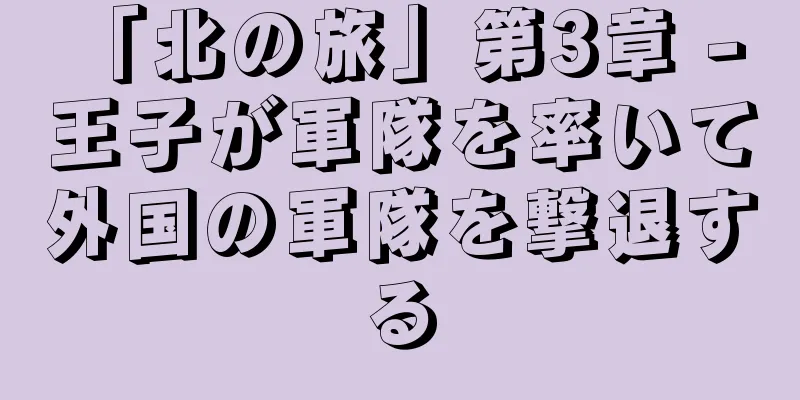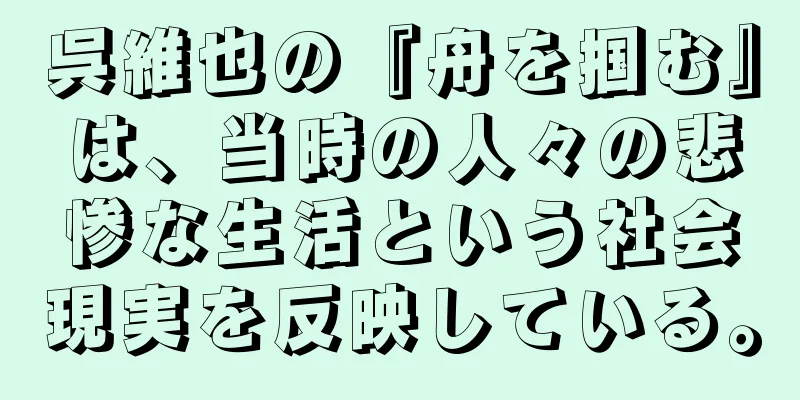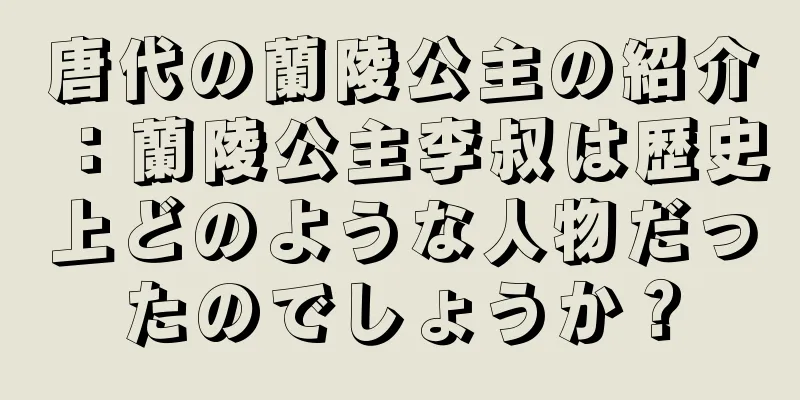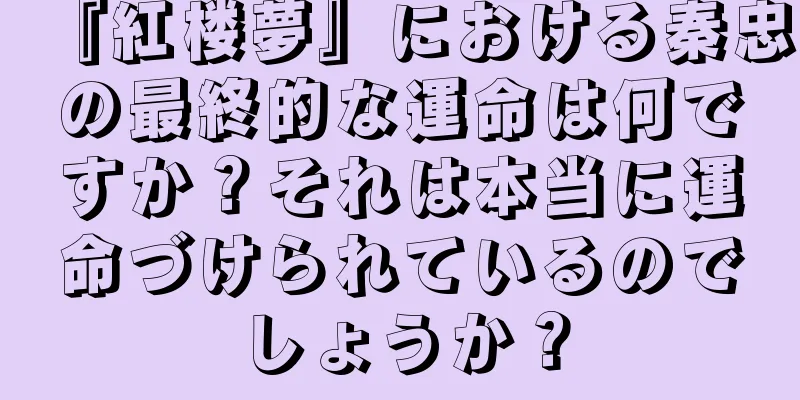歴史の記録から判断すると、鹿城の戦いはなぜ物議を醸す戦いなのでしょうか?
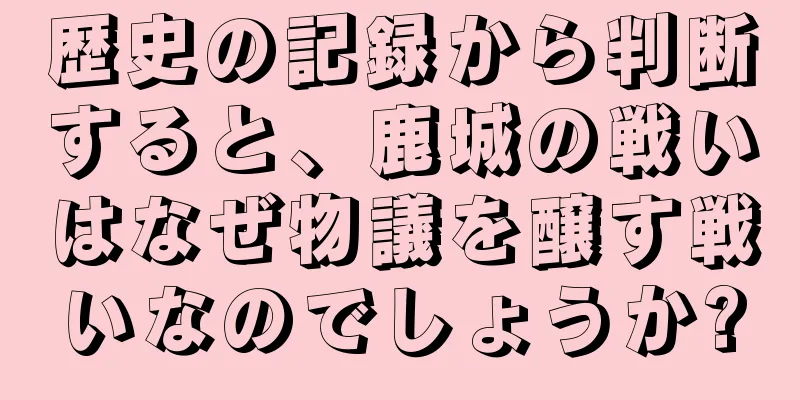
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、諸葛亮と司馬懿の間の鹿城の戦いについて詳細に紹介します。歴史の記録は異なります。真実はどうでしょうか? 見てみましょう! 呂城の戦いは、歴史の記録に矛盾があるため、さまざまな意見がある戦いです。陳寿の『三国志』にはこの戦いの記録はない。この戦いに関する最も古い記録は『韓進春秋』にあり、これは裴松之の注釈に付け加えられたものである。この記録によれば、諸葛亮は「鎧を着た頭3,000個、黒鎧5,000組、角弓3,100本を手に入れた」とされている。しかし、『晋書』ではこの戦いについて、司馬懿が諸葛亮を破り、諸葛亮の陣営を占領し、諸葛亮は撤退したと記録されている。司馬懿は諸葛亮を追跡し、その抵抗を打ち破り、数万の蜀軍を捕らえて殺した。 『資治通鑑』では『韓進春秋』の記述を引用し、諸葛亮が3000の甲冑の首を捕らえたとしている。 1. 鹿城の戦いの真実性。 これらの矛盾する歴史記録から、諸葛亮と司馬懿が鹿城で戦ったことは確かである。戦いの結果が諸葛亮の勝利であったか、司馬懿の勝利であったかは不明である。しかし、この戦いの結果から判断すると、どちらの側も決定的な結果を得ることはできず、引き分けに終わった。 諸葛亮の北伐の記録を見ると、撤退後に褒美を与えられたという記録はない。諸葛亮が呂城の戦いであれほどの功績を挙げたのであれば、貢献した者たちに報奨を与えないのは不可能だっただろう。しかし、『三国志演義』にはこの戦いの手がかりが残されている。例えば、『王平伝』にはこの戦いの記録が残されている。この戦いが勃発し、蜀軍がこの戦いを賞賛しなかったため、この戦いの結果は『漢晋春秋』に記録されているほど栄光に満ちたものではなかったことは確かです。 そして、司馬懿の戦績は『晋書』に記されているようなものではなかったはずだ。 『晋書』には、司馬懿が諸葛亮を打ち破り、撤退を余儀なくしたと記されている。追撃で主な成果が達成され、司馬懿は諸葛亮の軍を破り、数万の蜀軍を捕らえて殺害した。歴史的観点から見れば、この結果も不可能である。まず、諸葛亮の北伐における魏軍の最大の損失は張郃の死であったことはよく知られています。この曹魏の有名な将軍は諸葛亮を追跡中に死亡した。張郃は曹魏の追撃の主将だった。主将でさえ戦いで死んでしまったら、どうして敵を倒せるだろうか? 第二に、諸葛亮の蜀軍の兵力は限られていました。諸葛亮の時代、蜀軍全体の兵力はわずか12万人でした。最後の北伐を除いて、諸葛亮は常に軍の3分の1を戦場の警備のために国内に残し、軍の3分の2だけを率いて遠征に赴いた。この北伐では、諸葛亮は最大でも8万人の兵力しか連れてこなかった。もし諸葛亮がこの戦いで数万の軍勢を失ったら、蜀軍にとって大きな打撃となるだろう。 街亭の戦いの後、諸葛亮は失敗の責任を取るために自ら3階級降格することを決意した。もし今回も諸葛亮が失敗したら、彼は必ず責任を取るだろう。しかし、歴史の記録には同様の記録は見つかっていないため、鹿城の戦いは確かに起こったが、その結果はどちらにとっても決定的なものではなかったし、戦争の帰結にも影響を与えなかったことは確かだ。 2. 鹿城の戦いの全体的な流れ。 洛城の戦いは諸葛亮の第四次北伐の際に起こり、諸葛亮は蜀軍8万人を率いて漢中から岐山を攻撃した。魏軍は岐山、上桂、隴西などの要衝を押さえていた。曹真が病気だったため、魏の皇帝は曹真に代わって司馬懿を派遣し、敵に抵抗させた。 この北伐において、諸葛亮は岐山、上桂などの曹魏の拠点を襲撃せず、攻撃せずに包囲し、野戦で魏軍の主力と決戦を挑もうとした。そこで諸葛亮は司馬懿を決戦に誘い込むために一連の機動作戦を開始した。諸葛亮は司馬懿の全軍が旗山を救出しようとしていることを知ると、自ら3万人の軍を率いて上桂を攻撃し、上桂で小麦を収穫した。 司馬懿は軍を率いて上桂を救出するために戻ったが、諸葛亮との戦いには参加しなかった。諸葛亮は小麦を収穫した後、軍を率いて南へ撤退し、司馬懿は再び諸葛亮に従った。鹿城の近くで、諸葛亮は戦いを求めて引き返し、司馬懿は山に退却し、防御のために塹壕を掘った。このような状況下で、司馬懿の配下の将軍たちは皆、戦争を要求した。司馬懿は民意が激怒しており、鎮圧するのが難しいと見て、攻撃を命じざるを得なかった。 この戦いで、司馬懿は軍を二つのルートに分けた。彼は魏軍を率いて主力となり、諸葛亮の陣営を攻撃した。張郃は奇襲として、王平が守る諸葛亮の陣地の南側を攻撃した。この戦いで張郃は王平を攻撃したが、王平は持ちこたえたため、張郃が南威を捕らえることは不可能となった。諸葛亮が魏延、高襄、呉班に軍を率いて反撃させたため、正面から攻撃した司馬懿の軍も敗北した。司馬懿は敗れた軍を率いて陣地に戻り、撤退を拒否し、張郃もまた成功せずに帰還した。 鹿城の戦いは奇跡的な戦いと評されることもあるが、実際は最初から最後まで諸葛亮と司馬懿の戦いであった。諸葛亮は野戦で司馬懿を排除することを望んだが、司馬懿は諸葛亮に密着して従い、決戦には参加しないと主張。諸葛亮の最も根本的な弱点は兵站補給にあるからです。もし司馬懿が諸葛亮の弱点をつき、食料や物資が尽きて撤退せざるを得なくなったときに追撃していれば、勝利できたであろう。 実は、当時諸葛亮は司馬懿に包囲されていました。彼の背後には魏軍が守る旗山砦があり、諸葛亮の退却を脅かし、諸葛亮の兵站輸送に深刻な脅威を与えていた。司馬懿の軍隊が彼らの前に迫っており、少しでもミスをすれば災難が降りかかるだろう。このような状況下では、諸葛亮が司馬懿との決戦を望むなら、実際には大きなリスクを負うことになる。司馬懿はこれを見て、戦わずに常に従おうとしたため、諸葛亮は戦うことができず、窮地に陥った。この状況が続けば、諸葛亮は非常に困難な状況に陥るだろう。 この目的のために、諸葛亮は司馬懿に急速な戦闘を強いる戦略を採用した。軍事力を手に入れたばかりで軍全体の信頼を得られなかった司馬懿は、部下からの圧力により、意に反して諸葛亮と戦わざるを得なかった。しかし、呂城の戦いでは、司馬懿にバックアッププランがあったことがわかります。彼は正面攻撃に全力を尽くすのではなく、諸葛亮の軍を足止めし、張郃の王平への攻撃を援護することに努めた。張郃が成功すれば、諸葛亮の退路は断たれ、差し迫った危険に陥るだろう。 しかし、張郃の攻撃は失敗し、司馬懿は陣営に撤退した。諸葛亮は戦いに勝利したが、望んだ結果は得られなかった。諸葛亮は司馬懿の主力に大打撃を与えることも、司馬懿の陣営を占領することもできなかったからだ。一方、諸葛亮は領土の奥深くに一人でいた張郃に反撃できず、撤退を許した。このときから戦いの勝敗は明らかであった。 呂城の戦いの後、司馬懿は持ちこたえる戦略を継続した。諸葛亮は司馬懿によって半包囲された状況に陥り、食料や飼料の補給が困難になったため、最終的には撤退しなければならなかった。追撃勝利の戦略を実行するために、司馬懿は張郃の反対にもかかわらず、張郃を追撃に派遣した。張郃は木門で諸葛亮の待ち伏せを受け、銃殺された。諸葛亮も漢中へ撤退することに成功した。この時点で諸葛亮の第四次北伐は終了した。 3. 鹿城の戦いの結果。 鹿城の戦いは諸葛亮と司馬懿が史上初めて直接対決した戦いであった。この戦いの前に、両者は互いに知恵と勇気を競い合い、多くの戦術的作戦を実行した。両者は戦闘はしなかったものの、戦略や戦術の面ではすでに衝突していた。これらすべての戦闘戦略の効果は、呂城の戦いに反映されました。 諸葛亮は機動戦法を採用し、司馬懿を動員して野戦での決戦を模索した。同時に、彼らは自国の食糧供給の困難さも考慮し、敵国の小麦を収穫して軍の食糧を補充した。司馬懿は諸葛亮の食糧や草の補給が困難であることを利用し、諸葛亮を段階的に圧迫して行動を制限したが、諸葛亮と決戦をすることはなかった。このように、司馬懿は諸葛亮に圧力をかけ続けたため、諸葛亮は兵站の負担を負わされ、最終的には食糧と草の不足により軍隊を撤退させることになった。 実際、諸葛亮は攻撃を防御とする戦略を採用し、司馬懿は防御を攻撃とする戦略を採用しました。しかし、戦術の面では、両者は逆転し、諸葛亮は防御を攻撃とし、司馬懿は攻撃を防御としました。諸葛亮は司馬懿に挑戦していたが、これは司馬懿の攻撃的な姿勢に対する防御的な動きだった。司馬懿は諸葛亮の挑戦に遭遇したとき、踏みとどまって出てこなかった。これは諸葛亮に圧力をかけ、攻勢の姿勢を保つために取った防御策だった。 両者の盧城の戦いでは、諸葛亮は防御によって相手の攻撃を阻止し、その後反撃するという戦術を採用した。司馬懿は攻撃的な戦術を採用したが、実際に達成したかったのは防御効果だった。このように、司馬懿が諸葛亮の陣営を攻撃したとき、それは単なる試みに過ぎず、形勢が不利になるとすぐに撤退した。こうして、呂城の戦いは期待外れかつ痛烈な結果に終わった。 しかし、この戦いの後、司馬懿は諸葛亮の戦略と戦術を基本的に深く理解するようになった。同時に、この戦いを通じて、彼は部下と軍隊の戦闘効率についても理解を深めた。特に諸葛亮との対決においては、独自の戦略と戦術を確立した。それは戦わずに持ちこたえ、諸葛亮が食糧と草を尽きて退却するのを待ってから追撃することです。同時に、司馬懿は追撃中に張郃が奇襲を仕掛けたことに深く感銘を受けた。 諸葛亮の第五次北伐の際、呂城の戦いで双方が得た教訓が実践された。諸葛亮は、これまで成功していた機動戦を引き続き採用し、北源を占領し、陽水に奇襲を仕掛けた。しかし、諸葛亮の機動作戦は、これに備えていた魏軍の防御によって失敗に終わった。司馬懿は、戦わずに陣地を守り、諸葛亮が食糧を使い果たして軍を撤退させるのを待つという、実証済みの戦略を堅持した。一方、蜀軍が撤退すると、司馬懿は張郃の教訓を学び、慎重に行動した。蜀軍が反撃の兆しを見せると、直ちに撤退した。 諸葛亮は自らの兵站上の困難から学び、第五次北伐の際にこの問題の解決に注力した。彼はまず3年分の食糧と飼料を蓄え、運搬には木製の牛と流し馬を使いました。諸葛亮も司馬懿の戦闘拒否を利用し、戦場で土地を耕す戦略を採用した。彼は軍隊と現地の人々を混合させ、現地の荒れ地を開墾して農作物を栽培し、食糧と飼料の供給問題を解決しました。膠着状態が続くと、諸葛亮は司馬懿に戦略の変更を迫り、決戦を挑むことになるかもしれない。残念ながら、諸葛亮は過労のため五丈原で病死し、その願いは叶わなかった。 結論: 歴史上、鹿城の戦いについては様々な記録が残されていますが、この戦いは実際に存在しました。しかし、この戦いで誰が勝っても負けても、戦争に決定的な影響を与えることはなかった。さまざまな歴史文献から判断すると、諸葛亮がこの戦いに勝利したはずである。しかし、目立った成果がなかったため、諸葛亮は軍全体に報酬を与えなかった。 しかし、この戦いは諸葛亮と司馬懿の間の将来の戦争に大きな影響を与えました。二人はこの戦いを通じて敵の戦闘特性を深く理解し、その教訓を諸葛亮の最後の北伐に応用した。その戦いで、司馬懿と諸葛亮は何度も戦い、最終的に司馬懿が諸葛亮の攻勢を抑え、諸葛亮の野望は達成されなかった。これらすべては鹿城の戦いの結果でした。 |
<<: 春節連句を掲示する伝統はどのようにして始まったのでしょうか?
>>: 大晦日の起源 大晦日はどのようにして始まったのでしょうか? 大晦日にまつわる物語
推薦する
白居易の詩「楊柳世玉と過ごす幸せ」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「楊柳世玉と過ごす幸せ」時代: 唐代著者: 白居易月明かりの夜には土手に腰掛けて静かに語り、花...
明朝の内閣と清朝の太政官の違いは何ですか?どちらのシステムが優れているでしょうか?
明朝の内閣と清朝の太政官の違いは何でしょうか? Interesting History の編集者が関...
明代の太祖皇帝、馬皇后、高孝慈の簡単な紹介
明代の皇后、馬孝慈高(1332-1382)は、本名が不明で、安徽省蘇州の出身です。彼女は楚陽王子郭子...
『紅楼夢』では、香玲は赤い麝香のビーズを身につけていなかったのに、なぜ妊娠しなかったのでしょうか?
今日は、「興味深い歴史」の編集者が、なぜ香玲が長年側室として飼われていたにも関わらず妊娠しなかったの...
諸葛亮の死後、劉禅によって処刑を命じられた重要な朝廷役人3人は誰ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
なぜ朱元璋は朱彪の死後、若い朱雲文に帝位を譲ったのでしょうか?
洪武25年(1392年)、皇太子朱彪が病死し、明朝の初代皇帝は難しい選択を迫られました。しかし、建文...
『紅楼夢』で、西雪と李姐の追放は賈祖母と関係があるのでしょうか?真実とは何でしょうか?
賈おばあさんは、石老夫人とも呼ばれ、「紅楼夢」の主人公の一人です。上記の疑問は、次の文章で『おもしろ...
霊宝天尊は道教の「三清浄」の一人です。この天尊の起源は何ですか?
霊宝天尊は、フルネームを「上清霊宝天尊」といい、道教の「三清」の一人で、「三清」の中で第二位にランク...
幽慈公の詩の有名な一節を鑑賞する:明日は二階に上がって私への思いを表明しないで、二階には嵐が多すぎるから
幽慈公は、字を子明といい、別名を希智、寒厳ともいう。建安(現在の福建省建翁)の人。有名な儒学者幽左の...
古代では、遠くまで旅行するのはとても面倒なことでした。では、古代の人たちが遠くまで旅行するにはどれくらいの費用がかかったのでしょうか?
今日の技術的に進歩した社会では、遠くへ旅行することは非常に簡単で一般的なことになりました。しかし、古...
衝撃的な美しさ:宇宙のゾンビ銀河はとても美しい
科学者たちは、ほぼ完全に暗黒物質で構成されている銀河を発見しました。この銀河は非常に暗いため、ほとん...
2016 年の春節の日付はいつですか? 2016 年の春節の曜日はいつですか?
2016年の春節はいつですか?2015年の春節はまだ到来していませんが、多くのネットユーザーは、20...
西梁の宣帝の子孫である蕭聡についての簡単な紹介 南朝の蕭聡はどのようにして亡くなったのでしょうか?
蕭聡(558-607)、号文文は、西梁の宣帝蕭昭の孫であり、西梁の孝明帝の息子であり、隋の煬帝の皇后...
神と不死者の違いは何ですか?神と不死者ではどちらがレベルが高いのでしょうか?
神と仙人の間には違いがあり、範囲が広いため、高いとか低いとかで比較することはできません。神は天の祝福...
『魏志郷臣宛書』をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
魏太守志に送る王維(唐代)廃墟となった街は荒涼としており、広大な山々や川も空っぽだ。空は高く、秋の日...