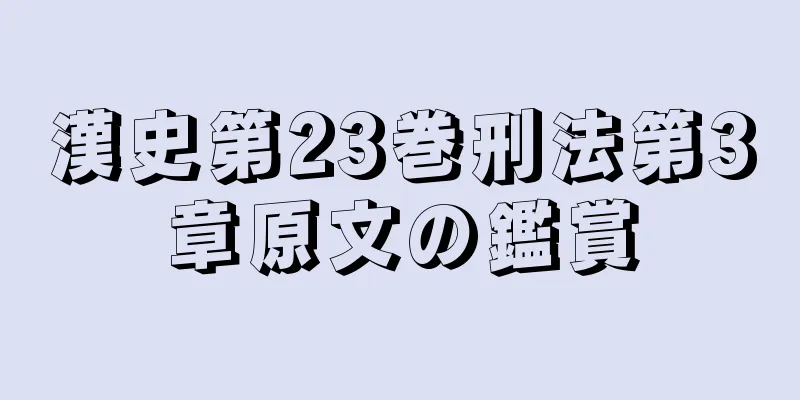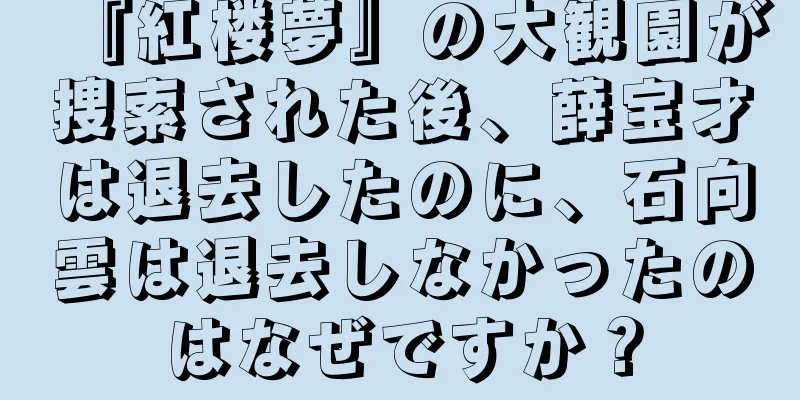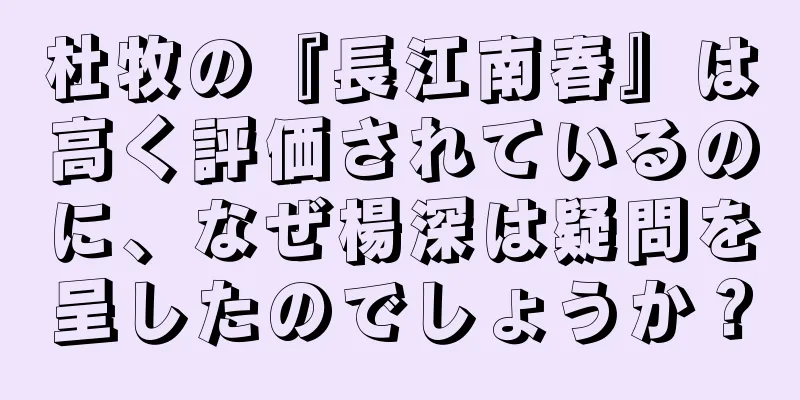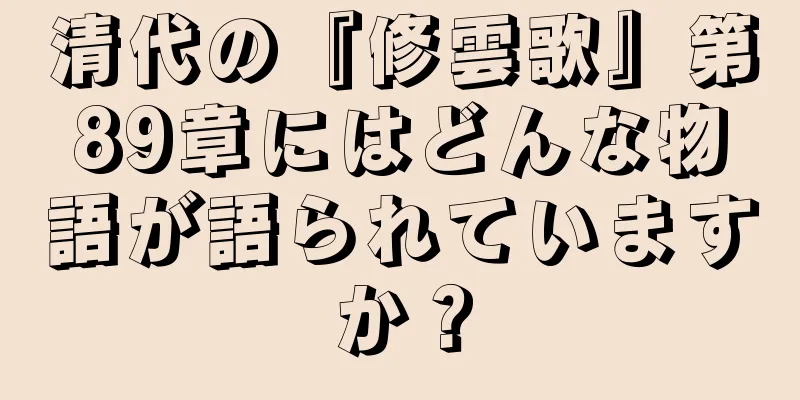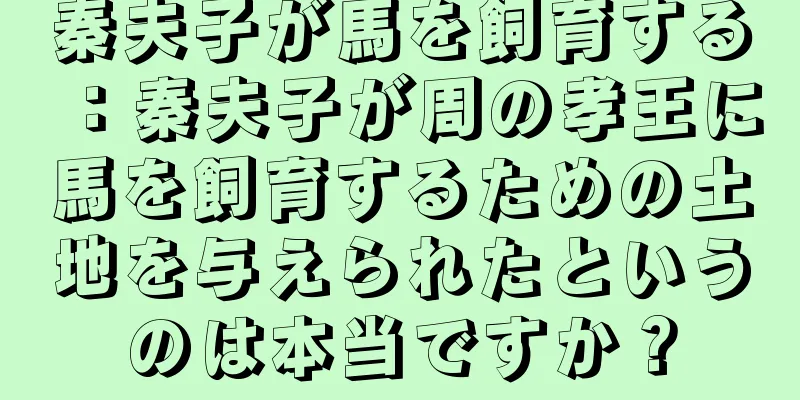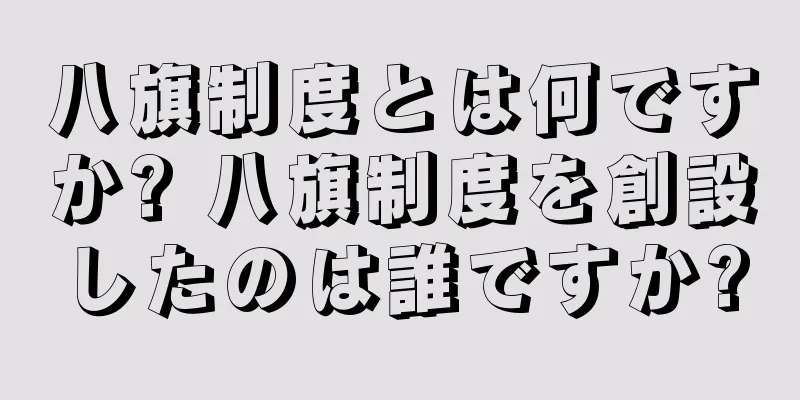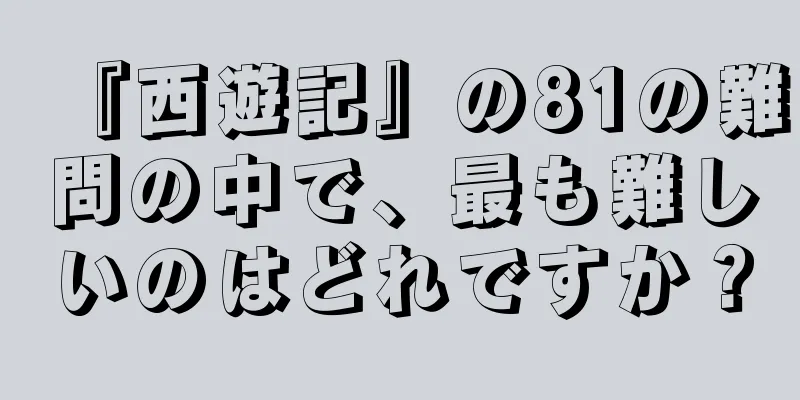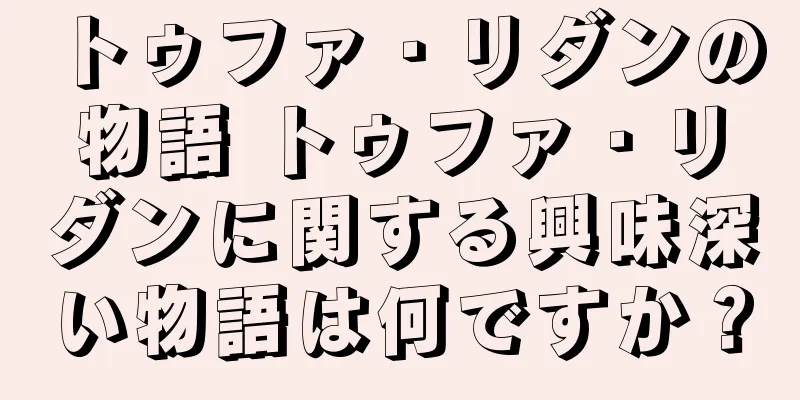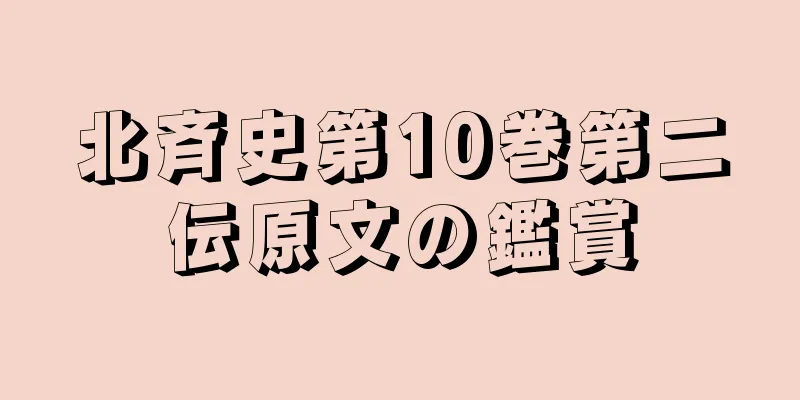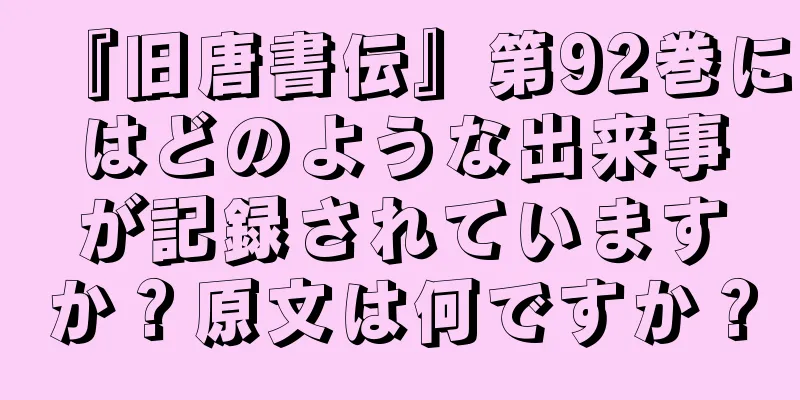正史における諸葛亮の軍事力はどのようなものだったのでしょうか?それは本当に強力なのでしょうか?
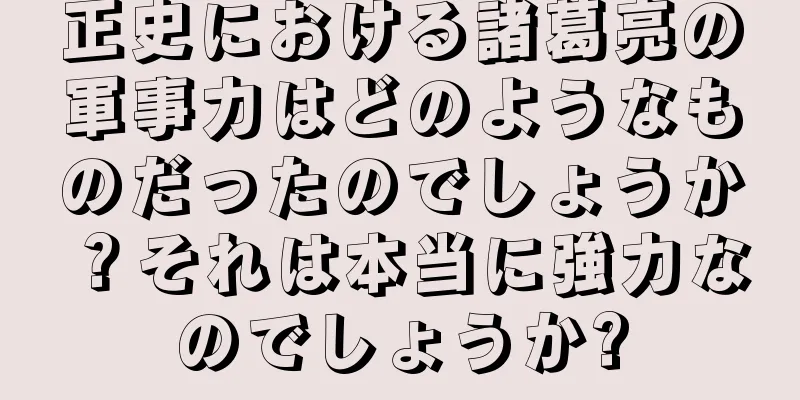
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、正史における諸葛亮の軍事力がどれほど強力であったかを詳しく紹介します。見てみましょう! 実は、諸葛亮の軍事力は時代を超えて高く評価されてきました。各王朝の名将たちも諸葛亮を高く尊敬していました。それらの権力者の目には、諸葛亮の軍事的業績が非常に高いことがわかります。その後、明代に『三国志演義』が出現し人気が高まり、諸葛亮の人気はますます広まりました。小説の中の諸葛亮は天文学や地理学に精通しており、まるで鬼のように賢い。他の人が考えつかないようなことを思いついたので、人々は諸葛亮を尊敬するようになった。私たちが幼かったころから、諸葛亮は私たちのお気に入りの登場人物の一人でした。 上記の段階では、諸葛亮は忠誠心と正義感、そして強力な軍事力で高く評価されていました。しかし、21世紀以降、インターネットの普及に伴い、諸葛亮に対する評価にもさまざまな声が上がり始めました。諸葛亮は劉禅を裏切り、魏延を殺害したため、忠誠心があまり強くないと考える人もいます。また、諸葛亮の軍事能力は平均的で、単なる兵站管理者だと考える人もいます。その中で、諸葛亮の軍事力は良くなかったという見方がますます強くなっています。諸葛亮について言及されるたびに、必ずこのようなコメントが出ます。今日この記事では、正史における諸葛亮の軍事力はどのようなものだったのか、本当にそんなに優れていたのか、ということに焦点を当てて議論します。 現在、インターネット上で最も多く語られている諸葛亮の軍事力に対する疑問は、主に3つの側面に分けられます。まず、『三国志』の著者である陳寿は、諸葛亮は国政を司るのは上手だが、軍隊を指揮するのは下手だと言った。第二に、諸葛亮の戦術能力は低く、司馬懿にかなわず、一度も司馬懿を倒せなかった。第三に、諸葛亮の軍事的洞察力は乏しく、何度も北伐を行い、民に多大な費用と労力を費やさせ、蜀漢の国力と軍事力を弱めた。次に、これらの質問を一つずつ分析してみましょう。 陳寿は『三国志』の著者です。彼は諸葛亮のすぐ近くに住んでいたため、彼の記録は常に皆から高く評価されてきました。彼はかつて諸葛亮の業績を記録した際に、このようにコメントした。 原文:諸葛亮は宰相のとき、民を慰め、規則を定め、職責を明確にし、制度を守り、誠実で、正義を広めた…彼は管と蕭に次ぐ統治の才能に恵まれた人物であると言える。しかし、長年にわたり国民を動員し続けてきたが成果は出ていない。緊急事態への対応や軍事戦略が苦手なのかもしれない。 陳寿のコメントの前半では、諸葛亮の国を治める能力を称賛しています。しかし、最後の文では、諸葛亮は軍事戦略が得意ではないと述べています。そのため、陳寿でさえ諸葛亮は軍事戦略が得意ではないと言ったことから、正史における諸葛亮の軍事的才能は確かに平均的であったことがわかると多くの人が考えています。しかし、一つの事実を理解しなければなりません。陳寿はもともと蜀漢の官吏でした。しかし蜀漢の滅亡後、彼は西晋の大臣になりました。彼の立場は異なっていました。そのため、彼は諸葛亮が非常に強力であるとは表現できませんでした。そうでなければ、西晋の統治者はどう思うでしょうか? 北伐における諸葛亮の最大の敵は、西晋皇帝の祖先である司馬懿でした。陳寿は、このとき司馬懿が諸葛亮に打ち負かされたとどうして記録できたのでしょうか。結局のところ、彼はまだ西晋の朝廷に仕えなければならなかったので、諸葛亮を賢くて強い人物と表現することは絶対にできませんでした。そうでなければ、司馬懿をどこに位置づけるのでしょうか。 また、「しかし、彼は何年も人民を動員したが、成功しなかった。おそらく、緊急事態への対応や戦略の立案が下手だったからだろう!」という文章には、「為」という言葉が使われている。この「為」は、大まかに意味する。つまり、陳寿が書いたのは推論であり、諸葛亮が北伐で成功しなかったのは、おそらく彼の軍事力が低かったためだろうと述べているだけである。これは断定的な発言ではなく、特にお世辞のようにも聞こえる。 最後に、陳寿は『諸葛亮伝』の中で、「天命には天地があり、知恵によって争うことはできない」という一文も書いています。これは、諸葛亮が北伐で失敗したのは、彼の無能さのせいではなく、天命が蜀漢になかったからだという意味です。天命とはどういう意味ですか?蜀漢の国力があまり良くないという意味ではありませんか?つまり、蜀漢の国力がそれほど悪くなければ、諸葛亮が成功する可能性が高いということです!これは諸葛亮の軍事力に対する賛辞です! 一般的に、陳寿が諸葛亮の軍事能力の低さを評価したのは、実は単なる憶測であり、しかもお世辞の憶測に過ぎない。結局のところ、彼は西晋のために働いていたので、西晋の敵を称賛することは不可能だった。さらに、「天の運命は運命によって決まり、知恵で論じることはできない」という言葉は、実は間接的に諸葛亮の軍事力が依然として非常に強いことを示しています。 諸葛亮の戦術能力は良くないですか? ネットユーザーが諸葛亮の戦術能力が良くないと考える理由は、一方では諸葛亮が何度も北伐を行なったが、司馬懿を一度も倒せなかったこと、他方では諸葛亮は正面から戦うことしか知らず、型破りな戦略を使えなかったことだ。魏延の紫霧谷を放棄する計画はその一例である。 実は、この二つの疑念は根拠のないものです。正史では、最初の三回の北伐における諸葛亮の主な敵は曹真でした。曹真が亡くなった後、司馬懿が権力を握りました。当初、司馬懿は率先して諸葛亮を攻撃しましたが、打ち負かされました。その後、彼は教訓を学び、二度と諸葛亮と対決することはありませんでした。第五次北伐の際、諸葛亮は司馬懿がいつも戦闘を拒否しているのを見て、女装を利用して司馬懿を辱めたため、魏の将軍たちは激怒した。しかし、皆が憤慨すると、司馬懿は数千里も旅して戦闘を要請し、皇帝を利用して将軍たちを鎮圧し、戦う意志がないことを表明し、またこれらの言葉を言った。 原文: 梁は野心は大きいが先見の明がなく、計画は多いが決断力に欠け、軍略は好きだが力がない。10万の兵を擁しているが、私の罠に陥り、必ず敗北するだろう。 司馬懿の言葉は彼と弟との間の手紙に書かれており、彼がすでに勝利を確定させており、諸葛亮は失敗する運命にあることを意味していた。今では多くの人がこの一文を使って諸葛亮が十分に強くないことを証明していますが、実際には司馬懿は鎮圧されています!兵数で見ても軍事力で見ても、魏軍は蜀軍よりはるかに強いですが、この場合、司馬懿は戦う勇気がなかったため、諸葛亮の相手ではないとしか言いようがありません!さらに、曹魏の皇帝曹叡は第一次北伐の際に、この機会を利用して蜀漢を殲滅すると宣言しました。その結果、第五次北伐の際、司馬懿の粘り強さに直面し、彼も賛同を表明しました。これは、彼も司馬懿が諸葛亮に勝てないことを知っていたことを示しています! 多くの人々は、司馬懿が敵を育てており、諸葛亮を滅ぼせば曹叡に殺されるのではないかと心配していたため、戦いに出なかったという陰謀説を抱いている。しかし、正史では、曹叡は司馬懿を本当に恐れていたわけではない。諸葛亮の死後、曹叡は司馬懿を脇に追いやったり殺したりせず、司馬懿に軍を率いて各地で戦わせた。曹叡は最期の瞬間にも、司馬懿に孤児の世話を任せた大臣を任せた。曹叡が司馬懿をどれほど信頼していたかがわかる!敵を生かして自分を守るというのは、まったくおこがましくて無理なことだ!さらに重要なのは、敵を生かしておく方法は、「敵」に自分を脅かさせないことだ。どうして「敵」に門前で阻まれて戦えるのか?これは何の敵を生かしておくのか? また、諸葛亮は魏延の紫霧谷の計を使用しませんでしたが、それは奇妙な計を好まなかったからではなく、魏延の計の成功率が低かったからです。鹿城の戦いで司馬懿を破り、その後張郃を待ち伏せして殺害したことは、すべて諸葛亮が奇妙な計をうまく利用した例です。このことからも、諸葛亮の戦術作戦が依然として非常に強力であったことがわかります。 諸葛亮は軍事的洞察力が弱かったのでしょうか? こうした疑問を抱くネットユーザーたちは、蜀漢の国力が弱すぎたため、そもそも北伐を行うべきではなかった、これは単に資金と人的資源の無駄遣いであり、諸葛亮の軍事に対する近視眼の表れだと考えている。しかし、実は北伐を主張することは蜀漢の生存のための必要条件なのです!北伐がなければ蜀漢は滅びてしまいます! 蜀漢は外部勢力によって建国された。荊州の人々は益州に赴き、益州と東州の人々を鎮圧した。もし三つの勢力に怒りをぶつける道がなければ、蜀漢は10年以内に必ず滅亡するだろう。諸葛亮は北伐を主張した。それは一方では蜀漢の内紛をそらし、曹魏に人々の注意を集中させ、外部の利益を掌握する希望を与えるものであったが、他方では魏の正常な発展を妨げるものでもあった。 周知のとおり、三国時代の中で魏は最も強い国であり、蜀漢は最も弱い国でした。もし両者が平和的に発展すれば、蜀漢が魏を追い抜くことは絶対にできないでしょう。10年以内に、両者の国力の差はますます大きくなります。その時までに、蜀漢は曹魏を滅ぼすことができないだけでなく、曹魏に滅ぼされるかもしれません!そのため、魏と蜀の国力の差を縮め、蜀漢の滅亡を遅らせるために、諸葛亮は北進しなければなりませんでした。そして事実は諸葛亮の北伐が依然として非常に効果的であったことを証明しました! 諸葛亮の北伐の際、曹魏は疲れ果て、安心して発展することができなかった。皇帝の曹叡でさえ、諸葛亮の攻撃を常に警戒しながら、倹約して質素な暮らしをしなければならなかった。曹叡は諸葛亮の死後、すぐに態度を変え、自分の楽しみのために大規模な宮殿を建てました。これは、曹叡が諸葛亮によっていかにひどく抑圧されていたかを示しています。さらに、その後の数十年間、魏は混乱状態にあったにもかかわらず、国力が急速に成長しました。司馬昭がついに権力を握ると、彼は直接蜀を滅ぼす戦争を開始し、蜀漢をいとも簡単に殺し、世界に衝撃を与えました。 一般的に、陳寿の「諸葛亮の軍事力は良くない」「諸葛亮は司馬懿を倒せなかった」「戦術力は良くない」「戦略的なビジョンが欠けている」というコメントは、すべて問題があります。正史における諸葛亮の軍事力は非常に強かったのです。次に、正史における諸葛亮の軍事力がどれほど強かったかを見て、どのようにして司馬懿を倒したかを見てみましょう。 司馬懿は、軍隊を迅速かつ決断力があり、正確かつ容赦なく運用することを重視した人物でした。孟達を襲撃し、遼東を征服し、王陵を全滅させたとき、司馬懿は電光石火の速さで突然攻撃し、敵の不意を突いたのです。しかし、諸葛亮と対峙したとき、司馬懿の策略は通用しなかった。鹿城の戦いで、司馬懿は初めて諸葛亮と戦い、5,000の黒甲冑を失うという大敗を喫しました。 原文: 5月23日、張郃は南衛の武当の首領何平を攻撃し、安中路から梁を攻撃するよう命じられた。梁は魏延、高襄、呉班を派遣して抵抗させ、彼らを打ち破った。彼らは3,000の甲冑、5,000組の黒甲冑、3,100本の角弓を奪取した。その後、宣王は陣営を守るために戻った。 この戦いでの司馬懿の損失に注目してください。鎧3,000段、黒鎧5,000枚、角弓3,100本です。古代では、誰もが戦闘で鎧を着ることができたわけではなく、エリートだけが鎧を着る資格がありました。つまり、この戦いで諸葛亮は少なくとも3,000人の司馬懿のエリート兵士を全滅させました。武器と弓が非常に多いため、一般兵士に換算すると、この戦いで司馬懿は1万人以上の人を失った可能性があります。もちろん、司馬懿の面目を保つために、『晋書』はこの戦いを認めず、諸葛亮が負けたとしています。しかし、諸葛亮は最初の北伐に失敗したとき、自分自身を3階級降格しました。この戦いの後、諸葛亮は自分自身を降格しませんでした。『晋書』のこの戦いの記録は隠蔽の疑いがあることがわかります。 敗北後、諸葛亮は李厳の妨害により撤退を余儀なくされました。司馬懿はこれを受け入れず、面目を保とうと、張郃を追撃させました。その結果、張郃は諸葛亮の待ち伏せを受けました。結局、五子の名将である張郃は諸葛亮に殺されました! 大きな損失を被った司馬懿は、もはや諸葛亮と戦う勇気がなかったため、諸葛亮が第五次北伐を開始したとき、司馬懿は全軍に直接戦闘を行わないよう命じ、諸葛亮の食料と草を枯渇させる準備をして待機した。諸葛亮が北伐の際、すでに食糧危機を解決していたことは、あまり知られていない。一方では、木製の牛と流馬によって穀物の輸送効率が高まり、他方では、諸葛亮が魏の領土で直接土地を耕作し、穀物を貯蔵していたことから、諸葛亮が長期戦を戦っていることが明らかになった。だから、このまま長引けば、司馬懿は間違いなく負けるでしょう!残念ながら、諸葛亮の体は司馬懿ほど強くなく、多くの後悔を残して早世してしまいました! しかし、諸葛亮の死の時期に、司馬懿の演技は再び人々を笑わせました! 司馬懿が諸葛亮を恐れ、正面から戦う勇気がなかったことは誰もが知っています。 では、諸葛亮の死後、司馬懿はどのような反応を示しましたか? 蜀軍が撤退したと聞いて、司馬懿は面目を保つために、すぐに部隊に追撃を命じました。 しかし、姜維が旗を掲げて太鼓を打ち、戦闘態勢をとると、司馬懿はすぐに怖がって逃げ去り、「死んだ諸葛が生きている中大を怖がらせた」というジョークだけが残りました。 司馬懿が諸葛亮を恐れすぎていたのは感動的です! 原文: 楊毅らは軍を編成して出陣したが、民は走って宣王に知らせたが、宣王は彼らを追いかけた。姜維は易に旗を掲げ、太鼓を鳴らして宣王を攻撃するかのように命じた。宣王は退却し、攻撃する勇気はなかった。そこで易は軍を整えて出発し、谷に入ってから葬儀を告げた。宣王が退位したとき、人々は「死んだ諸葛は逃げ、生きている中達は逃げる」ということわざを作りました。誰かがこれを宣王に伝えると、宣王は「私は生を予言することはできるが、死を予言することはできない」と言いました。 |
<<: 宋代の女性はなぜ「河東獅子」になることを敢えてしたのでしょうか?河東ライオンとは何ですか?
>>: 宋代の儒教の流派は何ですか?宋代にはどの学派が主流だったのでしょうか?
推薦する
『Bookside Stories』の執筆背景を教えてください。どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】澄み切った秋空にホルンの音が響き、兵士たちは監視塔に寄りかかる。春風が緑の墓に向かって...
岳飛物語第3章:岳先生は密室で生徒たちに教え、周先生はテントを張って生徒たちに教える
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
西遊記で最も強力な神は誰ですか?千里眼と超耳は最大のボスですか?
西遊記には多くの強力なキャラクターが登場します。最初は誰もが孫悟空が最も強力だと思っていました。しか...
西秦の君主、奇夫沐墨の簡単な紹介。奇夫沐墨はどのようにして亡くなったのでしょうか?
斉夫沐墨(?-431年)は、斉夫沐墨とも呼ばれ、字は安司馬といい、河西出身の鮮卑人である。西秦の文昭...
ソエツは歴史上忠実な大臣だったのでしょうか? ソエツを判断する方法
スオ・エトゥは忠実な大臣ですか?中国の歴史には王朝や歴史上の人物が多すぎます。後世の人々は彼らを忠臣...
「趙献州を斉河に送る」をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
趙献州を旗山へ送り出す王維(唐代)私たちは会うときには笑い、別れるときには泣きます。先祖伝来のテント...
第二集の第一巻は、巡礼者たちが金剛般若経を無造作に読み、獄から釈放された僧侶が巧みに法会を終えたという驚きの記録である。
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
『紅楼夢』の賈宝玉の性格的特徴は何ですか?賈宝玉の簡単な紹介
賈宝玉の紹介賈宝玉は、中国の古典小説『紅楼夢』の主要登場人物で、易洪王子、紅洞花王、金持怠惰男として...
東周時代の物語:唇と歯が破壊される
はじめに:西方の君主には斉の桓公よりも 2 つの特技がありました。それは、心が広く、忍耐力が強く、ど...
岑申の古詩「冬宵」の本来の意味を理解する
古代詩「冬の夕べ」時代: 唐代著者: セン・シェン冷風が天地を吹き渡り、温泉や温泉井は閑散としている...
五夷十六国の時代、傅充には何人の兄弟がいましたか? 傅充の兄弟は誰でしたか?
傅充(?-394年)は、洛陽県臨衛(現在の甘粛省秦安市)出身のディ族で、前秦の高帝傅登の息子である。...
『西遊記』では孫悟空が桃を盗んだ。なぜ桃園の地主はその事実を隠したのか?
『西遊記』で孫悟空が桃を盗んだのに、なぜ桃園の地主はそれを隠したのでしょうか?これは多くの読者が知り...
西王母の本来の姿は半分人間、半分獣だったのでしょうか?彼女はどうやって不死になったのでしょうか?
私の国の神話は長い歴史があり、それぞれの神話はロマンに満ちています。その中でも、西王母に関する美しい...
なぜ宋代には繁栄がなかったのでしょうか?宋代の経済と文化は十分に発達していなかったのでしょうか?
中国の王朝は秦漢の時代から、漢・三国時代、両晋・南北朝時代、隋・唐時代、五代、宋・元・明・清時代を経...
『紅楼夢』で、林黛玉が賈宝玉に酒を飲ませた後、賈おばあさんはその状況をどのように対処しましたか?
賈祖母は、施夫人とも呼ばれ、「紅楼夢」の主人公の一人です。Interesting Historyの編...