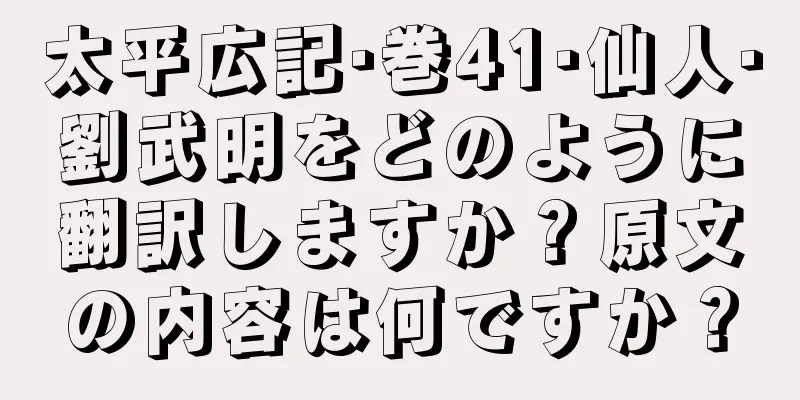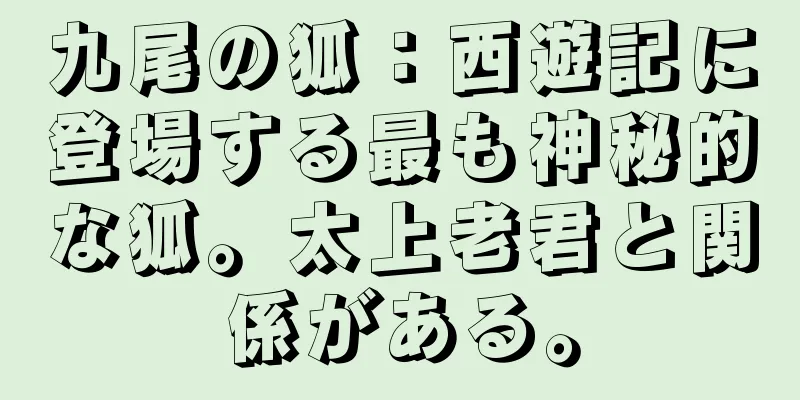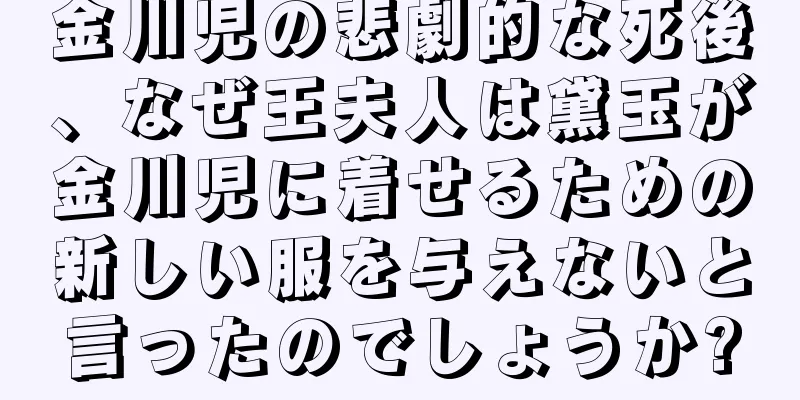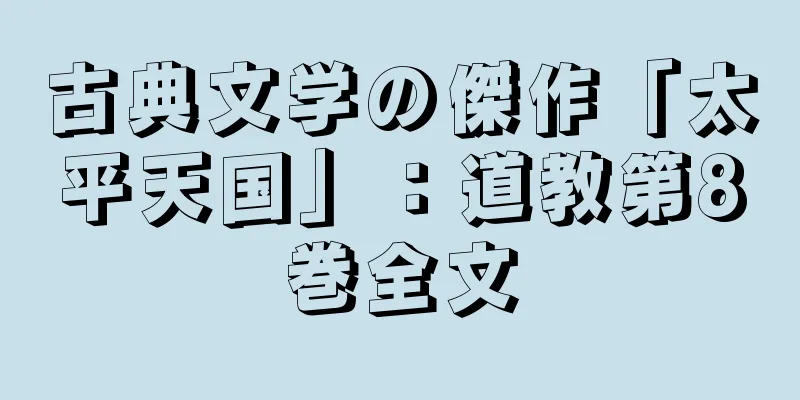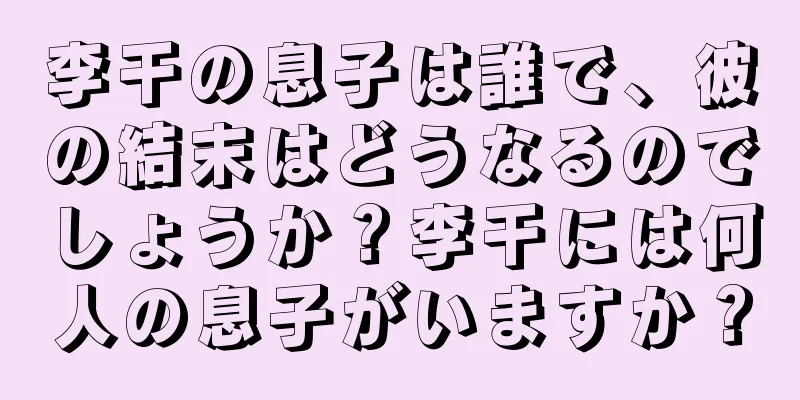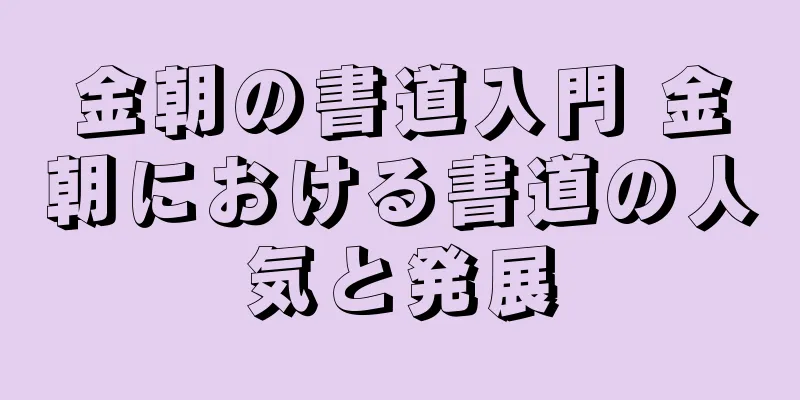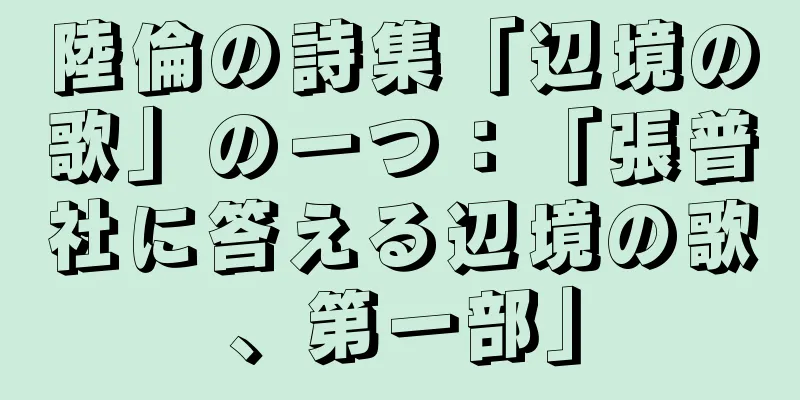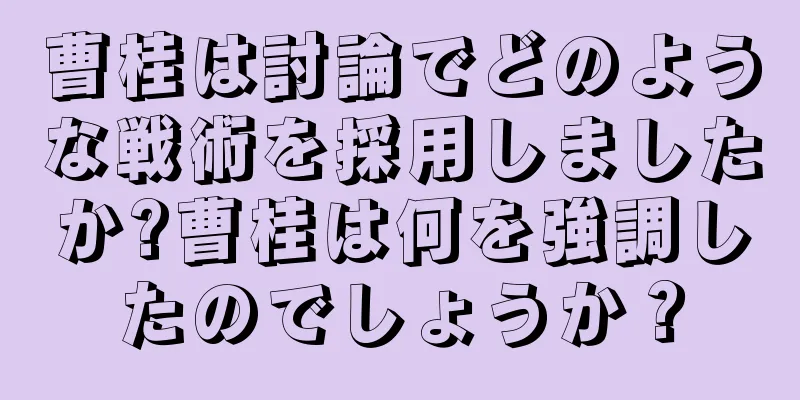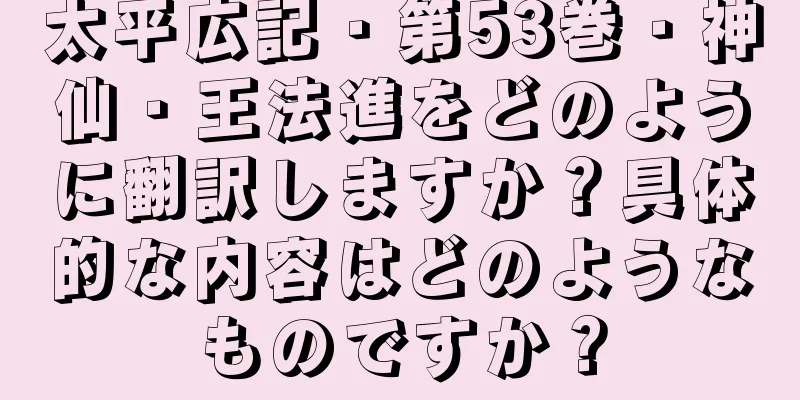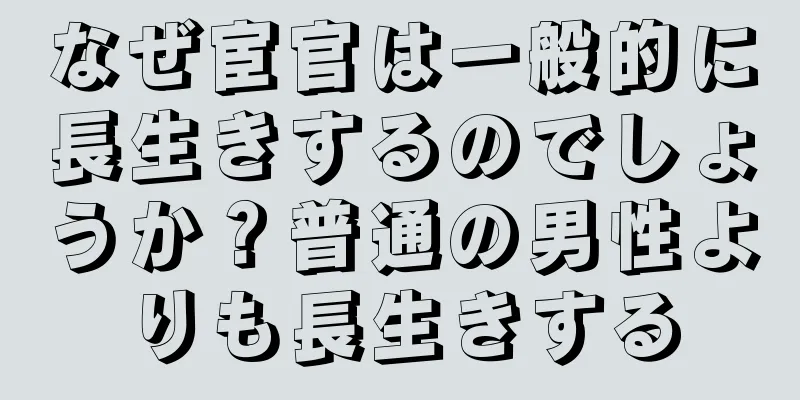なぜ曹操は強力な将軍を華雄と戦うために派遣しなかったのでしょうか?勝てないのではないかと不安ですか?
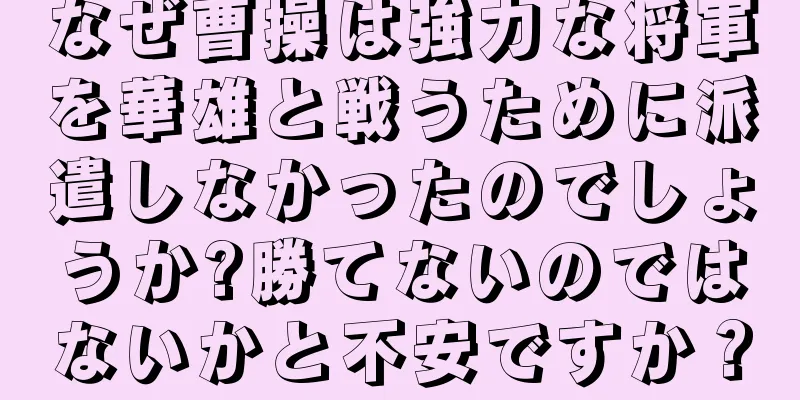
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、華雄が泗水関の前で数人の将軍を殺し、非常に傲慢だった様子を詳しく描写します。なぜ曹操の将軍たちは彼に追いつけなかったのでしょうか? 見てみましょう! 華雄は董卓の下で二番目に有力な将軍と言ってもいいでしょう。最も有力な将軍は言うまでもなく呂布です。華雄が初めて登場したとき、彼は「身長9フィート、体は虎、腰は狼、頭は豹、腕は猿」と描写されました。華雄は非常に強い戦闘能力を持つ屈強な男であることがわかります。そして、華雄のその後の戦闘記録も、彼の優れた武力を存分に証明しました! 華雄は戦場に出るや否や、鮑忠を直接殺害し、諸侯連合軍を不意打ちした。その後、華雄は再び孫堅と戦い、孫堅を惨敗させ、孫堅を恥ずかしげもなく逃走させ、孫堅配下の猛将祖茂を殺害した。諸侯連合軍の中で、孫堅の戦闘力は非常に強く、名声も高かった。黄巾軍を平定したとき、孫堅はその超戦闘力で名を馳せた。当時、誰もが孫堅に期待していたと言える。しかし、華雄との戦いで孫堅は容赦なく敗北し、華雄が扱いにくい相手だったことが分かりました。 華雄に対処するのは簡単ではないので、王子たちは知恵を絞って華雄を倒す方法を考え出す必要があります。しかし、同盟のリーダーである袁紹が提案したとき、他の者たちはただ反応せず、その場面は非常に気まずいものとなった。実際、ここから、当時の王子たちは実は隠れた動機を持っていて、全力で戦うつもりはなかったことがわかります。彼らは皆、躊躇していたのです。 諸侯たちの間での議論はゆっくりと進んでいたが、華雄は軍を率いて攻撃し、猛烈に挑発した。諸侯たちはそれぞれに下心を持っていたが、華雄の挑発を我慢できなかった。そこで袁術は勇敢な将軍の于社を派遣して華雄と戦わせた。3ラウンドも経たないうちに、于社は華雄に殺された。于社が亡くなった後、韓馗の配下の将軍、潘鋒が大斧を手に戦いに赴いた。潘鋒は大斧で戦い、将軍だったため戦闘能力も高かったに違いない。しかし、一瞬のうちに殺されてしまった。諸侯たちは二人の将軍を立て続けに失ったことで少し慌て、他の者を戦いに送る勇気はなかった。次に、勇敢で無敵の関二業が登場し、「温かい酒で華雄を殺す」という古典的なシーンが生まれました。 物語全体から判断すると、戦いの早い段階で華雄は十分に準備しており、基本的に王子たちの下では華雄の敵となる者は誰もいなかったため、騎馬弓兵の関羽が戦いを申し込んだとき、王子たちは関羽の戦いへの参加を承諾した。身分が重んじられたその時代、劉備ですら君主にすらなれなかった。関羽は騎馬弓兵だったので、身分はさらに低かった。袁術の言葉を借りれば、それは実は当時の状況をよく表している。 原文: 袁術はテントの中で叫んだ。「君主たちは、我々に大将軍がいないと騙そうとしているのですか? 弓兵一人しかいないのに、よくも馬鹿げたことを言うものだ! 私と一緒に戦え!」 しかし、現在の視点から見ると、袁術の言ったことは極めて間違っています。なぜなら、英雄は出自で判断されるものではないからです。実力がある限り、他人を見下してはいけません。しかし、当時の王子たちの立場で考えてみてください。彼らは非常に多くの人々を集め、数え切れないほどの勇敢な将軍を抱えていました。華雄との戦いで数人が亡くなったものの、彼らは人手不足ではありませんでした。その結果、このとき小さな騎馬弓兵が現れ、華雄を倒せると主張しました。これは王子たちの顔を平手打ちするのと同じではありませんか?通常、誰がこれを容認できるでしょうか? しかし、18人の王子のうち、異議を唱えた袁術を除く他の王子たちは実際にこの状況に同意し、曹操は率先して関羽を救出しました。これにより、誰かがこの背後にいるのではないかと疑われます。このような状況は実際の戦場では起こり得ません。 実は、この背後で操っていたのは羅管中だったのです! 普通に考えれば、関羽は身分の低い弓騎兵に過ぎず、諸侯は関羽が出陣することを決して許さないでしょう。それは諸侯の侮辱となるからです。しかし、羅管中が行動を起こすと、諸侯は屈服せざるを得ず、この状況に黙認するしかありませんでした。そして実は、この華雄は関羽を挑発するためだけに存在しているのです! 三国志演義では、華雄も董卓の部下ではあったものの、二番目に強い将軍ではなかった!三国志演義では、華雄が諸侯の中であれほど強く無敵だったのは、実は羅貫中が故意に彼を褒めたからである。彼を褒めた目的は、実は関羽に彼を殺させ、関羽の名声を高めるためだった!さらに、正史では華雄は孫堅に殺された! 『三国志』: 孫堅は再び軍を集めて楊仁で戦い、そこで卓の軍を破り、総司令官の華雄らを斬首した。 正史では、華雄を殺したのは孫堅だが、『三国志演義』では、孫堅を倒して関羽に殺されたのは華雄であり、「温酒で華雄を殺す」という暗示も生み出した。この賞賛と非難の交互は、羅管中の目的を示すのに十分である!彼は華雄を使ってすべての王子を粉砕し、華雄の超戦闘効果を強調し、次に関羽を戦場に出して華雄を収穫させ、関羽の比類のない無比を強調したかった。はっきり言えば、羅管中は関羽が非常に強力であることを証明するために、このような長い文章を書いたのです。曹操は関羽に目を付けていたため、当然ながら強力な将軍たちは道を譲らざるを得ませんでした。この時代、この場所では、関羽に比べれば他の全員は脇役であり、主役である関羽に道を譲らざるを得なかったのです。 実際、温かい酒で華雄を斬首したことに加え、その後の顔良と文愁の斬首も、関羽の無敵さを強調するために羅貫中が特別に手配したものだった! 白馬の戦いでは、顔良が20ラウンドで徐晃を破り、曹操の将軍たちは戦うことを恐れた。しかし、これまでの説明によると、曹操の配下だった許褚と夏侯惇はどちらも必死の男で、呂布と死闘を挑んだのに、なぜ顔良と対峙すると突然沈黙したのでしょうか?これは明らかに、羅管仲が意図的にやったことで、主人公の関羽を紹介し、関羽が顔良を簡単に殺せるようにして、関羽の強さを際立たせるためでした!正直に言うと、当時の顔良が呂布に取って代わられたとしても、羅管仲の記述によれば、関羽は呂布を殺すこともでき、一刀両断で殺す可能性も非常に高いのです! 延津の戦いでは、文秀は十分な準備を整え、張遼と徐晃の包囲に直面し、まず弓矢で張遼を射て落馬させ、敵の一人を減らして包囲を免れ、それから徐晃と戦いに向かった。文周の行動から判断すると、彼は非常に戦略的であり、包囲されることをうまく回避した。そして最後には徐晃を倒し、慌てて逃げ去らせたが、これは文周の武術の腕が非常に優れていたことを示している。羅貫中は文周を勇敢で機知に富んだ人物として描写し、非常に印象的だったと言える。その結果、選ばれた関羽と対峙した文周は、わずか3ラウンドで撤退を決意したが、これは驚くべきことだった。 原文: 突然、旗をはためかせた十数人の騎兵が現れ、剣を手にした将軍が彼らに向かって駆けてきた。関羽は叫んだ。「逃げるな、邪悪な将軍!」彼は文周と戦い始めた。3ラウンドも戦わなかった後、文周は怖くなり、馬を回して川沿いに逃げた。関公は速い馬に乗って文周に追いつき、剣で文周の頭の後ろを切りつけ、馬から落とした。 原文によると、文殊は3ラウンド後に逃げたとあるが、これは実はかなり怪しい!文殊は、顔良と同じくらい有名な、戦争経験が豊富な天下の名将だった。趙雲と50ラウンドから60ラウンド戦ったが、明確な勝敗は出なかった。どうしてたった3ラウンドで撤退して逃げることができたのか?これは明らかに、羅貫中のもう一つの意図的な計略だった。関羽の勇敢さを強調するために、彼は再び文殊を関羽の剣に送り込んだのだ! 全体的に、羅管仲は三国志演義全体を通して関羽をとても気に入っていました。華雄、顔良、文殊の存在はすべて関羽を引き立てるものでした。そのため、泗水関の前では、華雄がいかに傲慢で暴れ回っていたとしても、羅管中は王子たちに華雄と戦わせることはしませんでした。なぜなら、華雄は関羽のものだったからです。 実際、たとえ羅貫中が関羽を戦わせなかったとしても、当時の曹操が部下を率いて華雄を倒すことは基本的に不可能だったでしょう。曹操が将軍たちに戦わせなかったのはそのためです。 漢の霊帝の治世中、曹操はすでに朝廷の官吏となっていた。彼は黄巾の乱を鎮圧する戦いにも参加し、非常に優れた功績を挙げた。しかし実際には、董卓が朝廷に混乱を引き起こす前、曹操には独立した派閥はなく、独自の有力な将軍もいなかった。当時の彼の部下はすべて朝廷によって任命された人々だった。董卓が洛陽に入り、曹操が不満を抱き董卓のもとを去るまで、曹操は兵士を募集し、軍隊を指揮し始めた。 当時、曹操に降伏した最初の猛将は楽進でした。しかし、三国志演義における楽進の戦闘能力はそれほど強くありませんでした。彼の最高の戦績は、曹覇と凌統との引き分けでした。彼も一流の将軍と見なされていましたが、彼のレベルはまだ比較的弱いものでした。華雄は祖茂を楽々と殺し、王子たちを頭が上がらないほどに打ち負かした。彼のレベルは間違いなく一流であり、楽金は華雄に敵わなかった。 曹操に寝返った二番目の将軍は李典だった。しかし、李典の個人的な武芸は楽進よりもさらに悪かった。新野の戦いでは、わずか10ラウンドで趙雲に敗れたが、これは彼のレベルが一流でさえなかったことを示し、華雄にはまったく敵わなかった! 夏侯惇と夏侯淵の二人の兄弟は後に曹操に寝返った。この二人の兄弟の戦闘能力はまだ優れていたが、戦闘に参加したばかりで戦闘経験が不足していたため、当時のレベルからすると、たとえ戦場で華雄と戦ったとしても、華雄を倒すことはできないかもしれない。これは夏侯惇が呂布に数戦で敗れたことからもわかります。当時の夏侯惇はまだ十分に強くありませんでした。夏侯惇の本当の強さは、一連の戦争の後に爆発しました。濮陽の戦いでは、呂布を阻止して負けることなく、彼の力が後に成長したことを示しています。董卓と戦っていた時期、彼の強さは十分ではありませんでした! 夏侯惇と夏侯淵の兄弟の次に曹操に寝返ったのは曹仁と曹洪であった。この二人の兄弟の実力も優れているが、欠点は夏侯兄弟と同じである。彼らは皆、戦場に立つのは初めてであり、レベルも比較的低い。戦争の試練を経験して初めて、彼らは良いレベルで活躍できる。したがって、現時点では彼らは華雄の敵ではない。 一般的に曹操は配下に多くの勇将を抱えていたことで知られていましたが、董卓との戦役期間中、実際に配下にいた勇将は楽進、李典、夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪の6人だけでした。この6人は当時戦闘経験が不足しており、華雄に敵いませんでした。まさにこの理由から、曹操は彼らを戦いに行かせず、関羽に代わって戦いに行くよう激励したのです。 |
推薦する
杜神艶の『蓬莱三宮宴会図と中南山御勅答詩』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
杜神艶の『蓬莱三宮宴会及中南山詩文』、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!...
「三雑詩第3番」は沈全奇が書いたもので、明確な反戦感情が表れている。
沈全奇(656年頃 - 715年頃)、号は雲青、湘州内皇(現在の安陽市内皇県)の出身で、祖先の故郷は...
馮玄の「契約を燃やして正義を買う」 孟昌君田文の物語「契約を燃やして正義を買う」
戦国時代、斉の孟嘗公には馮玄という家臣がいた。最初、馮塵は田文が客をもてなすのが楽しいと聞いて、遠く...
孫斌と龐樂は二人とも桂甫子の弟子だったのに、なぜ弟子入りを終えた後に敵対するようになったのでしょうか?
孫斌と龐娟は桂姑子に師事し、学業を終えると、野望を叶えるために次々と隠遁生活を送りました。龐攸は幸運...
水滸伝で宋江がなぜそれほど名声を得ているのでしょうか?それは何に依存しているのでしょうか?
宋江といえば、まず人々の頭に浮かぶのは、中国古代四大古典の一つ『水滸伝』に登場する涼山の英雄のイメー...
李徳の民族性に関する論争とは何ですか?
李特(?-303年)、通称玄秀は、巴族の人で、巴西当曲(現在の四川省営山)の出身です。李特は東羌の狩...
『紅楼夢』の賈容はどんな人物ですか?とても賢い人
以下は、興味深い歴史の編集者がお届けする『紅楼夢』の賈容とはどんな人物でしょうか?興味のある方は、以...
辛其儒は江東安伏寺の参事を務め、『太昌寅:呂樹千に建康中秋の夜を捧げる詩』を著した。
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
第11章:周三衛は指示に従って剣を与え、宗六首は真の才能を取ることを誓う
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
「筆記体スクリーン」の作者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
草書体 韓維図 屏風スクリーンはどこにありますか?そこには明らかに懐素の痕跡が映っています。埃で汚れ...
釈迦牟尼の本名は何でしたか?釈迦牟尼はどこの出身ですか?
釈迦牟尼が悟りを開いた後、すべての人は彼を尊敬して釈迦牟尼と呼びました。では、釈迦牟尼の本名は何でし...
『紅楼夢』の美しい詩の評論
曹雪芹の『紅楼夢』は、小説の詩的な傑作である。流れるような散文には詩の香りが漂います。 『紅楼夢』に...
秦の恵文王が皇帝に金の雄牛を送ったという話は何ですか?秦の恵文王はなぜこのようなことをしたのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が秦の恵文王...
『紅楼夢』で平児が二度目に大観園を訪れたとき、何をしましたか?
『紅楼夢』を読んだことがない人でも、劉おばあさんが賈邸を訪れた話は聞いたことがあるでしょう。以下の記...
白居易の詩「妻が鶴の歌を奏でるのを聞いて韋止に答えてその意味を説き、四行の韻を踏む」の本来の意味を鑑賞する
古詩「韋子の返事、妻が鶴の歌を奏で別れるのを聞いて、その意味を4行加える」時代: 唐代著者: 白居易...