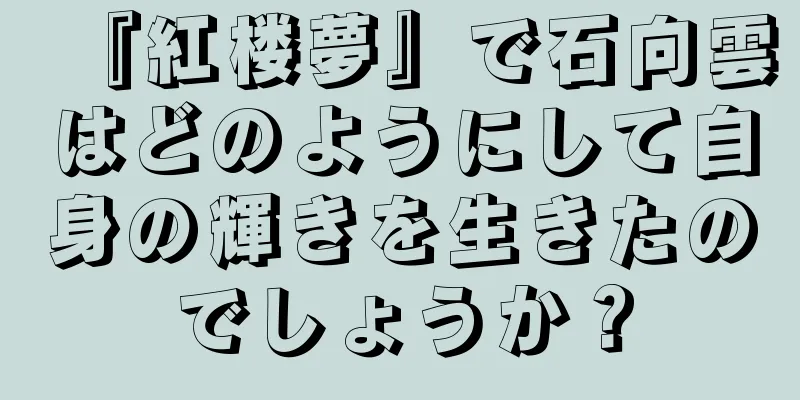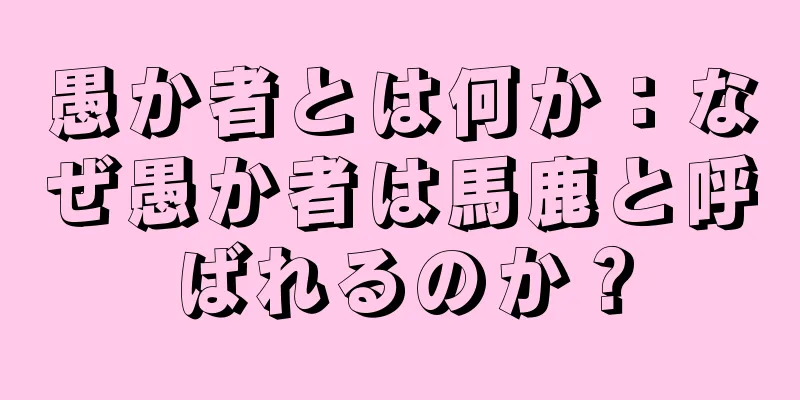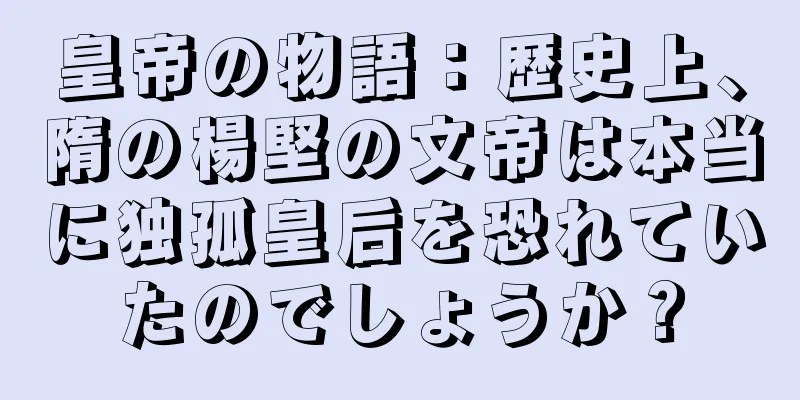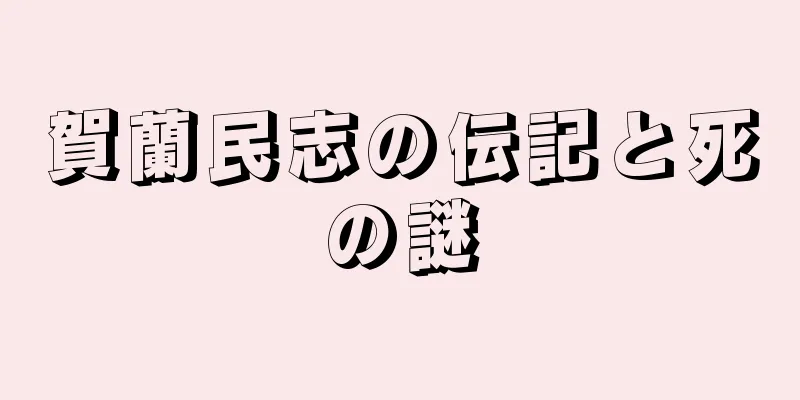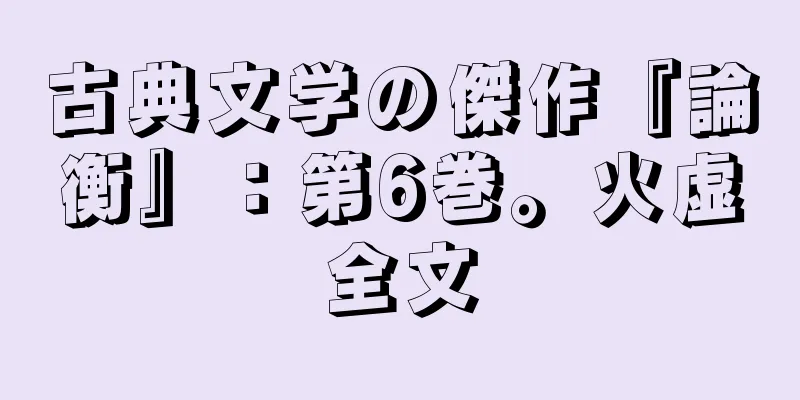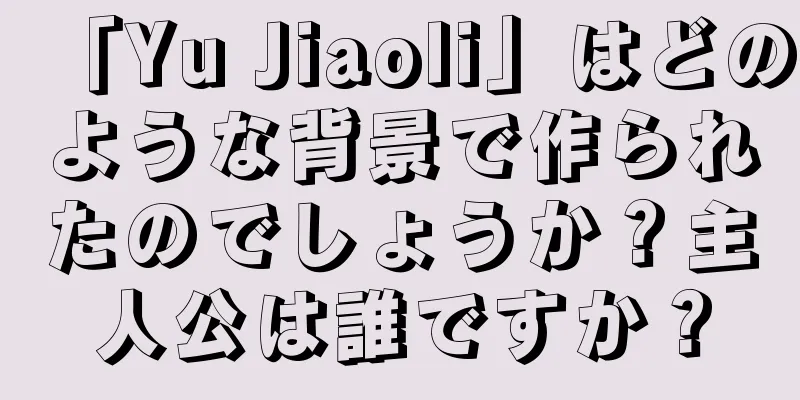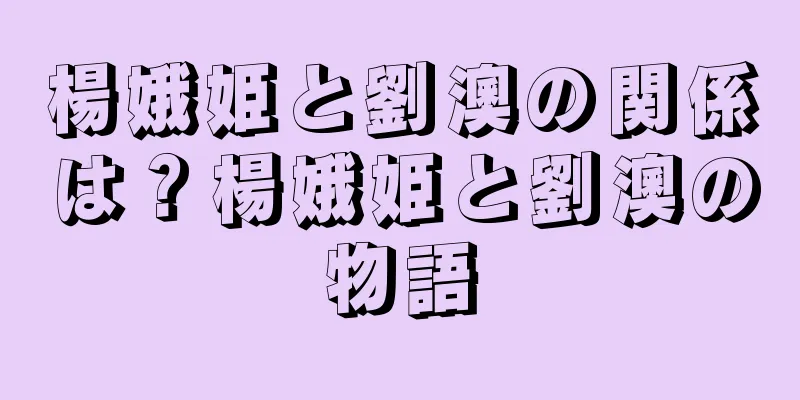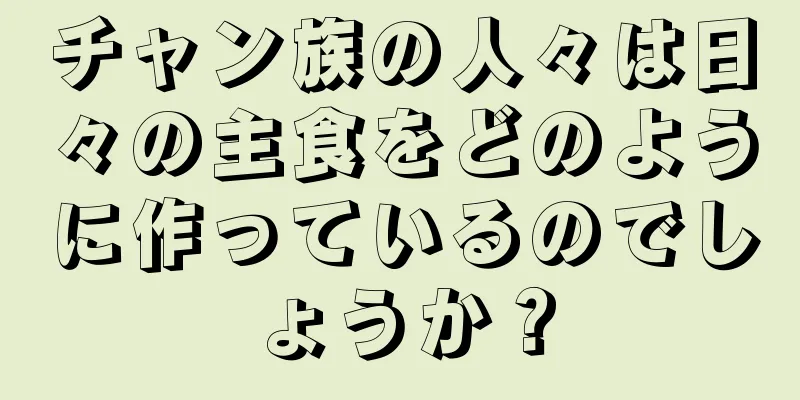頤和園の40場面のうち最初の「正大光明」はどのようなものですか?
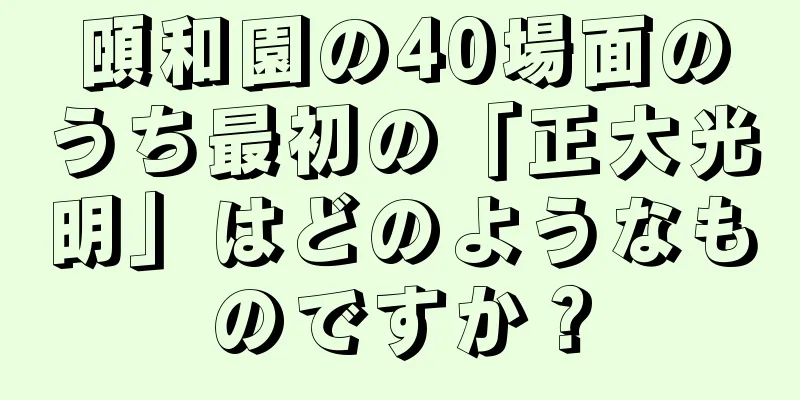
|
頤和園の40景のうち最初の鄭大光明はどのようなものですか? 頤和園の正門の中に鄭大光明があります。頤和園の40景のうち最初のものです。実は、頤和園は清朝皇帝の前の王朝のものです。このシーンは、南の宮殿門の大衝立壁から始まり、北の正大光明殿の後ろの寿山で終わります。長さは370メートル、東西は如意門で囲まれています。幅は310メートル、面積は10万平方メートル、建築面積は7,000平方メートルです。 レイアウト 仙良門は、頤和園の二番目の宮殿門としても知られ、5つの部屋と雍正帝によって書かれた「出贤良」という4つの文字の額を持つ南向きの門楼です。門の内側には7つの大きなホールがあり、内側の軒の高いところには雍正帝が書いた「正大光明」という4文字の額が掲げられています。このホールは、皇帝が朝廷での会議を開いたり、庭園で外国の使節を迎えたりした主要なオフィスでした。その機能は、故宮の太和殿や保和殿と似ています。 1725年(雍正3年)に完成した正大光明殿は、正味の幅が36.45メートル、中央ホールの幅が5.22メートル、全体の奥行きが16メートル、ホールの奥行きが12.16メートル、軒柱の高さが5.12メートルである。 正大光明の東西両側には、茶室、書斎、茶室、軍事室の5つの脇殿があります。正大光明殿は幅7間、奥行き5間で、前面と背面に廊下があり、灰色の瓦と寄棟屋根を備えています。館内には、雍正帝の「天の心をもち、昼夜勤労し、民の喜びを楽しみ、天地を調和させ、情を喜ばせる」という聯合と、乾隆帝の「安穏を求め、成功を見よ、手の届かないものはない、時宜に適って育てば、必ず居場所が見つかる」という聯合が飾られています。東壁には勅書『周武易』が掛かっており、西壁には『賓馮図』が掛かっている。殿の後ろには竹や石が置かれた寿山があり、後に頤和園の仁寿殿に移された。 関連資料 乾隆帝の『頤和園四十景』の詩より: 「オープンで公正」 庭園の南側、仙良門の内側には、彫刻や絵画がなく、松亭と茅葺き屋根の宮殿のスタイルを持つ正政庁舎があります。家の後ろには、尖端がギザギザの急峻な石垣が立っています。前庭は広々としていて開放的で、壁の外には木陰があり、赤や紫の花が果てしなく咲き誇っています。 この景勝地は霊園であり、古来の掟が豊かな春を守り続けています。この功績は短期間で成し遂げられ、易の世代は陳の中で永遠に生き続けるだろう。 易府の庭は玉で覆われ、圓波の水は銀のように流れている。緑の草は倹約を表し、山の静けさは慈悲深さを反映しています。 四角い部屋に行くことしかできないのに、なぜユジンのことを話さなければならないのか。壮大な建物を管理し、才能ある人材を呼び込みましょう。 心は常に澄み渡り、環境は涼しく、煩悩から解放されます。皇帝の馬車は、地方政府から一切の費用をかけずに雲関まで頻繁に移動されました。 商売は繁盛し、神の力も湧き出てきます。私はいつもあなたのことを考えていて、常に警戒しています。 |
>>: 頤和園の四十景の一つ「精進と徳」とはどのようなものなのでしょうか?
推薦する
水滸伝で、宋江はなぜ命をかけて趙蓋に手紙を届けたのでしょうか?
『水滸伝』の中心人物である宋江について、Interesting Historyの編集者と一緒に探って...
五代魏承班の「花宮雪降る」原文解説と鑑賞
花でいっぱいの宮殿、雪が降る五代:魏成班雪が降って、風が吹いて、玉浪はどこで飲んでいるのでしょうか?...
「漁夫の誇り:秋の思索」の鑑賞、詩人ファン・チョンヤンは陝西省の副使であり、兗州の知事でもあった
范仲厳(989年10月1日 - 1052年6月19日)、号は西文。彼の先祖の故郷は汀州であり、後に蘇...
宋王朝は歴史にどのような貢献をしましたか?これらの寄付は何に使われるのでしょうか?
本日は、Interesting History の編集者が中国の歴史における宋王朝の貢献についてご紹...
「魏鋒邸で曹将軍の馬図を観る」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
魏鋒の記録官邸、曹将軍の馬画を見る杜甫(唐代)建国以来、馬と鞍をつけた馬を描いた最も素晴らしい絵画は...
辛其記の『漢宮の春:会稽秋峰閣の昔を懐かしむ』:著者は長い間引退を望まなかった
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
唐代の詩人、図思空による『二十四の雅詩』の原文と注釈付き翻訳
屠思空(トゥ・シコン)の『二十四の詩 優雅』に興味がある読者は、Interesting Histor...
Geという姓の男の子に付ける名前にはどのようなものがありますか? Ge! のような詩的な意味を持つ赤ちゃんの名前を共有します。
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が赤ちゃんの...
金王朝はモンゴルと南宋の攻撃によって滅亡しました。モンゴルは西方への遠征の前になぜ金王朝に奇襲を仕掛けなかったのでしょうか?
本日、Interesting Historyの編集者がモンゴルの西征の物語をお届けします。金王朝はモ...
火山噴火の法則とは何ですか? 火山噴火の影響はどれくらい大きいですか?
西暦79年のある日の午後、イタリアのベスビオ山が突然噴火し、近くの2つの小さな町が噴火によって噴き出...
秦強で火吹きの技術を練習するには?どのようなフォームがありますか?
まだ分からないこと:秦強の火吹き法の練習方法とは?どんな形式があるの?秦強、通州邦子、西府秦強、...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 金持ち男』の原文の筋書きは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
中国のスタジオからの奇妙な物語からの「金持ち」の原文金持ちには多くの商人がお金を貸している。ある日、...
水力天文台の歴史的意義は何ですか?水力天文台の誕生は何を象徴するのでしょうか?
水力天文台は、北宋時代に蘇宋、韓公連らが発明・製作した大型の自動天文観測機器です。水車から出る水で駆...
馬超には劉備が信用できないと思わせるような個人的な「黒歴史」があったのだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古典文学の傑作『論衡』:第3巻:事物と情況の章の全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...