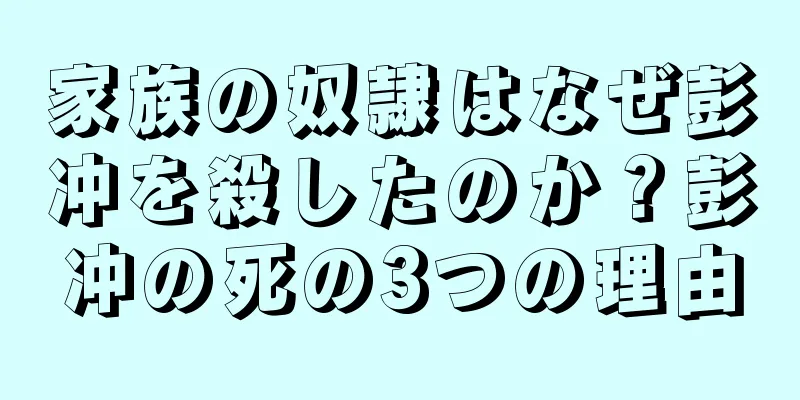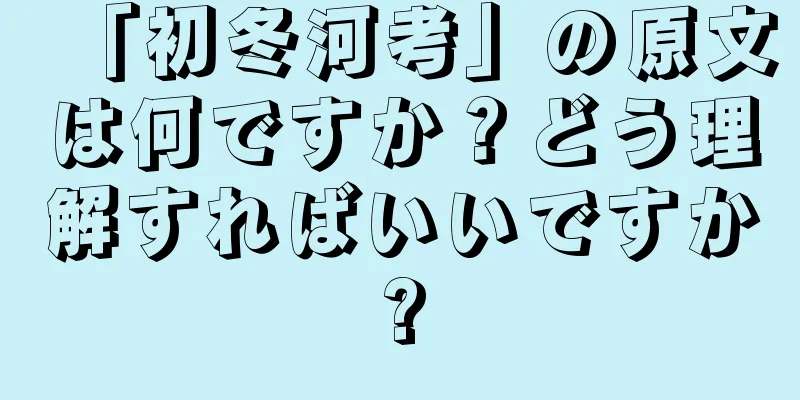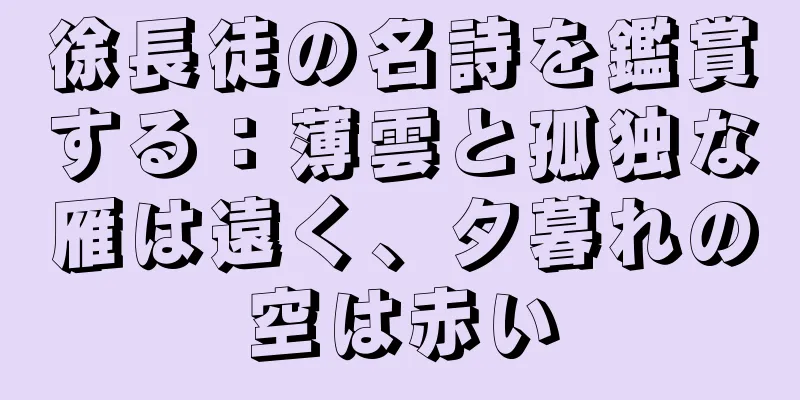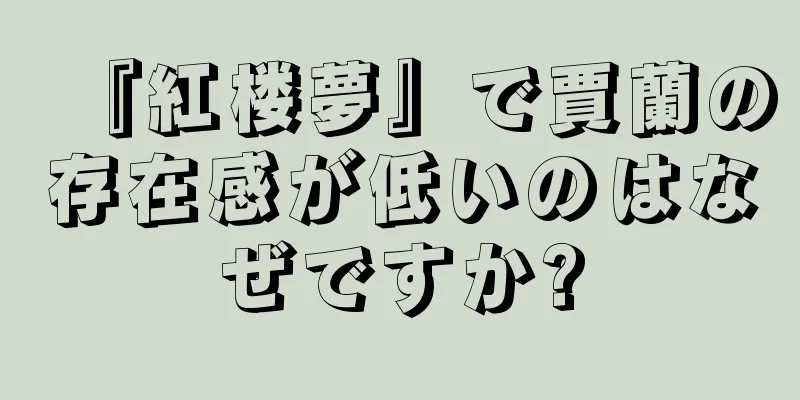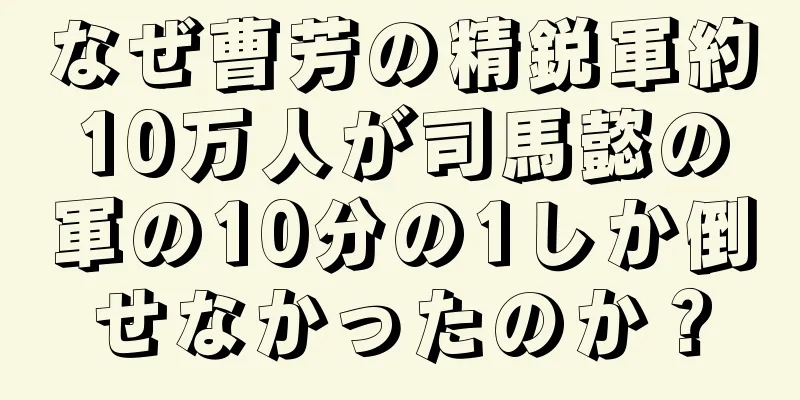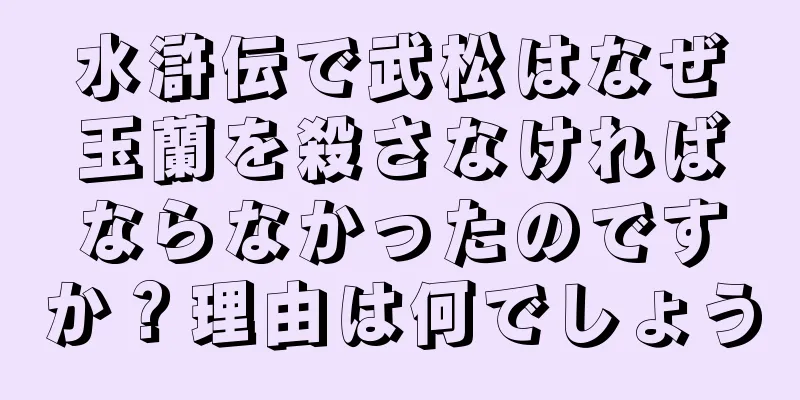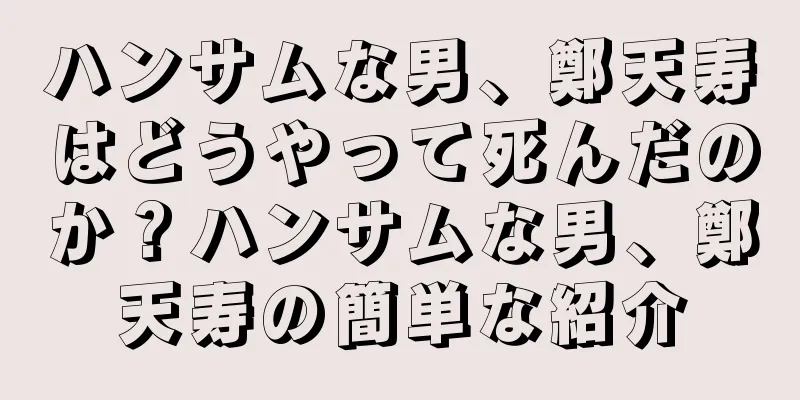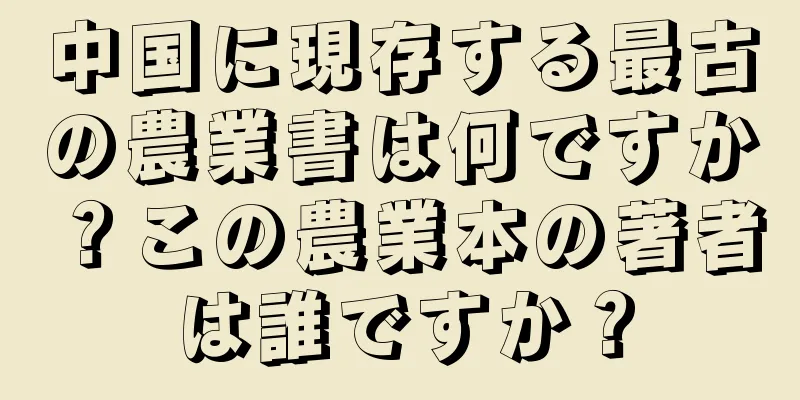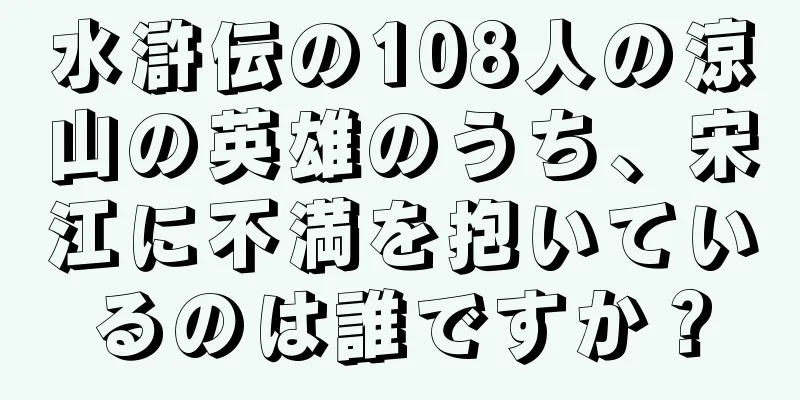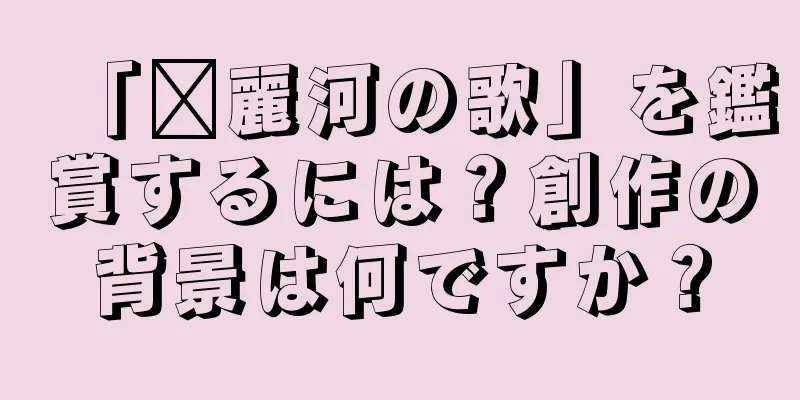杜甫の詩「蔡希曾大尉を竜游に送り、高三十武に手紙を送る」の本来の意味を理解する
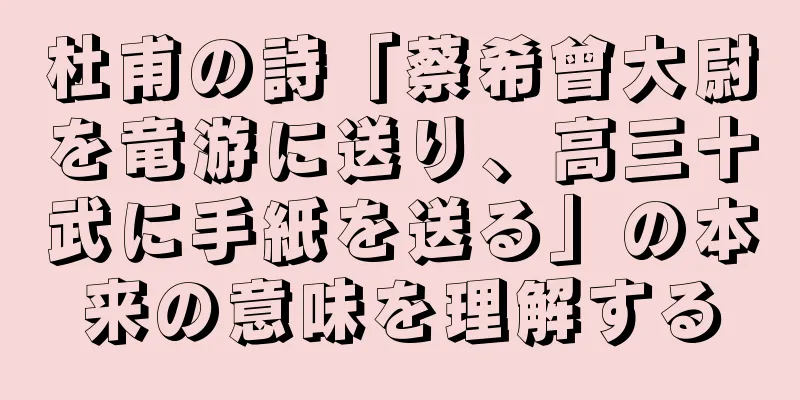
|
古代詩「蔡希曽大尉を竜游に送り、高三十武に手紙を送る」 時代: 唐代 著者: 杜甫 蔡紫勇は弓で胡族を射る習慣を身につけた。勇敢な男は勇敢な男でいるよりもむしろ死ぬまで戦うことを好む。 役人は先駆者であり、才能と運命をもって課題に立ち向かわなければなりません。軽い鳥が飛び去り、何千人もの人々が銃を構えて叫ぶ。 官庁が開くと雲の幕が開き、春城は上都へ向かう。馬の頭は金色のマントで覆われ、ラクダの背中はぼやけた錦で覆われています。 雲と山への道はすぐそこにあり、私は青海の端まで飛んで戻ります。公爵は依然として彼を支持しており、将軍が先導している。 漢の使節は黄河から遠く離れていたため、涼州の小麦は枯れてしまった。ニュースについて尋ねられたので、幸いなことに阮元宇がここにいます。 作品鑑賞 【注釈】: (原注:葛叔が報告にやって来て、蔡子に先に戻るように命じた。) 【朱注】『同鑑』:天宝14年の春、葛叔は朝廷に赴いたが、途中で脳卒中を起こし、都に留まった。そのため、蔡総督が先に戻り、公爵が見送りました。もし彼が11年目に宮廷に行くとしたら、それは冬であり、春に宮廷に行くことと矛盾するだろう。孟弼の発言は真実ではない。 『唐書』:各県に浙州都衛が 1 人ずつおり、各県に左国一都衛が 1 人ずついる。毎年冬になると、軍司令官が5つの学校を率いて、軍隊の隊列を組んで戦う方法を教えました。 蔡紫鎔は西方で弓を射て胡族を狙う習慣を身につけた。勇敢な男は学者であることを恥じるよりも、むしろ死ぬまで戦うことを好む。役人は先駆者であり③、人材は挑戦に立ち向かわなければならない④。軽い鳥が飛び去り、何千人もの人々が銃を構えて叫ぶ。 (蔡旭は野心が強く、激しい性格で、死ぬまで戦うことを好んだと伝えられている。当時は軍が優遇され、儒学者であることを恥じていた。世は次第に文学を蔑視するようになった。一羽の鳥が飛んでその速さを見た。一万人が叫び、その鋭さを恐れた。) ①『漢氏外伝』:「弓を曲げて射る。」漢の桓帝の治世中の童謡:「胡と戦う西の英雄はどこにいる。」 ②陳林の月府:「辺境の町には勇士がたくさんいる。」曹植の詩:「彼の名前は戦士のリストにあります。」 習近平は言った:戦士と勇士は兵士の名前です。天宝14年11月、都に10万人の兵士が徴集され、文武の英雄と呼ばれた。陳林の月府:「男はむしろ戦場で死ぬことを好む。」 ③ 咸豊、注釈は第2巻にあります。 ④『韓書・項羽伝』:「私は王に挑戦する用意がある。」 注釈:「挑戦とは、敵を挑発して戦いを求めることである。」 ⑤ 魏定の詩:「一羽の鳥が突然お互いに驚いた。」 張静陽の詩:「突然、それは通り過ぎる鳥のようだった。」 ⑥ 開元12年4月、皇帝は4つの軍の槍と戟を緋、緑、赤、青で区別するように命じた。 「玄宗の石路」:吐蕃が国境を侵略したとき、漢は半分折れた槍で攻撃を防ぎ、彼らを攻撃した。 『項羽伝』:「一万の敵を倒せるように学べ。」 杜牧の詩:「鷲を撃つ将軍は一万の敵を倒せるが、黒蛇の将軍は鳥のように軽い。」 これに基づく。 雲のカーテンが宮殿を開き、春城は上都へと向かいます。馬の頭は金色のビーズで覆われ、ラクダの背中はぼやけた錦で覆われています。雪を頂いた山道はもうすぐそこ⑤、青海の端まで飛んで戻ります⑥。公爵は依然として彼を支持しており、将軍が先頭に立っています。 (次の部分は蔡との別れを描写し、入朝して龍の元に帰ることを記している。官庁の役人は葛叔韓と称する。韓に恩恵が与えられ、韓は留まるとされる。先鋒は蔡が一人で行くことを言う。) ①王朱は言った:軍の司令部はテントだ。 『西都雑記』:成帝は甘泉に雲の幕を張った。 ② 沈月詩「春城は白日の下に美しい」 彼は言った:昔、首都は一般的に上都と呼ばれていました。保応元年になって初めて、景昭県は上都と呼ばれました。班固の『西都賦』:「それを私の上都にせよ。」 ③古詩:「頭に金の手綱をつけた馬。」 『西都雑記』:楊勝の『衝上賦』:「衝上は密で、私の王を覆っている。」 鮑昭の詩:「彫りの衝上は密で、幕は巻き上がっている。」 姜燕の『河上山賦』:「ワニは密で、巻き上がっている。」 『雲慧』:「猼7、ぐるりと回る様子。」 これは、金の手綱をつけた馬の頭を指し、その形は密で巻き上がっています。 ④『唐書』:葛叔韓が龍游にいた時、使者を派遣して報告させた。彼はいつも白ラクダに乗って、一日に500マイルも旅した。趙氏は言う。「せむしは錦のスカーフで覆われているので、ぼやけています。」 「猼7」と「模糊」はどちらも方言です。 ⑤【銭注】「環宇記」:古蔵南山は雪山とも呼ばれ、冬も夏も雪が降らず、武威県に属しています。樊河県の南側には天山、雪山とも呼ばれる山があり、その幅は千マイル以上あり、その高さで知られています。 『元河県及び国記』:雪山は瓜州金昌県の南60マイルにあり、夏でも雪が溶けず、南は吐谷渾の境界に繋がっている。 ⑥『詩経』:「家に帰り、高く飛ぶ。」青海、注釈はこの巻を参照。 ⑦『翟方金伝』:春秋実録の趣旨によれば、最も尊敬される官吏は「翟」と呼ばれる。 『晋書』には太夫と太保はともに高官であると記されている。 『易伝』:「軍隊に所属するのは縁起が良い、それは天からの恩恵である。」 ⑧『二の帝への手紙』:「突撃将軍は真っ先に前進する。」 突撃将軍は勇将や飛将のように突撃することができ、突撃騎兵も意味する。 「詩」:「王のために道を先導する。」 漢の使節は黄河から遠く離れていた①ため、涼州の小麦は枯れてしまった②。ニュースについて尋ねられたので、幸いなことに、Ruan Yuanyu③がここにいます。 (最後の部分は、高に手紙を送る意図についてです。川は遠く、麦は枯れています。秋の辺境は寒いです。高が来たので、彼の消息を尋ねたいです。漢の使者は蔡を指し、袁羽は高を指します。この章の最初の2つのセクションはそれぞれ8つの文で構成され、最後のセクションは4つの文で構成されています。) ①『荊楚水史記』:漢の武帝は張騫に大夏に行って川の源流を探すよう命じた。 『穆帝の行幸』:黄河は街市から南西に流れ、東に曲がって敦煌、酒泉、張掖各県の南に入り、条河と合流する。現在、唐代の龍游路によれば、漢代の龍渓、張掖、酒泉などの県と黄河がこの地域を流れていることが分かります。漢江は隴渓に源を発しているが、一文に二つの川を使うのは適切ではないので、漢使の助言に従うべきである。 ②「唐直」:涼州は武威県であった。孟弼曰く、「龍渓記録」:晩秋になると、各国は白麦を収穫して酒を造る。 【銭注】陳蒼麒の『本草綱目』:「黄河と渭河の西では、白麦は涼しい。春に植えられるため、2つの季節の気候に関係している。」顧延武曰く:杜の『通典』:涼州は白麦10石を貢いだ。 ③【朱注】幸いなことに、それは質問の言葉です。 『同監』:高力士が皇帝の勅令を発表し、「将軍と兵士は皆善良である」と述べた。白居易の詩:「善良なのは李士君である。」 『魏志・王燕伝』:阮玉は、号を元玉といい、若い頃、蔡雍に教育を受けた。太祖は彼を司空軍の軍事顧問と書記に任命した。軍書と国書のほとんどは陳林と阮玉によって書かれた。欧公の「詩談」:陳世仁は易経を追って、偶然に杜甫の旧版を手に入れたが、そこには多くの欠落や誤りが含まれていた。 「蔡大尉に別れを告げる」という詩の中で、「私の体は鳥のように軽い」という部分の下の単語が抜けています。陳氏と数人のゲストはそれぞれ単語を付け加えたが、「速い」と言う人もいれば、「落ちる」と言う人もいれば、「下がっている」と言う人もいたが、誰も決めることができなかった。その後、彼は良いコピーを手に入れましたが、そこには「過ぎ」という言葉がありました。陳さんは驚き、たとえそれがたった一語であっても、あなたたちはそのレベルに達することはできないと思いました。 |
>>: 杜甫の古詩「臨沂の山閣に着いたとき、李元外を思い、彼に感銘を受けた」の本来の意味を理解する
推薦する
古代の疫病神は誰だったのでしょうか?古代の疫病神の起源の詳細な説明
古代の疫病神は誰だったのか?これは多くの読者が関心を持っている質問です。疫病神について話すには、まず...
『紅楼夢』では、江玉漢はついに西仁と結婚しました。それは本当に自発的なものだったのでしょうか?
希仁は『紅楼夢』でも宝玉の心の中でも非常に重要な役割を果たしているが、宝玉はそんな大切な人を江玉漢に...
製紙技術の発明の過程はどのようなものだったのでしょうか?製紙技術に関する歴史的記録にはどのようなものがありますか?
製紙は中国の四大発明の一つです。紙は古代中国の労働者の長年の経験と知恵の結晶であり、人類文明史上傑出...
「竹枝二歌第一番」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
竹の枝の詩二首黄庭堅(宋代)浮雲は百八回循環し、夕日は四十八回輝きます。地獄の門は遠いなどと言わない...
Hu Lei という名前はどこから来たのですか?琵琶との違いは何ですか?
「胡雷」という名前は、一般的には「演奏すると突然雷鳴が鳴る」と解釈されるためこの名前が付けられました...
秀雲閣第19章:仙人が洞窟に集まって道教を論じ、華天翁が国外で神秘を語る
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
古代における王朝交代の根本的な理由は何ですか?古代の改革の目的は何でしたか?
古代の王朝交代の根本的な理由は何でしょうか? 古代の改革の目的は何でしょうか? Interestin...
劉炳忠の「南湘子・南北短長閣」:人生に対する前向きな見方を表現している
劉炳忠(1216-1274)は、本名は劉観、雅号は鍾会、号は蒼春三人で、邢州(現在の河北省邢台市)の...
『紅楼夢』で黛玉の趙叔母さんに対する態度はどのように変化しましたか?なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
趙叔母は『紅楼夢』の登場人物です。賈正の妾であり、賈丹春と賈歓の母です。以下の記事は、Interes...
『三朝北孟慧編』第110巻の原文には何が記録されているか?
延星の次の巻。それは建炎元年正陰5月1日に始まり、丸一日で終わりました。建延元年5月1日、大元帥の庚...
朱棣は荊南の戦いで勝利した後、建文帝のように諸侯の権力を弱め続けましたか?
朱雲文は朱元璋の前で孝行を装い、即位するとすぐに叔父たちを皆殺しにし、ある者は追放し、ある者は殺し、...
清朝の「康熙帝全図」を描いたのは誰ですか? 「康熙帝全領地図」にはどんな場所が含まれていますか?
本日は、Interesting History の編集者が「康熙帝の帝国領土の完全な地図」をお届けし...
もし崇禎が首都を南に移転することに成功したら、南部の役人たちは彼を支持してくれるだろうか?
崇禎帝は明朝の法定皇帝として、南下すれば当然南方の支持を受ける。しかし、南方の勢力が表面的には支持し...
張王はどれくらい強いですか?クラゲの女王を倒し、黄色い眉毛のモンスターを恐れないでください
『西遊記』には、王菩薩国師の弟子である張王が登場します。張王が才能を発揮した瞬間から、若いにもかかわ...
思想家王夫之が美学の直接性を重視したのは禅宗の影響でしょうか?
王扶之は明代末期から清代初期の著名な思想家であり、黄宗熙、顧延武とともに清代の三大啓蒙思想家の一人で...