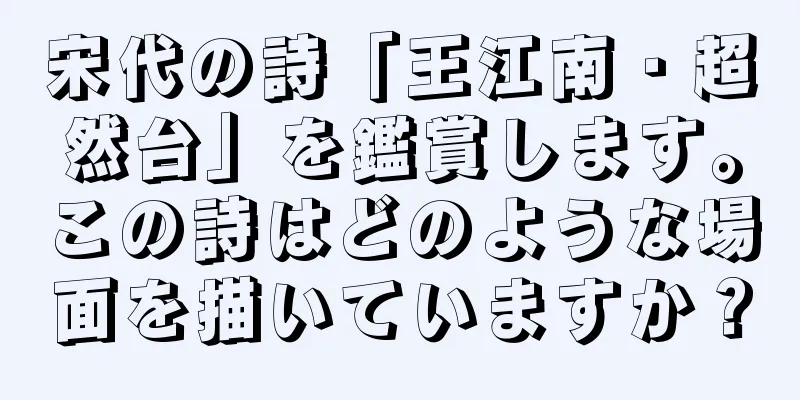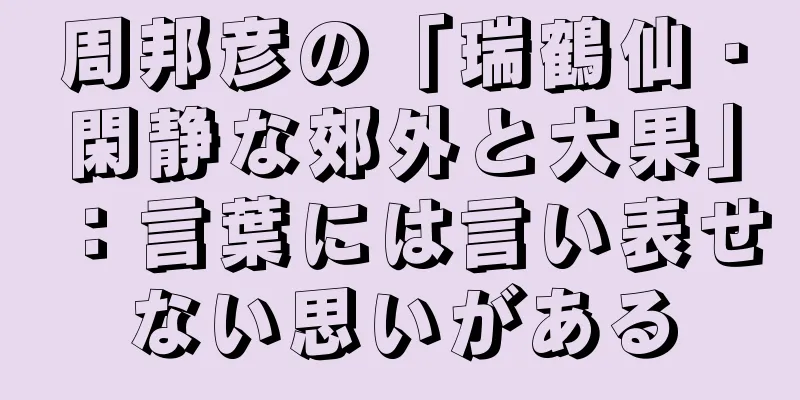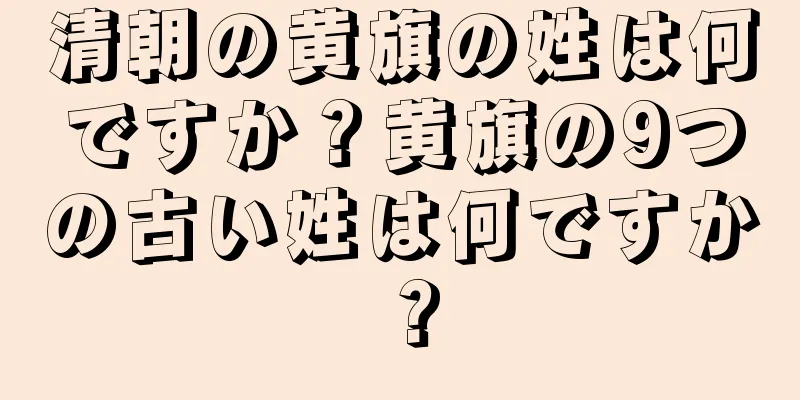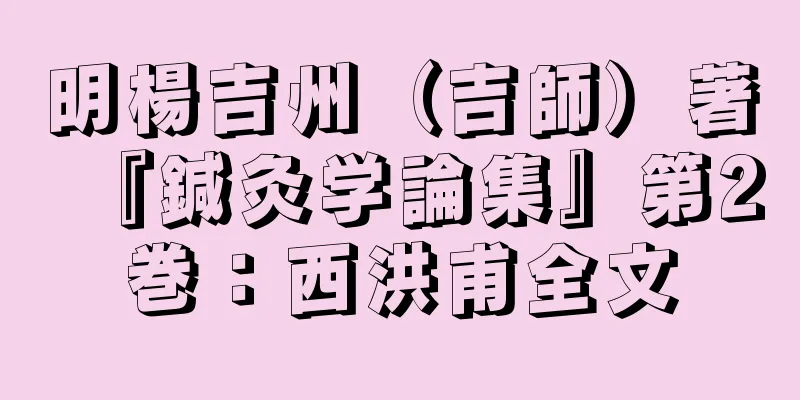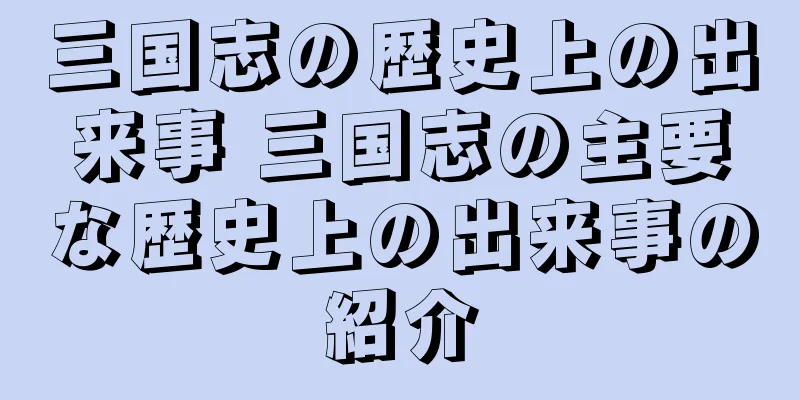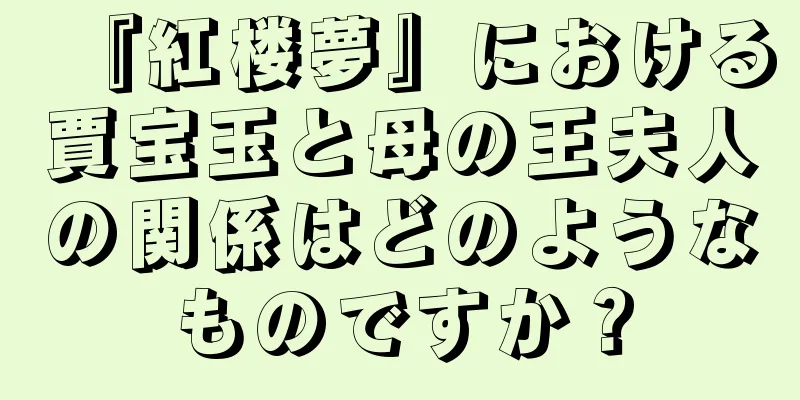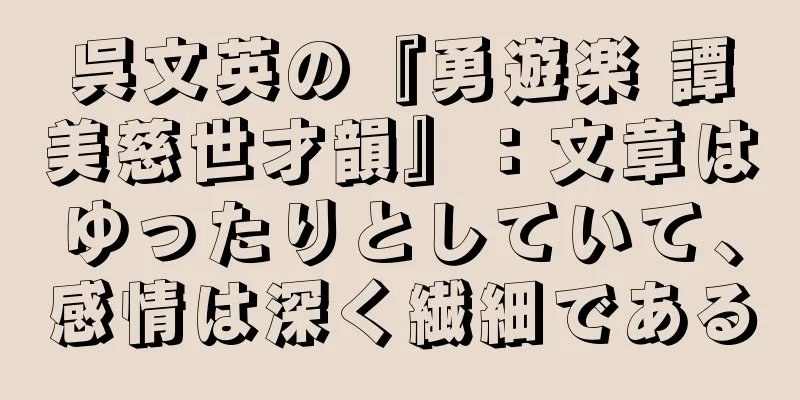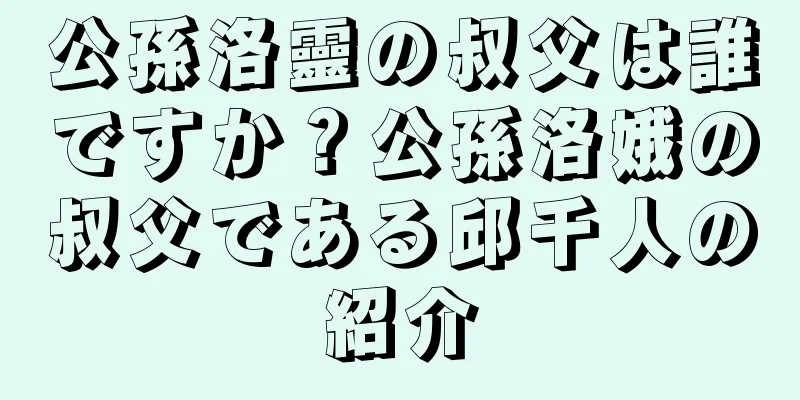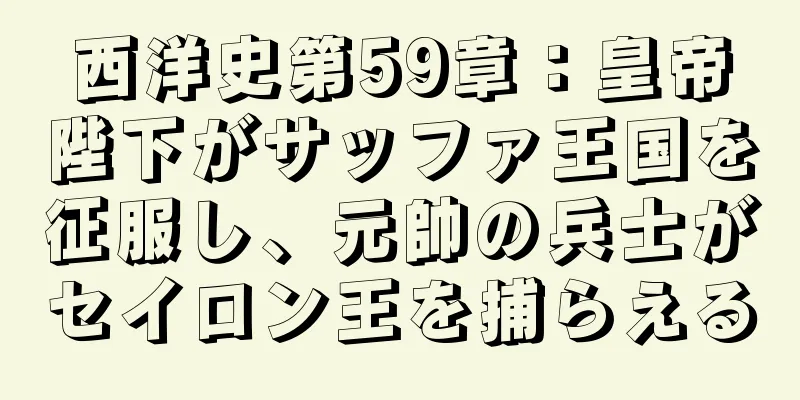「山と川は違うが、月と空は同じ」ということわざはどこから来たのでしょうか?この文の歴史的背景は何ですか?
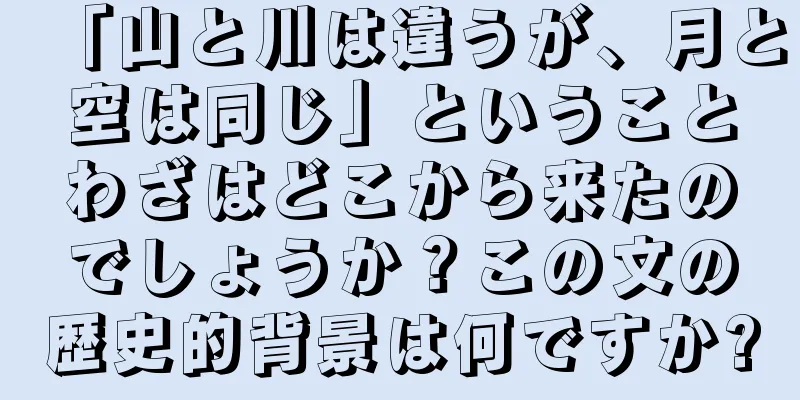
|
今日は、おもしろ歴史編集長が「山川は違えど月と空は同じ」の歴史的背景をお届けします。皆様のお役に立てれば幸いです。 最近、「山河異にして風月同」という言葉を聞いたことがある人は多いだろう。この言葉は日本が中国に寄贈した医薬品にも書かれていた。初めて聞いたという人も多いだろう。美しい言葉だが、意味がよく分からない人も多い。実はこの言葉には非常に深い歴史があります。そこで今日は、この歴史を学び、なぜ日本人がこの言葉を使うのか調べてみましょう。 1. 「山川は違えど、月と空は同じ」ということわざの由来 「山と川は違うが、風と月は同じだ」という詩について話しましょう。 この詩の作者は日本の「長屋王」です。『全唐詩』の注釈には「長屋は日本の宰相なり」とあります。長屋は天武天皇の孫で、高市王の長男です。684年に生まれ、729年に亡くなりました。当時の日本政治の重鎮でした。長屋王はかつて一揃いの袈裟を作り、中国の僧侶に贈ったが、その袈裟にこの詩を刺繍した。おそらく唐の玄宗皇帝の治世初期のことだろう。詩の全文は次の通りです。山と川は違うが、風と月は同じである。将来、絆を築けるよう、仏陀の子供たち全員に送ります。 この詩の最も大きな歴史的影響は、高僧鑑真が日本に対して極めて好意的な印象を抱くようになったことである。 742年、唐に留学していた日本の僧侶容睿と普昭が揚州の鑑真を訪ね、鑑真に優れた弟子を日本に送るよう依頼した。鑑真はこう答えた。「南越寺禅師が亡くなった後、倭国に生まれ変わり、仏教を広めて衆生を救ったと聞きました。また、日本の長屋王が仏教を尊び、この国の偉大な僧侶に与えるために千着の法被を作ったと聞きました。法被の縁には、「山河は違えど風月は同じ。仏子たちに贈る。縁を結ぶためだ」という四つの文が刺繍されていました。これを見ると、この国はまさに仏教が繁栄する縁のある国なのです。」 2. その歴史的背景は何ですか? この記録は、日本の僧侶である元楷が書いた『唐代東征大和尚伝』の中に見ることができます。長屋王が法服を贈ってくれた親切は、間違いなく鑑真が招待を受け入れて日本へ渡る決意を強めた。彼は弟子たちに、日本へ行って説法するというこの「遠き招き」に応じる意志のある者はいるかと尋ねたが、弟子たちは皆沈黙していた。当時の唐人の目には、日本は辺鄙で野蛮で未開の地だった。弟子の項厳によると、「国は遠すぎて、そこで生きていくのは難しく、海は広大で、行くところもなく、人間であることは難しく、中国に生まれることも難しい」とのこと。海を渡るリスクは高く、人間として生まれ変わるのは容易ではなく、中国で人間として生まれ変わるのはさらに難しいため、「僧侶たちは皆沈黙していた」という。これを見た鑑真は容瑞と普昭の方を向いて「あなたたちが去らないなら、私も去ります」と言った。 容睿と普昭は鑑真を招き、日本政府から与えられた使命を遂行するために東方へ旅立たせた。 733年に唐に到着して以来、二人は洛陽、長安などの著名な僧侶を訪問し招待したが、鑑真に会うまで成果はなかった。 日本政府が高僧を雇うために唐に人を派遣した理由は2つあります。まず、仏教が日本に伝来した後、長い間、完全な戒律体系が形成されておらず、特に、正式に戒律を授ける資格を持つ「三師七証」(計10人の僧侶)がいなかった。そこで、元興寺は、外国(範囲は唐代に限らず、高麗、インドなどの僧侶も含む)から戒律を授ける資格を持つ僧侶を雇用するよう嘆願書を提出し、皇帝の許可を得た。第二に、当時の日本では、税金や労働奉仕を逃れるために密かに出家する人が多く、それが国の財政収入や労働徴兵に影響を与えていました。資格を持った戒律師を雇用し、試験、戒律、戒律授記、公的検証の完全なシステムを確立することは、私的な戒律授記が蔓延している社会現象を変えるのに役立つでしょう。 唐の玄宗皇帝天宝2年、すなわち743年に鑑真と21人の志願兵が初めて東方への航海に出ました。彼らと一緒に旅をしていたのは、容睿らの招待を受けた道航(有力な大臣であった李林甫の弟の「家僧」)と如海(高麗の僧)であった。道航は自己評価が高く、如海を見下している。彼は如海が「教育を受けていない」という理由で、如海が東へ渡ることに反対している。激怒した汝海は地方政府役所に行き、道航が海賊と共謀するために船を建造して海に出て、「500人の海賊を街に誘い込む」計画を立てていたと告発した。地元政府は容睿、普昭、道航らを逮捕した。 4か月に及ぶ捜査の後、ル・ハイは虚偽の告発によりむち打ち刑60回を宣告され、ダオ・ハンとその取り巻きは釈放され、船舶は政府の財産として没収された。 同年12月、鑑真は二度目の東方への航海を行い、80名以上の僧侶、職人、画家などが同行した。出航後すぐに、船は風と波で損傷し、全員が船を修理するために陸に上がるしかなかった。船は修理後、3回目の東方への航海に出発したが、舟山に着いたところで再び座礁し、全員が再び上陸して明州(現在の寧波市にあった県都)のアショーカ王寺に一時滞在することになった。この間、ある「越州の僧侶」が、容睿らが中国僧侶を日本に誘い込んだと政府に通報した。容睿は地元当局に逮捕され、首都に送られた。容睿は死を偽装し、杭州を通過する際に逃亡した。 天宝三年、皆は四度目の東河渡河の準備をし、食糧と船を買うために福州へ向かった。霊游ら弟子たちは鑑真が再び東方へと旅をして命の危険にさらされることを望まなかったので、政府へ報告しに行った。このグループは黄岩県の政府当局者に捕らえられ、自宅に連行された。 天宝7年、容睿と普昭は再び揚州に行き、鑑真に会い、5回目の東航を計画した。一行は6月に揚州を出発したが、ハリケーンに遭遇し、海南島に到着するまでに10日間以上海上を漂流した。鑑真一行は海南に1年以上滞在し、天宝9年に雷州半島を経由して北上し、広西に迂回し、広東省と江西省を通過した。鑑真は北へ戻る途中、目の病気を治せると主張する外国人に出会った。そのインチキ医者は、もともと「視力が弱かった」鑑真を完全に失明させた。容睿も北へ戻る途中で亡くなり、普昭にとって大きな打撃となった。揚州に行って地方の役人に逮捕されるのも嫌だったし(鑑真を東へ誘い出した罪で)、高齢で体が弱い鑑真に海を渡って東へ向かうよう勧め続けるのも耐えられなかった(すでに63歳で、最も信頼していた弟子の襄厳も亡くなっていた)、途中で鑑真に別れを告げた。 天宝12年(753年)10月、遣唐使の藤原清河とその一行は鑑真を訪ねるために揚州へ向かった。藤原らは鑑真に、鑑真が東方へと5回航海したことはすでに知っていると告げ、都に着いたとき、使節団は唐の玄宗皇帝から鑑真が東方へ渡航する許可を得ようとした。しかし、唐の玄宗皇帝は「道教徒に行かせよ」と命じ、使節団が僧侶ではなく道教徒を日本に連れ帰ることを期待した。藤原は鑑真に、危険を冒して密輸し、6度目の日本行きを決めるよう頼んだ。鑑真は肯定的に答えた。 10月19日、鑑真とその一行は外交使節団とともにひっそりと揚州を出発し、12月10日に日本に到着した。彼は東方への航海を6回行い、合計12年を要した。 754年、鑑真は平城京に入り、東大寺大仏殿の前で聖武天皇、孝謙天皇、そして400人以上の僧俗衆に戒律を与えました。 758年、日本の朝廷は鑑真の功績を称え、「大和賢」の称号を授け、太子の旧居を鑑真の修行の場として寄進しました。これが後に有名な唐招提寺となりました。 3. 日本はなぜこの文章を書いたのでしょうか? 鑑真は10年間日本に住んでいました。この10年間の鑑真特有の状況(主に政治的な状況)については、学界でも意見が分かれています。王相栄の著書『鑑真』では、鑑真は思想概念の違いにより、日本の朝廷から無視され、「奈良古派」から追放されたとされている。重要な証拠の一つは、淳仁帝が758年に即位したその日に、鑑真を大住職の地位から解任したということである。王金林は、「鑑真は日本で支持され、尊敬されていた」と確信しており、その解任は「まず鑑真自身の申し出だった」と考えている。その証拠として、『元衡時書』には「この日、(大和尚に)鑑真という称号が与えられた。初めて大住職になった時、鑑真は複雑な事情に困惑し、このように釈明した」という記録がある。このことから、「鑑真自身が申し出なければ、朝廷は必ずしも彼を大住職の職から解任しなかっただろう」ということが分かる。 実際のところ、本当の歴史的状況は、これら 2 つの意見のどちらでもないかもしれません。前述のように、日本の朝廷による外国人僧侶の雇用は世俗的な政治目的があったため、政治レベルで特定の勢力から反対が起こったのは理解できることであった。鑑真が日本に渡った目的は、政治的地位を追求することではなく、文化の普及と交流であった。しかし、日本の朝廷にとって鑑真をどう扱うかは、単なる文化的な問題以上のものであった。鑑真が日本で過ごした10年間を振り返ると、次の2点が注目に値する。(1) 日本政府は鑑真の文化的地位と生活環境を決して尊重していなかった。(2) 政治的立場に多少の調整があったものの、それでも鑑真に対する大きな敬意を示していた。淳仁帝の勅旨によれば、鑑真が住職を解かれた公的な理由は「政情が乱れ、疲れ果てようとしなかった」というものであった。鑑真はその年すでに70歳で目が見えなかったことを考えると、彼の気力と体調は具体的な政務に巻き込まれるには十分ではなかった。淳仁帝は鑑真を大僧正の職から解任すると同時に、鑑真に邸宅と田畑を与え、また、宮中に戒律を伝える講堂として宮殿を授けた。 763年、鑑真は異国の地で亡くなりました。 76歳のこの男性は、数々の苦難を経験し、荒れ狂う海を航海し、残りの人生を長屋王の「山と川は違うが、風と月は同じだ」という言葉に応えて生きた。 これは「親切に親切で応える」というシンプルですが素晴らしい方法です。 |
<<: 「淮沙」を書いたのは誰ですか? 『淮沙』の中で最も有名な2つの文章は何ですか?
>>: 「翡翠の少女はどこで私にフルートの演奏方法を教えてくれるのでしょうか?」の「翡翠の少女」とは誰ですか?なぜこの詩は教科書に載らないのでしょうか?
推薦する
キルギスの結婚習慣 キルギスの結婚制度の紹介
キルギスの結婚式は非常に盛大で、婚約と結婚という2つの段階から成ります。婚約するとき、男性は馬に乗っ...
宋代の李剛とは誰だったのか?李剛の作品「王江南」を鑑賞する
宋代の李剛李剛は李伯基とも呼ばれ、宋代の人です。北宋末期から南宋初期にかけて金と戦った有名な官僚でし...
タタール人のユニークなスポーツ、ジャンプ競技の秘密を明かす
サバン祭り:「鋤の穂祭り」としても知られ、春に風光明媚な場所でよく開催されます。タタール人は歌と踊り...
「紅楼夢」では仲良し姉妹なのに、なぜ丹春は林黛玉の誕生日を忘れたのでしょうか?
周知のように、古代の貴族の家では礼儀作法が非常に重視されていたため、全員の誕生日には一連の手続きがあ...
袁潔の「愛内曲第2番」:この詩は楽観主義に満ちており、民謡の真髄を捉えている
袁桀(719-772)は唐代の中国作家であった。雅号は慈山、号は曼蘇、河蘇。彼は河南省廬山出身でした...
ご存知のとおり、東武には有能な将軍が不足したことはなかったのに、なぜ関羽は彼を完全に無視したのでしょうか?
三国志では、関羽は非常に誇り高く、うぬぼれの強い人物でした。実際、彼は非常に野心的で、自分を高く評価...
『六氏春秋・帰之論』の「勇士」には何と書いてあるのですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『呂氏春秋』の「直義の価値について」とはどういう意味ですか? どのように理解すればよいですか? これ...
ラフ族は死者をどのように埋葬するのでしょうか?
人が亡くなった後、その遺体は頭を内側に、足を外側に向けて、母屋の右側にある火床の横に置かれます。そし...
徐申の「二郎申:退屈でカササギを演じる」:詩全体が長引く複雑な感情を表現している
許深は、雅号を甘塵といい、三曲(現在の浙江省衢州市)の出身であった。生没年は不明だが、宋の徽宗の正和...
『紅楼夢』で、賈夫人が王禧峰のために開いた誕生日パーティーは宝釵にどのような影響を与えましたか?
『紅楼夢』第44章では、賑やかな誕生日パーティーが描かれています。以下の記事は、Interestin...
潘熙白の「大有・舞台前」:この詩は作者が重陽の節句に秋の悲しみを表現するために書いたものです。
潘熙白は、雅号を懐古、号を玉荘といい、永嘉(現在の浙江省温州市)の出身である。南宋礼宗の宝有元年(1...
『紅楼夢』では、薛宝才は美人コンテストに行けるのに、なぜ林黛玉は行かなかったのか?
皆さんご存知の通り、側室選びは側室選びです。どの王朝にも「選び」という行事がありました。宮殿に入って...
崇禎帝朱有堅の袁妃の紹介。袁妃の最後はどうなったのでしょうか?
袁妃(?-?)は、明代の宋宗皇帝(崇禎帝)の側室であり、父は袁有である。明代の側室伝記には袁妃に関す...
「八百里急行」は古代に孤立して存在していたのでしょうか?それは実際に国家機構の一部なのでしょうか?
天宝14年(755年)12月22日、唐の玄宗皇帝は臨潼の華清池で、安禄山が6日前に樊陽で反乱を起こし...
オズの魔法使い第48章:騒音を聞いて、好色な霊は文如玉を殺し、憎しみは嘲笑し、怒って金中児を殴った
『オズの魔法使い』はファンタジー小説というよりは社会小説です。冷玉冰は仙人となる途中で弟子を受け入れ...