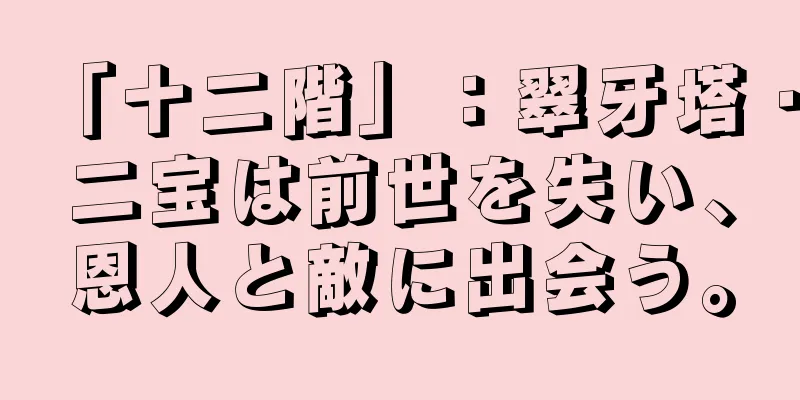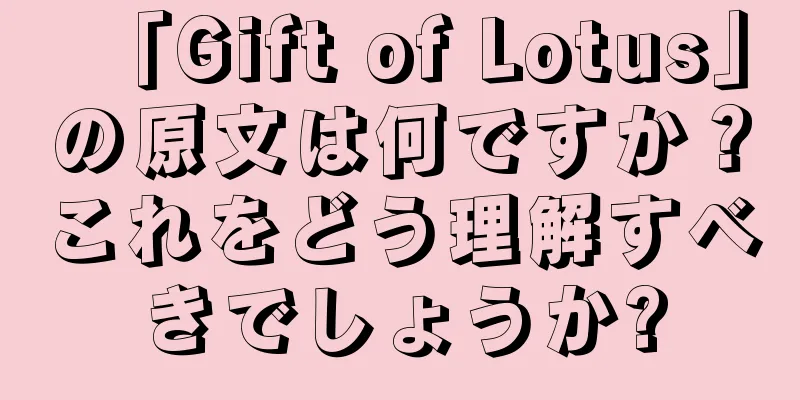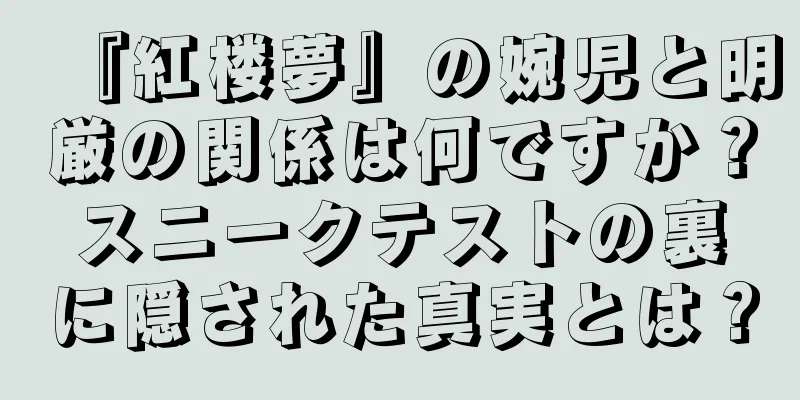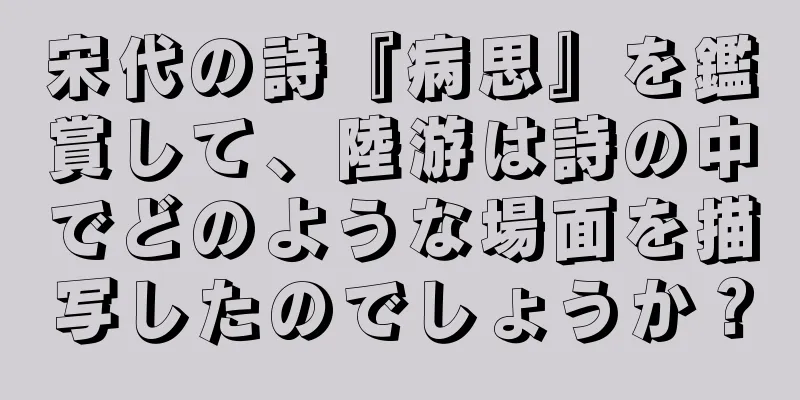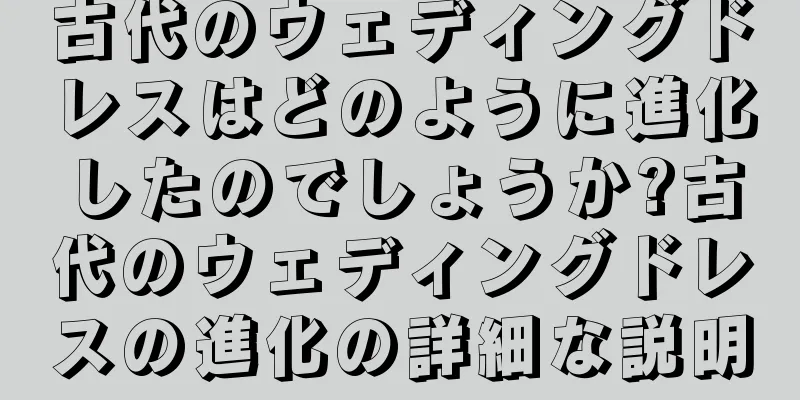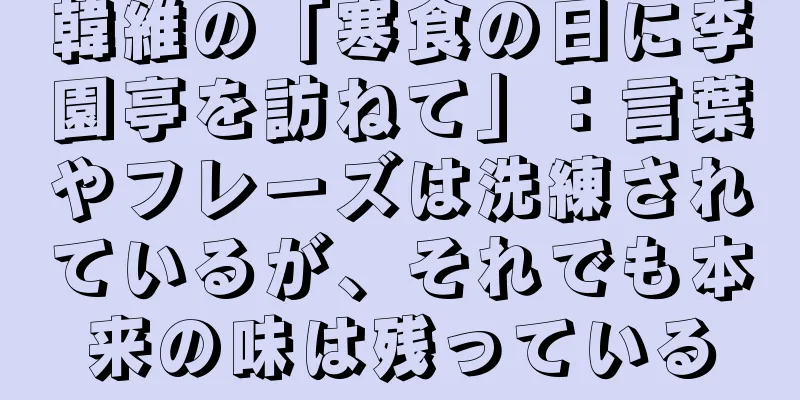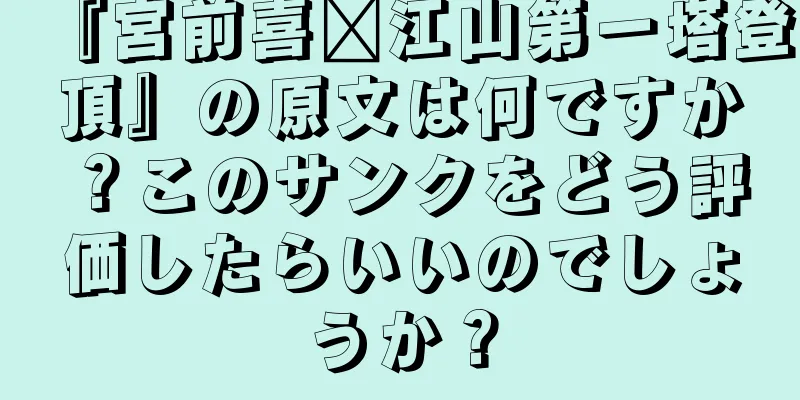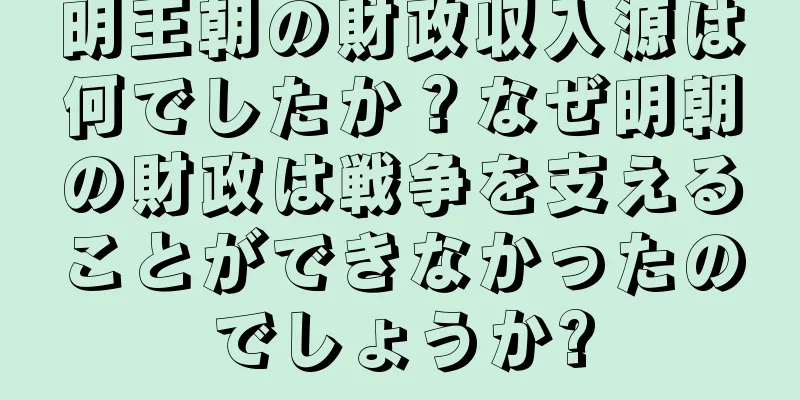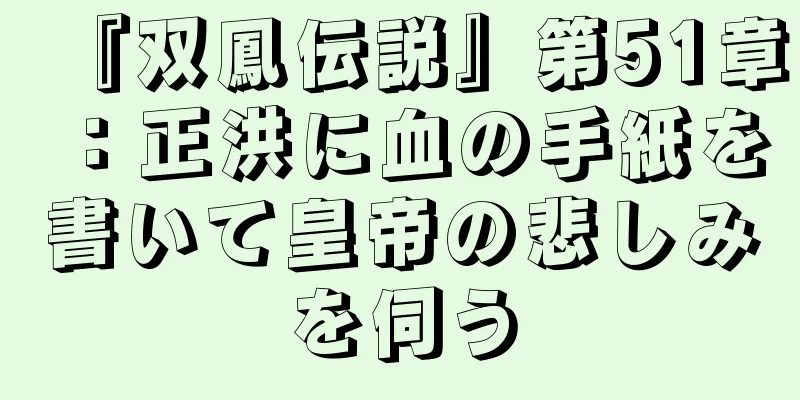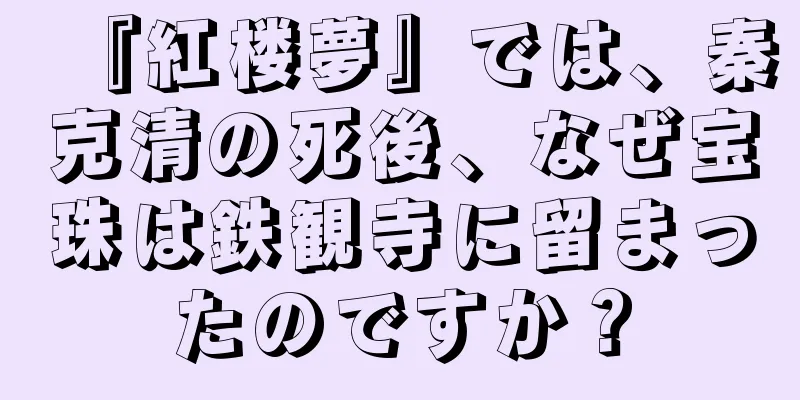『袁二を安渓に送る』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
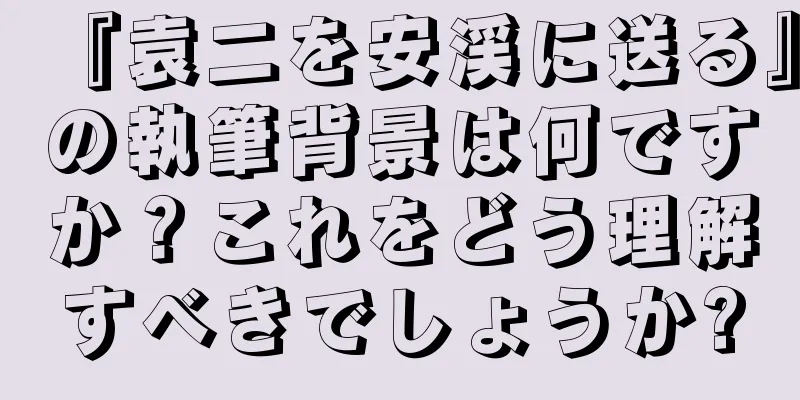
|
『袁児を安渓に遣わす』は唐代の詩人、王維が書いた詩です。この詩は、王維が友人を西北の辺境に送り出す際に書いたものです。後に、ある音楽家がこの詩に曲を付けて「陽官三貂」と名付けました。別名「衛城曲」とも呼ばれています。おそらく安史の乱以前に書かれたものと思われます。彼が見送られた場所は渭城であった。詩人は友人の袁児を遠く安西保護国に送り、長安から渭城賓館に送り、最後の別れの地に到着すると、この七字の詩を書いて別れを告げた。 この詩の最初の2行は、渭城郵便局の風景を描写し、別れの時、場所、雰囲気を説明しています。最後の2行は別れの悲しみについてですが、「悲しみ」という言葉は使わず、グラスを上げて乾杯するという表現だけで、別れの強い深い気持ちを表現しています。詩全体は、飾り気のない、明快で自然な言葉で別れの気持ちを表現しており、情景と雰囲気が溶け合い、奥深くていつまでも残る魅力があり、芸術的な魅力が強い。完成後は管弦楽器で演奏され、熱心に歌われ、時代を超えて受け継がれる名曲となった。 オリジナル作品 袁児を安渓に派遣 渭城の朝の雨が埃を湿らせ、客屋の緑の柳が新しく見えた。 もう一杯酒を飲むことを勧めます。陽関の西側には友人はいないからです。 方言翻訳 渭城の朝の春雨が軽い埃を濡らし、ゲストハウスの周りの緑の柳の木々は特に新鮮に見えました。 古い友人たちよ、別れの酒をもう一杯飲んでください。陽関西路を去れば、古い友人はいなくなるからです。 作品鑑賞 「元二を安渓に送る」という詩は、言葉は簡潔で、イメージは鮮明で、巧みな芸術技法で深く真摯な感情を表現し、別れを惜しむ共通の気持ちを伝えています。そのため、唐代に歌にされ、「陽官曲」と呼ばれる送別宴の送別歌になりました。白居易の『酒宴五歌』には「会ったら酒を飲まずにはいられず、陽官の四番目の声を聞く」という一文があり、「四番目の声は『酒をもう一杯飲むように勧める』である」と記されている。 王維の詩に「陽管三聲」という別名があるのは、詠唱するときに最初の文は繰り返さず、残りの3つの文をもう一度歌うからです。しかし、最後の文だけが 3 回繰り返されていると考える人もいます。白居易が「第四声」について述べたことによると、最初の文は繰り返さないが、他の3つの文は繰り返す必要があり、そうしないと「劝君」という文は「第四声」にはならない。白居易の詩から判断すると、唐代は「陽関以西に旧友なし」という詩を歌ったはずだ。 この詩の最初の 2 行は、別れの時間、場所、雰囲気を描写しており、別れの憂鬱な雰囲気を作り出しています。早朝、威城賓館、東西に果てしなく続く郵便道、そして賓館の周囲と郵便道の両側にある柳の木々。これらはすべて、私たちの目の前に広がるごく普通の光景ですが、読むと絵のように美しく、強い叙情的な雰囲気が漂います。ここでは「朝の雨」が重要な役割を果たします。朝の雨は長くは続かず、土埃を濡らしただけで止みました。 長安から西へ向かう道は、いつもは馬車や馬が沢山走り、砂埃が舞っていたが、別れの時になると、朝の雨は止み、天気は晴れ、道は清潔で爽やかに見えた。 「浥轻尘」の「浥」は濡れという意味で、ここでは非常に適切に使われており、雨が埃を払いのけるが道を濡らさないことを示しています。まるで神が人々の願いを叶え、旅人のために埃のない道を特別に用意したかのようです。ゲストハウスはもともと旅人の寄り添いであり、柳の木は別れの象徴です。作者は、これら 2 つのものを別れと関連付けるために意図的に選びました。これらは通常、別離や別れの悲しみと関連付けられ、悲しく胸が張り裂けるような気分を表現します。 しかし、この瞬間、その場所は朝の雨のおかげで明るく新鮮な表情をしています - 「ゲストハウスの緑の柳は新しいです。」平日は道路が埃っぽく、道端の柳は灰色の埃に覆われていることが多い。朝の雨が降って初めて、柳は再び青々とした色を取り戻す。だから「新しい」と言われるのだ。柳の新しい色が、民宿の緑を映し出すからだ。つまり、澄んだ空からきれいな道まで、緑のゲストハウスから青々とした柳まで、新鮮で明るい色彩の絵を描き、この別れに典型的な自然環境を提供しています。これは愛情のこもった別れですが、悲しい別れではありません。それどころか、明るく希望に満ちた雰囲気が伝わってきます。 「light dust」「green」「new」などの単語は柔らかく明るい響きがあり、読み手の感情を高めます。 四行詩の長さは厳しく制限されています。この詩は、送別会の様子、宴会で人々が頻繁にグラスを掲げて別れを告げたこと、出発するときになかなか去ろうとしなかったこと、船に乗り込んだ後に遠くを見据えたことなど、細かいことは何も書いていない。送別会の終わりに主催者が「もう一杯飲もう。陽関を過ぎたら、もう二度と旧友に会えないからな」と乾杯する場面だけが描かれている。詩人は熟練した写真家のように、最も表現力豊かなショットを撮影した。宴会は長く続き、別れの気持ちを込めたワインを何度も飲み、真摯な別れの言葉を何度も繰り返し、ついに友人が旅立つ瞬間がやってきました。この瞬間、主催者とゲスト双方の別れの気持ちは最高潮に達します。司会者が皆に向けて自然に発した乾杯の挨拶は、その瞬間の彼の強い深い別れの気持ちの凝縮された表現です。 3番目と4番目の文は別れを描写し、全体を構成します。出発前にこの乾杯の言葉に込められた深い愛情を深く理解するには、「陽関の西方」について触れなければなりません。陽関は河西回廊の西端に位置し、北は玉門関の向かい側にあり、漢代から内陸部から西域への通路となってきました。唐代は大陸と西域との交流が盛んな強国でした。繁栄した唐代の人々の目には、軍隊に入隊したり、陽関を越えて外交使節として出向いたりすることは羨ましい偉業でした。しかし、当時、陽関の西側は未だに不毛で荒涼とした地であり、その景観は内陸部とは大きく異なっていました。友人たちにとって「陽関を西へ進む」ことは英雄的な偉業であるが、彼らは数千マイルの長い旅を経験し、荒野を一人で歩く困難と孤独を経験しなければならないだろう。したがって、別れの瞬間に「もう一杯のワインを飲んでください」という言葉は、詩人の豊かで深い友情がすべて染み込んだ一杯の濃厚な感情の蜜のようなものです。 そこには、別れを惜しむ気持ちだけでなく、旅人の状況や心境に対する深い思いやり、そしてこれからの旅が素晴らしいものとなるよう心から願う気持ちも込められています。誰かを見送る側にとって、相手に「もう一杯ワインを飲もう」と説得することは、友人に友情をさらに奪わせるだけでなく、意図的または無意識的に別れの時間を遅らせて、相手がもう少し長く滞在できるようにすることです。 「陽関以西には古い友人はいない」という感覚は旅行者だけのものではない。別れる前に言いたいことはたくさんありますが、考えるべきことが多すぎて、どこから始めればいいのかわかりません。このような場合、しばしば言葉のない沈黙が訪れます。「ワインをもう一杯飲んでください」というのは、この沈黙を破り、その瞬間の豊かで複雑な感情を表現する無意識の方法です。 詩人が言わないことは、彼が言うことよりずっと豊かである。つまり、3 番目と 4 番目の文は、場面のほんの一瞬を捉えているに過ぎませんが、内容が非常に豊かな瞬間です。 この詩は最も普遍的な別れを描いています。特別な背景はないが、深い別れの気持ちが込められており、ほとんどの送別会で歌うのに適している。後に「月譜」に取り入れられ、最も人気があり、最も長く歌われている歌となった。 |
<<: 唐代の二大詩のうち二番目の『李白の夢』をどのように評価すればよいのでしょうか。また、杜甫がこの詩を書いた意図は何だったのでしょうか。
>>: 明らかに:「王倫が私にくれた愛はそれほど良くない」の王倫とは誰ですか?
推薦する
杜甫の『蜀宰相』:諸葛亮を讃える詩の中でも傑作
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
白居易の『草』:詩の中の平原の草は何かを表しているが、その比喩は明確ではない。
白居易(772-846)は、字を楽天といい、別名を向山居士、随隠仙生とも呼ばれた。祖先は山西省太原に...
古代では結婚に全く自由がなかったのでしょうか?すべては親の命令ですか?
古代の結婚には全く自由がなかったのでしょうか?すべて親や仲人によって決められていたのでしょうか?実は...
デュオガールの髪を隠してユウ・エルジエを通報?ピンエルはなぜこんなことをしたのか?
平児は王希峰の侍女で、持参金として彼女と一緒に来た。幽二潔と幽三潔は二人とも、彼女が善良な人柄で優し...
『紅楼夢』で仲人がタンチュンにプロポーズしたが失敗したのはなぜですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
狄青物語第21章:軍服を脱ぎ捨てて悪辣な計画を練り、王の命令で牢獄から脱出できたことを喜んだ
『狄青演義』は清代の李語堂が書いた歴史ロマンス小説で、楊宗豫、鮑正、狄青など、外国の侵略に抵抗し、お...
涼山の英雄武松の師匠は誰ですか?武松は暴力に暴力で対抗し、獅子塔に血が飛び散りました!
涼山の英雄武松の師匠は誰ですか?武松は暴力に暴力で対抗し、獅子塔には血が飛び散りました!次の興味深い...
五代十国時代の穀物輸送の状況を見て、穀物輸送が政権に与えた大きな影響を理解しましょう。
今日は、五代十国時代の水運事情と、水運が政権に与えた大きな影響について、おもしろ歴史編集長がご紹介し...
「三生不運、郡代が市に付く」とはどういう意味ですか? 「富国県」って何ですか?
「三度の不幸で郊外の郡代になる」とはどういう意味でしょうか?次の興味深い歴史の編集者が関連する内容を...
『紅楼夢』における宝仔と石向雲姉妹の関係にはどのような変化がありましたか?
『紅楼夢』の金陵十二美女本編に登場する女性たちは、それぞれに際立った特徴を持っています。次の興味深い...
明楊吉州(吉師)著『鍼灸学論集』第1巻:「いたずら鍼灸理論」全文
『鍼灸学事典』とも呼ばれる『鍼灸事典』全10巻。明代の楊其左によって書かれ、万暦29年(1601年)...
『清平楽:毎年雪が降る』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
清平楽·年年雪麗李清昭(宋代)毎年雪の中、梅の花に酔いしれることが多いです。善意もなく梅の花を摘み取...
『紅楼夢』ではなぜ薛叔母さんが陰険で野心的な人物だと言われているのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
秦と漢の時代の皇帝の衣服が主に黒だったのはなぜですか?
漢王朝の冠と衣服の制度は、主に秦の制度から受け継がれました。正式かつ完全な規則が導入されたのは、東漢...
唐代宗皇帝の娘、玉清公主の簡単な紹介
玉清公主(?-?)、唐の代宗皇帝李玉の娘。母親は不明。王女は若くして亡くなり、死後玉清公主と名付けら...