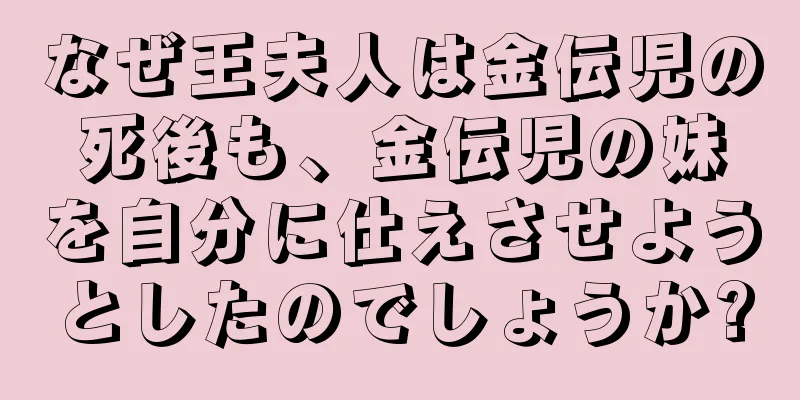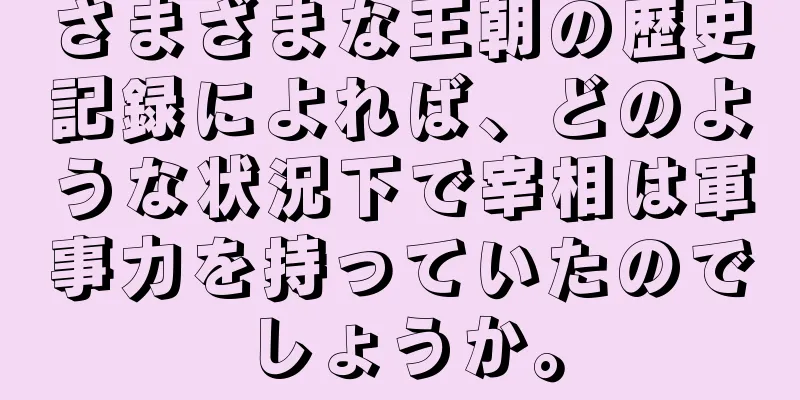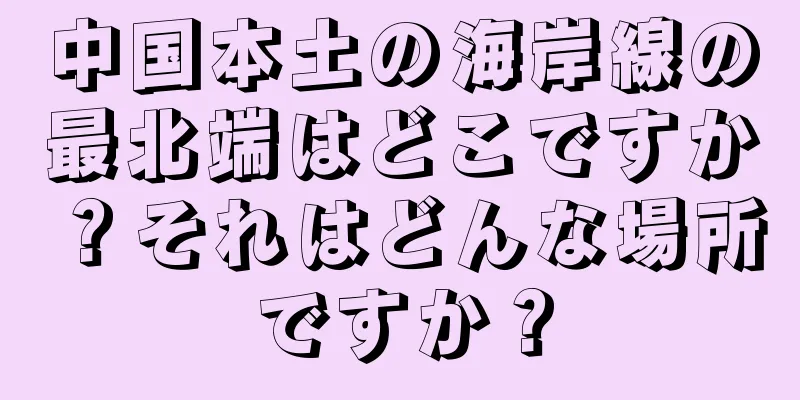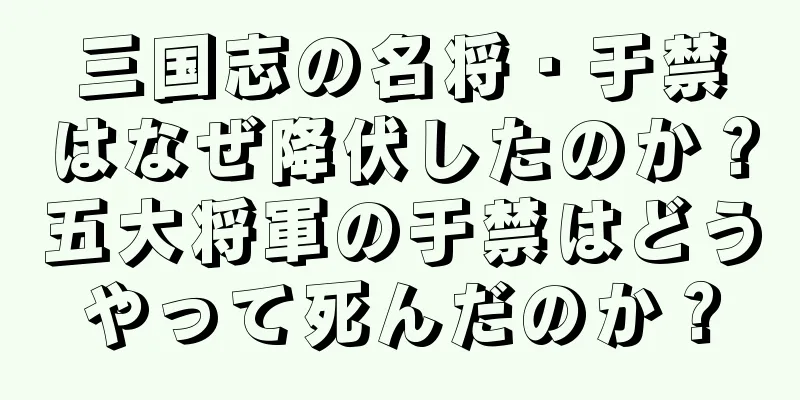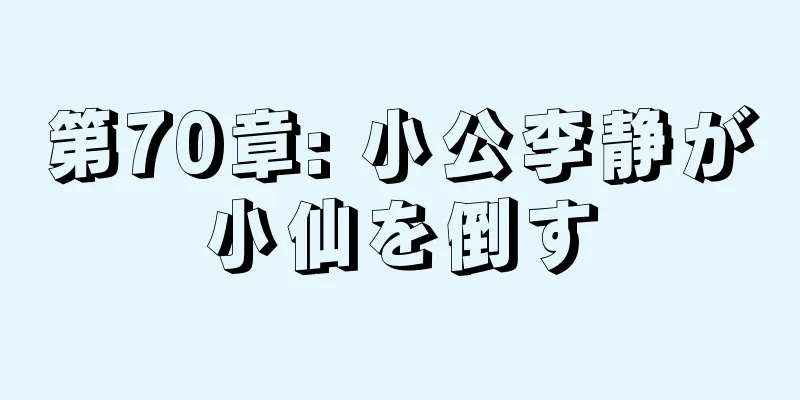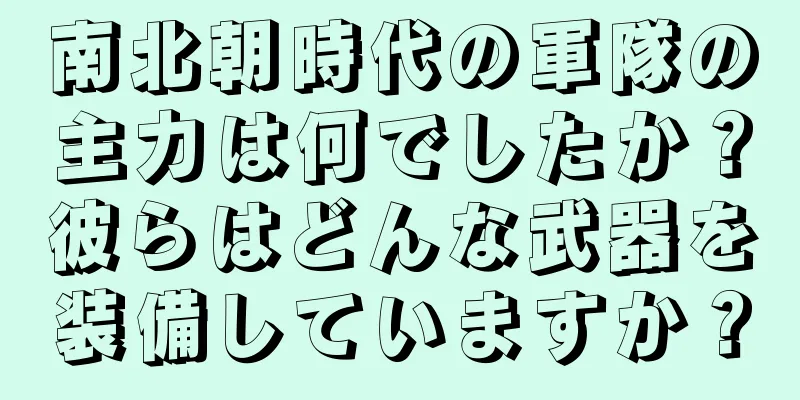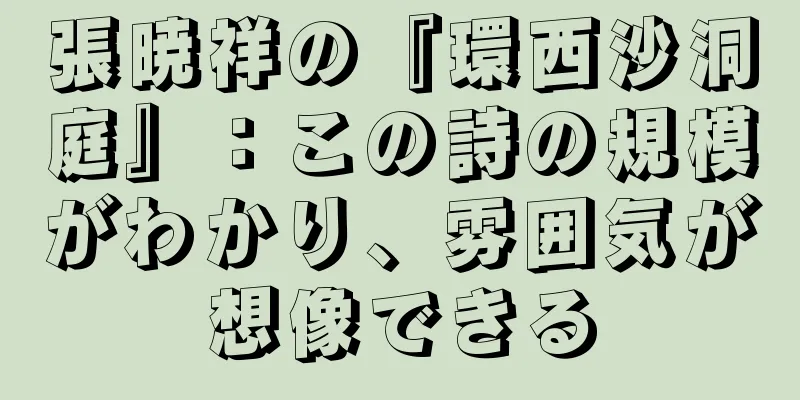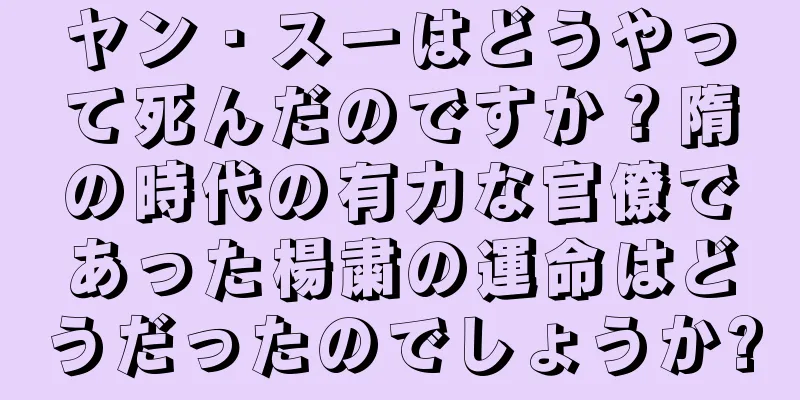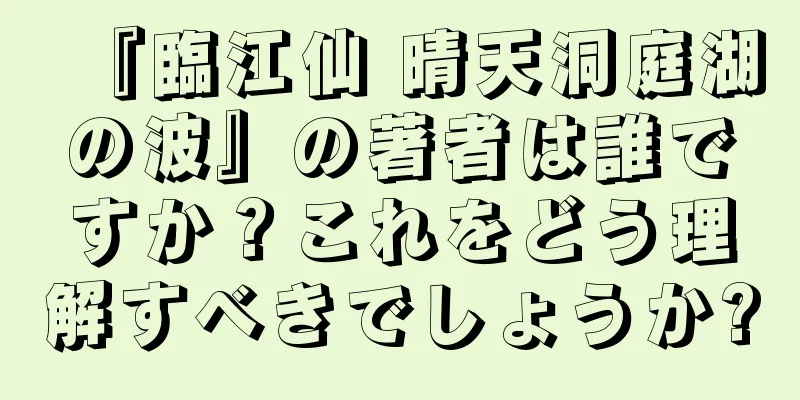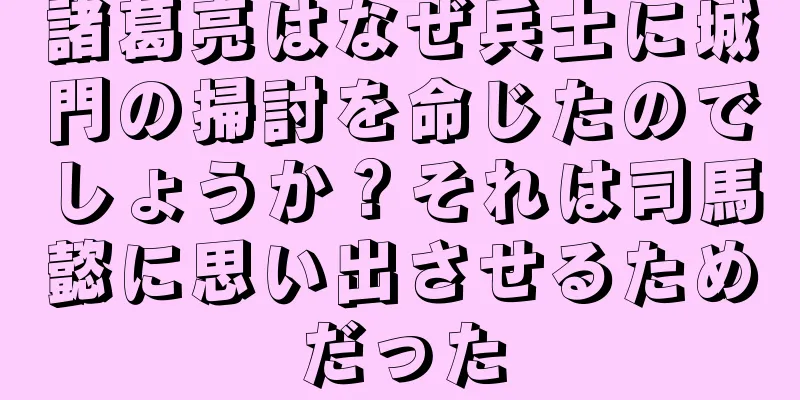韓維の「寒食の日に李園亭を訪ねて」:言葉やフレーズは洗練されているが、それでも本来の味は残っている
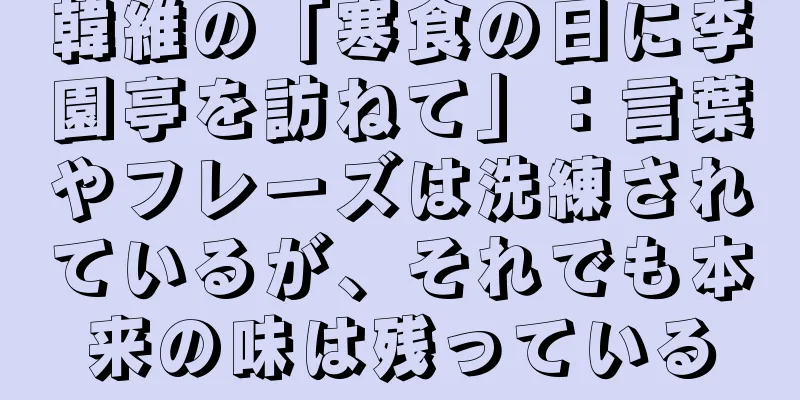
|
韓維(844年 - 923年)、号は智光、号は智堯、通称は東朗、号は玉山喬人、荊昭萬年(現在の陝西省西安市)の人。唐代末期の大臣、詩人。韓懿の弟で、翰林学者であり、「南安四賢」の一人。彼の詩集『玉山喬人記』は『四部従鑑』に再録され、現代まで伝えられている。また、『全唐詩集』には彼の詩が280編以上収録されている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、韓維の「寒食の日に李氏園亭を再訪」をお届けします。見てみましょう! 寒い日に李園亭を再訪 韓維(唐代) 以前、私たちは一緒に鑾安橋にいて、彼が赤い欄干に寄りかかって柳の花穂について詠唱しているのを見ました。 今日は一人で香りのよい道を歩いているのですが、人影も苔もありません。 3,000マイル離れたところであなたに会うのは悲しいですが、私は4、5年もあなたのことを考えていました。 外国で祭りをすると悲しい気持ちになることもあると思います。 この詩は、憂鬱な雰囲気で、寒食節に庭園を訪れ、数年前の女性との温かく優しい出会いを思い出し、長い間離れ離れになっている恋人への深い追悼を表現しています。 寒食の日には、柳の枝を折って戸口や軒先に挿す「明目」という伝統的な風習があり、成人の儀式やかんざしの儀式もこの日に行われます。そのため、寒食節には、親戚や友人、古い知人、恋人などを懐かしく思い出す人が多くいます。感傷的な詩人にとって、この日は興奮した心を落ち着かせるのが難しく、夢にまで出てくる恋人を深く思い出すためにわざわざ李園亭に来たのだろうと想像できる。 この詩のタイトルはすでに悲しみと郷愁の感覚を表しており、詩全体の雰囲気も決めています。 詩の冒頭で、詩人は、以前彼と恋人が庭で過ごした優しく愛情深い時間を限りない愛情をもって回想しています。 最初の文では、デートの場所が庭園の「鑾橋」にあることを示しています。この橋は魯庵にちなんで名付けられており、そこには深い意味があるのだろう。ここでは、南宋の范泰の『鸞鳥詩序』に出てくる話が暗示されています。伝説によると、昔、鸞鳥(神話の鳳凰に似た鳥)が捕らえられ、伴侶を失ったため3年間鳴かず、その後、鏡に映った自分の姿を見て泣き叫び、死んでしまったそうです。調和のとれたカップルのラブストーリーは、後に男性と女性のデートを暗示するようになりました。ここでは、男性と女性が「一緒に魯安橋の上にいる」。「同じ」という言葉は、お互いへの愛情と依存を頻繁に表現しています。そのとき、女性は赤い橋の欄干にもたれながら、詩人とともに柳の花穂について歌っていた。 『新説世界物語』の「談話」に出てくる古典的な話もここで言及されています。東晋の宰相謝安の姪である謝道君は、雪を柳の花穂に例えた詩を詠み、謝安に賞賛されました。その後、謝安はそれを女性が詩を書くことを指して使いました。 これら 2 つの文は非常に自然でカジュアルに見えますが、わずか 14 語の中に豊かな内容が含まれています。こんなに美しい環境でこんなに美しく魅力的な女性に出会うと、人々は彼女を永遠に懐かしく思い、甘い思い出を残すことになるでしょう。最初の連句は、少女との出会いの優しさと甘さを表現しており、記事の冒頭に配置されており、過去を回想するときに続く連句の悲しみと強力なコントラストを形成しています。 2番目と3番目の連句は、その日の庭での詩人の寂しい経験と、母親を失った悲しみを直接的に表現しています。 著者は、香りのよい花と美しい草に覆われた庭の小道を一人で歩いています。「一人」という言葉は、最初の文の「同じ」という言葉と対照的で、彼の孤独さがはっきりと表れています。あの日、赤い柵に寄りかかって柳の花を詠んだ男は跡形もなく消え、地面の苔だけが寂しい光景を呈している。こんなにも暗い寒食節に、過去を思い出して著者が特に悲しく感じるのも不思議ではない。しかし、旅は長く、山や川が道を塞いでいたため、彼女から連絡を得ることは難しく、彼女の状況を知ることは不可能でした。 指で数えてみれば、あっという間に4、5年が経ちました。過去は煙のように、人生は夢のようです。 「指を数えて考える」という4つの言葉はとても生き生きしています。読者は悲しみに満ちた男が庭をさまよい、指を数えて悲しく考えているのを見ているようです。第一連句の、鑾安橋で柳の花穂を詠唱している場面と比べると、あの時の明るく楽しい雰囲気はすっかり消え失せ、孤独で悲しい人だけが残り、さらに惨めな表情をしている。これら二つの連句は、よく言われるように明確で単純ですが、最初の連句と対比すると、その意味は依然として非常に微妙で深いものです。 最後の連句は予想外で、通常の連句とは異なっています。 2 番目と 3 番目の連句の考えに従えば、最後の連句はやはり作者の庭への訪問がいかに悲惨なものであったかを説明するはずです。しかし、ここで詩の調子が変わり、柵にもたれながら柳の花穂について詠唱している男性に焦点が当てられます。 詩人は、この寒食節の期間中、遠く離れた情熱的な女性も自分を恋しく思い、悲しんでいるだろうと推測した。ここでの「暗い」という言葉は熟考する価値がある。彼らが密かに悲しみ、公に愛を表現できなかったのは、過去に密かに愛し合っていたが、それを公にすることができなかったからである。その後、恋人たちはついに別れ、それぞれが心の中に言い表せない憎しみを抱え、地球の果てで引き離された。この女性は、心の中に溜め込んでいたが表現できなかった苦しみのせいで、過去4、5年間、極度の惨めさと疲労感を感じていた。 最後の連句は、記事の冒頭に反応し、美しく聡明な女性との対比を形成しています。彼女は以前は気楽でしたが、今は悲しそうでやつれているようです。別れの悲しみは本当に耐え難いものです!同時に、ある層を通して、女性の自分への憧れから、彼は女性への憧れをより深く反映しています。これにより、一般的な書き方を避け、より婉曲的で深遠に見えます。感情論理の視点から見ると、6番目の文の「指を数えて考える」とも密かに結びついており、考える気持ちがはっきりと表現され、無限の郷愁が十分に表現されています。 この詩は、特に対比と浸透の使い方において非常に厳密な構成をしており、詩全体が自然で起伏に富み、紆余曲折の中で憧れの感情が生き生きと表現されています。言語面では、「阮橋」や「柳面の歌」などの暗示を除いて、残りは基本的に常用慣用句であり、簡単で親しみやすく、明確で理解しやすいように見えます。しかし、よく噛んでみると、言葉の選択が非常に正確であり、洗練されているにもかかわらず、元の色を失っていないことがわかります。 |
<<: 周密の『春旅歌:東風の禁園の外』:詩全体に鮮明で美しいイメージがあり、旅詩の中でも傑作である。
>>: 宋志文の「江州満堂郵便局の冷食節」:南方への追放の悲しみが行間から伝わってくる
推薦する
『射雁勇者の帰還』の小龍娘の髪型が批判されている:宋代ではどのような髪型であるべきなのか?
最近人気の于正版『神雁勇者の帰還』でミシェル・チェンがとった角おだんごヘアスタイルに不満を言う人が多...
ウズベキスタンの衣装はどのように分類されますか?
ウズベキスタン人の伝統的な衣服は、男性も女性もさまざまな小さな花のついた帽子をかぶっているのが特徴で...
『年女嬌:娜紅一歌』を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
年女嬌·赤い船姜魁(宋代)私は武陵の客でした。湖北の仙芝はここにあります。古都、荒々しい水、そびえ立...
張慧燕の『水の旋律の歌:東風に何もすることはない』:歌詞では一人称「私が書く」がよく使われる
張慧延(1761-1802)は清代の詩人、随筆家であった。彼の本名は怡明、雅号は高文、別名高文、明科...
北宋初期の有名な宰相、李芳の物語。李芳に関する興味深い話にはどんなものがありますか?
李芳(925年 - 996年2月22日)は、字を明元(『直寨書録街鉄』では明書と表記)といい、神州饒...
『晋書』第60巻伝記30の原文は何ですか?
◎杰希(弟杰潔、弟游)孫其、孟観、千秀、苗伯(従弟殷)皇甫忠、張甫、李寒、張芳、燕定、蘇静(息子陳)...
なぜ日本人は左側通行をするのでしょうか?真実はとても残酷だ
初めて日本を訪れた中国人観光客は、日本人が歩くときもエスカレーターに乗るときも常に左側を歩き、右側を...
青文が追い出されたのは、本当に西仁の裏切りによるものだったのだろうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が Xire...
夷陵の戦いでの敗北後、劉備が失ったのは精鋭兵5万人だけだったのでしょうか?
西暦219年、関羽は殺され、蜀漢は偉大な将軍を失いました。関羽の死は間違いなく蜀漢の手を失い、蜀漢の...
「紅楼夢」では、鳳潔は妊娠7ヶ月で流産したが、その最大の原因は王福仁だった。
『紅楼夢』の中で、馮冀が妊娠7ヶ月で流産したことは、当時の環境について何を明らかにしたのでしょうか?...
王夫人が追い払おうとしていると知っていたのに、なぜ清文は賈夫人に助けを求めなかったのでしょうか?
青文は王夫人が自分を追い出そうとしていることを知っていたのに、なぜ賈おばあちゃんに助けを求めなかった...
「湘溪寺を通り過ぎる」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
湘濟寺を通過王維(唐代)そこに湘濟寺があることは知りませんでした。それは雲の中に数マイルも離れたとこ...
もし諸葛亮が関行と張宝に街亭を守るよう命じたら、彼らは街亭を守れるだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
曹操の「苦寒行」:この詩は彼の悲しく荒涼とした出来事を直接語り、彼の寛大な気持ちを表現している。
魏の武帝、曹操(155年 - 220年3月15日)は、雅号を孟徳、あだ名を阿満、吉理といい、沛国桥県...
『九歌:東煌太一』の創作背景は何ですか?
屈原の『九歌・東皇太一』の創作背景はどのようなものでしょうか? これは多くの読者が特に知りたい質問で...