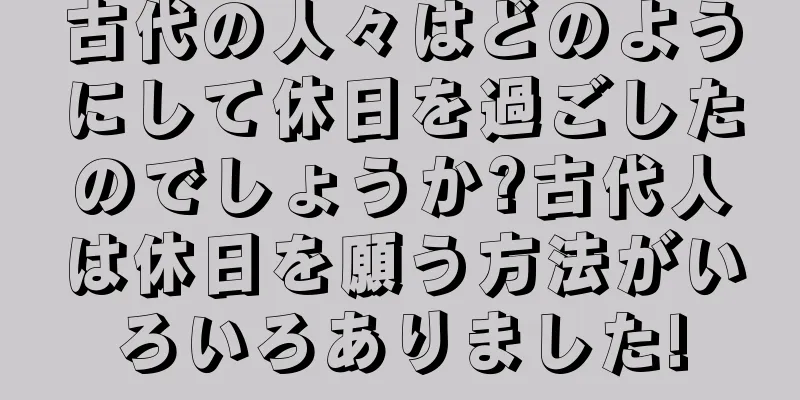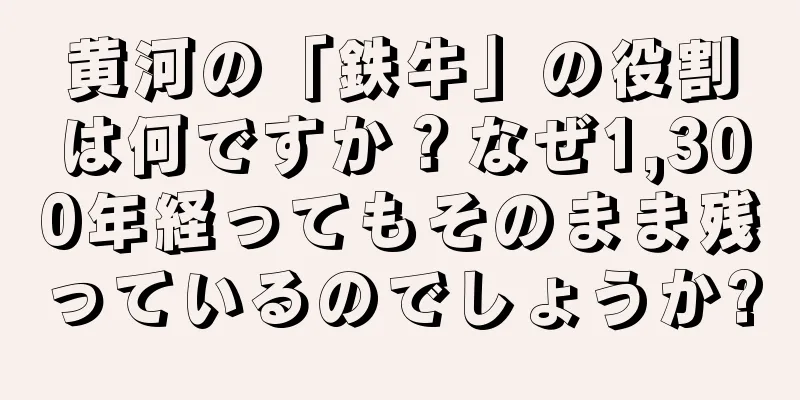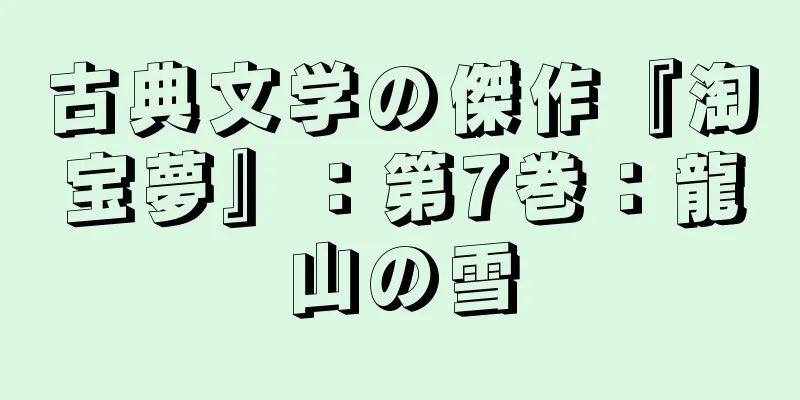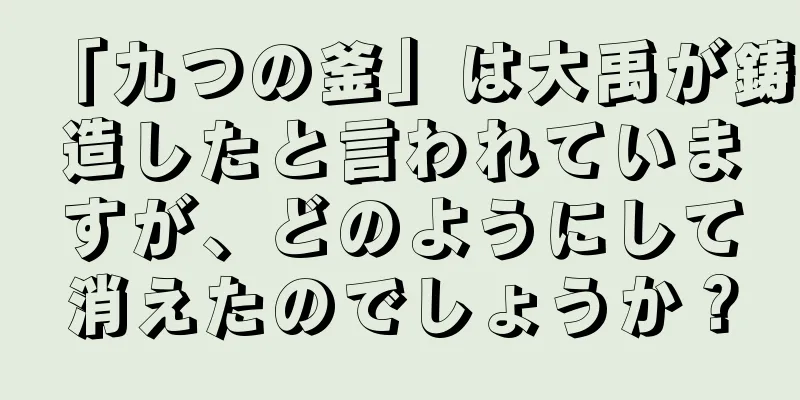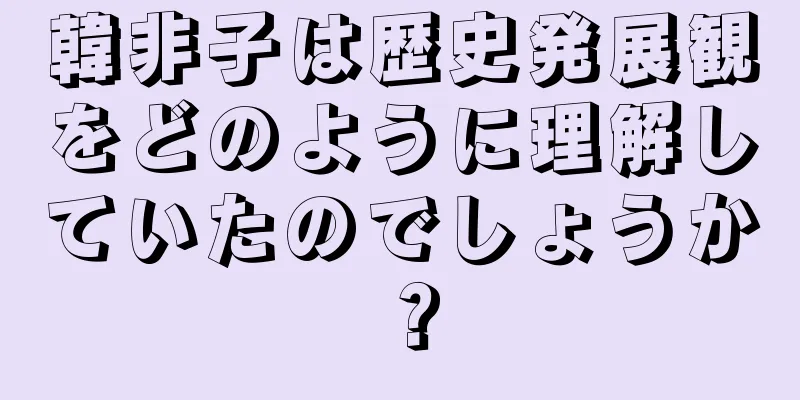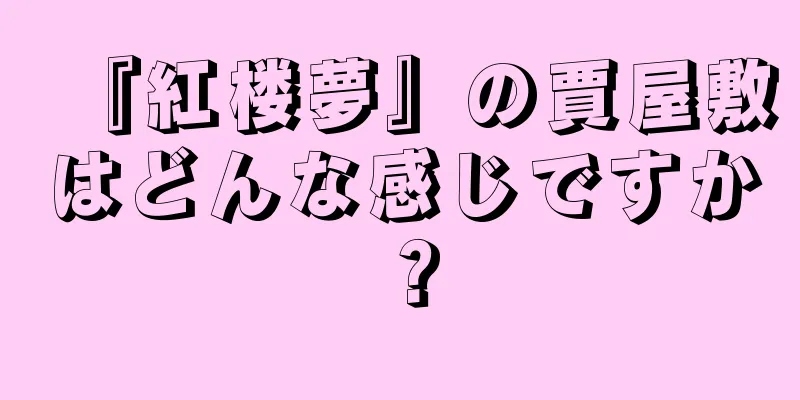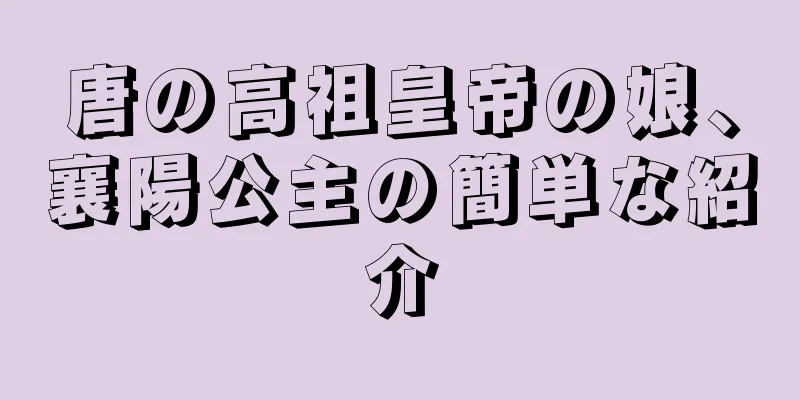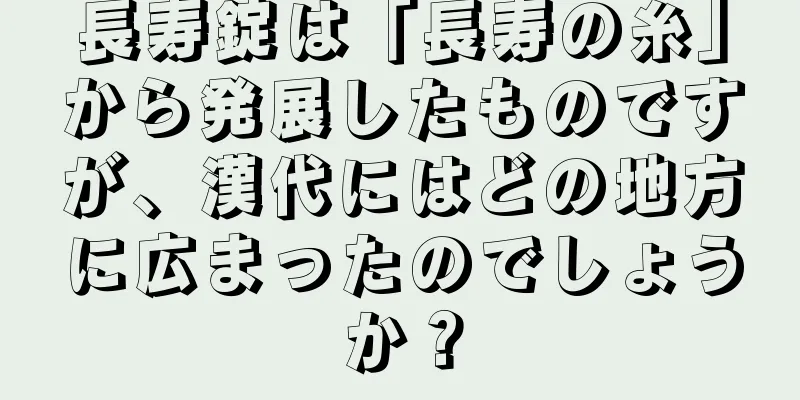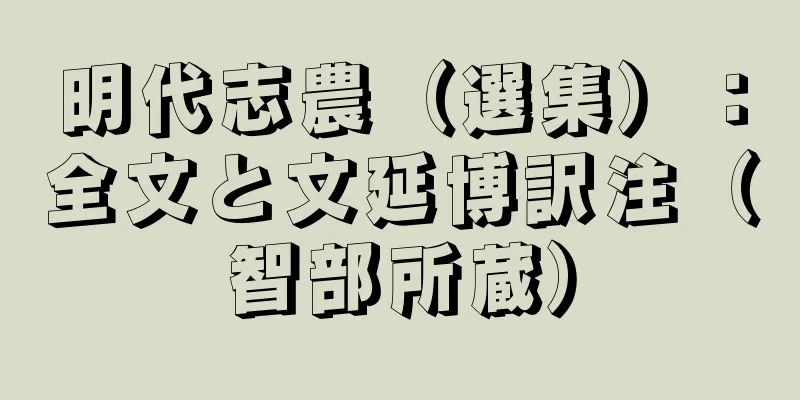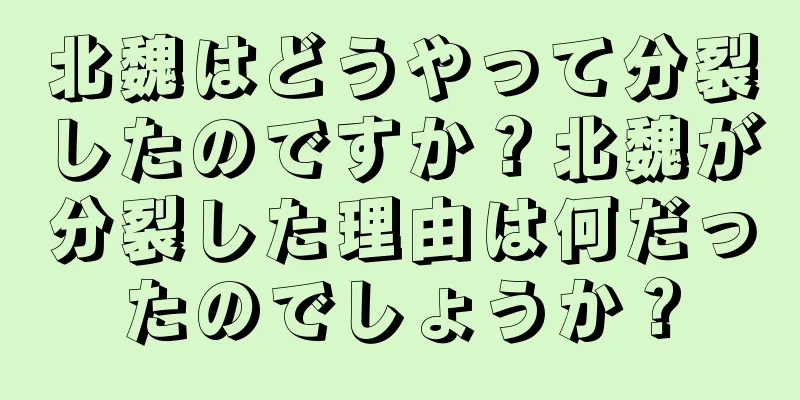韓鴻は唐の徳宗皇帝に「冷食」という詩を賞賛されました。この詩は何を言っているのでしょうか。
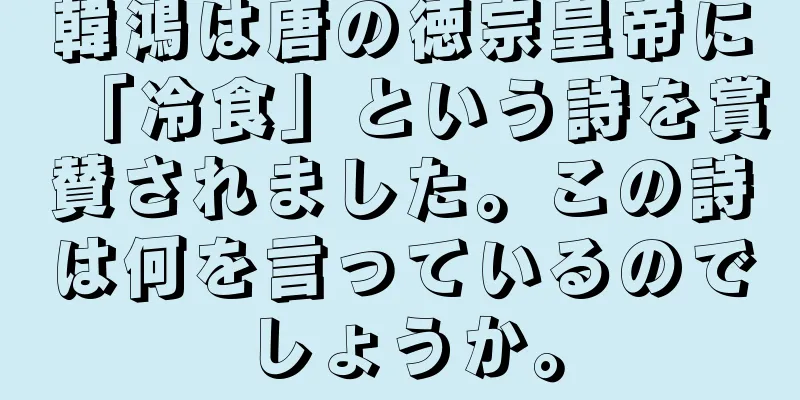
|
韓鴻(ハン・ホン)、号は君平、南陽出身。唐代の官僚、詩人で、大理十傑の一人でもあった。興味深い歴史の編集者と一緒に、韓鴻著『冷たい食べ物』について学んでみましょう。 韓鴻は天宝13年に進氏となった。彼は淄博・青州の太守である侯羲儀の宮廷に仕えていたが、職を解かれてから10年間怠惰な生活を送っていた。その後、彼は永平軍の太守である李勉の宮廷で憂鬱で不幸な生活を送っていた。しかし、彼の詩はますます有名になっていった。徳宗皇帝が即位した後、帝国編集者のポストに空きが生じた。事務局は2度候補者を指名したが、徳宗皇帝はどちらのポストも承認しなかった。その役職に誰を任命するかを決める許可を求めるしかなかった。徳宗は「韓懿と共に」と書いた。当時、江淮には韓懿という名の太守がいた。書記局は徳宗がどちらの太守を望んでいるのか分からなかったため、二人の韓鴻の名を一緒に提出した。徳宗皇帝は「春城には花が舞い散る」と韓懿を書いた。そして詩人の韓弘を勅令長官に任命し、後に中央書記官に昇進させた。大理時代の十傑の中で、韓毅は最高の官職に就いていた。彼が書記官になれたのは、彼の詩が皇帝に高く評価されていたからである。高忠武は『中興西季集』に収められた韓鴻の詩について「詩は面白みに富み、一節一節に独特の趣があり、朝廷の役人たちに重宝されている」と評した。また「比喩や暗示は劉長青よりも深く、細部は黄甫然よりも洗練されている」とも述べた。これは韓鴻の詩がより奥深く、文体がより力強いことを意味している。韓洛の詩集は現在5巻ある。全体的に見て、このコメントは適切である。具体的には、韓懿の五七字律詩は、真ん中の三連句に優れた詩節が多く、劉長清の詩よりも優れている。今日は彼の四行詩を一緒に鑑賞しましょう。 この詩のタイトルは「冷たい食べ物」で、全文は次の通りです。 春の街のあちこちに花が飛び交っています。 寒中見舞いの時期には、東風が吹いて皇居の柳の木が傾いています。 夕暮れになると、漢宮ではろうそくが灯されます。 五侯爵邸宅に薄い煙が漂ってきた。 この詩は徳宗皇帝が賞賛した詩であり、当時はおそらく何千人もの人々が朗読し、皇帝自身も暗記していた。この詩を理解するには、まず古代人の火の使用に関連する古代の寒食節を理解する必要があります。寒食節は毎年冬至の104日後に始まります。寒食節は3日間続きます。寒食節の次は清明節です。寒食節の初日から清明節の3日目まで、計7日間は唐代の休日でした。この期間中、官民ともにピクニックや宴会、娯楽などを行ったため、唐代の詩には寒食節や清明節について書かれたものが多く残されています。寒食節の3日間は火気厳禁日です。この3日間は火気厳禁で、食べ物や飲み物はすべて数日前に調理された調理済みの食べ物となります。この3日間は冷たい食事だけを食べるので、冷たい食べ物祭りと呼ばれています。関中の人々はこれを「煮込み料理祭り」とも呼んでいます。花火が禁止されているため、禁煙デーとしても知られています。 古代にはマッチはなく、人々が火を起こすのは非常に困難でした。最も原始的な方法は、木をドリルで穴を開けて火を起こすことでした。春にはニレやヤナギを、夏にはナツメやアンズ、クワやナツメを、秋にはカシやカシを、冬にはイネ科やビャクダンを掘ります。この状況は唐代、宋代まで続きました。火を起こすには、鉄刀と灸と石を使う方がはるかに便利ですが、これは宋元時代以降のことであり、西域から伝わった方法だったと思われます。火を起こすのは簡単ではないので、人々は毎日火を絶やしません。火を保つ方法は、灰の中に赤く熱した炭や木炭を埋めて、いつでも紙の棒で火をつけることができるようにすることです(揚子江の南の人々はそれを紙炭頭と呼びます)。この火は1年間燃え続け、寒食節に完全に消えます。人々は火が熱を失ったと信じ、それを古い火、または古い火と呼んだからです。清明節には、人々は木を掘って再び火を起こします。これを「変火」といいます。この火が新しい火です。なぜ寒食節は3日間に延長されたのでしょうか。なぜ2日目に新しい火を灯さなかったのでしょうか。これは、人々が法律を遵守しているかどうかを確認しやすくするためでした。3日間連続して調理による煙が出なかった場合にのみ、家族が古い火を消したことが分かります。この習慣は古い歴史があり、商・周の時代にもこのような法律があったと言われています。周の時代には、水利を担当する官僚と同じくらい重要な、火事の禁止を担当する司遼という官職がありました。しかし、後世に伝わったとき、その起源は不明であり、山西省の人々はそれが杞子推を記念する祭りであると信じていました。寒食節と清明節は唐代の主要な祭りでした。清明節に宮殿では役人全員を招いて宴会が開かれましたが、食べ物は冷たかったです。夕方、宴会が終わると、彼らはその日掘っておいた新しい火を持ち出しました。ろうそくに火を灯し、それを高貴な親戚や側近に贈ることを「新たな火を贈る」といいます。この制度は北宋時代にもまだ使用されていました。南宋時代以降、火打ち石を使って火を起こすことが一般的になり、喫煙を禁止して代わりに火を使う習慣はなくなりました。そのため、後世の人々はそれをあまり理解しませんでした。 ハン・ホンの詩については、2番目の文から議論を始めるべきです。寒食節の期間中、東風が皇居の庭園の柳を斜めに吹き飛ばし、柳の花穂が街中に舞い上がりました。ここで「花」という言葉が「ポプラの花」を指していると言えるのはなぜでしょうか。その理由は次のとおりです。(a)「柳」という言葉が 2 番目の文に出てくるので、それがポプラと柳の花を指していることがわかり、したがって 2 つの文は関連しています。 2 番目の文は原因であり、1 番目の文は結果です。 (2)唐の詩に出てくる「飛花」という言葉は、ほとんどがポプラの花穂を指しています。あるいは、「空飛ぶ花穂」はポプラの花である柳の花穂を指します。その他の種類の花を指す場合は、「落ちた花」が一般的に使用されます。 「飞」という単語を使う必要がある場合は、「花」という単語を避けて、代わりに「飞英」などの単語を使用してください。 (3)賈道は「清風が柳の花穂を吹き、新火が厨房の煙を上げる」(この文章の断片は『世文雷句』に見られる)と詩を書いた。陳玉易は「春に飛柳の花穂はまだ寒く、外食はさらに寒い」(『路上の冷食』)と詩を書いた。胡子は「飛柳の花穂と散り花は晩春、強風と大雨が夕方に冷たくなる」(『条西遊韻叢花后記』第34巻参照)と詩を書いた。唐宋の詩人たちは、冷食や清明節の詩の中で、飛柳の花穂をよく言及していることがわかる。 もう一つの疑問は、柳はどこにでもあるのに、なぜ「皇室の柳」と特に言うのか? 街中に舞っている柳はすべて宮廷の柳の花穂なのか? この疑問には2つの説明がある。(1)唐代には宮廷に最も多くの柳があり、唐代の詩人たちは宮廷の詩の中で柳についてよく書いている。賈詡の朝廷前の詩には「千本の弱々しい柳が緑の髪に垂れ下がっている」とある。岑申の詩にも「柳は旗に擦れ、露はまだ乾いていない」とある。杜甫の詩「左野の遅出」にも「朝廷が終わって花は散り、庭に戻る途中、柳の中に迷い込んだ」とある。これらはすべて証拠となる。 (2)「皇帝の柳を用う」は、三文目の「漢宮」と共鳴し、詩の前半と後半が密接に関連している。 3番目の文の「夕暮れ」は寒食節の3日目の夕方を指します。寒食祭は毎年3月上旬に開催されます。開元7年に公布された暦では、3月9日が寒食節と定められました。そうなると、清明節は3月11日になるはずです。 「漢宮」は「唐宮」です。その日の午後、宦官は貴族や大臣たちに新しい火を灯したろうそくを配ったので、人々は「五侯」の家々までかすかな煙が立ち上るのを見ました。 「五侯」の由来は3つあります。その一つは、前漢の和平の年2月6日、成帝が王旦をはじめとする王妃の5人の兄弟に侯爵を授けたことです。当時、彼らは「五侯」と呼ばれ、大きな権力を持っていました。 2つ目は、東漢の桓帝の治世中、将軍梁基が権力を乱用し、息子、叔父、その他5人に侯爵の称号を与えたことです。当時、彼らは「梁家五侯」と呼ばれていました。 3つ目は、梁基の失脚後、梁基を殺害した山超を含む5人の宦官に侯爵の称号が与えられ、後に「五侯」と呼ばれるようになったことです。 「五侯爵」という表現が詩の中で使われる場合、それは通常、最も権力のある貴族、王族、または皇帝の最も寵愛を受けている役人を指します。唐如遜は、この詩は粛宗と代宗の治世中に寵愛を受け権力を濫用した宦官たちに対する風刺であると考えた。呉昌奇は、作者が王家の五侯爵を貴族の親族を表すために使用したと考えた。沈徳謙は、彼が言及している「五侯」が誰であろうと、要するに「高貴な側近」のことを言っているのだと信じていた。これら 3 つの解釈のうち、Shen Deqian の解釈は確かにより柔軟で、非の打ちどころがありません。唐説と呉説のどちらを選択するかを決めるには、韓鴻がこの詩を書いた時代を調べる必要がある。天宝時代に書かれたものであれば、楊貴妃の一族のことを指すと考えられる。皇帝の妃の3人の姉妹は皆、女官の称号を与えられ、従兄弟の郭忠と荀はともに高官であった。彼らは当時「五家」として知られていた。もしそれが大理時代に書かれたものであれば、権力を乱用した宦官を指していると考えられる。 唐如胤は次のように述べている。「当時、喫煙はまだ禁止されていたが、宮殿では蝋燭を回し、火を共にしていた。これは、皇帝に近く、皇帝の寵愛を受けていた五侯の家に最初に与えられた特権であった。」(『唐詩解』)彼は、寒食節の期間中、喫煙はまだ禁止されていたが、宮殿では蝋燭を回し、火を共にしていたことから、これは五侯の家に与えられた特権であったと考えていた。彼はまた、袁震の詩「特別令により宮殿に蝋燭を灯す」を例に挙げた。呉昌奇は「清明に火を焚くのは、寒食節の夜が近づいているからだ」とコメントした。これは唐に対する彼の反論だった。彼は寒食節の最終日の夜に新たな火を焚くことができると考えていたため、これは特権ではないと考えた。ここで疑問が湧きます。清明節に新たな火を灯す必要があるのでしょうか?清明節の前日の夕方に新たな火を焚くことは許されるのでしょうか?この疑問は、宋代の学者である葛立芳が著書『雲于洋丘』の中で昔から提起している。「『年夏隋史記』によれば、長安では毎年清明節になると、内園の役人の子弟が宮殿の前で火を焚く。最初に成功した者には絹三枚と金の鉢が褒美として与えられる。」これは、宮殿では、皇室庭園を管理する役人の子弟が清明節に宮殿の前の木に火を焚くことを明確に述べている。 杜甫の詩『清明』には「朝に火が消えて、また煙が上がる」とある。また「一族は青楓で火を掘る」とも書かれている。杜甫の一族は清明節の朝に楓で火を掘っていたことがわかる。戴樹倫の詩『清明節』には「朝、台所は新しく灯り、暗闇の中で柳に霜が舞う」とある。王堅の詩『寒食節』には「清明節には農家ではどの家庭も火を起こすのが遅い」とある。魏荘の詩『長安の清明節』には「宦官がまず清明の火を授け、宰相が無料で配った」とある。これらの唐代の詩から、清明節の朝には新しい火が使われていたことが分かる。張季には「寒食宴会」という詩があり、寒食の日に宮殿で宴会が開かれた様子が記録されています。状況は、人々が午前中に宮殿に入り、正午に宴会が開かれたというものです。食事をしている間、ホールの前でポロの試合が行われていました。宴会の後はアクロバットなパフォーマンスがあり、夕方まで続きました。詩の中には「宮廷の厨房は廊下に冷たい食べ物を配る」という一節があり、当時の宴会で出された食べ物はすべて冷たい食べ物だったことがわかります。冷食宴は唐代の宮廷における古い風習で、毎年行われるのが通例で、年一回のビュッフェとも言える。 この詩は、典型的なテーマを選択し、適切な暗示を引用して、寵愛を受け権力を持つ宦官の堕落を風刺することに長けています。非常に微妙に書かれているが、歴史的な暗示や唐代中期の社会状況の確認のヒントにより、読者は詩の主題を理解することができる。この詩は中唐の代表的な四行詩であり、永遠に残る傑作でもあります。 |
推薦する
古代の速達産業:魏晋時代に唐代に水産物を配達するために制定された規則
いつの時代も「速達」には距離とスピードの条件があります。秦と漢の時代、徒歩の配達員は一般的に短距離を...
明代『志農(撰)』:商之部・唐高祖全文と翻訳注釈
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
封神演義における渾源金杯の威力はどのくらいですか?それは最終的に誰のものになるのでしょうか?
渾源金杯は『神々の封じ込め』に登場する最も強力な古代魔法兵器の一つであり、その空間的パワーは巨大で、...
二十四節気における「白鹿」の意味は何ですか?白露節気とはどういう意味ですか?
葦は青々と茂り、白い露は霜に変わります。太陽が黄経165度に達すると、白露になります。通常は毎年9月...
「朱馬亭・鳳凰枕と雁幕」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
鳳凰枕と魯庵幕を聴く劉勇(宋代)フェニックス枕とフェニックスカーテン。 2、3年経つと、私たちは水と...
非常に鋭く、錆びない Kazhu チベットナイフはどのように作られるのでしょうか?
カジョ剣は一族の秘伝のレシピで作られ、鋼は11回彫られ、22日間磨かれます。 ナショナルナイフとして...
曹髙に関する逸話や物語は何ですか? 曹髙は何をしましたか?
曹魏(241年11月15日 - 260年6月2日)は、雅号を延氏といい、魏の文帝である曹丕の孫であり...
田万:崇禎帝の義父、陳元元にとっての三番目の男
陳元元の人生における3番目の男は田万(田紅宇)でした。田万は崇禎帝の義父であり、田妾の父であり、高官...
「武士の都への帰途に白雪を送る歌」は岑申の作で、辺境の軍営で都へ帰る使節に別れを告げる心温まる情景を描いている。
高史とともに「高實」と呼ばれた坤深は、唐代の辺境詩人です。坤深は長年辺境に住み、辺境の風景、軍隊生活...
李毅:唐代で最も冷酷な詩人だが、最も古典的な失恋詩を書いた。
本日は、Interesting Historyの編集者が、皆様のお役に立てればと願って、李毅の物語を...
「5月1日」の国際労働者の日の由来は何ですか?それはどんな話ですか?
19世紀には資本主義が急速に発展し、資本家は利潤追求のために労働時間と労働強度を増加させ、労働者を残...
水滸伝の「小呂布」こと方傑は、とても強大な人物でしたが、最後はどのように死んだのでしょうか?
水滸伝の「小呂布」こと方傑は、一人で五虎将軍の一人を殺せるほどの実力を持っています。彼は最後にどうや...
「君子は党を作らないから、困ったときに支援が得られない」とはどういう意味ですか?誰がそんなことを言ったのですか?
「君子は党を組まないから、困ったときに支援者がない」とはどういう意味でしょうか?誰が言ったのでしょう...
夜露燕溪は自ら軍を率いて万燕阿大を倒すことができるのか?
半年間の休息の後、阿具達はすぐに大量の兵士を補充した。その中には遼領内の渤海人や漢人が含まれていた。...
孟浩然の詩「永嘉河に留まり山陰の崔少夫国夫に手紙を送る」の本来の意味を鑑賞する
古詩「永嘉河に留まり山陰の崔少夫国夫に手紙を送る」時代: 唐代著者: 孟浩然私は水がたくさんある貧し...