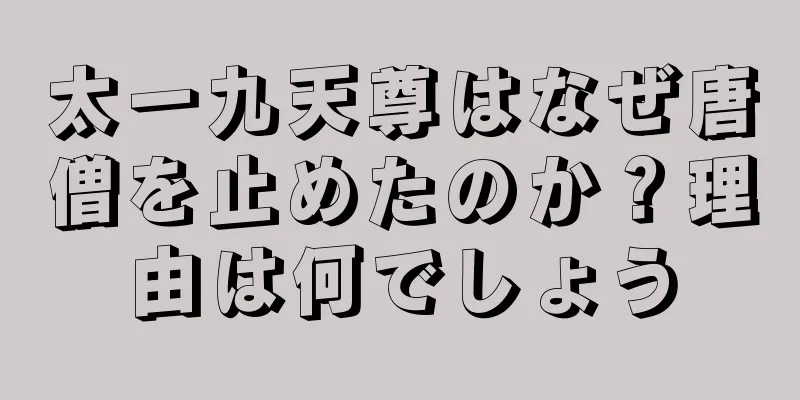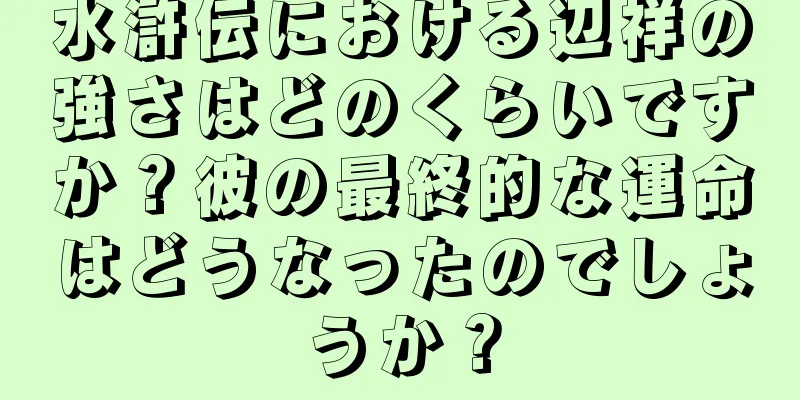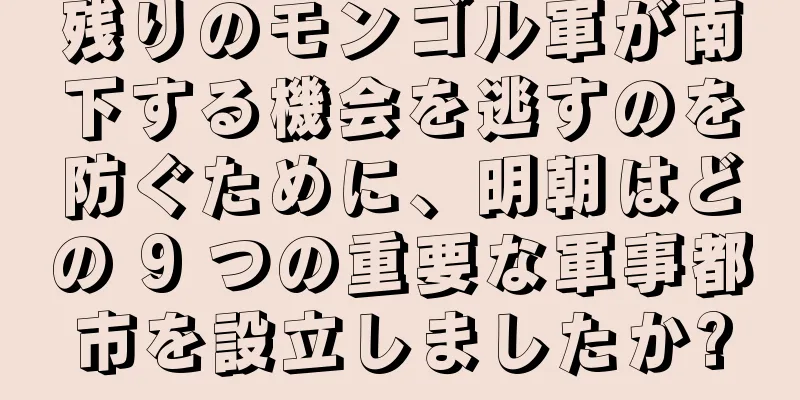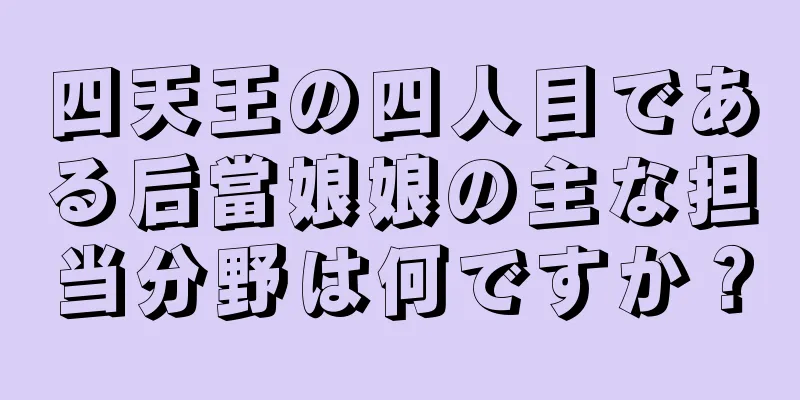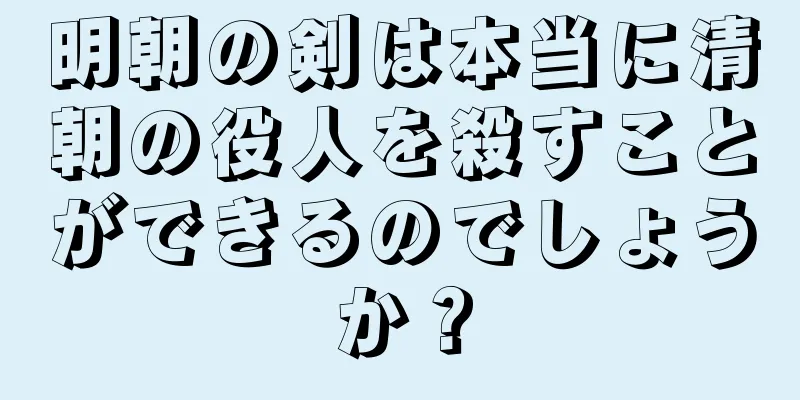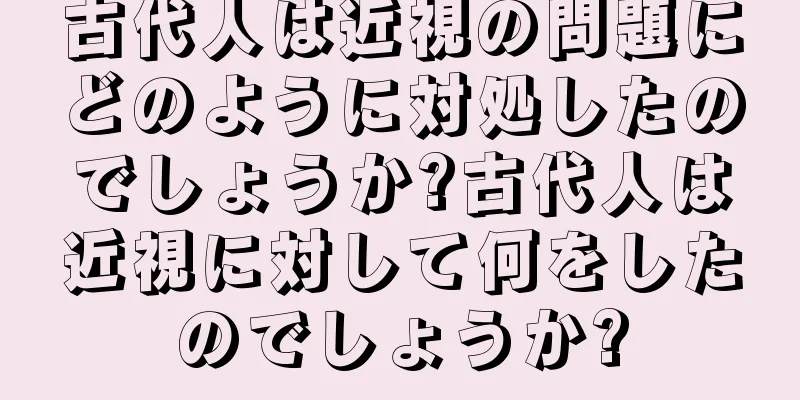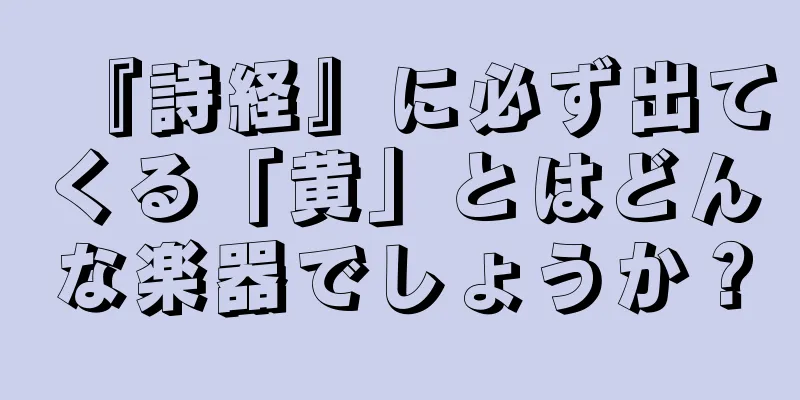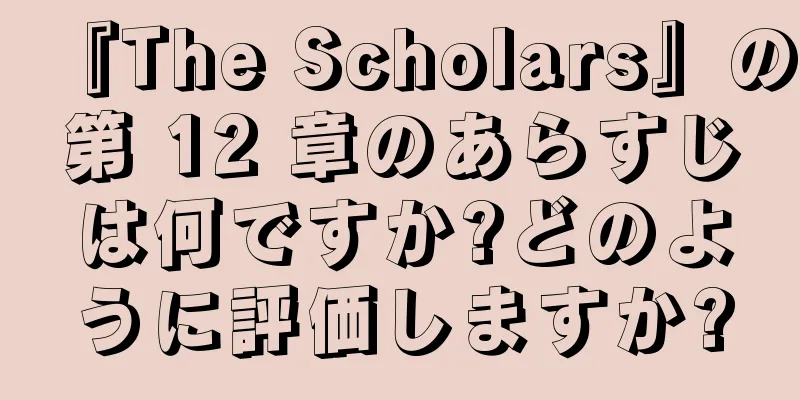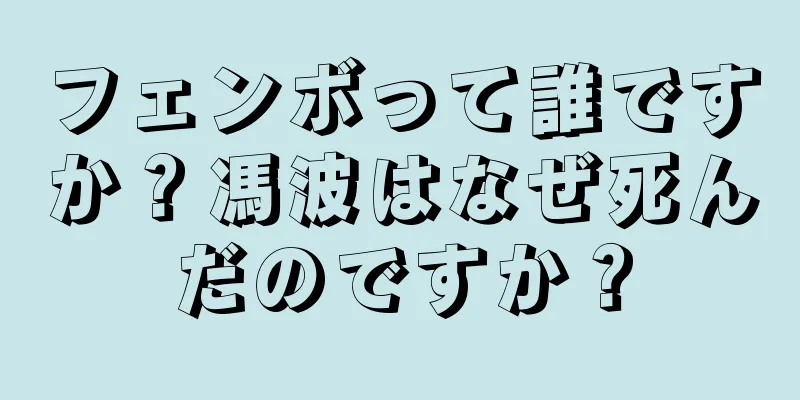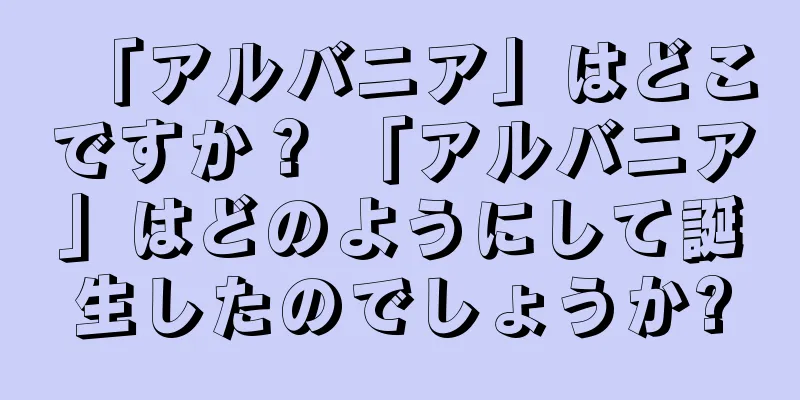龔子珍の『季海雑詩集・第5号』:政治的野心と個人的な願望の融合
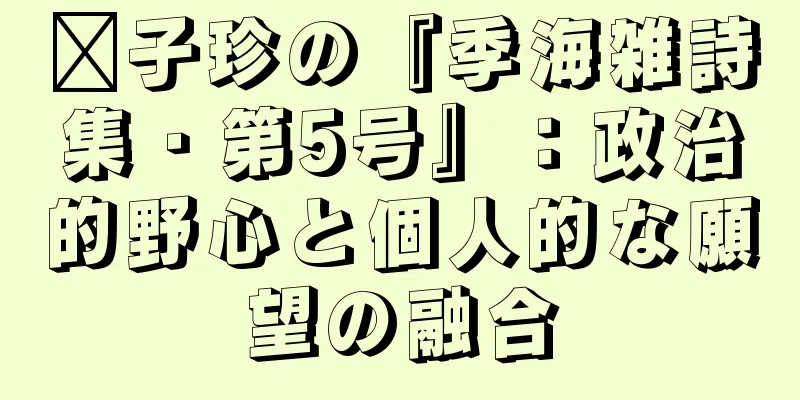
|
龔子真(1792年8月22日 - 1841年9月26日)、号は于仁、号は丁干(丁干とも呼ばれる)。漢民族、浙江省仁河(現在の杭州)出身。晩年は昆山の玉奇山閣に住み、玉奇山民とも呼ばれた。清朝の思想家、詩人、作家、改革主義の先駆者。彼は『定安随筆集』を著し、300以上の論文と800近くの詩を残しており、現在では『龔子真全集』にまとめられている。有名な詩『季海雑詩』には全部で315編の詩が収録されています。彼の作品のほとんどは郷愁と風刺に関するものである。それでは、次の興味深い歴史編集者が、龔子珍の『季海雑詩集・第5号』をお届けしますので、見てみましょう! 季海の雑詩·第5号 龔子真(清朝) 別れの大きな悲しみに圧倒されながら日が沈む。鞭を東に向けると、地平線はすぐそこにあった。 落ちた花びらは無情なものではなく、花を守るために春の泥に変わるものなのです。 この詩は1839年(旧暦の済海年)に書かれたもので、詩人の代表作である。その年、詩人は官職を辞して南の故郷に戻り、その後北へ嫁いで家族と再婚したが、その往復の途中で傑作とも言えるこの七字四行詩を創作した。この詩群は、詩人が見聞きしたことを回想し、過去を回想し、感情を表現したものであり、人生、思想、社会交流、公職、著作など、詩人の豊かな経験が芸術的に再現され、反映されており、詩人の社会理解力と現実批判力が晩年に新たなレベルに達したことを示している。アヘン戦争勃発前夜に書かれたこの詩には、国と時代に対する詩人の懸念が力強く表現されている。この詩は、詩人の辞職の決意、国家に奉仕するという信念と使命、改革の理想に身を捧げる崇高な精神を表現しており、楽観的な調子と鮮明なイメージを持ち、芸術的な魅力に満ちています。 詩の最初の 2 行は叙情的で物語的であり、無限の感情の中に大胆で自由な精神が表れています。別れは悲しいものですが、何と言っても私は長年首都に住んでいて、多くの古い友人がいて、過去は煙のようです。一方、別れは心が安らぎ、喜びでもあります。何と言っても私は檻の束縛から逃れ、外の世界に戻って何か違うことをすることができます。このように、別れの悲しみと帰郷の喜びが絡み合い、「別れの大きな悲しみ」と「歌いながら鞭を東に向ける」、そして沈む太陽と広大な地平線がそこにはあります。これら 2 つの絵は互いに補完し合い、その日の詩人の気分を忠実に反映しています。 中国の古典詩では、詩人は日没を自然現象やはかない時間の象徴として用いて、恋の悩みの激しさや別れの苦しみを表現することが多い。 「私が鞭を東に向けると、世界の終わりがすぐそこに迫っている。」 「韻編」は詩人の馬鞭を意味し、「東志」は今回の旅の目的地である詩人の故郷(浙江省)を指しています。 「世界の終わり」というのは、まだ家から遠いという意味です。鞭が振り上げられると、世界の終わりが目の前に迫り、首都からどんどん遠ざかっていく。元の時代の馬志遠は『天静沙』の中で秋の思いについて次のように書いている。「枯れた蔓、古い木、カラス、小さな橋、流れる水、人々の家。古い道、西風、痩せた馬。日は西に沈み、世の終わりには悲しむ人がいる。」 龔子真は「広大」で別れの悲しみを修飾し、「斜陽」で別れの悲しみを際立たせ、「世の終わり」で別れの悲しみを対比した。この多層的な描写方法は、馬志遠の「日は西に沈み、世の終わりには悲しむ人がいる」に似ている。ただ、龔子珍の「鞭で東を指し示せばこの世の終わり」は、彼が「悲嘆に暮れる男」であると直接言ってはいない。 論理的に言えば、龔子真は礼部での退屈な生活に不満を抱き、決然と職を辞し、故郷の杭州に戻って何かをしようと準備した。一人で都を離れた彼には、旧勢力に対する断絶と憎しみの感情しかなく、別れの大きな悲しみを感じることはなかったはずだ。唐代の詩人、劉璋は『北遊記』の中で「何の理由もなくまた桑干河を渡ると、汀州が故郷だった」と書いている。彼が言いたいのは、流刑地となったため、滞在した場所も故郷になったということである。違いは、龔子真は浙江省人河(現在の杭州)の出身であるにもかかわらず、子供の頃に北京に住み、10年以上にわたって礼部などの役人として働いていたことです。首都は長い間彼にとって第二の故郷となっていました。龔子真は自ら辞職を申し出たが、辞職の理由は下級官僚に転落し、生活が苦しく、そうせざるを得なかったためであり、客観的に見ると、北京を去らざるを得なかった。したがって、「離別という大きな悲しみ」には、仕事で成功しなかったこと、世間から無視されたこと、政治や思想における孤独感などに対する嘆きが含まれている。また、龔子珍は当時、遊女の霊霄と非常に親しい関係にあった。『季海雑詩』のテーマの十分の一は霊霄に関するもので、詩の一つには「赤は恋煩い、緑は悲しみ」と恋に落ちるとある。霊霄は都にいないが、このような状況下では、過去の生活に別れを告げる際に、しつこく残る「別れの悲しみ」を拭い去ることは難しい。龔子真が表現した「別れの悲しみ」が持つ意味は豊かで複雑かつ多面的であることが分かる。 夕暮れに舞い散る花びらが詩人の憂鬱をかき立てる。仕事は未完成で、年月は流れ、青春は去り、赤い太陽は沈み、彼は今回都を離れ、二度と戻らないかもしれない。散花の描写の専門家である詩人は、「春を訪ねる」のが好きだが、「春を見る」のがもっと好きで、花が咲くのが好きだが、もしかしたら花が散るのを見るのがもっと好きかもしれない。彼はかつて「西郊散花歌」の中で、飛んでいるサンザシの花は不思議な龍と鳳凰で、人間の世界に漂い、留まるためにやって来たと述べ、サンザシが強風で枯れる不思議な光景を「夜の銭塘の波のようで、朝の昆陽の無敵の戦いのようで、8万4千人の仙女が一緒に顔を洗って口紅を塗っているよう」に例えました。 「また、浄土の落花は深さ4寸とも聞き、特に目を閉じて思い描くことに魅了されました。」 「果てしなく花が咲き、新しく美しい雨が降る木があり、落花の時期が360日も続くなんて、あり得るのだろうか?」と想像しました。彼は散りゆく花びらについて数多くの素晴らしい比喩を使ってきたが、今、詩人は突然、散りゆく花びらのように感じた。京都に別れを告げ、馬車で都を後にした詩人は、道中、散りゆく花を眺めながら、感傷的な気持ちに浸り、豊かな想像力を膨らませました。官僚社会の抑圧、重苦しい雰囲気、息苦しい人間性、困難な生活、詩人は自らの人生経験を散り散りになった花と完全に融合させた。 「散った花びらは無情なのではなく、花を守るために春の泥に変わるのだ」。詩人は別れの気持ちを表現することから、祖国に奉仕するという野望を表現することへと口調を変えている。また、陸游の「泥に落ちて塵になっても、香りだけが残る」という言葉を裏返しています。落ちた花びらは、もともと枝から落ちた花を指しますが、無情なものではありません。たとえ春の泥になっても、美しい春の花の成長を育む意志があります。自分の香りのためではなく、花を守るためです。この詩は、官職を離れた後も、国の運命を気にかけ、国に奉仕するという志を忘れていないことを示しています。これは、死ぬまで国を愛する彼の情熱を表現しており、詩人の崇高な志を十分に表現しており、代々受け継がれる名言となっています。 散った花は決して無情な無駄ではありません。詩人は、故郷に戻って学院を率い、教えるべき学生を集め、学生たちに自分の知識や考えを伝え、変化への熱意と未来へのビジョンを学生たちに植え付け、国と人々のために最後の力を尽くすために、祭祀省長官の職を辞しました。花は根元に落ちて春泥となり、新たな春を生み、その色と香りを後世に残す。詩人は絶えず変化する自然の法則にインスピレーションを受けています。花は自然の中で咲いたり散ったりし、風雨にさらされても自然に、感情を持たずに咲いたり散ったりします。散った花びらが「有情」であるか「無生物」であるかは、一概には言えません。詩人が自分の人生経験と散った花びらを完全に融合させ、自分の感情を移入したからこそ、散った花びらも人間の感情を持ち、有情となるのです。落ちた花には愛情があり、それは「花を守るために春の泥になる」という新しい色彩の世界を創りたいという願いに反映されています。この時点で、詩人はついに自分の混沌とした思いを舞い散る花のように捕らえ、悲しみから解放され、時代の使命感を持って荘厳で神聖な領域に昇っていった。 「春の泥になって花を守る」は飛花の孤独であり、腐敗した官僚制度と決別し、暗黒の勢力と戦うという詩人の厳粛で神聖な誓いでもある。国と国民のため、花の繁茂のため、私は自らを犠牲にして春の泥になることもいとわない。 この短い詩は、政治的野心と個人的な願望を統合し、叙情性と議論を有機的に組み合わせ、詩人の複雑な感情を生き生きと表現しています。龔子真はかつて詩について「詩と人は一体であり、人の外に詩はなく、詩の外に人はない」(『唐海秋の詩集を書いてから』)と語っており、彼自身の創作はこれを最もよく証明している。 |
<<: 李白の「王長齢が竜彪に降格されたと聞いて、遠くからこの手紙を彼に送った」は同情と心配に満ちた詩である
>>: 蘇軾の最も優美な詩:「滴蓮花 - 春は衰え、草は枯れる」
推薦する
「花鴨」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
花鴨杜甫(唐代)アヒルは泥をつかまず、階段の前をゆっくりと歩いています。羽は独立性を知っており、黒と...
さまざまな歴史記録には甘寧の生誕と没年について何が記録されているでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
東周史第38章:周の襄王は混乱を避けるために鄭に逃げ、晋の文公は約束を守って元に降伏した。
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
古代において「暴君を倒し、裏切り者の大臣を斬首する」ために使われた 4 つの偉大な魔法の武器の区分は何ですか?
古代に「暴君を倒し、裏切り者の大臣を斬首する」ために使われた四大武器とは何か知りたいですか?この四大...
唐代の女性はどんな服装をしていたのでしょうか?唐代の衣服は本当に露出度が高かったのでしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が皆さんのために用意しました: 唐代の衣服は...
銃に赤い房を結んでいるのは見た目のためだけでしょうか?古代の銃身にはそのような機能があったのでしょうか?
よく言われる「十八の武術」は実は「十八の武器」であり、「銃」もその一つで、我が国では非常に長い歴史と...
秦国を弱体化させるために燕王丹がとった戦略は何でしたか?燕国は暗殺者に運命を託した
燕国は秦の王によって完全に滅ぼされた4番目の国であり、戦国時代の七国の中では漢を除いて最も弱い国でし...
孟子:梁慧王書第七章(上)原文、翻訳、注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
「紅楼夢」の邢夫人は道徳心がなく、迎春を全く教育できない
『紅楼夢』の邢夫人は応春の継母であり、嫡母でもある。応春は嫡子ではないが、彼女を教育するのは邢夫人の...
「秦の秋の情に関する袁先生への手紙」の内容は何ですか? 「秦中秋を袁先生に送る」の詩を鑑賞
本日は、『Interesting History』の編集者が「秦秋詩」(袁先生に贈る詩)の解説をお届...
「紅楼夢」の賈家は以前ほど良くはないが、素晴らしい背景を持っている
「痩せたラクダは馬よりも大きい」ということわざがあります。『紅楼夢』の賈家は以前ほどではありませんが...
なぜ誰も古代の銀紙幣を偽造しようとしなかったのでしょうか?偽造防止技術は非常に進歩している
ご存知のとおり、世界最古の紙幣は我が国の宋代に登場しました。当時の紙幣は、餃子や会子と呼ばれていまし...
中国皇帝の乳母はどれほどの権力を持っているのでしょうか?古代における乳母の役割
古代の王家の乳母はどれほどの権力を持っていたのでしょうか?古代において、乳母とは、他人の子供に乳を与...
孫光賢の「環西沙・刺繍のカーテンから漂う香りを風が運ぶ」:この詩は女性の嫉妬を描いている
孫光賢(901年 - 968年)は、孟文と号し、宝光子と号し、陵州桂平(現在の四川省仁寿県湘家郷桂平...
『紅楼夢』で甄世銀が太虚を訪れた際に突然起こった災難の目的は何だったのでしょうか?
長い時間の流れは止まらず、歴史は発展し続けます。『Interesting History』の編集者が...