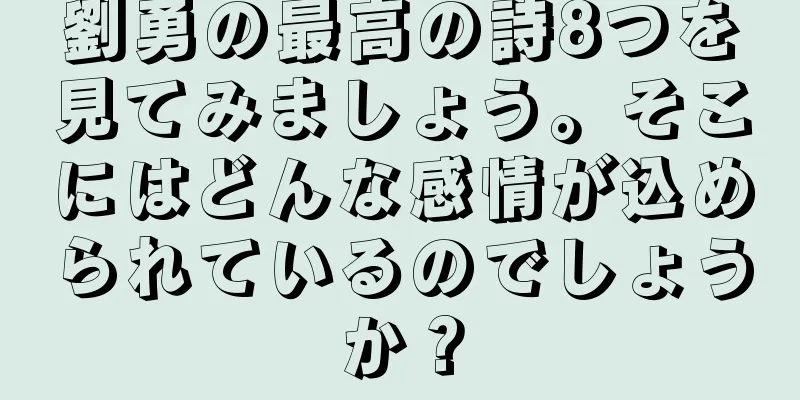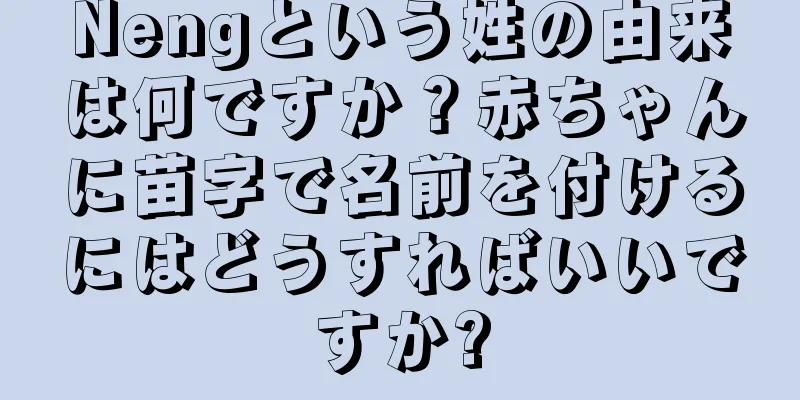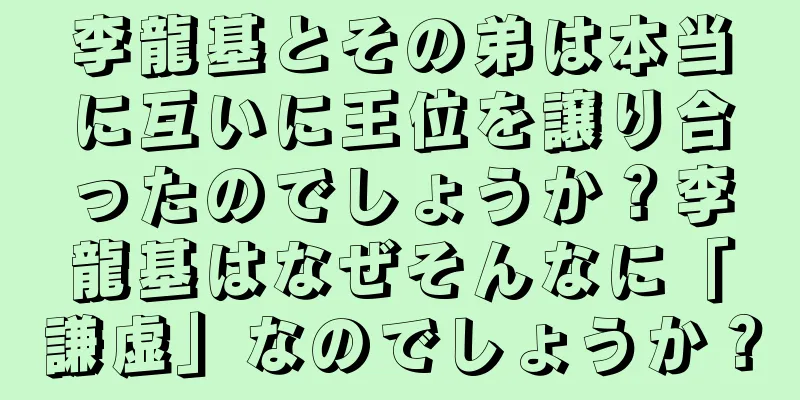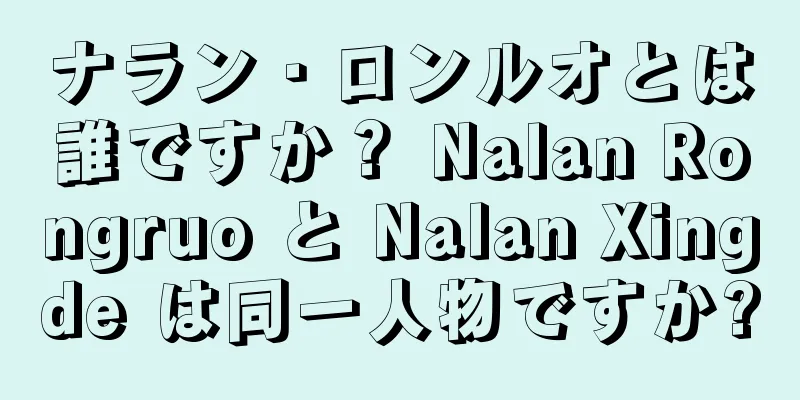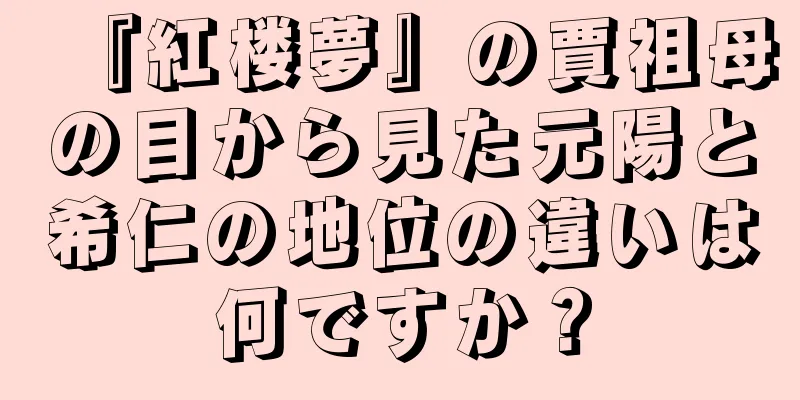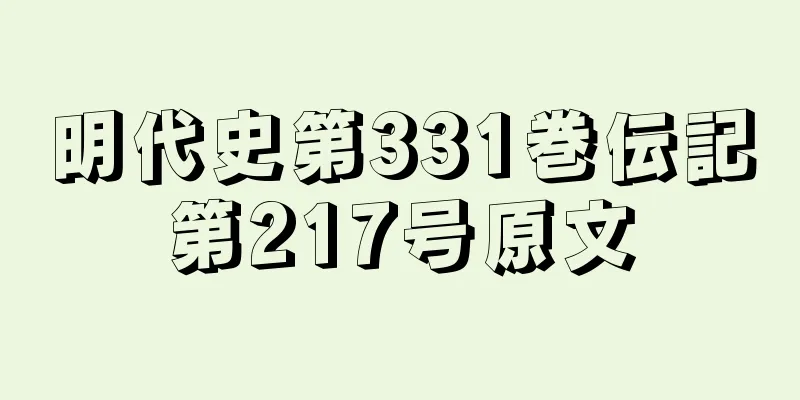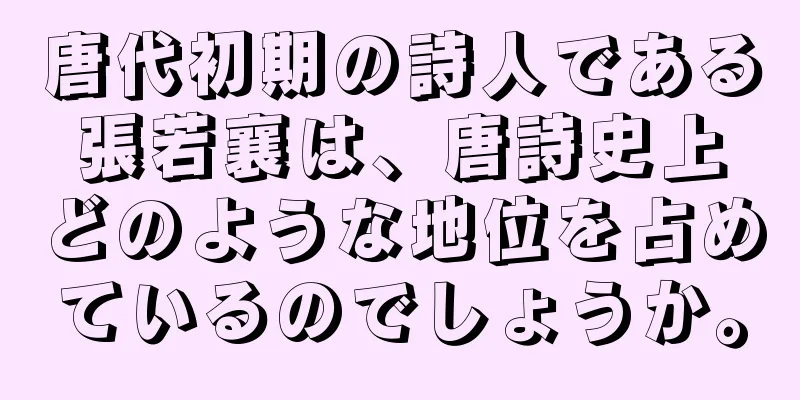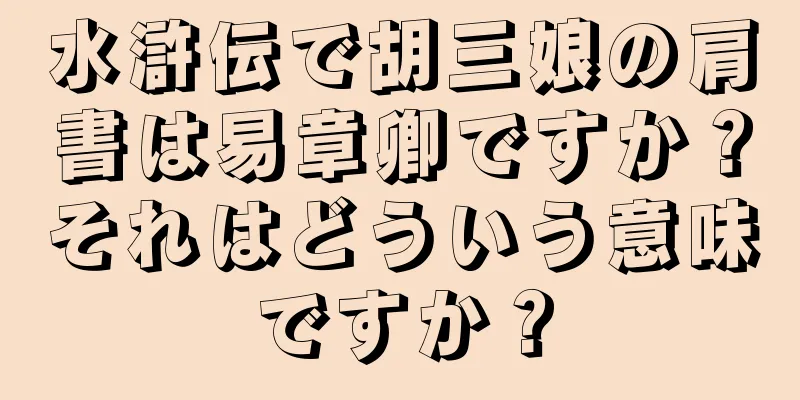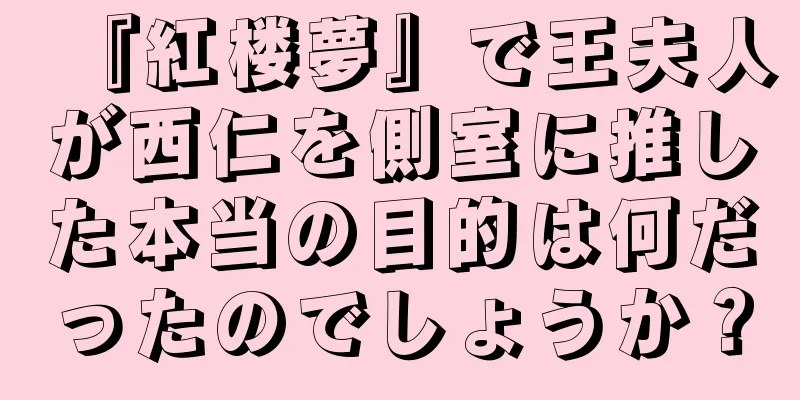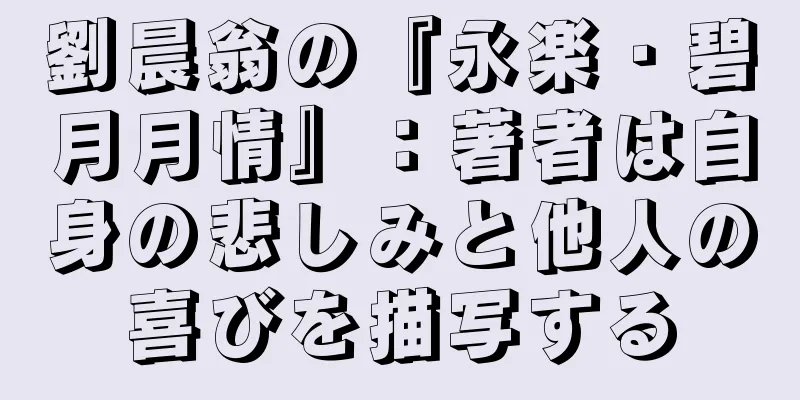張九玲の『夫徳子君子初易』:この詩は新鮮で愛らしく、強い生命感に満ちている
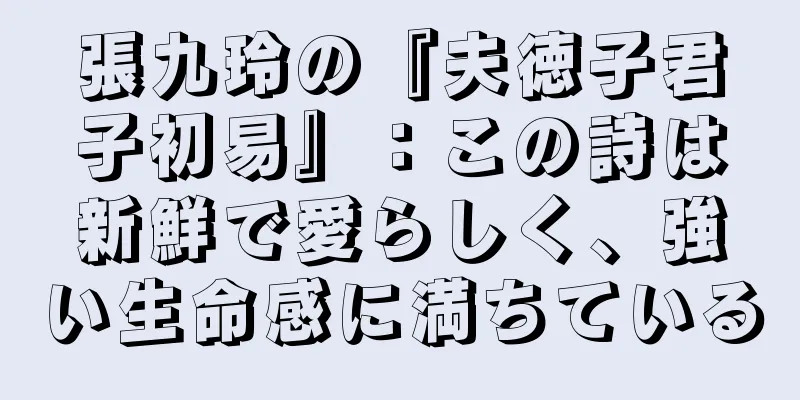
|
張九齢(673-740)は、雅号は子首、通称は伯武で、韶州曲江(現在の広東省韶関市)の出身である。唐代開元年間の有名な宰相、政治家、作家、詩人であり、西漢代の劉侯張良の子孫であり、西晋代の荘武公張華の14代目の孫である。彼は、五音節の軽妙な文体の古代詩を積極的に創作し、簡潔で平易な言葉で人生に対する深い志を表現し、特に唐代初期に実践されていた六朝の贅沢な詩風を一掃することに多大な貢献をした。彼は『曲江集』を著し、「嶺南第一の人」と賞賛された。それでは、次の興味深い歴史編集者が張九玲の『夫徳子君之初易』をお届けしますので、見てみましょう! この詩はあなたから生まれました。 張九齢(唐代) あなたが去ってから、私はもう残った機械のことを気にしなくなりました。 あなたに対する私の思いは、夜ごとに輝きが薄れていく満月のようなものです。 この詩は賦の形をしています。賦詩の題名であろうと、賦詩の行であろうと、それは模倣です。六朝から唐代にかけて、これを模倣した人が数多くいました。詩人は詩を学ぶ練習としてそれを真似した。 最初の文「Since you left」は完全な文です。愛する人は家から遠く離れて旅をし、戻ってきませんでした。これは時間の概念を示しています。この詩には恋人がどれくらい家を離れていたかは書かれておらず、「壊れた織機の手入れはもうしない」という一文だけが書かれており、考えさせられる。第一に、織機は壊れていて長い間修理されていないことから、恋人が長い間家を離れていて、女主人が長い間織機を使って織っていないことがわかる。第二に、家が空っぽだと言えば、空虚感や孤独感を与える。そして、男が織機を壊したまま立ち去るシーンも、古くて退廃的で、雰囲気が寂しく荒涼としているように感じさせます。第三に、織機の上の布は何度も織られていますが、決して完成しません。これは、女主人が気が散っていて、織る意志がなく、内心非常に不穏であることを物語っているようです。 以上が事件の原因の要約です。その後、詩人は比喩を使って彼女の心の奥底の活動を描写します。「あなたを思う私の思いは、夜ごとに明るさが減っていく満月のようなものです。」 『十九古詩』の「別れの日は遠くなり、私の衣服は日に日に緩んでいった」(『歩いてまた歩いて、十九古詩』)という行は、夫を恋しがる女性の衰弱したイメージを直接描写しており、文章は非常に具体的で際立っています。ここで詩人は明るい月を使って、女性の感情の純粋さ、無邪気さ、忠誠心、献身を象徴しています。 「夜の経過とともに空の明るさは薄れていく」という一節は、繊細で、巧みで、誠実で、感動的な方法で書かれています。比喩は素晴らしく適切であり、想像力は斬新でユニークであり、詩全体が新鮮で美しく、力強い生命の息吹に満ちています。 |
<<: 張九玲の『情と出会いの詩十二篇 第七』:気取りや飾りや曖昧さのない
>>: 張九玲の「鏡を見ると白髪が見える」:詩全体はわずか20語だが、感情は深く暗い
推薦する
遼・金・元の衣装:元代の人々の衣装
元代の人々の衣装の一つ元代の人々の服装:元代の漢人のほとんどは頭にスカーフを巻いていましたが、決まっ...
三国志演義第87章:宰相は南の侵略者を征服するために大軍を編成し、蛮族の王は最初に捕らえられた。
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
諸葛孔明の八図とは何ですか?
八卦陣は、諸葛亮が若い頃に易経を研究して作ったものです。太一は三才を生み、三才は四象を生み、四象は八...
蕭叔妃の娘である易陽公主、李夏玉、易陽公主はどのようにして亡くなったのですか?
中国の唐の時代の皇帝高宗李治の長女、李夏玉(640年代? - 691年)は、初め宜陽公主と名付けられ...
琵琶刑法とは何ですか?琵琶演奏に関する刑法の詳しい説明
琵琶を弾く刑罰とは何ですか? 琵琶を弾く刑罰は明代に発明された拷問で、主に金義衛と東昌が拷問の際に使...
西遊記の玉兎の仙女の起源は何ですか?彼女はなぜ地球に来たのですか?
テレビドラマ「西遊記」をご覧になった方は、西遊記の最後の妖怪が玉兎だということはご存じでしょう。これ...
『紅楼夢』の劉おばあちゃんのキャラクターはどんな感じですか?彼女はどんな役を演じたのですか?
劉老洛の性格特性まず第一に、劉おばあさんは人との付き合いにおいて抜け目がなく、機転が利く人です。劉お...
孟浩然の詩「秋に李世玉に随って宋子河を渡る」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「秋に李世玉に随伴して宋子河を渡る」時代: 唐代著者: 孟浩然李世宇と宋子江を渡る南鶏渓は広大...
古代皇帝の長寿の秘密は何だったのでしょうか?錬金術はなぜ「黄白の技法」と呼ばれるのでしょうか?
古代の皇帝にとって不老不死の秘密は不老不死の薬を作ることでした。初期の錬金術では、「外部のエリキシル...
「秋の音への頌歌」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
秋の音への頌歌欧陽秀(宋代)欧陽子は夜、本を読んでいると、南西の方から音が聞こえた。彼は恐れながら耳...
南宋時代の魏清志の詩集『詩人の玉塵』第5巻全文
『詩人の玉塵』は南宋時代の魏清志が書いた詩談集です。魏清志は、字を春甫、号を聚荘といい、南宋時代の建...
『紅楼夢』で、賈宝玉はなぜ薛宝才と一緒に暮らすよりも僧侶になることを選んだのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
李尚銀の「無題:莫愁堂の重厚な幕が深く引かれる」:言葉遣いは優しくて悲しく、感情は繊細で揺るぎない
李尚鑫(813年頃 - 858年頃)は、字を易山、号を毓曦生といい、淮州河内(現在の河南省沁陽市)の...
魏史書 五皇記 第五巻◎高宗皇帝の記録原文
高宗文成帝は、本名を鈞といい、公宗景武帝の長男であった。彼の母親の名前はルーでした。真君は治世の元年...
古代人が最も好んで使った言葉は何か:古代文学に最も頻繁に登場する言葉
わが国の古代文学は膨大で数が多く、代表的なものとしては、秦以前の文学、漢籍・漢楽譜、南北朝の並置散文...