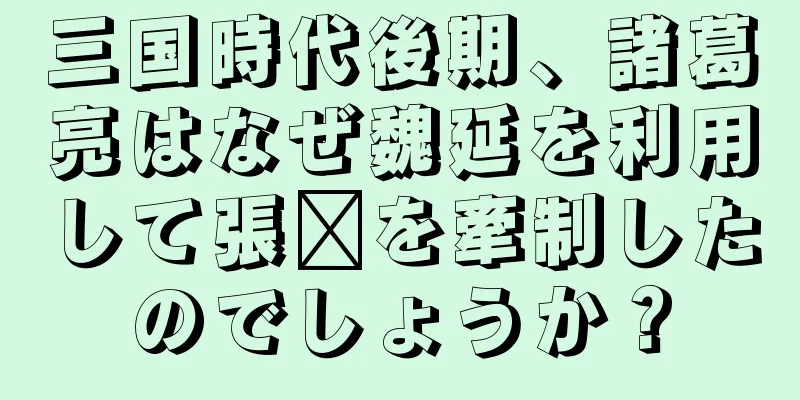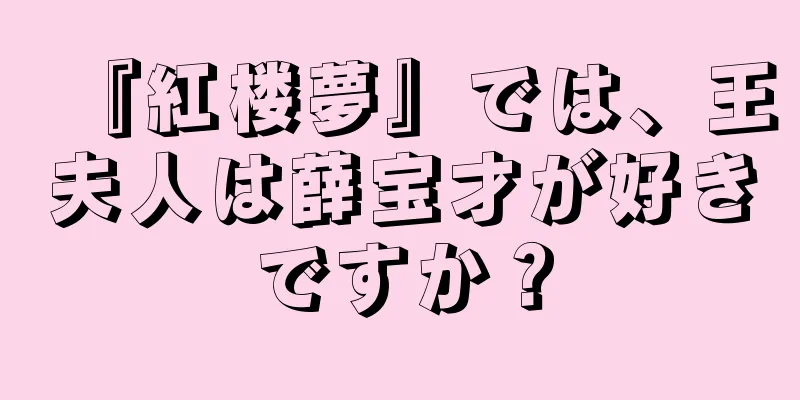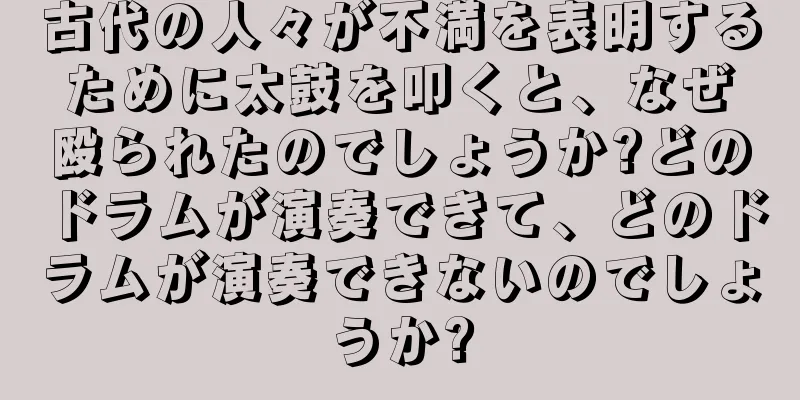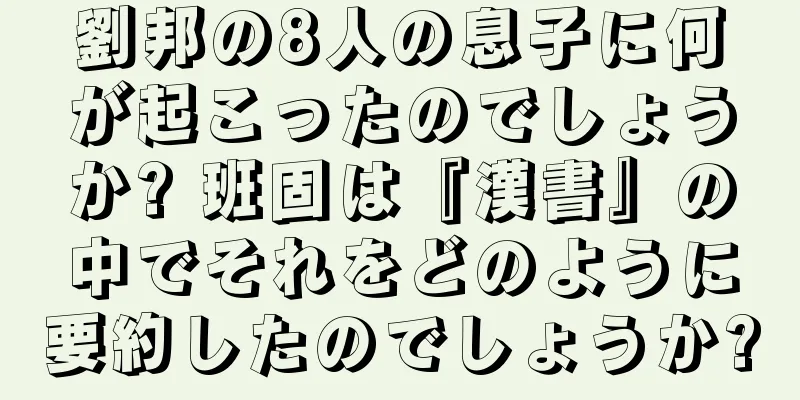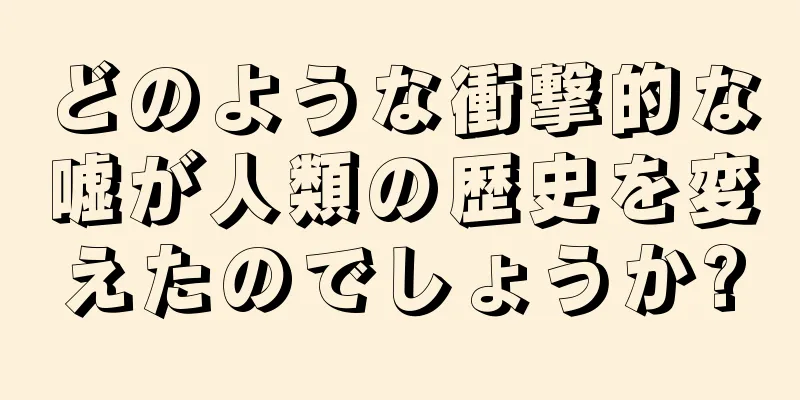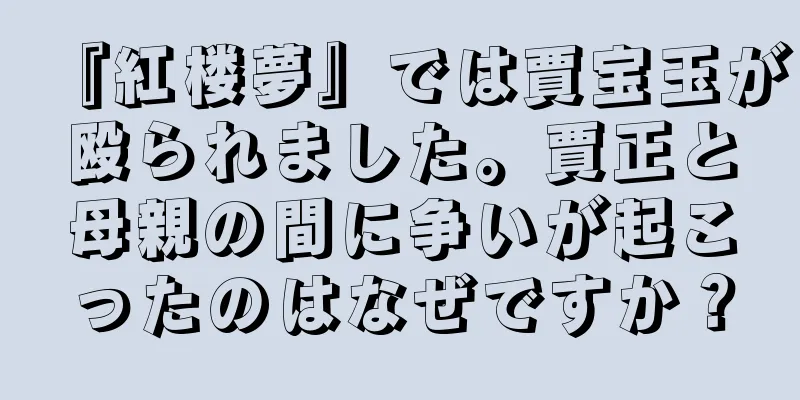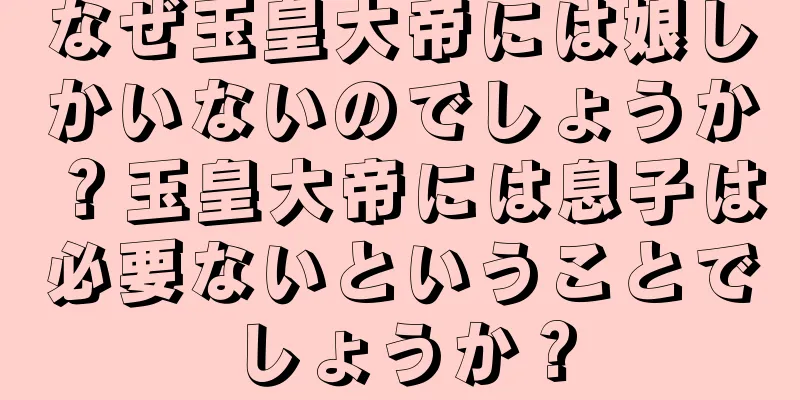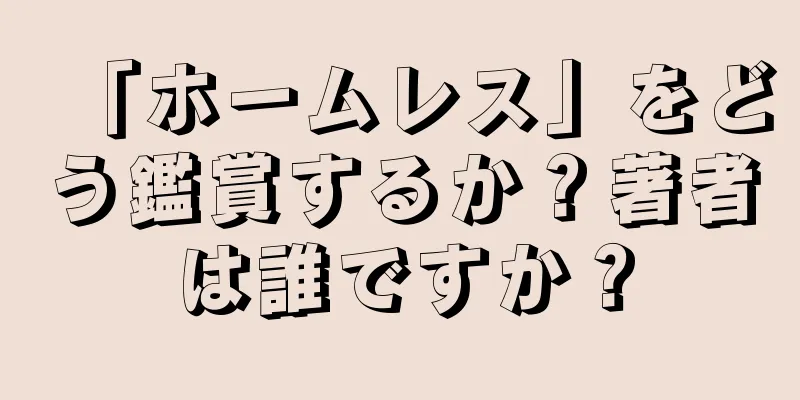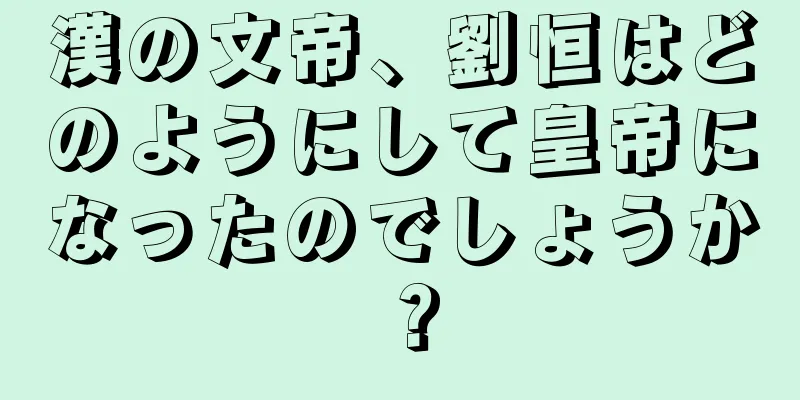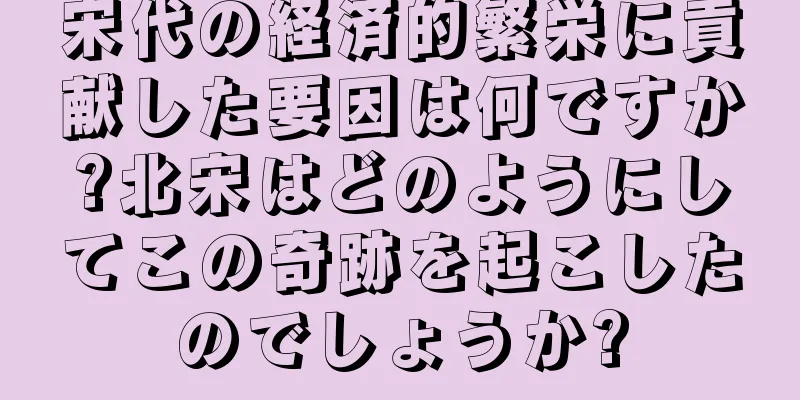詩集:国の風:詩の衰退
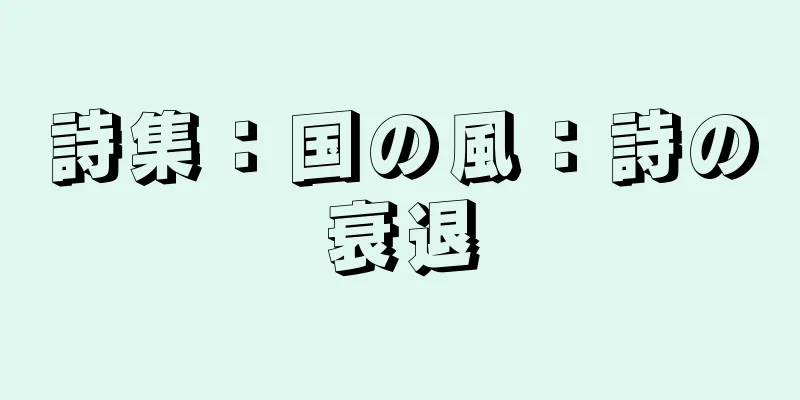
|
アノニマスの衰退 衰退している、衰退している、なぜ戻らないのか?あなたがいなかったら、なぜ真ん中に身をさらすのか? 衰退、衰退、なぜ戻らないのか?謙虚な自分ながら、なぜ泥沼にはまっているのか? 翻訳 暗いよ、暗いよ、どうして家に帰らないの?君主のためじゃないなら、なぜまだ露の中で働いているの! 暗いよ、暗いよ、どうして家に帰らないの? 君主のためじゃないなら、なぜまだ泥の中で働いているの! この詩の主題について、『茅詩』は、李侯が濟に追われて魏に追放されたとき、臣下たちが李侯を説得して帰国させるためにこの詩を書いたと伝えている。劉湘の『女人伝 貞節篇』には、衛侯の娘が黎荘公に嫁いだが拒絶されたとある。ある人は彼女に帰国を勧めたが、彼女は「最後まで貞潔を守り、女の道徳に違反せず、王の命令を待った」とあり、この詩を詠んでその志を表現した。どちらの説も無理がある。なぜなら、それが実際に李侯のことなのか、それとも李荘の女性のことなのかを裏付ける歴史的証拠が欠けているからだ。于観英は「これは労働に苦しむ人々の嘆きである」(詩選)と考えており、これがこの詩の最も適切な意味であると考えました。 この詩は 2 つの章から成り、どちらも「衰退している、衰退している、なぜ家に帰らないのか」で始まります。暗くなってきた、暗くなってきた、なぜ家に帰らないのか。その後、詩人は理由を説明します。「あなたがいなかったら、なぜ私は露にさらされていたのでしょうか」「あなたがいなかったら、なぜ私は泥の中にいたのでしょうか」これは、君主の務めと高貴な身体を養うために、一年中昼夜を問わず露と泥の中で懸命に働かなければならないことを意味します。わずか 2 章と数文で、奴隷たちの非人道的な状況と支配者に対する彼らの憤りが読者に非常に深い印象を残します。 芸術的に見ると、この詩には2つの特徴があります。 1つは、質問することで言語効果を強化することです。詩全体から判断すると、「衰退している、衰退している、なぜ戻らないのか」は、疑いから尋ねられた質問ではなく、確固とした考えを念頭に置いた意図的な質問です。詩人は支配者から抑圧を受け、昼夜畑仕事をし、家に帰ることもできず、ひどく苦しんでいた。当然、不満を吐き出したいと思ったが、直接話せば、すべてを言い表すのは簡単だ。疑う余地はないのにわざと疑念を抱かせるこの疑問形の使用は、詩を屈折して感傷的に見せ、同時に注目を集め、人々に考えさせる。諺にあるように、表に出さなくても恨みは深い。 2つ目は、韻を使って感情的な雰囲気を作り出すことです。この詩は2章10文から成り、各文に押韻が用いられているだけでなく、各章ごとに押韻が変わっています。そのため、詩全体が簡潔で、リズムが短く、緊迫した雰囲気があり、労働者たちの苦しい心境と、暴政を放棄する決意が十分に表現されています。この詩に使われている韻から判断すると、第一章では「微雲」と「雨雲」が使われており、第二章では「微雲」と「秦雲」が使われている。これらの韻は、悲しみや痛みの感情を表現するのにより適している。詩人が自分の感情に応じて韻を使うことで、韻を通して詩の感情的な調子が十分に強調されます。そのため、方雨潤はこの詩について次のように評した。「言葉は単純だが、意味は深く、無限の真理を含んでいる。不注意な人が不用意に読むことは許されない。」 (『詩原集』) 毛師はこの詩を帰郷の勧めと解釈し、歴代の史師を研究した人々は主に毛師の解釈に従ったため、「史為」という言葉は次第に中国の古典詩における「隠遁」のイメージへと変化していった。例えば、王維の「私はここの悠々自適を羨み、憂鬱に史為を詠む」(『渭川の農民』)、孟浩然の「あなたが故郷を離れるので、私は遠くから史為へ詩を送る」(『都の鄭に辛博士を送る』)、管秀の「東風が吹いて史為を詠むと、深い雲の中の道士が私を故郷に呼び戻す」(『杜将軍に告す』)などであり、この詩が後世に与えた影響も明らかである。 |
<<: 『詩経・国風・毛丘』の意味は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
>>: 『詩経・果鋒・瓜の葉は苦い』の意味は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
推薦する
「The Scholars」に登場するルー家の若旦那はどんな人物ですか?
「士大夫」は清朝の呉敬子が書いた小説です。ご存知ですか?次は、Interesting History...
曹操が孫権に宛てた手紙の中で、赤壁の敗北は周瑜の火攻めによるものではないと書いたのはなぜですか?
蘇軾は『年女嬌・赤壁の昔を偲ぶ』の中で、「東風は周朗に不利で、喬姉妹は春の深まりに銅駁亭に閉じ込めら...
「彭公事件」第2章:主人公は怒って張紅を殴り、徳の高い大臣が悪党を訪ねる
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
政治的、経済的観点から、楊広はなぜ大運河の建設によって国を失ったのでしょうか?
私の国には、混乱の時代を終わらせた有名な統一王朝が 2 つあります。初代皇帝は文人としても軍事戦略家...
劉毓は貧困の家庭に生まれました。どのようにして彼は庶民から出世し、南宋の建国者となったのでしょうか。
庶民が皇帝になるのは珍しいことだが、不可能ではない。南宋の創始者劉裕もその一人だ。劉宇は貧しい家庭に...
『呂氏春秋・士人出現論』の尚農の原文は何について語っているのでしょうか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『呂氏春秋・士容倫』の原文は何を語っているのか?どのように理解するのか?これは多くの読者が関心を持っ...
古代の硬貨はどのようなものだったのでしょうか?古代のお金と硬貨は同じものですか?
一般的に、今日総称して「貨幣」と呼ばれるものは、実は起源が異なります。前者は農具に由来する「安価な物...
『旧唐書』巻135の前半にはどんな物語が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
どちらの色がより高貴でしょうか?古代人の「色の階層」という概念!
今日は、Interesting Historyの編集者が、皆さんのお役に立てればと願って、古代の「カ...
遼・金・元の衣装:金の男性の衣装
晋の時代の男性は頭に黒いスカーフを巻き、丸襟のローブを着て、腰に胡帯を締め、黒い革のブーツを履いてい...
Qifu Chipan の紹介 Qifu Chipan はどのようにして亡くなったのでしょうか?
河西鮮卑の奇夫久凡(?-428年)は、西秦の武元王奇夫千桂の長男であり、十六国時代の西秦の君主であっ...
シベ族の慣習や習慣におけるタブーは何ですか?
シベ族のタブー文化特定の歴史を持つ国であれば、長い発展の過程で何らかのタブーが生まれます。それは社会...
実は孫悟空には宿敵がいます。その宿敵とは誰でしょうか?
『西遊記』を全部読んだ後、多くの人が疑問に思うのは、孫悟空が権力を握ったばかりの頃は天宮で騒ぎを起こ...
三国志演義では、関羽は三日月形の剣を使って四方を征服しました。この剣は本当に歴史上に存在したのでしょうか?
小説『三国志演義』では、緑龍三日月刀は関二業の武器です。英雄にふさわしい貴重な刀です。関二業は緑龍三...
劉勇の『斉史・晩秋』:宋人は『李燮』と比較した
劉雍(984年頃 - 1053年頃)は、もともと三弁、字は景荘であったが、後に劉雍、字は斉青と改めた...