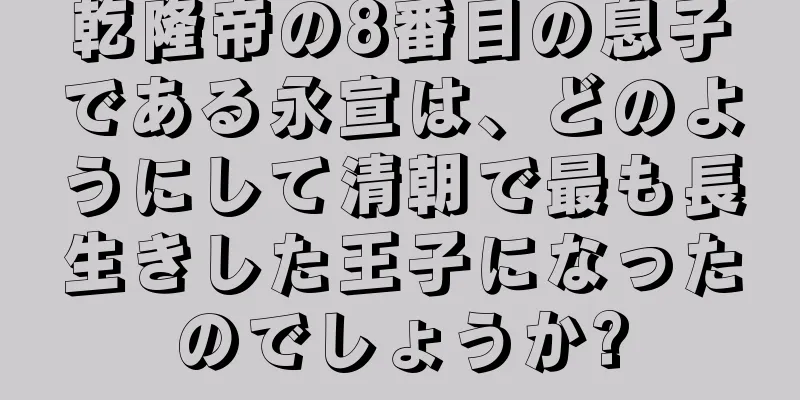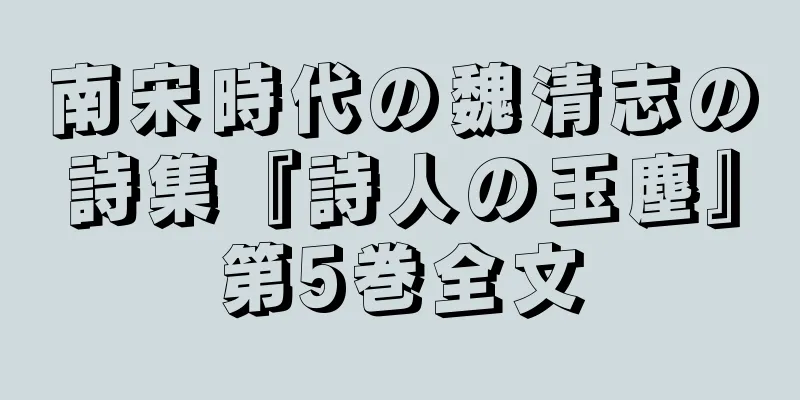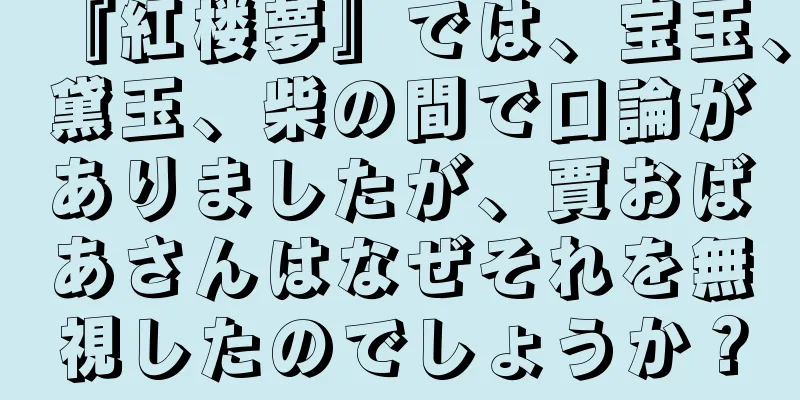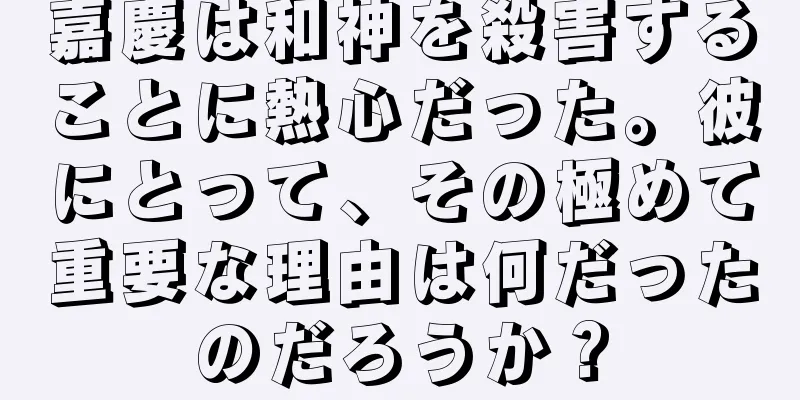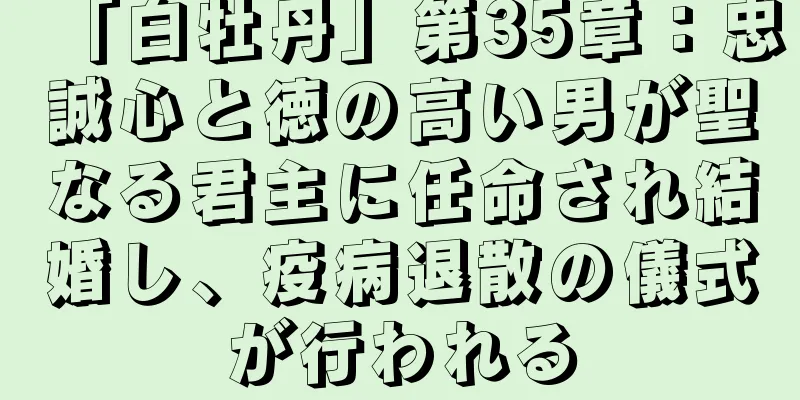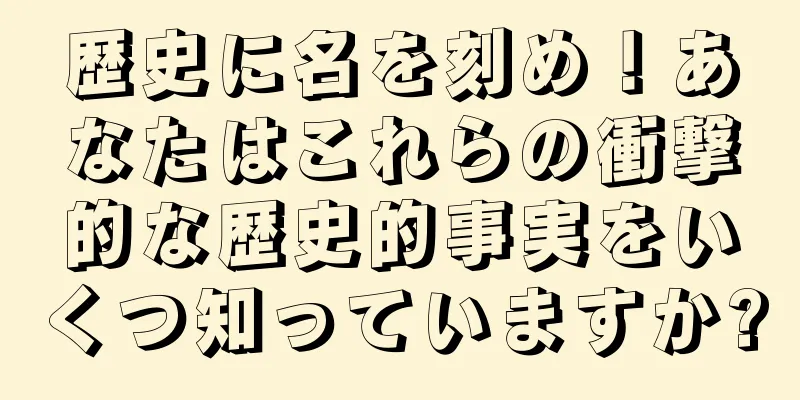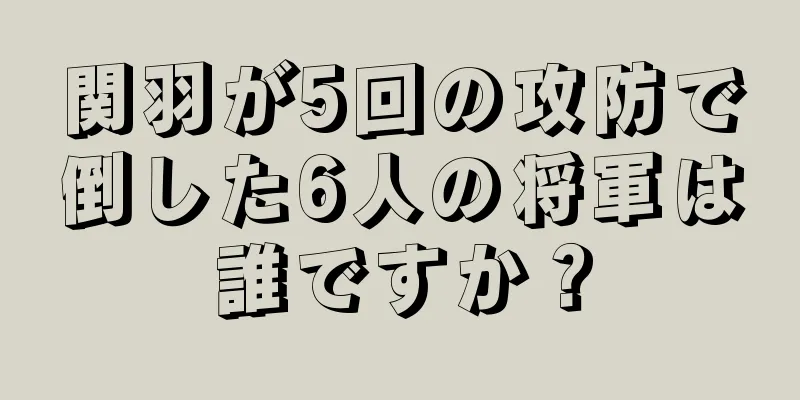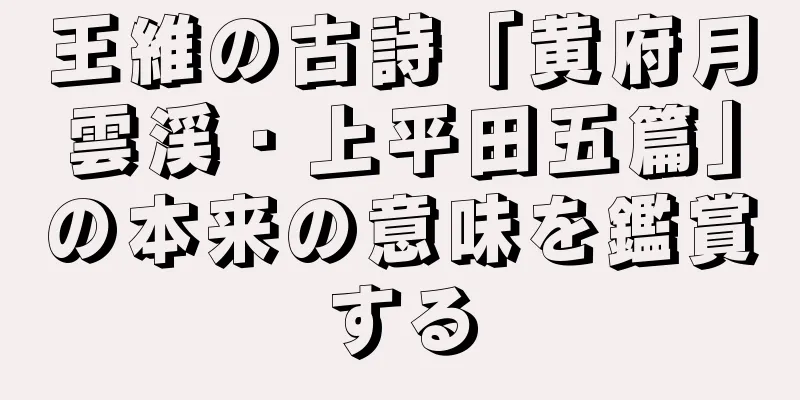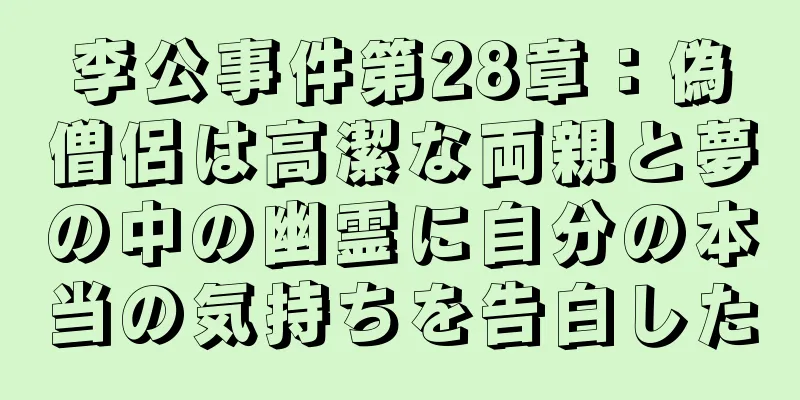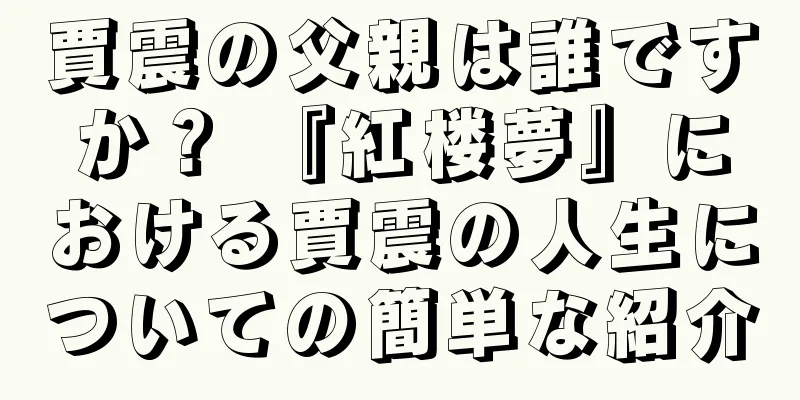「Que Tadezhi: 無駄な感情は長い間捨てておいてもよいと誰が言ったのか」の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
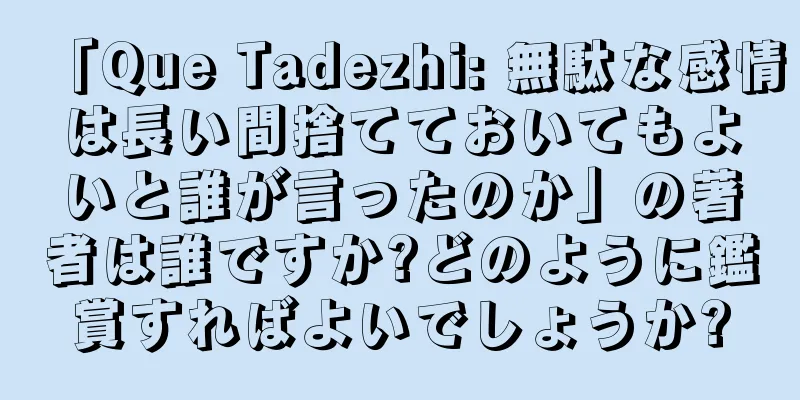
|
Que Tade Zhi - 怠惰な感情は長い間捨てられると誰が言ったのか 馮延氏(五代) 怠惰な気持ちが長く続くと誰が言ったのでしょうか? 毎年春になると、憂鬱な気持ちが残ります。私は毎日花の前で酔っぱらうことが多く、鏡で見た私の顔は痩せてきているとは言い難い。 (捨てる:放棄する;あえて拒否する:拒否しない) 緑の川岸と堤防の柳に、私は新たな悲しみについて尋ねます、なぜそれらは年々戻ってくるのでしょうか?私は小さな橋の上に一人で立っています、風が私の袖をいっぱいに吹き、人々が戻った後の平らな森に新月があります。 翻訳 悲しみは長い間忘れられてきたと誰が言ったのでしょうか? 早春が来るたびに、私の憂鬱な気分は以前と同じです。彼は毎日、酔うたびに花の前で酒を飲んでいた。鏡に映るかつてはバラ色だった自分の顔がどんどん痩せていっていることに、彼はまったく気にしていなかった。 川岸には緑の草が生い茂り、柳の木が川岸に日陰を作っています。私はなぜ毎年新たな悲しみを抱えているのだろうと悲しく思いました。私は橋頭堡に一人で立ち、そよ風に袖がなびいていました。人々が帰った後、森の中に三日月が昇りました。 注記 清代の王鵬雲は『班堂定高・武翁集』の中で「馮正中の『何大徳之』の詩十四篇は比喩と暗示が豊かで優雅である」と述べている。その曲名は「滴連花」である。 誰が言ったか:現代の学者、梁啓超は言った。「嘉宣の『莫言』の起源はここから派生した。文章の前に文章があり、黄河の流れのように、その源泉は果てしない。」 (『楊春注釈』より引用)のんびりとした気分:つまり、怠惰な悲しみと春の悲しみ。 アルコール依存症: 過度の飲酒によって引き起こされる身体的不快感。 辞任することを敢えてしてください。避けたり恐れたりしないでください。若々しくバラ色の肌、朱炎。 Zhuyan: ここではバラ色の顔色を指します。 青草:緑の草。 坪林:平原にある森。李白の「菩薩男」:「森は荒涼として、煙は織物のようだ。」 新月: 毎月初めに現れる三日月。 感謝 孤独と憂鬱を表現したロマンチックな詩です。詩全体は、心の中にある一種の永遠の憂鬱と悲しみを描写しており、一人で背負わなければならない孤独と荒廃に満ちています。感情的な状態を伝えるだけでなく、深い意味と微妙な感情を伴う強くて独特な個性も表しています。 最初の節は、単刀直入に始まります。最初の文は修辞的な疑問を使って、捨てたいけれど忘れられない「余暇」を取り上げています。最初の節全体は、最初の文で提起された複雑で矛盾した雰囲気と常に密接に結びついており、それが繰り返し現れて、作者の苦しい内面の感情を表現しています。 「怠惰な感情をいつまでも放っておいていいなんて誰が言った?」たった7語だが、千の紆余曲折を経て書かれており、望んでいるのにできない感情との葛藤の痛みを表現している。しかし、この感情の起源は明確に述べられておらず、「余暇」という2つの単語だけが使われています。どこから来るのか誰も知らないこの「怠惰」こそが最も苦痛であり、一部の感傷的な詩人にとって、この理不尽な「怠惰」は、山の崖や木の枝のように、生まれつきのものであり、逃れられないものである。詩人はまずこの文の冒頭で「誰が言った」という2語を使った。「誰が言った」というのは、自分はできると思っていたが、できないと誰が知っていたかという意味だ。だから修辞的な口調で問いかけた。この2語で、次の5語「長い間、怠惰な気持ちを捨ててきた」で表現された苦労と努力はすべて無駄になった。 「春が来るたびに、憂鬱は残る。」 上部の「each」、下部の「still」、そして最後の2つの「still」という言葉は、この憂鬱が永遠に続くことを表すのに十分です。 「春ごとに」とは、春は万物が芽生え、生命と感情が目覚める季節であるという意味です。詩人の心が春に目覚めたとき、彼が書いているのは、普通の人のように恋煩いや別れなどの本当の気持ちではなく、ただ暗に「憂鬱」という言葉を使っています。 「憂鬱」とは、心が何かを失い、また何かを求めているような、一種の混乱した感情です。特定の人や物に縛られる恋煩いや別れとは異なり、恋煩いや別れよりも孤独で無力な感情です。 「私は毎日花より酒に酔うことが多いが、鏡の中の痩せた顔は気にしない。」 このようなどうしようもない憂鬱があり、それは捨てられたという苦労と努力の後にも永遠に残っているので、馮石は後悔のない口調で次の2つの文章を言った。「私は毎日花より酒に酔うことが多いが、鏡の中の痩せた顔は気にしない。」 心から重荷を背負う決意を表した。上には「日ごとに」と書いてありますが、これは花の前で憂鬱な気持ちを拭い去るのが難しく、彼にできるのは「日ごとに」飲むことだけであることをさらに示しています。 「日々」という言葉は、おそらく酒を飲む以外に一日を過ごす手段がないということを示しているのだろう。次の「鏡の中のバラ色の顔は痩せ細った」というセリフは、「毎日酒に酔う」生活の必然的な結果です。 「鏡の中」という言葉は、内省や衝撃の感覚を暗示していますが、上では「ためらわず」という言葉が使われています。『李索』には「たとえ九回死んでも後悔しない」という一文があります。「ためらわず」という言葉は、死んでも後悔しないという一種の感情を表現しています。 次の節では、絶えず更新されるこの怠惰で憂鬱な気分がさらに表現されています。詩人は、この当惑と困惑を、極めて率直ともいえる疑問という形で、ここでもはっきりと顕著に表現している。また、「川辺の緑の草と堤防の柳」というイメージは、極めて微妙ともいえる、長く続く繊細で果てしない愛情と想いを暗示している。 「川岸の草は青く、堤防の柳は青く」。詩節の後半は、「川岸の草は青く、堤防の柳は青く」という文で始まります。この詩では、この 7 つの単語だけが風景を完全に表現しています。しかし、この 7 つの単語は実際には風景だけを表現している文ではありません。風景を感情の引き立て役として使っているだけです。したがって、この詩は春の風景を描写しているものの、生い茂った枝や柔らかい芽の色彩の乱れについては書いておらず、「緑の雑草」と「柳」についてのみ言及している。 「武」は青々とした草を意味します。「武」の緑の草は地平線まで伸びており、「柳」の柔らかい枝はさらに優雅です。地平線に広がる果てしない緑の草、風に揺れる果てしない柔らかな枝。それらはどのような長く繊細な感情を呼び起こし、あるいは象徴しているのでしょうか。そして、この草の色は今日始まったのではない。川辺の草は毎年青く、堤防の柳も毎年青く、この長く繊細な愛情も年々尽きることはないだろう。 「私は新たな悲しみについて尋ねる、なぜそれらは年々戻ってくるのか。」次の 2 つの文は、「私は新たな悲しみについて尋ねる、なぜそれらは年々戻ってくるのか」と言い、毎年の緑の雑草や柳から「年々戻ってくる」という「新たな悲しみ」までを正式に書いています。 「毎年起こる」悲しみであるにもかかわらず、「新しい」と言われています。一方では、この詩の冒頭で「長い間、怠惰な気持ちが捨てられてきた」と述べられており、「捨てられた」後の葛藤の期間を経て、再び蘇った「悲しみ」であるため、「新しい」と言われています。他方では、この悲しみは古いものですが、その憂鬱な気持ちは鋭く、深く、毎年常に新しいため、「新しい」と言われています。上には「尋ねるために」という言葉が使われ、下に「どうした」という言葉が使われ、それを放棄しようとする無駄な努力から、なぜ毎年新しい悲しみを抱えるのかという問いかけまで、そしてそのような努力と反省にもかかわらず、彼がまだ問題を解決できないことを示すまで、強い疑問の調子を作り出しています。この激しい問いかけの後、詩人は突然筆を置き、何も答えず、自分の外にある風景や出来事について二行だけ書き記した。「風に袖をなびかせながら、小さな橋の上にひとり立ち、人々が帰った後の平らな森に新月。」よく考えてみると、この十四語は本当に深い憂鬱感を表現している。 「小さな橋の上にひとり立って、袖に風が吹いて、みんなが帰った後の平らな林に新月が見える。」 「ひとり立って」という言葉だけを見ても、孤独さが想像できます。そして「袖に風が吹く」という3つの言葉を見ると、さらに寒さが想像できます。 「小さな橋」という言葉を使うことで、彼が立っている場所の孤独と無力さが目の前に鮮明に浮かび上がってきます。 また、「袖に風が吹く」の「満」という言葉は、冷たい風と人々への襲撃を表しており、これも満ち足りた力強い書き方です。孤独と寒さ、そして逃げ場のない状況で、彼がどれほど孤独で惨めな気持ちだったかは、次の7つの言葉からも想像できる。「人々が家に帰った後、平らな森に新月が輝く。」 「平林の新月」は月が木の梢から昇り、だんだん夜が更けていくことを意味し、「人が帰った後」は道が人影もなく寂しく寂しいことを意味します。先に書いた「川辺の青草」の鮮やかな色彩から判断すると昼間の情景であるはずだが、この文章はそのまま月が昇り人々が落ち着く時間を指し、詩人が袖を寒風にあてながら一人で橋の上でどれほど長く立っていたかが想像できる。もし心に苦しい感情がなければ、誰が真夜中まで冷たい風と露の中、橋の上で直立しているだろうか。 |
<<: 「霧の雲は数日でどこへ行くのか」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
>>: 「ジンメン訪問 風が突然立ち上がる」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
推薦する
5つの峠を越え、6人の将軍を殺さなければならなかった守備隊が曹陣営の8人の将軍だったとしたら、関羽は突破できたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
有名な詩人であり画家でもある張文涛の妻は誰でしたか?
張文涛は、乾隆29年5月27日に河北省官涛県に生まれた。清代の著名な詩人であり、優れた書家、画家でも...
「彭公安」第153話:英雄が夜に府城寺を訪れ、3人の英雄が小義村で騒動を起こす
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『紅楼夢』における寧国公と容国公の地位は何ですか?
賈家の寧公と容公は皇帝を支えた功績により公爵の位を授けられたが、その高い地位を過小評価すべきではない...
古代に言われていた「上品な人の4つの美徳」とは何を指すのでしょうか?
古代、琴(主に古琴を指す)、将棋(主に囲碁と将棋を指す)、書道、絵画は文人(名家の婦人を含む)が修行...
『十六心與文学』第46条に記録されているのは誰の言行ですか?
『十朔新于』は、魏晋の逸話小説の集大成です。では、『十朔新于・文学・第46号』には、誰の言葉や行いが...
杜甫の詩が後世に大きな影響を与えたのはなぜでしょうか?
杜甫は、字を子美といい、河南省貢県の人である。自らを少陵老人と称し、後世に詩聖と崇められた。彼の詩は...
武門の四大師とは誰ですか?彼らの代表作は何ですか?
興味深い歴史の編集者である武門の四大師が関連コンテンツをお届けしますので、ご興味がありましたらぜひご...
賈宝玉が里香園で飲んでいたとき、なぜ林黛玉は李馬に立ち向かったのですか?
長い時間の流れは止まらず、歴史は発展し続けます。『Interesting History』の編集者が...
七剣十三英雄第115章:将校と兵士を派遣して野営地の盗賊を焼き払うという素晴らしい計画が考案された
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
趙蓋が死ななかったら涼山は降伏しただろうか?涼山は第二のファンラになるのでしょうか?
今日、『Interesting History』の編集者は皆さんに疑問を提起します。もし趙蓋が死なな...
西遊記の八戒はなぜ間違った体に入ってしまったのでしょうか?真実とは何でしょうか?
朱八戒は、仏名を武能といい、唐和尚の二番目の弟子である。下記の興味深い歴史編集者が詳細な解釈をお届け...
『黄帝内経』第48章「霊鷲」の原文
雷公は黄帝に尋ねた。「羲子は学問を修め、九針六十章に精通しています。昼夜を問わず熱心に学んでいます。...
明の万里の長城が今日まで崩壊していない理由は何でしょうか?古代人はどのようにして城壁を築いたのでしょうか?
明の万里の長城はなぜ今日まで崩壊していないのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので...
桃の宴にはどんな人が参加できますか?孫悟空はなぜ仏陀になった後も参加できなかったのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が、桃の宴にはどんな人が参加できるのかをお伝えします。皆さんの参考になれば...