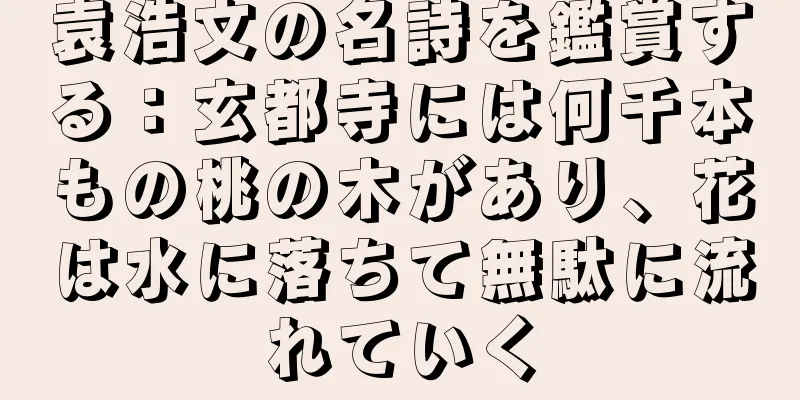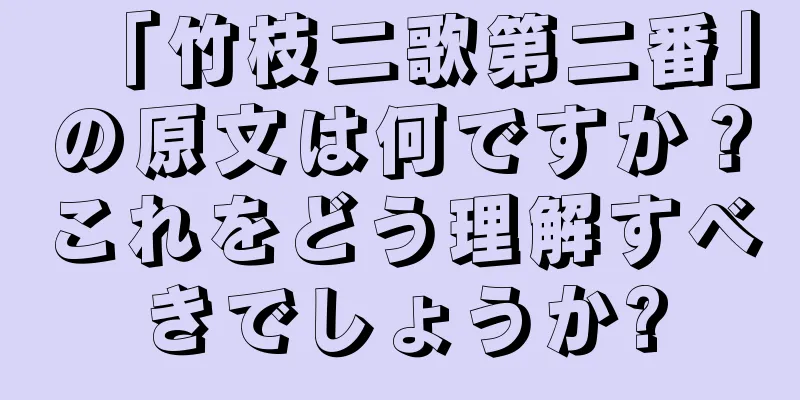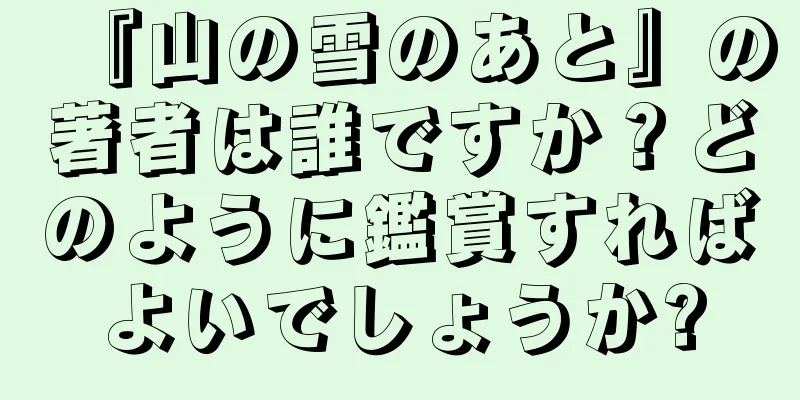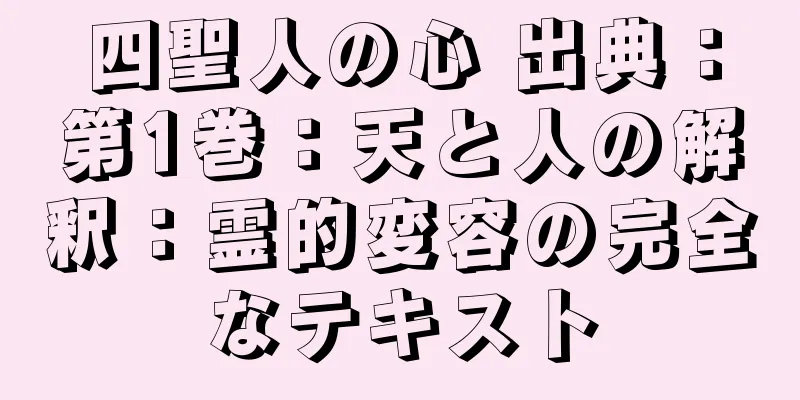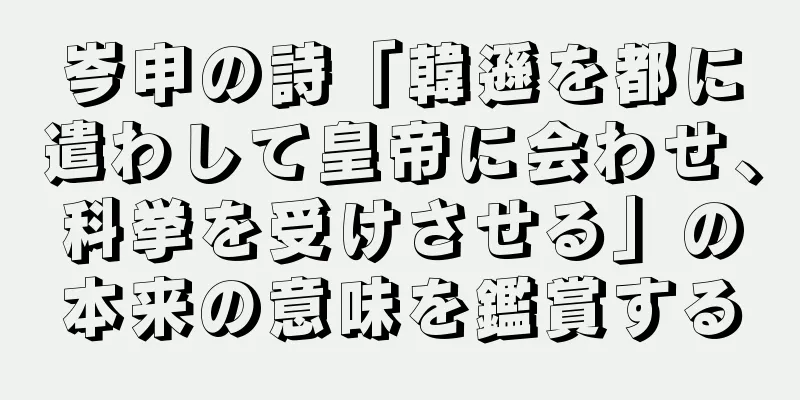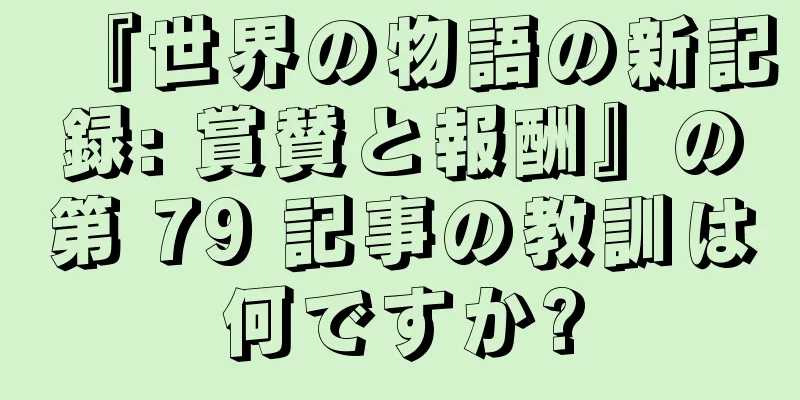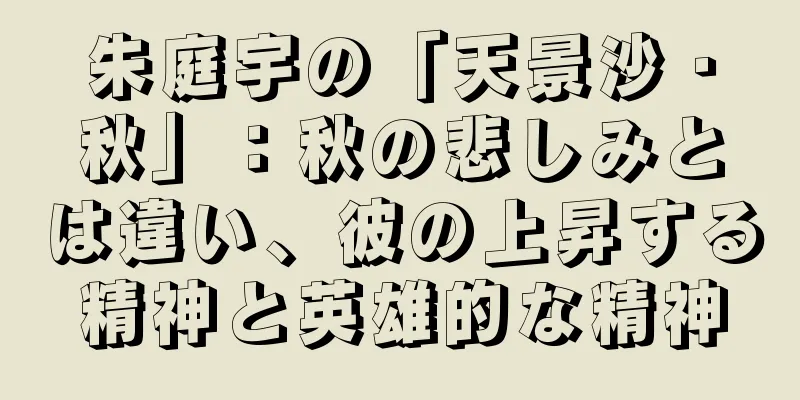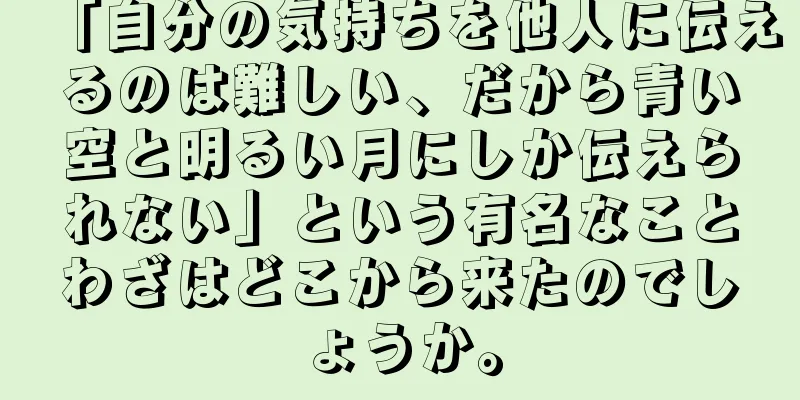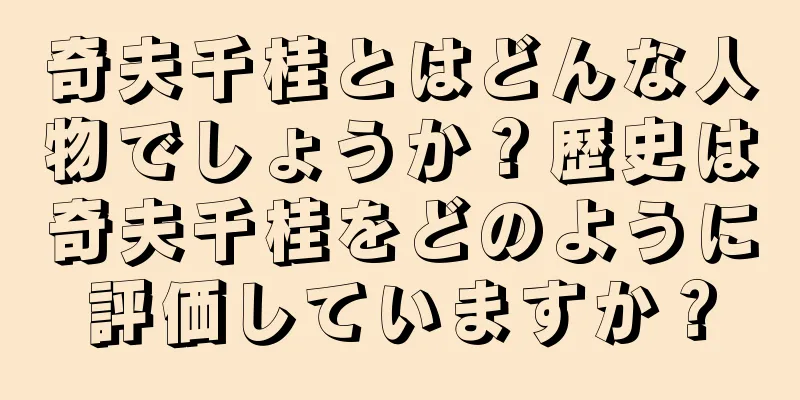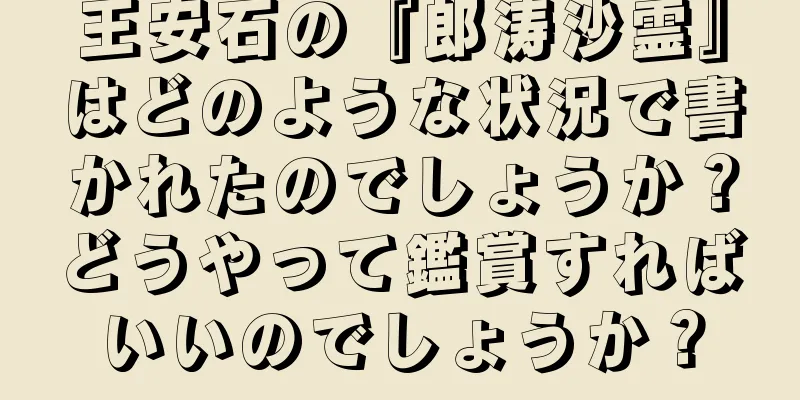蒋子牙の『太公六道』:「六道・龍道・将帥の選択」の作例と評価
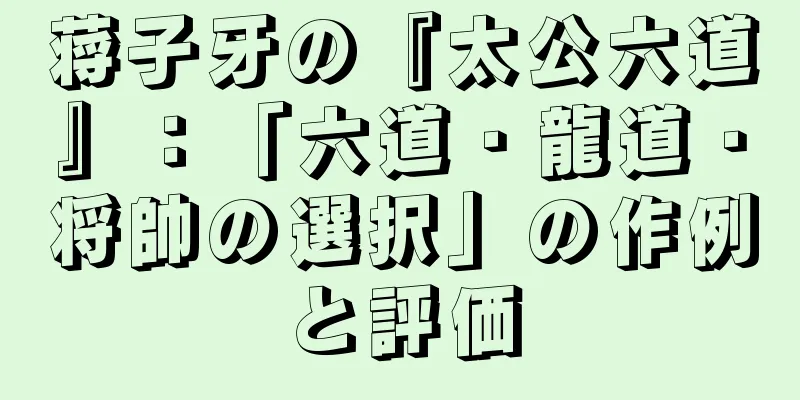
|
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われています。中国の古典的な軍事文化遺産の重要な部分として、その内容は奥深く、思想は豊かで洗練されており、論理は厳密で、古代中国の軍事思想の真髄が凝縮して体現されている。この本は周代初期に太公王(呂尚、姜子牙)によって書かれたと言われており、全編が太公と文王、武王との対話の形でまとめられています。それでは、次の興味深い歴史編集者が、姜子牙の「六策・龍策・将の選択」をお届けしますので、見てみましょう! 【オリジナル】 武王は太公に尋ねた。「王が軍隊を立ち上げるとき、英雄を選び、優劣を知りたいと思うでしょう。どうすればいいでしょうか?」 太公は言った。「外見と心の内情が一致しない学者が十五種類ある。厳格だが無価値な者、温厚だが盗人、礼儀正しいようだが傲慢な者、正直そうだが誠実でない者、几帳面だが感情がない者、誠実だが誠実でない者、計画は上手だが決断力がない者、大胆だが何もできない者、信用できない者、漠然としているが忠誠心がある者、狡猾だが有能な者、勇敢そうに見えて臆病な者、厳粛だが移り気な者、ためらいがちだが静かで誠実な者、力も外見もないが外に出ると無能な者。世間で蔑まれているものは聖人の価値観であり、凡人には分からない。大智がなければその限界を見ることはできない。これらは外見と心の内情が一致しない学者である。」 武王は「どうして知るのですか?」と尋ねました。太公は答えました。「知るには八つの方法があります。一つ目は、彼に質問をして言葉を見ることです。二つ目は、彼に言葉で質問して変化を見ることです。三つ目は、彼の密偵に相談して誠実さを見ることです。四つ目は、彼にはっきりと質問して徳を見ることです。五つ目は、お金を使って誠実さを見ることです。六つ目は、彼の外見を試して貞操を見ることです。七つ目は、彼に難しいことを言って勇気を見ることです。八つ目は、彼を酔わせて態度を見ることです。八つの方法をすべて備えていれば、徳のある人と悪い人の違いがわかります。」 【翻訳】 武王は太公に尋ねました。「王が軍隊を立ち上げるとき、賢く勇敢な人物を将軍に選ばなければなりません。その人物の能力と道徳的誠実さを知りたいのです。どうすればよいのでしょうか?」 公爵は答えた。「学者の外見と内面が一致しない状況が15種類あります。高潔なように見えても実は不誠実な者、親切なように見えても実は泥棒である者、礼儀正しいように見えても実は傲慢な者、慎み深いように見えても実は不誠実な者、有能そうに見えても実は無学な者、親切そうに見えても実は不誠実な者、機知に富んでいるように見えても優柔不断な者、決断力があるように見えても実は無活動な者、正直そうに見えても実は信用できない者、優柔不断そうに見えても実は忠誠心のある者などです。」 言葉や行動は極端でも仕事は有能な人もいれば、勇敢そうに見えても実は臆病な人もいれば、真面目そうに見えても実は親しみやすい人もいれば、厳格そうに見えても心は穏やかで優しい人もいれば、弱々しく醜いように見えてもどこでも任務を遂行し、何でも成し遂げられる人もいます。普通の人々から軽蔑されるものが、聖人からは高く評価されることが多い。普通の人には理解できず、深い洞察力がなければその謎を見ることは不可能です。これらは学者の外見が彼の内面の感情と一致しないさまざまな状況です。 ” 武王は尋ねた。「どうすれば彼らを本当に理解できるのか?」 太公は言った。「彼らを理解するには八つの方法がある。第一に、質問して、相手が明確に説明できるかを見る。第二に、詳細に尋問して、相手が返答できるかを見る。第三に、スパイを使って、相手が忠誠心があるかを見る。第四に、故意に質問して、相手が隠し事をしていないかを見て、相手の道徳心を試す。第五に、金銭を管理させて、相手が正直かどうかを見る。第六に、女性を使って相手が誠実かどうかを見る。第七に、危険に対処して、相手が勇敢かどうかを見る。第八に、相手を酔わせて、相手が平静を保てるかどうかを見る。この八つの方法を使えば、その人が徳のある人かどうかがはっきりとわかる。」 【図】 将軍を選ぶのは簡単なことではありません。外見だけで将軍を選ぶと、言葉と行動が必ずしも一貫しているとは限らないため、信頼できないことがよくあります。将軍を選抜する唯一の方法は、その行動や発言を総合的に分析し、つまり、実践を通じて才能を検査し、見極め、軍隊を率いて戦いに臨むという重要な任務を遂行できるかどうかを見極めることである。漢の文帝がヤフの才能を見抜いた鋭い目はその典型的な例である。 文帝の后元6年(紀元前158年)の冬、匈奴は大規模な侵攻を開始し、その狼煙は甘泉(現在の陝西省春化の北西)にまで達し、首都長安を揺るがした。文帝は国境防衛のために軍隊を派遣したほか、長安防衛のために3つの軍隊も派遣した。そのうち、周亜夫は軍を率いて西六(現在の陝西省城陽の南西)に駐屯し、劉礼は軍を率いて巴上(現在の陝西省西安の東)に駐屯し、徐礼は軍を率いて集門(現在の陝西省未陽の北東)に駐屯した。その後、文帝は自ら三軍を訪ね、将兵を慰め、士気を高めた。 まず彼らは巴上と集門に到着した。兵舎では馬車や馬が自由に駆け回り、人々は自由に行き来していた。各階級の将軍たちが自ら彼らを迎え、大歓待で見送った。その後、西柳に到着すると、状況は一変していました。兵士たちは皆、兜と鎧を身につけ、刀を抜き、要塞は強固で、戦争に備えているような雰囲気でした。護衛将校は皇帝の到着を叫び、皇帝を迎えるために陣営の門を開けるよう命じた。しかし、陣地の門にいた兵士たちは馬を止め、周将軍が命令を出したと答えた。「軍は将軍の命令に従うだけで、皇帝の勅令には従わない。将軍の命令なしに陣地に入ることは許されない!」文帝は自ら前に出たが、兵士たちは依然として門を開けようとしなかった。 文帝は、勅令を伝えるために、権威の印を持った使者を派遣した。「私は、軍隊に恩賞を与えるために陣営に入りたい。」ヤフは権威の印を見て初めて、門を開けるよう命じた。軍門が開くとすぐに、門番は文帝とその一行に周将軍が「軍隊内では誰も高速で走ることは許されない」と命令したと警告した。文帝は命令に従うしかなく、ゆっくりと中央軍のテントの前まで歩いていった。周亜夫は軍服を着て刀を携え、落ち着いて皇帝に挨拶し、頭を下げて「私は甲冑を着ているため、ひざまずいて頭を下げるのは不便です。どうか軍儀礼で私を迎えてください」と言った。文帝は軍儀礼の規則に従って身をかがめ、馬車の前の横木を掲げて周亜夫に敬意を表し、人を遣わして「皇帝は将軍のご苦労を尊敬しています」と礼を述べた。儀式が終わると、文帝は宮殿へ向かった。 皇帝の馬車が陣地を離れると、随行していた各階級の官吏たちは憤慨せざるを得なかった。「周亜夫は皇帝に対してこのような無礼なことをするなんて、あまりにも大胆だ!」しかし文帝は怒らず、ずっと彼を褒め称えた。「周亜夫は真の将軍だ!もし彼が巴商や集門の軍隊のように軍規を冗談のように考え、自由に兵舎に出入りしていたら、攻撃されたら皆敵に捕らえられてしまうのではないか?秀里陣地を見れば、陣地の規則はあまりにも厳しく、私ですら自由に出入りできないのに、どうして敵が侵入できるというのだ!」それ以来、周亜夫は文帝に深く評価されるようになった。 それから一ヶ月余り後、匈奴軍は国外に撤退し、漢軍も次々と防衛軍を撤退させた。周亜夫は中尉に昇進し、首都警備隊を指揮して長安の防衛を担当した。翌年、文帝は危篤となり、死去する前に皇太子(景帝)に、国が危機に陥った場合には周亜夫に軍を率いてもらうよう頼むと告げた。景帝が即位した後、周亜夫を車騎将軍に任命した。その後、呉と楚の七国が反乱を起こしたが、周亜夫は期待に応えて軍を率いて反乱を速やかに鎮圧し、前漢の安定と統一に不滅の貢献をした。 |
<<: 蒋子牙の『太公六涛』:「六涛・龍涛・李君」の作例と鑑賞
>>: 蒋子牙の『太公六道』:「六道・龍道・将軍論」の作例と評価
推薦する
劉晨翁の「貴い三脚が現れた:赤い服と春の騎手」:元宵節への郷愁と祖国への哀悼の詩
劉晨翁(1232-1297)、雅号は慧夢、号は許熙としても知られる。彼はまた、徐喜居士、徐喜農、小娜...
なぜ火炎山の土地神は火炎山の火は孫悟空が起こしたと言ったのでしょうか?
僧侶とその弟子たちは数え切れないほどの苦難を乗り越えて火焔山にたどり着きましたが、山の火が西への道を...
曹雪琴の「薛宝才の白ベゴニアへの頌歌」:この詩は意図的に白ベゴニアを使って自分自身と関連づけている。
曹雪芹(1715年5月28日頃 - 1763年2月12日頃)は、本名を詹、字を孟阮、号を雪芹、秦溪、...
古代の天才児で、弁論家の田を出し抜いた呂仲廉の物語は、彼の才能をどのように示しているのでしょうか。
呂忠蓮は呂連子とも呼ばれ、呂連とも呼ばれます。戦国時代の斉の出身者。歴史書によると、彼は稀代の天才で...
今年も中秋節がやってきました。月餅の歴史についてどれくらいご存知ですか?
毎年恒例の中秋節が近づいてきました。「お祭りごとに愛する人を恋しく思う」と言われますが、家族の再会を...
桃の花、杏の花、桜の花、梨の花、梅の花、リンゴの花の区別を教えます
草が青々と茂り、鳥が飛び交う季節がやってきました。少し寒くて雨が降っていますが、そよ風と暖かい日差し...
陰陽気瓶に閉じ込められた孫悟空は、なぜ命を救うために髪の毛を使うことを思いついたのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
古典文学の傑作『太平楽』:文学部第18巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
誰もが賈宝玉を愛しているのに、なぜ賈蘭と喬潔はいつも無視されるのでしょうか?
『紅楼夢』では、嫡男の賈宝玉は毎日星に囲まれた星のように暮らしていますが、賈蘭と喬潔はいつも取り残さ...
戒名と寺号の違いは何ですか? 戒名と寺号の違いは何ですか?
清朝皇帝を例に挙げてみましょう。まず「寺号」についてお話しましょう。宣統帝を除いて、清朝の12代の皇...
漢王朝時代に宦官が政治に介入したという教訓があるのに、なぜ唐王朝は依然として宦官をそれほど優遇したのでしょうか?
宦官は中国の歴史において悪評を博している。それは、宦官が数々の大規模な武装暴動を引き起こし、社会の混...
『紅楼夢』の金陵十二美女の中に薛宝琴がいないのはなぜですか?理由は何でしょう
金陵十二美人は『紅楼夢』に登場する最も目立つ12人の娘たちです。本日は、Interesting Hi...
西漢時代の主要な宮殿はどの宮殿でしたか?本殿の名前の意味は何ですか?
未陽宮は西漢の正宮であり、漢王朝の政治の中心地であり、国家の象徴でもありました。長安城の安門街の西に...
呉文英の「霜葉舞い散り、煙散り」:この詩は、重陽の節句に昔を思い出すために山に登ったときに書かれたものです。
呉文英(1200年頃 - 1260年頃)は、雅号を君特、号を孟荘といい、晩年は妓翁とも呼ばれた。思明...
曹魏は軍事力が強かったとはいえ、文化をどの程度重視していたのでしょうか?
三国時代の文化や文学といえば、そのほとんどは魏の時代から来ています。曹魏は軍事力が強かったが、文化も...