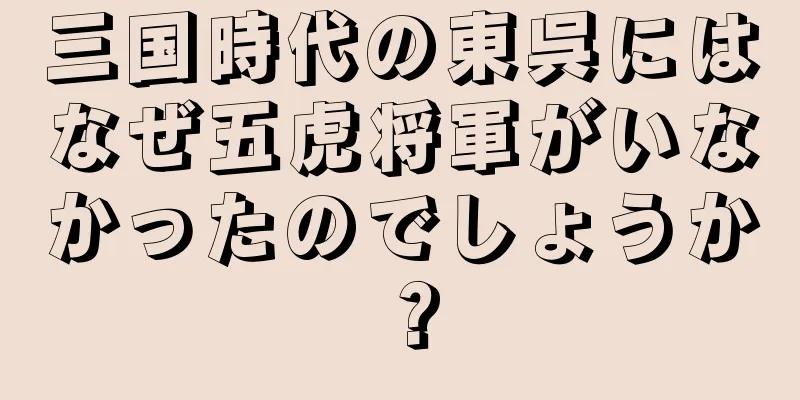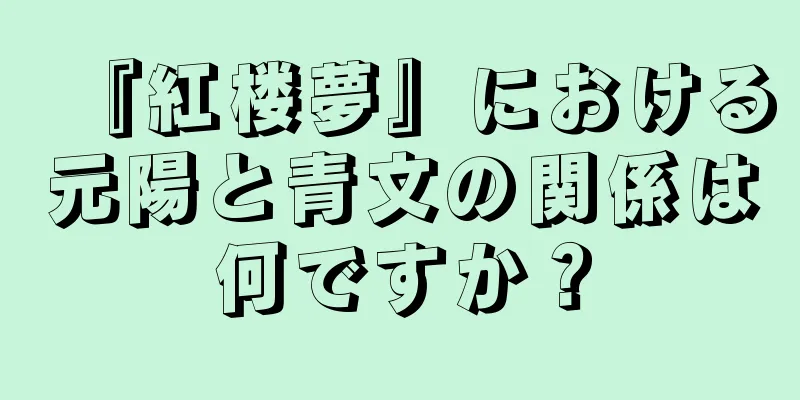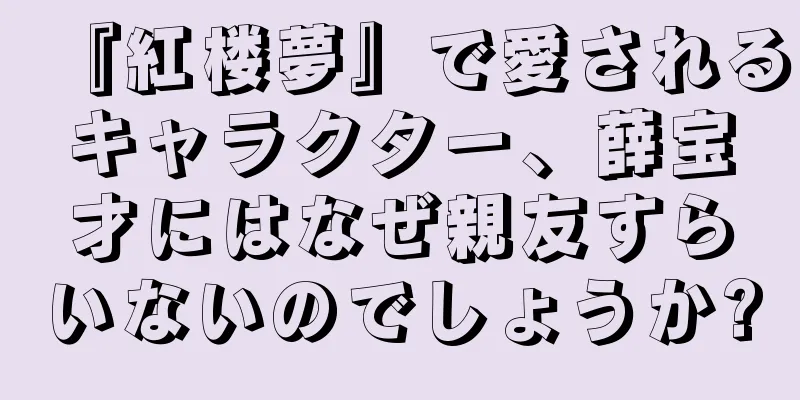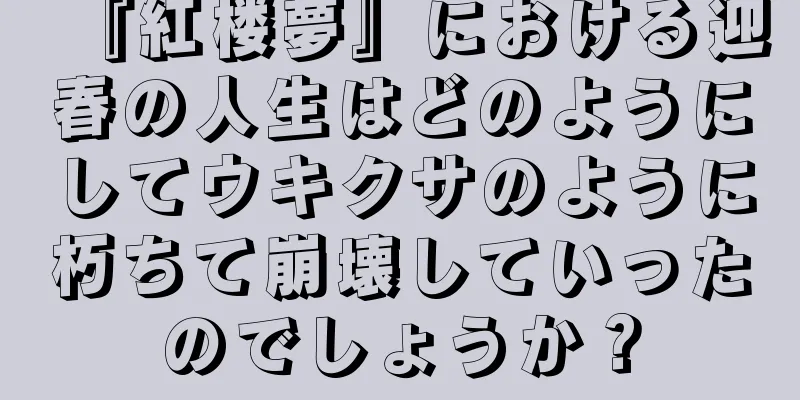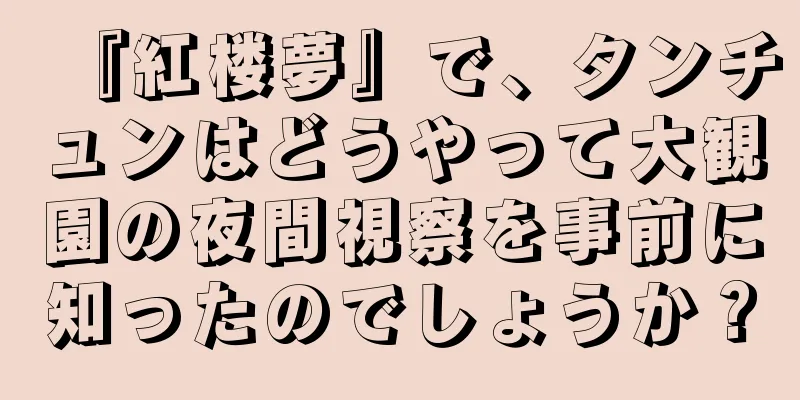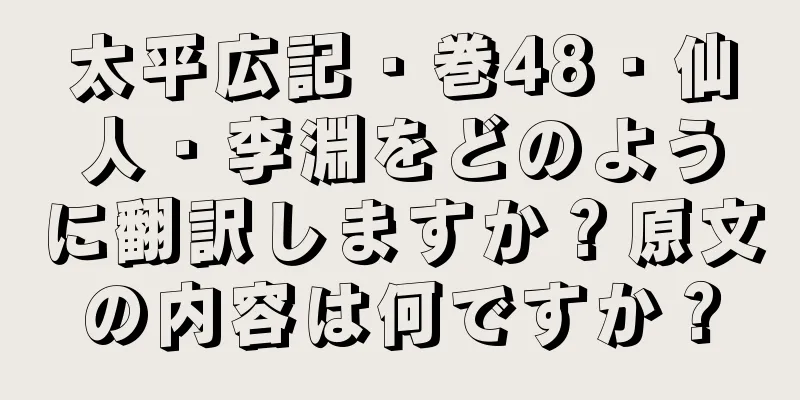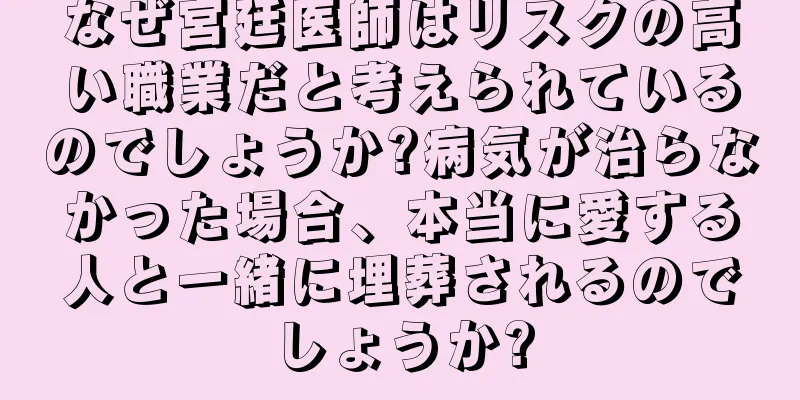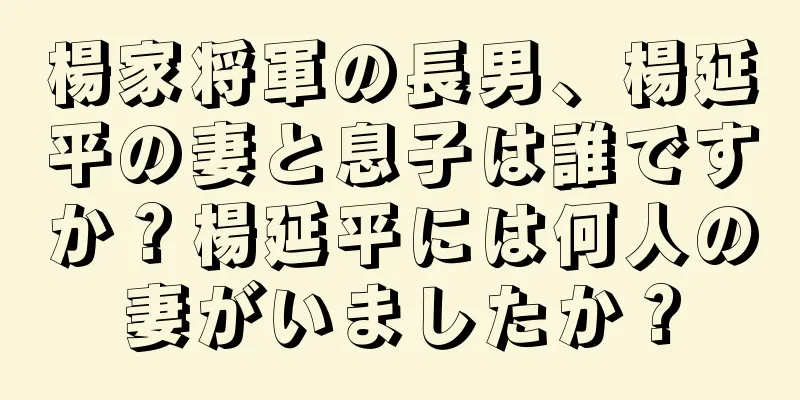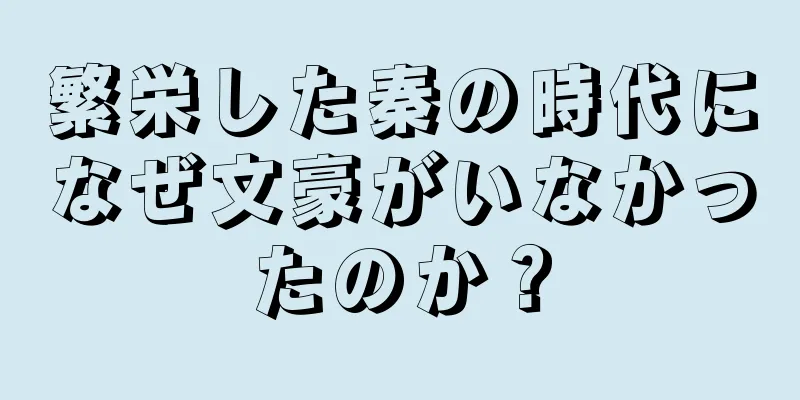老子の『道徳経』第 71 章とその続き
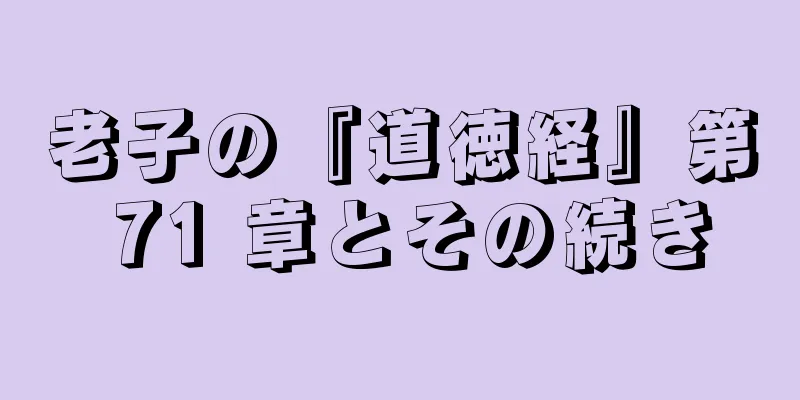
|
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古代中国で秦以前の哲学者が分裂する前に書かれた作品であり、道教の哲学思想の重要な源泉です。 『道徳経』は2部に分かれています。原典では上段を『徳経』、下段を『道経』と呼び、章は設けられていません。後に、最初の37章を『道経』、38章以降を『徳経』と改められ、81章に分かれています。そこで今日は、Interesting History の編集者が老子の『道徳経』の第 71 章をお届けします。見てみましょう。 [オリジナル] 自分が知らないことを知るのは良いことであり、自分が知っていることを知らないのは病気である。賢者は病気になるのではなく、自分の病気を利用して自分自身を病気にするのです。あなたが病気から解放されるのは、自分の病気に気づいているからに他なりません。 [翻訳] 知らないことがあると知ることは素晴らしい知恵です。知らないのに知っていると思い込むのはひどいことだ。道を備えた賢者には欠点がありません。なぜなら、欠点を欠点として捉えるからです。彼は自分の欠点を欠点として捉えているからこそ、欠点がないのです。 [注記] 1. 知っているかどうか: 注釈者は一般的にこの文に対して 2 つの解釈をします。一方は知っていると言っているが、知っているとは思っていない。もう一方は知らないことを知っていると言っている。 2. Shangyi:「Shang」は「shang」と同じです。 3. 無知な知識: 知らないのに知っていると思っていること。 4. 病気: 病気、問題、欠点。病気を病気として治療してください。 [拡張読書1] 王弼の『道徳経』の注釈 自分が知らないことを知るのが最善であり、自分が知っていることを知らないのは病気である。 自分が知っていることが十分ではないと知らないのなら、それは病気です。 あなたが病気でないのは、自分の病気に気づいているからに他なりません。賢者は病気にならない。なぜなら、自分が病気であることを自覚しているからであり、それゆえ病気にならないのだ。 【拡張読書2】蘇哲の『老子解説』 自分が知らないことを知るのが最善であり、自分が知っていることを知らないのは病気である。 道は思考や考慮の範囲を超えているため、追加することはできません。しかし、知らない場合、知識がなければ入る方法はありません。すでに知っていて知識を保持している場合、知識が問題になります。したがって、知っていながら知らない人は優れており、知らないけれども知っている人は病気です。 自分の病気に気づくことによってのみ、病気を避けることができます。 それは私たちが知るべきことであり、また知るべきではないことでもあります。知識は病気であることを知っている人だけが、長い時間が経てば自然に治ります。 賢者は病気にならない。なぜなら、自分が病気であることを自覚しているからであり、それゆえ病気にならないのだ。 |
推薦する
なぜ王希峰が最も気にかけているのは賈廉ではなく王子騰なのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
秦の始皇帝が孟姜女に結婚を強要したとき何が起こったのですか?この話はどのようにして噂になったのでしょうか?
秦の始皇帝が孟姜女を強引に結婚させたのは一体どうなったのか?この話はなぜ噂になったのか?興味がある方...
「麗州南渡」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】空の水面は沈む太陽に面しており、曲がりくねった島は広大な緑の丘とつながっています。波の...
中国初の宗教的世界遺産、「媽祖」とは誰?
ギリシャ神話には多くの女神が登場しますが、エイレーネは有名な「平和の女神」です。 1980年代、国連...
『後漢書 班彪伝』の原文と翻訳、『班彪伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
5 つの要素がすべて存在する場合、どのように名前を付けますか?五行に基づいた命名の要件は何ですか?
五行命名に興味のあるお友達はぜひ見に来てください!実際、五行に基づいた名前をつけることにこだわる人は...
前趙の昭文帝・劉堯とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は劉堯をどのように評価しているのでしょうか?
前趙の昭文帝劉瑶(?-329年)は匈奴で、号は永明。前漢の光文帝劉淵の養子で、前趙最後の皇帝。筆記に...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源第114巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
何卓の「杵の音と金床のきらめき」:この詩は作者の国家と国民に対する懸念を表現しています。
何朱(1052-1125)は北宋時代の詩人。号は方慧、別名は何三嶼。またの名を何美子、号は青湖一老。...
歴史上、海を渡る八仙人の中で唯一の女性仙人は誰ですか?彼女はどのようにして仙人になったのですか?
八仙渡海は中国人の間で最も広く伝わっている神話や伝説の一つです。 Interesting Histo...
バン・グは人生で何を経験したのでしょうか?バン・グは若い頃はどんな人でしたか?
東漢時代の歴史家。号は孟建。扶豊安陵(現在の陝西省咸陽の北東)の出身。彼は9歳で文字を書くことができ...
姚雲文の「紫玉祥曼・重陽節近く」:詩人は重陽節を利用して悲しみと遠い故郷への思いを表現している
姚雲文は宋代末期から元代初期の著名な作家で、本名は聖瑞、別名は江村。江西省高安の出身。咸春4年に進士...
杜甫は成都に5年間住んでいたので、「登楼記」を書いた。
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
中国の歴史上、大きな疫病はいくつ発生しましたか?古代の人々は疫病とどのように戦ったのでしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が、古代の人々が疫病とどのように戦ったかを紹...
「私を喜ばせる春の夜」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
春の夜李尚閔(唐代)場所は世俗的な事柄よりも優れており、体はゆったりとしており、良い年月を懐かしんで...