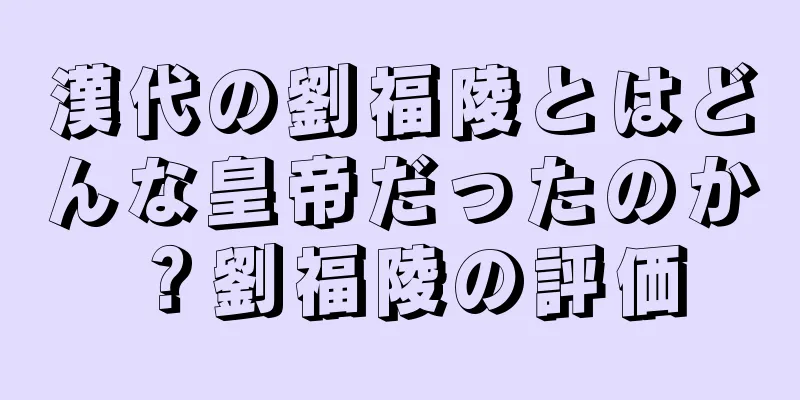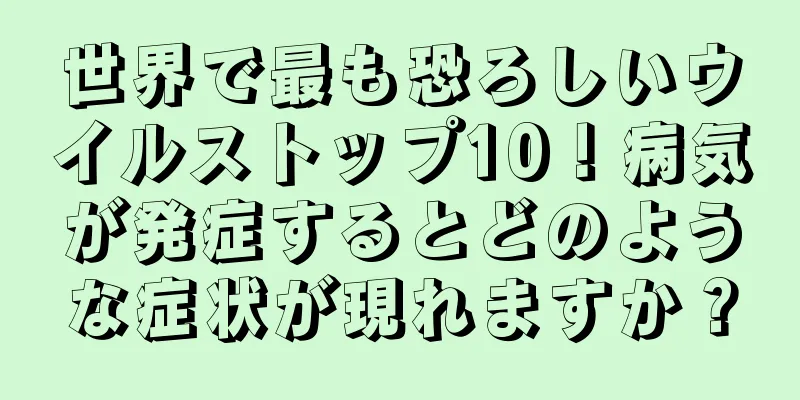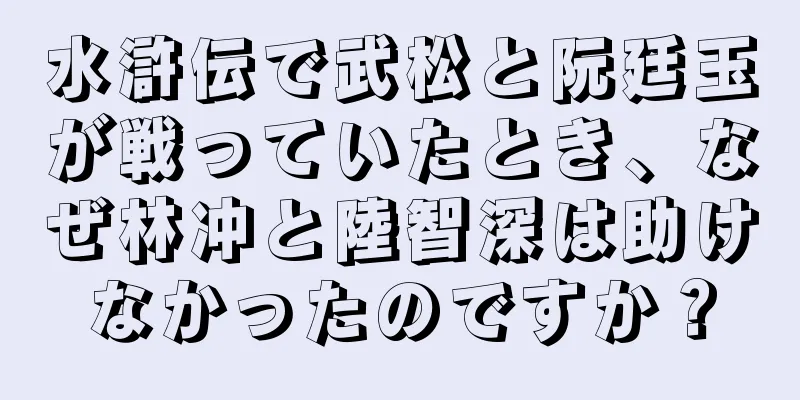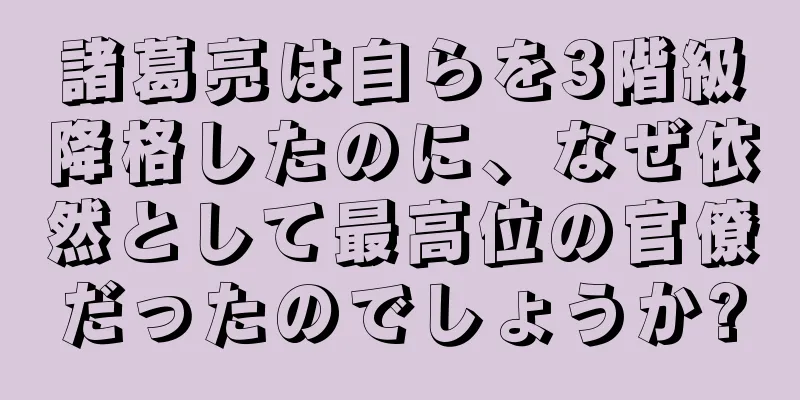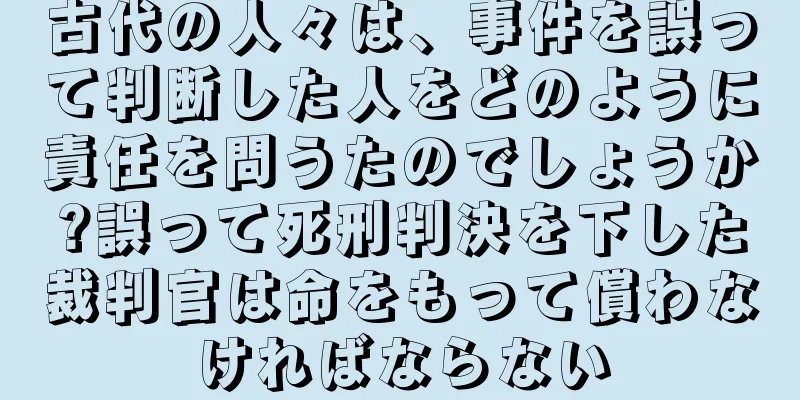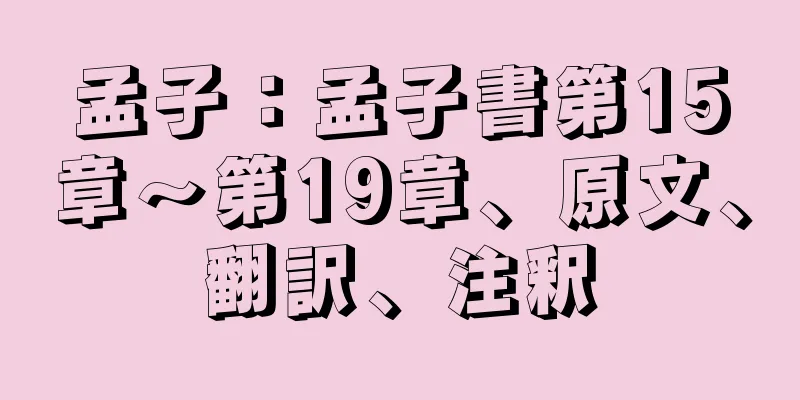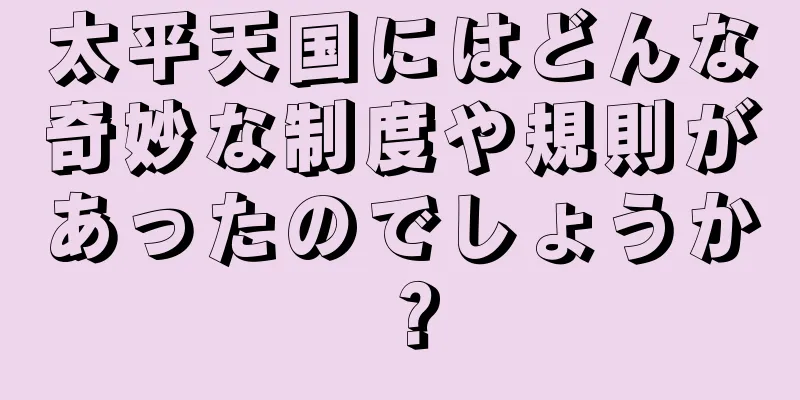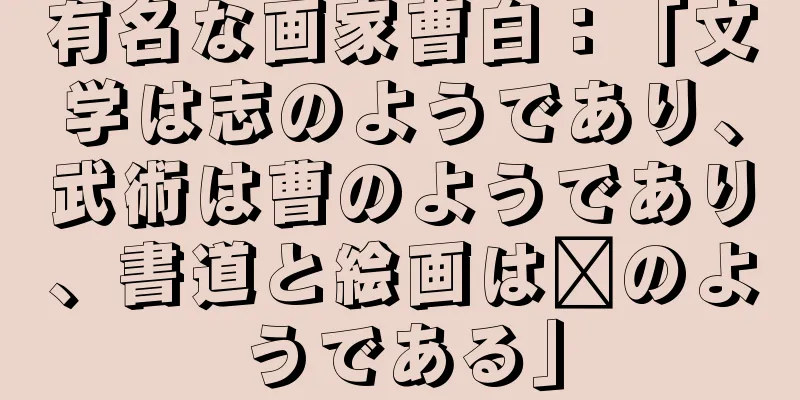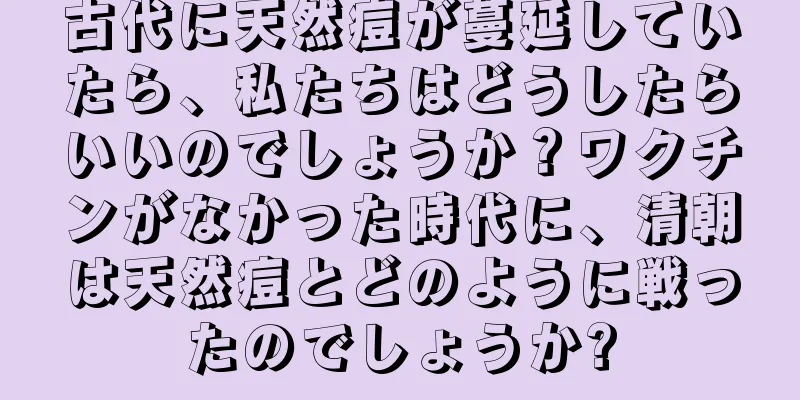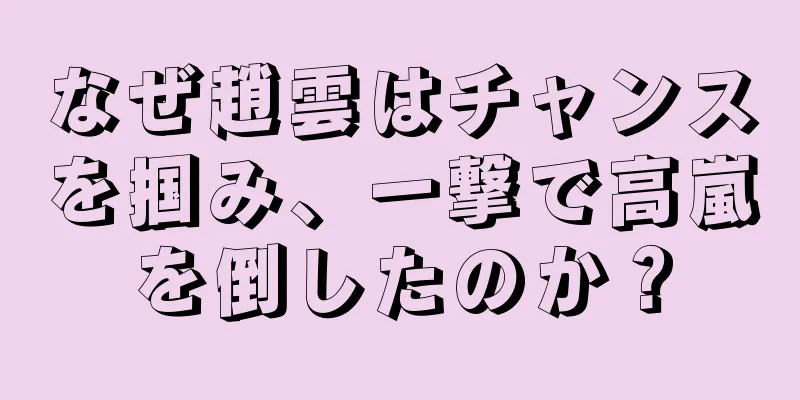清朝の老人保健に関する論文集『老老衡衍』第5巻、上36
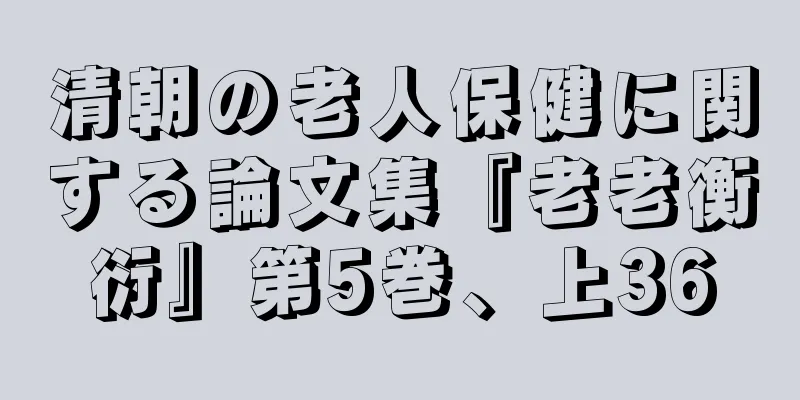
|
『老老衡厳』の著者は清代の学者曹廷東で、老年期の健康維持に関する論文集で全5巻からなる。周作人はこれを高く評価し、還暦の贈り物としてふさわしい良書と評した。最も優れた版は、清朝の乾隆38年に曹廷東自身が印刷した版である。それでは、次の興味深い歴史編集者が第5巻トップグレード36の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 蓮の実粥(『聖慧芳』より:中を養い、意志を強め、精神を養い、脾臓に利益を与え、精気を固め、すべての病気を取り除くことができます。皮と芯を取り除き、新鮮な蓮の実を使って粥を調理すると、最高の結果が得られます。乾燥した蓮の実を焙煎すると、肉が固くなり、調理できなくなります。または、粉末に挽いてスープに加えます。皮が薄く、肉がしっかりしているため、亭蓮の実は建蓮の実よりも優れています。) 蓮根粥「慈山神肉」:熱、喉の渇き、下痢を治し、食欲を刺激し、消化を助け、滞った血を分散させ、長期摂取で人を幸せにする。粉末にして食べるととてもあっさりとした味で、スライスしてお粥にすると甘くて香りがよいです。 「すべてのものは作り方が違う」「匂いや味も変わる」など。 蓮鼻粥「慈山神乳」:蓮鼻は葉の茎で、活力を生み出し、脾臓と胃を助け、喉の渇きを癒し、下痢を止め、精液を固める働きがあります。茎と葉も使用できます。色は緑色で、形は直立しており、内部は空洞で、真六十四卦のイメージです。真珠カプセルはスープに入れて煮たり、ご飯と一緒に炊いたり、脾臓の治療薬と混ぜたりすることができます。また、お粥を作るのにも使用でき、香りがよく、味も美味しいです。 『本草綱目』には、「ゴルゴンの実粥は精気と意志を強め、耳を鋭くし、目を明るくする」とある。また、湿気や関節炎、腰痛、背骨や膝の痛み、失禁や帯下にも効果がある。米には、ジャポニカ米ともち米の2種類があります。どちらも性質は同じで、お粥に加える前に炊く必要があります。新鮮なものほど良いです。楊雄の『方言』には「南楚では『鶏頭』と呼ぶ」とある。 『広済方』の「ハトムギ粥」には「長期にわたるリウマチや関節炎を治す」とある。また『散復旦書』には「脾臓と胃を養う」とある。また、けいれんや水虫の治療、浮腫の解消にも効果がある。張時正の『観有録』には「辛家軒はヘルニアを患っていたが、東壁土でハトムギを炒めてこれを服用したところ、すぐに治った」とある。これは最高級の滋養強壮薬である。 レンズ豆粥(『長寿の秘訣』には「体を調和させ、五臓六腑を養う」とある。また、熱や湿気を取り除き、解毒する作用もある。長期摂取すると白髪を防ぐことができる。レンズ豆の鞘は緑と紫で、皮は黒、白、赤、斑点がある。白は温かみがあり、黒は冷たさがあり、赤は中性である。粥に加える前に皮を剥いておく。乾燥したレンズ豆の方が良く、新鮮なものは風味が劣る。) 皇室粥(開宝本草:「帯下や消化不良の症状を治療し、竹の汁と混ぜて粥に加えることができる。」これは「アヘンの種子」であり、「花卉目録」では「利春花」の名で、風気を治療し、病熱を排出し、吐き気、痰の停滞、下痢を治療し、乾燥を潤し、精気を固めるのにも使用されます。水で挽いて粥に濾すと、非常に香りがよく、滑らかです。) 生姜粥(本草綱目:「中を温め、悪い気を払う。」また、「手記方」:「粥をつぶした汁で調理すると吐き気を治す。」風寒を払い、心を開き、多くの効果があります。「朱子玉録」には「秋の生姜は人の寿命を延ばすことができる」とあるので、病気の治療にはこれに固執しないでください。「春秋雲豆書」には「玄星が散って生姜になる」とあります。) 香米の葉粥「慈山神儒」:さまざまな書物によると、これらはすべて燃やして灰にしてから汁に浸して使用する必要があります。ただし、「寨元妙法」には、帯下を治療するためにもち米の葉と露を一晩煮ると書かれています。 『本草綱目』には、味は辛くて辛いと書かれていますが、実際はそうではないかもしれません。お粥を作るときに使います。味は薄味ですが、香りは澄んでいます。薄味で利尿作用があり、香りは食欲を刺激します。 ヘチマの葉粥「慈山神々」:ヘチマは冷たい性質があり、熱を取り除き、腸に良い影響を与え、血液を冷やし、解毒します。葉の性質は似ています。メロンは細長いため「馬鞭瓜」と呼ばれ、葉は利用できません。一方、メロンは短く太いため「丁子瓜」と呼ばれ、葉を粥にすると美味しいです。髪を拭き取るか、生姜汁で洗います。 桑の芽粥(善居清功:「喉の渇きを癒し、視力を明るくする。」五臓六腑に効き、関節を清め、疲労と熱を癒し、発汗を止める。子碩曰く:「桑は東方の聖なる木である。」新しく生えた立派な芽を使って粥を作る。芽はまだ芽の中にあり、香りが芳しく、味は甘い。五地之:「煎って乾燥させてお茶として飲むと、体液を促進し、肝火を清める。」) クルミ粥(海枝芳:「陽虚、腰痛、排尿困難、五痔に効く。」押すと肌に潤いを与え、髪を黒くし、排尿を促進し、風邪の咳を止め、肺を温め、腸を潤す。皮をむいてすりつぶし、水でかき混ぜて汁を濾し、ご飯が炊けた後に加える。さらに煮て油ガスを作るか、トチュウとフェンネルを加えて腰痛を治す。) アーモンド粥(『食医鏡』には「5種類の痔の出血を治す」とある。風熱咳嗽を治し、乾燥を保湿する。関西産は「マーダン」と呼ばれ、甘くて美味しい。皮をむいて穂先を落とし、水ですりつぶして汁を濾し、粥を作り、氷砂糖を少し加える。『野人談』には「毎朝7粒噛めば、老人に良い」とある。) 胡麻粥(『金塊秘録』には「肺を養い、飢えや渇きに抗う」とある。胡麻は広雅語で「騰紅」と呼ばれる胡麻である。骨盤を強くし、目と耳を明るくし、動悸を止め、すべての病気を治す。黒いものは「菊生」と呼ばれ、仙経で高く評価されている。栗のものは香りがよいが、香りが強すぎる。炒めてすりつぶし、水を加えて濾し汁を粥に入れる。) 松の実粥(本草綱目では「心臓と肺を養い、大腸を整える」とある。関節炎の治療、水蒸気と冷えの解消、五臓六腑の栄養補給、腸と胃の温めにも効果がある。白い実を取ってすり潰し、粥に加える。少し黄色く、油っぽい匂いがするものは食べないほうがいい。仙人伝では「松の実を食べるのが好きな人は、体毛が数センチ伸びる」とある。) 菊花の苗粥(天宝単方:「頭と目を清める」。胸の熱を取り除き、風とめまいを取り除き、胃を落ち着かせることもできます。花浦によると、「茎は紫色で、葉は甘くて食べられる」とのこと。甘いものは「苦いハトムギ」と呼ばれ、使えません。苗は成長の気で、上に集まるので、頭と目を清めるのに特に効果的です。) 菊粥「菊参」:肝臓と血液を養い、顔色を良くし、風邪やめまいを取り除き、熱を取り除き、喉の渇きを癒し、視力を改善します。この植物には何百もの種があります。花カタログには、「野生で、花びらが1枚です」と書かれています。小さな花をつけた白い花が最もよく、黄色い花がそれに次ぐもので、お茶を作るのにも適しています。お粥を作るときは茎を取り除き、天日で乾燥させ、粉にしてお粥に混ぜます。 梅花粥(財真記によると、「緑の萼と花びらの梅の花を雪水で煮ると、熱と毒を和らげることができます。」また、さまざまな傷や毒を治療することができます。梅の花は寒さの中で咲き、春に香りが立ちます。春は万物に最初に命を与える季節です。その香りは辛く、純粋な寒さではありません。炊いたお粥に加えて沸騰させます。皮牙は「梅の花は北に行くと杏に変わる」と言っています。) ベルガモット粥(『官旅記』には「福建人はベルガモットを使って漬物を作ったり、粥にしたりしますが、香りがよくて食欲をそそります。」とあります。皮は辛く、果肉は甘くて少し苦いです。甘さは胃を落ち着かせ、辛さは気を補うので、心臓や胃の痛みの治療に適しています。古いものが一番よく、新鮮なものは粥に使い、あまり長く煮込まないでください。) 百合粥(本草綱目処方には「肺を養い、中枢を整える」とある。また、熱、咳、脚気の治療にも使える。季漢本草綱目では「白い花と広い葉は百合、赤い花と尖った葉は百合で、薬にはならない」とある。花や葉は違うが、形や味は似ていて、性質が全く違うわけではないと思う。) アモムム・ビロサム粥(『養生良方』によると、嘔吐や腹痛に効く。咳、膨満感、膨満感にも効く。脾臓を目覚めさせ、気滞を取り除き、寒湿を払い、腎臓と肝臓を温め、炒めて白内障を取り除く。粉末にして粥に加える。乾燥に潤いを与える。韓茂の『医通』には「腎臓は乾燥を嫌い、心臓は潤いを与える」とある。) エゾウコギの芽粥(『家宝方』には「視力を改善し、喉の渇きを癒す」とある。『本草』には「エゾウコギの根の樹皮には多くの効能がある」とある。また「葉は野菜として皮膚リウマチの治療に使用できる。若い芽は乾燥させてお茶にして喉を潤す。粥は緑色で香りがよく、同じ効果がある」とも書かれている。馬謖の易武誌では「文昌草」と呼んでいる。) クコの葉粥(川心芳:「五つの疲労と七つの怪我に効く。豆腐汁と米と一緒に炊く。」また、上焦の外熱、リウマチ、視力回復、精神安定にも効く。甘くて涼しい味で、根皮や種子とは少し性質が違う。『碧潭』:「陝西省で群生するものは抱きしめられるほど大きい。葉を摘んでお茶にする。」) ビワの葉粥(枕草子には「熱咳を治すには、ビワの葉に蜂蜜水を塗り、粥にして葉を取り除いて食べる」とある。気を下げて喉の渇きを癒し、夏バテの毒を取り除く効果もある。霜が降りた古い葉を使うときは、髪の毛を拭き取り、甘草スープで洗ったり、ショウガ汁で黄色くなるまで煎ったりして、肺病のお茶の代わりに飲むこともできる。) 明州の『保生姑』には、「痰を取り除き、消化を助け、煮て濃いスープにしたり、お粥に加えたりできる」とある。また、ショウガを加えるとマラリアや赤痢も治る。 『茶経』には「茶には五つの名前がある。一は茶、二は昔の茶の木を指す甲甲、三は中国の薬草の一種である茅、四は明、五は茶の古い葉、すなわち粗茶である」とある。『茶書』には「早く摘んだ葉は茶、遅く摘んだ葉は明である」とある。『丹前録』には「茶は『土』の古語である」とあり、『詩経』の「土は苦いと言う者あり」という一節は真実である。 水粥「慈山神如」:「本草綱目」によると、「米を炊くのに使い、気を促進し、筋肉をリラックスさせ、粥に入れるのと同じ効果があります。」これは風寒を消すだけでなく、痰を取り除き、血を調和させ、痛みを和らげる製品です。裏面は紫色で、より良いです。 「本草綱目」には「中を養い、気を補充する」とある。残念ながらそうではありません。 ) シソ粥(『簡方』には「咳止めと逆流止めに効く」とある。また、『済生方』には「ゴマを加えるとガスや腸の調子がよくなる」とある。痰をなくし、肺を潤す効果もある。『本草経』には「シソ粥を定期的に食べると太り、白くなり、香りがよくなる」とある。『丹方鏡源』には「シソ油は五金八石を柔らかくする」とある。) 火香粥(易玉路は「夏の暑さを消し、悪い気を払う」と述べている。また、脾臓と胃、嘔吐、コレラ、心臓と胃の痛みを治療し、食欲を増進する。『交光誌』は火香は木本植物だと述べている。金楼子厳は「五香はすべて同じ木から採れ、葉は火香である」と述べている。粥には南方のハーブを使用し、新鮮なものの方がよい。) ミント粥の「易玉露」:「喉をすっきりさせ、口の中を香ばしくします。」また、痰や咳を止め、頭痛や脳の不整脈を治療し、発汗を促し、消化を助け、ガスを解消し、舌の詰まりを取り除く効果もあります。 『本草綱目』には「煮汁や炊飯は熱を消すのに効果的で、特に粥状になるのが適している」とある。楊雄の『甘泉附』では「茇[bá 草の根] 葀[kuò mint〔菝葀〕」と表記されている。 松葉粥(聖慧芳:「細かく刻んで汁を煮て粥を作ると、軽くて体に良い。」また、リウマチを治し、五臓六腑を落ち着かせ、髪を生やし、心臓を保護して飢えに抵抗する効果もあります。または、汁をすりつぶして粉末にし、天日で乾燥させて粥に加えることもできます。子朔:「松とヒノキはすべての木の王です。松は人のようで、ヒノキは老人のようです。」) ヒノキの葉粥(尊勝八鑑曰く「仙人の食べ物」。腐血、血便、下痢、膨満感にも効く。ヒノキの葉を使い、四季に応じて摘み、すり潰して汁にし、粉末にして粥にする。本草延易曰く「ヒノキは西を指し、金の陽気を得る、貞潔の陰木である」) 山椒粥(『養生本草経』には「口内炎に効く」とある。また『千金易』には「下痢、腰腹冷えに効く。粥を作るときは焼きそばを加える」とある。中腎を温め、湿を取り除き、腹痛を和らげる。口を開けて使うが、閉じると毒になる。『馬舒奇記』には「四川清渓県産が良い」とある。香りも違う。) 栗粥(岡木レシピ:「腎気を補い、腰と足に効き、米と一緒に炊く。」食欲を増進し、血行を促進する効果もあります。砂を湿らせて集めると、夏には新品同様になります。サンスクリット名は「杜家」、平らな部分は「李謝」と呼ばれ、特に血行促進に良いです。「経験処方」:「毎朝風乾した栗を噛み、豚の腎臓粥を加えると腎臓を強壮する効果があります。」) 緑豆粥(普済方:「喉の渇きと飲水に効く」。岡木にも「熱と毒を和らげる」とある。排尿を助け、腸と胃を強くし、夏の暑さと気の衰えを取り除き、皮膚と肉を落ち着かせる。髭と皮を使い、まず汁を沸かし、豆を取り除いて米を加える。易建志には「トリカブトの毒を和らげる」とある。) 鹿の尾粥「慈山神肉」:鹿の尾は広東省産の乾燥したものが最高で、脂肪膜を取り除き、中に凝固した血液があり、柔らかいレバーのようで、珍味です。細かく刻んでお粥にすると、あっさりとして脂っこくなく、独特の香りがします。非常に虚弱を補う。陽気は角に集まり、陰血は尾に集まる。 ) 燕の巣粥(医学書:「肺を養い、痰を消し、咳を止める。滋養強壮で滞らない。粥を炊いて軽く食べると効能がある。」本草書には記載されていないが、全南雑注に収載されており、何なのかは不明である。色は白く、肺を養い、肌理は澄んでおり、痰を消し、味は淡白であることは明らかな証拠である。) |
<<: 清朝の老人保健に関する論文集『老老衡衍:第4巻:トイレの全文』
>>: 清朝の老人保健に関する論文集『老老衡衍』第5巻第27部
推薦する
なぜヨーロッパに中国人労働者の像が建てられるのでしょうか?中国人労働者の像はどのようにして作られたのでしょうか?
なぜヨーロッパに中国人労働者の像が出現するのか?中国人労働者の像はどうやって作られるのか?興味のある...
古典文学の傑作『太平天国』:周君部第二巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
もし孟天が趙高の邪悪な陰謀を許さなかったら、秦王朝はこんなに早く滅びただろうか?
蒙恬はご存知の方も多いと思います。蒙恬は戦国時代後期の秦の将軍です。蒙恬は六国を征服しましたが、その...
呉文英の「雲河を渡る:恥ずかしさと憎しみで顔を赤らめ、しかめ面する」:終わりのない失望と喪失を明らかにする
呉文英(1200年頃 - 1260年頃)は、雅号を君特、号を孟荘といい、晩年は妓翁とも呼ばれた。思明...
『紅楼夢』の薛宝才はなぜわざわざカニ料理の宴会を企画したのでしょうか?
薛宝才はなぜ『紅楼夢』の中でわざわざ蟹宴会を企画したのでしょうか? 明らかに、石向雲は当初詩歌会を運...
『Bald Mountain』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
ボールドマウンテン王安石(宋代)役人たちと召使たちは広大な海の上にいて、山々を眺めるために船を止めま...
『紅楼夢』で、賈祖母はなぜ元陽を守ったのに青文を守らなかったのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
黄帝内経素文慈之論第53章原文の鑑賞
黄帝は尋ねた。「私は空と現実の鍵を知りたいのです。」斉伯は答えた。「気が満ちていれば身体も満ちている...
老子の誕生の物語はどれほど奇妙なのでしょうか?老子の誕生物語の紹介
皆さんご存知の通り、老子は古代の思想家、哲学者、作家、歴史家であり、道教の創始者であり代表者です。一...
紙幣に書道を残した最初の人物は誰ですか?
現在見られる「開元通宝」貨幣は、唐の武徳4年(621年)に鋳造されたものです。『旧唐書・食貨記』によ...
趙炳文の「清星二:風雨が花を悲しませている」:以前の作品とは異なり、自然な性格
趙炳文(1159年 - 1232年6月2日)、字は周塵、晩年は仙仙居士、仙仙老人とも呼ばれた。磁州阜...
もし劉備が夷陵の戦いを始めていなかったら、曹魏が占領していた関中を占領できただろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『清代名人逸話』文学芸術部門第9巻の登場人物は誰ですか?
◎黄鶴楼の三大奇観畢秋帆は朝廷の大臣で、武昌に政府を樹立しました。彼の同僚の多くは、当時の優雅で賢明...
なぜ端午節は蘭沐浴節とも呼ばれるのでしょうか?玉蘭祭の詳しい説明
まだ分からない:端午節はなぜ沐浴蘭節とも呼ばれるのでしょうか?これは、古代人が5月5日の沐浴を非...
西安は13の王朝の古都として知られています。その13の王朝とはどの王朝でしょうか?
西安はかつて長安と呼ばれ、千年の歴史を持つ首都です。イタリアのローマ、ギリシャのアテネ、エジプトのカ...