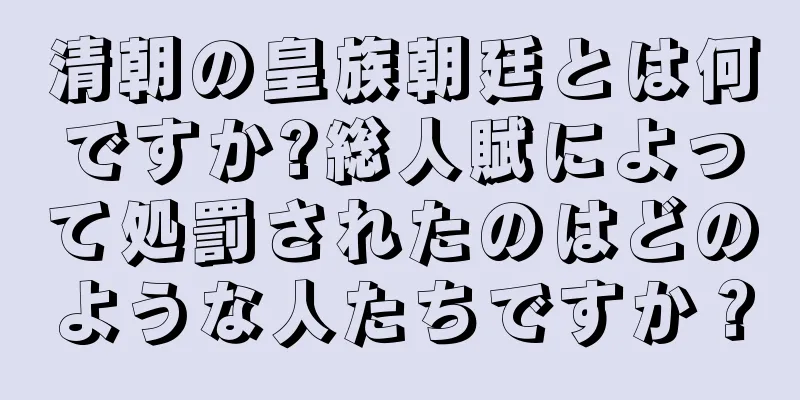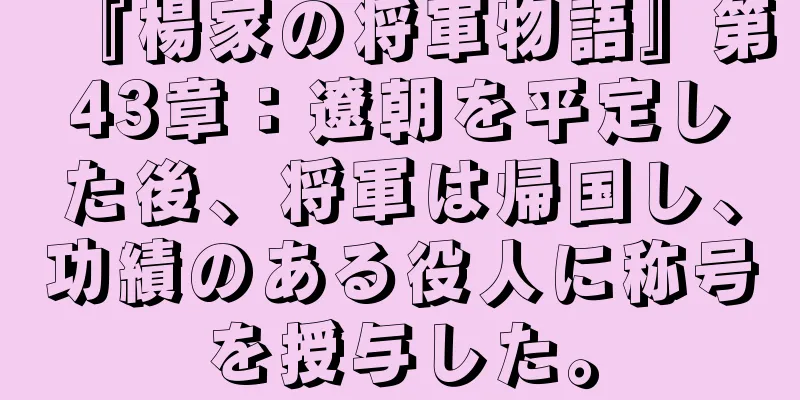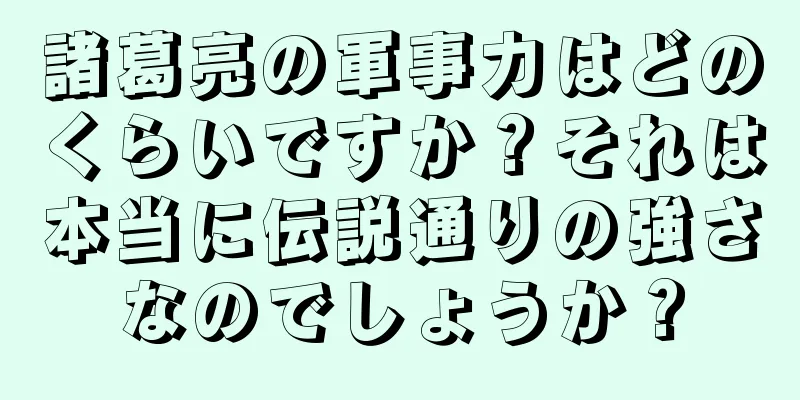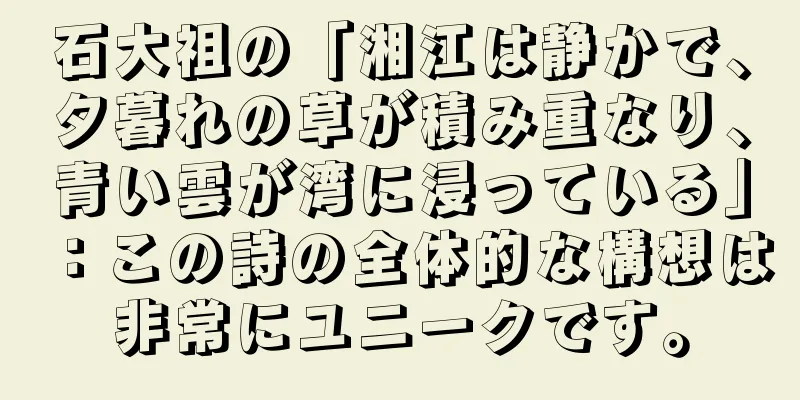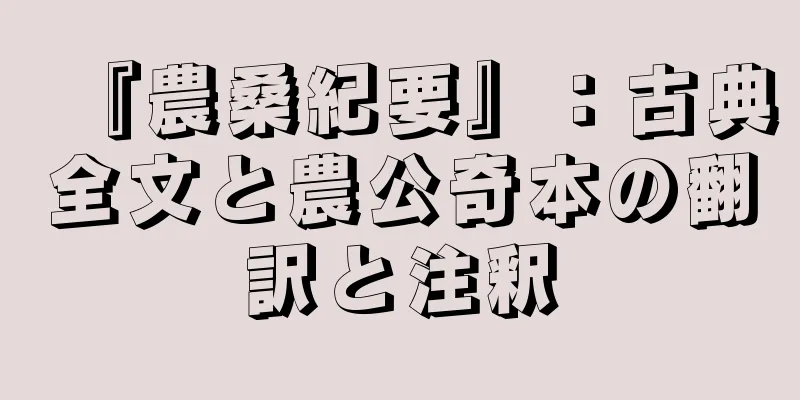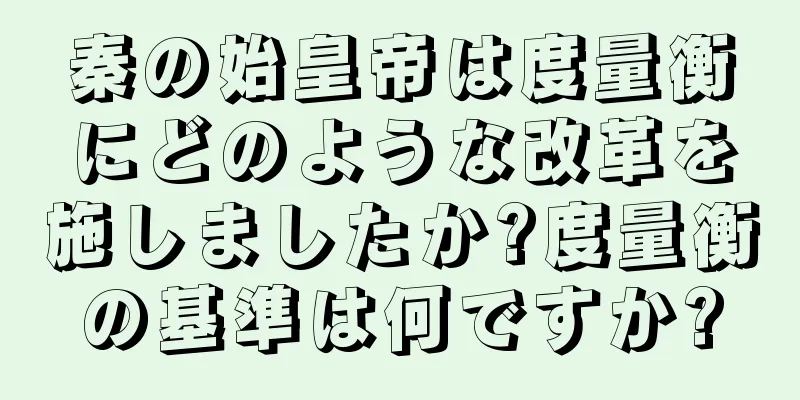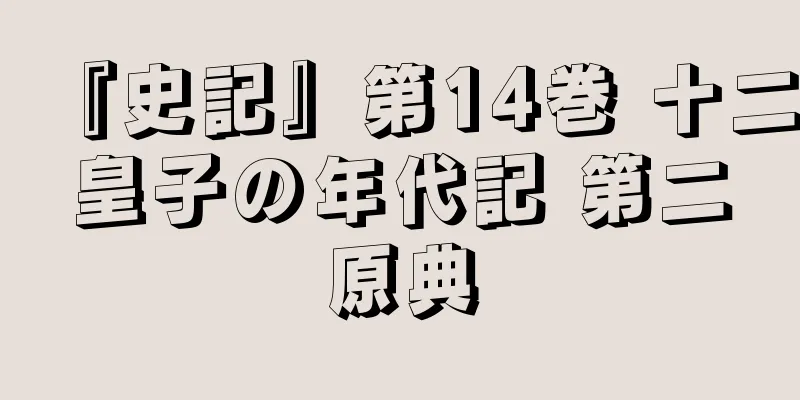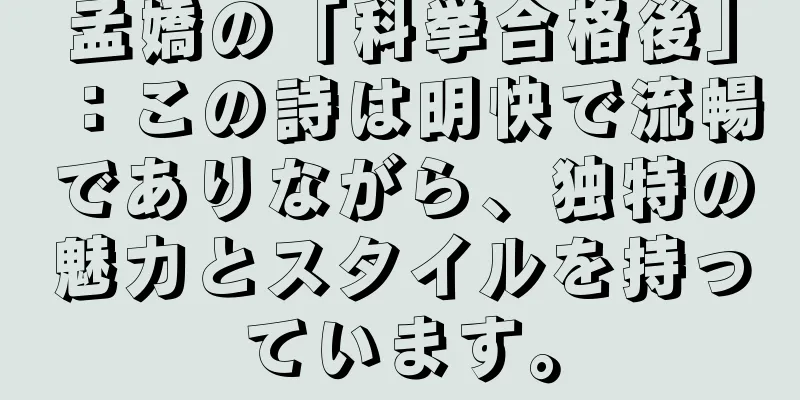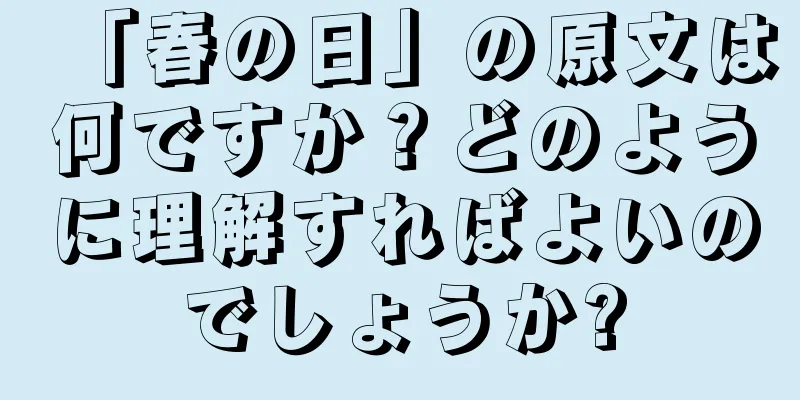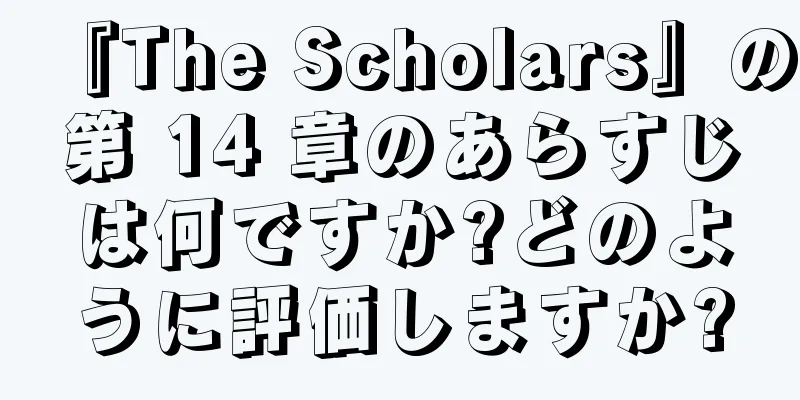清朝の老人保健に関する論文集『老老衡衍』第5巻第27部
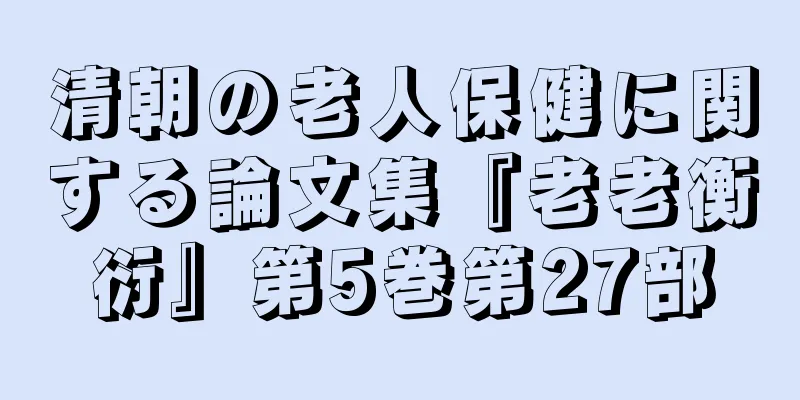
|
『老老衡厳』の著者は清代の学者曹廷東で、老年期の健康維持に関する論文集で全5巻からなる。周作人はこれを高く評価し、還暦の贈り物としてふさわしい良書と評した。最も優れた版は、清朝の乾隆38年に曹廷東自身が印刷した版である。それでは、次の興味深い歴史編集者が第 5 巻、中級 27 の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう。 ヤムイモ粥(体験記:「慢性下痢の治療には、もち米を一晩水に浸し、ヤムイモを炒め、砂糖と胡椒を加えて調理する。」また、腎精を養い、胃を強くする効果もあります。葉の間に実る種子は鐘ほどの大きさです。お粥に加えると良いでしょう。『杜蘭香伝』には「これを食べると霧や露を防ぐことができる」とあります。) 白毫椰子粥(『志志方』では「心虚、夢精、帯下を治す」とあり、『剛母方』では「上半身を清め、下半身を満たす」とあり、『財真記』では「眠気と不眠を治す」とある。『史記帰世伝』では「『涪霊』と名付けられ、松の精が隠れているという意味。心を落ち着かせ、湿気を取り除き、脾臓に効く」とある。) 小豆粥(日用必需品:「むくみを解消する。」また、本草綱目では、「排尿を促進し、脚気を治し、邪気を払う。」とある。喉の渇き、下痢、腹部膨満、嘔吐にも効く。飲食本には、「冬至に小豆粥を食べると疫病の鬼を追い払うことができる。」とある。邪気を払うという意味。) ソラマメ粥(『善豎清公』には「胃と脾臓を癒す」とある。内臓にも良いとされているが、古典には記載されていない。『万表記善湯方』には「誤って針を飲み込んだら、ソラマメをニラと一緒に食べれば、便から針が出てくる」とある。内臓に良いと証明されている。粥を作るときは、露のついた若い豆を摘み、皮をむく。皮には渋みがある。) 天草の根粥(千金月齢:「喉の渇きを治す」。天草の根の根です。『宝枝論』には「丸いのが天草、長いのが楼で、根は同じ」とあります。粉末にして粥に加えると、落ち着きと熱を取り除き、虚を補って中を落ち着かせ、熱と狂気を治し、肺を潤し、火を減らし、咳を止めることができ、虚熱の人に適しています。) 麺粥(外大米要:「風邪赤痢や下痢の治療には、小麦粉を黄色くなるまで炒め、米と一緒に炊く。」また、体を強壮し、欠乏を補い、五臓六腑を助ける。岡母曰く:「北の麺は性質が中性なので、食べても喉が渇かない。南の麺は性質が熱いので、食べると喉が渇く。」地元の気候によって異なる。サンスクリット名は「Jia Shi Cuo」。) 福建粥(慈山神儒:福建は生食です。どんな豆でも作れますが、主に白豆です。肺を潤し、膨満感を和らげ、大腸の濁気を取り除き、排尿を促進します。夏は汗が有毒です。北部では「甘いお粥」と呼ばれています。石炭中毒を和らげる効果があります。人々はこれを肩に担いで早朝に市場で売ります。) 竜眼肉粥(高麗人参入り。食欲と脾臓を刺激し、心臓を養い、知能を高め、心を開き、五臓を鎮めます。効果は絶大です。『本草眼益』には「これは果物であり、薬として使われたことはない」と書かれていますが、それは真実ではありません。『明易別録』には「悪霊を治療し、毒を取り除くことができます。長期摂取すると、魂を強くし、体を軽くし、老化を防ぐことができます」と書かれています。) ナツメ粥(慈山神具:道教の処方と薬材によると、「ナツメは良い餌であり、皮は良く、肉は滋養がある」。皮をむいて使用する。脾臓を養い、胃を落ち着かせ、肺を潤して咳を止め、五臓を養い、すべての薬を調和させる。ナツメにはさまざまな種類があり、青州の黒ナツメが良い。南ナツメは軽くて少し酸味があるので使用しないでください。) サトウキビの果肉粥(財鎮記によると、咳、虚熱、口や舌の乾燥に効果があります。また、脾臓の働きを助け、大腸と小腸に利益をもたらし、イライラと熱を取り除き、アルコールを解毒します。青と紫の2種類があり、青の方が良いです。果肉に絞って粥に加えます。火で煮ると、本来の効能が失われ、砂糖のアイシングと変わりません。) 柿粥(『食養生本草経』には「秋赤痢に効く」とあり、『生計方』には「鼻づまりに効く」とある。脾臓と腸を強化し、出血と咳を止め、痔にも効く。白柿は天日干し、黒柿は火干し。白柿の方が良い。干した柿の皮をむいて瓶に入れ、白霜がつくのを待ち、その霜をお粥に加えるのが良い。) 梔子粥(『慈山神略』によると、一般的には「鶏冠」と呼ばれ、形は珊瑚のように丸まっており、味はナツメのように甘い。『古錦朱』には「木の蜜」と呼ばれ、落ち着きのなさや熱を和らげ、特にアルコール中毒を和らげる効果がある。酔った翌朝の空腹時にこの粥を食べるのは非常に適している。古い枝と柔らかい葉を煮て汁にすると、甘さが2倍になり、落ち着きのなさや渇きを和らげることもできる」と書かれている。) クコ粥(『本草綱目』の処方には「精血を補い、腎気を養う」とある。喉の渇きを癒し、風を払い、目を明るくし、心を落ち着かせる。諺に「家から何千里も離れたところでクコの実を食べてはいけない」とあるように、陽のエネルギーを強めると言われている。『本草綱目』には「種子はわずかに冷たく、現代人は腎強壮薬としてよく使う」とある。古典の意味は検討されていない。) 菌粥(桂一芳は「痔の治療には、桑、イナゴ、コウゾ、ニレ、ヤナギを五菌として用いる」と述べている。神農の『本草経』には「気を補い、飢えを防ぎ、体を軽くし、心を強くする」とある。しかし、すべての木は菌を生やし、良い毒と悪い毒も木の性質による。粥にして調理すると、赤腸の治療にもなる。非常に柔らかく調理しなければならず、味は淡白で澄んでいる。) 麦粥(『医食同源』には「喉の渇きを癒す」とある。また、排尿を助け、肝臓と心臓を養い、発汗を止める。『本草綱目』には「麦麺は温かく、糠麺は熱く、四季の気で調理して熱を治す」とある。皮は熱いので剥がさない。まず汁を沸かし、麦を取り除いて米を加える。) ヒシの粥(本草綱目では「腸と胃に効き、体内の熱を解消する」とある。本草綱目では「ヒシは病気を治すことはないが、少しは効く」とある。種は様々。池に生える野生のヒシの実もある。殻は硬くて小さい。乾燥させて粥にすると、より強い香りがする。左伝の「曲刀希覚」はこの植物のことである。) 薄竹の葉粥(紫山人参入り。春に生育し、茎は細く、竹のような緑の葉、花は緑色で、花びらは蝶の羽のようです。イライラや熱を鎮め、排尿を促進し、心をすっきりさせます。『本草綱目』には「薄竹の葉を水で煮て米と一緒に炊くと熱を逃がす効果がある」とあります。米や粥を炊く方が適切です。) バイモ粥(紫聖録:「痰を溶かし、咳を止め、出血を止める。すり潰して粥にする。」喉の痛みやめまい、うつ病の緩和にも効果がある。一粒でも有毒。詩経には「虻をとる」とある。虻の原語は「莔」。爾耶:「莔[méng、中国の薬草の一種、すなわち「バイモ」]は、バイモである。」詩経はもともと欲求不満のために書かれたため、「虻をとる」ことでうつ病を治すとある。) 竹の葉粥(『養老書』には「内熱、赤目、頭痛を治すには石膏と砂糖を加える」とある。中景が「竹の葉石膏粥」と表現したのはこの意味である。また、病因による発熱にも効き、竹の葉だけで粥を炊くと喉の渇きを癒し、落ち着きのなさを和らげることもできる。) 竹汁粥(『本草綱目』:「熱と風を治す。」 『手足清編』:「痰と火を治す。」 また、口内炎、目の痛み、喉の渇きにも効きます。 痰が経絡や四肢にある場合は、これなしでは痰に届きません。 粥を炊いた後に追加します。 『本草綱目補遺』には、「竹汁は痰を取り除くことができますが、生姜汁なしでは痰を取り除くことはできません。」とあります。) 牛乳粥(『千金易』:「牛に白水晶と黒豆を与え、牛乳粥を作ると、太って健康になる。」また、脾臓を強化し、黄疸を取り除くことができます。『本草世易』には、「水牛は黄色い牛よりも良い」と書かれています。ゴマペースト、焼きそば、お茶、塩、牛乳を加えます。北部では「麺茶」と呼ばれ、高齢者に良いです。) 鹿肉粥(高麗人参入り。広東省には乾燥した鹿肉の細片があり、それを酒で軽く煮てから粥に切ります。香りがよく、とても美味しいです。中臓を養い、気力と体力を高め、五臓六腑を強化します。『首氏清編』には「鹿肉は滋養を与えず、陽を弱める」とあります。『別録』によると、角は陽のエネルギーが上昇するため、陽を弱める可能性があります。) ムール貝粥(『星芎瑶』:「下痢を止め、腎臓を養う。」疲労、精血不足、吐血、腸鳴り、腰痛、甲状腺腫にも効く。海藻と同じ効能がある。『甘思要葱』には「大根や紫蘇、冬瓜をご飯と一緒に炊くのが一番良い。高齢者に最も効能がある。」とある。必要に応じてお使いください。) 鶏のスープ(『医食同鏡』には「狂気を治すには白鶏を使え」とある。また『養老書』には「脚気を治すには黒骨鶏を使え」とある。また、体と血を養うこともできる。荀は風と鶏を象徴するため、風病の人は食べないように。『陶洪景正経』には「白鶏を飼うと邪気を払うことができるが、野生の鶏は人間にとって良くない」とある。) 鴨汁粥(『医食同鏡』には「水病で死にそうな場合は、緑頭鴨を五香粉で粥状に煮る」とある。また、虚を補い、熱を消し、排尿を促し、熱性赤痢を止める効果もある。『鳥経』には「白いものは良い、黒いものは有毒、年老いたものは良い、若いものは有毒」とある。野鴨は特に病人に良いが、クルミ、キノコ、黒豆と一緒に食べてはいけない。) ナマコ粥(『星楚易』には「インポテンツを治し、下腹部を温める」とある。腎臓を養い、陰を補う。『南民記文』には捕獲法として「女性を裸で水に入れれば、追いかけて来る。好色である。黒い色は腎臓に入り、これも同じ種類である。まず材料を煮て細かく切り、米を加え、五味を加える。」とある。) 干し魚の白粥(尊勝八鑑は「食欲を刺激し、脾臓を和らげる」と述べている。消化を助け、赤痢や腹部の膨張を止める効果もある。爾耶易は「干し魚はすべて干し魚だが、石頭魚ほど良くないため、白という名前が付けられたのは石頭魚だけだ」と述べている。呉地志は「干し魚の字は美しい魚の字と魚の字で構成されているため、干し魚の字は同じではない」と述べている。生姜と発酵した黒豆と一緒に粥を調理する。) |
<<: 清朝の老人保健に関する論文集『老老衡衍』第5巻、上36
>>: 『紅楼夢』では、王希峰は最終的に離婚しました。賈憐はどこからその自信を得たのですか?
推薦する
項羽の覇王槍はどれくらい重かったのでしょうか?現在の重量換算は本当でしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が項羽の物語をお届けします。興味のある読者は...
蒋子牙の生涯にわたる業績を見て、歴史上誰が彼についてコメントしたでしょうか?
歴史上、蒋子牙について言及した人は数多くいます。蒋子牙の人生は波瀾万丈でしたが、壮大で神秘的なもので...
王安石の「仁城寒食節」は、改革が実行できなかった後に引退したいという彼の願望を表現している。
王安石は、号を潔夫、号を半山といい、北宋時代の政治家、改革者、作家、思想家であった。彼は文学において...
「2月2日龍が頭を上げる」とはどういう意味ですか?ドラゴンを家に招き入れる4つの方法
「二月二日は龍が頭を上げる」とよく言われますが、これはどういう意味でしょうか?実は、龍が頭を上げると...
デアン族の衣服の民族的特徴は何ですか?
デアン族の服装は非常に特徴的です。男性は主に、大きな襟の付いた青または黒のジャケットと幅広の短いズボ...
『紅楼夢』の黛玉と宝釵はなぜ同じ判決を下したのでしょうか?理由は何でしょう
『紅楼夢』では、岱玉と宝仔は同等の地位にある二人の少女です。Interesting History ...
曹操が南の荊州を占領したとき、劉備はなぜ何十万もの民間人を川を渡らせて南に撤退したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
北宋時代に司馬光によって制定された成人の儀式とはどのようなものだったのでしょうか?
儒教を語るとき、儒教と新儒学の祖である朱熹を忘れることはできません。後世の儒教を学ぶ人は、朱熹の資料...
王維 - 「夏に青龍寺の曹禅師を訪ねる」という詩の本来の意味を鑑賞する
古代詩「夏に青龍寺の曹禅師を訪ねる」時代: 唐代著者: 王偉年老いて弱々しい老人が、禅寺までゆっくり...
「月橋の両側に花が半分咲いている」とはどのように理解すればよいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
月橋の両側に半分咲いた花甄徳秀(宋代)月橋の両側の花は半分咲いています。赤くて香りのよい皮が密かに観...
『西遊記』で観音が唐の僧侶に仏典を手に入れるよう頼んだのはなぜですか?
『西遊記』は、唐和尚とその三人の弟子が仏典を求めて西へ渡り、81もの困難を乗り越えてついに仏典を持ち...
「岳陽塔登頂記」は杜甫によって書かれたもので、「岳陽塔」と「洞庭湖」について書かれたものだけではない。
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
劉琦はどうやって死んだのですか?なぜ彼は死ぬ前に軍隊を劉備に引き渡したのでしょうか?
荊州太守劉表の長男劉琦は、継母の蔡瑁と張雲の罠にかかったため、西暦208年に江夏へ逃げなければならな...
ヌルハチの名前の意味は何ですか?ヌルハチはなぜイノシシ皮と呼ばれるのでしょうか?
ヌルハチは、満州語の本来の意味によれば、「イノシシの皮」を意味します。ヌルハチの両親は、長男が森のイ...
「迪蓮花:花びらが風に舞う」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
蝶の愛の花·風に舞う散り花欧陽秀(宋代)散りゆく花びらが風に舞い上がる。柳は濃い煙に覆われ、雪片が舞...