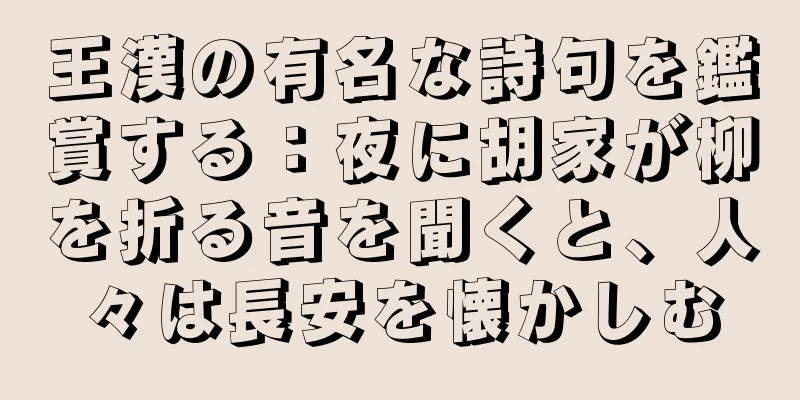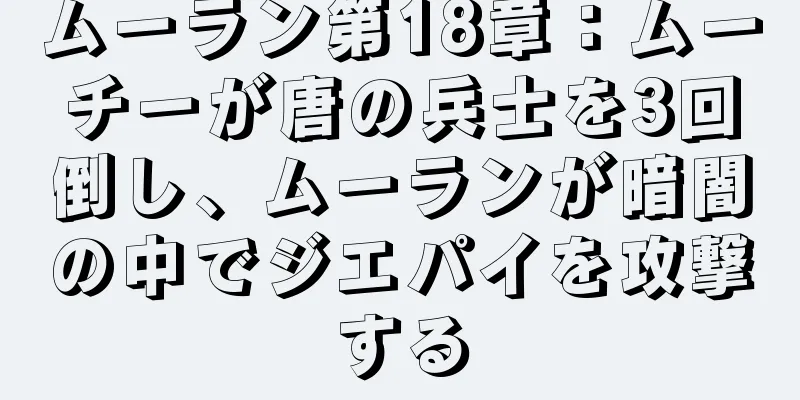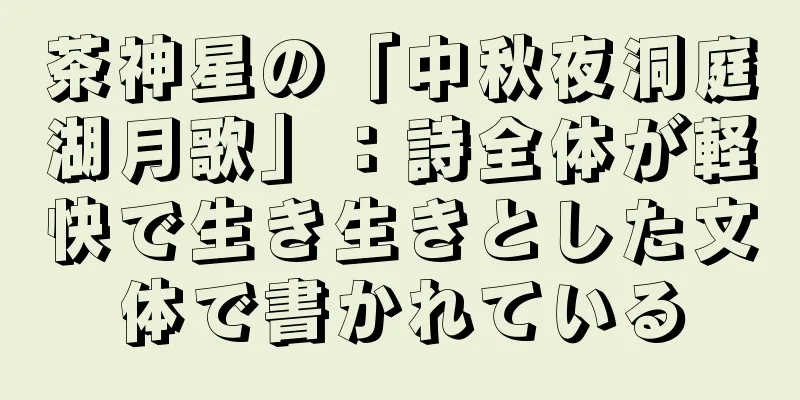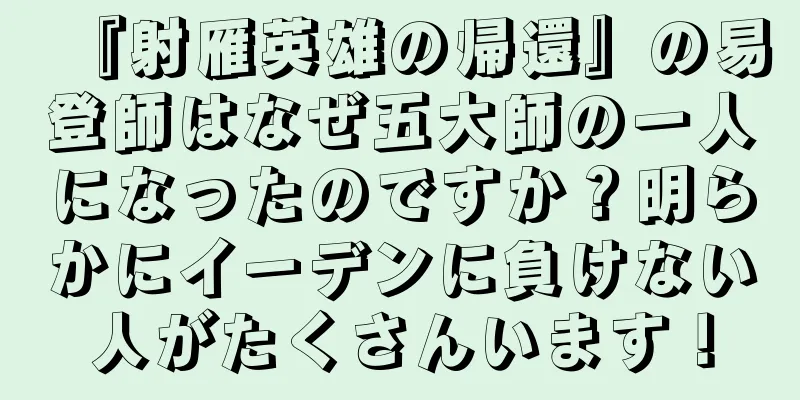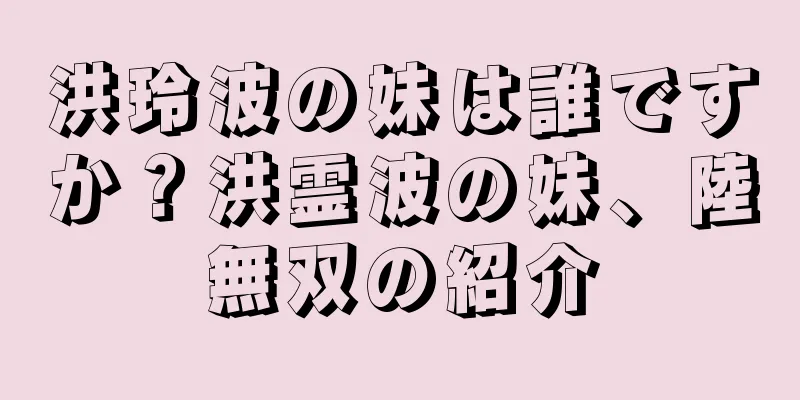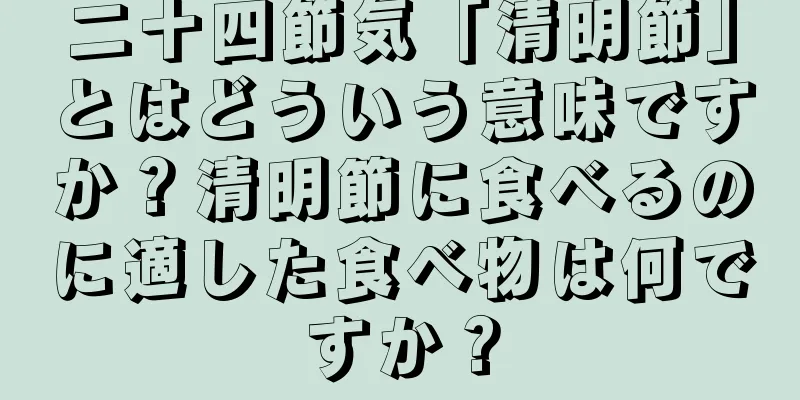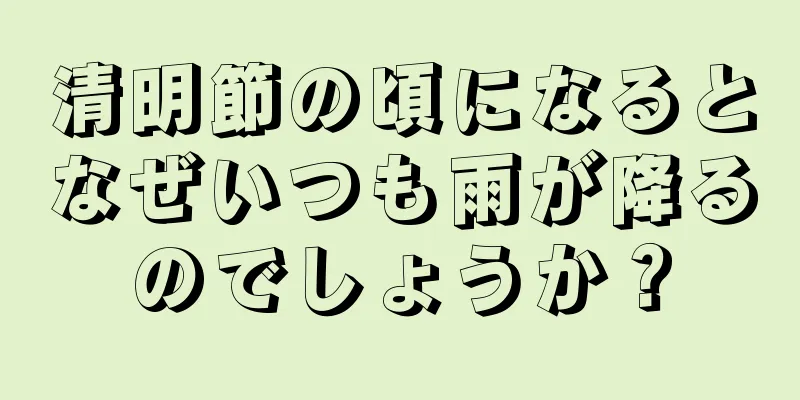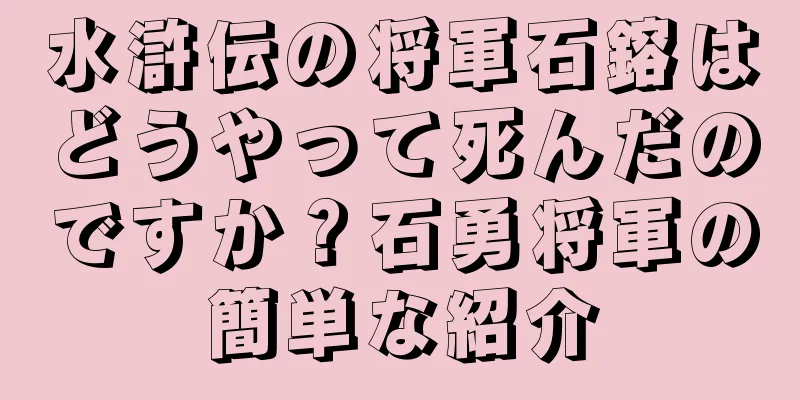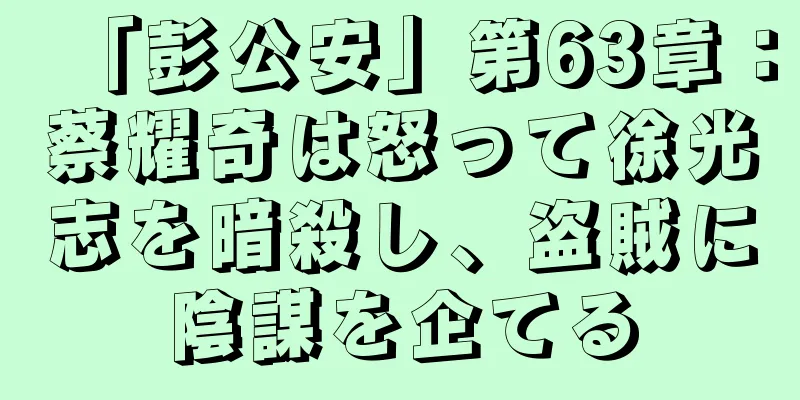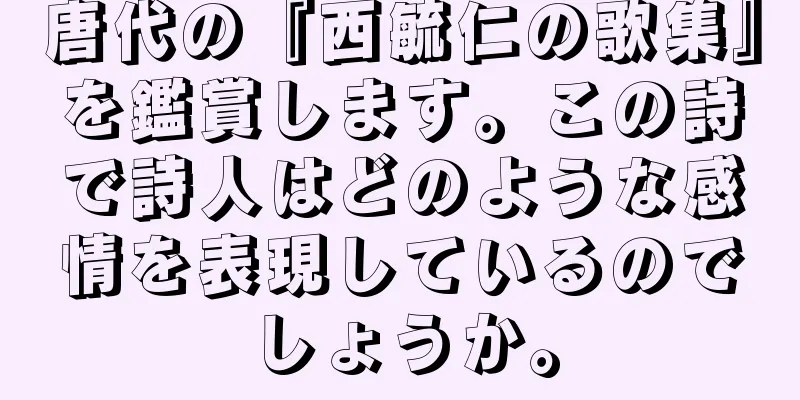旧暦の最初の月にひげを剃らないという習慣はどのようにして伝わったのでしょうか?その裏にある物語は何ですか?
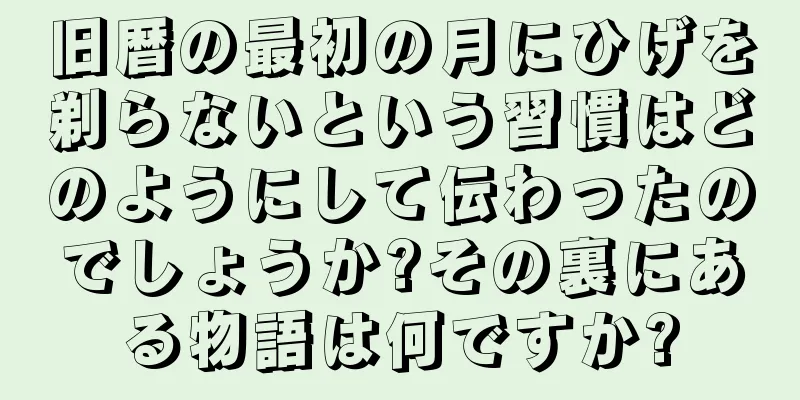
|
私の国には、旧正月には髪を切らないという民間伝承があります。そのため、ほとんどの人は大晦日の前に髪を切り、その後、龍が頭を上げる旧正月2日に髪を切ります。そのため、人々の間では「旧正月に髪を切らないと叔父が死ぬ」という噂があります。この噂は本当ですか?専門家が古書を調べたところ、旧正月に髪を切らないという習慣は瀋陽に始まり、清朝が中原に進出したときに始まったことがわかりました。 1644年、清軍が関に侵入し、李自成を破った後、順治は瀋陽皇宮で「剃髪令」を発布した。当時の清朝政府は「辺を剃り中原を守る」政策を実行するために、前髪から頭頂部まで髪を剃り、さらに生え際を全体的に剃り落とし、真ん中に集中した部分と長い三つ編み(金銭鼠の尾)だけを残すという奇妙な髪型を実施することを決定しました。清朝政府は国家を統一し、特にイデオロギーを統制するために、漢民族の間でこの髪型を推進しました。 「旧暦の正月に髪を切ると叔父が死ぬ」という言い伝えは、実は噂です。「叔父が死ぬ」というのは、実は「過去を懐かしむ」という意味です。この言い伝えの起源も瀋陽に関係しています。清朝が成立した後、当時の多くの漢人は明朝への郷愁を表現するために旧暦の正月に髪を切らなかったが、清朝政府に公然と対峙する勇気はなかった。そのため、「旧暦の正月に髪を切ると叔父が死ぬ」という諺があり、それが今日まで受け継がれている。 「旧暦の1月に頭を剃らないと叔父が死ぬ」という諺が生まれたのは、中国の伝統文化で「体の毛や皮膚は親から受け継いだもの」と考えられているためです。漢族の男性は古来から髪を伸ばしており、「髪」を命とみなしています。「髪を剃る」ことは罰なのです。三国時代に曹操が頭の代わりに髪を切り落としたのはこのためです。 清朝政府は民族衣装を統一するため、漢民族に満州族の髪型に変え、頭を剃り、袈裟を着けるよう強制したが、これは強い国民的抵抗を引き起こし、「床屋になるよりは髪を束ねた幽霊になりたい」というスローガンが生まれ、「江陰十日」のような反髭剃り闘争が起こった。 「その後、民間語の助けを借りて、2部構成の寓話的なことわざが作られました。「年の最初の月に頭を剃ると、死んだ叔父になります。」 「死んだ叔父」の同音異義語は「過去を懐かしむ」ことを暗示し、国家抑圧の暗い支配下での国家的な抵抗感を表現しています。 「髪を切ると叔父が死ぬ」はもともと漢民族が清朝に反抗した際に発した言葉である。300年以上の伝承を経て、別の意味に進化し、今では血縁を重視する中華民族の個性と文化的伝統をより反映している。「社会は進歩し、民俗習慣は発展している。人々は民俗習慣の文化的継承にもっと注意を払うべきだが、それによって正常な生活を遅らせてはならない。真に「習慣を区別し、それを正す」のだ。」 ” |
<<: 酒を飲みながら英雄を論じていた曹操は、なぜまだ台頭していなかった劉備をそこまで評価したのでしょうか。
>>: なぜ徐庶は劉備を第一軍事顧問として見捨てたのでしょうか?
推薦する
謝凌雲の「年末」:年末の気持ちを詩にした詩、時間は再び長く静かな夜になる
謝霊雲(385-433)、本名は鞏義、号は霊雲、号は可児、陳君陽夏県(現在の河南省太康県)の人。東晋...
小説『射雁英雄の帰還』の中で、なぜ欧陽鋒は楊過に自分を名付け親として認めてもらいたいと思ったのでしょうか?
まず、『射雁英雄の帰還』における楊過と欧陽鋒の間に関係があるかどうかについて話しましょう。まず、楊過...
世界のトップ10の自然の驚異は何ですか?トップ 10 の自然の驚異はどこにありますか?
今日は、Interesting History の編集者が、世界で最も息をのむような自然の驚異 10...
『春秋飯録』第1巻の主な内容は何ですか?
楚の荘王 No.1 "King Zhuang of Chu killed Chen Xia...
『紅楼夢』の玉川児の影は誰の影ですか?リン・ダヤユ?
玉川は『紅楼夢』の登場人物。金川の妹であり、王福仁の侍女である。 Interesting Histo...
李清照の『滴蓮花:長楽亭に泊まり姉妹に宛てた手紙』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
李清昭の『十里蓮花:長楽亭に泊まった姉に宛てた手紙』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?これは...
韓鶴帝の尹皇后についての簡単な紹介 韓鶴帝はなぜ尹皇后を廃位したのか
漢の河帝(80-103年)の皇后、名前は不明だが、南陽市新野(現在の河南省新野)の出身である。彼女は...
于謙は明朝を救ったが迫害された。彼を迫害した裏切り者の役人たちはどうなったのか?
明の正統14年、土木の戦いの後、オイラトの騎兵隊は北京の街に直行しました。危機に直面して、陸軍大臣の...
『太平広記』巻178の公殊1の原文は何ですか?
進士試験の概要 進士が礼部に戻って各県を試験する 試験雑文トピックの発表 雑文リストの発表 五大老リ...
朱元璋が死ぬ前に、名将耿炳文を残しました。なぜ朱雲文は彼を利用しなかったのでしょうか?
皇太子朱彪の死後、朱元璋は彼のために戦い帝国を築いた「淮西貴族」を容赦なく殺害した。しかし、同じ淮西...
『紅楼夢』で、賈家の財産没収の中心人物は誰ですか?北京王でしょうか、それとも仲順王でしょうか?
『紅楼夢』では、賈一家が最終的に略奪され、その中心人物は北京王と仲順王であった。興味のある読者は編集...
尖底ボトルの底はなぜ尖っているのでしょうか?底が尖ったボトルにはどんな種類がありますか?
尖底ボトルの底が尖っているのはなぜでしょうか?尖底ボトルにはどんな種類があるのでしょうか?興味のある...
秦瓊と于池公はどちらも唐代初期の有名な将軍です。なぜこの二人はよく比較されるのでしょうか?
秦瓊と于致公はともに唐代初期の名将で、唐の太宗李世民の即位を共に助けた。二人とも霊岩閣の二十四人の功...
思想家としては王扶志と王守人、どちらがより優れているでしょうか?
王扶之は我が国の明代末期から清代初期の偉大な思想家、作家です。彼の生涯は伝説に満ちており、特に彼の思...
秦荘襄王英子楚の父親は誰ですか?
秦の荘襄王の父は秦の孝文王であった。秦の孝文王は安国公としても知られ、戦国時代の秦の君主でした。秦の...