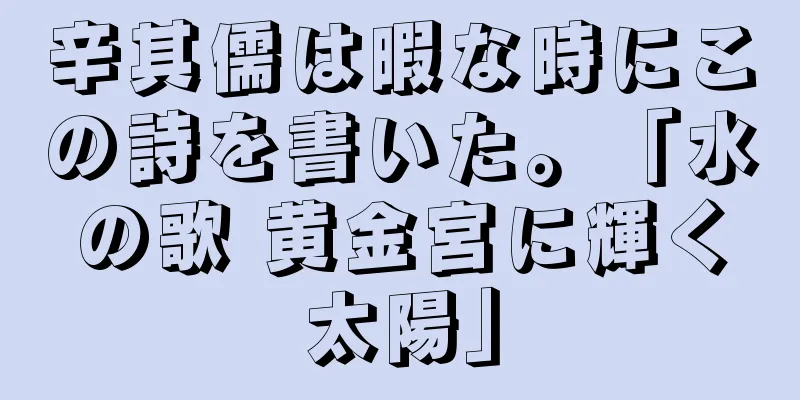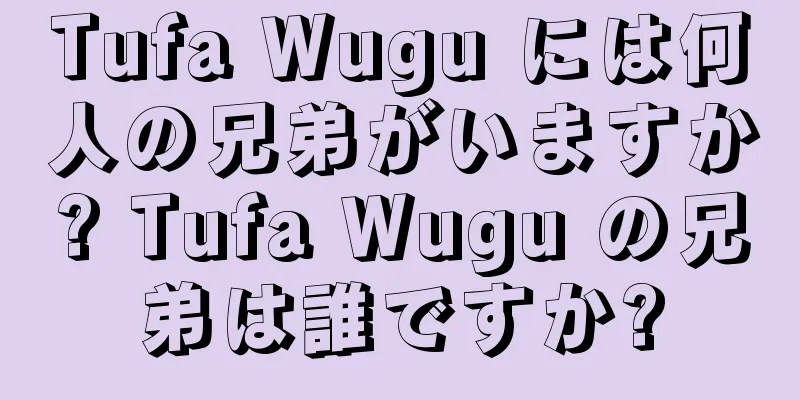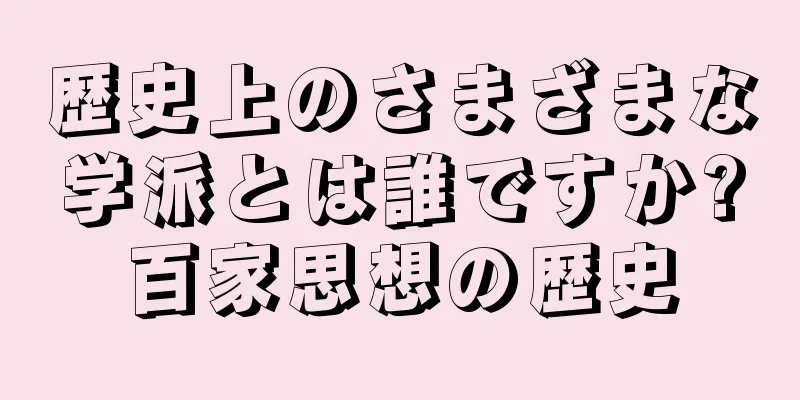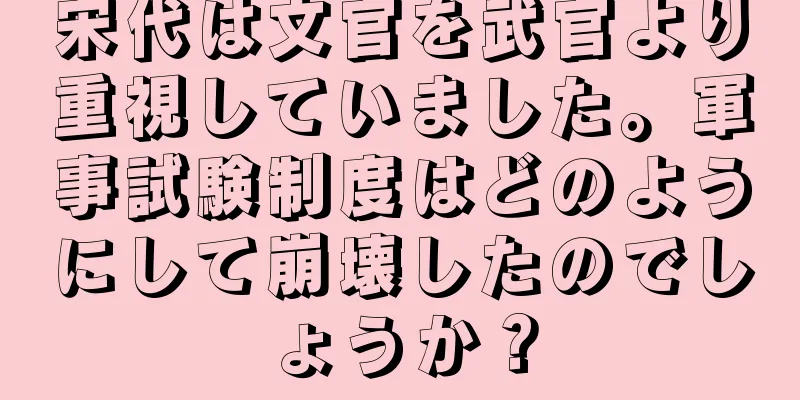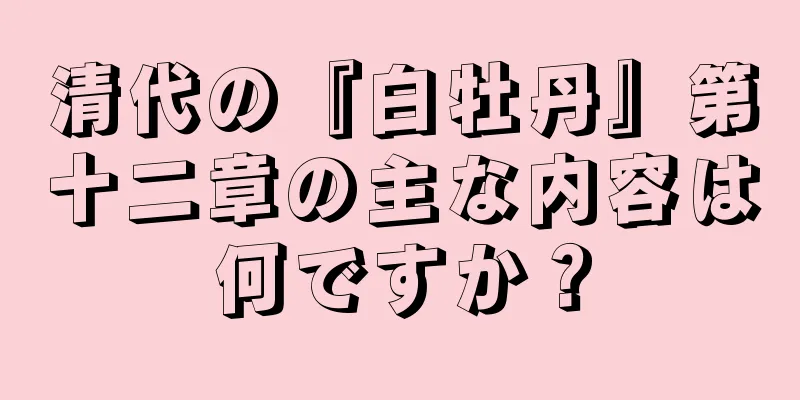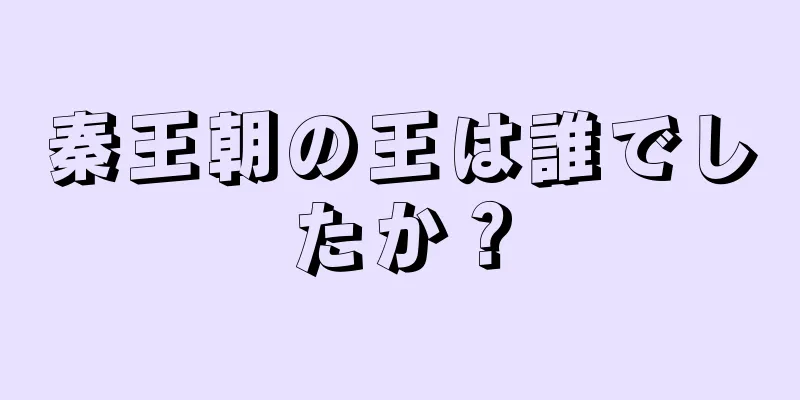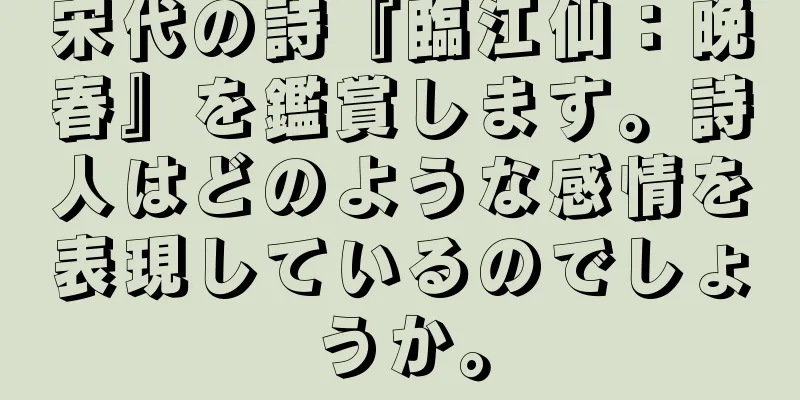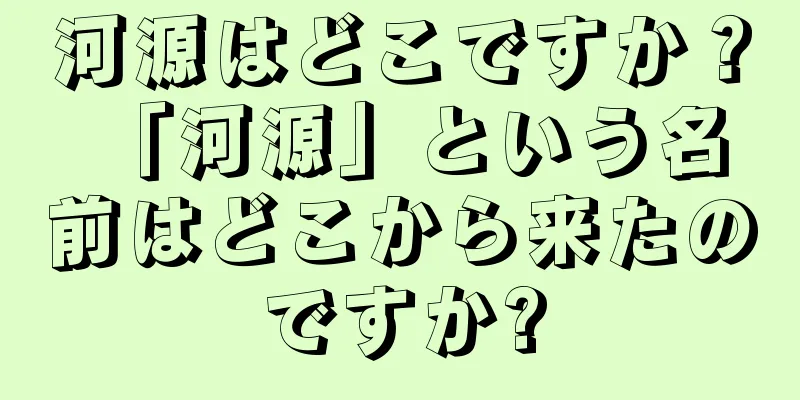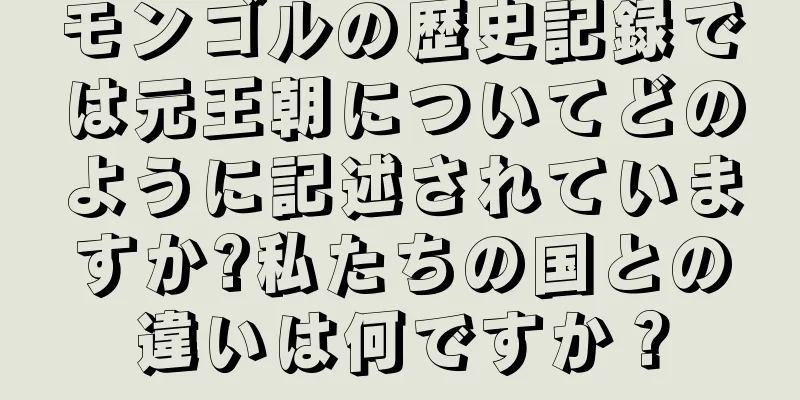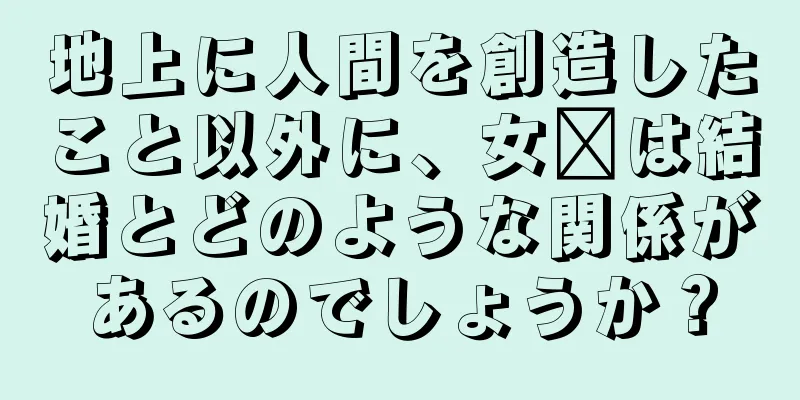実際の関羽はどんな武器を使っていましたか?
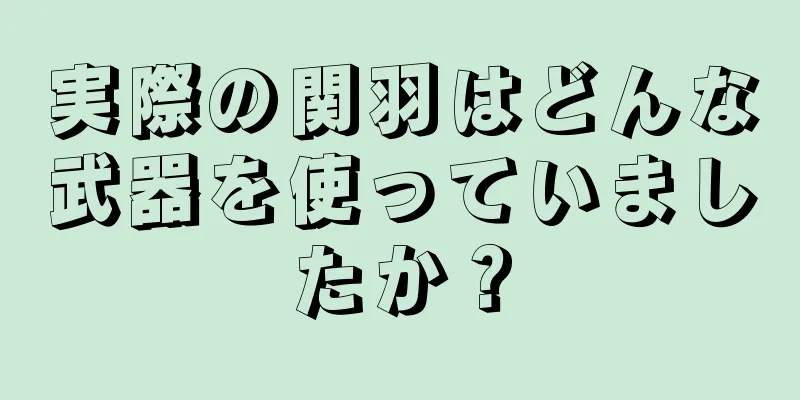
|
中国の小説『三国志演義』では、関羽が使用した武器は緑龍三日月刀です。この小説では、緑龍三日月刀の重さは 82 斤 (現在の 49.2 キログラムに相当) とされており、冷眼鋸としても知られています。関羽はこれを使って多くの将軍を殺したため、後世の人々はこれを「緑龍三日月刀 関刀」とも呼んだ。関羽が殺された後、緑龍三日月刀は呉の東の将軍潘璋によって奪われました。その後、関羽の息子である関行は父の復讐のために潘璋を殺し、緑龍三日月刀を取り戻しました。そのため、関羽と緑龍三日月刀は互いの象徴であると考えられています。しかし、このほぼ無敵の三日月形の刀は、羅貫中の小説の中の伝説に過ぎません。歴史上の実際の関羽は本当にそのような刀を持っていたのでしょうか? 武聖関羽は義を最も重んじる人物でした。後世の記述では、青龍三日月刀は関羽と切り離せない存在でした。人と刀が完全に一体化しており、刀は関羽のイメージに欠かせないシンボルとなったと言えます。 伝説によると、世界最高の鍛冶屋は、緑龍三日月刀を鍛造するために満月の夜だけを選ぶそうです。工事がほぼ完了したとき、突然嵐が起こり、空から1,780滴の血が滴り落ちました。地元の魔術師はそれが青龍の血であると分析した。そのため、「緑龍三日月刀」という名前が生まれ、緑龍三日月刀は1,780人を殺せるという言い伝えがあります。 小説では、緑龍三日月刀の描写が最高潮に達します。例えば、『三国志演義』の第一章では、劉、関、張が千キロの鉄を手に入れ、関羽が「冷美鋸」という奇妙な名前の付いた緑龍三日月刀を鍛造したことが語られています。虎牢関での3回の戦いについて、呂布は次のような詩を残している。「激しい戦いにも勝者は出ず、関羽は戦線の前で怒り、緑龍剣は霜と雪のように輝き、オウムのような戦衣は飛ぶ蝶で覆われている。」緑龍三日月刀と赤兎馬は関羽の目印となった。雪の中で羌の兵を破ったとき、次のような一節が編まれた。「雲霧の中にぼんやりと将軍の姿が見えた。顔はナツメのように赤く、眉は眠っている蚕のようで、緑の衣と金色の鎧をまとい、青龍の剣を持ち、赤兎馬に乗り、手には美しい髭を蓄えていた。」この筋書きは非常に英雄的で、関羽の雄大なイメージが人々の心に徐々に深く根付いていった。 それだけでなく、『三国志演義』では、緑龍三日月刀をめぐって、剣を持って錦の衣を拾ったり、剣を持って一人で会議に行ったり、剣を失くして取り戻したりと、他にも多くの刺激的なストーリーが描かれています。緑龍三日月刀は、関羽よりも長く小説に登場するようです。 緑龍三日月刀の描写が素晴らしいですが、本当に関羽の武器なのでしょうか?歴史研究によると、小説や伝説に出てくる三国時代の名将、関羽が使用した緑龍三日月刀は当時は存在せず、本物の緑龍三日月刀は唐代にのみ登場した武器でした。関羽の三日月形の剣の名前は北宋時代の『武経宗瑶』に登場します。それは当時の有名な戦士たちが、他とは違うことをして自分を際立たせるために作った武器でした。この種の剣は重い武器であり、日常の武術の訓練で使用されますが、基本的に戦闘隊形では使用されません。重すぎて、戦闘に柔軟性がありません。 宋代の龔聖宇は『宋江三十六人礼讃』の中で「大剣の達人である関勝をどうして長孫と呼ぶことができようか。関勝は義勇であり、汝はその子孫である!」と書いている。彼は、すでに存在していた大剣を使う関羽のイメージについて語っており、平化の芸術家によって形作られた後、後の青龍延月のイメージが考案された。その後、『水滸伝』に登場する刀剣男士・関勝は関羽をモデルに作られた。三国志演義では、関羽も剣を使って「呂布に抗う三勇士」に参加しました。「3日目に呂布が再び挑戦し、すべての王子が陣営から出てピンブと戦いました。張飛は槍を持って出てきました。張飛と呂布は20ラウンド戦いましたが、勝者はいませんでした。関公は激怒し、馬に乗って剣を振り回し、2人の将軍は呂布と戦いました。最初の君主はそれに耐えられず、両刃の剣を使い、3頭の馬で呂布と戦いました。呂布は敗北し、北西の虎牢関に逃げました。」 実は、関羽が剣で戦ったかどうかはずっと疑問だった。『三国志』には「曹公は張遼と関羽を先鋒として派遣した。関羽は梁の旗を見て馬に乗り、群衆の中で梁を刺し、梁の首を切って戻った」とある。陳寿の「刺す」という言葉には多くの疑問があった。剣なら「切る」か「切る」かのどちらかであるべきだ。 漢王朝末期には、馬に乗って剣を持って戦う者もいたが、彼らは皆、短い武器である輪柄の剣を使用していた。戦場での戦闘において、切り刻むことに特化した、一枚の刃と厚い背を持つ短い武器である「輪柄刀」は、構造上大きな利点を持っています。三国時代、各国の軍隊は大量の輪柄の剣を生産し、鋼を揚げる、鋼を百回精錬する、焼き入れするなどの漢代の製鋼技術を採用しました。 『太平天国溥儀伝』には、三国時代の諸葛亮がかつて「溥元」という男に刀を作るよう命じたことが記されている。溥元は謝谷でその仕事を始めた。良い刀を作るために、彼は特に蜀江の水を使って刀身を焼くように指定した。彼が作った3000本の刀は非常に質が良く、「魔剣」と呼ばれた。南朝梁の陶洪景は『刀剣記』の中で、黄武5年(226年)に孫権が剣10本、刀1万本を作ったと記している。当時、刀は娯楽用の武器となり、刀は兵士が実戦で使用する武器であったため、作られた刀の数は数万本に上ったことがわかる。関羽が剣を使うなら、このような短い武器であるはずです。 では、なぜ後世の人々は関羽に緑龍三日月刀を装備させなければならなかったのでしょうか?北京大学の博士である楊子然氏は次のように語っています。「清朝時代、関羽は死後26文字の称号を授けられました。そのため、大武聖者は自分にふさわしい武器を持つべきだと一般大衆は信じていました。緑龍三日月刀の形状が非常に威圧的に見えるため、いくつかの歴史的伝説と相まって、有名人にとってはその効果がより顕著になる可能性があるため、清朝から関羽がこの緑龍三日月刀を装備することが習慣になったと思います。」このように、後世の人々が意図的に時空を超越する緑龍三日月刀を関公に装備させたのは、関公の強大なイメージを形作るためでした。武聖と称えられた関公のイメージは、後世の人々の目には確かに「高く、偉大で、完全」であり、人々が関公への敬意を表すために「緑龍三日月刀」という言葉を思いついたのも理解に難くない。 |
>>: 劉備が諸葛亮を三度訪ねたという話は本当でしょうか、それとも嘘でしょうか?
推薦する
「野蛮人の家を訪ねての感想」の著者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
陸游の『野人の家を通る時の考え』の注釈付き翻訳と解説【オリジナル詩】「野人の家を通り過ぎて思うこと」...
朱元璋は皇城を巡視した後に朝廷に赴いた際、なぜ多くの大臣を処刑したのでしょうか?
朱元璋は貧しい家庭に育ち、やがて乞食となり、最終的に僧侶になった。しかし、彼は自らの努力で軍内で着実...
中国の暴動は一体何なのでしょう?全国的な暴動は何年に起こりましたか?
成王と康王の治世中、周王朝の政治情勢は比較的安定していた。その後、奴隷を所有する貴族が搾取を強め、戦...
曹髙が死んだ後何が起こったのですか?曹髙の死後何が起こったのですか?
曹髙の死後、司馬昭は宮殿に入り、大臣全員を召集してこの件について協議した。左大臣の陳泰が来なかったの...
『紅楼夢』で、林黛玉が北京に行って賈邸に住むように手配したのは誰ですか?
林黛玉は『金陵十二美女』本編に登場する二人の名のうちの一人であり、西霊河仙草の生まれ変わりである。容...
「酔って落胆して:鷲への頌歌」をどう理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
酔って意気消沈:鷲への頌歌陳衛松(清朝)寒山がいくつもあり、弱い風が中原への道を遮っています。秋の空...
苗華山祭は別名何と呼ばれていますか?苗華山祭の簡単な歴史
華山祭は彩花山としても知られています。これは四川省南部に住むミャオ族にとっての壮大なショーです。花山...
清朝の郡知事はどれほどの権力を持っていましたか?清朝において県知事になるための要件は何ですか?
清朝の県知事について本当に理解していますか?Interesting Historyの編集者が詳細な関...
王維の古詩「玉壺の氷のように澄んだ」の本来の意味を理解する
古代の詩「翡翠の壺の中の氷のように澄んでいる」時代: 唐代著者 王維玉壺は何の役に立つのでしょうか?...
『三朝北孟慧編』第98巻の主な内容は何ですか?
景康時代、巻七十三。石茂良は戦を避け(兵士に改め)、夜に話した。金人が再び侵攻した(到着に改め)。閏...
『太平広記』巻182にある「公居呉」の原文は何ですか?
崔立、陸昭、丁玲、顧飛雄、李徳宇、張福、玄宗、陸沃、劉推、苗太夫、張度、徐道民、崔銀夢、燕宇、温廷雲...
四聖心の源泉:第1巻:天と人 解説:異例の経典の全文
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
中秋節はいつ始まったのでしょうか?どのような習慣や習慣がありますか?
中秋節はいつ始まったのでしょうか?次は、Interesting Historyの編集者が歴史の真実に...
古代と現代の不思議 第29巻: 内心恨んでいる召使いが主人に報告する(前編)
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
戦国時代の楚の詩人、屈原の『九歌・邵思明』の内容を鑑賞する
「九歌・邵思明」は、屈原作曲の組曲「九歌」の中の一曲です。「九歌・大思明」の姉妹曲で、楚の人々が邵思...