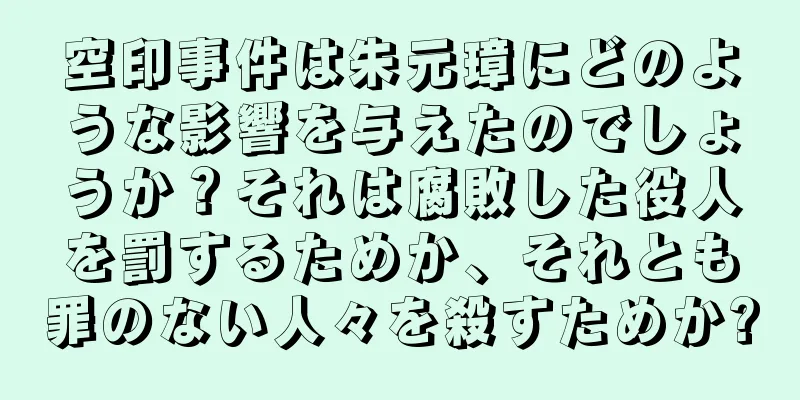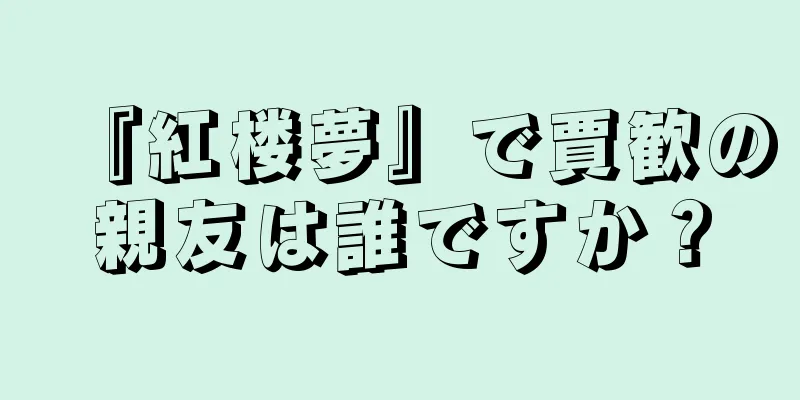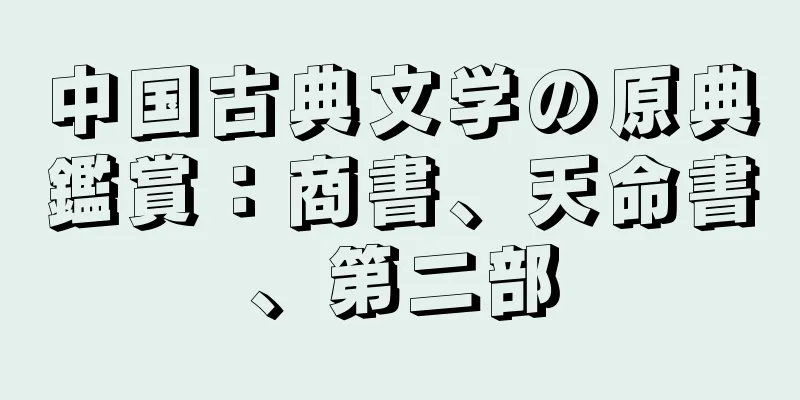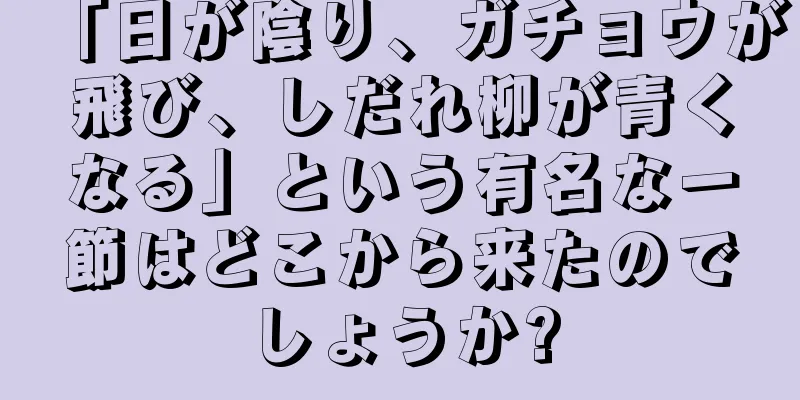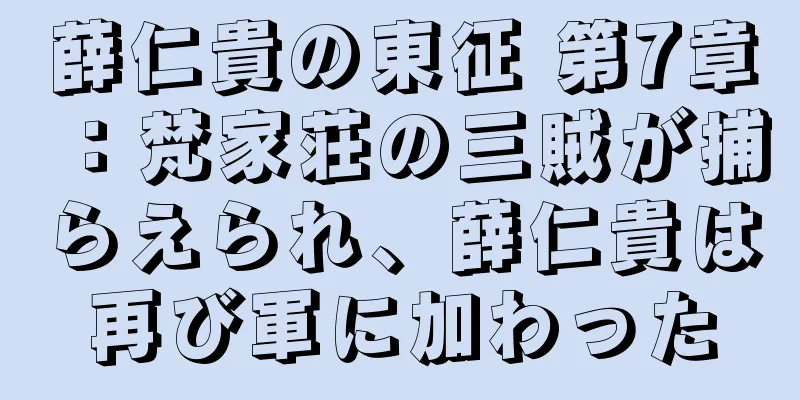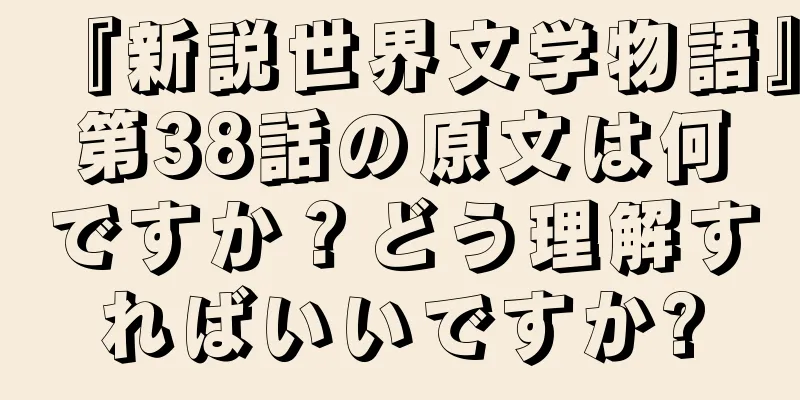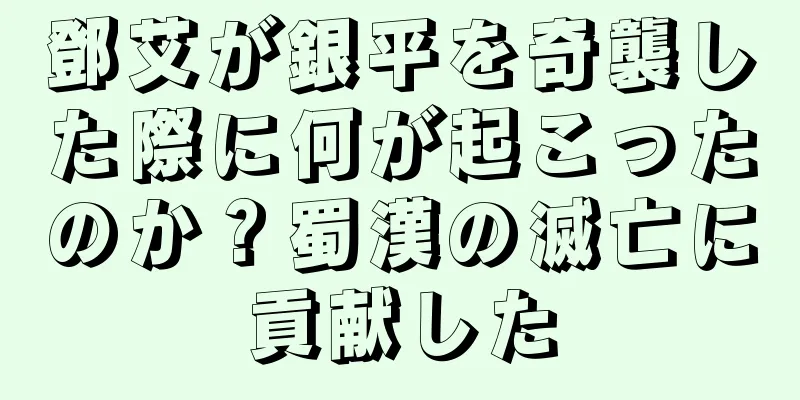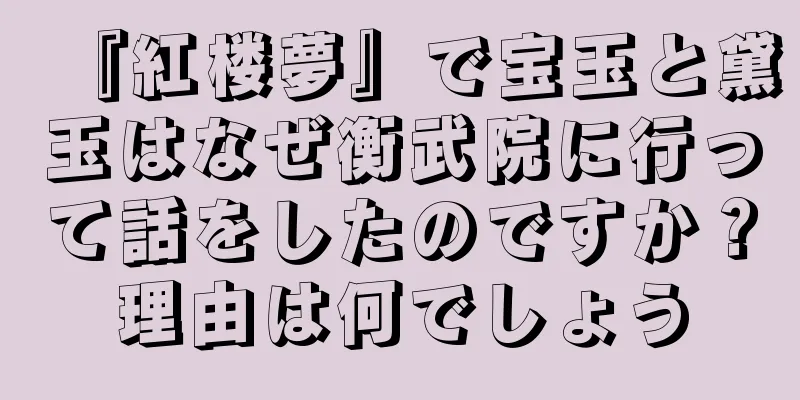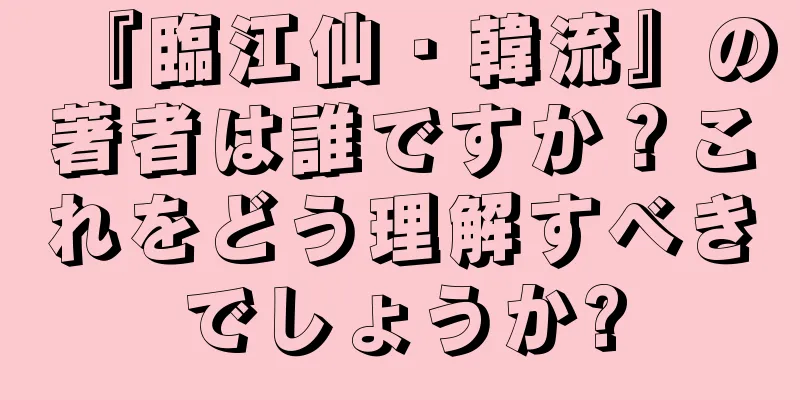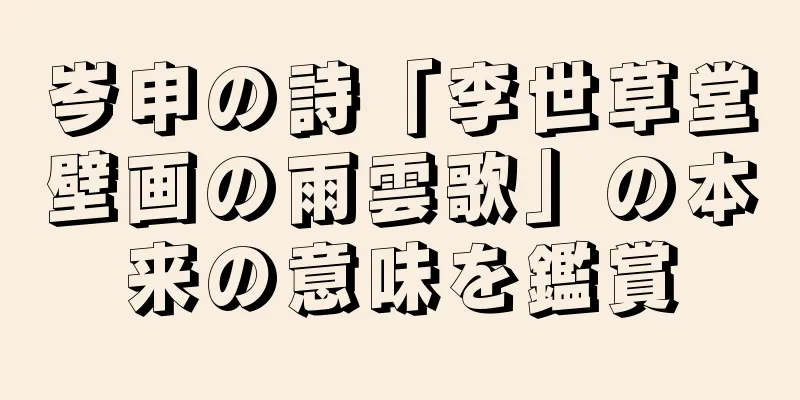明治維新が成功した理由 明治維新はなぜ成功したのでしょうか?
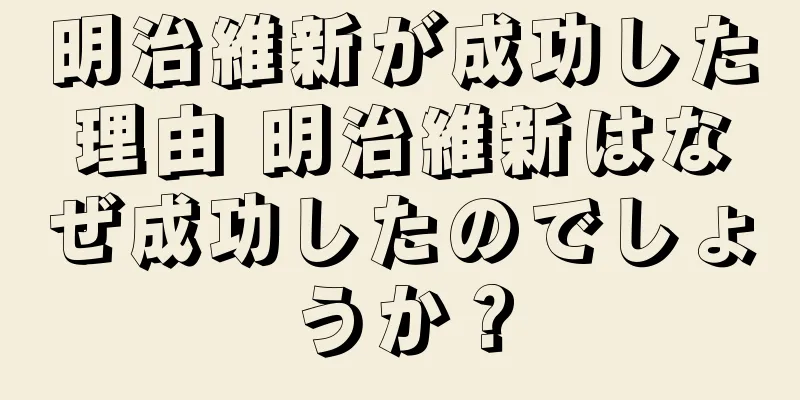
|
明治維新は、19世紀中期から後半にかけて日本のブルジョアジーによって開始された大規模な近代化運動でした。それは日本が封建社会から資本主義社会へと移行する上での大きな歴史的転換点であった。260年以上続いた幕府の封建社会を終わらせ、資本主義発展の道を歩み始め、国家の独立を守り(「日本は完全な独立を持つ唯一の国である」)、アジアで初めて欧米列強に追いつく国となり、東洋のまばゆいばかりの「彗星」となった。明治維新の成功は「世界の奇跡」として称賛された。 明治維新と文明開化運動は、二つの近いアジアの国の間の近代化をめぐる真の競争でした。結果は誰もがよく知っていますが、その理由についてはさまざまな意見があります。 伊藤博文率いる日本の志士たちは世界に目を向け、憲法制度の確立が明治維新の成功の鍵であると信じていたが、中国ではその逆であったというのが一般的な見解である。梁啓超はまた著書『李鴻章伝』の中で、李は「国家の原理を理解せず、世界情勢を理解しず、政治体制の起源を知らない」と述べた。 では、日本の成功の秘訣は何でしょうか? 1. 外部要因: 1. 良好な国際環境。当時、中国とアジア諸国の反封建、反植民地の闘争が盛んに行われ、西洋植民地主義者の日本への侵略と干渉は抑制され、弱体化していた。米国は国内で南北戦争に忙しく、ドイツとイタリアは統一の絶頂期にあり、ロシアも農奴制改革を進めていた。同時に、彼らは日本の政策に対して独自の思惑を持っており、合意に達することができなかった。また、西洋列強と日本の封建勢力との癒着はまだ深くなかった。これらすべてが、明治維新のための穏やかな環境を作り出しました。 2. 西洋の科学、技術、文化の影響により改革のペースが加速した。幕末の頃から、日本西南部は長崎港を通じてオランダとの貿易関係を維持していた。オランダ人の流入を通じて、一部の知識人は西洋の技術を学び、世界の政治情勢を理解し、西洋のブルジョアジーの政治・経済思想を研究し、オランダの制度を模倣して日本に社会改革を実施すべきという政治提言を行った。これら蘭学者の改革提言は、その後の明治維新運動に大きな影響を与えた。 2. 内部要因: 1. 特殊な地理的環境と日本独自の文化(外国文化を受け入れやすい国民性) 海によって隔絶されていることが日本に及ぼす最も重要な影響の一つは、島嶼文化に特有の孤独感です。島国はどこも孤独感を抱えていますが、ヨーロッパの中でイギリスも例外ではありません。しかし、イギリスは古くから大陸ヨーロッパと密接な関係を保っており、大陸諸国からも認められているため、孤独感ははるかに弱いのです。しかし、「日本は、英国がヨーロッパ大陸から隔絶されている以上に、アジア大陸から隔絶されている」ため、孤独感はさらに深刻である。 海に隔絶され孤独を感じる日本人は、内向的な心理的特性を持つだけでなく、「外部からの刺激に非常に敏感」でもある。 (一方、中国は国土が広く人口も多く、自然条件も場所によって大きく異なります。海岸や河川沿いの一部を除き、その他の地域では交通が不便です。そのため、列強が侵略戦争を仕掛けたり、首都を占領したりしても、各省の内陸部は依然として非常に安全で、敵に対する団結意識が高まることはめったにありません。地理的障壁により、中国全体の発展は、経済、政治、文化のいずれの面でも極めて不均衡です。両国を比較すると、中国で全国的な自強運動を展開する上で遭遇する困難は、日本で同じ運動を推進するよりもはるかに困難であることは明らかです。)島国である日本は、海の向こうのあらゆるものに対して常に強い好奇心と新鮮さを感じています。この時代の日本人は、古来より冒険心や探究心を持ち、孤立や孤独を打破したいという願望と、長い間孤立し閉ざされてきたため外に目を向ける傾向を持っていました。 島国の相対的な小ささ、自然の限界(災害に見舞われやすい自然環境)、文化史の移ろいやすさと外向性は、日本人の心に深い衝撃を与え、日本国家に影響を与えてきました。日本人の国民精神は、何よりもまず、自然の力に対して無力であるという宿命論、そして幻滅感、憂鬱感、危機感に満ちている。しかし、抑圧感と危機感は、強い自己認識と自己規制能力、そして日本国家の変化に適応することを選択する能力を育み、幻滅感と孤独感は、現実に焦点を当て、今この瞬間の人生を楽しみたいという願望、そして視野を広げようとする願望と努力を育んできた。つまり、日本人は運命の存在を認めながらも、それに抗おうと全力を尽くしているのです。 日本は海に感謝すべきである。なぜなら、日本に近代化の機会を与えたのは海だからである(海は日本を中国の華夷秩序から完全に独立させた。歴史的に中国は東アジア全域とその周辺地域にまで及ぶ天帝国祭祀統治システムの構築に成功したが、日本はそれに完全に組み込まれることはなかった。最も重要な要因は近代以前の海洋の巨大な障壁機能であり、それが中国の力を日本に投影することを妨げていた)。中国と日本の間に海の障壁がなかったと仮定すると、日本は華夷体制と封建的な朝貢制度から逃れることはできないだろう。日本独自の近代化への成功の道は存在しなかっただろう。 日本の文化について: 日本は伝統をあまり重視していません。日本は歴史を通じて常に文化を輸入し、他の文化を模倣する長い伝統を持つ国でした。 「大化の改新」の頃、日本は中国から文字、制度、宗教、礼儀作法、商工業の技術などを大量に輸入しました。近代に入ると中国から西洋に目を向け、あらゆる面で有利な立場にあった西洋諸国から学ぶのは当然のことでした。日本の文化的「劣等感」と中国の文化的「優越感」は対照的である。 (中国文化をもう一度見てみましょう。中国文化は負担が大きすぎます。中国文化はそれ自体が完璧なシステムであるため、数千年にわたって東アジア文明の唯一の中心でした。その長い歴史により、わが国は過去の伝統の重い負担を負っており、非常に短い期間で急速に方向転換し、新しい近代ヨーロッパ環境にスムーズに適応することは困難です。儒教は常に中国文化の正統派であり、厳格な構造と高い芸術的概念を備えています。そのため、長い発展の過程で、中国文化は自尊心と傲慢さの根深い優越感を形成し、自国の文化システムの欠陥を発見したり警戒したりすることは容易ではありません。さらに、数千年の間、わが国は常に文化輸出国の立場にあり、現代の西洋文化がいくつかの側面または全体として優れているという事実を認めることは容易ではありません。) 2. 蘭学運動の啓蒙的役割 社会の変化や革命の前に、西ヨーロッパ諸国では思想的解放運動(ルネサンス、宗教改革、啓蒙主義など)が起こりました。日本も同様です。明治維新以前には、蘭学運動という思想解放運動もありました。 蘭学とは、日本人がオランダ人との貿易や交流を通じて、オランダの書籍や百科事典から苦労して発掘した西洋近代科学の知識や学問のことです。医学、軍事、冶金、地理、天文学などの分野をカバーしています。蘭学は16世紀に西洋文明との接触から始まり、19世紀後半に徐々に頂点に達しました。蘭学の発展は明治維新の確固たる思想的基礎を築き、それはまず日本人の地理観と世界観の変化として現れた。この変化により、日本は当時の国際秩序や慣例に従って冷静に外交問題に対処できるようになりました。第二に、日本の文化的価値観の変容です。日本人は伝統的な東洋文化と近代西洋文化の違いに気づき始め、価値観は西洋化と近代化へと移り始めました。それは医学の変化に最も顕著に反映されました。最終的には、「日本精神と西洋の才能」が「日本精神と中国の才能」に取って代わり、この考えが徐々に普及しました。第三に、統一された国民・国家意識の覚醒。西洋の影響と、西洋の学問に基づく啓蒙運動によって、大英帝国のような国家体制を確立したいという日本人の願望はますます強くなり、多くの武士や知識人がそのためにすべてを捧げるほどでした。これは同時期の中国の文人とは比較になりません。 3. 武士階級の役割 明治維新の指導者たちは、ブルジョア階級化した下級武士、つまり現在「志士」と呼ばれている人々でした。「志士」は、大きな野心を持った熱狂的な過激な国家主義者および政治活動家であり、ブルジョア階級の思想を、あるいは部分的に受け入れていました。彼らは主に下級武士や武士階級の知識人から選ばれました。彼らは忠誠心、勤勉さ、勇気、名誉といった伝統的な武士の価値観を持ち、同時に西洋の学問と近代西洋文明の直接的または間接的な影響を受けて、すでにある種の近代西洋思想の芽を育て上げている。彼らは変革のアイデアを推進し、改革勢力を育成した。中でも最も有名なのは、中国学と西洋学の両方に精通していた吉田松陰とその師匠の佐久間象山です。彼らの生徒には、明治時代の指導者である伊藤博文や山県有朋、明治維新の三大立者の一人である木戸孝允、長州藩の過激派指導者である高杉晋作や久坂玄瑞などがいた。彼らは明治維新とその後の日本の歴史において重要な役割を果たしました。 「愛国者」たちは近代西洋列強のビジョンを持ち、日本を世界大国にするという野望を抱いていた。さらに重要なことは、彼らは近代西洋の先進的な兵器とシステムを備えた軍隊を編成していたことだ。 明治維新が成功した理由の一つは、幕末に文学と武術の才能に恵まれ、国家主義と愛国心、そして世界的なビジョンと近代的な政治思想を兼ね備えた一群の志士たちが日本に現れたことであった。 (想像してみてください、「明治維新の三英傑」がいなかったら、近代日本はどうなっていたでしょうか?) 4. 日本社会システムの独特な枠組み構造 幕藩体制は土地制度に対応しており、日本の大名に徳川幕府からの半独立の伝統を与え、長州藩や薩摩藩などの藩は幕府の意に反して西洋から科学、文化、軍事技術を学び、幕府に対抗する拠点となった。 中国は完全に発達した封建制度を持つ国であり、社会の内部構造は比較的安定しており、社会の矛盾を規制する強力なメカニズムを備えています。日本はそうではありません。中国と比べると、日本の封建制度の発達は明らかに不十分です。封建国家であった日本においては、幕府に対抗する封建国家の存在が「志士たちの拠り所」となり、それが倒幕運動や明治維新の勝利の重要な要因となった。 日本の明治維新が近代化への独自の道として成功したのは、内外の複雑な要因が複合的に作用した結果である。上記の4つの理由のほか、歴史的伝統、政治・経済構造、幕府の腐敗した統治、国民の役割、好ましい国際環境などもある。 (追加質問)ここで言う明治維新の成功とは、日本を豊かで強い国にしたということである。明治維新によって日本が強くなったことは疑いの余地がない。しかし、成功が近代化変革、つまり日本を近代社会に変え、経済的には成熟した市場経済を、政治的には民主主義政治を確立することを指すのであれば、この点で明治維新は明らかに失敗したと言える。明治維新後、比較的民主的な時代が数年あったものの、いわゆる大政奉還、つまり昭和時代以前から明治時代以降の時代は、日本社会にとって最も開放的で啓蒙的な時代であった。しかし、その時代はあっという間に過ぎ去り、日本はやがて独裁主義、ファシズム、軍国主義となり、ついには軍事独裁とファシズム軍国主義の道を歩んでいった。したがって、成功や失敗は相対的なもの、つまりさまざまな側面からの分析の結果にすぎません。しかし、我々は次のことを確信しなければなりません。改革が国を繁栄に導くことができる限り、それは成功した改革なのです。 |
<<: 日本の明治維新の意義と影響は何でしょうか?明治維新を客観的に評価するにはどうすればよいでしょうか?
>>: 明治維新の三英雄は誰ですか?明治維新の三偉人について簡単に紹介
推薦する
慕容衛の発音は?慕容衛の生涯の簡単な紹介。慕容衛はどのようにして亡くなったのか?
慕容惟(350年 - 384年)、号は景茂、鮮卑族の一人。昌黎郡吉城(現在の遼寧省宜県)の人。前燕の...
なぜ夏侯淵は徐晃と張郃を指揮できたのでしょうか?彼と曹操はどのような関係にあるのでしょうか?
張魯が曹操に降伏した後、曹操は将軍の夏侯淵を城の守備に残した。夏侯淵は徐晃を使って陳式を倒し、張郃を...
史公の事件第244章:李坤の家に泊まって悪魔を鎮圧したため、謝宝は復讐のために暗殺された
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
張安石の父親は誰ですか?張安石の父親、張唐の紹介
張安石(?-紀元前62年)、法名は子如、荊昭都陵(現在の陝西省西安市)の出身で、前漢の大臣であった。...
秦の始皇帝が鋳造した12人の青銅の男はどこへ行ったのでしょうか?
秦の始皇帝は最初の封建王朝の政権を強化するために、元の政治制度を基礎として統一された中央集権的な封建...
『紅楼夢』の花祭りはどんな感じでしょうか?グランドビューガーデンでフラワーフェスティバルを祝いました
現代の女性には独自の祭りがあります。3月8日の女性の日です。古代の女性にも独自の祭りがありました。花...
唐代の食文化はどのようなものだったのでしょうか?主食は何ですか?
唐代の食文化に非常に興味がある方のために、Interesting Historyの編集者が詳しい記事...
歴史上、富春山の本当の住居とは何ですか?
富春山居:富春山居は、描かれた瞬間から伝説となる運命にあった。なぜなら、70歳になるまで画家になろう...
水滸伝における張順のイメージとは?彼にはどんな物語があるのでしょうか?
張順は108人の英雄の一人で、30位にランクされ、「波中の白鮫」として知られています。では、「波中の...
戦場で死ぬことは軍の将軍にとって最高の行き先だが、なぜ張飛は部下によって殺されたのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
康熙帝の第15王女である和碩曇可公主の実の母親は誰ですか?
康熙帝の第15王女である和碩曇可公主の実の母親は誰ですか?十五公主は康熙帝の15番目の娘で、公主の中...
古典文学の傑作『太平天国』:官部編第12巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
万暦朝における国家建国をめぐる争いとは何でしたか?三十年戦争は明朝に大きな損害をもたらした!
今日は、Interesting Historyの編集者が、万暦朝の建国をめぐる論争についての記事をお...
宋宇の『風風』の芸術的特徴は何ですか?どう理解すればいいですか?
宋渭の『風賦』の芸術的特徴は何か知りたいですか? どのように理解しますか? 『風賦』は、賦文学の初期...
『漢寿城春景』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
漢首城の春の風景劉玉熙(唐代)春には漢首城のそばに野草が生い茂り、廃墟となった神社や古墳にはイバラや...