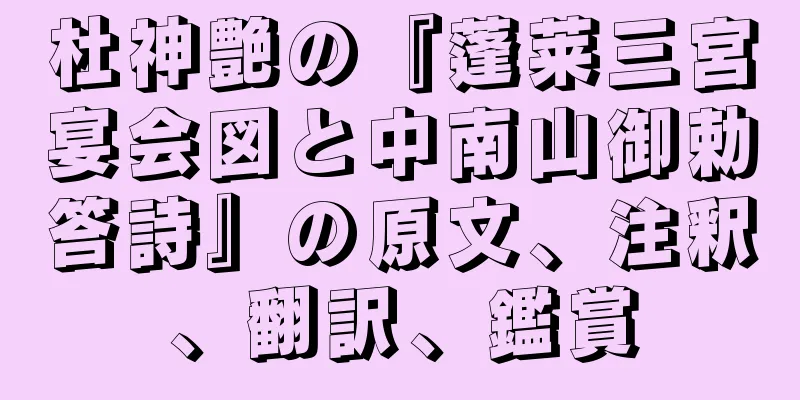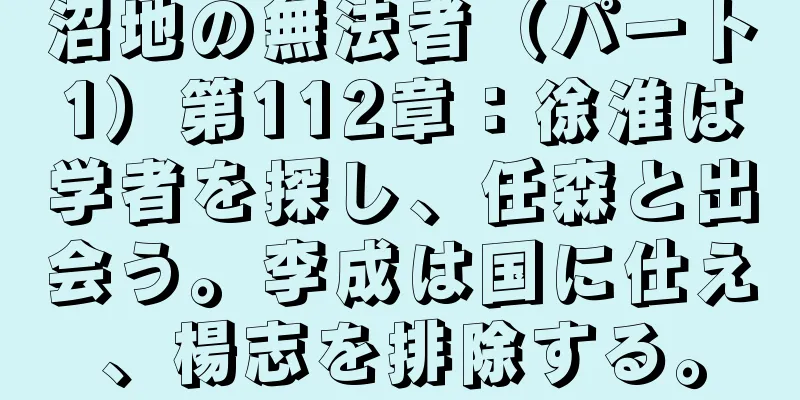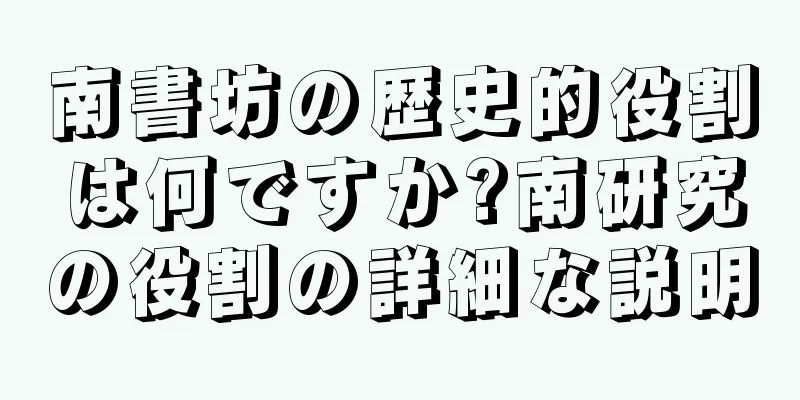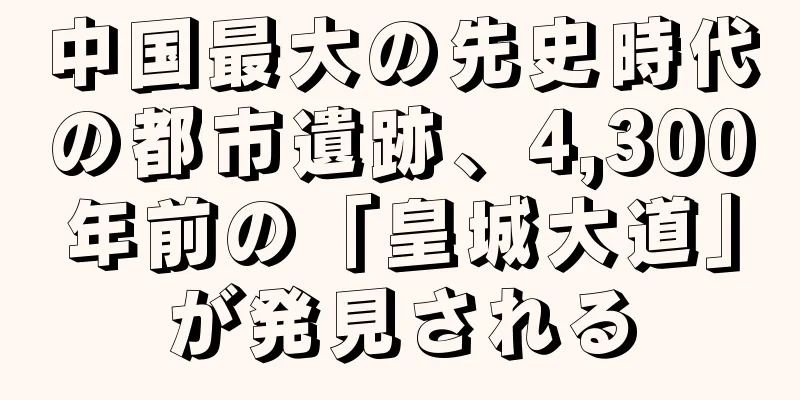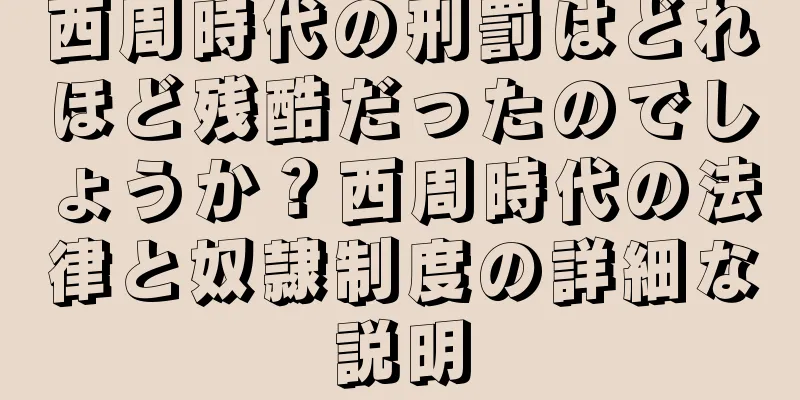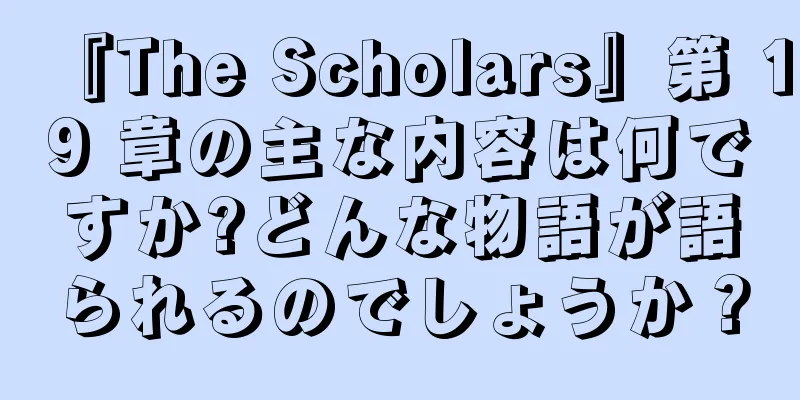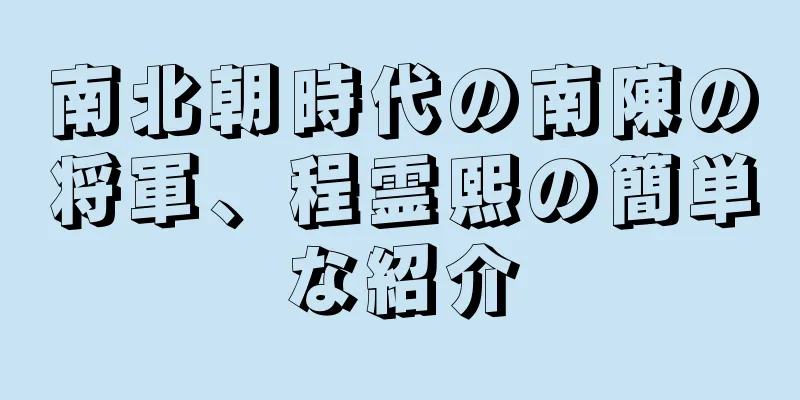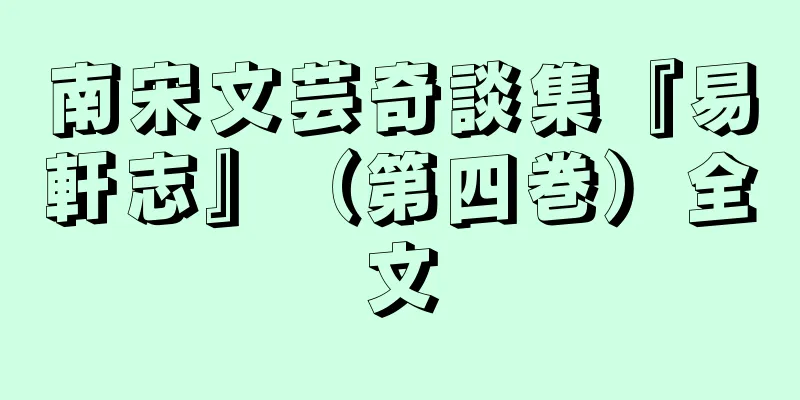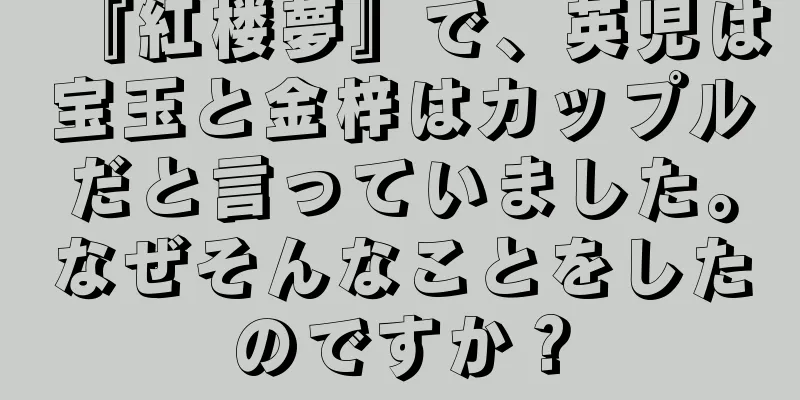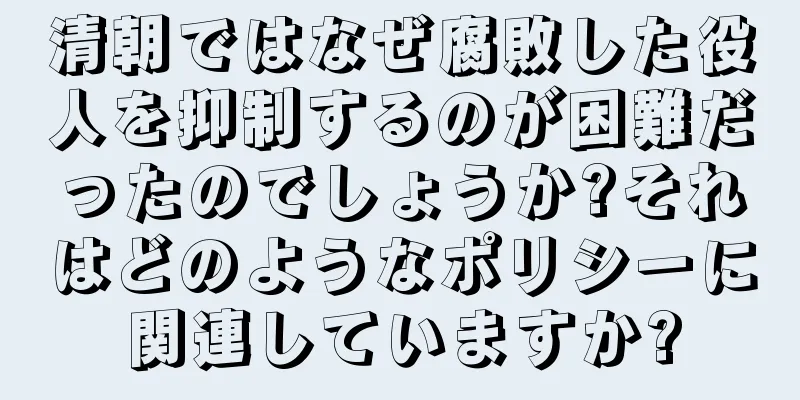明治維新の先駆者、高杉晋作の簡単な紹介 高杉晋作はどのようにして亡くなったのでしょうか?
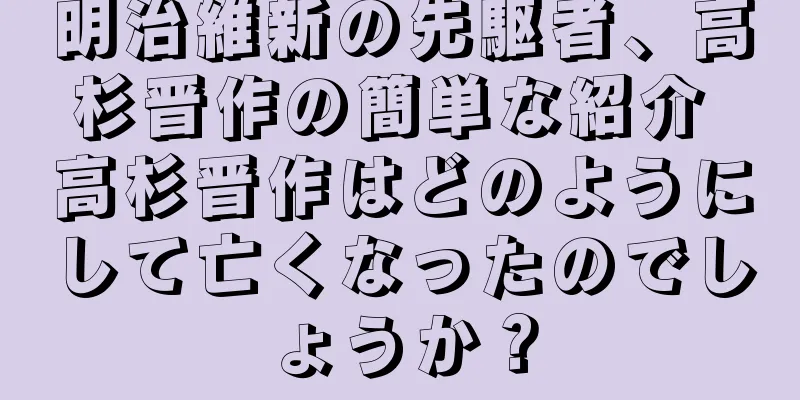
|
高杉晋作は、江戸時代後期の有名な政治家、軍事戦略家でした。長州尊皇派の指導者の一人であり、奇兵隊の創設者でもあります。幕末の尊皇攘夷運動や討幕運動に参加した志士。 高杉晋作は長州藩出身の日本の武士でした。幕末の長州藩で尊王攘夷の活動家として活躍した。また、奇兵隊などの様々な部隊を創設し、幕末の長州藩の討幕運動にも貢献した。禁忌名は春風、通称は金工。東夷、和珠、莫生、雅号は長福、東興、西海益圓生、東陽益圓生とも呼ばれる。別名は谷仙蔵、谷梅之助、備後屋助一郎、三谷一助、蕗武太郎、宍戸桂馬、西浦松助など。後に顧千蔵と改名された。正四位贈位(1891年(明治24年)4月8日) バイオグラフィー 少年時代 高杉晋作は、天保10年8月20日(1839年9月17日)、長門国安芸城下菊谷横町(現在の山口県萩市)に、長州藩士高杉春樹(高杉小忠太)の長男として生まれました。高杉家康は200石の高官であった。 10歳の時にヘルペスにかかりました。初めは中国の塾で学び、1852年に藩校明倫館に入学して剣術を学んだ。 さらに詳しく 安政4年(1857年)、松渓村塾の吉田松陰に入門し、久坂玄瑞とともに松門の二本柱と称された。吉田実を松門三傑に加え、鄭九易とともに松門四天王の一人となった。後に明倫館主となり、藩主子弟の侍役を務め、藩政に参画した。吉田松陰の粘り強い探究心、幕府の腐敗政治への猛烈な攻撃、知識の実践への応用の提唱、教育の平等の理念は、晋作のその後の発展に大きな影響を与えました。吉田松陰の紹介により、晋作は佐久間象山と親交を深めました。 1859年、安政の大獄で吉田松陰が亡くなり、幕府の政治に対する憎悪がさらに深まりました。安政の大獄後。 1858年、甚作はさらなる学問の勉強のため江戸幕府の学校である昌平荘に入学した。長州藩士益田弾正に宛てた書簡では、「富国強兵の理念は『富国の基礎は倹約にある』」「富国の極みは国産にある」「強兵の極みは民心の統一にある」「強兵の極みは両国の民に洋式技術を習得させるにある」と富国強兵の理念を説いた。 1860年、晋作は山口町奉行井上平右衛門の次女・正子と結婚し、航海術を学ぶため軍艦教授職に就いた。彼は東北に留学し、相沢靖、加藤亜林、佐久間象山、横井小楠らと出会った。旅の途中で視野を広げ、特に佐久間象山の幕府批判と開国論に感銘を受け、横井小楠の開国・富国強兵の思想を吸収した。彼は古い学問(儒教や漢学)を批判し、実学を主張し、積極的に外国の学問を研究・普及し、西洋のブルジョア文明を学ぶ道を歩み始めた。晋作は東北留学から帰国後、明倫館の学務官を務めた。 1861年、公は彼を江戸藩邸の侍従に昇進させた。 高杉晋作 中国ニュース 1861年、藩主は晋作に海外視察を許可し、翌年、晋作は中国に派遣された。 2月、幕府が貿易のため千歳丸を上海に派遣した際、薩摩の五代友厚、佐賀の中室内蔵助らとともに同乗した。船が長崎を通過したとき、彼は「長崎貿易戦略」を検討し、「アメリカ、フランス、イギリスの蛮族と対話できれば大きな利益があるだろう」と考えた。太平天国革命が最高潮に達した6月初旬、「千歳丸」は上海に到着した。甚作は上海に滞在した二ヶ月間、あらゆる手段を講じて中国の状況を観察する。太平天国について彼が収集した情報には、太平天国軍が信頼でき、誠実であるとも記されていたが、江南各地から戦争を逃れて上海に逃れてきた地主、貴族、地方官僚らと接触する機会が増え、彼らから太平天国軍に対する中傷を聞き、太平天国軍に対する嫌悪感を抱くようになった。例えば、中国人のヤン・ジュは晋作にこう語った。「私は昨年の冬、太平天国の賊から逃れるためにここに来ました。今年3月、私の家は焼け落ち、家にあった本や碑文はすべて持ち去られました。言葉にできないほどの悲劇でした。」高杉晋作は「これを聞くと涙が出てきます」と言った。高杉晋作の目には、中国の姿は消えていた。天津港には外国商船が行き来し、通りには外国商館が立ち並んでいた。 滞在中、五代有朋は晋作に「太平天国軍は超人的な勇気を持っていたが、少数の英仏軍の前に大敗した。これからは新しい大砲と軍艦の時代だ」と言った。晋作もそれに同意し、有朋を新しい大砲を見に行くよう誘った。彼は、清朝が衰退した理由は、外洋における外国の侵略者に対する防衛方法を知らなかったためだと信じていた。つまり、数千マイルの波を越えられる軍艦を造らず、数十マイル離れた敵から身を守ることができる大砲も造らず、その国の愛国者によって翻訳された『海国図鑑』を絶版にしてしまったのです。 富国強兵から清朝打倒への転換 長崎に戻ると、晋作は藩の名義で軍艦を購入する契約をオランダ商人と急遽結んだが、藩に拒否されただけでなく、一時は物笑いの種となった。 9月、京都で公武と泰の仲介をしていた藩主に中国の情勢を説明し、その後江戸に出て清学院の院長に就任した。高杉晋作は、全国に広がった排外運動に参加し、朝廷と軍部との調停をやめさせ、毘荘・長宿両藩の富国強兵、すなわち分離独立を成し遂げることを目指した。文久3年(1863年)1月、晋作は神奈川の下田屋で久坂玄瑞ら11名と血盟を結び、外国人の暗殺を計画した。 1月31日、彼は自ら13人を率いて、江戸市品川区御殿山に建設中だったイギリス大使館を焼き払った。高杉晋作にとって、使節団襲撃は形式的には攘夷行為であったが、その目的は分離独立政権の樹立を求めることであった。幕府の許可を得た後、西行師の故事を倣い、東行と名乗り、剃髪して萩に隠棲した。 状況の変化により、金左は長い間隠遁生活を送ることはできなかった。 1863年、長州藩などの殖民派の推進により、孝明天皇は攘夷の大赦を発令し、将軍は朝廷に対し「攘夷の件は6月25日(旧暦5月10日)に定める」と確約せざるを得なくなった。6月25日、長州藩は真っ先に攘夷の火を点けた。久坂玄瑞率いる光明寺を拠点とする尊王攘夷派のいわゆる光明寺党は、下関海峡を通って長崎に向かっていたアメリカの商船ペンブローク号に砲撃を加えた。 7月8日にはフランスの通信船「建昌」が砲撃され、11日にはオランダの軍艦「メディッサ」が砲撃された。 16日、米軍艦「ワイオミング」は長州藩の砲兵と軍艦に猛烈な報復攻撃を開始し、長州軍艦3隻を沈没させ、下関海峡を封鎖した。沿岸の士族や一部の民間人は山中に避難し、海峡一帯は無人となった。フランス東洋艦隊も、旗艦「セミラミス」と「タンクレード」を派遣して反撃し、21日には下関と長門の間にある前田砦の前に到着して攻撃を開始した。約250名の海兵が上陸し、前田砦、ダヌラ砦などの砦を占拠し、道中の村々を焼き払った。長州藩の志士たちは粘り強く抵抗したが、兵力の差が大きく、列強の強力な艦船や砲火の前に大きな損害を受けた。 長州藩は危うい状況にあり、侵略される寸前だった。 軍改革と「各種チーム」の設立 1863年7月18日、長州藩は高杉晋作を任じて下関の防衛を命じた。 19日、高杉晋作は特別部隊を組織した。奇兵隊の名は、藩の正規軍とは対照的な非正規軍という意味である。甚作の政策は強力な軍隊を組織することだった。彼は、上流階級の武士は役立たずで、上等な衣服や美味しい食べ物にしか関心がなく、体力も知力もないと信じていました。そのため、特殊部隊を組織する際には、身分を問わず人材を募集し、参加を希望する一般の農民、商人、職人を募集したが、主に藩内の最下級の武士を募集した。 1864年の特別部隊の隊員559人の身元から判断すると、48.7%が武士、42.3%が農民、4.5%が商人や一般市民、4.5%が僧侶や修道士であった。奇兵隊の制服、武器、訓練はすべて西欧諸国のものをモデルにしており、日本初の近代的な軍隊であった。奇兵隊は結成後、直ちに幕府の「内は専制、外は妥協」の統治に対して攻撃を仕掛けた。当時24歳だった高杉晋作は自ら奇兵隊の総督を務めたが、10月に辞任した。特殊部隊は急速に成長し、1840年までに4,000人以上の隊員を擁し、多くの裕福な農民や商人の支援を得ました。奇兵隊の出現は日本の新しい軍隊の歴史の幕開けとなり、学者と庶民が混在する数多くの民衆武装勢力の出現を促した。最終的に高杉晋作は指揮と訓練を統一し、総称して「諸隊」と呼んだ。この新しいタイプの軍隊は、徐々に幕府を倒し改革を進める運動において信頼できる軍隊となっていった。 高杉晋作の映画とテレビのイメージ 8月18日 ソンネンコ派によるクーデター 尊攘派は、孝明天皇が幕府に定期的に排外布告や大赦令を発布するよう命じたことで、幕府の勢力が強まり、幕府の不安定化を招いたことを知り、さらに大胆になった。尊攘派の指導者の一人である真木和泉は、天皇が大和に赴き、自ら率いて外国の侵略者に対する遠征を行うことを計画した。その時、随行する将軍に突然命令が下され、直ちに攘夷行動を取らされる。もし従わない場合は、各藩に蜂起して幕府を倒せという命令が下される。この頃、攘夷は幕府を倒す手段となっていた。孝明天皇は攘夷を主張しながらも、終始、熊渡政策を主張し、熊渡政策に尽力した薩摩藩や、宗主徳川家の危機を救おうとした会津藩に絶大な信頼を寄せていた。 7月5日、尊攘派公卿・青小路幸智の暗殺未遂事件が突如発生した。 14日、尊王攘夷派は薩摩藩士田中新兵衛を殺人犯として名指しし、薩摩守護稲荷門を解任するよう朝廷を説得した。しかし、天皇は青蓮院宮殿に手紙を書き、これは「偽りの命令」であると述べた。 8月9日、尊攘派の動きを監視していた京都守護職の松平慶保を追い出すため、朝廷を説得して慶保に関東の情勢を視察するよう命じる勅命を下させた。 13日、天皇は吉保に手紙を書き、これは「本当の勅ではない」と説明した。その後、会津藩と薩摩藩は軍事クーデターを計画し、青蓮院親王の支援を受けた。 9月25日(旧暦8月18日)、会津藩と薩摩藩が手を結び、御所の九つの門を守り、尊王攘夷派の武士や公家たちは長州藩へ逃れざるを得なくなった。これは歴史上「八月十八日の政変」として知られている。この頃、長州藩は尊王攘夷派が集まる拠点となっていた。 1864年までに長州の特殊部隊は4,000人以上にまで成長し、一定の力を獲得し、裕福な農民や商人の支持を得ていました。その結果、ソンニャン派は闘志に満ち溢れていたが、中には焦りを見せる者もいた。真木和泉と久坂玄瑞は京都における尊攘派のかつての権力を回復するために、軍を率いて都に入ろうとしていた。高杉晋作は、自分の力は十分ではなく、時期も熟していないので、力を蓄え続けて行動する適切な機会を待つべきだと考えました。そこで彼は真木和泉らを説得するために三田尻の軍事基地へ向かった。しかし、泉たちは自分の意見を主張し、甚作を卑怯者と嘲笑した。やがて、「池田屋事件」により真木和泉と久坂玄瑞が兵を率いて京都へ急行した。説得も効果がなく、晋作は藩主への出頭義務を放棄して京都へ逃亡し、後に脱走罪で萩獄に収監された。 禁じられた門 1864年7月、京都守護の指揮下にある新選組は、京都池田屋に集結した尊王攘夷派の地下組織を襲撃し、壊滅させた。この事件は奇兵隊を激怒させ、8月に真木和泉と久坂玄瑞の指揮の下、奇兵隊は京都に向けて進軍した。説得が失敗した高杉晋作は、藩主への出頭義務を放棄して京都へ逃亡したため、脱走罪で扇市監獄に投獄された。それは幸運なことであり、そのおかげで高杉は災難を免れたのである。 8月19日夜、真木和泉と久坂玄瑞は京都御所の萩御門を攻撃し、門を守る会津兵と激戦を繰り広げたが、思いがけず薩摩軍の側面からの奇襲を受け敗退。真木和泉や久坂玄瑞など尊王攘夷派の指導者の大半が戦死または自害した。これが「禁門の変」である。 攘夷から清朝の打倒まで 長州藩はイギリス、アメリカ、フランス、オランダの連合艦隊の報復攻撃を受けた。連合艦隊は、イギリス東洋艦隊司令官の久場提督が指揮を執り、288 門の大砲と 5,019 人の兵士を擁する 17 隻の軍艦と 3 隻の連絡船で構成されていました。 9月5日、艦隊は下関への攻撃を開始し、3日間砲撃してすべての砲台を破壊した。長州軍は粘り強く戦ったが、結局は戦力差で敗れた。 9日、長州藩主は高杉晋作を松島桂前義郎の号で和平使節として連合艦隊に派遣し、久場との間で攘夷を放棄する「下関条約」を締結させた。 8月24日、幕府は禁門の変で京都御所を襲撃した長州兵の責任を問うため、長州藩討伐の勅命を得て各藩に出兵を通達した。討伐軍は三大藩の一つ、尾張藩主徳川慶勝が率い、6藩から総勢15万人の軍勢が長州攻めに臨んだ。しかし、諸藩は財政難に陥っていたことや、幕府が三会交代を復活させたことに不満を抱いていたため、戦う意志はなく、軍の動きは鈍かった。薩摩藩士で遠征軍参謀長の西郷隆盛は、長州人を捕らえて長州過激派を処罰するという妥協案をこの問題の解決策として提案した。 12月9日、長州藩保守派は「服従降伏」の印として、排外派の老中3人を斬首した。第一次長征はこうして終わった。 内外からの攻撃を受け、長州藩は幕府に降伏、保守派が藩政を掌握し、諸隊の解散や尊攘派の処罰を命じ、長州藩内に形成された尊攘派に大打撃を与えた。甚作は迫害を逃れるため、谷梅之助という偽名を使い、自宅を抜け出して九州筑前藩の改革派婦人、野村基尼の平尾別邸に隠れた。困難で厳しい環境の中、長州藩の討幕勢力は解散するどころか、内部で結束し軍事訓練を強化し、幕府との最終決戦に備えた。 長州の討幕勢力が窮地に陥ったちょうどその時、筑前に亡命していた高杉晋作は武力で藩権を奪取し、最後まで幕府と戦う決意を固めていた。彼はこっそりと下関に戻り、蜂起を計画するために密かにさまざまなチームに連絡を取った。 1865年1月14日、晋作は下関の公山寺で挙兵した。彼は藩内の保守的かつ腐敗した役人たちの罪を列挙し、国民に国のために誠心誠意協力し、国を災難から救うよう呼びかけた。下関の蜂起は裕福な農民や商人から熱烈な支持を受け、「荘武同盟」を組織して農民蜂起を組織することを誓い、多額の資金と物資の援助を提供した。 1月28日、晋作は伊藤博文の力士団を動員し、下関伊崎倶楽部を急襲し、大量の軍資金と武器弾薬を押収した。 2月1日、甚作は『叛逆者を処罰せよ』を発布し、軍を率いて会堂で保守軍と決戦し、一挙に幕府を奪取した。 討幕派が政権を握ると、晋作は西洋の富国強兵の経験を学ぶために海外に渡航しようと計画したが、長崎のイギリス人武器商人グラブから、今は海外に渡航せず、長州藩がイギリスから大量の新型兵器を入手できるよう、留まって開港を主張すべきだと助言され、晋作もこれに同意した。高杉晋作は、国家の威厳を損なわずに下関港を開港してこそ富国強盛が築かれると指摘した。甚作らは「富国強兵」「商工業の振興」「開港」という近代化政策のもと、一連の政治・経済・軍事改革を実施した。藩や身分制度を廃止し、型破りな人材の選抜、軍制改革と軍備の近代化、港湾貿易の活発化と産業の育成などにより、長州藩はますます強固なものとなり、「倒幕」の拠点として発展していった。 1866年夏、幕府が発足させた第二次長州征伐の際、晋作は藩軍総司令官として軍艦「豊進丸」に乗り込み、砲火と銃弾の雨の中、自ら指揮を執り、大島、小倉の反撃に参加し、長州藩を完勝に導いた。 明治維新が始まろうとしていた1867年5月17日、高杉晋作は下関新地で結核のため亡くなり、奇兵隊の本拠地であった吉田に埋葬するよう言い残した。政治家としてのキャリアは短いが、華やかで、壮大で、浮き沈みの多いものである。幕末の諸勢力の再編の過程で、学問に励み、思索に長け、将来への備えを怠らず、機転が利いた人物であった。高杉晋作の生涯は短かったが、自らの輝かしい経歴を刻み、幕末の暗黒時代を彩った。 |
<<: 宗沢耶氏へのインタビュー:なぜ明治維新は文明開化運動よりも成功したのでしょうか?
>>: 維新前の三偉人の一人、吉田松陰の紹介 吉田松陰はいかにして亡くなったのか?
推薦する
水滸伝で、涼山で誕生日プレゼントを運ぶのに最も適した人物は誰ですか?
誕生日プレゼントを巧みに捉える場面は、『水滸伝』の名場面とも言える。 Interesting His...
春秋戦国時代の良き助言に従う物語
春秋時代、紀元前585年頃、鄭国は楚国に敗れ、晋国に救援を求めた。晋の将軍、阮叔は救援に出向くよう命...
涼山の英雄たちのリーダーとして、宋江はどのような人々を恐れていましたか?
宋代末期の統治者は無能であったため、多くの人々が様々な理由で涼山に集まり、山を占領して王となり、宋代...
清代の『白牡丹』第8章にはどんな物語が語られていますか?
劉金はお金を稼ぎ、妹の孟雄とともに蘇州へ皇帝に会いに行った。劉金は文貴の家族が山東省に逃げ帰ったこと...
『清平月:博山王寺独居』の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
清平楽·博山王寺に一人で泊まる新奇集(宋代)空腹のネズミがベッドの周りを回っており、コウモリがランプ...
「八月十五日の夜、張公曹に贈る」は、当時張公曹とともに検閲監督官を務めていた韓愈によって書かれた詩である。
韓愈(768年 - 824年12月25日)は、字を随之といい、河南省河陽(現在の河南省孟州市)の人で...
『西遊記』の黄色い眉の怪物の本当の持ち主は誰ですか?超大型背景
『西遊記』の黄色い眉毛の怪物の本当の所有者は誰ですか?彼はなぜあえて如来仏のふりをしたのですか?次の...
諸葛亮は曹魏に対して絶対的に不利であるとわかっていたにもかかわらず、なぜ依然として「好戦的」行動を続けたのでしょうか?
劉備の死後、諸葛亮は数年のうちに5回の北伐を遂行し、その後継者の姜維もこのルートを全面的に継承した。...
『環西沙:小楼の冷たさ』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
環西沙 - 冷たく荒涼とした小さな建物秦管(宋代)小さな建物の中は冷気も少なく、空気も冷たく、どんよ...
「天龍八百」の九寨子はテレビシリーズで誰も殺さなかった
テレビシリーズ「半神半魔」を見た視聴者は、テレビシリーズの九寨芝(李国林が演じる)が優れた武術のスキ...
魏英武の「秋夜秋氏宛書簡」:詩全体は強い言葉やフレーズで読者を惹きつけるものではない
魏英武(生没年不詳)、号は易博、荊昭県都陵(現在の陝西省西安市)の出身。魏蘇州、魏左司、魏江州として...
司馬光の「異国の初夏」:危険な言葉も美しい言葉もない、素朴な小詩
司馬光(1019年11月17日 - 1086年10月11日)、号は君子、号は幽素、山州夏県蘇水郷(現...
小説『剣士』の登場人物の戦略・戦術・戦法のランキング
7位:項文天項文天は寛大で、英雄的で、勇敢である。善と悪の両派の追撃から一人で逃れて任無星を救出し、...
宋仁宗はどのようにして人材を獲得したのでしょうか?学校建設に関する勅令は彼の決意を表明した
宋仁宗は帝国の長期的な安定を確保するために、人材を頻繁に発掘して活用し、そのために「学校設置の令」を...
孟浩然の詩「科挙に失敗した従兄の雍に会って会稽に行く」の本来の意味を鑑賞する
古代詩:「科挙に失敗した従弟の雍を会稽に送り出す」時代: 唐代著者: 孟浩然強い風が帆を吹き飛ばし、...