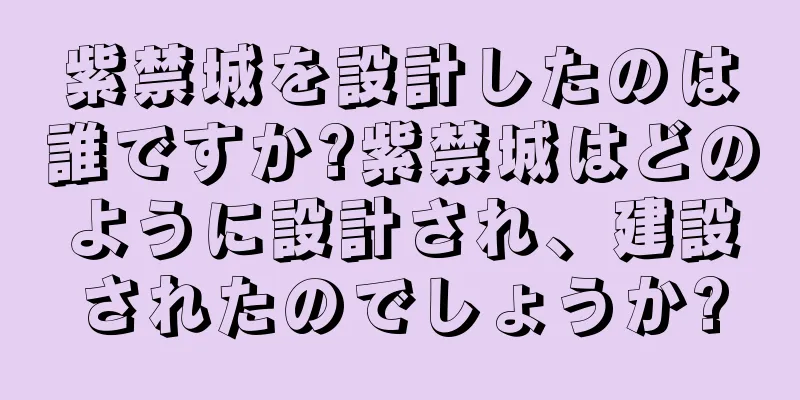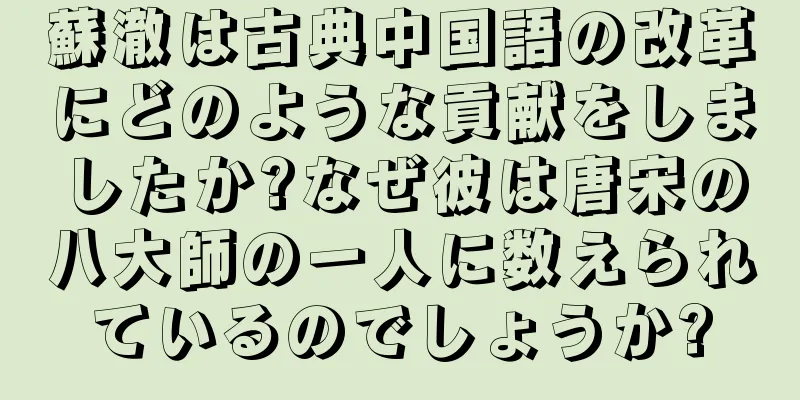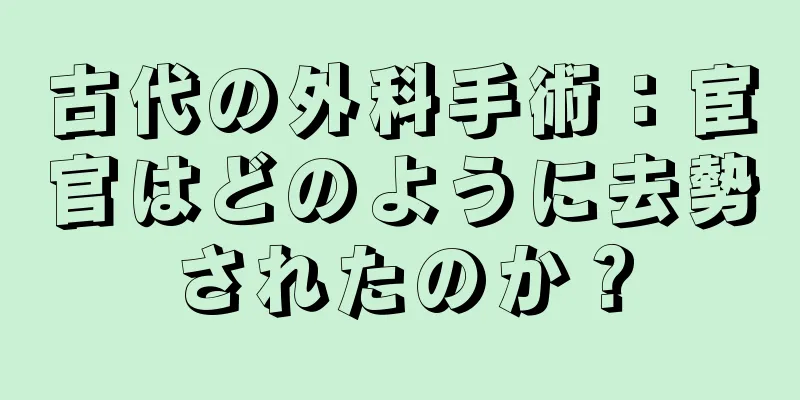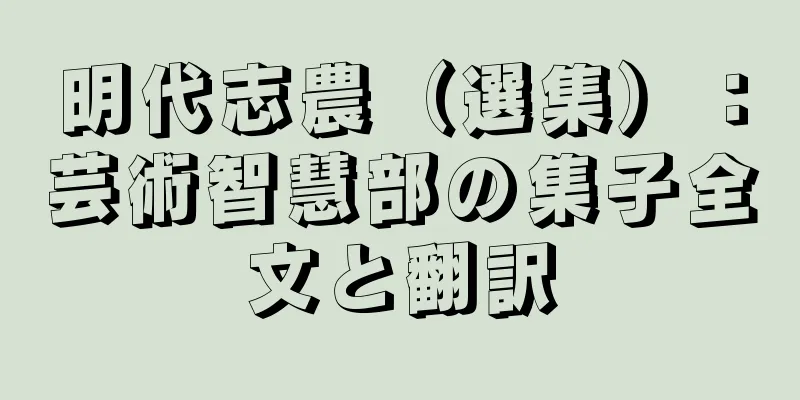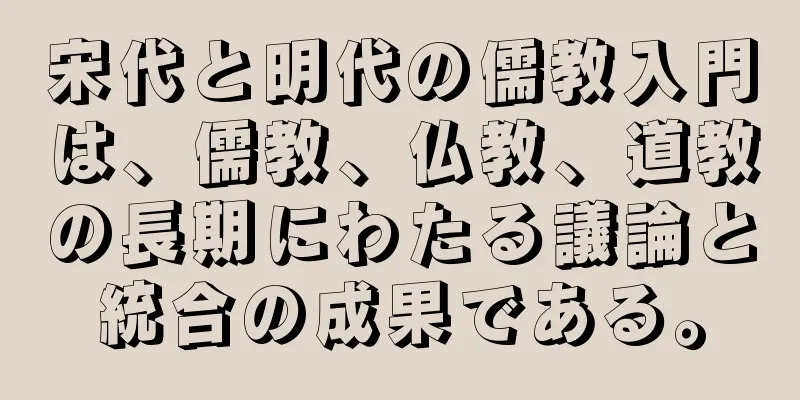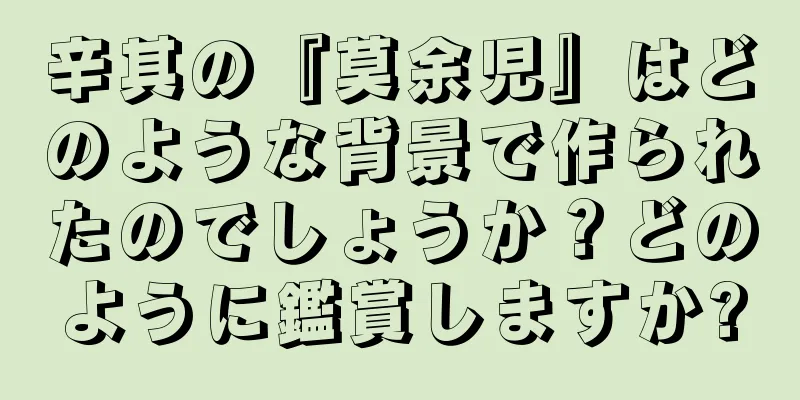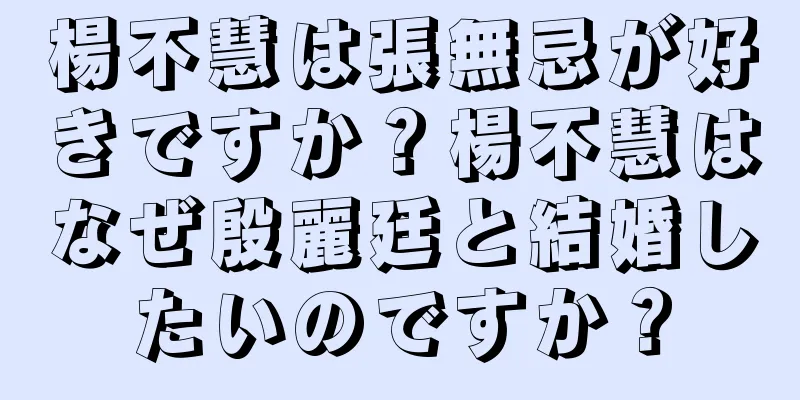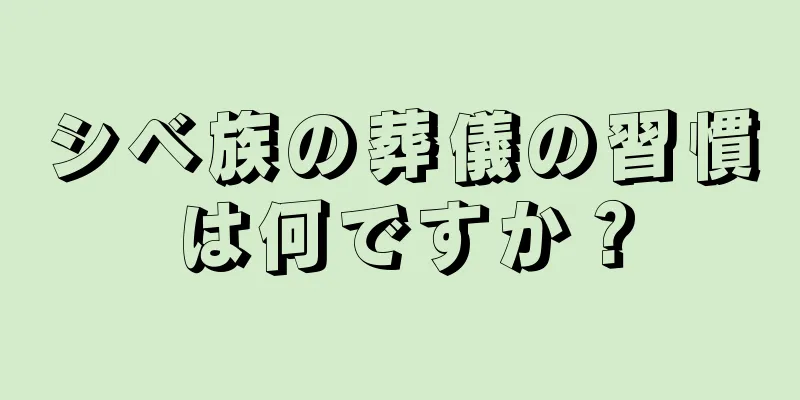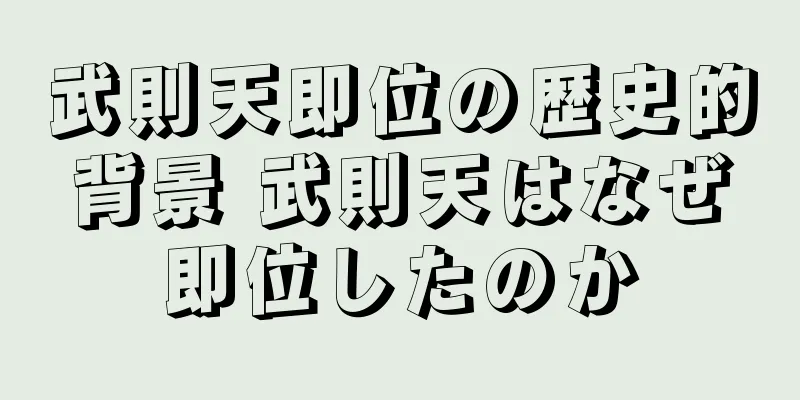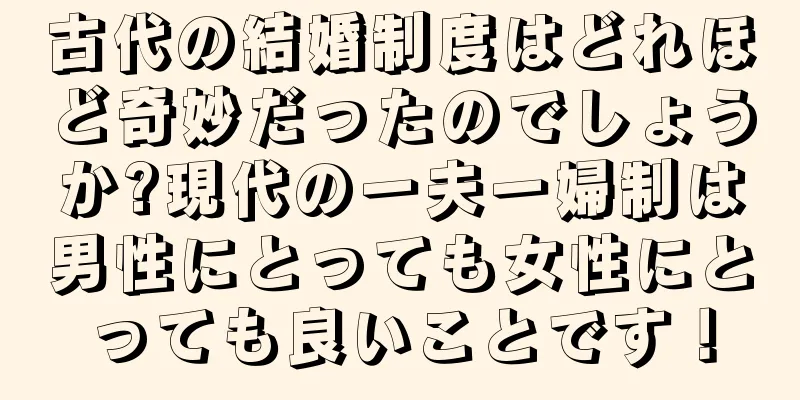諸葛亮は曹魏に対して絶対的に不利であるとわかっていたにもかかわらず、なぜ依然として「好戦的」行動を続けたのでしょうか?
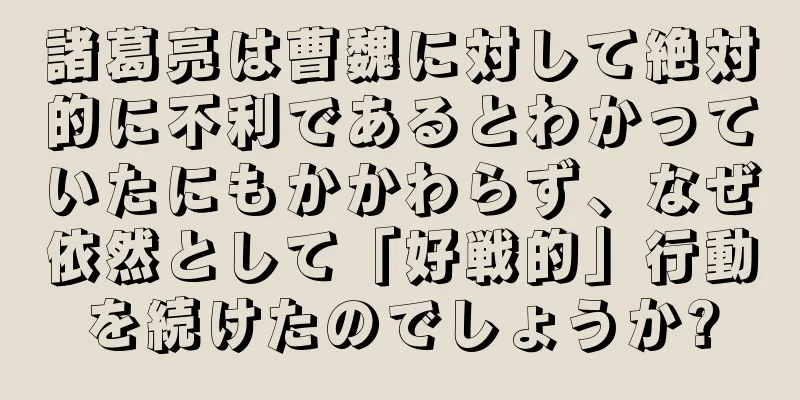
|
劉備の死後、諸葛亮は数年のうちに5回の北伐を遂行し、その後継者の姜維もこのルートを全面的に継承した。では、曹魏に対して絶対的に不利であるとわかっていたにもかかわらず、諸葛亮はなぜそのような「好戦的」手段に訴えたのでしょうか。次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう。 「国は小さく、人口も少なく、戦争は絶え間なく続く。」諸葛亮が権力を握った後の狂気の北伐については、現代の私たちだけでなく、当時の蜀漢の朝廷内でも反対意見が絶えなかった。 西暦228年初頭、諸葛亮は最初の北伐を開始しました。一時は勢いがつき、曹魏の関中地方に動乱を引き起こしましたが、街亭で大敗し、漢中へ撤退しなければなりませんでした。 この敗北により、馬蘇が殺害されただけでなく、諸葛亮自身も宰相から右将軍へと三階級降格され、同時に蜀漢政府と民衆も両者の力の差を痛感した。 しかし、諸葛亮自身はこれに落胆しなかった。彼は「小さな貢献を評価し、英雄的な行為を特定し、自ら責任を取り、領土内での過ちを公表した」。つまり、彼は軍事的功績を評価して報い、殉教者の家族に哀悼の意を表した。同時に、彼は自分自身を批判し、自分の過ちを公然と公表した。さらに、「軍隊を訓練し、将来に備えた」 - 彼は軍隊を訓練し、次の遠征に備えた。 同年11月、曹魏が東呉との東部戦線で敗北し、関中の軍が東方に転じたことを知った諸葛亮は、第二次北伐を決意したが、朝廷ではこれに疑問の声が相次いだ。曹休が敗れ、魏軍が東方に進軍し、関中が弱体化したことを知った諸葛亮は、軍を派遣して魏を攻撃しようとしたが、多くの大臣は懐疑的だった。 この「より多く」という言葉の範囲は曖昧だが、反対者がかなり多いのは明らかだ。戦争に勝つには正当な理由が必要なので、諸葛亮は劉禅に手紙を書き、北伐の理由を詳しく説明した。 第一:「先帝は漢と反乱軍が共存できないこと、そして王の大義が中途半端ではいけないことを深く憂慮し、反乱軍と戦う任務を私に託した。」 つまり、北伐は劉備前皇帝が個人的に計画した作戦であり、諸葛亮が参戦したいと思っていたものではない。劉備がこのような戦略的な取り決めを残したのは、蜀漢政権の正当性を維持する必要があったためである。古代人の心の中では、中原を占領した政権だけが正統な中華国家とみなされていました。蜀漢は辺鄙な場所にあり、その建国の基礎は自らを正統な漢王朝とみなし、過去400年間の漢王朝の継続とみなすことであったため、国名は「漢」と名付けられました。もし曹魏と平和に暮らし、互いに干渉しなかったら、それは彼らが地方の分離主義政権であることを認めたに等しいことになり、劉朝は完全に道徳と法的存在根拠を失うことになるだろう。正義と雄弁の旗がなければ、蜀漢の朝廷はどうして民心を集め、軍隊を率いることができようか? 第二に、兵士の自然死は深刻だった 諸葛亮は、漢中に留まったのはわずか一年で、趙雲、馬羽など七十余名の将軍と、「土江、武衍、青強、三騎、武騎」など千余名の精鋭兵士が老齢などの理由で自然死したと述べている。これらの兵士は、劉備が以前から中原各地から集めた精鋭部隊であり、益州だけで調達できるものではない。「彼らは皆、数十年の間に全国から集めた精鋭部隊であり、一国の所有物ではない」。したがって、ただ座して何もしなければ、数年のうちに蜀漢軍の屋台骨は失われ、曹魏に対抗できなくなるだろう。 そして事実は、蜀漢軍の戦闘力が低下傾向にあったことを証明しています。 第三に、蜀漢は北方全域と戦うために一つの国だけで長期にわたる戦争を続ける余裕がなかった。 地図上の3つの王国の領土の大きさから判断すると、その差はそれほど大きくないようです。しかし、当時、各地の強さは、大きさではなく、土地の発展と人口密度で比較されていました。当時の中原は中国文明の発祥地であり、数千年の開発を経て、人口は密集し、土地は肥沃でした。歴史書の「中国」は、もともと中原を指していました。対照的に、南部は「地下が低く湿潤」で、気候は高温多湿で、生産性の限界と相まって、人口がまばらで、経済状況が遅れていました。五夷の時代に人々が南へ移動して初めて、南部は大きく発展しました。 下の図は東漢時代の国の区分です。蜀漢は1つの国しか占領していないことがわかります。広い地域に見えますが、実際にはかなり空っぽです。そのため、諸葛亮は追悼文の中で朝廷の役人に「1つの国を使って敵と長期戦をするつもりですか…」と質問しました。長期戦を戦うには、自分の力と回復力で敵を粉砕するという大前提が必要です。そうでなければ、死を招くことになります。 第四に、時が経つにつれ、中原の人々は漢王朝からますます疎遠になっていった。 漢王朝は約400年間続き、当時の人々にとって依然として一定の魅力を放っていました。諸葛亮が第一次北伐を開始すると、曹魏の管轄下にあった天水、南竿、安定などの郡はすべて反乱を起こし、蜀漢軍に応戦した。民衆の支持はある程度は戦力不足を補うことができるが、時が経つにつれて曹魏政権が安定し、漢朝に情を抱く老人たちが徐々に離れていくと、蜀漢が中原を回復するのはますます困難になるだろう。 したがって、上記の要因を考慮すると、時代は曹魏にとって有利であり、蜀漢にとっては非常に不利であった。諸葛亮は7年間で5回連続して北伐を行った。彼は、北の生産力がまだ完全に回復していない、両者の差が最も小さい機会を利用しようとした。 人間は外的な問題を抱えていなくても、内面的な問題を抱えている。要塞は必ず内部から破られる。外敵の存在はしばしば内部の団結を促す原動力となる。逆に、外部的には平和で繁栄していても、利害の分裂などの要因により内部で徐々に対立が生じ、最終的には国が崩壊することが多い。これは中国でも海外でも、古代から現代に至るまでの真実です。 桓水の戦いでは、前秦の百万近い軍勢と対峙し、数十年にわたって戦ってきた東晋の王家、謝家、桓家といった名家がかつてないほど団結し、敵に対する共通の憎しみを共有し、少数の兵力で敵を倒すという奇跡を起こした。しかし、危機後、彼らは北部の崩壊に乗じて北伐を起こさず、再び内紛に陥り、中原が再び比較的安定した強大な政権を形成するのを見守った。 宋代以前、中原における王朝の滅亡は基本的に内部要因によるものでした。百年にわたる戦争の後、漢の宣帝の時代に西漢は強敵である匈奴を鎮圧した。しかし、外敵を失った後、その後の代々の君主たちは進取の精神を完全に失い、政治はますます腐敗し、外縁の独占と土地の併合が深刻になり、ついには王莽による権力の簒奪と緑林・赤眉の反乱を招いた。司馬一族の晋は三国を統一したが、敵を失った後、絶え間ない内紛が始まった。八王の乱は西晋の軍事力を消耗させ、移住した少数民族に武力で権力を奪取する機会を与えた。その後の隋や唐の時代でも同じことが起こりました。外からの脅威を力ずくで排除した後、すぐに内乱に陥りました。 この原則は現代社会においても時代遅れではありません。世界超大国として、米国は常に仮想敵を見つけなければなりません。これは経済的利益と、国の多民族・多文化社会を統合する必要性の両方に関係しています。 しかし、当時の諸葛亮が直面していた状況ははるかに複雑でした。劉備は蜀に入ると、荊州の軍を率いて武力で益州を占領した。彼らは権益の再分配を通じて地元の貴族の大半の承認を得たが、蜀漢政権が鉄壁の体制になったわけではない。例えば、劉備の死を知ると、南部諸郡で大規模な反乱が即座に勃発した。 同時に、古代の学者官僚階級は、出身地や学派などの要素に基づいて派閥を形成することを常に好んでいました。公正な心を持つ諸葛亮も例外ではありませんでした。劉備は何度も彼に「大げさな」馬蘇を再使用しないように注意しましたが、彼は頑固に自分の意見を主張しました。それは必然的に彼と馬蘇が荊州出身であり、兄の馬良と仲が良かったという事実によるものでした。 戦争状態であれば、各方面が争いを脇に置いて敵と戦うことに集中する十分な理由と手段があるだろう。劉備の死後、蜀漢は三国の中で最も弱体となり、客観的に見て状況を安定させ、団結を維持し、危機を克服するために特別な国家を必要としていた。 事実は蜀漢政権が内部的には安定を保っていたことを証明しているが、絶対的な力の大きな差のため、諸葛亮も姜維も奇跡を起こすことができなかった。結局、両者の溝は広がり、この地方政権は逃れられない運命に直面した。しかし、その後数千年にわたって蜀を統治した政権と比べると、蜀漢は最も長く続いた政権であった。 |
<<: 馬素が街亭を失った後、彼のために弁護した李妙と江万はどうなったのでしょうか?
>>: 于禁と関羽はどちらも降伏した将軍なのに、なぜ関羽は降伏したことで批判されなかったのでしょうか?
推薦する
金庸の小説『鹿鼎』に登場する雲南省穆宮の若き王女穆建平の人物紹介
穆建平は金庸の小説『鹿鼎』の登場人物である。雲南省穆宮の小公女。明朝の建国の将軍穆英の子孫。祖先は安...
蘇軾の詩『臨江仙』はどのような雰囲気を表現しているのでしょうか?
以下に、興史編集長が蘇軾の『臨江仙・揚州夜宴記』の原文と評価をお届けします。ご興味のある読者と興史編...
「秘色月焼」の創作背景とは?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
シークレットカラー月旗呂桂孟(唐代)九秋の風露とともに岳窯が開き、千峰の緑の色を捉えます。夜中に吉仲...
古典文学の傑作『太平天国』:食品飲料第7巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
なぜ劉備は蜀漢の全力を結集して呉を攻撃したのでしょうか?張さんの閉店のせいでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「音楽を聴きながらがっかりした時の自叙伝」は詩空舒が書いたものです。詩人の心の中にある「がっかり」の本当の理由は何でしょうか?
漢拏は、字を太充といい、唐代中期の画家、政治家、書家です。漢拏の「五牛図」は、中国に伝わる十大名画の...
四つ折りと一序の紹介:これは元代の劇の脚本であり、非常に柔軟性があり、多くの機能を備えています。
元座歌は北座歌とも呼ばれ、元朝時代に北方の曲調で上演された伝統的なオペラ形式です。宋代に形成され、元...
古代中国の有名な小説「封神演義」の第35章、趙天の兵士が西斉を探検する物語の原文は何ですか?
黄一族は凧のように国境を抜け、西岐の天まで到達することを望み、兵士たちは沈黙のうちに五つの峠を越え、...
希仁は賈宝玉が勉強が嫌いだと知っていたが、それでも勉強するふりをするようにアドバイスした。なぜだろう?
今日は、Interesting Historyの編集者がXirenについての記事をお届けします。ぜひ...
『前漢民話』第55話はどんな物語を語っているのでしょうか?
反乱軍の太衛は、弱った王臨鋒を救い、命乞いをする功績を挙げた。しかし、呉と楚の王は、食糧補給路が遮断...
『射雁勇者の帰還』における孫おばあちゃんの役割は何ですか?
孫おばあさんは金庸の小説『射雁英雄の帰還』の登場人物です。詳しい出自は不明だが、死ぬまで林超英の弟子...
『紅楼夢』の寧国屋敷の女主人である有施の結末はどうなりましたか?
ヨウシは、おばあちゃん、ジェンおばあちゃん、ジェンの嫁とも呼ばれ、ジア・ジェンの2番目の妻です。彼女...
『紅楼夢』で夏金貴は薛家に嫁いだ後何をしましたか?なぜ宝仔は気にしなかったのでしょうか?
ほとんどの人の心の中では、夏金貴は王希峰と同じように嫉妬深く攻撃的な意地悪な女だ。多くの読者が気にな...
『西遊記』に登場する未来を予言する3つの魔法の力とは何ですか?
西遊記に登場する未来を予言する3つの魔法の力とは何でしょうか?仏教と道教にはそれぞれ1つの魔法の力が...
曹操の五大将軍の一人である楽進は本当に関羽を倒したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...