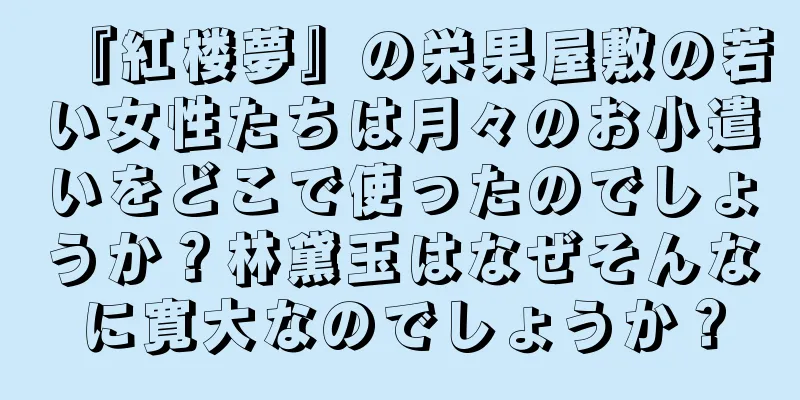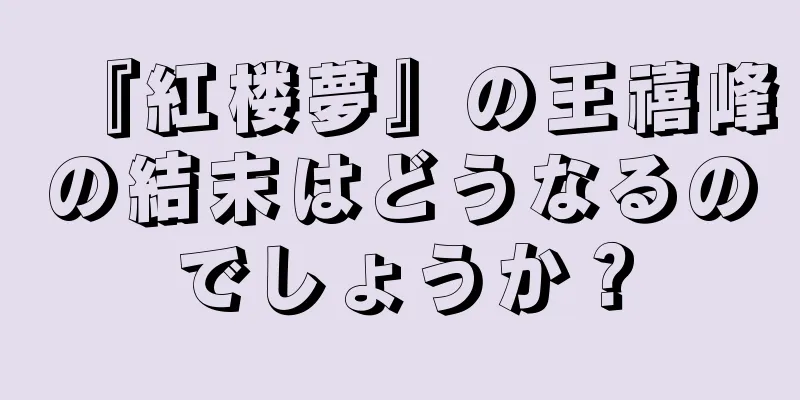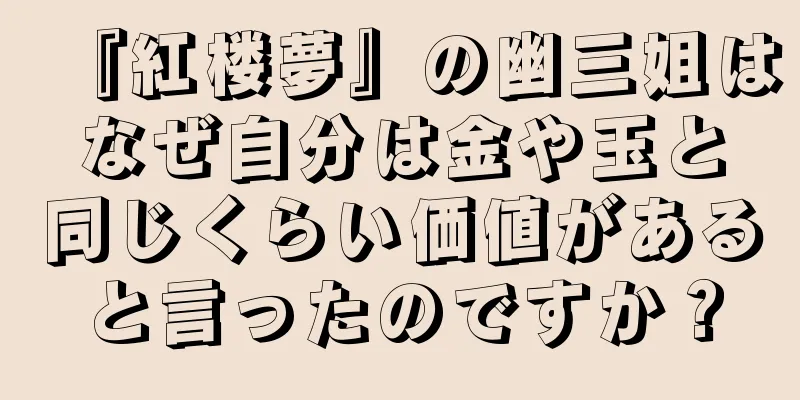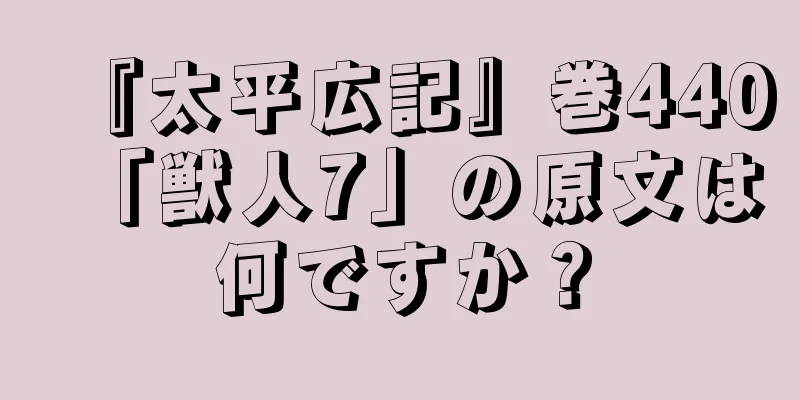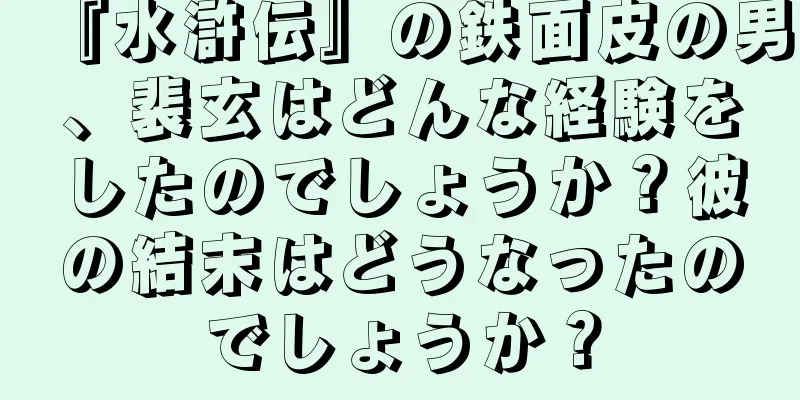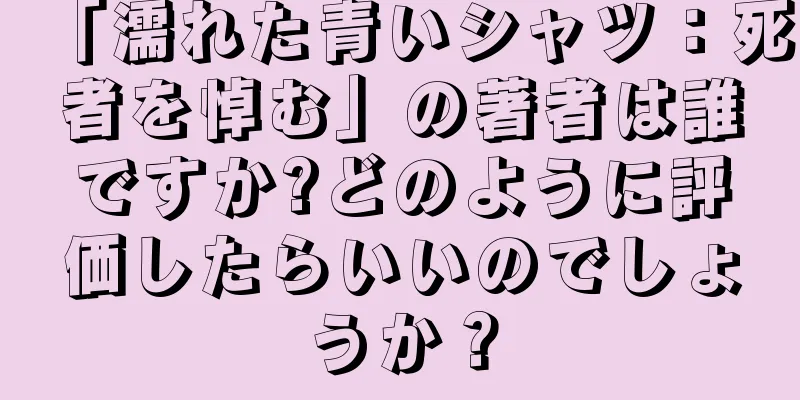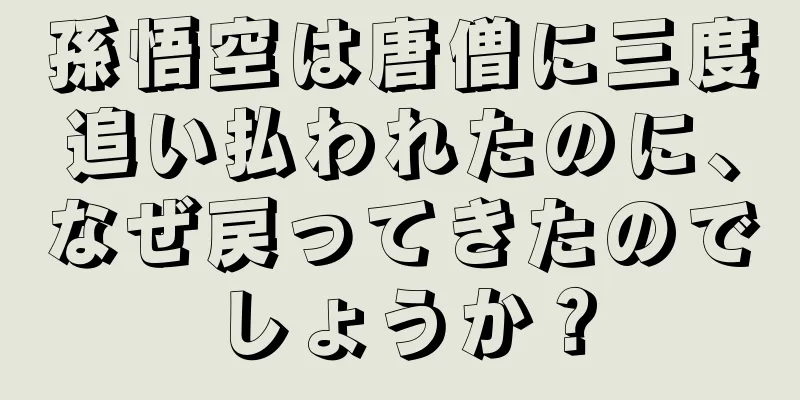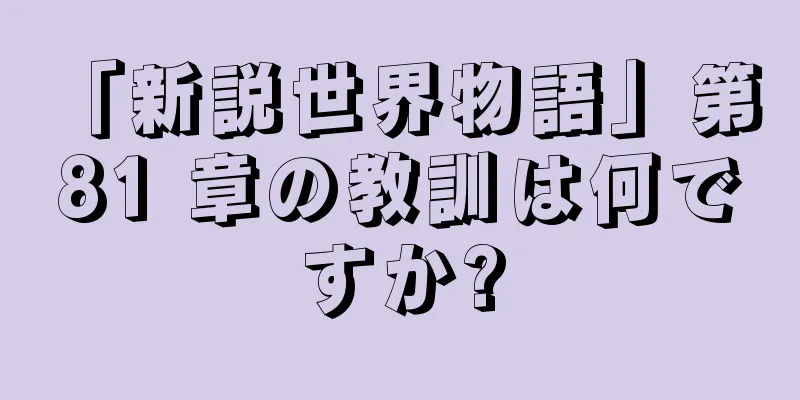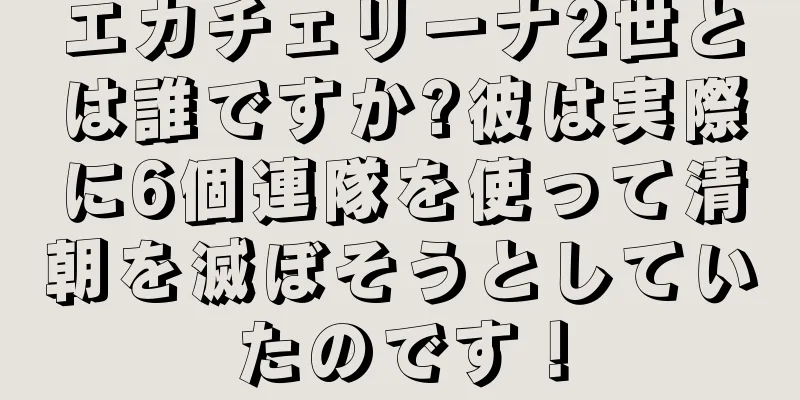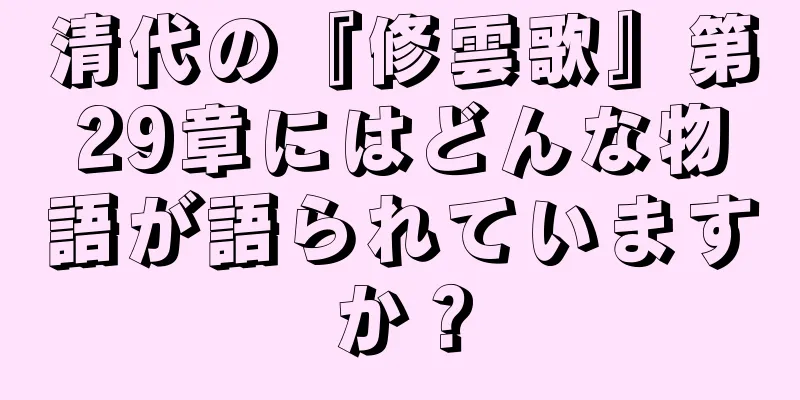明治維新の三英傑の一人、木戸孝允の紹介 木戸孝允はいかにして亡くなったのか?
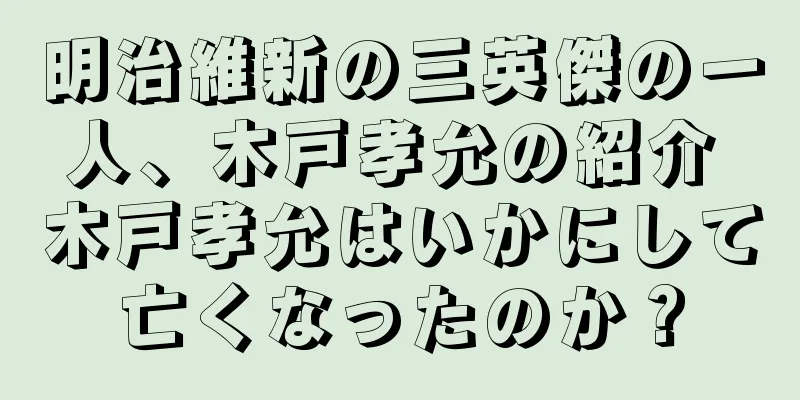
|
木戸孝允(1833年8月11日 - 1877年5月26日)は桂小五郎として生まれた。長州藩に生まれ、吉田松陰を兄と崇め、斎藤弥九郎に剣術を、江川榮龍に西洋兵学を学んだ。尊皇攘夷運動や討幕運動の指導者として活躍。維新後は五箇条の御誓文の起草に携わる。政府の中心人物として、版籍奉還や廃藩置県を推進。西郷隆盛、大久保利通とともに「維新の三英傑」と呼ばれる。 少年時代 天保3年6月26日(1833年8月11日)、長門国萩城下郷府町(現・山口県萩市)に藩医和田政景の長男として生まれる。母は彼の2番目の妻であり、彼には最初の妻と2番目の妻の間に生まれた2人の姉がいた。彼は長男であったが、病弱で成長できないと思われていた。長姉は文容と結婚して家業を継いだ。長姉が亡くなった後、彼は次姉と結婚した。天保13年(1840年)、小五郎は和田家の向かいの桂家の養子となり、武士の身分と俸給を与えられた。翌年、桂家の養母が他界したため、和田家に戻り、実父、母、次姉に育てられた。 10代になってから、藩主毛利敬親の前で即興の漢詩や『孟子』の解説を2度披露し、いずれも賞賛されるなど、長州の若き才能として注目されるようになった。 嘉永元年(1848年)、次姉と実母を相次いで病気で亡くした彼は、悲しみのあまり長い間寝たきりで、次姉と実母のために祈るために出家したいと周囲の人々に言い続けた。 1849年、吉田松陰に兵法を学んだ。松陰は桂を「君には物事を成し遂げる才能がある」と評し、「私が大切に思う人」とも評した。師弟関係だけでなく、家族や友人のような関係も保っていた。 剣士時代 1846年、長州藩の剣術家・内藤作兵衛の新陰流道場に入門。嘉永元年(1848年)、元服後、桂家の大組司を継承し、和田小五郎より桂小五郎となる。小五郎は人一倍熱心に剣術の修行を積み、強さを増すにつれ、次第に周囲から認められるようになった。 1852年、小五郎は剣術修行という名目で私費で江戸に留学することを決意し、藩の正式な許可を得て、他の5人の官費留学生とともに江戸に渡った。 江戸三大道場の一つ「力の斎藤」に入門し、神道無念流の免許皆伝を受け、入門から1年後に道場長に就任。背が高くハンサムな桂小五郎は、戦うときは竹刀の上部だけを使い、「周りの人は皆、彼の穏やかで堂々とした精神に感銘を受けた」と言われています。大村藩の渡辺昇と桂小五郎は、斉藤道場から同時に免許皆伝を受け、道場の二本柱として知られた。同時期の江戸では、武市半平太が桃井春蔵の志学館の道場主を務めており、『義の千葉』では坂本龍馬も桶町千葉道場の道場主を務めている。 幕府の小武繁頭取・大谷誠一郎の直弟子に敗れ、5年以上に渡って剣術道場の頭を務めた。その間に剣士として名声を博し、江戸藩大村藩士に剣術を教えるために雇われた。安政5年10月、桃井道場で小五郎、武市半平太、坂本龍馬が剣術大会に参加したと伝えられるが、実際には武市と坂本は9月に土佐藩に帰藩しており江戸にはいなかった。 海外に留学し、国家を樹立し、条約を破り、外国の侵略者を追い出そうとする野心的な人々 道場長を勤めていた頃、ペリーの第2回来航(1854年)に感銘を受け、師匠の斎藤弥九郎の紹介で江川榮龍に視察を申し込み、随行員として同行し、ペリー艦隊を自らの目で見届けた。 松陰が下田踏み海中作戦を遂行する際、同行して手伝うことを希望したが、弟子を心配した松陰は断固としてこれを阻止した。その結果、下田踏み海中作戦が失敗に終わった後、幕府から処罰を免れた。その後、義兄の栗原良蔵とともに藩に留学申請書類を提出し、松陰の「下田踏海行」後の幕府の監視に追われていた藩に再び衝撃を与えた。留学は江戸幕府の鎖国令に違反するに等しい行為であり、倒幕の考えがまだなかった長州幕府は秘密裏であっても留学を認める勇気はなかった。叱責を受けた後、小五郎は当時の最先端の技術を吸収して自分のものにしたいと願い、錬兵館道場の道場主宰を務めながら、当時の著名人の間で勉強を始めました。 文久2年(1862年)、小五郎は幕府の中枢に台頭し、朱子学政之助、久坂玄瑞(義助)らとともに松陰の海上英雄論を基本政策とし、幕府に有利な長州藩主永井正学らの「遠洋航海論」を打ち破り開国を果たした。その後、長州藩の論調は開国攘夷論に傾き、同時に幕府の意に反して外国勢力に屈服して開港し、その後鎖国・鎖国・攘夷を行なった幕府の政策を「言うに及ばず」と非難した。文久二年春から三年春にかけて、長州藩の開明的な指導者たちは次第に意見が一致し、欧米に留学生を派遣して欧米の文化を吸収させ、最終的には攘夷と独立国家の樹立という目標を達成した。 1863年5月、長州藩は密かにイギリスへ留学生を派遣し、横浜から出発した。長州五大留学生、伊藤博文、山尾庸三、井上勝、遠藤謹助はいずれも藩費で留学した。この政策が可能になったのは、留学を志す小五郎を周布が藩政の中枢に登用したからである。さらに小五郎は、オランダ語と英語に堪能な村田蔵六を藩政の中枢に登用した。その結果、長州藩の権力中枢は次第に開明派が権力を握る状況が形成された。久坂玄瑞は、朝廷の命により江戸幕府が出した攘夷大号令に従い、それまでの小五郎や高杉晋作の慎重な意見を無視して、長州軍を率いて下関の関門海峡を通過する外国船を砲撃し、攘夷戦争の幕開けとなった。この戦争は約2年間続いたが、当然条約は破棄されず、長州藩は最終的に敗れた。高杉晋作が主導した交渉の結果、イギリス、アメリカ、フランス、オランダの連合軍は攘夷令を出した幕府に賠償金の支払いを要求した。 5月、藩命により江戸から上洛し、京都では久坂玄瑞、真木和泉らと条約破棄攘夷運動に取り組み、諸藩が結束して大政奉還を実現し、新国家を建設することを政治的目標とした。 萩門の変遷 八月十八日の政変は小五郎らの不断の努力により正当性を保ったが、池田屋事件は尊攘派の憤激を招いた。小五郎、朱房之助、高杉晋作らは反対したが、それでも先遣隊三百人の上洛を阻止することはできなかった。久坂玄瑞は山崎天王山に、来島又兵衛は嵯峨天龍寺に、福原越後軍は伏見に軍を配備し、朝廷に長州藩主父子や長州藩公卿の不満を解消させることを期待した。これに対して朝廷も、「会津藩から長州藩に京都守護職を移すところまで話が進んでおり、幕府は朝廷に関わることはもう関知しない」と応じた。会津藩や幕府の敵になるとは思ってもいなかった孝明天皇や公卿たちは、あっさりと怯んで考えを変え、一気に長州軍を殲滅させようとする幕府の意向に従い、朝廷は期限内に長州軍に撤退するよう最後の警告を発した。 長州軍は武士に名誉を賭けていたため、目的を何一つ達成できずに不名誉なまま領国に帰るしかなかった。そこで、瀬戸内海に残っていた森貞広率いる長州軍主力2,000人に帰藩を要請する嘆願書を提出し、長州先鋒軍は天皇への直訴と集団決死を賭けて萩門へ突入し、禁門の乱が勃発した。この時、小五郎は因州藩を説得して長州陣営に加わらせようと計画し、有栖川宮で因州尊攘派の有力者河田経興と最後の交渉を行った。因州藩が御所の警護役を務め、長州軍が直接御所に入るという案であった。しかし、河田は状況が絶望的だと見て、まだ時期尚早であるとして長州との同盟を拒否した。裏切られ、約束を破られた小五郎は、孝明天皇が御所を去った後、避難の途中で直訴を待ち、失敗して高木邸に背を向けて脱出を試みる。それからは幾松や対馬藩士の大島知則の協力を得て、本当の潜伏生活が始まった。禁門の変後、会津藩をはじめとする幕府軍は長州人を追討し、殺害したが、もはや京都に隠れることはできないと悟った長州人は京都を去った。 長州征伐 幕府は朝敵となって敗れた長州に対し第一次長州征伐を行なった。このとき長州の義政は退き、保守派に取って代わられた。この征伐の結果、長州は戦わずして敗れ、家老や家臣は責任を取って自害、あるいは処刑された。長州の保守派は義勇軍を粛清し始めたが、高杉晋作率いる改革軍が蜂起し軍事クーデターを起こして勝利し、改革派が政権を握った。大村益次郎、高杉晋作らは小五郎の潜伏場所を知り、長州正義派のリーダーとして小五郎を長州に迎え入れた。長州藩主を務めた後、高杉らが望んだ軍備・服従の政策を実現するため、軍制改革や藩政改革に動いた。 長州藩は土佐の土佐左衛門、中岡慎太郎、坂本龍馬らの仲介により、薩摩と密かに同盟を結んだ。同盟締結後、桂は龍馬に丁寧に手紙を書き、交渉内容が正しいことを確認して承認を求めた。内容の要点は以下のとおりです。 1866年1月22日の京都同盟以来、桂は長州の代表として薩摩の小松泰等、大久保利通、西郷隆盛らと度重なる会談を重ね、薩長同盟をより強固なものにしていきました。この同盟のもと、長州は薩摩の名においてイギリスから武器や軍艦を購入した。 幕府は長州無兵衛の服従と大村益次郎らの秘密貿易を口実に第二次長州征伐を強行した。長州軍は薩長同盟を通じて秘密裏に武器や船舶を購入し、大村益次郎の指導のもと近代的な軍制改革を実施したため、士気は非常に高かった。当時長州にいた坂本龍馬はこれに強い思いを持ち、薩摩に宛てた手紙の中で「長州軍は日本一強い」と書いたほどである。藩政府はまた、民衆の団結を図るため、長防民協約を36万部印刷し、学者、農民、商人、職人を問わず領内の各家庭に配布した。大島口、芸州口、石州口は、短期間で次々と幕府軍を破り、残った小倉口も、最後まで戦うつもりだった肥後軍が戦意を喪失したため、長州軍の勝利を確定させた。この結果、天領、石見銀山を含む浜田藩領の大半と小倉藩は、1869年の返還までに長州藩(討幕派)の支配下に入った。 明治維新政府 明治新政府が発足すると、岩倉具視は高い政治的見識があると自負し、唯一総裁室顧問に任命され、すべての政策の最終決定の責任者となった。太政官制度改革後は外務長官、参議、参議、文部大臣を歴任した。明治元年(1868年)以来、度々啓発的な提言を行い、政策の実施に先頭に立って取り組み続けた。明治政府は、五箇条の御誓文、新聞の発達、封建的慣習の廃止、版籍奉還、廃藩置県、人材優先、四民平等、憲法制定、三権分立の確立、二院制の確立、教育の改善、法治の確立などの建議を徐々に実行に移していった。さらに、軍人の閣僚就任禁止や地方警察・司法制度の確立など、当時としては極めて近代的で啓発的な提言を行った。 1868年3月14日に出された五箇条の御誓文について、木戸は福岡講事の草案を参考にして、第一条の「侯爵昇進会議」を「国進会議」に改めた。「五箇条の御誓文」は、明治天皇自ら文武両道の官僚を率いて天地民に誓う儀式で、木戸の発案によるものだった。木戸は抵抗する保守派を説得し、天皇に改革を真剣に受け止めさせた。 岩倉使節団とその影響 明治政府初期の政策変更や百家争鳴の状況を払拭するため、明治4年6月の廃藩置県で多少は安定し、西郷隆盛、大久保利通、岩倉具視、三条実美らは連名で木戸の単独参議就任を要請した。誰もが「一政一致」による効率的な体制の構築を望んだが、公開性と協調性を重んじる木戸はそれに反対し続けた。大久保の妥協案では、木戸は西郷と二人で参議を務めることに同意したが、政務に詳しい西郷を補うために肥前も参議を務めるよう西郷に進言した。西郷も応じ、薩摩、長州、土肥から一人ずつ参議を務める共和制の合議内閣が成立した。しかし、執行官の木戸が後に海外視察の全権を持つ副使に任命されたため、薩長土肥各1名によるいわゆる共和制内閣は長く続かなかった。 海外視察団と駐在官団の間には「視察終了までに書簡で合意しない限り、明治政府の主要制度、人事は変更できない」という取り決めがあったが、駐在官の運用に関しては、この取り決めは形骸化していた。海外視察団が合意どおりに帰国しなかったため、当初の短期視察計画は2年近くにまで延び、駐在官の責任を問うことは不可能となった。海外視察団は、残された政府が提案した韓国侵攻の考えを、決して同意できない愚かな行動だとみなした。 (当時の日本には朝鮮半島への大規模な遠征は不可能だった。戦争を起こしたくても、朝鮮の後ろ盾である清国と戦う力はなかった。残留した人々は国内の対立をそらし和らげるために戦争を起こすことを考えていた。視察に来た人々は留学が長く、日本と世界の隔たりをすでに理解していた。彼らは戦争を起こすよりもまず国内の統治を改革した。)木戸は海外視察中に海外に出た唯一の参議であった。帰国後、原因不明の激しい頭痛などの古病が突然再発し、再発と悪化を続けた。病気のためであったかどうかは不明であるが、この時点から木戸はもはや明治政府の実権を握ることができなくなった。 幕末以来の木戸の悲願であった開国・条約破り・攘夷、すなわち不平等条約の廃止と平等条約の締結のため、岩倉使節団の全権副使として条約改正の予備交渉や欧米への視察を行った。欧米の文化が進歩しただけでなく、民主主義の不完全性と危険性を見抜いて、開放的な急進主義から漸進主義へと転じた。結局、欧米と日本の文化の違いはあまりにも大きかったのだ。さらに、征韓論を撤回して内政を優先させる必要性を痛感し、憲法制定や二院制議会の設置を積極的に主張し、国民教育や皇室教育の充実に努めた。その後、自ら文部大臣を務め、国民教育の充実に尽力した。西郷隆盛らの朝鮮出兵や大隈重信・西郷徹道らの台湾出兵(牡丹事件)には一貫して反対した。さらに木戸は、農民を不公平な税制や重税から解放するために積極的に進められた地代改革や、武士の特権を廃止して新たな生計手段を強制するために構想された俸給制度にも強く反対した。 1874年5月に政府が台湾派兵を決定したとき、彼はこれに抗議して参議を辞職し、故郷の山口に戻った。 立憲政治の方向性の確立 1868年の議事堂、1869年の公議事堂は、いずれも木戸が開明的な政策に基づく組織を実現しようとした成果であり、国会の衆議院に相当する機能を持つ組織の実現を願ったものである。しかし、江戸時代の封建意識が色濃く残る各地の不満士族が臨時に役職に就き、自由に発言することを認めることは、改革の方向性や現実的可能性からあまりにもかけ離れており、大久保らは時期尚早で非現実的、無意味であるとして「廃止すべき」とさえ主張した。さらに、これらの会合は「廃刀令」や「四身平等」が実施される前に開催されたものであり、薩摩、長州、土肥を除く特権を剥奪された武士たちの不満をぶちまける場となっていた。 木戸は、その後も現代の国会に相当する衆議院の必要性を探求し、その必要性を主張し、環境を整えて時期が来たと判断し、1875年6月20日から7月17日まで第1回地方役人会議を招集し、自ら議長を務めた。当時成立した五法案はいずれも地方警察や地方議会などに対する地方自治を推進する法案であった。しかし、大久保内務省の台頭により、これらの事業は木戸の思惑通りには実行されなかった。 1877年2月に西南戦争が勃発すると、木戸は直ちに自ら鹿児島への遠征隊を率いることを要請した。大久保も和平使節として西郷に直接会うことを要請した。伊藤博文は両者に反対し、最終的には徴兵命令に従って国軍を派遣し、木戸は明治天皇とともに京都へ出張した。病状が悪化し危篤となったため、明治天皇も見舞いに訪れた。木戸孝允は5月26日に死去した。彼は43歳でした。 木戸孝允の日記には彼の心の葛藤が表れている。木戸は長州藩の利益が中央政府の利益と衝突するのではないかと懸念を表明した。彼は友人を裏切ったと非難されたとき、しばしば自らを弁護しなければならなかった。当時の日本では近代国家という概念がまだ形成されていませんでした。これは、社会が大きく変化した時代に、元々の武士集団が直面した問題のひとつでもありました。武士は元々、自分の大名に仕えていましたが、上司がいなくなった今、誰のために、誰のために働くかを考えなければなりませんでした。 |
<<: 維新前の三偉人の一人、吉田松陰の紹介 吉田松陰はいかにして亡くなったのか?
>>: 維新の三偉人の一人、大久保利通の紹介 大久保利通はいかにして亡くなったのか?
推薦する
張翠山はなぜ自殺したのか?張翠山の個人情報の紹介
張翠山は優しくて正直で、善と悪をはっきりと見分けることができます。彼は幼い頃から張三峰を師と崇めてい...
『紅楼夢』で、賈おばあさんは薛おばさんが長い間賈の家に住んでいた後、どうやって薛おばさんを追い出したのですか?
薛叔母さんが薛潘と宝柴を北京に連れてきた後、彼らは長年賈邸に住んでいました。本日は、Interest...
白居易の「清明夜」:この詩の美しさは、作者が清明の寒さについて書いていないことにある。
白居易(772-846)は、字を楽天といい、別名を向山居士、随隠仙生とも呼ばれた。祖先は山西省太原に...
『太平広記』第176巻の「奇亮」の原文は何ですか?
楽光、劉仁貴、楼世徳、李吉、李日志、呂成青、裴面、郭子怡、宋澤楽光晋の楽県知事である広の娘は、成都の...
皇帝の物語:劉嬰は劉邦に好かれていなかったのに、どうやって皇帝になったのでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
「無題の4つの詩」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
無題の詩4つ李尚閔(唐代)彼は空虚な言葉とともにやって来て、跡形もなく去っていった。月は傾き、時計は...
「鄭州滞在」をどう楽しむか?創設の背景は何ですか?
鄭州に滞在王維(唐代)朝は周の人たちに別れを告げ、夜は鄭の人たちと一緒に一泊しました。異国の地を旅す...
太湖にはどんな伝説がありますか?太湖はどのようにして形成されたのでしょうか?
今日は、「Interesting History」の編集者が、皆さんのお役に立てればと、太湖の歴史的...
『紅楼夢』で、ムスク・ムーンはシレンを「花おばあちゃん」と呼んでいます。これは不適切でしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
パンダの血液はどのように形成されるのでしょうか?パンダの血を引く人は多いのでしょうか?
パンダの血液がどのように生成されるかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting ...
元王朝の成立は、歴史上元王朝がどのように成立したかを明らかにする
元王朝の成立:元王朝(1271年 - 1368年)は、正式名称を大元またはモンゴル元といい、中国史上...
蜀漢が建国され、劉備が皇帝になった後、なぜ彼は諸葛亮に背き始めたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
宋代の詩「祝清」はどのような場面を描いているのでしょうか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
清朝を祝う:禁じられたテントが低い [宋代] 李清昭、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をも...
宋代の詩『滴蓮花』の「西湖の春景色を食べる」という詩の初期の鑑賞。この詩の作者は私たちに何を伝えたいのでしょうか?
戴蓮花 - 西湖の早春の風景を味わう [宋代] 欧陽秀、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を...
曹操は世界中の英雄たちを味方につけることができたのに、なぜ関羽の忠誠心を得ることができなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...