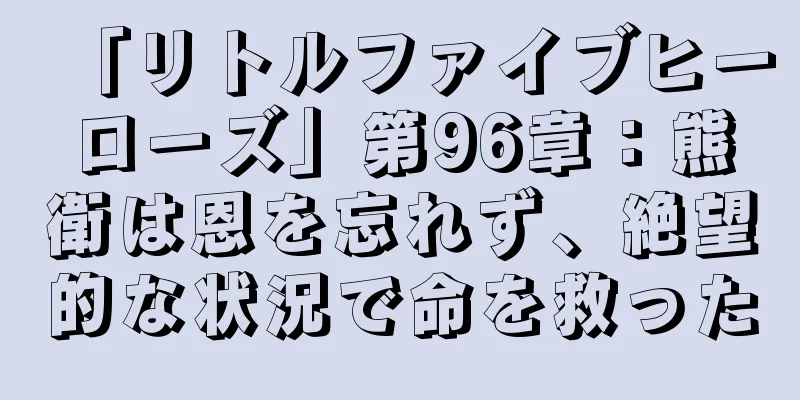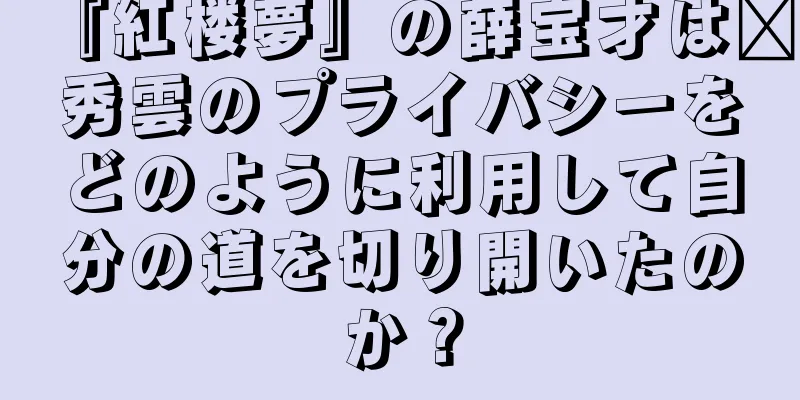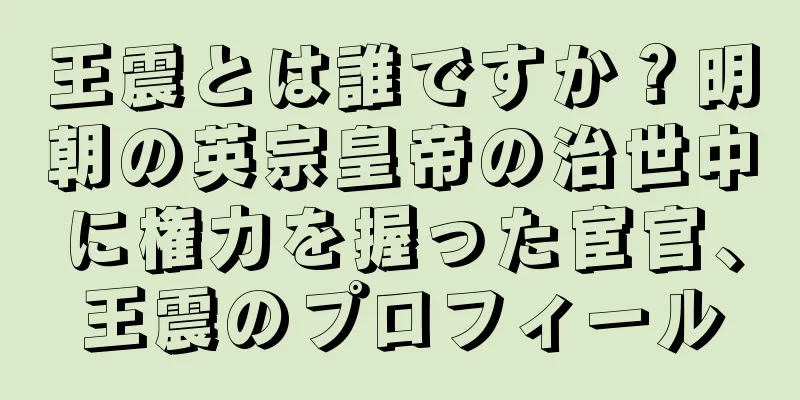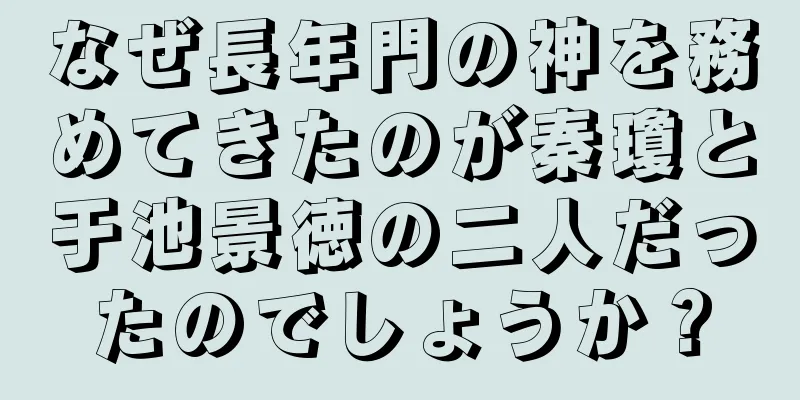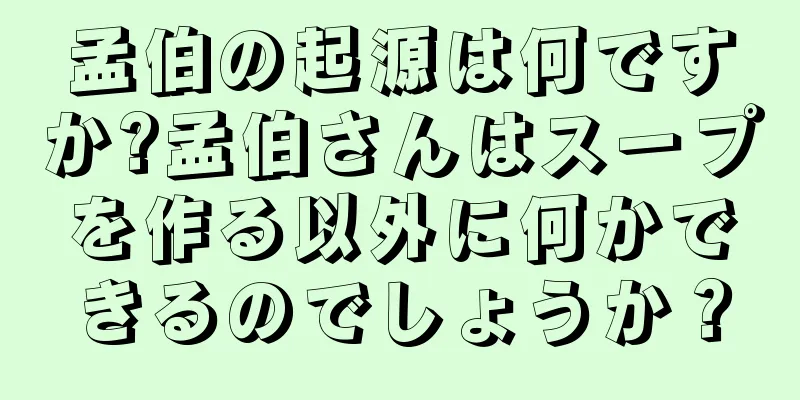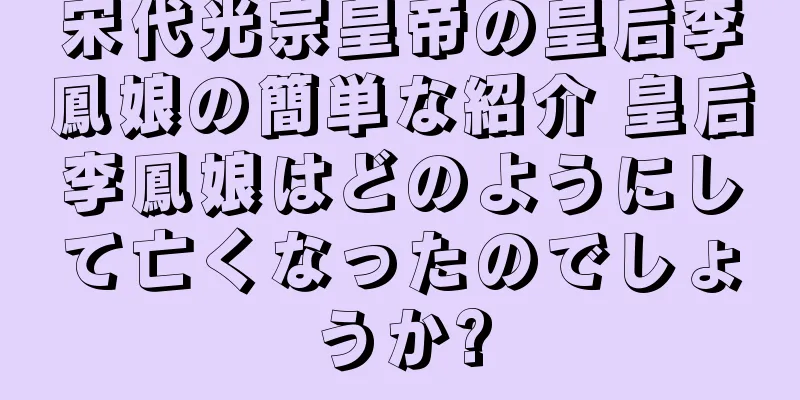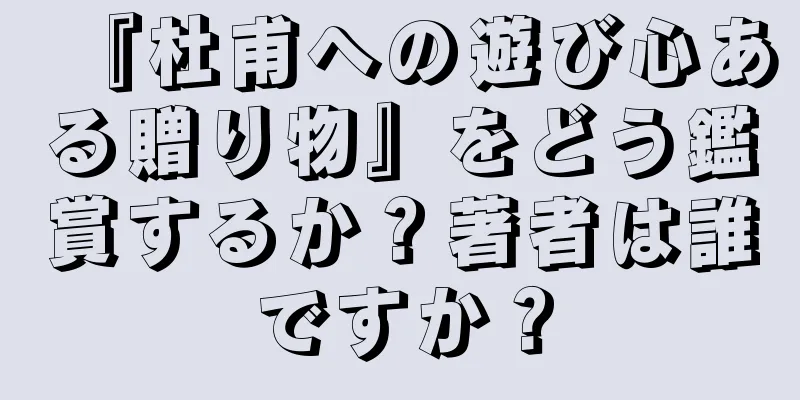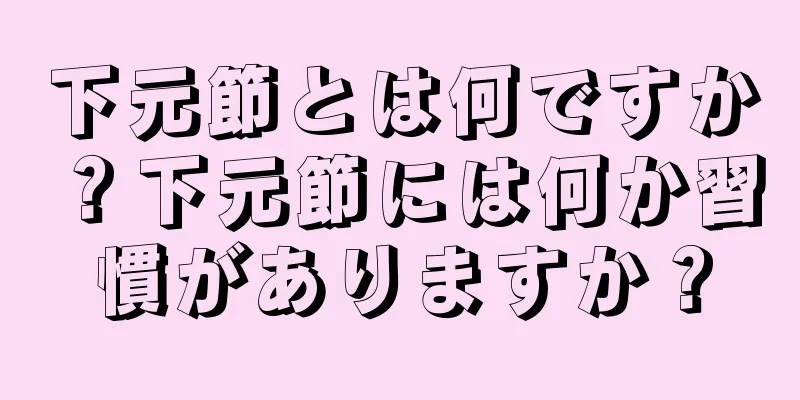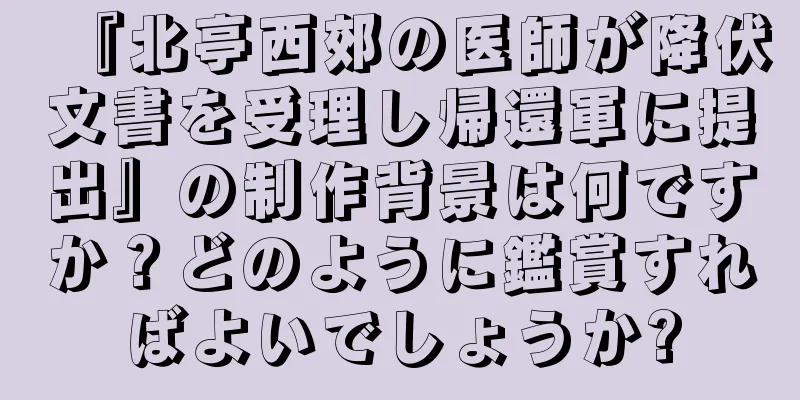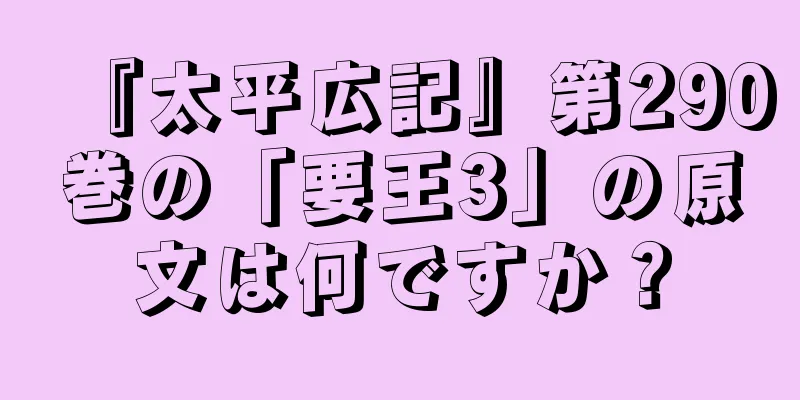劉備が息子を諸葛亮に託したとき、「お前が自分で取って行け」と言ったが、それは陰謀ではなかった。
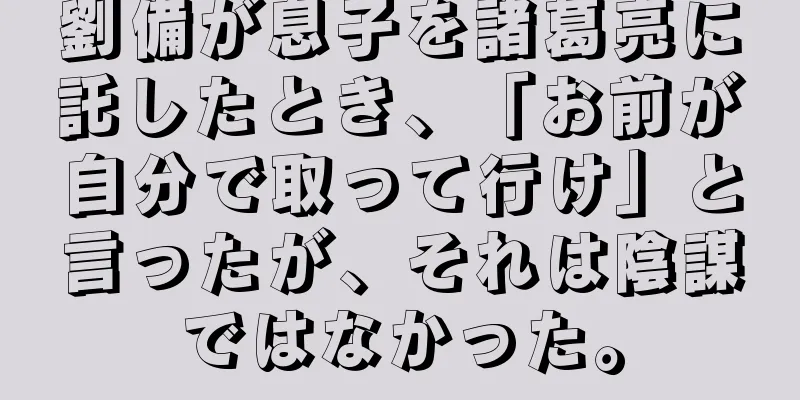
|
劉備が白堤城で息子を諸葛亮に託したことについて、『三国志 諸葛亮伝』には次のように記されている。 章武三年の春、主君は永安で重病にかかり、梁を成都に呼び寄せ、今後のことを託した。主君は梁に言った。「あなたの才能は曹丕の十倍だ。あなたは必ず国を安定させ、重大な問題を解決できるだろう。後継者に能力があれば、彼を助け、能力がなければ、あなたが引き受けなさい。」梁は涙を流して言った。「私は全力を尽くしてあなたに忠誠を尽くして仕え、あなたと共に死にます!」主君はまた、後主君に勅を下し、「あなたは宰相と共に働き、父のように彼に仕えるべきだ。」 劉備の簡潔な最後の言葉は、何千年も記憶に残る有名な事件となった。劉備は本当に自分の地位を放棄したかったのであり、諸葛亮が自らその地位を放棄しないことを決断したことは、彼の忠誠心と誠実さをさらに証明したと考える人もいます。また、劉備は表面上は寛大に話していたが、実際は疑り深く、わざと諸葛亮を試したり、決意を表明させたりしていたと考える人もたくさんいます。 劉備が病気のために意味不明なことを言っていた可能性を除けば、上記の2つの動機の説明は、少なくとも劉備、さらには諸葛亮自身を過小評価していると私は個人的に思います。 まず、誠実になって他の人に道を譲りましょう。 出来ますか?ここで君主と臣下の道徳を無視し、世界情勢と蜀漢の大義の展開だけを考えれば、劉備が屈服することは不可能であり、諸葛亮がそれを受け入れることは不可能であることがわかります。まず、劉備が益州という小さな州だけで皇帝になれた根拠を理解する必要があります。確かなのは、劉備の姓が「劉」であるということ。血統の正統性が極めて重要視された当時、これは蜀漢政権にとって常に切り札であった。曹操が生涯を通じて自らを皇帝と称せず、皇帝を利用して諸侯を支配することを選んだのも同じ論理に当てはまります。曹丕の即位は曹操が生涯をかけて揚子江以北の中原地域を平定した功績に基づいていた。それでも劉備は、漢の献帝が退位した2年後に自ら皇帝を名乗る機会を捉えた。曹丕の選択が賢明であったか賢明でなかったかは言うのは難しいが、少なくとも彼には皇帝になるための基本的な条件は備わっていた。 劉備は、諸葛亮の才能は曹丕の10倍だと言った。この比率が真実かどうかは別として、たとえ諸葛亮の才能が曹丕の100倍、1000倍だったとしても、どうして曹丕と同じ条件で皇帝になれるのだろうか?いわゆる「益州は疲弊し」、窮地に立たされている。蜀漢が生き残り、正統性を保てるのは劉政権だからだ。もし諸葛亮も曹丕の役割を演じ、劉を諸葛に変えれば、最大の切り札を手放し、自ら反逆者になるのではないだろうか。道徳的に言えば曹魏と同等かそれ以下であり、実力もはるかに劣っている。どうして長く生き残れるのだろうか?この時、諸葛亮が国家の安全を守る才能を最大限に発揮したとしても、益州で生き残れるのは数年だけであり、再び南北を征服しようとすれば、間違いなく自らを滅ぼすことになるだろう。 一時的な快楽のためにこのようなトラブルに巻き込まれるのは、項羽のような無謀な男だけだろう。諸葛亮は「曹丕の10倍の才能」を持つ必要はなく、曹丕と同じことをする条件さえ整っていないのに、曹丕と同じことをしようとはしなかった。対照的に、諸葛亮は生涯を通じて劉家の正統性を切り札として堅持し、北伐の際には「討敵復興」の旗印を公然と掲げた。後世の人々でさえ、道義的な観点から蜀漢に同情せざるを得ず、中原で正統な地位を占めていた曹魏を裏切り者と感じた。 もし劉備が本当に物事や人を理解する能力を持っていたなら、この点はずっと前に理解していたはずだ。蜀漢が存続し成長したいなら、劉という姓を持たなければなりません。諸葛亮が帝位を簒奪することは不可能だった。たとえ望んだとしても、北伐を成功させ、中原を平定するまで待たなければならなかった。劉備が敗れて死ぬとき、「やっと大事は済んだ」などと大きなことを言ってはいたものの、そんな奇跡が起こったらどうするかなど、本気で考えていなかったのでしょうね… したがって、賢者に譲歩することは単なる空論であると結論付けることができます。劉が譲歩することは不可能であり、諸葛がその申し出を受け入れることは不可能です。 第二に、疑いと誘惑の理論です。 上記の続きですが、もし諸葛亮に少しの政治的先見の明があったら、このような状況下で王位を奪おうとする意図はなかったはずです。では、なぜ劉備は疑念を抱くのでしょうか?疑念を抱くということは、諸葛亮の基本的な政治的先見性にさえ疑念を抱いていたということだ。そして「あなたの才能は曹丕の10倍だ」などと言った。どうして彼はそんな近視眼的な人間に自分の生涯を安心して託せるだろうか? 確かに権力者は往々にして混乱する。諸葛亮の地位は高すぎ、才能も大きすぎた。常に疑念を抱く君主は存在する。しかも劉備は死期が迫っていたので、疑念を抱いた可能性もあった。 しかし、諸葛亮に本当に隠された目的があったとしたら、劉備が息子を他人に託すという策略でどうやってそれを阻止できただろうか?劉備の「自分で取れ」という言葉が、実は諸葛亮に「自分で取れ」ないように強制したと考える人もいる。公平に言えば、この言葉には本当にそれほど大きな力があるのだろうか?劉備の言葉は2通りの解釈が可能であり、諸葛亮の知恵があれば、これらの言葉を自分の利益のために利用し、劉備の嘘を現実にすることは十分に可能だった。 したがって、もし劉備が本当に諸葛亮を疑っていたのなら、彼の言葉は単なる空論に過ぎなかった。唯一の目的は、死ぬ前に諸葛亮に、本当に彼を信頼していないことを明らかにするためだった。すでに深刻な状況の中で、彼は長年かけて築き上げてきた王と臣下の親密な関係を破壊した。諸葛亮が不信感から反乱を起こさなかったとしても、一度幻滅してしまえば、将来的には忠誠心はあっても賢明さはなくなり、劉備は得るものよりも失うものの方が多いだろう。 誰かを疑うなら、その人を雇ってはいけません。誰かを雇うなら、その人を疑ってはいけません。もし劉備が本当に疑っていたなら、おそらく裏目に出るであろう愚かなテストをするよりも、諸葛亮を雇わないか、あるいは殺した方がよかったでしょうし、大勢の人の前でそうするべきではなかったでしょう。 そういえば、劉備の本当の動機は何なのだろうか? 個人的には、劉備がこれを言ったのは諸葛亮のためではなく、劉備の子孫や蜀漢の大臣たちのためだったと思います。蜀漢が生き残り発展するためには、劉備は諸葛亮に絶大な権力を与え、彼の才能を十分に発揮する機会を与えなければなりませんでした。しかし、これは諸葛亮を大きな権力の座に就かせることに等しい。劉備の死後、どうして彼はそのような地位を維持できたのだろうか?誰かが彼を非難したり、噂したりするでしょうか?周公ですら噂を恐れていたのに、卑しい出自の外国人である諸葛亮はなおさら恐れていた。正直に言うと、諸葛亮が衰弱して亡くなったと読んだとき、悲しい気持ちと同時にほっとした気持ちもありました。少なくとも、皇帝を傷つけた悪人に殺されたわけではないのですから。多くの功績ある官僚が殺されたのを見て、あの激動の時代に諸葛亮は良い最期を迎えたと感じました。 劉備は困難が待ち受けていることを悟り、息が残っているうちに諸葛亮に皇帝の剣を与えた。 「自分で取っていい」というのは、本当に自分で取っていいということではなく、みんなに聞こえるように言うということだ。諸葛亮が私に取って代わろうとしたとしても、私はそうさせてあげる。そうすれば、誰も彼の権力に疑問を抱くことはないだろう。彼は息子に諸葛亮の道を切り開くために「父親のように仕える」よう具体的に指示した。さらに、この言葉は劉禅に対する警告でもあり、諸葛亮を軽々しく解雇したり、さまざまな事柄で行き過ぎたりすることを防ぐものでもある。考えてみてください。劉備が死ぬとき、彼は諸葛亮が「無能」で「扶養に値しない」と疑っていました。これが本当なら、諸葛亮が自ら帝位に就くことは確かにできませんでしたが、劉備の他の息子の中から別の息子を選ぶことはできたのでしょうか? 歴史上、劉備の言葉は確かにそのような役割を果たしました。諸葛亮の生涯を通じて、劉禅は大きな変化をしませんでした。「政事の大小を問わず、すべては梁が決める」彼は常に少し慎重でした。蜀の大臣たちも諸葛亮がそのような権力を持っていることを認めていた、少なくとも公然と反対する者はいなかった。もし劉備が息子を諸葛亮に託していなかったら、諸葛亮は簡単にそのような地位を獲得できたでしょうか? そして諸葛亮自身はどう考えていたのでしょうか?彼の反応から判断すると、彼は劉備の意図を理解し、彼を疑うのではなく自分自身を信頼するべきだった。 「梁は泣きながら言った。『私は全力を尽くしてあなたに仕え、死ぬまで忠誠を尽くします!』」この文章をよく見ると、なぜ劉備への直接的な返答のように聞こえないのでしょうか。特に「自分で取る」という言葉は非常に敏感ですが、諸葛亮は「そのようなつもりはありません」という慌てた言葉さえ言いませんでした。唯一理解できることは、劉備の意図が自分のために奪うのではなく、蜀漢の未来を自分の肩にかけることだと理解し、感動して涙を流し、余計な言葉や行動をせずに、死ぬまで忠誠を尽くすと劉備に心配しないように伝えたということだけです。愚かなほど忠誠心の高い頑固な老人のように驚いて、陛下がどうして私の忠誠心を裏切り者の曹丕と比べられるのかと言い、忠誠心を示すために柱に頭を打ち付ける代わりに。 対照的に、『三国志演義』には「これを聞いた孔明は全身に汗をかき、手足が震え、地面にひざまずいて涙を流した。『私はどうして全力を尽くして死ぬまで忠誠を尽くさないのか!』と言い終えると、孔明はひれ伏して血を流した」と書かれている。これは諸葛亮の反応を誇張し、実際に君主と臣下の間に亀裂があるかのように見せかけ、諸葛亮の答えを自然な心の表現ではなく恐怖の反応に変えてしまった。では、諸葛亮は人生の後半で何をしたのでしょうか?主君に盲目的に忠誠を誓う?それとも劉備の策略のせいで戦い続けざるを得なかったのでしょうか? 諸葛亮の領域はこれに限らないと個人的には思います。若い頃の気楽な様子を見ると、彼は平民で下級生だったが、隠遁生活から抜け出す意志を持つまでに劉備は3度彼を訪ねた。さらに、戦場には賢明な戦略や計画が数多くあるのに、学者のような人がそれをどうやって管理できるというのでしょうか。もし劉備が本当に自分を信頼していないことがわかったなら、ここに留まって天意に逆らうのではなく、とっくに去って自分の野に帰るべきだった。少なくとも、何度も北伐を始めて、ついには疲れ果てて死ぬようなことはすべきではなかった。 諸葛亮が劉家の統治のために戦うことに献身したことは、彼が劉備の行動に心から感動し、友に報いるために天の意志に逆らうこともいとわなかったことを反映している。どうしてこのような真摯な気持ちが一方的な陰謀論によって消し去られてしまうのでしょうか? しかし、その一方で、権力が大きければ大きいほど、責任も大きくなり、危険も大きくなります。たとえ劉備の「自分で取ってください」という言葉が誠実な託しから出たものであったとしても、それが将来諸葛亮に必ずしも災難をもたらすとは限りません。正確に言えば、諸葛亮が状況をうまく処理していれば、劉備は彼に最高の条件を与えただろう。状況をうまく処理していなければ、「自業自得だ」という言葉で人々に非難され、何もしていなければ諸葛亮は永遠に呪われただろう。しかし、これを理由に劉備を責めるのは行き過ぎだろう。結局のところ、彼は当時はただの死にかけの男であり、将来の全体的な状況をコントロールする能力はなかったのだ。この剣は諸葛亮に与えられた。諸葛亮がすべての障害を乗り越えられるか、あるいは傷つけられるかは諸葛亮自身にかかっている。 諸葛亮は実に大胆で、この皇帝の剣の使い方が上手でした。数年後、諸葛亮は北へ向かい、出発前に『下都追儺』を書きました。冒頭部分は長い文章で、劉禅の行動規範を定めた真摯な訓戒でした。これは、当時の諸葛亮がどのような地位にあったかを示しています。また、 「先帝は私が慎重な人物であることを知っていたため、死ぬ前に私に重要な仕事を任せた」とも記されている。少なくとも諸葛亮自身の考えでは、劉備が私にその任務を任せたのは、彼を傷つけたり利用したりするためではなく、彼が本当に彼のことを「知って」おり、彼の「慎重さ」でその問題を処理できると信じていたからである。そうなれば、今は武侯に対して特に同情する必要はない。 |
<<: 曽国藩は南京を征服した後、なぜ皇帝にならなかったのですか?
>>: 私の国で最初の鉄道は何でしたか?かつてはラバや馬に引かれていた
推薦する
呉勇が使ったものは戦略ではなく、卑劣な手段としか言えないのはなぜでしょうか?
『水滸伝』は中国史上初の農民反乱をテーマとした章立ての小説である。作者は元代末期から明代初期の史乃安...
『紅楼夢』の天祥塔はどこにありますか?賈珍はそこで何をしたのですか?
賈震は、曹学芹が書いた中国の古典『紅楼夢』の登場人物です。Interesting Historyの編...
老子が三清浄に変身した物語は何ですか?三人の清らかな者とは誰ですか?
「一気三清」は、徐鍾麟著『封神抄』に初めて登場した。太上老君と同田教主が戦っていたとき、太上老君が一...
唐代の作家陳志玄の『五歳花頌』の原文、翻訳、注釈、鑑賞
羅銀の『五歳花頌』に興味がある読者は、Interesting History の編集者をフォローして...
「水の旋律」の「明るい月はいつ現れるか」をどのように理解すればよいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
水の旋律の歌:明るい月はいつ現れるのか?蘇軾(宋代)冰塵の中秋節に、私は夜明けまで飲んで酔っぱらいま...
岑申の古詩「秦中の旧友に宛てた手紙、普関に入る前」の本来の意味を鑑賞する
古詩「普関に入る前に秦中の旧友に宛てた手紙」時代: 唐代著者: セン・シェン秦山のいくつかの点は藍の...
山海経の奇妙な獣とは何ですか?最強の獣の順位は?
山海経に出てくる最強の怪物のランキングを知っていますか?知らなくても大丈夫です。おもしろ歴史編集長が...
韓愈の『ザクロの花について』:客観的な風景の描写で人生哲学を伝える
韓愈(768年 - 824年12月25日)は、字を随之といい、河南省河陽(現在の河南省孟州市)の人で...
唐の太宗皇帝の娘、玉章公主の紹介。玉章公主の夫は誰でしょうか?
唐の太宗皇帝李世民の9番目の娘、董陽公主(?-701年)で、母親は不明。 東陽公主は高禄興と結婚した...
劉克荘は、サンザシの花について書くことで、自分自身の経験を暗示するために「莫余實·ベゴニア」を書いた。
劉克荘(1187年9月3日 - 1269年3月3日)は、原名は卓、字は千福、号は后村で、福建省莆田県...
王維の古詩「千塔師」の本来の意味を理解する
古代詩「千塔の主」時代: 唐代著者 王維宿にいる時は楽しいのですが、これ以上出航することはできません...
『紅楼夢』で、賈家が略奪された後、趙叔母の結末は王夫人の結末と比べてどうでしたか?
賈正の側室である趙叔母は、『紅楼夢』の登場人物です。今日は、Interesting Historyの...
小説『紅楼夢』で、金陵十二美女の第一位は誰ですか?嬪玉ですか、それとも宝仔ですか?
黛玉は小説『紅楼夢』のヒロインであり、『金陵十二美女』本編の最初の二人の登場人物の一人です。『Int...
『詩経・暁・暁明』の意味は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
シャオミン 匿名 (秦以前)空は明るく輝き、下の地球を見守っています。私は西に向かって行進し、荒野に...
「堤防上の三つの詩」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
堤防上の三つの詩劉玉熙(唐代)堤防の上にはワインの旗が向かい合って立っており、堤防の下にはマストが、...