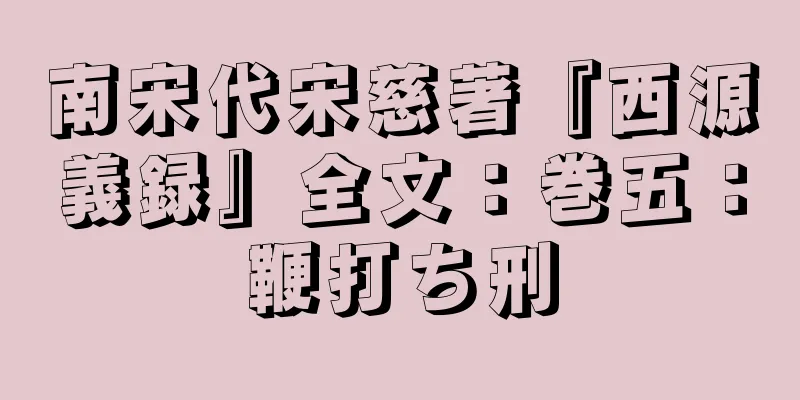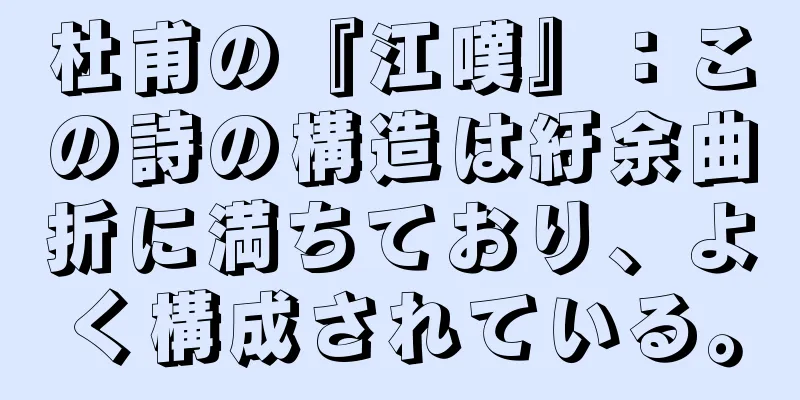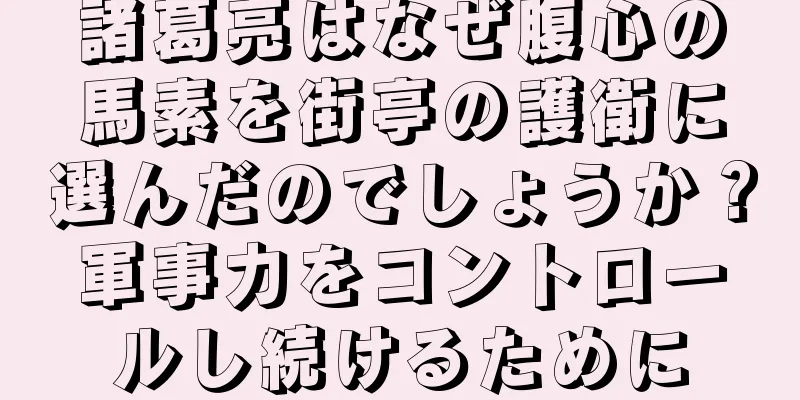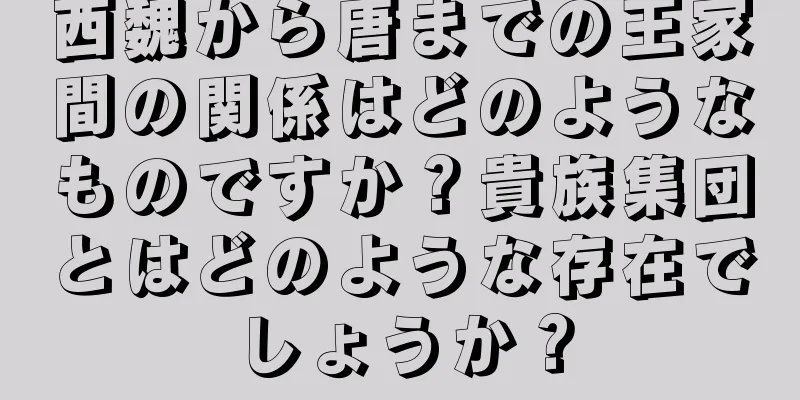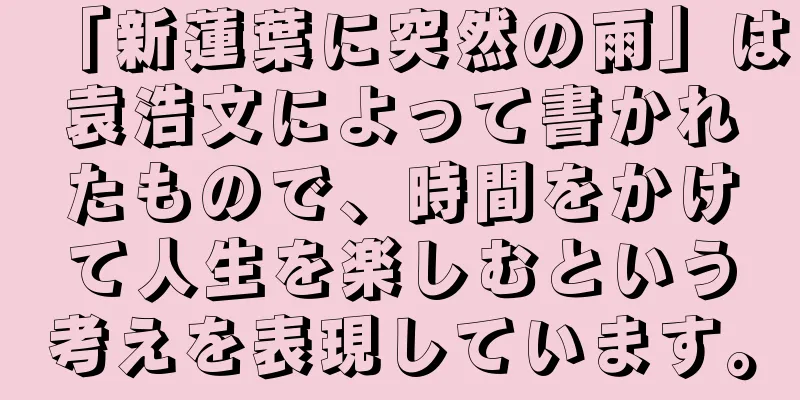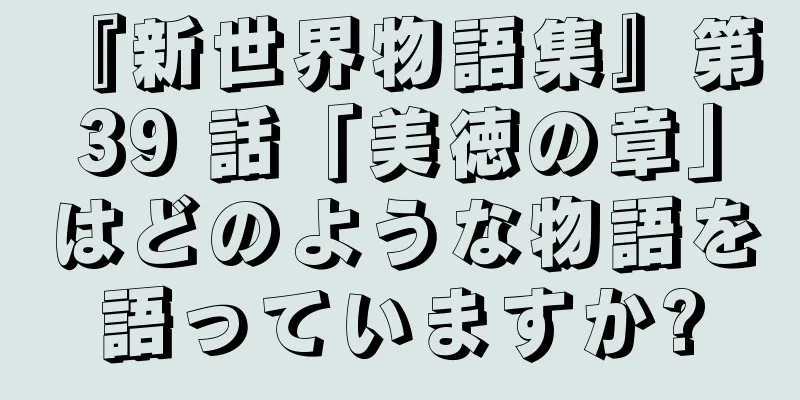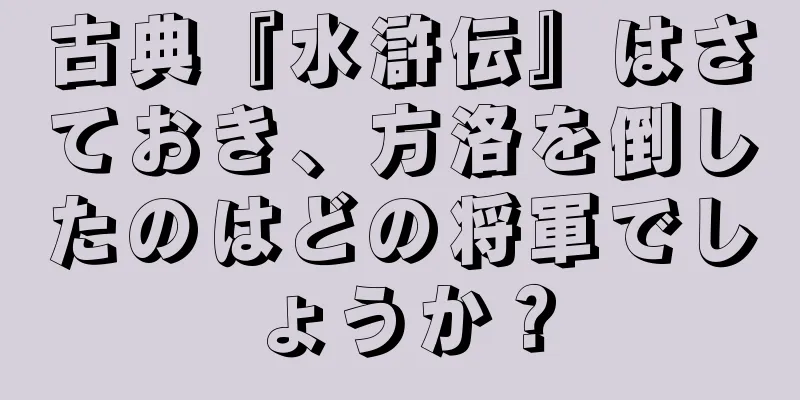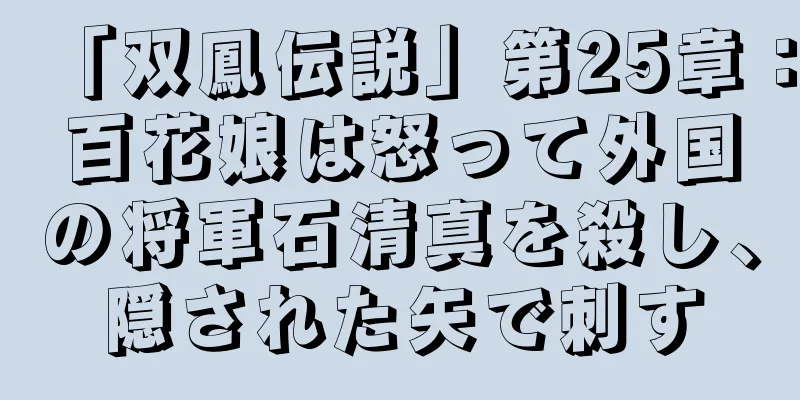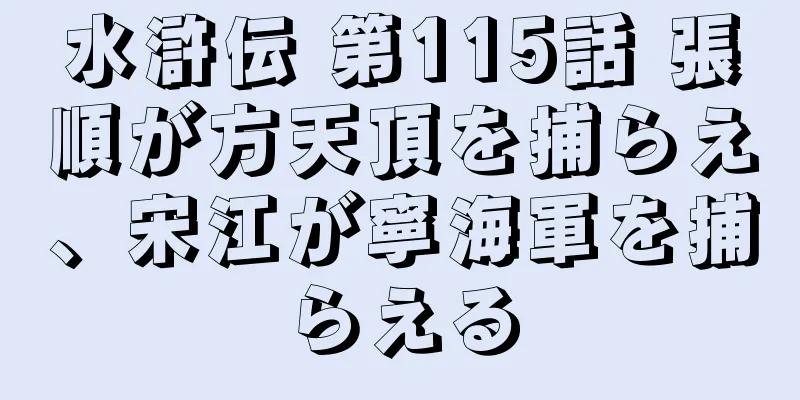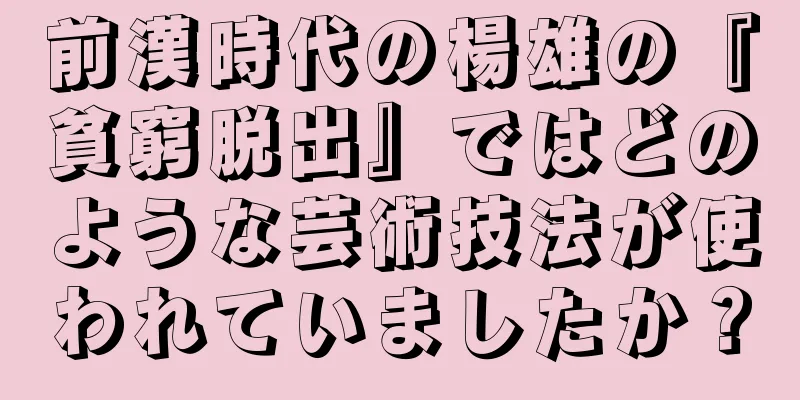古代人はどうやって人を毒殺したのか:毒を盛られた後、7つの穴すべてから出血して死ぬことはあり得るのか?
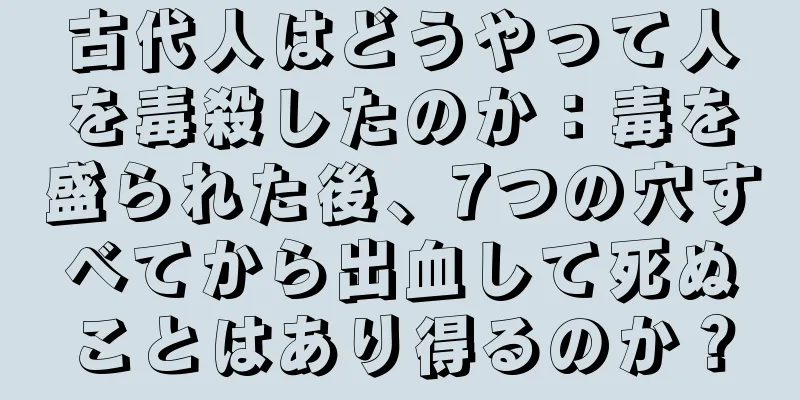
|
以前人気があった「大頭皇后小頭帝」-「武美娘伝説」では、官軍の闘争で毒殺され、血が噴き出す犠牲者が数多く登場した。劇中の人物たちも中毒の時期や症状が異なりますが、本当にこのような毒物が存在するのでしょうか?毒を盛られた後はどんな感じですか?歴史上の伝説上の本当の毒と嘘の毒について話しましょう。 毒とは何ですか? 毒は、7,000 年の歴史を持つ人類文明と同じくらい古いものです。天然の植物や動物から化学物質、殺人から医療まで、毒は文明の発展に大きな足跡を残してきました。人類は毒物を使用する新しい方法を発明し続けており、ローマ時代には1000種類近くの毒物が記録されています。私の国では、東周の時代から5種類の毒物(水銀、ヒ素、サポニンまたは胆石、磁鉄鉱、そしてもう1種類未知の毒物)を殺人に使用した記録があります。古代中国語では、毒は「毒物」と同じではないことに注意が必要です。古代中国における毒とは、非常に標的を絞った強力な薬や、耐え難い味と毒性を持つ本当に有毒な植物を指します。 「飲む薬」だけは、様々な種類の薬や毒物を指します。 戦国時代にはすでに古典に「薬は毒が多い」と明記されていたが、その毒性は通常は副作用とみなされ、「大、中、小」と漠然と述べられていた。1247年に宋慈が初めてさまざまな毒の中毒現象を体系的に記述した。後に李時珍は40種類以上の毒性の強い物質を意図的に1つのカテゴリに分類し、当時の人々が「毒」についてより深い理解を持っていたことを示している。ヨーロッパでは、1541年に法医学毒物学の概念が導入され、毒物は特定の化学物質として標準化されました。また、当時の医師は、すべての物質は毒であり、無毒の物質は存在しないと信じていました。これらを区別する唯一の基準は投与量です。 古代中国における毒物は通常、金属毒(水銀、ヒ素、重金属塩など)、有毒植物(アコヤガイ、ゲルセミウム・エレガンス、有毒な瘴気など)、有毒動物(毒蛇、魚の胆、蜂の毒など)の3つのカテゴリーに分類されます。作用機序としては、臓器に病理学的損傷を引き起こす破壊毒、中枢神経系の機能を妨げる神経毒、血液の変化を引き起こす血液毒などがあります。時には単一の効果ですが、多くの場合は複数のタイプの複合効果です。ただし、複合薬は必ずしも1+1>2を意味するわけではありません。失恋草と恋花の毒の話は信憑性に欠けますが、ある毒が別の毒を妨害し、その毒性を弱めたり無効にしたりするという原理は事実であり、医学では拮抗作用と呼ばれています。 毒を盛られて7つの穴すべてから出血して死ぬことはあり得るでしょうか? 植物の場合、この可能性は極めて低く、出血は主に口、鼻、外陰部、肛門(便中の血)から起こることが多いです。実際、「七つの穴すべてから出血する」という表現は、元代の小説に初めて登場した可能性がありますが、当時の医学書では、この用語は中毒の症状を説明するために使用されていませんでした。これは、後の小説で、毒を盛られた悲惨な状態を表すのによく使われています。これは「西元季録」に由来している可能性があります。「毒を盛って死ぬ人は、口、目、耳、鼻から血が出る」。実際、これは冒頭の要約に過ぎず、ここでは異なる状態を区別していません。後世の人々はこれを読んで、7つの穴すべてから同時に血が出るという意味だと解釈しました。 しかし、実際の毒の症状はそれほど明白ではありません。結局のところ、毒が依然として人気があるのは、便利で安価だからですが、さらに重要なのは、中毒後に体が特定の病気の兆候を示すことが多く、宋慈によって確立された体系的な解剖の概念と技術がなければ、実際の病気と区別することが難しいことです。毒は目に見えない形で人を殺し、非常に隠されています。こんなに血が流れていたらどうやってプレーすればいいのでしょうか? もっと有名な「七つの穴から出血する」は『水滸伝』に由来するかもしれない。宋代の話ではあるが、書かれたのは明代である。銀を使って物を買うなど、多くの日常の細かい描写は明代の状況を反映しており、このような描写があっても不思議ではない。原作では、武大浪が毒殺されたとき、潘金蓮は7つの穴から出血することで身元が判明するかもしれないと気付いており、武大浪の血を拭うという筋書きがあったが、残った「かすかな血痕」が武松に復讐を決意させる手がかりの一つとなった。 宮殿の毒殺:飲酒 劇中で「七つの穴から血を流して」死んだ最初の側室、鄭万如は、鴛鴦の毒壺の水を飲んで自殺した。唐代の人々の最も鮮明な記憶は、おそらく「李白は百杯の酒を飲み、百の詩を書いた」と「金杯をむだに月に向けるな」という一節でしょう。唐代の酒一斗は、現代の5リットルビール樽とほぼ同等である。「李大賢」という名前を「李大同」と改名した方が適切だろう。 古代人がこのように飲むことができたのは、彼らの帯の品質が高かっただけでなく、当時のワイン製造技術にも関係していました。簡単に言えば、古代人が言う「濁った酒」は、現代の発酵させたもち米汁(甘いもち米酒)です。古代は衛生状態が悪かったため、醸造されたワインの色は、劣るものから良きものまで緑、赤、黄、琥珀の4色があり、味も酸っぱくて苦いものからほんのり甘いものまで様々でした。洗練された富裕層はそれを濾過しますが、「冬の収穫を迎える黄酒と緑酒」を書いた白居易のような自由奔放な文人は、濾過されていない黄酒と緑酒を指します。漢民族が水で食べ物を煮るのとは異なり、唐民族は殺菌のため食べ物を火にかけて沸騰させました。この工程は「少春」と呼ばれています。この方法で作られたワインは味は甘いがアルコール度数は低く、ブドウ酒よりもさらに低い。そのため、李大同氏らは「一度に300杯飲まなければならない」が、これは肝臓よりも膀胱のテストである。しかし、鄭夫人が注いだ酒は透明で、これは通常、濾過後の粗悪な緑酒の色であり、王族がこれを飲むのはみすぼらしいだけでなく、無色無味の毒物として大きな挑戦となった。 劇中では毒に冒された人々がワインを飲んでいましたが、蒸留法が中国に導入されるまでは、このようなワインは実際には存在しませんでした。 ワインの話のあとは、この「金杯」とオシドリの毒壺の話をしましょう。まず第一に、オシドリ鍋は存在します。それを使用する人は、そこに「毒」という言葉が入っていることを絶対に望んでいません。戦国時代にはすでに存在していたと考えられており、遅くとも前漢時代には記録に残っています。実物が発掘されていないため、動作原理は不明です。2010年に現代のアーティストが負圧の原理を利用してこれを再現することに成功しました。ハンドルの空気穴を押すだけで、2つの異なる液体を注ぐことができます。 劇中で使われる鴛鴦壺には、壺の取っ手にある機構を回すことで、毒のある酒と無毒の酒の2種類の酒を注ぐことができる仕組みが備わっている。 鸩については、神話上の、あるいは絶滅した古代の獣だという説と、カンムリハゲワシ(Spilornischeela)だという説があります。背中と首に大きく目立つ黒い羽があり、蛇やサソリなどの有毒昆虫を捕食し、樹冠に生息します。これらはすべて、本に書かれている鸩の記述と一致しており、わが国に広く分布しています。鸩を撃って毒や毒酒を使うという考えは古代から現在まで南から北まで記録されていることを考えると、その原因は鸩の羽にあった可能性もあるが、まったく有毒ではない。また、古代では羽は装飾品や日用品としてよく使われていたという説もある。羽は目立たず、災難を避けるために捨てることもできる。そのため、「鸩毒」とは、特定の鳥(唐代にはいたるところにいた家禽のガチョウだったかもしれない)の羽の空洞構造を利用して毒を吸収し、それを酒に浸して使用する毒の運搬方法を指すのかもしれない。しかし、この主張を裏付ける考古学的証拠がないため、「鸩」は単に致命的な毒の同義語である可能性があります。 『武美娘伝』では、鄭さんが突然亡くなった後、戴青(実際は戴周)は、それは墨北の刺青毒であり、感染した者は即死するだろうと語った。タトゥーの毒そのものは検証できないが、問題はドラマの冒頭で飲んだら3日以内に死ぬと言っていたのに、なぜ急に急死したのかということだ。脚本家の不注意を無視するとすれば、死者が生前に抱えていためまい、躁状態(プロット上の要素は無視)、唇の乾燥、顔面蒼白、嘔吐(劇中では血が噴出)などの症状から判断すると、最も可能性の高い毒物はクロランサス科のクロランサス・セラトゥスと、同科同属の他の植物である。 日陰や湿った林に生える多年草で、江蘇省、安徽省、湖北省、福建省、広東省、広西チワン族自治区、貴州省などに分布しています。 一般的には転倒による外傷の治療に外用薬として使用されます。その毒性は唐代の『新訂本草綱目』(中国初の法的拘束力のある薬学論文集。テレビドラマ『呉侠客』でカニを食べて死亡した李春鋒も編纂した)に初めて記録されました。中毒は通常、多量または複数回服用したり、骨折などの開いた傷口に多量の薬を塗ったりすることで発生します。摂取後約8時間で症状が出たという記録があり、日本酒に混ぜた根汁を飲んだ直後に症状が出た例もある。しかし、死亡は通常、摂取または外用後約2日で発生し、ドラマの描写とより一致している。また、緑色で酸味と苦味があるはずの「日本酒」を混ぜた汁は、検出が容易ではない。この薬の標的臓器は肝臓です。飲み込むと黄疸が出て、肝臓や腎臓に深刻な損傷を与え、胃にも強い刺激を与えます。死後の解剖では、重度の毒性肝壊死と皮膚や臓器の広範囲の出血が見られます。この場合、7つの穴どころか、宋慈の言う「すべての穴から出血している」という言葉を使う方が適切です。 ドラマでは、死者の爪が紫色になっていることも映し出されている。この症状は、吐血と同じように、中毒死のほぼ標準的な症状となっている。宋慈は「手足の爪はすべて青く黒ずんでいた」とも語っている。実際、紫色は中毒によって引き起こされる場合もありますが、中毒が必ずしも紫色を引き起こすわけではありません。窒息、脱酸素ヘモグロビンの増加、化学物質中毒などによりチアノーゼが生じる可能性があります。有毒植物の多くの主要なカテゴリの中で、主に中枢神経系を攻撃するものがこの現象を引き起こすことが多いです。 劇中で毒を盛られた人の爪がチアノーゼになっているのは、実際には爪床全体が紫色に変色していることを意味するはずです。 しかし、この中毒による爪のチアノーゼは、爪床全体が紫色に変色するはずです。ドラマで中毒者の爪の根元だけが紫色に変色するのは、脚本家が爪の半月が健康と関係があるという誤った考えに影響されたのではないかと思います。 有名なゲルセミウム・エレガンスを例にとると、そのゲルセミウムアルカロイドは延髄の呼吸中枢、迷走神経系に直接作用し、運動中枢に抑制効果をもたらします。中毒患者は、まず消化管に激しい焼けつくような痛みを感じます(ハーブの名前はこれに由来し、この「腸が破れる」ような症状を引き起こすハーブをハーブと呼ぶのですが、ゲルセミウム・エレガンスが最も一般的なハーブです)。続いて手足のしびれ、ろれつが回らない、視界がぼやけるなどの症状が現れ、最終段階では不整脈、呼吸困難、筋肉の震え、けいれん、後弓状緊張(ストリキニーネ中毒の症状に似た脊柱の硬直)などの症状が現れ、通常 8 時間以内に呼吸不全で死亡します。検死の結果、結膜点状出血、唇や爪のチアノーゼなど、窒息死によく見られる症状が明らかになった。 ゲルセミウム・エレガンス、別名ゲルセミウム・エレガンス。しかし、現在ではゲルセミウム・エレガンスと呼ばれる有毒植物が各地に16種類近く存在しており、各種の解毒療法は信用できない。 スイカズラに似たゲルセミウム・エレガンスは、ありふれた猛毒雑草として、本当に警戒が必要な植物と言わざるを得ません。一方で、腫れや痛みを和らげ、リウマチや頭部白癬の治療に効果があることから、古代では広く使用されており、感染する確率は比較的高いです。また、スイカズラに似ているため、現代でもハーブティーを作るために誤って摘み取られることがよくあります。さらに、植物全体が有毒であるため、ゲルセミウム・エレガンスの花粉を含む蜂蜜を飲んでも害を及ぼす可能性があります。 宮殿中毒ダイエット 食べ物の話をする前に、まずは劇中で刺されて死んだ馬(ライオンスタリオン)の話をしましょう。ドラマでは、馬の餌にチョウセンアサガオと心臓を食べる草を混ぜると、馬は血を見ると怒り狂ってしまうと語られている。ナス科の植物(チョウセンアサガオ、アトロパベラドンナ、ヒヨス属など)には、ヒヨスチアミン、スコポラミン、少量のアトロピンが含まれています。他の現代の合成アトロピン製剤と同様に、呼吸器系、血管系、その他の中枢神経系に刺激を与える効果があり、有機リン中毒の治療薬としても使用されています。恋の毒や失恋草の物語の真の原型として、このタイプの植物による中毒後の初期の興奮と頻脈は、すぐに聴覚と視覚の幻覚、精神混乱、躁病、そしてうつ病や昏睡に変わり、最終的には心不全または窒息で死に至ります。もしこの馬が吸血鬼でないなら、血の匂いがしなくても躁状態になるかもしれない。ドラマの中で呉美娘が一本のナイフでライオンを刺し殺すシーンは非常に残酷に思えますが、実際には、チョウセンアサガオは発見されて以来、有名な薬用植物です。一部の歴史資料では、麻妃散の主成分はチョウセンアサガオであると信じられており、現代医学の分野では今でも高い実用価値を持っています。 チョウセンアサガオ(Daturastramonium) 秦の時代以前から漢の時代、そして唐の時代まで、牛は重要な農業資源であったため、牛を殺した者は通常、強制労働か斬首の刑に処せられました。唐の時代には、人々は牛肉をほとんど食べず、主に羊肉と鶏肉を食べ、次に豚肉と様々な狩猟肉を食べていました。これにより中毒が発生しやすくなります。第一の理由は、当然ながら羊肉は羊肉特有の強い臭みがあり、調味料で処理しなければならなかったからです。第二の理由は、冷蔵庫がなかったため、肉を保存する一般的な方法はマリネすることであり、それにも多くの調味料が必要だったからです。当時の主な調理法は煮る、焼く(灸)であり、肉料理に最もよく使われた調味料は、イリシウム科の中国特産であるスターアニス(Illicium verum)でした。もちろんスターアニス自体には無害ですが、その近縁種の中には問題のあるものもあります。それらはスターアニスとよく混同され、外見が似ているため中毒を引き起こします。症状は通常、摂取後 1 日以内に現れます。重症の場合は、上腹部の灼熱痛、激しい頭痛、噴出性嘔吐が見られ、少量の血を吐くこともよくあります。また、重症度によっては、てんかん性けいれんが起こることもあり、最終的には高熱と呼吸不全で死亡することもあります。 鶏肉の付け合わせとして最適なキノコの種類は言うまでもありません。現在、わが国には300種類以上の食用菌類、80種類以上の有毒菌類、数十種類の致死菌類が存在します。その被害の種類の中で最も一般的で最も深刻なのは、肝臓と腎臓にダメージを与えるタイプです。この病気は通常、摂取後 24 時間以内に発症します。最初の症状は胃腸炎で、約 2 日間続き、腹痛と下痢を伴います。その後、毒性の程度に応じて、すぐに死亡する人もいれば、突然元気になったように見える人もいます。実際、内臓、特に肝臓への損傷はすでに始まっており、患者は最終的に機能不全に陥り死亡することになります。唐の時代にタイムスリップしてキノコをむさぼり食い、胃腸炎の症状が出たら、宋慈のアドバイスは、すぐに便を飲み込んで吐かせることです。私のアドバイスは、他に手段がなければ、とにかくやってみることです... これらが安全でないなら、他に何を食べればいいのでしょうか? 魚介類はどうでしょうか?今日私たちが食べられるすべての魚介類や川魚に加えて、当時もさまざまな魚介類がありました。生の魚を食べるのが好きな人もとても幸せになるはずです。なぜなら、いわゆる日本の刺身や刺身の祖先は唐代の魚のフライだからです。新鮮な川魚や海魚を非常に細い糸やスライスに切り、切り身と呼びます。ネギ、生姜、唐辛子、酢につけて食べる。塩を少し多めにふりかけると傲慢なシェフに食べ方を間違えていると叱られるかもしれない日本料理よりも、ずっと美味しい。 しかし、生魚の寄生虫問題と比べると、厳密に言えば「中毒」とはみなされないアレルギー反応についてここで話すべきです。普通の人にとって無害な量や物質が、アレルギーのある人にとっては致命的な「毒」になる場合があります。一般的な例としては、ペニシリンアレルギーや蜂アレルギーなどがあります。 ドラマ「呉」でカニを食べながら窒息死した人物もこの範疇に入るが、ドラマの中で「喉頭腔の腫れで死亡した」と表現するのは適切ではない。正確な死因は気管支粘膜浮腫とそれに伴う気管支痙攣で、呼吸困難に陥り最終的に窒息死したからである。こうした非外的窒息死の場合、明らかな窒息の兆候はなく、ドラマのような首の腫れも見られません。死期が早ければ、唇や爪のチアノーゼ、まぶたの結膜の点状出血などの兆候も現れないことがあります。古代では死因が分からないのが普通でしたが、現代でも浮腫や内臓のうっ血で死因が分かります。ドラマで彼が「アレルギー体質」だとは言われなかったのは称賛に値する。なぜなら、アレルギー(当時は特定の植物で起こる季節性疾患と呼ばれていた)の概念と研究はペルシャでは西暦9世紀まで生まれていなかったし、2世紀前の宋慈のいない唐の時代には、たとえそのような現象の記録があったとしても、この不幸な子供は天の秘密を漏らし神を怒らせたために死んだと解釈される可能性が高いからだ。歴史上、天文学、暦学、気象学に精通した李春風のような人物が確かにいた。『新唐書』には、彼が太宗皇帝に「唐は弱く、女戦士に取って代わられる」という占いをしたと記録されているが、彼は次の皇帝が亡くなる直前まで生きていた。 劇中では、李春鋒はカニ肉を混ぜた食べ物を食べて亡くなりましたが、外見に異常はなく、宮廷の医師でさえ死因を突き止めることはできませんでした。 追伸:この記事を中毒のガイドとして使用するのは間違いです! |
推薦する
『紅楼夢』で刺繍の入った小袋を見つけた後、王夫人は何と言いましたか?
王夫人は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公の一人です。次の『Interesting History』編...
道光皇后孝神成はどのようにして亡くなったのでしょうか?小神成皇后は何歳でしたか?
道光皇后孝神成はどのようにして亡くなったのですか?孝神成皇后は何歳でしたか?孝神成皇后(1790-1...
後秦の武昭帝、姚昌の伝記 姚昌はどのようにして亡くなったのでしょうか?
後秦の武昭帝の姚昌(330年 - 394年)は、字を景茂といい、南安市池亭(現在の甘粛省隴西市西梁家...
『後漢書 漢朗伝』の原文と翻訳、『漢朗伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
「農桑料理」野菜とレタス全文と翻訳ノート
『農桑集要』は、中国の元代初期に農部が編纂した総合的な農業書である。この本は、智遠10年(1273年...
李玄覇は李世民の弟ですか?李玄覇と李元覇の関係は何ですか?
李玄覇は李世民の弟ですか?李玄覇と李元覇の関係は?Interesting Historyの編集者と一...
赤壁の戦いの失敗後、曹操はなぜ郭嘉と郭鳳霄のために激しく泣いたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『西遊記』に登場する人物は皆、自分は偉大な賢者だと主張しているのに、なぜ孫悟空だけが認められているのでしょうか?
『西遊記』では、孫悟空が花果山をさまよっていたとき、孫悟空と牛魔王は互いに尊敬し合っていました。孫悟...
『正月十五夜』は蘇維道によって書かれたもので、元宵節の夜の長安の人々の楽しい情景を描写している。
唐代の政治家、詩人であった蘇維道は、漢代の汪州知事蘇章の子孫であり、宋代の文壇を支配した「蘇家」の祖...
庚子年とは何を意味するのでしょうか?庚子年に生まれた有名人は誰ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が庚子年に生まれた有名人を紹介します。興味のあ...
『紅楼夢』の王夫人はどんな人ですか?彼はいい人ですか、それとも悪い人ですか?
『紅楼夢』では、王夫人は賈正の妻であり、賈珠、賈元春、賈宝玉の母であり、優しそうな女性像である。 「...
なぜ呂久遠の『心学』は張天石に由来すると言われるのでしょうか?陸九源と張徳清の関係は何ですか?
『心について』は、宋代末期の第30代天師張継先が江西省貴西上清龍湖山天師草堂(現在の上清宮)で執筆し...
明代初期、手工芸経済のどの産業が最も急速に発展しましたか?
明朝初期に最も急速に発展した手工芸産業には、綿織物、磁器製造、鉱業、造船業などがありました。明朝初期...
薛安復の『西湖秋雑詩』:この短い詩は想像力に富み、深い芸術的構想を持っている。
薛昊甫(1267-1359)は元代の紀書家であった。ウイグル人。彼の本名は薛超武であり、彼は自分の名...
『紅楼夢』では、賈家の祖先である賈祖母は、どのように若い世代を教育したのでしょうか?
賈おばあさんは、石夫人とも呼ばれ、賈家の皆から「老夫人」「老祖」と敬意をもって呼ばれています。彼女に...